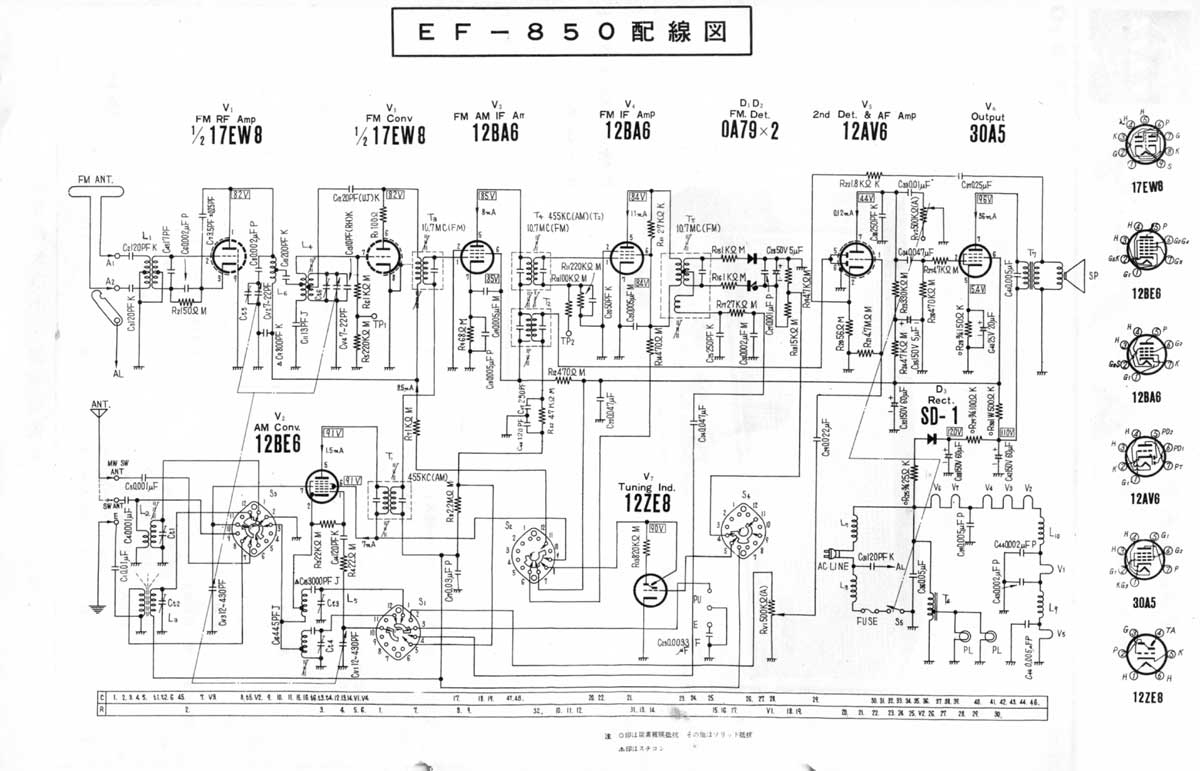この時代の日本製スーパーは非常に珍しい。

昭和初期に販売されたテレビアン 山中電機のスーパー
この時代の日本製スーパーは非常に珍しい。

終戦後に一時流行したありあわせの真空管を使ったスーパー
名前はスーパーでも高1より感度が悪かった可能性があります、骨董市で同じ言うな物を偶然1台買ったことがあります。
高1を改造した物は時々見かけますが、一流メーカーの製品としては珍品の部類。
仇花に終わりました。
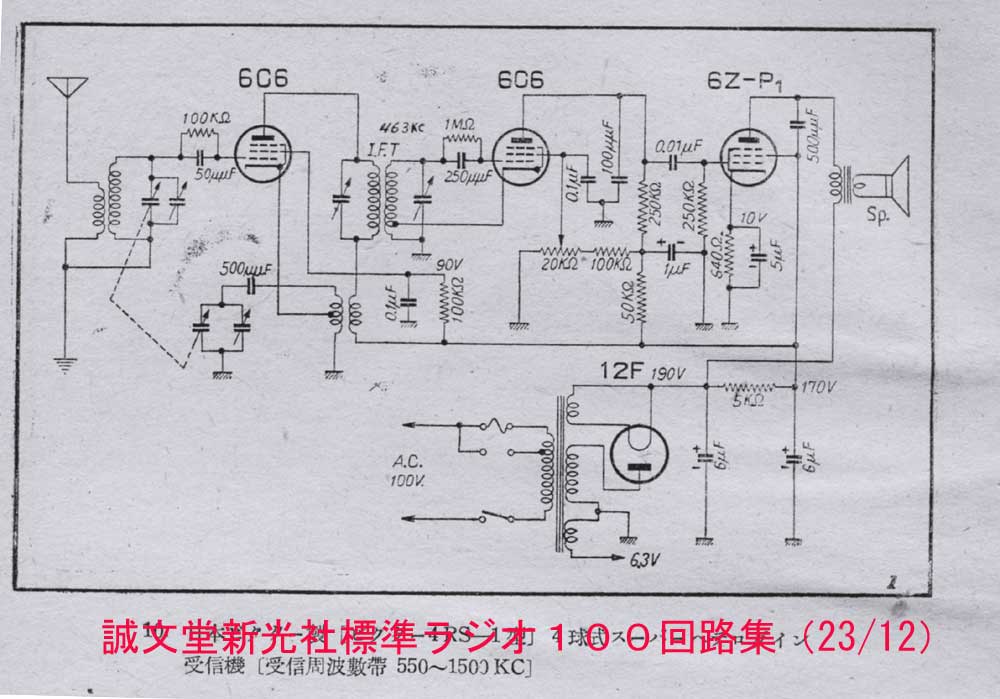
三田無線の2バンドスーパー
戦前からスーパーの製造経験あり、終戦直後といえども本格的です。
回路は標準的ですが、スピーカーのフィールドコイルがB電源のマイナス側に入れられています。
最近は殆ど見かけませんが、当時は比較的使われた方法です。
フィールドコイルに発生するマイナス電圧を、100Kと500KΩの抵抗で分割して出力管のバイアスに利用しています。
これは半固定バイアスと呼ばれる方法です。
B電圧の利用効率がよい、カソードのパスコンが不要など当時としてメリットがありました。
ただ抵抗が断線した時、出力管が過負荷になるなどの副作用もあります。
このような半固定バイアスの回路は戦前の4ペン(高1)ラジオにもよく見かけます。
動作の原理を理解しておくと良いでしょう。
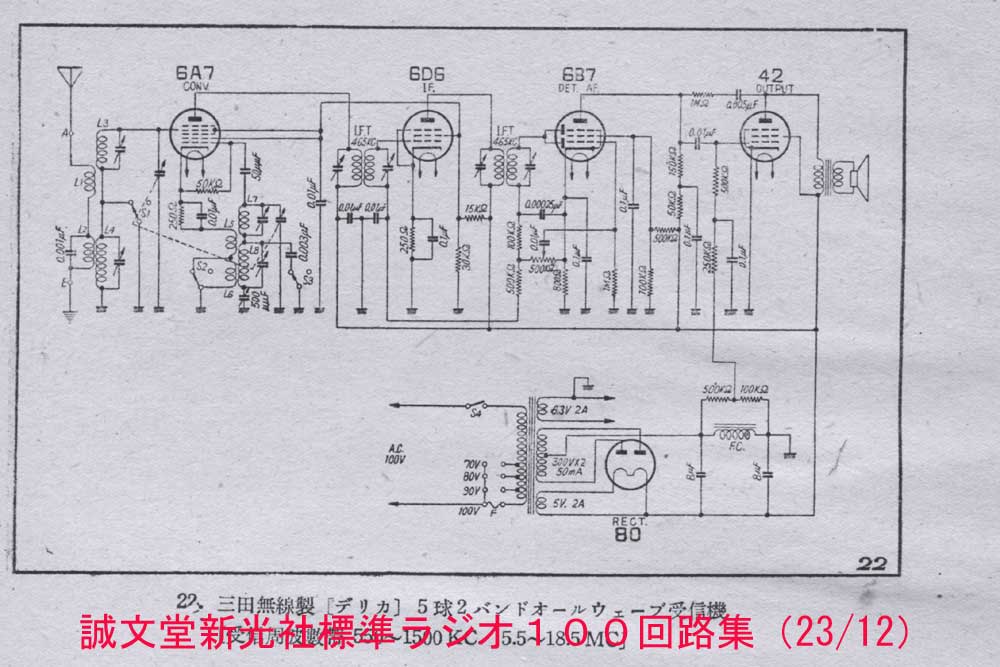
昭和20年代初めに市販されていたシャープ製ラジオの回路。
23年に6W-C5や6Z-DH3が販売されています、6Z-DH3Aは同じく23年発売ですが、6Z-DH3より少し遅れています。
このラジオはスーパー用真空管開発過渡期の製品といえます。
なお6Z-DH3AはNECが最初に発売し、マツダも追随したそうです。
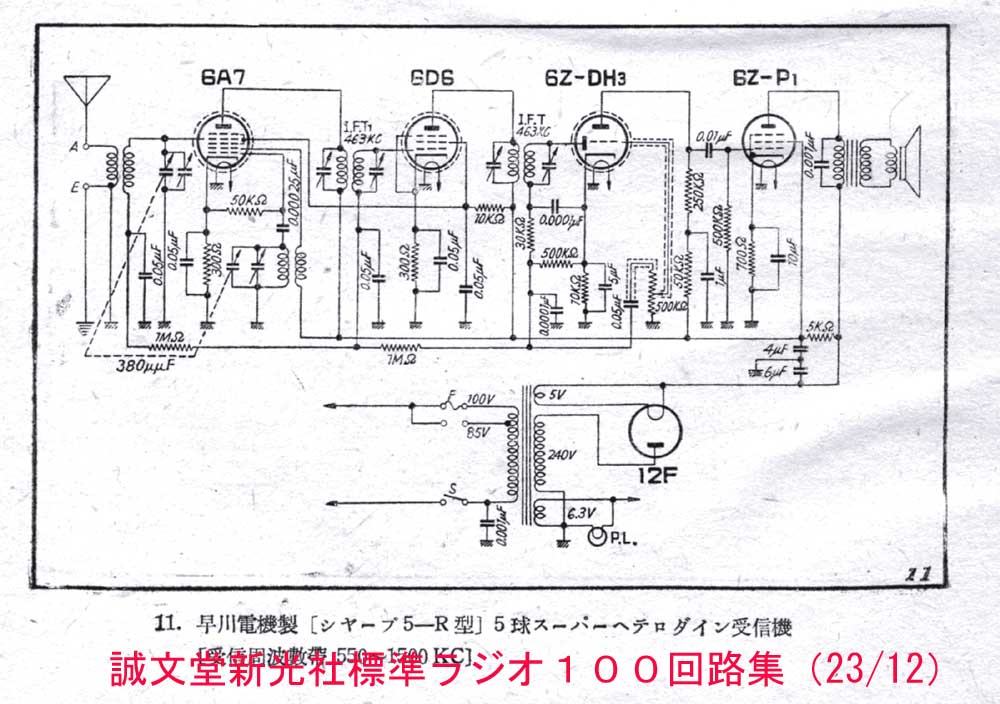
民間放送が開局した時代の標準的な5球スーパーの回路図。
回路も教科書的で、原理を勉強するには非常に良いと思われます。
初歩のラジオと無線と実験の共同編集で、ラジオ実体配線図集 スーパーと電蓄の巻より
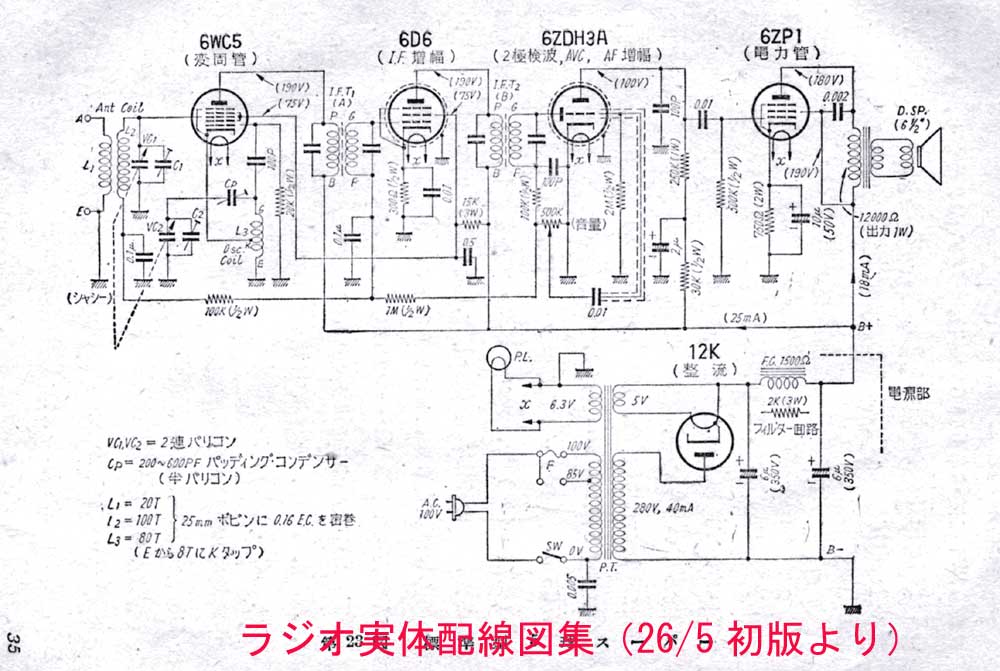
アメリカ製 ARVIN 540T型
子供のプレゼント用のラジオといわれる。
アメリカではおもちゃに近いラジオなのでしょう、ただ感度は馬鹿に出来ません。
IF増幅がありませんが、IFTの1次側にタップがあり、これで12SA7に再生をかけ、感度不足を補っています。
金属ケースに入れられているので、フローティング・アース方式です。
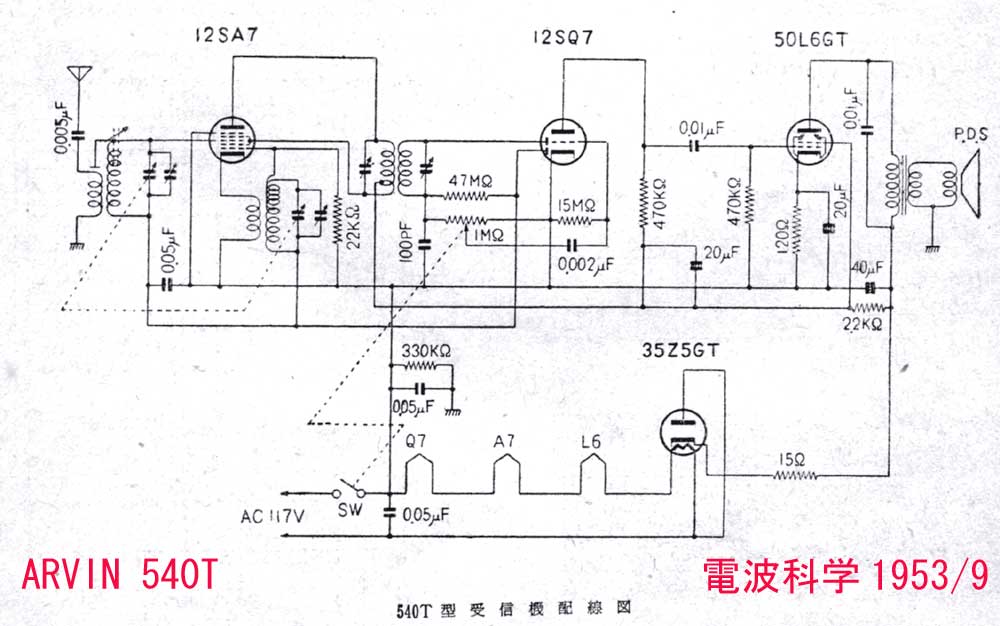
東芝 514A
6W-C5 6D6 6Z-DH3A 42 12F
このラジオは、ここまで省略するのかと思われるほど部品が節約されています。
どこまで省いても大丈夫かという例として取り上げました。
回路で、特に目立つのが、中間集波増幅管6D6のカソードバイアス回路の省略です。
6D5のバイアスはAVCによる電圧のみです。
原理的に利得が落ちますが、実用的には問題ないと割り切ったのでしょう。
PU端子の切替もついているだけで、実際使うと、レコード演奏にラジオが混信します。
アンテナを外す、同調をずらすなどの工夫が必要です。
514Aそのものには、フィールド型のスピーカーが使われています。
パーマネントスピーカーを使った513A型も、ほぼ同じ回路が使われています。
42 12Fの組み合わせは、アンバランスに見えますが、B電圧を下げ、消費電流を少なくして有ります。
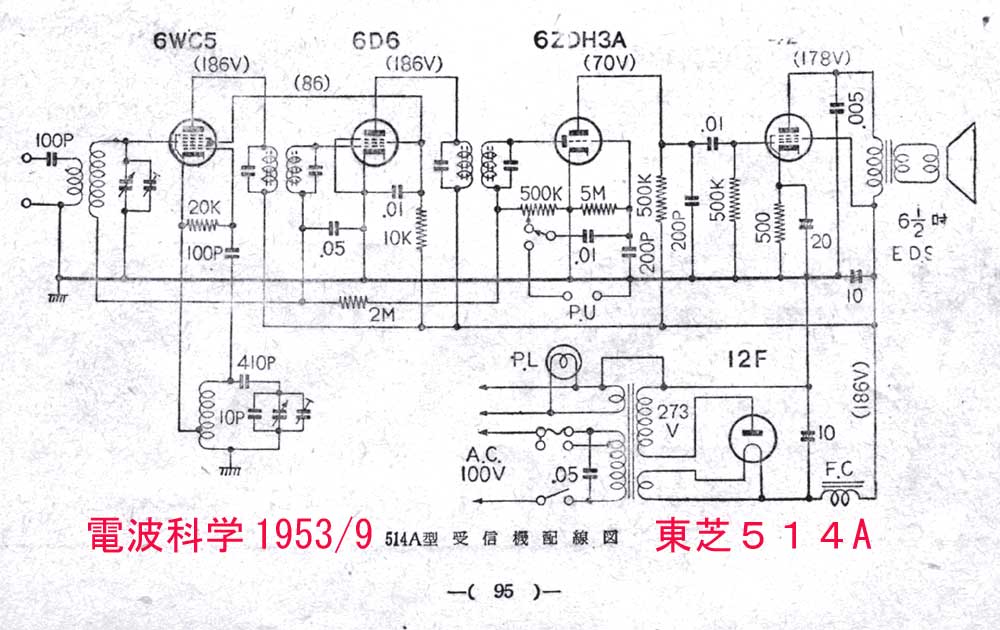
日本コロムビア製 R-524型
標準的な回路図
特にPU入力は入力を切り替えるだけでなく、PUに切り替えた時6W-C5と6D6への10KΩを切断し、ラジオの混入を防ぐ仕組みがしてある。
これは2回路2接点のスイッチつきVRを使っている。
現在ではこのようなスイッチ付VRは入手できないのが悩ましいところ。
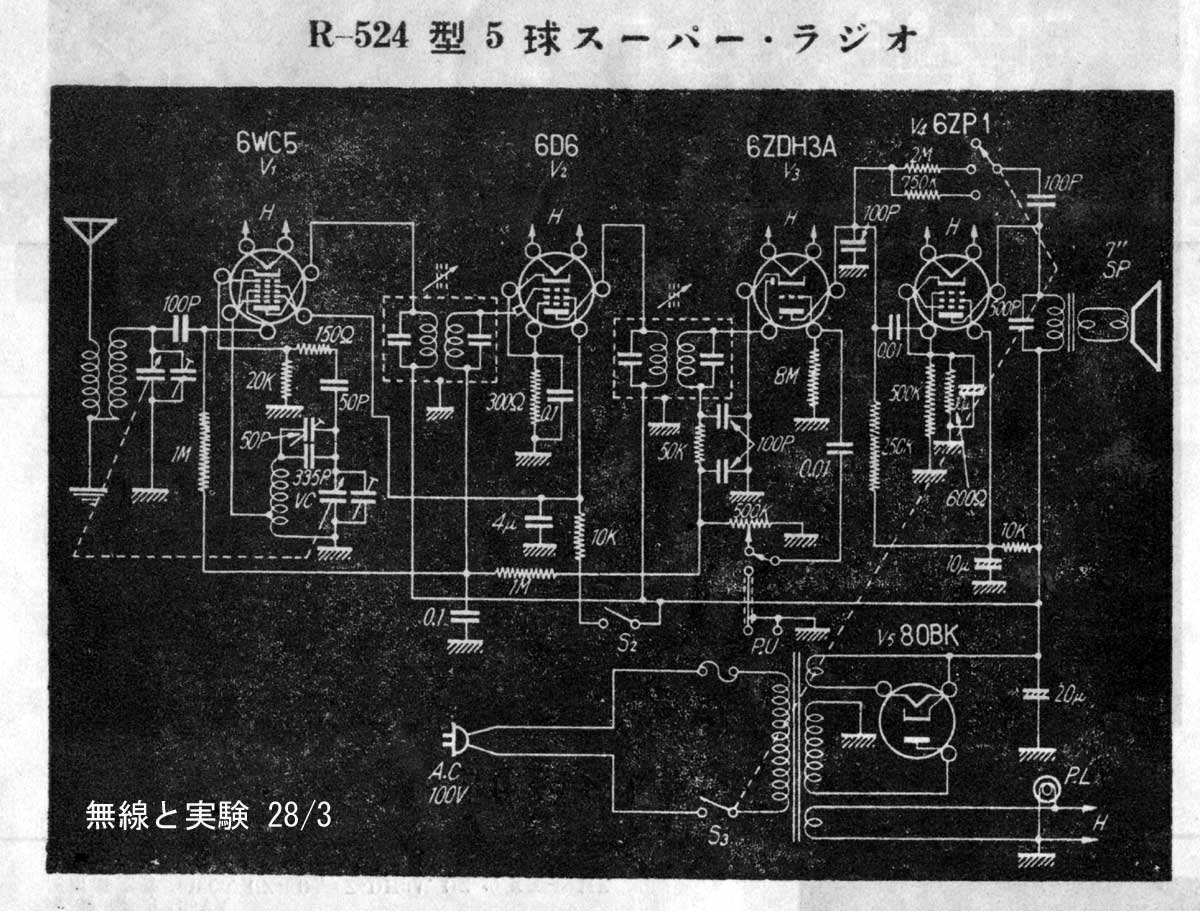
日本コロムビア GT ST混合のスーパー
アメリカではmT GT メタル管と混合使用したものは多いが、日本のメーカーでこのように混合使用は非常に珍しい。
コロンビアとビクターの両社に存在するのは、ある意味で面白い。
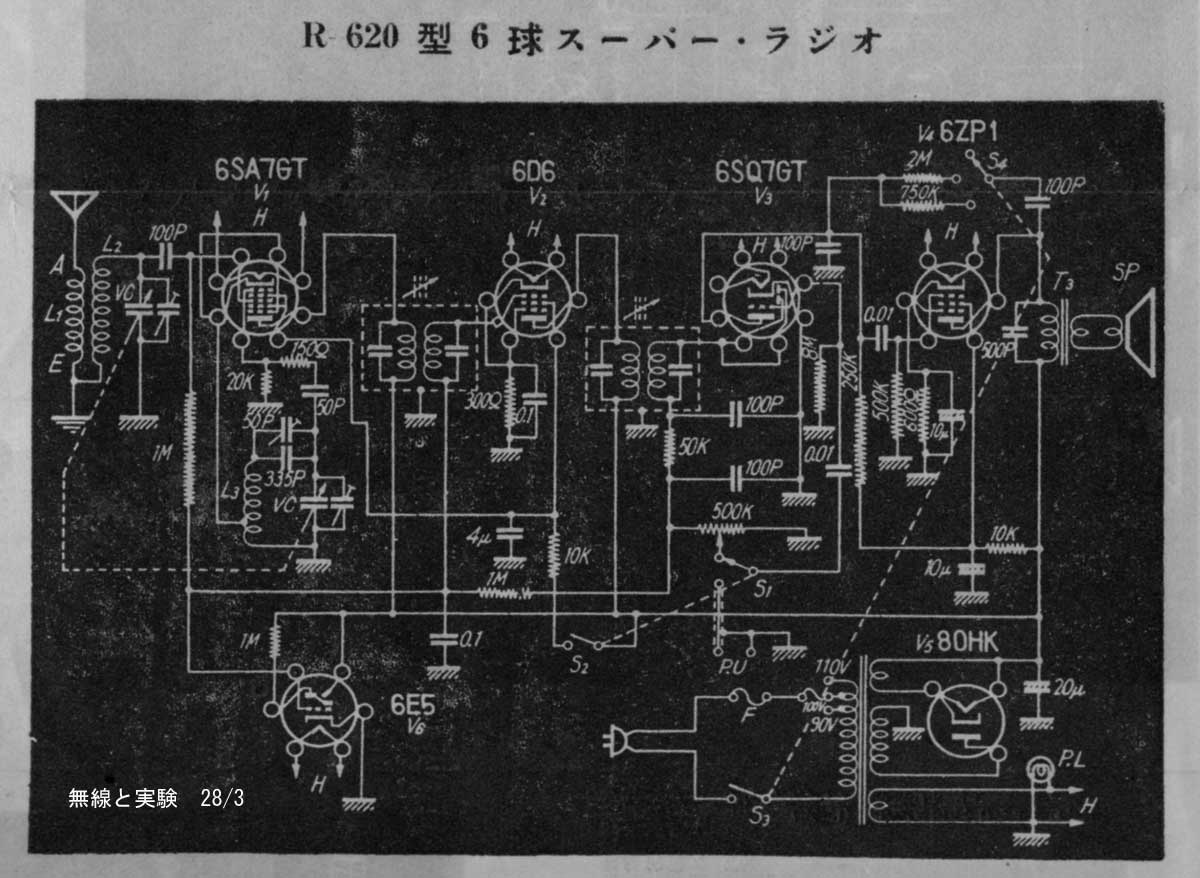
テレビアンで有名な山中電機製のスーパー
PUの切替回路が珍しい、PUに切り替えると発振回路のカソードタップがアースされる仕組み。
発振を止めると、6W-C5の電流が多少増加する恐れがあるが、普通の切替式スイッチ付VRが使えるのが魅力。
回路をまねて応用する時は配線の引き回しで、他の動作に悪影響が無いことを確認する必要がある。
電源トランスのB巻線の電圧が280Vと表示されているが、誤植の可能性が高い、B電圧から推定して230Vくらいか。
AS-4M型はST管ラジオとしては珍しい2バンドタイプ。
当時はラジオ短波(現在のラジオ日経)の開局前で、6~18mcが受信範囲の物が標準的。
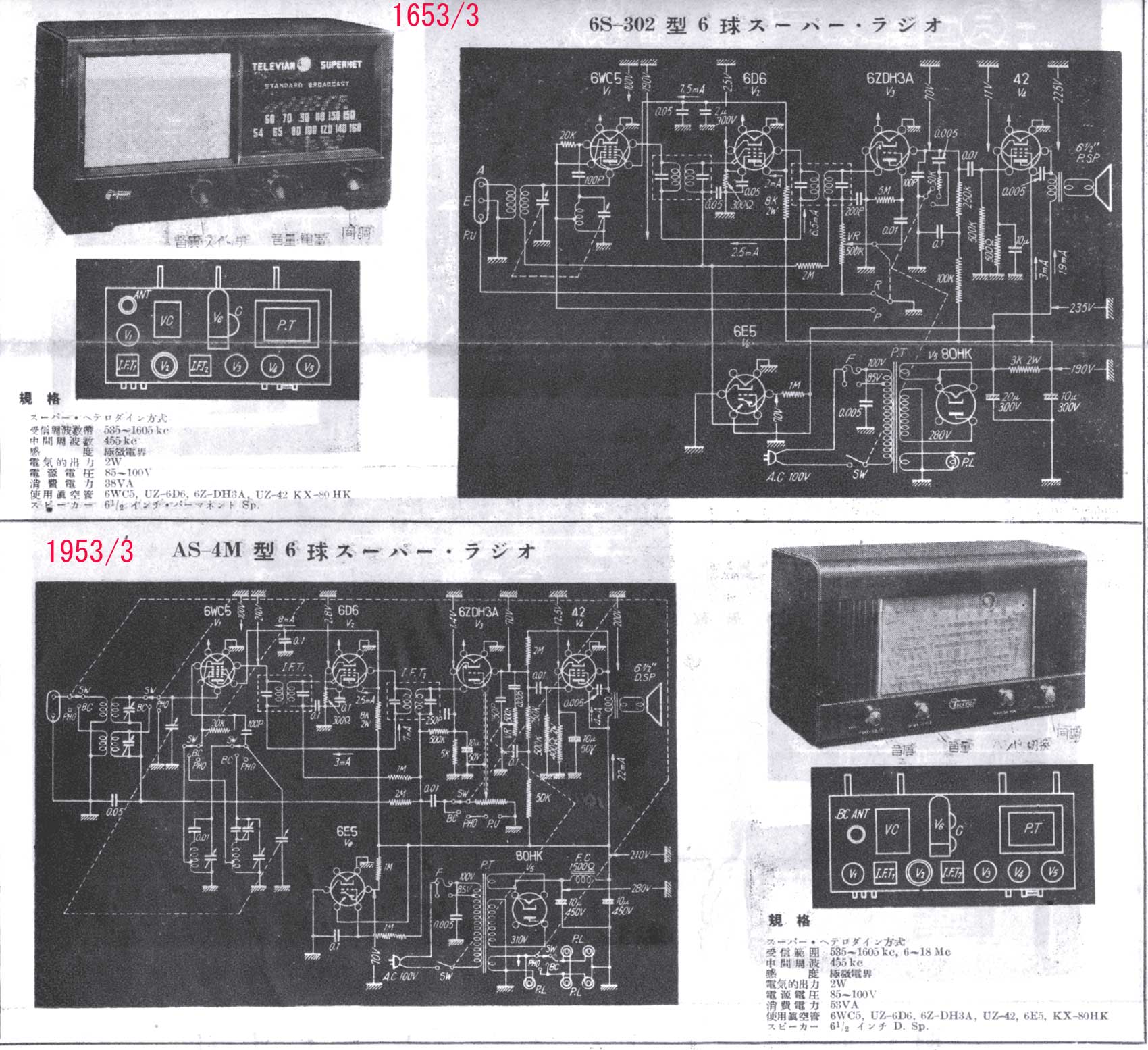
マツダのmT管スーパー 517A型
ミュー同調を使ったスーパーで、日本の家庭用ラジオとしては非常に珍しい。
PU端子の切替も特殊スイッチ付のVRが必要、なお回路図には誤植があります、このままでは不具合です。
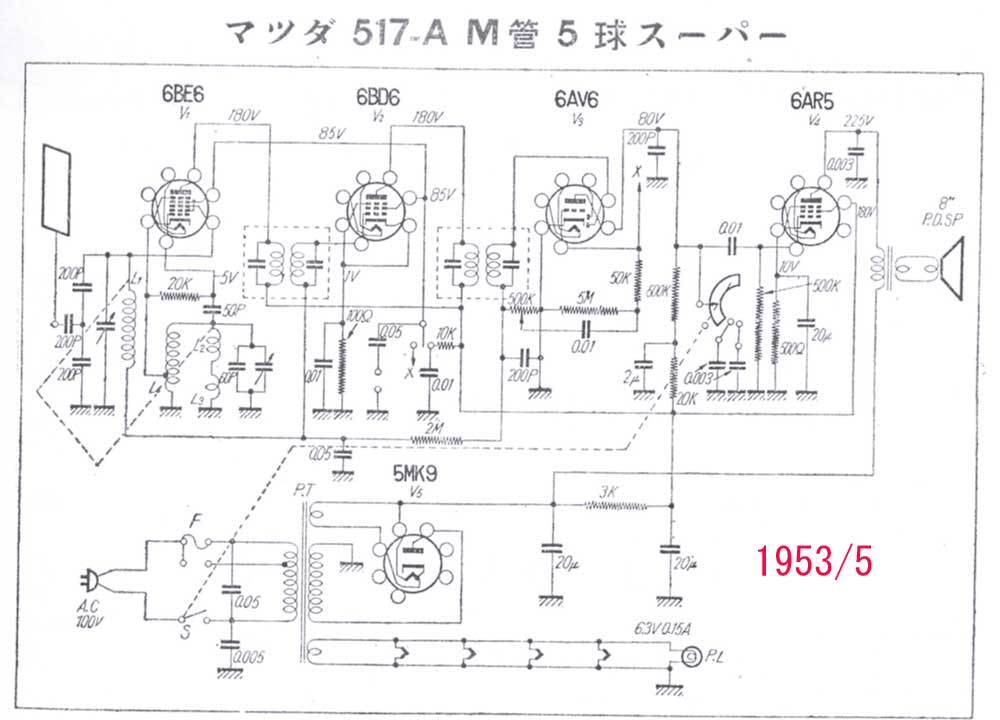
サンヨーのラジオ
ごく標準的な回路構成です、電圧 電流も回路図に記載されているので、参考にするには良いでしょう。
V1 V2 G2電流の値が1.2mAと読めるが、これは6D6 G2回路のみの電流値です。
PU切替もよく出来ていますが2回路双投のスイッチつきVRが必要で、現在では入手が難しい。
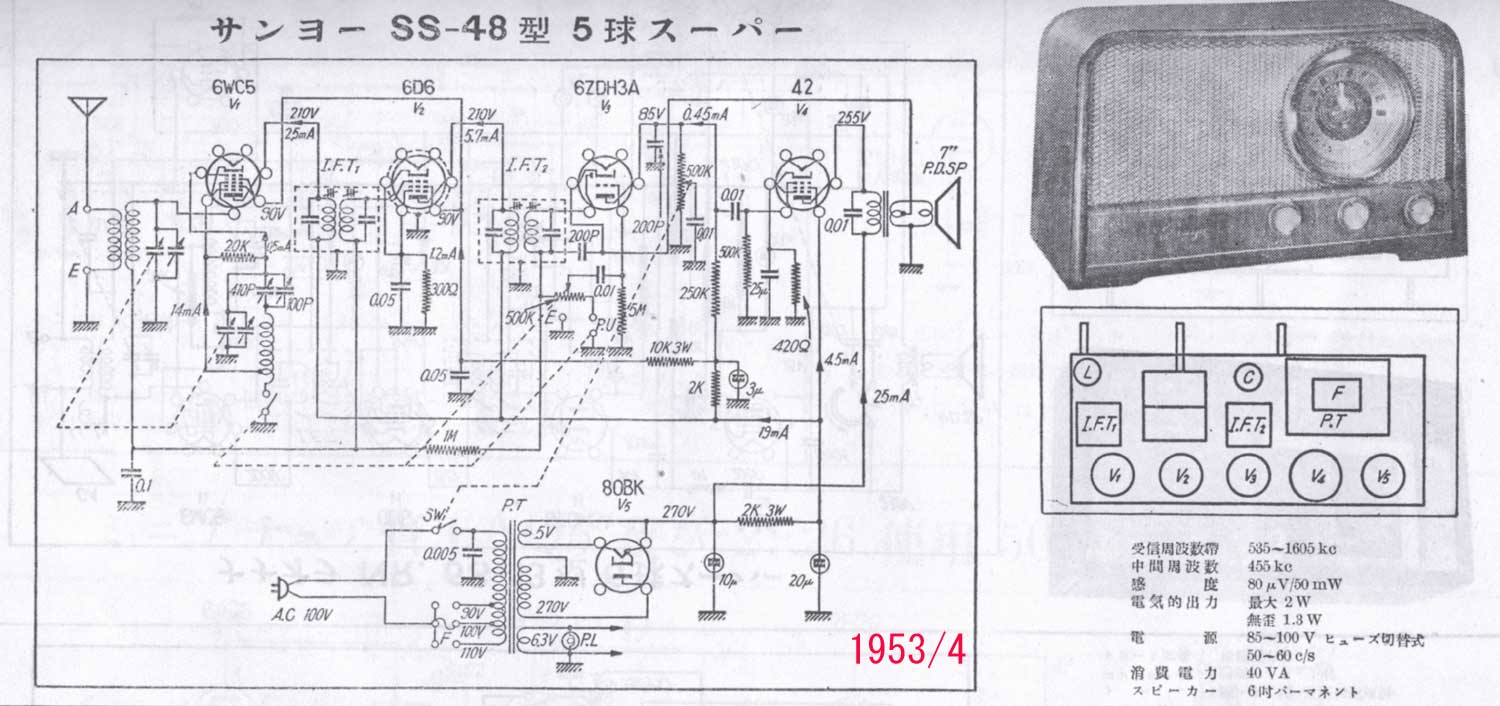
サンヨー SS-55
普及価格のラジオ、PU接続回路も簡略化されている。
V1 V2 G2電流の値が1.2mAと読めるが、これは6D6 G2回路のみの電流値です。
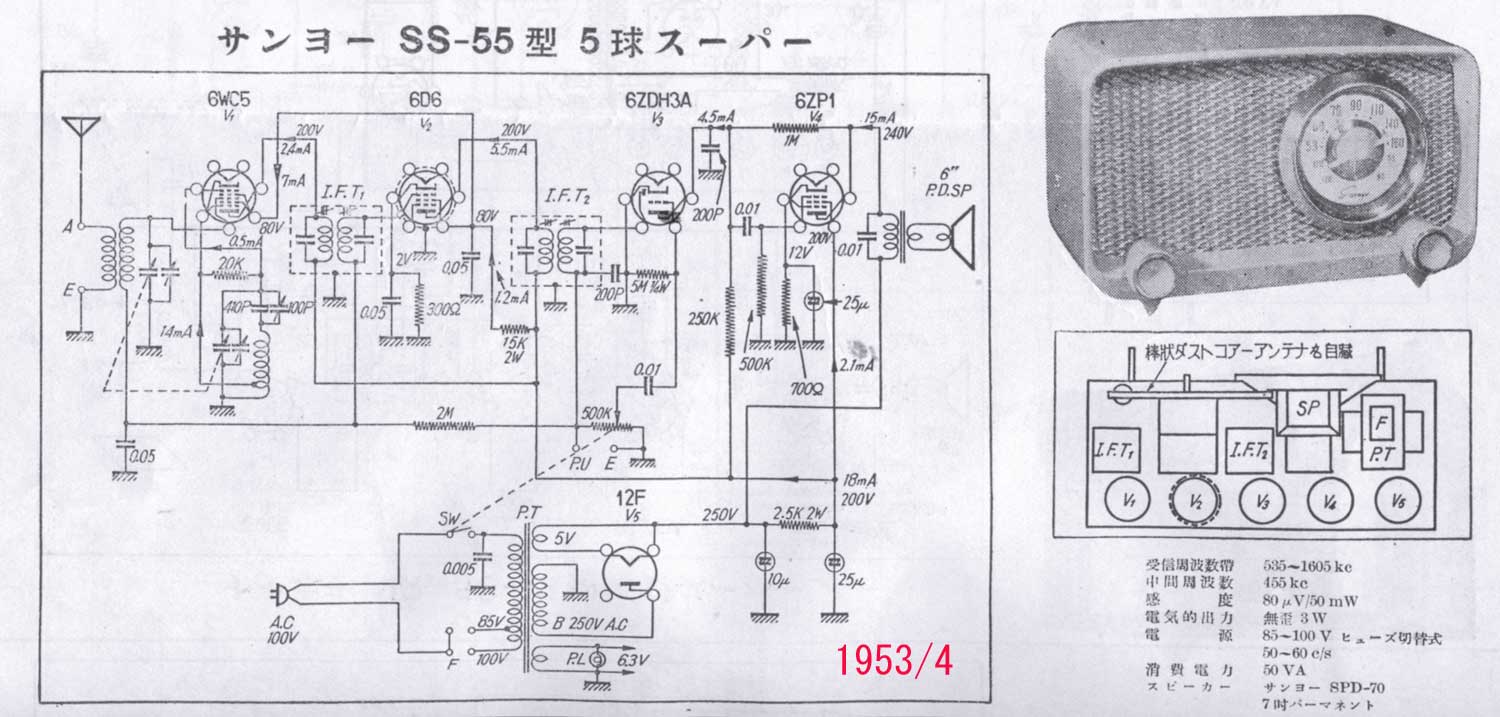
シャープ・サービス・ブックより
シャープの高周波増幅付7球スーパーで当時の高級品です。
電界強度の弱い地域向けに作られたのでしょう。
フィードバックをかけて、音質完全をしています。
発振コイルとコンバーター管発振グリッド(G1)との結合はコンデンサーでは無く、L6と表示した巻き線を使っています。
これはコンデンサーを省いて、安く作るための工夫です。
③PUとラジオの切替は2回路双投スイッチ付のVRが使われています、PUに切替時発振回路を停止させ、ラジオの混入を防ぎます。
AR-330 5R-730の場合、IF回路もOFFにしていましたが、この機種の場合その回路は有りません。
高周波増幅がついていて、6D6×2 6W-C5の3本構成のため、6WーC5をOFFにしてもG2の電圧が異常に上昇しない為と推定されます。
定価 18,000円(昭和28年発売)
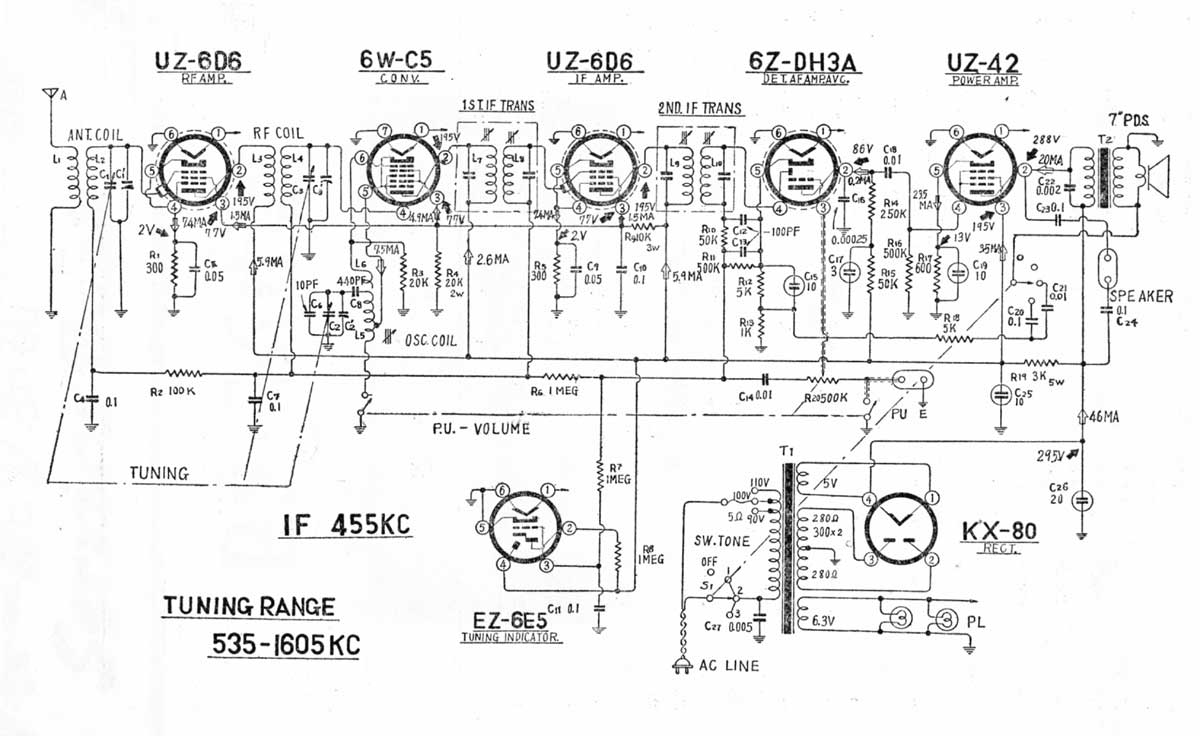
シャープ・サービス・ブックより
高級機種です、電気的出力はRS-350と同じ2W。
発振コイルとコンバーター管発振グリッド(G1)との結合はコンデンサーでは無く、L4と表示した巻き線を使っています。
これはコンデンサーを省いて、安く作るための工夫です。
③PUとラジオの切替は2回路双投スイッチ付のVRが使われています、PUに切替時発振回路を停止させ、
さらにIF回路をOFFにすることにより、ラジオの混入を防ぎます。
定価15,900円
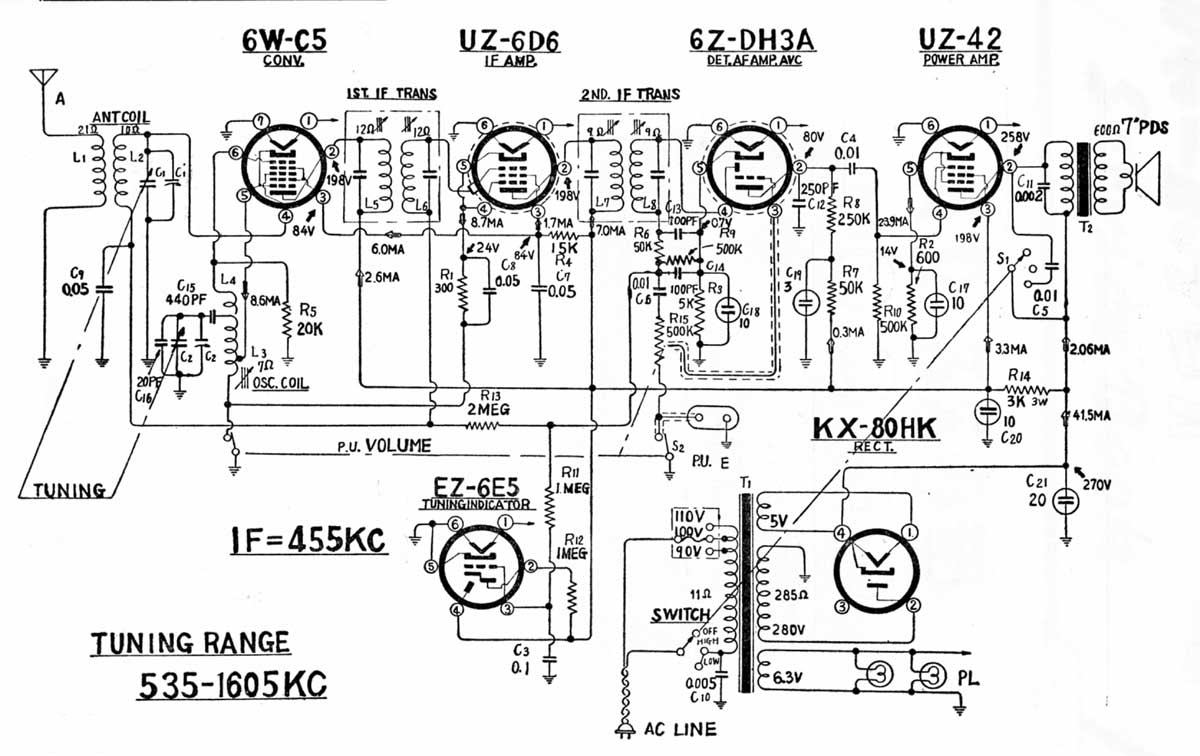
シャープ・サービス・ブックより
標準型スーパーと広告しているが、実際は普及型。
それまでは6Z-P1出力だった物を42出力に変更、その為1.2Wの出力。
定価12,700円。
①12Fの最大整流電流は定格では40mA、出力管42では荷が重いが、G2電圧を下げてB電流を下げる工夫がしてあります。
同じ回路を使う場合は要注意。
②発振コイルとコンバーター管発振グリッド(G1)との結合はコンデンサーでは無く、L4と表示した巻き線を使っています。
これはコンデンサーを省いて、安く作るための工夫です。
③PUとラジオの切替は2回路双投スイッチ付のVRが使われています、PUに切替時発振回路を停止させ、
さらにIF回路をOFFにすることにより、ラジオの混入を防ぎます。
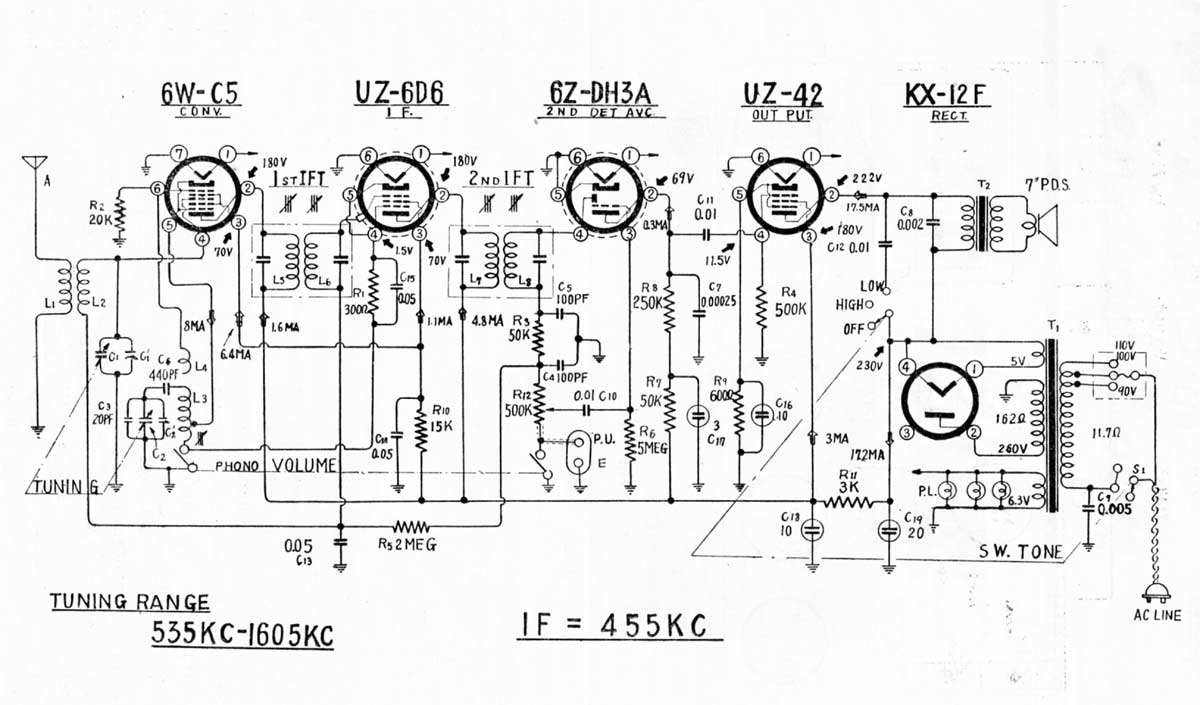
ナショナル・サービス・データより