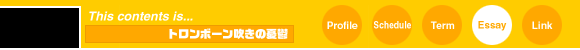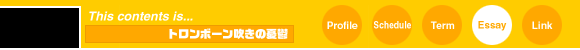バンドマン的短編小説 【 テッド・ヒースを聴きながら 】
ミツオは、そんなに親しくは感じていないバンドの先輩が、自分が住んでいる家の近くにあ
る大きな病院に入院している、ということを聞いて知っていた。が、おっくうに感じて
ずっと行かないままだった。しばらくたったある日、一度は顔を出しといたほうがいいか、という
義務感にかられて、その病院を訪ねてみることにした。
「その方は別の病院に移られましたよ」。
受付でそう言われ、肩透かしと安堵の入り混じった気持ちで帰ろうとすると、窓口に「入
院者リスト」が置いてあるのが目に入った。なにげなくパラパラとめくっていると、警備員が近寄ってきて
「それは病院の資料です、見てはいけません」と、そのリストを激しくひったくった。
「ああ、そうなんですか」と言ったが、その先輩の名前と移転先の病院はしっかり目に焼き付いて
いた。
「ここまで来たんだし、行ってみるか」。
次に行った病院は、前の病院に比べてこじんまりとしていて、さびれて見えた。おまけに窓口が閉まってい
るのを見て、やっぱりやめにしようと、引き返そうとすると、「時間外の入り口はあちら
ですよ」と、見舞いを終えたらしい人が裏口の戸を指さした。
二階の四人部屋の、廊下側のベッドに、先輩は起き上がって本を読んでいた。
一年間だけ、同じキャバレーで働いたことがあった。もっとも、タイバン(キャバレーなど
に入っている二つのバンドのうち時間毎に入れ替わって演奏するもう片方のバンド)だっ
たので、めったに言葉を交わすことはなかったし、それに、知的で服装がオシャレで、演奏
も日本人離れしてあか抜けていて、自分からは遠い存在の人だと感じていた。年齢も二回り離
れていて、それも見舞いをおっくうに感じる要因の一つだった。
「ああ、来てくれたの、ありがとう」。
明るく違和感のない言葉に、うす暗い病室の中で、ミツオは少し和んだ。
馴染まない口調で世間話などをしたあと、「ナニかをと思ったけど、とりあえず『テッド・ヒ
ース』、持って来ました」。ミツオはバッグからカセットテープを取りした。「ああ、いいね」、
先輩はそのテープを、枕元に置いてあるラジカセに入れると、スイッチを押した。
「これ、CDも聴けるけど、操作が面倒くさくて」。
ラジカセからはザーッという雑音とともに「フライング・ホーム」が流れ始めた。「やっぱ
りテープが簡単でいい」と言う先輩の側でミツオは、花とか果物とかの見舞いを持って来ず、聴
き古したカセットテープだけ持って来たことを、少し恥じた。
「イギリスのバンドは端的でいいよね」。
二曲目の「チェロキー」が流れ始めると、先輩は本を置いてベッドに座り直し、周りを気
にしながらラジカセのボリュームを少し上げた。「そうですね」とミツオは言った。が、実はテッ
ド・ヒースがイギリスのバンドだということを知らなかった。サウンドがスッキリし
ていて馴染み易すかった、ただそれだけの理由でテッド・ヒースを選んだ自分を、また少し恥じ
た。
「まだ吹いてるの?」。
三曲目の「ビギン・ザ・ビギン」の途中、先輩が訊いた。「ええ」とミツオは答えたが、その言葉の
力の無さから、自分の演奏に確信が持てないでいるのを見透かされたと思った。自分の取
り得が何なのか、何を目指すのか掴めないまま、バップ、ラテン、ムード音楽から、果ては
歌謡曲まで、あれこれ手を出しては行き詰る、そんな繰り返しの日々まで、すっかり見透かされてしまったような気がした。
「またおいでね」。
四曲目の「インドの歌」のトロンボーンソロが流れ始めたころ、先輩はいつのまにかベッドに体を横た
えていた。「はい、今度はナニを持ってきましょうか」。
柔らかな、それでいてメリハリのあるトロンボーンのソロに聴き入っているのか、それとも眠ってしまっ
たのか、先輩はそれに答えず目を閉じていた。どちらともわからない沈黙が続いた。ミツ
オはそっとベッドに近づきラジカセのボリュームを落とすと、他のベッドの三人に軽く頭を下げて、そっと部屋を出た。
「またおいでね」。
あの言葉から数ヶ月後に、その先輩が亡くなったことを、ミツオは人の噂で知った。別のテープを持
って行くことはないままだった。
「まだ吹いてるの?」
病院での会話をミツオは思い返していた。先輩は、あの言葉に何かを込めようとしたのだ
ろうか。「諦めずに自分の道を求めなさい」という意味の裏返しだったのか、
それとも単に「まだ諦めがつかないの」という意味だったのか。
あれからずっと、モヤモヤしたものが心に引っ掛かっていた。
それからまたしばらくたった頃、ミツオは、
棺桶にあのカセットテープが入れられていた、という話を人づてに聞いた。なぜだか、そのとき少しだけ、心のモヤモヤが
晴れたような気がした。
<完>
この物語はフィクションです。実在の人物や出来事とは一切関係ありません。
|