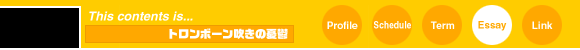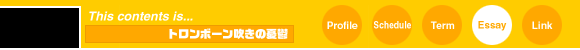バンドマン風短編小説「蜘蛛の意図(下)」
しかしバンドマン界と地獄との間は、何万里となくございますから、いくら焦(あせ)って見
た所で、容易に下へは出られません。ややしばらくくだる中(うち)に、とうとうカンダ
タもくたびれて、もう一たぐりも下の方へはくだれなくなってしまいました。そこで仕方
がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途につかまりながら、遥かに目の
上を見上げました。 すると、一生懸命にくだった甲斐があって、さっきまで自分がいた
バンドマン界は、今ではもう暗の地上にいつの間にかかくれて居ります。それからあのぼんやり
光っている恐しい借金の山も、頭の上になってしまいました。この分でくだって行けば、
バンドマン界からぬけ出すのも、存外わけがないかも知れません。カンダタは両手を蜘蛛の糸に
からみながら、バンドマンになってから何年にも出した事のない声で、「しめた。しめた。」と笑い
ました。
ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の上の方には、数限(かずかぎり)もないバン
ドマンたちが、自分のくだった後をつけて、まるで蟻(あり)の行列のように、やはり下
へ下へ一心によじくだって来るではございませんか。カンダタはこれを見ると、驚いたの
と恐しいのとで、しばらくはただ、莫迦(ばか)のように大きな口を開(あ)いたまま、
眼ばかり動かして居りました。自分一人でさえ断(き)れそうな、この細い蜘蛛の糸が、
どうしてあれだけの人数(にんずう)の重みに堪える事が出来ましょう。もし万一途中で
断(き)れたと致しましたら、折角ここへまでくだって来たこの肝腎(かんじん)な自分
だけでなく、他のバンドマンたちも地獄に落ち着いてしまうかもしれません。そうなれば、
自分だけがエエカッコして閻魔大王様に取り入ることができなくなります。そんな事があっ
たら、大変でございます。が、そう云う中にも、バンドマンたちは何百となく何千となく、
まっ暗なバンドマン界の底辺から、うようよと這(は)い下って、細く光っている蜘蛛の糸を、
一列になりながら、せっせとくだって参ります。今の中にどうかしなければ、糸はまん中
から二つに断れて、地獄に落ちてしまうのに違いありません。
そこでカンダタは大きな声を出して、「こら、バンドマンども。この蜘蛛の糸は己(おれ)
のものだぞ。お前たちは一体誰に尋(き)いて、くだって来た。上がれ。上がれ。」と喚(わ
め)きました。 その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急にカンダ
タのつかまっている下の所から、ぷつりと音を立てて断(き)れました。するとカンダタ
もたまりません。ちょうどゴムパッチンの反動のようにあっと云う間(ま)もなく風を切って、独楽(こま)のようにくるくる
まわりながら、見る見る中に地表へ、まっさかさまに昇ってしまいました。
後にはただ地獄の蜘蛛の糸が、きらきらと細く光りながら、地下鉄もマグマもない地の
中途に、短く垂れているばかりでございます。
三.
閻魔大王様(えんまだいおうさま)は地獄の血の池のふちに立って、この一部始終(し
じゅう)をじっと見ていらっしゃいましたが、やがてカンダタがバンドマン界の底辺へ軽石のよ
うに浮いてしまいますと、悲しそうな御顔をなさりながら、またぶらぶら御歩きになり始
めました。自分ばかりカッコつけて人間を助け出そうとする、カンダタの偽善心ではあるが、
その心相当な許しをうけて、元のバンドマン界へ昇ってしまったのが、閻魔大王様の御目から
見ると、苦々しく思召されたのでございましょう。「これが蜘蛛の意図か、残念・・・」
しかし地獄の血の池のラフレシアは、少しもそんな事には頓着(とんじゃく)致しません。
その肉まんのような赤い花は、閻魔大王様の御足(おみあし)のまわりに、ゆらゆら萼(う
てな)を動かして、そのまん中にあるウコン色の蕊(ずい)からは、何とも云えない酷(ひ
ど)い臭(におい)が、絶間(たえま)なくあたりへ溢(あふ)れて居ります。地獄もも
う午(ひる)に近くなったのでございましょう。
< 完 >
※尚、この「蜘蛛の意図(上)(下)」はフィクションであり、この世に存在するものと一切関係ありません。
|