![]()
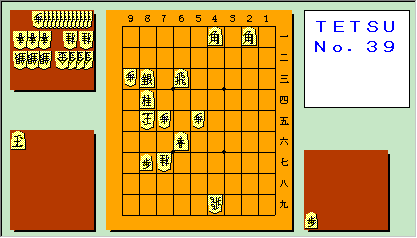 「解答:TETSU-No.39」 SOFTV3 9−2885 1998年11月15日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「明き王手する一手だな。 65飛成とかすると41角をとられて続かない。 ということは、43飛成だ。 待てよ。持駒が歩だから、打歩詰になるかもしれない。 43飛不成かな。」
そうですね。 とりあえず成か不成か保留しておいて、先を読んでみましょう。
「95玉なら96歩、84玉、74角成で簡単。 84玉なら74角成だと打歩詰だな。 あっ、73飛成なんていう手があるぞ。 同玉に74角成まで。 95玉でも75竜までぴったり。 あとは76玉か。」
「76玉でまた明き王手か。 49飛をとるのも有力そうだけど、これで詰んだらきっと余詰だろうな。 素直に47竜(飛)か。 47竜だと66玉で打歩詰。 わかった、やっぱり43飛不成から47飛不成だ!」
(解答1)
▲4三飛生 ▽7六玉 ▲4七飛生 ▽6六玉
▲6七歩 ▽5六玉 ▲7四角成 まで7手きれいに詰みましたね。 でも合駒されたら?
「えっ。 合駒が効くの? えーと。 そうか74桂の捨て合があるな。 同角成なら95玉で打歩詰。 でも、同角不成ととれば。 84玉なら94銀成、95玉でも96歩、84玉、94銀成で詰む。 9手駒余りだ。 変だなあ。」
実は、63歩という打診中合があるのです。
同角成なら、74桂合、同馬、95玉で打歩詰。
同角不成なら、84玉、74角成、95玉で、やっぱり打歩詰。
この形になっては詰みません。「ほかに手はなさそうだけどなあ。」
・・・
63歩合に同角不成、84玉とした局面をみてください。
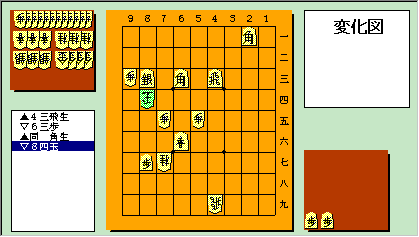
変化図は ▲8四玉 まで
ここで43飛が竜だったら?
「竜だったら54竜があるね。 95玉なら94竜と捨てて、同歩、96歩、84玉、74角成、93玉、92銀成まで。 54竜に83玉なら、74竜、92玉、72竜で詰む。 でも初手43飛成は76玉で打歩詰になってしまうんじゃ」
そうですね。 この打歩詰の局面を良くみてみましょう。
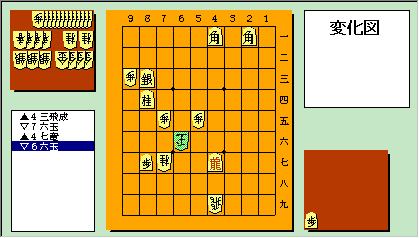
変化図は ▲6六玉 まで
「わかった! 65角成と捨てて74銀で詰みだ!」
(解答2)
▲4三飛成 ▽7六玉 ▲4七竜 ▽6六玉
▲6五角成 ▽同 玉 ▲7四銀生 ▽6六玉
▲6七歩 ▽7六玉 ▲3二角成 まで11手「さっきの中合の変化の方が長かったみたい。 変だなあ」
・・・
それでは、種明かししましょう。
(正解)
▲4三飛成 ▽6三歩合 ▲同 角生 ▽7六玉
▲4七竜 ▽6六玉 ▲6五角成 ▽同 玉
▲7四銀生 ▽6四玉 ▲6五歩 ▽5三玉
▲5四歩 ▽6二玉 ▲7二桂成 ▽5一玉
▲4一角成 まで17手63同角生と取ることで、解答2の74銀生、64玉の変化の63角成ができなくなって、 この順が成立するわけです。
本局、初手43飛不成と見せて、43飛成の順を読ませなくする、心理的構想作でした。
![]()
- YUNO さん:
- TETSU さんの打歩詰作品とあらば解かざぁなるまい (^-^) 。 面白いですね。 明き王手と〇〇中合が交錯して考えさせられます。
正直に言うと、明き王手で紛れを求める最近の風潮を余り好みませんが、 本作は明き王手をしながら同時に明き王手局面を作るのが新鮮です。 ついでに飛不成も入ればなお良かったけど、これは望蜀というものですね。
さっそく見ていただき、ありがとうございます。 それにしても出題から2時間もたっていないのにはビックリ。 いつも朝アクセスされているのかな。
- YUNO さん:
- 大変失礼しました。 原図 (詰パラ昭和49年7月号) を見ていなかったので (当時は冬眠中で捜したら該当号には折り目がなかった) 見当違いの感想を述べてしまいました。 原図 (下記) は飛不成だったのですね。 不詰手順を生かした今度の図のほうがずっと良いと思います。
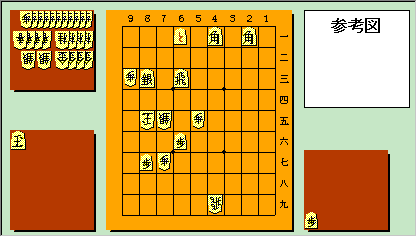
参考図 加藤徹作 詰将棋パラダイス 1974年7月 (不詰)
- YUNO さん:
- しかし、飛不成の初志貫徹は出来ないものでしょうか。 これは桟敷席の無責任な発言です (^-^) 。
原図の解は前述の解答1で、ストレートに飛不成が狙いだったのですが、 本局では、不成がすぐ見える局面での成という、心理的妙手を狙ってみました。
- 首猛夫さん:
会議室のみなさんのおかげです。 首さんも気が向いたらまた感想を書き込んでください。
- 首猛夫さん:
詰工房では、みなさん、素直にはまってくれました。
- 首猛夫さん:
- そうなんですよ。 みなさん! この人は大道棋教室で誤答率8割の作品作った人です。 だまされちゃいけませんよ。 ( 「赤尾敏」 風に。 数寄屋橋での街頭演説は面白かったなあ)
わかっていてはまるのも、また一つの楽しみ。
- 首猛夫さん:
- しかし、私の作品はこれが作意だ!やったーといってからが勝負なんですよ。 その意味では ( TETSU さんの作品は) 正統的な作品ではないでしょうか。 もちろん、評価は高い。 駒が幾重にも意味が重なる作品は必ずと言っていいほど妙味があるものです。
これを読んで、正統ってなんだろうと考えてしまいました。
正調の捨駒作品を尊ぶ人からみれば、妙手のない趣向詰は変則かもしれない。 打歩詰の攻防のような論理的な作品も変則というかもしれません。 要は、何に面白さ、楽しみを感じるかで、現在のように楽しみ方が多様化している時代には、 どれもそれぞれの立場では正統といえるのではないでしょうか。
首さんの作品のように、局面の微妙な綾を楽しむ作品、 大道棋のように、誘い手により心理的に作意を発見しにくくする作品、 本局も、そういった流れの中にある作品ですが、 TETSU にとっては正統といえるのかもしれません。
みなさんにとって、正統的な作品とはどんな作品ですか?
- 首猛夫さん:
- さりげない (でもないか) 84桂あたりに何かヒントが ・・・ 。 おっとおっといけないいけない。 盤上にある何か不自然な、「あれこりゃなんだろう」 というのは必ず裏がある? そんなことがヒントになるというのはいいのですが、 時々迷わせるために 「飾り」 で置きたくなる時もあります。 もちろん TETSU さんの作品にはそんなものはない。
84桂でヒントになる人はかなりスルドそう (^^;
- 波崎黒生さん:
- 橋本龍太郎さんが間違ったというので慎重に解きました。 (^^; 合っているか分かりませんが ・・・・
龍太郎さんの名誉のためにいっておくと、間違ったのではなく、 変化紛れを作者の希望通り順番に読んでくれたのです (^^)
- 首猛夫さん:
- 詰将棋界には橋本姓の天才がたくさんいるんですね。 龍太郎氏の名誉のために言うと、すぐに見えちゃうんです。 図を見てあっという間に、初手はこうだとね。
- 波崎黒生さん:
- □手目の応手にはビリビリです。 この手は□□□とは関係なく、後でその地点での□を防ぐ目的。 不思議やな〜 ・・・・ これもかなり珍しいのではないでしょうか? □□□をからめて他の意味付けを持たせるのは、まだまだ可能性がありそうですね。
□を埋めよ −− 詰パラ×学校入試問題。 みなさんはもうお分かりですね。
- 首猛夫さん:
- 一つの構想が出るとそれを未然に防ぐ手筋や変化に角捨て順などが開発されてきます。
- 波崎黒生さん:
- こういった構想がポロポロ出てくる。 少し分けてチョーダイ! (^^;
- 首猛夫さん:
- いや、そういうあなたの頭脳も少し分けてもらいたい。
結果的に面白い意味付けになりましたが、 不詰になったのをなんとか詰ませようとしただけなので ... ということは、まず、逃れ図式の創作から始めるのはどうでしょうか (^^;
- 首猛夫さん:
- 般若一族の、「今井光問題」 「千山」 「猿知恵」 などはみんな逃れ図式からの出発でした。
- taka−o さん:
- ちょっと横道にそれますが、記憶が確かならば 千日手局面から …… というアプローチもあったような。 龍鋸 (または馬鋸) 作品についてのくだりだったかな? このコメントツリーを読んでいて、ふとそんなことを思い出しました。
夜通しで詰パラの答案を作成していて大寝坊、詰工房には大遅刻。 しらふで詰将棋を見る時間がほとんどありませんでした。 (^^; きょうの横浜は好天で、布団を干してる間に解図です。
そうか、ちょうど10月号の締切り日だったんですね。 眠そうな人がいたのは、そのせいだったのか。
- taka−o さん:
- 持駒歩だし、この形で明き王手をするなら ●●→●● のライン。 とりあえず変化を読んでる途中で裏返すか裏返さないか決めればよかろうと考えてしまったのですが …… 結局、●● を成るか成らないか、さらには ●● をどこに打つのか打たないかまで、 候補をほぼ一通り読むことになってしまいました。
安易な読みの省略が許されないところ、 作意・変化紛れの詰ませかたが意外にアナログなところが、解いていて面白かったです。 「解く」 というのは元来こんなだったかもなあ、とも思ったり。 でも、ひょっとしたらこれがまた誤答だったりして …… (^^;
作意から、変化、紛れまで、フルコースで味わっていただいたようで、ありがとうございます。 変化とばしの術を使うと痛い目に会いそう。 詰ませ方がアナログというのは面白い表現ですね。
- 池田ママス&パパスさん:
- # 詰工房の席上で見せていただいていたんで、ちょっと静観してましたが、 今回もすごい反響ですね。
大顰蹙で感想ゼロだったらどうしようかと思いましたが、ホッ。
- 池田ママス&パパスさん:
- 「何か隠すときには一度捜した後へ隠せ」 とか。 詰将棋も、一度捨てた筋にもう一度かえって考える、というのはやりにくいですね。
# さすがに 「スピード詰将棋」 の手順には落ちないでしょうが、 うっかりすると短い順にを解答してしまいそうです。 「応手に注意」 と言うところですね。
こういう心理的な難しさを狙う問題は、いろいろ開拓の余地があるように思います。
推理小説なら、最後にもう1回ぐらいどんでん返しがあったりして。 実は詰工房で並べた手順も偽作意なんですとか (^^; そこまでできれば首さんですね (^^)
- Ura さん:
- 最初、飛生、飛生の七手詰が見えたので、なかなか飛を成って考えることが出来ません。 2手目の間駒も二重の意味を持つなかなか玄妙な味わい。 49飛も思いのほか重要な役割でした。
作者の狙いをストレートに味わっていただき、ありがとうございます。 新人のころの TETSU には、この合駒が見えなかったようです。
- Ura さん:
- さて、詰将棋を考えるのにも色々なやり方があるようで、 筋ワル生さんのような組織的・緻密な考え方、 佐々木聡さんのように詰まなそうな所から読み始めて変化・紛れを十分に味わうという方法、 私はとにかく詰む手を探すばか詰方法。 今回の出題は私の方法では難航でした。
普通の問題なら 「ばか詰法」 が一番速そうですね。 若島さんのように 「作意 (と思われる順) から読む」 解き方も一種のばか詰法でしょうか。
- Ura さん:
- 以前は寝る前に考えていて、朝起きるとなぜか解けているということがあったのですが、 最近はあまりなくなりました。 またあの夜明けがこないかな?
夢の中で作図してしまう人もいましたね。 TETSU にも1局ぐらいできないかな (^^)
- 天津包子さん:
- 手数が書いてなかったのがいじわるでした。 (解答2の)11手ですネ。 まさか変化ではないでしょうネ。 変化でもいい。 なにか詰め得て得をした感じです。 43飛成のところ不成と思ったり (変化詰まず)、 49飛成と飛を取ったり、紛れにはまりましたよ。
その、まさか、でした。 惜しい。
- 鳥本敦史さん:
- 打歩詰にならないように不成にしても打診中合でやっぱり打歩詰になるとは面白いですね。
![]()
解いていただいたみなさん、ありがとうございました。
また、次の No.40 でお楽しみください。
![]()
本局、詰棋めいと第26号でも出題しました。 そのときいただいた感想です。
解説は安江久男さんです。
初手は飛を開く一手。それも43しかない。 76玉に47龍、66玉で67歩が打歩詰。 はは〜ん不成かと、こんな手順が映ります。
43飛生、76玉、47飛生、66玉、67歩、56玉、74角成まで。
これでは曲がありませんね。
そう、76玉の前に74桂という捨合があります。 同角成は95玉で打歩詰。 飛角連続不成、いかにも作意風ですが変です。 95玉、96歩、84玉、94銀成は駒余り。 捨合する前に、更に一本飛角の交点へ63歩と打診中合する手がありました。同角成は今度こそ74桂合で不詰、といって不成では84玉でこれも詰みません。 あらら、頭が混乱しそうですね。
ここで43飛が龍ならばどうでしょう。 63同角生、84玉に54龍が効きます。
種はここにありました。 しごく当然と思われた初手の飛不成が実は作者の仕掛けたワナ。
打歩局面を回避するため当然と見えたのですが、念のため初手43飛成を掘下げてみましょう。
43飛成、76玉、47龍、66玉、65角成、同玉、74銀生、66玉、
67歩、76玉、32角成まで。
打歩局面は43龍でも打開できました。 するとこれが作意?
いやいや、63歩合、同角生、84玉の変化のほうが長そうですよ。 作意を見て下さい。
43飛生の紛れに対する逃れ手筋として用意された63歩合が 76玉と逃げる作意にもしっかり効いているのですから、まあ贅沢なものですね。
大橋健司さんに「ドラゴンパラドックス」という解答者に飛をひっくり返させない名作がありますが、 そのミニ版とも言うべき心理作でした。
- 里見良幸さん:
- 43飛不成から47飛不成は詰将棋の真髄。
- 平井正敏さん:
- 歩詰には不成有で、とどめは74角成ではなく74角不成と思われる。 これで不成作品となる。
- 田口正明さん:
- 降参です。 43飛生、63歩、同角成、74桂、同馬、95玉 で手の施しようがない。 初手は合ってそうなんだけど無念。
お三方ともペテンにハマってしまいました。
- 穂上武史さん:
- あっさり成ることの難しさ。
- 阿部健治さん:
- 初手、なかなか飛が裏返せなかった。
- 今川健一さん:
- 攻方の飛車の動きは面白いですね。 中合不成と盛り沢山だが収束はダラケる。
- おかもとさん:
- 深謀遠慮、虚々実々、その2。 よく見ると、最終手も限定でした。
- 金子恒男さん:
- 49飛を忘れて調子に乗りそうな展開。
- 久後生歩さん:
- 中合いが桂か歩か考えさせられる。
- 鈴木芳己さん:
- 歩合、角生等々。
- 天津包子さん:
- なーるほど。中合してから上へ逃げるのか。
- 橋本哲さん:
- 飛不成が第一感だったが・・・。
- 橋本守正さん:
- 飛の直角の動きが鋭い。
![]()
鑑賞する| 次(発表順)| 次(コース)| 作品一覧| 表紙に戻る
![]()