なまずの話
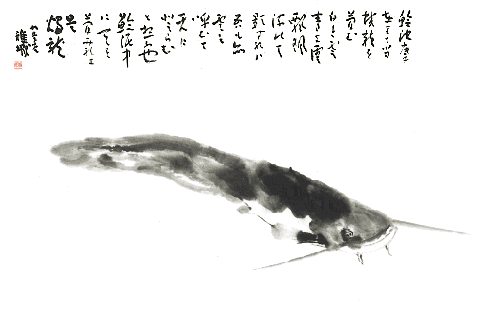
なまずの話 阪 本 雅 城
なまずを描いて、かれこれ三〇年になる。
別に深い動機があつて鯰を特に選んで画題にしたわけではない。ただ鯰というやつが妙に野趣みたいなものがあり、どこかにトボケたところがあるのが面白いと思つたのである。鯉や鯛を描くえかきは沢山いるから、それはその人たちにまかして、自分は魚なら鯰一本ときめたのである。
はじめは水槽の大きなのを備えつけて、その中に鯰を放つた。そして明けても暮れても鯰を見て暮らした。 時々そいつを出して、皿の上にのせて写生をした。右に向けたり、左に向けたり、裏返しにしたりして、細かく写生をした。鯰が弱つてくると、近くの川へ放つてやる。水槽で死なすのはいやだからである。
群馬県に実家を持つ女性が、泊まりがけで鯰をとりに行つてくれた。彼女の兄弟が夜中にたんぼのドブ川に梁を仕掛けてとつてくれたのを、朝一番の汽車で運んでくるのである。雷魚までいつしょに持つてきてくれたが、この雷魚だけは描く気にならなかつた。鯰は三年子と言うのが、最も堂々としている。一年子や二年子とは比べようもないほど貫禄をもつている。
世の中には親切な人が多く、鯰が好きだとなると、方々から鯰を持つてきてくれる。土浦市に蓮田の農場をもつYさんなどは、鯰をとりにこいと、時々電報をくれる。行くとわざわざ蓮田の水を汲み乾して鯰をとつてくれるのである。大きな蓮田だから、水を汲み上げるのにも電気仕掛けのモーターだから大がかりである。こんなわけで、年中鯰にはこと欠かないのである。
かくして、ようやく鯰をのみこむことができた。しかし、とは言うものの新しく見るたびに新しく発見し、気がつかないことに気がつく。写生というのは、繰り返し本を読むようなものである。また人が、いろいろに教えてくれるのである。こどもの時から鯰釣りの名人がいたり、鯰の生態についてくわしい人がいる。色、形、動作、性癖などについても、驚くべき知識をもつている人がいる。それらの人たちが、画を見て感想をのべたり注意をしてくれるのである。それらは、すべて生きた経験であり、実地の観察によるものだから力強い。「君の顔が鯰に似てきた」と、友人が笑うようになつた。悪口と知りながら、満足すべき状態に吾ありとほくそ笑むようになつた。
かくして、鯰というものがわたくしの腹に完全に入いつてきた。眼をつぶつても、眼裏に鯰がいとも鮮やかに浮かぶ。鯰の背ビレをつまみ上げたと想像しただけで、その感触が手の先きに伝つてくる。その鯰のもがき、重量がそのまま感じられる。ゴションと体をゆすると水がはねかえる態までが感じられるのである。 ところが、そこまでいつても、それがすぐ画になるものではない。まさに画は鯰であるが、鯰の本性が掴まれているとはいえないのである。じぶんでは、鯰と一枚になつているつもりなのだが、なかなかそこまで行つていないのであるらしい。鯰になりきり、物我一体の境地にならなければならないのだが、この一枚は口では易しいが、容易なことではないことがわかる。
わたくしぐらいまでくると、鯰らしい画は描ける、しかし、鯰らしい画から一歩出て、鯰そのものが描けるようになるのが大変である。いや、鯰そのものは描けるのだが、更に、そこを脱け出た鯰、鯰であつて、なお鯰でない、鯰でなくてやつぱり鯰であるところの何ものかが描けるようにならなければならぬのである。
写生だけで画ができるなら、画ほどやさしいものはない。しかし、ほんとうの画というものはそれは大変なものなのである。白隠や仙崖のような高僧で、しかも画の方でも名手である人たちの作品でも、全部が全部物我一如の境地に至つているかというと、必ずしもそうではない。画というものは(わたくしのいう画とは南画を指すのであるが)気合いの芸術であるということがわかる。気合いの乗ると乗らないと、充つると充たざると、いろいろな場合がでてくるのである。画というものは、まことにむずかしいものである。