”湘南市合併”は誰のため?
95年の「合併特例法改正」以降、合併を推進するためのお膳立てが次々と旧自治官僚によって進められました。
下記のように、主には、05年3月までを時限とした補助金等による誘導政策です。
また、旧自治官僚から都道府県に出された「指針」は「市町村の主体的な取り組みが必要である」とうたう一方、「市町村の合併パターンは都道府県が作成するものとする」と決めつけ、「新指針」では「市町村合併の推進はもはや避ける事のできない緊急の課題」と断じる上意下達のやり方です。
各省庁の官僚の出す「指針」「通達」の類は通知されるだけで、都道府県はそれを「命令」と解釈し、市町村に対して同様の「強制」が行われる仕組みで、中央官僚の意向が法制化を待たずに貫徹されているのです。
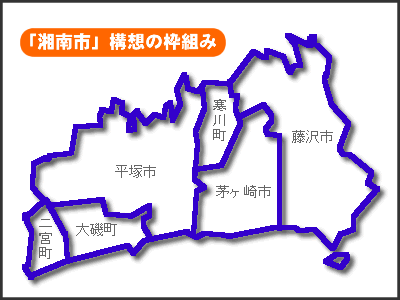
・有権者の2%(50分の1)の署名で、設置自体が「合併を前提とした」法定合併評議会(※1)を直接請求できるようになる
・合併後5年間は従前の地方交付税を継続する特例期間を設けて財政支援する
・地方交付税を継続する特例期間を合併後10年に延長(※2) ・合併特例債の発行可(※3)
※2 合併後10年は、しなかった場合の普通交付税の全額保障。国はその後に地方交付税の大幅削減を果たせるのです!
※3 最大で事業費の95%までを地方債(借金)発行でまかなえ、元利の償還70%を地方交付金で保障。こうしてまた、地方財政の赤字増による「合併バブル」の懸念が・・・・・・・
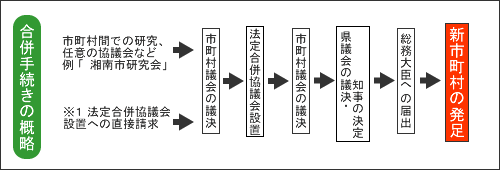
合併を巡る急展開は、行革大綱の示すように、地方財政の借入金残高が01年度末で188兆円と見込まれる中、将来、地方に対する国の負担を減らしていくためのもので、「自立した地方財政を」と自らの既得権益を手放さずに合併議論を主導する国家官僚の裁量の下に進められているのです。
議会がはじめて説明を受けたのは2月22日の議員全員協議会。以下はその議論の要点です。
「(中核市でやっている事はほとんどやっている状況で)私自身はつまらない。グレードの高いというとおかしいかもしれないが政令市を目指したい」「もっと強い財政力と組織力を目指したい」
「2市3町の首長は、将来的にも合併をしていっていいものではないかとの思いの中から研究を進めていこうという事」
「交付税の事とかもどうなるのか、それもこれから(研究する事)。このままだと自治体はどんどん衰退していってしまう」「県や国からの話しでは全くありません」
「選挙で問うという形もある。私はどうしようか考えていますけど(笑)」
与党会派 市議 「多いに研究し情報を出して欲しい」「早く茅ヶ崎市をどうにかすべきでは」
原田 「議会への説明があまりにも遅い。議会軽視では?」「研究会の議事録は公開するのか」
市長 「全部、議会に問わなければならないというものではない。とんでもないと言うのであれば、議会で予算を否決していただくしかない」
原田 「推進している人だけで話し合って、合意したものだけ情報公開するというのであれば、メリットだけ出てくるのは当たり前。意見の違い、それがどういう問題なのかも出して明らかにすべき。その用意もなく『研究会は議論する場であって一定の方向に結論を導くものではない』と言っても、そもそも信用されないのでは?
市長 「研究会が信用あろうとなかろうと、それはあなたの判断で私には言われたくない問題(怒)」「さっぱり分からない。答えたくない」「議事録の透明性というがこれは私一人で決められない。研究の成果という事ではこれからも発表していこうと思います」「絶対主義の市長を求めているのか?他の首長と話し合って決めていかなければならない事で、私も藤沢の一市民として言わせていただければ、それを伝えるという形になるわけでございます」
原田 「・・・?(苦笑)」
※検索については掲載が次議会直前で遅いのですが。http//www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gikai
議会も「湘南市研究会」や市長に対して「デメリットも示せ」というだけでは、事の本質を明らかにすることは不可能だという事です。
どこから合併議論がはじまったのか?市民生活はどうなるのか?財政力アップは本当?・・・・等々、誰のための合併なのか、問題点をシリーズで明らかにしていきたいと思います。