当然の成り行き『介護保険の破たん』
政府が当面の保険料軽減・徴収延期などの「特別対策」を打ち出したのに対して、野党の民主党などは「選挙対策だ」と批判し、予定通りの実施を求めてきました。けれども、総選挙を控えた自自公政権が「これでは選挙を戦えない」ほど「介護保険制度」は破たんがあらわになってきているのです。
「破たん」に頬かむりをしたまま四月実施につじつま合わせをはかる厚生官僚。財源も権限も与えられず実務処理に忙殺される自治体。 黙っていれば、ツケは、介護を必要とする人、保険料・税を負担する国民に回ってきてしまいます。
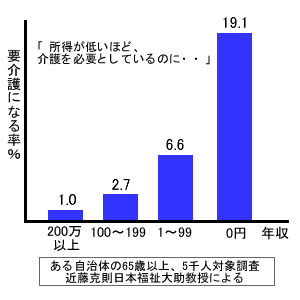
カネ次第「介護保険」は福祉ではない!
要介護の1次判定を行うコンピューターソフトが実態とかけ離れた結果になる事について厚生省は「直ちに、ソフトを見直す必要はない」と開き直っていますが、2次判定は一人に対して審査に平均5分の時間も保障していないのです。
本人の身体的能力だけを基準にし、本人の意思や家族等の生活環境を無視して判定をするやり方は、厚生省が最初から「提供サービス総量」を限定する意図を持って制度を進めようとしているあらわれです。
また、サービスを提供する業者は、利用料の1割を直接利用者から受ける事になるので、金払いの良い方が優先されたり、保険外の追加サービスを買う事のできる高額所得者に集中する事が予想されます。
業者の情報開示義務や規制は無いに等しい情況で、苦情を市の窓口に言っても県の介護保険審査会で不服申立てを行い、回答の期限も約束されていません。
「介護保険」で「サービスの選択が可能になる」と宣伝されましたが、逆に業者が利用者を選別することが懸念されるているのです。
65歳以上の保険料は、自治体が決める基準額をもとに、高齢者の所得に応じて最大1.5倍〜最低0.5倍と階層毎に区分されます。つまりどんな高額所得者でも最低ランクの3倍の保険料で済み、しかも最高税率50%(課税所得1800万円以上)の高額所得者を例に取ると保険料も半額は還付され、所得ゼロの層より安い保険料になる異常な逆転ケースもあり得るのです。
一方、生活保護ギリギリで生活してきた世帯からも保険料を徴収し、未納・滞納者にはサービスの停止や削減が設定されています。月1万5千円以上の年金受給者は保険料を天引きされますが、年金だけに頼る高齢者世帯は5割を越えるのです。厚生省は保険料・利用料の減免措置を「特別な事情」で許可していますが、大震災や世帯主の死亡などに限り、「低所得」はこれに当たらないとしています。
与党の「特別対策」は期限付きで、完全実施されれば、2兆円の増税が低所得者層を直撃するという介護保険の本質を明らかにしたに過ぎません。国民年金対象者の3分の1が支払わない今の状態の上に新たな負担が成り立つわけがないのです。
「介護保険制度」以外の選択肢が、広く議論される事なくここに至りましたが、「公的介護保障」は介護を必要としている人の、所得や家族形態、年齢に関係なく提供されるべきです。障害者は真っ先に除外され、低所得者層を排除する原理の保険方式は福祉とは言えません。保険なら「権利性の確保」になるという意見がありますが、義務教育も税金ですが当然の権利として誰もが認識していますので、税方式はダメという結論は早計です。特に、税は税でも社会保障の財源としては、高額所得者や企業が応分の負担をして、累進性で所得再分配が働く直接税を中心に考えるべきではないでしょうか。
介護保険とは、「介護」を家族介護支援という政策に永年止めてきた厚生省の責任を棚上げにして、破たんした医療保険の原因を高齢者医療費にのみ求め、国民への負担増で大蔵省からも独立した財源を手にするという厚生官僚のご都合の賜物なのです。
長引く不況に、介護保険による国民負担増は政策としても最悪です。不要不急の公共事業に毎年10兆円、金融機関の破たんには60兆円以上の公的資金が投じられ、待ったなしの介護にどうして2兆円の税金が回せないのでしょうか。税金をどこに使うのか、それを問う事のない永田町の政治に存在意義はありません。一緒に市民の党をつくりましょう!
ある自治体の65歳以上 5千人対象調査 近藤克則日本福祉大助教授による 「所得が低いほど、介護を必要としているのに・・・」
利用者が直接、民間からサービスを買う事となる介護保険では自治体の直接の責任はなくなるのですが、無責任な国に振り回され介護保険の実態を誰よりも知っている地方行政が、国に対してどのように発言していくのか。民間事業者との関係はどうなるのか。何より、保険以外のサービス提供を自前でどれだけ充実させていくのか・・・判断が問われているのです。
厚生省は昨年9月、実習先の施設側の受け入れが限界になったため、ヘルパーの資格に必要な実習時間の半分を「模擬実習でもよい」と変更。「保険料取られて、サービスなし」との批判回避に、2004年度まででホームヘルパーの整備目標を「現行17万人から35万人」としたのですが、数合わせが顕著になってきているのです。
|
派遣
|
身体
|
家事
|
合計
|
|
回数
|
49037
|
59747
|
108784回
|
|
時間
|
67749
|
99555
|
167304時間
|
一方、介護サービス事業者のある大手では、「ヘルパー2万4千人稼動のためには、給与面に不満を持ち辞める人がかなり出てくるだろうから4〜6万人の登録ヘルパーが必要」とし、8割を非常勤で雇う計画との事。不況、就職難に研修者は急増しても定着せず、人材は育たないばかりか社会的地位は一層低下します。
藤沢市の場合、市が100%出資してきた財団法人・社会福祉事業協会が公的ホームヘルプサービスを行なってきましたが、やはり市の正規職員は13人で、サービスの約90%は時給で働く登録ヘルパーが担っていたのです。
|
利用世帯
|
派遣回数
|
派遣時間
|
週あたり一件の平均介護時間(h)
|
|
|
98年
|
1593
|
108784
|
167304
|
2.0
|
|
97年
|
1340
|
91643
|
150949
|
2.2
|
|
96年
|
1105
|
78592
|
133730
|
2.3
|
介護保険においては、介護の必要を認定された人のケアプランを作成する立場となるケアマネージャーの責任が重大です。ほとんどが介護サービス事業者に所属する立場から、利用者の立場に立ってプランを立てるにも「業者のセールスマンになってしまう」という懸念があります。ある大手企業のケアマネージャー募集説明会では「(重度介護者が)死なない程度に長生きしてもらう介護を」との要請も。利用者に親身になれば雇用主の利害と対立し、板挟みになる事態もあります。
ケアマネージャーが、自立した専門職として育っていく事は、介護保険の行方にかかわらず、安心介護に責任を持つ有能な人材が不足している現場に緊急に求められています。
単にケアプラン作成だけでなく、計画変更の必要等を継続してフォローし、逆に事業者の介護サービスが計画通り実施されているか、苦情処理などの窓口になれば、チェック機能にも実効性を持てるのではないでしょうか。そうした人材を育てていく環境づくりに、公的な投資が不可欠です。
介護保険対応のサービスが貧困なものにならざるを得ない中、保険外の介護計画についても利用者に応じて責任を持ち、生活地域で在宅介護と施設介護の垣根を取り除いて、総合的なニーズ判定の出来る人材が必要です。そのような介護のプロさえいれば、公的な資金で民間にもっとサービスを求めていいわけです。
現状では24時間介護等、要介護の潜在的な要求にとても応えられていません。
介護予防においてもヘルパーの役割・社会的な地位は見直されるべきなのです。
「医療費高騰の元凶は高齢者医療だ」と介護保険を作り、一方でまた医療費を値上げし看護婦増員すら出来ずにいる厚生省こそが元凶です。官僚にかわって市民が政治を動かし、介護のプロを育てていけば、やはり医療費抑制も可能です。
藤沢市も、税金で蓄積してきた人材を活かし、介護のプロ育成を放棄すれば、それこそ「税金のムダ使い」とならざるを得ません。人材の育成に投資し、民間も含めたサービスの質向上に行政が責任を持つべきではないでしょうか。