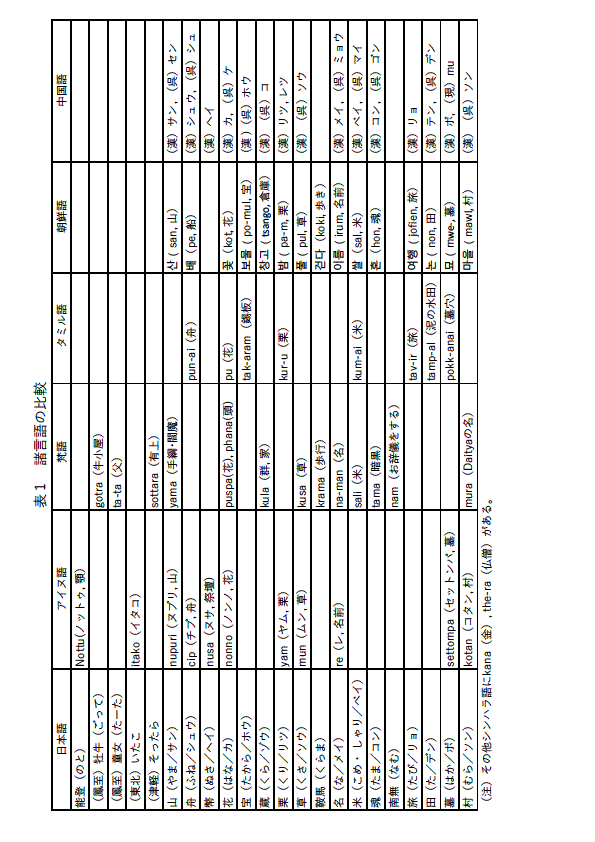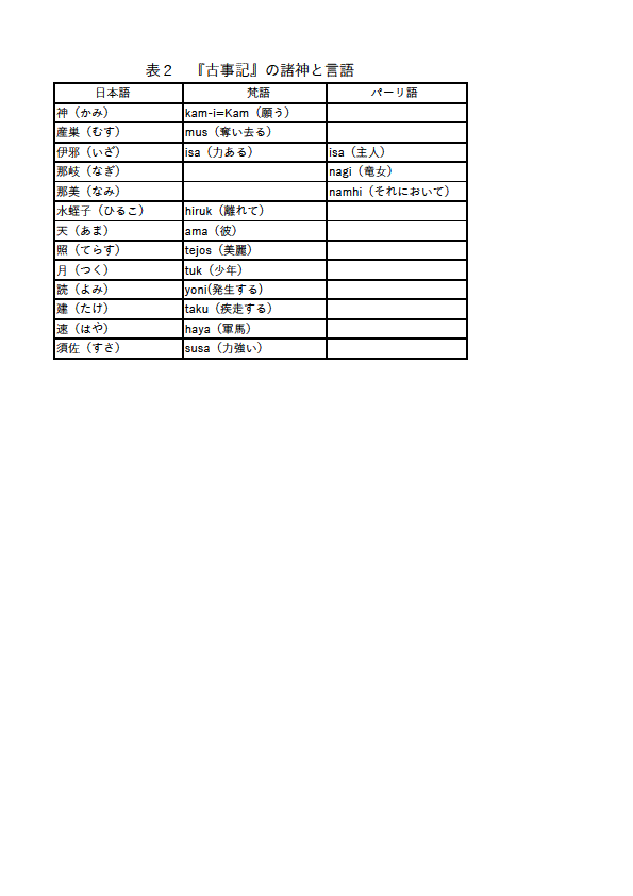���{��̃��[�c�|�A�C�k��E����E�^�~����E�p�[�������Ƃ���
�@
�|�J����
�@
�@
�@�@�@�y�v�|�z�u�\�o�v�̌ꌹ�ɂ��ăA�C�k��Nottu�i�m�b�g�E, �{�j�ɒH��
�@�@�@ ������, �\�o�̕����u�����i�����āj�v�E�u�����i���[���j�v�͞� ��
�@�@�@gotra�i�������j�Eta-ta�i���j�ł��邱�Ƃ����������B�X��, ���{��u���v
�@�@�@�ɑ������鞐��kusa�i���j,�u����, �V�����^�x�C�v�ɑ��鞐��sali�i�āj,
�@�@�@�^�~����kum-ai�i�āj�E���N��sal�i�āj�E������x�C�i�āj����������,
�@�@�@��̓`���̓C���h�[���N�[���{,�@��C���h�[���{�ƒ����[���{��3���[
�@�@�@�g�ŏ����������Ƃ���r����w�㔻����, ���{��̌P�͑S�Ăł͂Ȃ���,
�@�@�@�A�C�k��ƌÑ�C���h�n����Ɉ��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���w�Î��L�x
�@�@�@�{���V�j�̃X�T�͞���susa�i�͋����j���w�Î��L�x�̏��_�̓C���h�n��
�@�@�@�Ꞑ��E�p�[����Ɉ��邱�Ƃ��q��, �w�Î��L�x���u�B�c���X�̓C��
�@�@�@�h�A���lHilda Alleyn�i���j�����N����B
�@
�@�@�@ �L�[���[�h�F�A�C�k��E����E�^�~����E���N��E������E��̓`���E
�@�@�@ ��r����w�E�P�E���L�E�B�c���X
�@
�͂��߂�
�@���{��̋N���ɏA���Ă�, ��X�M�d�Ȓ��Ȃ��ꂽ��,������܂ޔ�r����w�I��@�͌��@���Ă����i���1994�E���s��w�i�ҁj2017�E�ߓ�2022�j�B�{�_���͞���Ƒ��팾��̔�r�ɂ����{��̃��[�c�𖾂�ړI�Ƃ�, �悸�\�o(�̂�)�̌ꌹ����������B�\�o�́w�`�����x�Łu�ڈΌ��j�������i���s��w�i�ҁj1981�F495�j�v�Ƃ���, �u�����v���ł���B������,�@�n�}���Ȃ��Ñ�ڈ�(���݂�)�l�͔\�o���ƔF���ł����ł��낤���H ���, �A�C�k�l�͓��{�̍L�͈͂ɕ��z�����ƍl�����Ă���̂Łi��c2020�j, �ڈΐl�̓A�C�k���b���Ă����Ƃ̑O��ŃA�C�k��Ɏ茜������߂��B���̌���, �u�m�b�͊{�ł���, �n���̏ꍇ�́w���x, nottu�m�b�g�D�͖�,�@���n�ׂ̍��Ƃ����ĊC�֓˂��o�Ă��鏊�i����2024�E���R2013�E�c��1996�j�v�Ƃ���, �u�\�o�̌ꌹ��NOTTU�m�b�g�E�v�������y�E�����i�|�J2022:14�E2024:32�j�B�]����, ���c�ꂪ���y�������{��̃��[�c�ł���Ì�̓A�C�k��i���c��1933�j���Ǝv�ʂ��Ă����Ƃ���, ����ɐG���@�����i�ԏ�2024�E��؊w�p�i�ҁj1979�j, ��������Q�Ƃ���Ɓi���J2018�E����2005�E���2002�j, ���{��̃��[�c�ł���P�ǂ݂͑S�Ăł͂Ȃ���, �ꕔ�A�C�k����Ê��C���h�i�V���j�n����i�T���X�N���b�g��j�E�p�[����E �^�~����E�V���n�����ɂ�����l��������������B
�@�����"a"�ŏI�~����ꂪ��������i��؊w�p�i�ҁj1979�j�ɂ���, �u�g(�n)��(��)�Ɖ]��, ���ƕ�(���m)�D(�k�t)�j(�n��)�̖��ɂ�,�i�����j�ސj(�c���o��)�Ɖ]�Ȃ�B�i�����j�g(�n)��(��)�͞���Ȃ�Ɖ]���, �{���ւ���Ђ���(�R�g)�Ȃ�i�{���i��j�E�q��i�Z���j1996:275�j�v�Ƃ���, ���V�n(�A���c�`)��(�N)�y(�j)�̂��肩���ɂ��āu�V���m���̐��Ȃǂ́i�����j�_(�A�Q�c��)�ӂɂ����炸�i�{���i��j�E�q��i�Z���j1996:383�j�v�Ɩ{���͞���ƃC���h���̌̎�������S�ے肵���B����u�ɜQ���E�ɜQ�f�g�n�Ҟ���i�� 277�E4�j�v�ƞ���m��_�����ꂽ�B�ŋ߂ł�, �u�P�ǂ͞���Ƙa��̓��ꐫ�������Ƃ���, ��������{��ɖ|�邱�Ƃł���ƌ�����i��2010�F41�j�v�Ƃ̒����������̂�, ����Ɠ��{��̔�r���s�����Ă����B�^�~����ɂ��Ă͑��ɂ����{��N���_�����ɖ��ꂽ�B�]����, ����E�^�~������܂߂�������̔�r�����\1�Ŏ���,�@�X��, �w�Î��L�x�̏��_�ɂ��Ę_������B
�@
2.�@�e�n�����ƃA�C�k��y�ў���
�@�A�C�k��ƍ���ɂ��āu�A�C�k�l�����̚��y�̌��Z���ł������W��, �Ⴕ��, �A�C�k�ꂪ, ���䢂֗��Ě������Ă���X��a�����̚���̊�b�ɂȂ�������ł͂Ȃ��������Ƃ������ł���i���c��1933)�v�ƒ�N���ꂽ�A�C�k���, �k�C�������ł͂Ȃ��B�u1���U��N�O�ɓꕶ���オ�n�܂�, �ꕶ������1��3��N�����B���̊�, �嗤���番�����ꂽ���{��, ���������L����, ���ʂ��錾�t����܂ꂽ�ƍl������B�i�����j�A�C�k���, �ꕶ�̌��t�v�ł���i��c2020�j�v�Ƃ���, �ΐ쌧�\�o�n���ł��A�C�k��NOTTU�͑��݂����B������, �\�o�n���̒��j�P���S�i���݂̖P��S�j�ɂ���������ŃA�C�k�ꂩ�Ƃ��v���鉲���i�����āj, �����i���[���j�i�ΐ쌧�P���S�i�ҁj1985�F307�j�ɒ��ڂ���B���̂Ȃ�Ή���n���ł́u�����������v, �x�R���ł́u���[���v���ŋ߂܂Ŏg���Ă�������ł���B����, �A�C�k�ꎫ�T�ׂĂ������B������, �w����Ώƞ��a�厫�T�x�i�ȉ�, �w���a�厫�T�x�Ɨ����j�������ĎQ�Ƃ��ꂽ�̂��\1�ɂ��鞐��gotra�i�������j��ta-ta�i���j�ł���B�O�҂͋������������ƔF���������ʂł���, ��҂͓�����A�ꂽ���̈ӂ������ɕϗe������ł���B
�@����, ���k�n���̌��t�u�������v�̓A�C�k���itako�i�C�^�R�j�Ƃ���, �X���E��茧�ł̃C�^�R�̑��݂ƍ��v���Ă���B�X��, �u��������v�͒Ìy�n���ł̕����ł���, ����ׂ�ƞ����sottara�i�L��j������B�u�L��v�͊���ł���, �u�������炱�Ƃ������ȁv�́u��ɂ��鎖�������ȁv�̈Ӗ���������Ȃ��B����, ���{�e�n�Ɏc������͓��{�̌Ì�ł���, �A�C�k��݂̂Ȃ炸����̉e�������Ă���B����ł�, ����̓��{��ɂ��Ă͂ǂ����낤���B���߂Ō�������B
�@
3.�@�A�C�k��E����E�^�~����E���N��E������
�@�悸�R�i��܁^�T���j�ɂ��Ĕ�r�E��������B�A�C�k��ł�nupuri�i�k�v��, �R�j�Ƃ���, ���݂̓��{��u��܁v�Ƃ͕ʌn���B�����yama�͂��邪, �Ӗ��́u��j�v�u腖��v�B �u������R��腗��i腖���, ������腗��j���{����i�˖{�i�ҁj1960�j�v�Ƃ���B������, �R��腖��͓��`�Ƃ܂ł͌����Ȃ��B������N��́isan, �R�j�ł���, ������̊����i�w�p��厚���x�j�T���ƈ�v�B����ł�, ���N��͑S�Ē�����n���Ƃ����ƌ�q����@����v���Ȃ����ꂪ�����B�Ƃ���ƎR�͞���̓����C����ł��낤�B
�@�M�i�ӂˁ^�V���E�j�͂ǂ��ł��낤���B�A�C�k��ł�cip�i�`�u, �M�j�ł�
��, ����͊Y���Ȃ��B������, �^�~�����pun-ai��p-f���C�ω��`�B���N��́ipe, �D �j, �����ꊿ���̓V���E�ł���B�]����, �^�~����͏M�œ`���, �M�̓^�~����ߎ�����ƌ�����B
�@���, ���i�k�T�^�ւ��j�̓A�C�k��nusa�i�k�T, �Ւd�j������, ����E�^�~����ɊY���͖����B�A�C�k��k�T�ɂ��Ă͌�ɘa�ꂪ�������ꂽ�Ƃ̍l�������낤���Ǝv���邪, �䕼(���ւ�)���͂܂��Ւd�ƍl������̂ŃA�C�k��nusa�͗L�́B�Ƃ����, ���i�K�ł͓��{��̌Ì���A�C�k����Ê��C���h�n����E�^�~�����ɂč\������Ă���Ǝv�l�����B
�@�I�ɂ���,�@�A�C�k���yam�i����, �I�j, �^�~�����kur-u�i�I�j, ���N��́ipa-m, �I�j�ł���, �^�~����ɋ߂��B
�@���ɂ��āC�A�C�k���mun�i����, ���j, �����kusa(��), ���N��́ipul, ���j, �����ꊿ�E�����̓\�E�ł���, ���͞��ꂻ�̂��̂ł���B
�@�Ɣn���͓ޗǎ��㖖���̕�T���N�i770�j�ޗǁE�����̊Ӑ^�a��̍���E�Ӓ���l���Ɣn�R�ɓo�R, �S���ɏP��ꂽ�Ƃ���������V�ɏ������, ������V���J�鑐�������̂��J��Ƃ̂��Ɓi���j�b���{�R�Ɣn��2015�j�B���݂͂��̈Ɣn�̒n�̈Ɣn���ɂ̓P�[�u���J�[�ŎQ�w�ł���̂���, �u�������ĂƂ������Ɣn�̂Â炨��Ƃ������i�r�c�E�ݏ�E�H�R�i�Z���j1958�y166�z�j�v�ƋL�q����Ă���@��, �Ñ�͕����ēo�鏄��̎��ł������B ����, �Ɣn�i����܁j�͞���krama�i���s�j�����`�Ȃ̂ł���Bkrama��kurama�ɂȂ������R��, �q���A���̏ꍇ�̕ꉹ�}���ł��鞐��ratna���p�[����ratana����������iWikikipedia�u���}���v�j�B
�@
4.�@����E�^�~����E���N��E������
�@���͖�15,000�N�O�C���h�A�b�T���n��, �����암�_��Ȃ���^�C, �~�����}�[�t�߂Ŏn�܂����l�����Ă���(UNIPHOTO PRESS2000)�B��ւɂ��Ă͒������]�ȉ͛G�n(������)��ւ��L����, �N���7,000�`5,300�N�O�B���c�Ղ�������, �����_�̊e��╨�Ɠ��A���ّ��̂��o�y�����i����1998�G�����E��2020�j�B�]����, �Ă͒����ƒ��N������{�ɓ`�������Ƃ̍l������������Ă���悤���B������, ��r����w�ɂČ����Ă݂�B
�@���{��̕Ăɂ�, �u���߁E�����^�x�C�v�̓ǂ݂�����B������Ɣ�r���悤�B�A�C�k��ɂ͕Ă͖���, ����ł�sali, �^�~����ł�kum-ai, ���N���sal, ������i���j�̓x�C�����������B�u�����v�͎��i�p�̂��т̈ӂƂ��v���邪, �w�L�����x�ł́u�ɗ�, ���ɂ܂��͐��҂̈⍜�B����, �Ăԁv�Ƃ���, �Ăŗǂ��B�Ƃ���ƕē`���͎��̃��[�g���l������B �@sali�i����j�|sal�i���N��j�|�����i���{��j, �Akum-ai�i�^�~����j�|���߁i���{��j, �B�x�C�i������j�|�׃C�i���{��j�B����, �C���h������蒩�N�o�R���{, �C���h�암��蒼�ړ��{,�@������蒼�ړ��{��3���[�g�ł���B���N�͒����ł͂Ȃ��C���h�����삪�`�������悤���B��, �C���h�̕Ă̓C���f�B�J�Ă�A�z���邪, �C���h�ł͑���ނ̕Ă��͔|���Ă����悤��, �W���|�j�J�Ă��͔|��ł������Ɛ��ʂ����B
�@
5.�@���ꥒ��N��E������
�@�_���ɂ����鎮�N�J�{�ɂ��āu�Èł̂Ȃ�, ���g�́w�o��x�O���ɂ�Đ_�삪�V�{�ɑJ��i���{�@��{�i�ҁj1994:234)�v�Ƃ���悤�ɍ�(����)�̈ړ��͈Èő�������tama�i�Í��j���ɍs����B�����p��얳�i�Ȃށj�ɂ��Ă�, �^���@�Łu�얳��t�ՏƋ����v�B��y�@�E�^�@�E���@�Łu�얳����ɕ��v, �����@�Łu�얳�߉ޖ��v, ���@�@�E�@�؏@�Łu�얳���@�@�،o�v �Ɠ얳�͋A������Ɩ�Ă��邪, ����nam����namas�͂����V������Ӂi�˖{�i�ҁj1968�ł͋A��j�ł���, �A�����铙�ƋX�����\���̌��`�͂����V�����邱�Ƃ̂悤���B
�@
6.�@�A�C�k��E����E�^�~����E�p�[����E�V���n����E���N��E������
�@���i���с^�����j�̓A�C�k��E����ɂ͖���,�@�^�~�����tav-ir�i���j�B���N���jofien(��), ������i���j�̓����B����, �P�ǂ݂̓^�~����, ���ǂ݂͒�����ł���B�c�i���^�f���j�̓^�~�����tamp-al�i�D�̐��c�j, ���N���non�i�c�j, ������i���j�Ńf���B������P�ǂ݂̓^�~����ł���B��i�͂��^�{�j�̓A�C�k��ŃZ�b�g���o�i��j, �^�~�����pokk-anai�i�挊�j, ������i���j�{��, ���ǂ݂͒����ꂾ��, �P�ǂ݂͌���I�ł͂Ȃ����^�~����ɋ߂��B���i�ނ�^�\���j�̓A�C�k�ꂪ�L����kotan�i���j�ł���, �����Vinus�_�̖��Ƃ��Ă�mura������B ���N���mawl�i���j, ������i���j�i���j�Ƃ��\���ł���B�C���h�ł͑��̓�����ɋ������q�ł���_�����ۂ��������������悤���B
�@���,�@���̌`���ɃT���X�N���b�g��E�p�[����y�у^�~����̉e��������, �������Z�C���������̒n��I�ȕ����y�є����̍��ق����ꐄ�i���ꂽ�V���n����ɂ�kana�i���j, the-ra�i���m�j�����������i���2002�j�B�]����, ���{��i�P�ǂ݂Ǝq���E�ꉹ�A�ڂ��܂ށj�̃��[�c�̓A�C�k��̑f�n�ɃC���h�n�Ì�ł��鞐��E�^�~����E�p�[����E�V���n����̗����Ɉ���ƌ��_�Â�����B���̌㒆������̕��T�ɂ���������E�����̉��ǂ݂������������Ƃ͘_��ւ��Ȃ��B
�@
�V. �w�Î��L�x�ɂ����鞐��E�p�[����
�@ �w�Î��L�x�ɂ͐��X�̐_���o�ꂷ��B�\2�Ŏ����@��, �u�_�v�ɂ��Ă͞����kam-i��Kam�i�肤�j�ӂł���B����̉�X���_�O�ŋF��, �肤�ΏƂƂ��Ă̈ӂɍ��v���Ă���B
�@�u���V(������)�̌��ɐ����_�v�̈�l, ����Y(�����݂�)��(��)��(�Ђ�)�_�̎Y���i�ނ��j�͞����mus�i�D������j�Ƃ���Bmus�ɂ��Ă�, �u���c(������)�Y��(�ނ��Ђ�)��(�݂���), �c��(���߂݂�)���~(����)���܂��, ���̒n(����)�ɌN��(���݂Ƃ�����)�͂ނƂ��B��(����), ��(��)���ɉ�(���)��(�ӂ���)���~����(����)����, �쏜(�͂�)�Е���(����)�߂��ށB��(���܂�)����(������)���@(������)�B��(��)��܂�ނ��(����)��i��{�E�Ɖi�E���E���1967:138�j�v�Ƒ�ȋM�~(�������Ȃނ��̂���)�i�嚠�����~�j�ɍ����������������Y�����͗��D�҂ł���B
�@��, ��������̑O�c���ƁE�]�˂̓���ƍN�����͂𗪒D��, ���Ƃ͋�����R�_�ЁE�ƍN�͓������Ƌ{�̐_�ƂȂ����B��������ɞ���mus�i�D������j�̓I�m�\���B
�@����, �т����y�����ɜQ���E�ɜQ�f�i�w�Î��L�x�ł͈Ɏדߊ�E�Ɏדߔ��j�ɂ��āw���a�厫�T�x���Q�Ƃ����, ����isa�i�͂���j������B����nagi�Enami�͑��݂��Ȃ��B������, �q���A���̏ꍇ�̕ꉹ�}����Ƃ��đO�q�����C���h�n�Ì�p�[��������������, isa�i��l�j, nagi�i�����j, namhi�i����ɂ����āj������B�u�p�[����̓Z�C�����i�X�������J�j, �r���}�i�~�����}�[�j, �^�C�i�V�����j���̓��������i��`�����j�̐��T�̗p��ł�����, �i�����j�C���h��ł͞���ƃp�[����̉��C�͑�̗ގ����Ă���i����2005�j�v�Ƃ���̂�, �Ӗ��͏��X�قȂ邪, �w���a�厫�T�x��������ł̗т��u�ɜQ���E�ɜQ�f�g�n�Ҟ���v���͓K�X�Ȏw�E�ł������ƌ����悤�B
�@��(��)�g�q(�邱)�͈Ɏדߊ�E�Ɏדߔ��̍ŏ��̎q�Łu���D�ɓ���ė����ċ�(��)�Ă��v�Ƃ���悤�ɐ��ɗ���Ă������q���B���ʂ͏��_�Ƃ����������i�ɓ�2025:307�j�B�V�Ƒ�_�͏]�����_�Ƃ��ꂽ��, ����ama�i�ށj�ł���, �V�Ƃ͔���̔ނ̈ӁB�Ƃ���Βj�_�ł���B��(��)�͏��N�ł���, ��͂�j�_�B
�u���̌��(�͂�)����\����(�Ƃ��邬)����, ���̎�(���낿)���U(�ق�)�肽�܂Ђ��i�q��E���c�i�Z���j1978:87�j�v�ŗL���Ȑ{���V�j���̐{��(����)�͕\2�Ŏ����@�������susa�i�͋����j�ɑ�����, ����(�����͂�)�{���V�j�͎�������R�n�̂悤�ɗ͋����j�Ş��ꂪ�҂�����ł���, ������j�_�B�Ƃ���ΗB��̏��_�͑O�q�̂��Ƃ����g�q�ɂȂ邾�낤�B
�@��, �C���h�n�Ì�̗p�Ⴊ�������Ƃ��w�Î��L�x���u�B�c���X�̓C���h���A�������C�^�R�ł���, �w�����АV�p�a�厫�T�x�Ō��������Hilda�i�������jAlleyn�Ɛ��肷��B�ܘ_, Hilda Alleyn�i�q�G���_�@�A�����j�͐��m�l���ł���, ���{�l���̃��[�}���\�L�ł͂Ȃ��B�Ƃ����, �w�Î��L�x�ɑ�(������)���ݗ�(�₷�܂�)���������u���B�c, �����X, �i�q��E���c�i�Z���j1978:46�j�v��, ���{�l���Ɛ��m�l���ɂ����鐩�Ɩ��̓|�u�ł���, �|�u�͑��̎��ォ�瑶�݂����B�]����, �u�����X, ���B�c, �v�����������ƂɂȂ�B
�@
�W.�@����
�@�_�͂���̂������iMikoto�j�́w���a�厫�T�x�ɂ͖����B�݂��Ɓu���v��,�u���M�Ȑl�̋����������B�w�䌾(�݂���)�x�̈ӁB�u�݁v�͐ړ���B�܂����̐l��ł����Ƃ�, ��(�݂���)�E��(�݂���)�����̖��ɂ����Ă������Ƃ�����i����2007:685�j�v�Ƃ���B�m���Ɂu�䎖�v�Ɠǂ߂�ӏ�������̂����w�Î��L�x�S�ʓI�ɂ͑��̂̈ӂƎv����B�����, �u�Î��L�ł͐_�Ɩ�����ʂ�, �_�͏@���I, ���͐l�i�I�Ӌ`�ɂ����ėp�����Ă���i�q��i�Z���j1997:19�j�v�Ƃ̋r����薾�炩�ł���B�]����, �䎖���͕ۗ���, Mikoto���̐��̊m��ׂ��悸koto����������B����koto�ɂ��Ă�, kota������kotta�Ɠ��`�Łu��v�u�ԁv�Ƃ���Ba-o���C�ω��Ƃ����, ���͘a��ړ���Mi�������āu���v�ɊY�����鑸�̂�����Ȃ��B
�@�B�c���X���A�C�k��ƃC���h�n�Ì�ł��鞐��E�^�~����E�p�[����E�V���n����ɒʋł��Ă���_�ɏA���Ă�, �u��x�j�n�������j���L�V�^�����K�i�C�i�O��F147�j�v, �����u�C���h�ł͈��u�ɂ���Čo�T����`����������������i���c�E�Ζ�2024:87�j�v�悤��, �ꕶ��ł���A�C�k��̓y�n�ɃC���h�e�n����n���A�������W�c�̋��Z��ɕB�c���X���C�^�R�Ƃ��đ��݂������Ƃɂ��ƍl������B�C���h����̓n���ɂ��Ă�, ���厛�啧�J�ዟ�{�̓��t���A�߁iBodhi Senna�j���C���h�m�ł��������Ƃ�肻�̗�͑����������̂Ǝv����B
�@��, �w�Î��L�x�ɂ͕\2�ȊO�̐_�X�����������݂���B�����͑S�ĕB�c���X���u�݂ł͂Ȃ�,�@���̑n�삪�啔�Ȃ̂ł��낤�B
�@
�X�D������
�@���{��̃��[�c�ɂ��Ă̓E�����A���^�C�ꑰ�ł���, ��̓I�ɂ͓��{�l�̓o�C�J���Ύ��ӂ������ė����Ƃ����u�o�C�J���ΔȋN�����v, �u�I�z�[�c�N������S�����l�X�͌���̃A���[���͉͌���̐�Z���ɋ߉��ł������v�i���s��w�i�ҁj2017:81�j, �i���c2025:120�j�Ƃ̐�������, �A�C�k�ꂪ���[�c�Ƃ̍l�����嗬�ł������B������, ���̌���{��ƃ^�~����Ƃ̓��n�W�����ꂽ�B ����ɂ��Ă�, �������ǂ�����Ȃ��ߗт́w�{���_�Ѝl�x�������Ğ���[���{�ꃋ�[�c���͒�N����Ă��Ȃ������B���݂́w����厫�T�x������, ���̔��ǂ͗e�ՂƂȂ�, �������������Ɠ��{��ɑ������鞐�ꓙ�C���h�n�Ì�̗p�Ⴊ�����B�]����, ���{��̃��[�c�ł���P�͑S�Ăł͂Ȃ����A�C�k��E�C���h�n�ÌꞐ��E�^�~���ꓙ�Ɉ��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł����B
�@��, ��r����w�I��@�ɂ���̓`���̓C���h�[���N�[���{,�@��C���h�[���{�ƒ����[���{��3���[�g�ł��邱�Ƃ������B
�@�X��, �w�Î��L�x�ɂ�����_�X��, ������S�Ăł͂Ȃ���, ����E�p�[����ɏ�����,�@�B�c���X���u�݂Ɋ�Â����Ƃ�_�������B
�@����, �A�C�k��ƃC���h�n�Ì�ɂ��X�Ȃ���{��Ƃ̗ގ��Ⴊ���o������̂Ǝv���, ���{��̃��[�c�𖾂ɂ�����i�W�����҂����B
�@�����ł���, �������������w�l�ԎЉ�w��l���w�ތ���w��啪�싳�����]�_�i�搶�Ɋ��ӂ̈ӂ�\���܂��B�@
�@
�Q�ƕ���
���W�i1994�j�w���{��̋N���x�����F��g�V��.
���s��w���w�����ȕҁi2017�j�w���{��̋N���ƌÑ���{��x���s�F�Ր쏑�X.
�ߓ�����i2022�j�w���{��̋N�� ���}�g�R�g�o���߂���ꌹ�w�x�����F�}�����[.
���s��w���w������w�����w�������i�ҁj�i1981�j�w���{�W���@�`�����ڏ��x[�O��]���s�F�Ր쏑�X.
��c�p���i2020�j�u���t���E�A�C�k��n���́w�ꕶ�̒n���x�vhttps://www.hitohaku.jp/publication/book/kyousei15-p055.pdf/.
�������q�i2024�j�w�A�C�k��n���̗��j�x�����F�g��O����.
���R�T�l�i2013�j�w�A�C�k��Ìꎫ�T�x�����F���Ώ��X.
�c�������q�i1996�j�w�A�C�k�ꍹ���������T�x�����F������.
�|�J�����i2022�j�w�����u�R�̎��v���@�Q�[�L���Ȃ�u�f�B�Y���ւ̗U���x�x�R�F�j�V��.
�|�J�����i2024�j�u�m��F�\�o�̌ꌹ�̓A�C�k��NOTTU�m�b�g�D�v�w�ΐ싽�y�j�w��X���x57�F32-34.
���c�ꋞ���i1933�j�w����w�@�A�C�k��ƚ���x�����F�������@.
�ԏ����F�i2024�j�w�T���X�N���b�g����@�C���h�̎v�z����u���S�Ȍ���v�x�����F�����V��.
���؊w�p���c�i�ҁj�i1979�j�w����Ώƞ��a�厫�T�x�����F�u�k��.
���J�K���E��e����E�����E�E�����i�Y�i�ҁj�i2018�j�w���w�ف@�ؓ����T�x�����F���w��.
����O���i2005�j�w��������p�[���ꎫ�T�x�����F�t�H��.
������i�i2002�j�w�V���n���ꎫ�T�x�����F��w����.
�{���钷�i��j�E�q�쌛�i�i�Z���j�i1996�j�w�Î��L�`�i4�j�x�����F��g����.
�ї��R�w�{���_�Ѝl�xhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100452561/4?ln=ja.
�������i2010�j�w�����Ɠ��A�W�A�\�P�ǂ̕������x�����F��g�V��.
�P���S�����i�ҁj�i1985�j�w�ΐ쌧�P���S���x���s�F�Ր쏑�X.
�˖{�P���i�ҁj�i1960�j�w�]�������厖�T�@��ꊪ�x�����F���E���T���s����.
���j�b���{�R �Ɣn���i2015�jhttps://www.kuramadera.or.jp/rekishi.html.
�r�cꝊӁE�ݏ�ē�E�H�R�i�i�Z���j�i1958�j�w���{�ÓT���w��n19 �����q�@���������L�x�����F��g���X.
Wikipedia�u���}���vhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E6%8C%BF%E5%85%A5.
UNIPHOTO PRESS�i2000�j�u���E�̈��vhttps://www.uniphoto.co.jp/special/rice/.
�����G�u�i1998�j�w���̋N����T��x�����F��g�V��.
�����T��E���k�i2020�j�w�͛G�n�ƗǏ��\������앶���̋N���x�����F�Y�R�t.
���{�@��{���{�����������i�ҁj�i1994�j�w�_�����T�x�����F�O����.
�˖{�P���i�ҁj�i1968�j�w�]�������厖�T�@��l���x�����F���E���T���s����.
��{���Y�E�Ɖi�O�Y�E������E���W�i�Z���j�i1967�j�w���{�ÓT���w��n67 ���{���I ��x�����F��g���X.
�ɓ����i2025�j�w�_���Ƃ͉����@����Łx�����F�����V��.
�q�쌛���E���c?�g�i�Z���j�i1978�j�w���{�ÓT���w��n1 �Î��L �j���x�����F��g���X.
����Ái2007�j�w�V�����P�x�����F���}��.
�q�쌛�i�i�Z���j�i1997�j�w�Î��L�x�����F��g����.
�O��`�v�w�������w�j�x�����F������.
���c�S�E�ΖؗE�i2024�j�w���w�̎v�z�x[����]�����FNHK�o��.
���c����(2025)�w�q�g�ƃq�O�}�[�����N�}����V��܂Łx�����F��g�V��.
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
Last updated on Nov. 15, 2025.