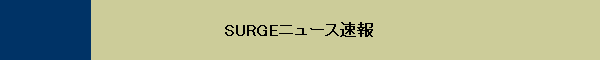
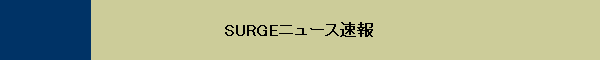
教育改革国民会議と改革を支援する文部省との間に最近、公立学校の学級定員の在り方をめぐって考え方の違いが表面化しつつある。教育改革国民会議では現行40人の学級定員を30人以下に引き下げるべきだという意見が強まっているが、これに対して文部省では現行40人の基準を維持しながら、習熟度別指導などの本格的導入など緩やかな教職員定数改善を図ろうという方針で、来年度概算要求の編成を前に両者の議論の行方が注目されている。
もともと文部省は学校の自主性・自律性確保を提言した中教審の地方分権答申を受け、学級定員はあくまで教職員定数の算定基礎に過ぎず、実際の学級編成は地方自治体が弾力的に行うべきだという考えを持っている。この背景には学級定員削減が国の財政事情からみて困難であると同時に、国による一律の学級定員が「学級」単位ですべてを行うという教育の画一化につながっているという反省があるからだ。教職員配置改善計画の今年度完成を受け、文部省は8月の来年度概算要求で新方針に基づく教職員定数改善を準備している最中だっただけに、夏に予定されている教育改革国民会議の中間報告に学級定員一律削減が盛り込まれることは何としても避けたいというのが本音だ。
両者の議論は一見、教育環境改善を目指す国民会議に対して、財政難を理由に文部省が横槍を入れているともみえるが、「学級」とは何かという国民意識、国がどこまで学級編成に関与すべきかという大問題が根底にあるといえる。
(河合塾Kei-Net mail 2000 ==vol.07 2000.5.16==より転載)
![]()