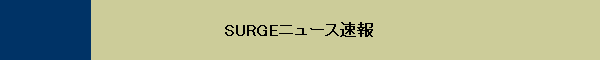
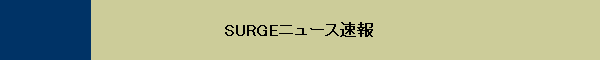
大学審議会は4月28日、大学入試センター試験の複数回実施を柱とする中間報告を公表した。センター試験の複数回実施といわゆる資格試験的扱いとすることなどは、これまでも臨教審、中教審でさまざまな論議がされてきたが実現しなかったもので、今回の中間報告の意味は非常に大きい。しかし、中間報告には早くも「妥協の産物」という批判が出ており、全国高校長協会や国立大学協会は、ともに表立っては反対していないが、「本音のところは受け入れられない」(全高長幹部)というのが実情のようだ。
センター試験の複数実施は当初、夏と春の2回で議論されたが、夏では高校教育に与える影響が大きすぎると指摘され、結局、12月と1月に落ち着いた。資格試験化も高校教育自体の在り方にかかわってくるため、各大学の判断に任せるということになった。これに対して、12月に実施しても事実上、センター試験の受験態勢が12、1月と2ヵ月間続くことになり、業務に携わる大学関係者の間では負担増が厳しくなるとの反発が強い。また、高校も3年生の学習期間が実際には11月までになってしまうほか、センター試験の会場提供の負担も増えると消極的な受け止め方がほとんどだ。全高長、国大協ともに「慎重に検討する」としているが、主要関係2団体の消極的姿勢が今後の正式報告までの議論にどのような影響を与えるかが注目される。
(河合塾Kei-Net mail 2000 ==vol.05 2000.5.2==より転載)
![]()