時は夕刻から夜へと静かに移ろう。
朱色から蝋色へと変わる部屋の中を見渡し、オスカルはゆっくりと深呼吸をした。
柔らかくなつかしい香りの中で、窓辺に置いた燭台の影が床にぼんやりとした幾何学模様を描いている。
オスカルは近付き、身を屈めると燭台に触れ、そのままそっと指で輪郭をなぞった。
その燭台はジャルジェ家で長年愛用される調度品の中でも特に逸品と呼ぶのに相応しいものであった。特注で作られたのか台座部分には美しい女性と白鳥のレリーフがはめ込まれ、その白鳥が羽根を広げたかに見える脚の部分には真鍮製とは思えないほど繊細な透かし彫りが施され目を惹いた。
優美で上品な黄金色のレリーフ。その中で女性は愛おしそうに白鳥を撫で、また白鳥はまるで女性を抱き締めるかのごとく大きく羽ばたき、頬を寄せていた。


幼心にも、不思議な造形だった・・・・・。
オスカルは暮れゆく部屋の中で目を閉じ、暫しの間、子供時代に思いを馳せる。
・・・そう・・・夜になるのが待ち遠しかった時期があった。
6歳頃だったか・・・昼の間さんざんはしゃぎ回って遊び疲れ、クタクタになってもなお、陽が暮れるのが口惜しかった。そして、屋敷の中で最後まで明るい場所は何処か調べようと思い立ち・・・・・私はこの燭台に出会った。
屋敷には普段使われない部屋というものがいくつかあり、そこには大抵ばあやに不要とみなされた哀れな調度品や絵画、それに棚から溢れた蔵書の類が眠らされている。しかし、最上階にあるその部屋だけは少し様子が違うようだった。
辺りの気配を伺いながら重い扉を開け、そっと中を覗くと、オレンジ色の光線が目の前いっぱいに飛び込んで来た。ハッとし、眩しさで一瞬目が眩んだものの理想的な空間を見つけた驚きと嬉しさで、私は思わず歓声を上げていた。
下の階ではすっかり頼るべき光源が陽の光から炎の灯りへと交代しているというのに、その部屋ではいまだ太陽光線が主役で部屋中を明るく照らしていた。
そこが物置でないことはすぐに分かった。
殺風景と思える程に綺麗に片付けられた部屋・・・ほんの少しだけ誇り臭さを感じるも不思議な安らぎに満ちていて、射し込む光が大きな化粧鏡に反射し、美しかった。その上、確かあれは初雪が降るのを待ちわびていた時期で外はとても寒かったのだけど・・・その部屋だけは随分と暖かかった。
眩しさに目が慣れて来ると鏡の傍に置かれた丸テーブルと椅子2脚、古びたキャビネットが確認出来た。それから・・・私は目を見張り、導かれるように部屋の中へ入ると、“それ”をじっと見つめた。
丸テーブルの中央に置かれた燭台が夕日を浴びて、まるで黄金で出来た彫像のようにキラキラと光り輝いていた。
その姿は幻想的で・・・夢のようだった・・・。
だいぶ経ってから知らされた事だが、その部屋はアンドレが屋敷に引き取られて間もない頃に、就寝前のわずかな時間、ばあやが貴族社会のしきたりや振舞いについて毎夜懇々と彼に説いて聞かせていた場所なのだった。
日中陽が当たらないその部屋は陰気臭いと使いでがなく、さりとて強烈な西日のおかげであらゆる物が傷むとばあやが言うので物置にも適さない。それで、活路・・・と言っては大袈裟過ぎようが、見出したのが祖母と孫の勉強及び特訓部屋だった・・・というわけらしい。
そんな事とは露知らず、発見した日からその部屋は、夕刻から夜へと変わるひと時の間、私の一番心安らげる場所となった。
そうそう・・・おかしいのがアンドレの反応で・・・今でもよく覚えている。
私が何も知らず彼の手を引き「宝物を見せてやる」とその部屋に案内した時のことだった。
「此処なのかい・・・?」と一瞬困惑した表情を見せた後、アンドレは自分から恐る恐るといった様子で扉を開けた。そして、「うわっ!?ゼウス様の電光だー!!」と叫んだかと思うと次の瞬間、勢いよく床に突っ伏した。
今にして思えば随分と芝居がかった調子で不自然な点もあったのだが、その時の私はとにかく予想していなかった彼の反応にポカンとして、その場に立ち尽くしてしまったのだった・・・。
考えてみれば、その頃から彼の方がずっと大人で読書家で・・・恐らく、その勉強部屋で芸術分野についてのさまざまな出来事も、私以上に学んでいたに違いない。
そんなことがあって以来、私は夕暮れ時になるとその部屋へ行き、オレンジ色の光を浴びながら飽きもせず何時間でも燭台を眺めては傍でうたた寝をしてしまう日々を過ごした。
そんな私を見かねて・・・ある時、父はこの燭台をゼウスの電光の部屋から私の部屋へと運んだのだった。
物心つく頃になると、神話の中に登場するレダという女性が“彼女”なのだろうな・・・と、推察できるようになった。でも、何故か周囲に確認することがはばかられ、特に父には一切のことが聞けぬまま、私は大人になった。
自分の境遇を不幸だとか不自然だとか、感じる間もなく月日は流れた。
気が付けば本来の性から随分と遠いところに来てしまったと不安に駆られた時期があり、一方で成長期には思わぬ変貌を遂げ、自分の意思に反してぐいぐいと女を主張するかのような自分の体に戸惑いもした。自分の存在を不完全だと思い込み、葛藤する心を持て余し、ひとを傷付けもした。女だから・・・こんなにも激しく気持ちが揺れ動いてしまうのだと、もがき苦しんだ・・・。
だが・・・女だからこそ決断し、貫き通せることもある。と・・・今は思う。
オスカルは振り向き、壁に掛けられた父の肖像画をじっと見つめた。
薄闇に浮かび上がる父の顔は凛々しく、厳格な軍人そのものであった。
見慣れたはずの父の顔。
肖像画の父は、フランス王家を守り抜くために我等は此処に在るのだと、今この瞬間も私に向かい、一心に教え諭している。
そう、いつも父はこういう顔をしていた。だが、目を閉じると浮かんで来る・・・。
奇妙なもので、燭台をオスカルの部屋へ運べと言った時に見せた「やれやれ・・・」という、少し困ったような笑顔・・・滅多に見せないその笑顔が、思い起こせば私にとって、一番印象深い父の顔なのであった。
太陽が一層傾き、サーと音を立てて部屋が闇に包まれた。
オスカルは肖像画の父から目を逸らし、笑いながら小さく溜め息をつくと蝋燭の炎を用いて燭台に火を点けた。
闇の中に鮮やかな緋色の光が次々に浮かび上がる。
中世の時代から、レダと白鳥を題材にした作品はその官能表現が道徳上好ましくないとの理由で故意に傷付けられたり破棄されたり、しばしば迫害とも言える災難に見舞われてきたのだという。非難の対象の殆どは絵画なのであろうが、そう露骨に否定することもあるまいと、私は目の前のレリーフを見て思う・・・。
あの頃と少しも変わらない。キラキラと零れる黄金の粉のような燭台の光は、暗闇の中で身動き出来ずにいる私にいつだって希望を与えてくれる・・・。
そう、傷付けられることなどあってはならない。
私の宝物・・・燭台の中の“二人”は、本当に美しいのだから・・・。


レダと白鳥の燭台によって明るさを取り戻した部屋で、オスカルは鏡に向かい軍服を整えた。
明朝8時、武装しチュイルリー広場へ進撃。他の軍隊と協力し暴徒化した市民を鎮圧せよ。
先ほど聞いたアランの伝言が繰り返し脳内にこだまする。
制限時間はそこまでか・・・・・
心臓がトクンと脈を打つ。
覚悟は、出来ているか?
鏡の中の自分に問い掛けた。
この時を迎えて、もっと悪足掻きするかと思われた自分の気持ちが意外な程に凪いでいることに、オスカルは不思議な感慨を覚えていた。
「・・・単なる諦めだと思うか?」
鏡に向かい、微かに声に出してそう呟くとオスカルは静かに首を振った。
込み上げる想いに、またしても涙が溢れそうだった・・・。
さっきまで泣いていたせいかいつもより瞼が重たい。瞬きする度に感じる目元の違和感がせっかく落ち着いている感情を刺激し、たまらなくもどかしい気持ちになった。
駄目だ。こんな暗い表情の女など・・・彼の目に魅力的に映るわけがない。
オスカルはもう一度、今度は大きく首を振り、深呼吸をすると髪型を整え、そして鏡に向かって・・・にっこりと笑い掛けた。

軍服の襟を正し腰に剣を装備すると、オスカルは引き出しの中から2通の手紙を取り出した。
宛名を確認し、1通をテーブルの上に置くともう1通は封を切る。そして何枚にも渡って書かれた文章を読み返すと父の肖像画の前に立ち、その瞳を真っ直ぐに見つめた。
それから、オスカルは元通り便箋を折り畳むと封筒へ戻し、それを燭台の炎へゆっくりと近付けた・・・・・。
ゆらゆらと揺れる蝋燭の炎が暗闇の中に幻想的に浮かび上がる。
近付けた手に熱さと共に微かな生命力のようなものが伝わる・・・そう感じた瞬間、白い封筒の端がしゅっと微かな音を立てた。
火が点き、みるみる黒く焦げてゆく手紙。
それは数日前に父に宛て、オスカルがひと晩かけて認めたものであった。
手紙を持つ右手がじりじりと熱せられ痛みが走った。その感覚に少し躊躇する素振りを見せたものの、オスカルはそのまま部屋を移動し、手紙を暖炉の中へ投げ入れた。
数日前にこの手紙を書いた時と今この瞬間・・・特に心境に変化があったわけではない。
それでも、この手紙を残して行くことにためらいを感じたのは何故だろう・・・?
丁寧に書き連ねた想いが青白い煙となって消滅するのを見届ける間、改めて、オスカルは父に対する複雑な感情を噛み締めていた。
長い間待ち望んだ男児誕生の瞬間を・・・裏切ったのは、私なのだろうか・・・・・?
そればかりか・・・私は人生の終わりに、父の名誉に取り返しの付かない傷を付けようとしている・・・。
ドロドロとした感情が一気に溢れ出て眩暈がするようだった。
オスカルは唇を噛み締めながら、消えゆく手紙を見つめた。
紙が焼けるチリチリという切なげな音が静まり返った部屋の中では妙に大きく聞こえる。
集中し耳を澄ますうち、いつしかその音は聞き慣れた自分の叫び声に変わった・・・。
父上・・・父上・・・・・ただ私は・・・・・あなたに愛されたいのです・・・・・!!


遠い思い出の中を漂いながら、オスカルは考えた。
落胆、いや、絶望から始まったはずの私への思いが、いつしか希望に変わり、ついには・・・「お前を誇りに思う」と・・・・・・言われたことがあった。
父の・・・そのたった一言が、どれほど嬉しかったことか・・・!
嗚呼、だけど・・・私を認め、信頼し、満足げに微笑むあなたを見る度に・・・安堵はしたけれど・・・でも、そんな自分は何故だか他人のようで・・・・本当の自分の価値を知りたくて・・・自分の生まれて来た意味を知りたくて・・・・・いつだって私は叫んでいた。
過去の出来事が次々と思い出され胸が締め付けられそうになる中、静かに手紙は燃え尽きた。
呆気ない程に、跡形もなく・・・・・・。
我に返ったオスカルは数回瞬きを繰り返し、ふっと息をついた。
・・・解き放たれたのだ・・・・・これで私は、自由になれる。
複雑に絡まった感情がするすると解ける感覚に包まれ、オスカルは嗚咽した。
軽くなった身体に気力が満ち、自分の人生なのだと実感する。
当たり前のことが妙に新鮮に感じられ、熱い感情でみるみる心が満たされた。
刻一刻と迫り来る時の中、新しい便箋と封筒を引き出しから取り出し、涙を拭ったオスカルはさっとペンを走らせる。
『私ごとき娘を愛し、お慈しみ下さって、本当にありがとうございました』
愛する父上・・・・・・・ただ一言でよかったのだ・・・・・・・。
それは一滴の蒸留水のように純粋で清々しい、娘からの感謝の想いであった。
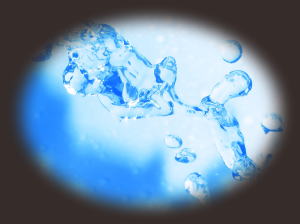
|

