Message for you
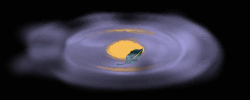
|
まだまだ残暑は続きそうなものの、やはり9月と言えば秋の始まりの爽やかさを期待してしまったりします。
夜になれば、庭から聞こえる虫の声、空にはくっきりと明るい月・・・
と言うわけで、今月は月がテーマです(ちょっと安易?)
現代の夜は、なかなか真の闇にはならないですよね。
家の明かり、街灯、夜遅くまで開いているお店、車のヘッドライト等々。
何かしらの光があります。時には人口の光が鮮やかすぎて、月も星も昔ほど目立たない(?)のかもしれません。
昔でも当然家から漏れる明かりはあったでしょうけれど、それはきっと現代とは比較にならないほどかすかだったはず。
周りも空も真っ暗な中、ぽっかり満月だけが浮かんで見えていたら・・・なんとも神々しい光景だったでしょう。感嘆や陶酔、神秘だけでなく、もしかしたらある種の恐怖すら覚えたかもしれないほど。
月が人に与える感情と言うのは、どちらかと言うと静的なものが多いように思います。
ゆったりと落ち着いたり、しみじみとしたり、物悲しくなったり・・・
なんだか「かぐや姫」みたいだけど(^^; 月を見て変身しちゃう狼男と言うのは、やっぱり西洋的な発想かなあ(笑)
昔の人々は、そんな月をたくさん歌に詠んだのでしょうね。
百人一首の中にも、月を詠んだ和歌が多いです。
春の月、夏の初めの月、冬の月、もちろん秋の月も。
いくつか秋の月の歌を拾ってみました。
秋風に たなびく雲の絶え間より もれ出づる月のさやけさ
(右京大夫顕輔)

月みれば ちぢにものこそ悲しけれ わが身一つの秋にはあらねど
(大江千里)
「ちぢに」と言うのは「千々に」、さまざまに際限なくの意味だそうです。
それほどに月を見ていると、あれこれ悲しいことが浮かぶ、そしてそれは「私一人だけの秋ではないのに」と結んでいます。
次に、秋の月と明記されてはいないのですが、同じように月を見て嘆く歌をもう一首。
嘆けとて 月やはものを思はする かこち顔なるわが涙かな
(西行法師)
「月やは」の「やは」は反語だそうで、ですから「月が嘆けと言って物思いさせているのか、いや、そうではない」とここでは詠んでいます。
にもかかわらず、月のせいだと言いがかりをつけるように涙が流れると。
西行法師は、出家者でも恋の歌が多いのだそうです(^^;
美しい秋の月を見て、自分の恋を憂えていたのでしょうか。
平安時代初期、漢詩文からの影響からか、秋を悲しい気分でとらえたり、月を見ることを忌むべきことと考えたりするようになったそうです。
今来むと 言ひしばかりに長月の 有明の月を待ち出づるかな
・ width="300" cellspacing="0" cellpadding="10">
|
|