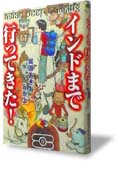 戦前は南方や満州へ、戦後は五木寛之、バブル時代には沢木耕太郎、最近はちょっとレベルが落ちるが猿岩石に感動し、なぜか日本男児は大陸をめざす。
戦前は南方や満州へ、戦後は五木寛之、バブル時代には沢木耕太郎、最近はちょっとレベルが落ちるが猿岩石に感動し、なぜか日本男児は大陸をめざす。その魅力を、堀田あきお&かよ夫妻がバックパッカーとしての体験をもとに描く傑作紀行が本書。真実は小説よりも奇なりの(日本人には)ほとんど不条理とも思えるインド社会のディティールと、そこを通過する彷徨える日本人像が克明に描かれ、紙の上の旅に引き込まれる。
ご覧のショッキングなコマ(157ページ5〜6コマ目)は、主人公スギタ青年が、インドで最後に寄った聖地バラナシにて、ガンジス河のほとりの火葬場を眺めるシーン。この地にはインド中から人々が「死を待つ」ために集まり、その遺灰は河に流されるしきたりだが、実際には遺体は生焼けで流され、野良犬たちを太らせる始末。おおよそ日本人の我々が思う「死の尊厳」には遠い光景だ。
しかし、インドで過ごすうちに、スギタの眼にはだんだんとそれが自然に感じ始められる。「死」を隠蔽(いんぺい)せず、日常の信仰の中でそれと向い合うインド社会に、やがて尊敬を感じ始める感動的なシーンだ。
描き方によっては説教臭くなりそうなテーマがスッと心に染みる秘密は、この主人公スギタくんの存在だ。ある意味で誘惑いっぱいの道中で、ヤバいハッパに手を出すわけではなし、頼られた女の子と得恋するわけでもなし。我々は彼と同行するものの、
いったい彼がどういう人間かは最後までわからない。成すすべもなく放心してインドを吸収して歩く主人公スギタだが、やがて彼こそ伝統的な価値とも宗教とも切り離され、戦後民主主義に育った私たち自身という「真空」の、個々の煩悩を抜いた共通像だと気付く。それが漂う宿命にあるのも納得できる。
「今どきアフリカやインドへ行って人生が見つかると思うこと自体が、陳腐で幼稚な発想」とは、友人がオウム真理教幹部として逮捕された時に、映像作家・山崎幹夫氏が発した名言だが、むしろそういう単純な人たちがうらやましいとさえ思えてしまう中途半端な我々の眼となって、青年スギタは旅を続けてくれている。続編を待つ。