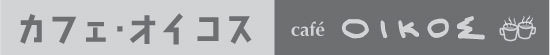
|
東・西・南・北、4つの方位。 さて、正確な方位の測り方を知っていますか?
地球は球形をしていて、地軸を中心に回転(自転)しながら、太陽の周りを回転(公転)しています。 その地軸の両端の点を北極点、南極点とよび、北極点の方向が〈北〉です。 これを〈真北、しんぽく〉といいます。
いっぽう、地球は大きな磁石の塊のようなもので、簡単にいうと、N極とS極があります。 方位磁針を使ってはかる〈北〉は、〈磁北〉といって、この地球のN極の方向をさししめします。 このN極=磁北点は、北極点と少しだけずれています。 そのため、真北の方向と磁北の方向もずれることになり(日本では3°から9°ぐらい)、 たとえば東京では、真北は磁北より約7度東側にずれるのです。
では、真北はどうやって測ればいいでしょう?
一日のうちで太陽が一番高く昇ったとき(南中時刻)の太陽の方向が真南、 つまりその時刻に地面に垂直に立てた棒の影の方向が真北です。 その日その場所の南中時刻が分かれば簡単に測ることができます。
★真北のはかりかた 理科年表を見ると、「東京」の毎日の南中時刻が出ています。 この「東京」とは、東京港区にあった旧東京天文台(東経139度44分29秒)です。 標準時や、緯度・経度を測る基準点に、定められています。
地球は1日24時間をかけて地軸の回りを一回転します。 (地球にいる私たちからみると、太陽が一日かけて地球の周りを一周します。) 太陽が動くにつれて、太陽が一番高く昇っている場所も刻々と移動するのです。
その速さは、地球の経線を考えるればよくわかります。 地球の経線(北極・南極を結ぶ線)は、イギリスのグリニッジ天文台を基準に、 東経180度、西経180度の合計360度となっています。 一日24時間を経度360°でわると、経度1°あたり4分、経度1′あたり4秒、 経度1°のぶんだけ回転するのに4分かかります。
測定したい地点、例えばあなたの家の経度を調べて、 基準点の経度(東経139度44分29秒)の差を出せば、南中時刻を計算することができます。
日本の中なら、観測地の東経が東京の東経より 小さいと(東京より西にある)南中時刻は東京より遅れ、 大きいと(東京より東にある)南中時刻は進むことなります。
緯度・経度を知るには地図サイトなどを利用します。 例えばgeocodingでは、住所を入力すると、緯度・経度が表示されます。
《例》 139度44分29秒-135度44分29秒=(経度)+4度 経度1度=時間4分より、4×4=16となり、16分遅れることになります。
11時47分46秒+16分=12時03分46秒 となります。 垂直の柱や窓サッシの影でも測れます。
いえや学校など、好きな場所で方位をはかってみませんか? はかりたい場所の住所または緯度・経度、測りたい日時をおしらせください。 南中時刻をお知らせします。 ◆緯度経度は地図サイトなどで調べられます。 ◆太陽が出ないと測れないため一週間分の南中時刻をお知らせします。 |
||||||||||||||||||||
| 南中測定プロジェクト
皆さんの測った南中測定データを掲載します。ご参加ください! |
||||||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||||