『土左日記』桃園文庫旧蔵為家本(青谿書屋本)の翻刻および校訂です。底本は以下の書によりました。
『影印本 土左日記』【萩谷朴氏編/新典社/昭和四十三年】

 『土佐日記』について
『土佐日記』について
土佐の国に赴任していた紀貫之が、都に帰るまでの出来事を日記の形式にのせて綴った書。「男もすなる日記といふものを女もしてみんとてするなり」という書き出しは、その意味深長な内容とは裏腹に枕草子の「春は曙云々」や徒然草の「つれづれなるまま、日暮らし硯に向かひて云々」に匹敵するほどまで人口に膾炙している。
その内容は、門出の承平四年(934)十二月二十一日から帰宅する翌二月十六日までの出来事を書き連ねるというものであり、海路の不安や任国で失った愛娘への惜念などが生き生きと描くものである。しかし詳細に検討すると、ここに書かれている内容はけっして記録的なものではなく、数々の虚構も含まれていることがわかる。考えようによっては、それは『土佐日記』の成立事情、すなわち帰京の道中に書きとどめていたであろうものがその素材とはなっているとはいえ『土佐日記』という形にまとめられたのは帰京後の天慶年間(938〜)ことであるという事情によるところもあると思われるが、時間が経ってからまとめたがために生じる齟齬とは考えられない意図的な虚構も認められ、「日記」と銘打ったときの作者意識についても検討の余地がある。
また、作者紀貫之は当時すでに歌壇の第一人者に目されていた自負からか、和歌に関する教導的な叙述や、和歌の先駆者である業平思慕もここかしこに見いだすことができ、貫之の和歌を考えるうえでの重要な手がかりを提供するものでもある。
さらに文学史的にみると、『土佐日記』の成立は漢文謳歌の時勢から仮名文字の隆盛に移行していく時期にあたっていることから仮名散文初期の様態を探ることもでき、そればかりか、その作者が和歌の第一人者であったことから、仮名散文における和歌的表現の役割を知る上でも重要な書であるとも言える。
なお現在に伝わる『土佐日記』は、貫之の手による祖本ではない。しかし、祖本から直接転写したとされる為家筆本があり、その模本である青谿書屋本が影印本で刊行されており、手軽に利用できる。

 紀貫之について
紀貫之について
9世紀後半から10世紀前半にかけての人。出生についてはあきらかになっていないが、貞観十年(868)または十四年(872)とされる。貫之に直接結びつく史料で、もっとも古いものは是貞親王家歌合および寛平御時后宮歌合に提出された歌であり、是貞親王家歌合が寛平(889〜)のはじめ頃、后宮歌合が寛平四年(892)頃のこととされ、貫之二十歳前後のことであったという。王朝歌壇への登場の頃よりすでに将来を嘱望される新進歌人であったようだが、やはりその名を後世にまで長く残すこととなったのは、『古今和歌集』撰上である。紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑とともに命を承けたのだが、実質的には四人の中でもっとも年齢の若い貫之が撰定の中心になったという。
『古今和歌集』撰定については、当時の醍醐天皇主導の事業であったのか、あるいは宇多上皇によるものであったのかという問題や、そもそもなぜ他の三人に比べて若輩の貫之が指名されたのかなど不明のところは少なくない。しかし、三十代の若さでこの国家的な事業に参画したことでその名声は不動にものになったのは確かである。
だが歌壇での名声と位階は結びつくものではなく、常に有力貴族の庇護をあてにせねばならない境遇にあったようである。貫之の履歴をみると、『古今和歌集』を奏上した当時の御書所預以降は、越前権少掾、内膳・典膳、少内記、大内記、加賀介、美濃介、大監物、右京亮と続いており、この中で地方官としての職も現地赴任のしない遙任であったことから、延長七年頃までの貫之は京都に留まる専門歌人としての活動が主であった。そして当時の専門歌人というものが、有力貴族からの依頼によって屏風歌を作ることでその存在が認められるのであるならば、まさに有力者の庇護が不可欠の生活であったということになる。
こうした貫之の半生を見ると、五十九歳という老境にさしかかっての任地赴任には彼を取り巻く状況、たとえば最大のパトロンであった藤原兼輔の立場等に何らかの変化があったものと思われる。貫之が土佐の守に任ぜられたのは延長八年(930)正月のことであるが、すでに醍醐治政の次を睨む空気が政界に広がっていたのかもしれない。
ともかく実生活に利する官位の昇進という点についていえば、貫之の人生はけっして恵まれたものではなかった。『土佐日記』の中にたびたび見られる在原業平に対するまなざしにも、歌詠みの先達としての尊敬も含まれるにせよ、思えば権力闘争からはじき出されて風雅の生活に遊んだ業平に自らの境遇を重ねているかのようにも読めなくはない。
体裁・表記ともに底本のとおりに翻刻しました。
底本での改行は日次の変わる箇所のみです。翻刻でも改行しています。
底本では和歌の前に約一字分空けられているところがあります。翻刻では一字分スペースを置きました。
傍書・補入・ミセケチ・墨滅等も底本どおりに残し、本文とリンクする形で下フレームに原態(GIF画像)を提示しました。
二字以上に相当するの踊り字は*で示しました。
一音節語は字母の意味が文脈に対応するときのみ漢字のまま残しました。
解読できなかった文字は□で示し、原態を掲げました。
字母「旡」の「む」と、字母「无」の「ん」の判別は困難なので、語彙的に撥音便とならないものは「む」とし、それ以外は撥音便と見なして「ん」としました。
 「をんなもしてみむとて」の「みむ」。「む」の撥音便と判断して「ん」と翻刻。
「をんなもしてみむとて」の「みむ」。「む」の撥音便と判断して「ん」と翻刻。
 「すむたちより」の「すむ」。この場合、「ん」と字形は似ているが音便化しないので「む」と翻刻。
「すむたちより」の「すむ」。この場合、「ん」と字形は似ているが音便化しないので「む」と翻刻。
各行には通しで行番号を施しました。
なお新日本古典文学大系『土佐日記 蜻蛉日記 紫式部日記 更級日記』(土佐日記担当・長谷川政春氏/岩波書店/平成元年)の校訂本文を参考にしています。
句読点は適宜施しましたが、以下の方針を原則としています。
- 明らかに文末と判断できる箇所には句点を施しました。
- 独立した文形式を持ちながらも、内容的に後続表現の説明等となっているものは挿入句と判断して読点としました。
- 一文中で条件関係を示す係り承けがある場合には読点で区切りました。
- 条件関係が判然としなくても、冗長になる場合は適宜読点を施しました。
- 主部が判然としない場合は読点で区切って明示しました。
- 和歌の直前の連体形は地の文と和歌が連続する形とみなして読点にしました。
濁点は諸注釈書に従って適宜施しています。諸注によって見解が分かれる場合や私案によって改変している場合は特記しました。
漢字の当て方は品詞を基準とし、以下の方針を原則としています。
- 仮名のまま残すもの 付属語、補助動詞、代名詞(こそあど系)、副詞、連体詞、接続詞、感動詞
- 漢字を当てるもの 名詞、代名詞(人称代名詞)、動詞、形容詞、形容動詞
- なお後者の品詞群でも漢字自体が一般的でないと判断した場合は仮名のまま残しました。
ex 「あやし」→×「奇し」、
次のケースは例外としております。
(例外)
「こと」「ところ」「もの」「ため」「とき」(形式名詞としての用法、およびそれに準ずると判断した場合)
「〜といふところ」の「いふ」(発話以外の「いふ」)
詳細の不明な人物名は姓名とも仮名とし、太字を用いました。また清濁については一律濁音記号を付さず原文のまま残しております。
地名は典拠を明示して漢字を当てました。
多義語は文脈を考慮して漢字を使い分けました。一応の目安は以下の通りです。
- 言/こと(事) 「言葉」の意味に重点がある判断した箇所は「言」と漢字を当てました。それ以外は形式名詞と判断して仮名としました。
- 波/浪 海上のうねりの高さ・激しさに主眼のある場合は「浪」の漢字を当てました。
- 日/陽 陽光や日差しについては「陽」を当てました。
- 歌/謡 和歌の場合は「歌」、歌謡の場合は「謡」としました。ただし「舟唄」などの慣用的用法には従いました。「歌ふ」「謡ふ」についても同じ基準です。
掛詞が用いられている語句については仮名のまま残しました。
改行および文字下げは以下の方針を原則としました。
- 日次の変わる箇所は一行あけました。
- 和歌、歌謡の前後は一行あけました。
- 同日記事でも主題が変わるところでは改行しました。
会話文には前後の文脈から判断して「 」を施し、地の文と区別しました。
なお作中人物の発話箇所は会話文として「 」を施しましたが、心内語については「 」はつけません。発話か心内語かの判定は私案によります。先学の諸注釈と見解の異なる箇所については注記を施しました。また形式的に発話であってもその始まりと終わりが不完全な箇所については注記を付けることにして、片方の記号を施しました。
名詞句の並立によって意味が通じにくくなる箇所ではナカグロ「・」を用いました。
歴史的仮名遣いが一般的用法と異なる箇所は訂正し、★印で指示しました。
青谿書屋本の独自異文は訂正せず、☆で指示しました。
踊り字による反復範囲は通例に従って解釈しました
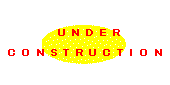
語釈
形容詞注
語法
地名注
年中行事註
習俗・信仰・儀礼
典拠
歌論的評釈
影響
私案
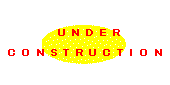
| 資料名 | 出版情報orURL |
| 『影印本 土左日記』 | 萩谷朴氏編,新典社,昭和四十三年 |
新日本古典文学大系
『土佐日記 蜻蛉日記 紫式部日記 更級日記』 | (土佐日記担当)長谷川政春氏,岩波書店,平成元年 |
| 『土佐日記全注釈』 | 萩谷朴氏,角川書店,昭和四十二年 |
| | |
| | |
| | |
| | |
 「をんなもしてみむとて」の「みむ」。「む」の撥音便と判断して「ん」と翻刻。
「をんなもしてみむとて」の「みむ」。「む」の撥音便と判断して「ん」と翻刻。 「すむたちより」の「すむ」。この場合、「ん」と字形は似ているが音便化しないので「む」と翻刻。
「すむたちより」の「すむ」。この場合、「ん」と字形は似ているが音便化しないので「む」と翻刻。