|
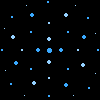
ひゅるるるるるる〜
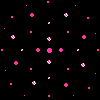
パン!
ドドォーーン!!
音が鳴り響く度に、沢山の人の声があがる。その場にいる全ての人が空を見上げ、夜空に美しく咲く花火を見て、惜しみない歓声や拍手を送っていた。
ドン! ドン!
だがしかし、打ち上げられる花火に酔いしれている人々を後目に、あくせく働いている人達がいた。
「いいなぁ。やっぱこういう場所は、可愛い彼女と来たいもんだよな」
「本当、何が悲しくてこんな事してんのかね」
そんな風にぶつぶつとぼやきながら交通整理をしている若い警察官二人は、丁度側にいた小太りの年配の上司に聞き咎められて注意されていた。
「おい、お前達。文句言ってないで、しっかり仕事に専念しろ」
偉そうにそう言った後、彼は視線を車に戻し、後部座席に座っている、自分より更に上の立場の人物に媚びを売る様な作り笑いをした。
「申し訳ありません。全く、今の若い警察官は緊張感が無くて…」
汗を拭きながら話しかける彼を一瞥し、その人物は苦い顔をしていた二人の部下達に生真面目に声を掛けた。
「たまには息を抜くのも良いだろう。だが、そろそろ終了の時間が近付ている。これから混雑が酷くなると予想されるから、全員気を引き締めて仕事にあたってくれ」
警察組織の常識からいけば雲の上の存在である彼が、自分達の様な下っ端の人間に直接声を掛けてきたのにも驚いたが、上司の叱責から幾分庇うかの様な発言をした事に、彼等は多いに驚きながらも「はい」と元気良く返事を返した。
「私はA地区を見て来る。ここは君に任せて良いか」
「勿論です、任せて下さい」
張り切って任務を了解する部下の言葉を聞いたその人物は、静かに肯いた後に落ち着いた軽い身のこなしで車から外に出た。
その予測しなかった行動に、回りの人間は慌てた。
「課長? どちらへ?」
「A地区だ」
さっき言っただろう、と言わんばかりの口調で答える。
「では…」
「歩いた方が速い」
部下の言わんとしている事に即座に返事をして、さっさと人混みの中を歩いて行く。
人波を掻き分けながら、あまりの人の多さに彼はつい眉間に皺を寄せてしまった。
全くよくこの状況で毎年人が集まるものだ。
半ば呆れながらも前に進んでいく。
本当に、これが仕事でなければ、自分は絶対こんな所には来ようとは思わないだろう。あの男だったらば、きっと嬉嬉として参加するのだろうが。
「あれ、室井さん?」
考え事をしていたら、背後から急に自分を呼ぶ声が聞こえたので、彼は反射的に立ち止まった。
この声の主は、今自分が思い出していた…。
「青島?」
振り返ると、そこにはTシャツにジーパン姿の、団扇を片手に持った青島が立っていた。浴衣姿でないのが不思議な位に、彼はこの場にしっかりと馴染んでいた。
「室井さんも、花火を見に来たんスか?」
「馬鹿者、仕事だ」
突然現れて、相変わらず脳天気な事を言う男に内心脱力しながらも、室井は冷たく言い放った。
「はぁ、そりゃ大変っスね。ご苦労様です」
団扇をぱたぱたと扇ぎながら、他人事の様に(実際他人事なのだが)言う青島に、室井はついムッとして嫌みの一つでも言ってみる。
「仕事で無ければ、私がこんな所に来る訳が無いだろう。君の様に、わざわざ混雑した所にデートに来る輩と一緒にしないで貰いたい」
「? 俺、デートじゃ無いッスよ」
室井の言葉に驚いた様に目を見開いた後、青島はあっさり否定した。
「実は湾岸署の皆と一緒にいたんです、さっきまで」
苦笑しながらそう答える青島の台詞に、室井は疑わし気に睨み付けた。
そんな室井の様子に、青島は肩を竦める。
「本当ッスよ。すみれさんと雪乃さんや圭子ちゃん達と、ついさっきまで一緒だったんスよ」
「……別に君のプライベートに口を挟むつもりはない」
「え、本当ですってば。……ああ」
自分の今の姿を思い出して、室井の疑いに納得する。
「この姿は、今日張り込みの手伝いをしていたからッスよ。着替えようと署に戻ったら、すみれさん達に無理矢理引っ張って来られちゃって。そのままの格好で来ちゃったんスよね」
その言葉に何故か安心する自分を見つけて、室井は慌てて打ち消した。
しかし、花火はまだ終わっていないのに、側に誰もいないという事は……。
「…はぐれたのか?」
「はい」
頭を掻きながら笑って答える男に呆れて、室井は盛大な溜め息を吐いた。
「君は一体いくつだ」
「しょうがないじゃないッスか〜。こんなに混んでるんですもん、大人だって迷子になりますよ」
情けない顔で弁解する彼に、室井は心の中で微笑した。
「捜さなくて良いのか?」
気を取り直して打ち上がった花火を呑気に眺めている青島に、沸き上がった離れ難い自分の気持ちを無視して室井は問いた。
「いいッスよ。どうせ花火もあと少しですし、捜したってこの人込みじゃ見つからないだろうし。向こうだって俺の事なんてほっといて、さっさと帰っちゃいますよ。それより、こんな大勢の人の中で室井さんに会えたなんて、何か運命的って感じがしません?」
満面の笑顔でさらっと言い流したその台詞に、らしくなく動揺する。
ドン!
その時大きな音と共に、今迄の中でも一番大きな花火が打ち上がった。
ついうっかりと見上げて見てしまった室井に、青島はにっこり笑って言った。
「綺麗ッスよね」
「…仕事中だ」
一瞬職務を忘れた自分を思い出し、青島に乗せられてしまった様な不本意なこの状況が、室井をいつもより更に仏頂面にさせてしまった。しかし、そんな室井に青島は全く頓着せずに、サラリととんでもない事を言い出した。
「じゃあ、今度は仕事抜きで見に来ませんか?」
「…男二人で花火を見て、何が楽しいんだ」
「室井さんとなら、俺は楽しいと思いますよ」
狼狽える気持ちを必死に隠しながら、なるべく冷静に言った室井の言葉に、青島は満面の笑顔で答えた。
「…機会があったらな」
「約束ですよ」
目線を反らし、何とか平静な声を作って素っ気無く返事を返してやると、青島は無邪気に喜んで、ちゃっかり約束を取り付けてしまった。
全く、この男はよく恥ずかしげもなくそんな台詞がすらすらと出て来るものだ。
しみじみ思う室井を余所に、だが、純粋に喜んでいるらしい青島の様子を見ていると、気恥ずかしさを感じつつも気分は良かった。
実際、内心では喜んでいたのだが、その気持ちを相手に(しかも青島に…)素直に伝える事は、やはり室井には難しかった。
ふと気付くと、目的地のA地区にたどり着いていた。
名残惜しい気持ちを押さえて「じゃあ」と切り上げる室井に、青島は声を掛けた。
「お仕事頑張って下さい。あ、室井さん」
「……何だ?」
立ち止まって振り返った室井に、青島はにっこりと微笑んで、
「……たまには一緒に食事でもしましょうね」
と言って、人混みの中を歩いて行った。
その姿を見送りながら、たったそれだけの青島の言葉で元気が出てしまう自分を自覚して苦笑する。
「…全く、私も現金なものだな」
そう呟いた後、気を引き締めて己の仕事に戻って行く姿は、青島が密かに惹かれている室井の警察官の姿だった。
END
|