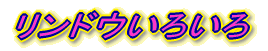
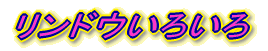

|
「リンドウは枝さしなどむつかしげなれど、異花などのみな霜枯れたれど、いとはなやかなる色合いにてさし出たるいとおかし」・・・・枕草子 リンドウは日本の秋を代表する花であるが、山上憶良の秋の七草の中には入っておらず、文学に登場するのは 「枕草子」 からで、清少納言がその生態や風情を上記の様に見事に述べている。 「リンドウは茎が倒れて枝ぶりはうっとうしいが、他の花が皆枯れてしまう頃に華やかな色合いで咲き、実に趣がある」 の意味である。 現代、我々が良く見るリンドウはエゾリンドウやミヤマリンドウを改良した園芸種で、枝ぶりもすっきりしているが、古来からの野生のリンドウはササリンドウとも呼ばれるようにササの葉に似た葉で、茎が倒れやすく地を這う傾向がある。 |
 |
 |
 |
リンドウ
 |
 |
 |
ツルリンドウの花と赤い実
 |
 |
 |
エゾリンドウやミヤマリンドウから改良された園芸種のリンドウ
|
リンドウは薬として名があり、かっては水田周辺の草地やため池の堤防等、何処にでも見られ、その可憐な花姿から秋を代表する花であり、仲間のツルリンドウの赤い実は秋の山野の風物詩ではあるが、現在ではこの近辺の散歩道で見つける事はなかなか難しくなってきている。 |