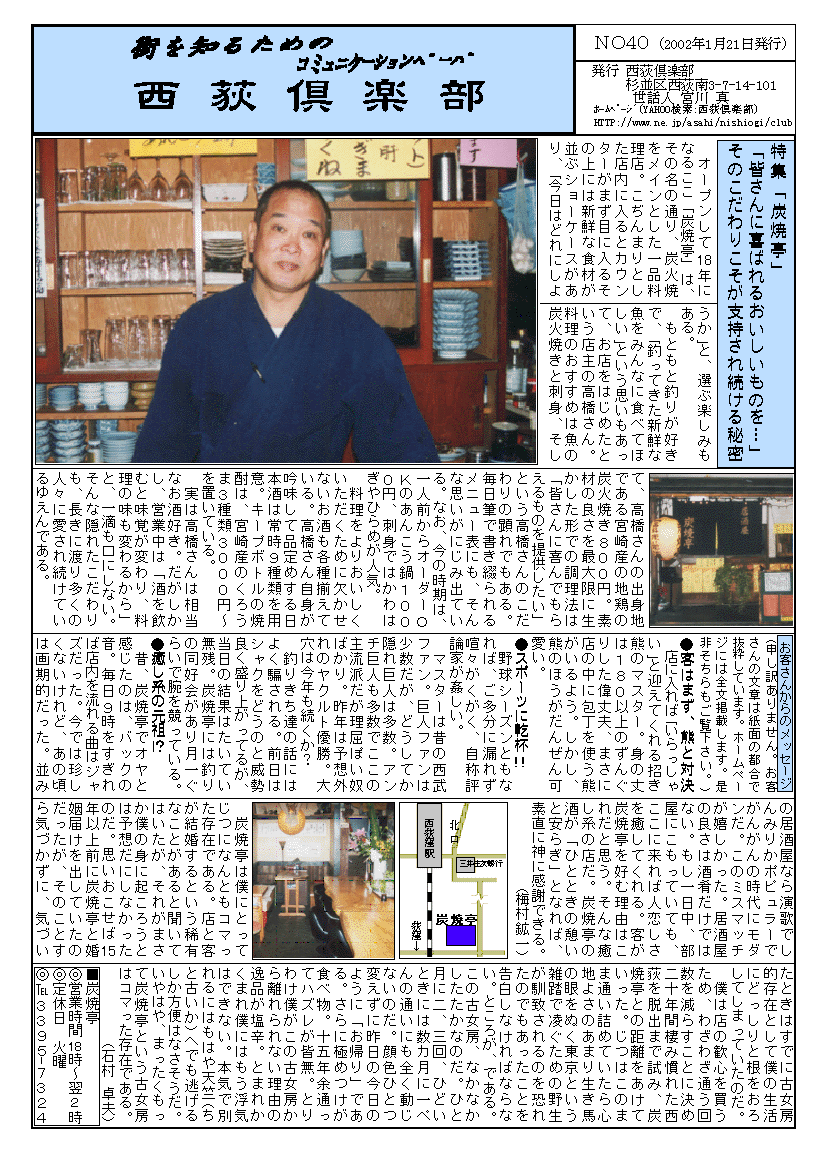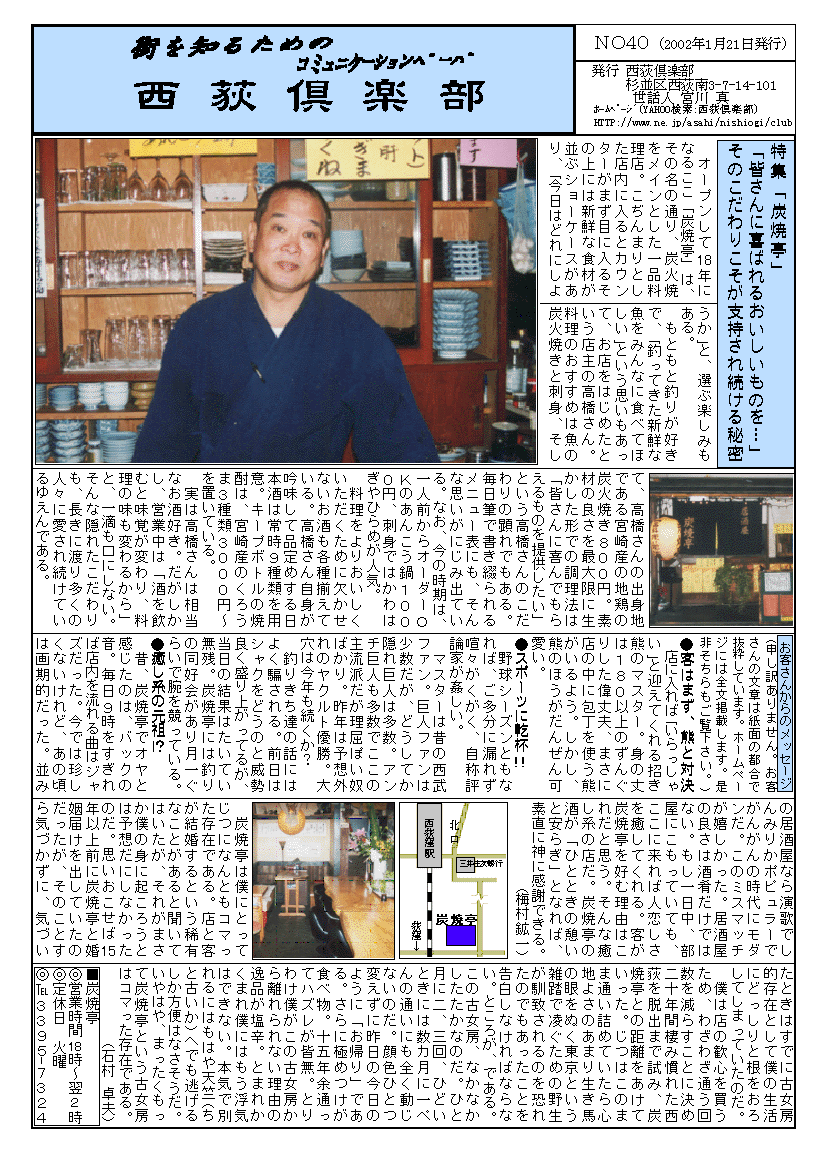
石村さんの全文を掲載します。
炭焼亭は僕にとってじつになんともコマった存在である。
店と客が結婚するという稀有なことがあるとは聞いてはいたが、それがまさか僕の身に起ころうとは予想だにしなかったのだ。思いおこせば15年以上前炭焼亭と婚姻届けを出していたのだったが、ウカツなことにそのことすら気づかずに、気づいたときはすでに古女房的存在として僕の東京の生活にどっしりと根をおろしてしまっていたのだ。因みに僕にとって東京とは西荻であり、西荻といえば炭焼亭である。そして奇妙なことにその炭焼亭にはもう一人。高橋のケンちゃんという文字通りの亭主がいる。このご亭主、宮崎出身の九州男子で海坊主とにらめっこをしたような人相風体、どうみても僕のほうが男前であるのにかかわらず僕より先にこの店と結婚していたフシがある。その証拠に僕が馴染みになったときすでにカウンターの中に入っていたのだ。ということは店と肉体関係があったという紛れもない証拠だ。僕と同郷の青森出身の細君と子供が三人もいるにもかかわらずだ。僕は激しくシットした。僕は店の歓心を買うため、わざわざ通う回数を減らすことに決め二十年間棲み慣れた西荻を脱出まで試み、はては練馬、東村山と炭焼との距離をあけていった。じつはこのまま通い詰めていたら心地よさのあまり生き馬の眼をぬく東京という雑踏で凌ぐための野生が馴致されるのを恐れたのでもあったことを告白しなければならない。ところが、である。この古女房、なかなかしたたかである。ひと月に二、三回、ひどいときには数ヶ月に一ぺんの通いにも全く動じないのだ。顔色ひとつ変えずに昨日の今日のように「お帰り」、である。さらに極めつけがこの店の食べ物。まことに律義に日替わりのメニュー表を手書きしているのはまだいいとして、それらの食べ物にハズレがないのである。十五年余通ってハズレが皆無。これは奇跡である。いや、これは女房自慢の惚気ではない。とりわけ僕がこの古女房から離れられない理由の逸品が塩辛。
百聞は一味にしかず。塩辛が苦手でいまだ炭焼の塩辛を食せずにいる人は生まれてきたことの存在意義をもう一度真剣に自問してみることだ。少なくとも文化とか品とかはどういうものか分かる筈だ。とまれかくまれ僕にはもう浮気はできない。本気で別れるにはもはや天竺(ちと古いか)へでも逃げるしか方便はなさそうだ。
いやはや、まったくもって炭焼亭という古女房はコマった存在である。
(石村 卓夫)