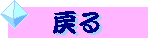新潟県糸魚川市小滝 |
採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|---|---|
| 翡翠 | 少ない | 運しだいですね |
| 軟玉 | 少ない | 運しだいですね |
| 曹長岩 | 多い | 狐石の代表です |
| 石灰岩 | 多い | 山一つ全部ですから |
| 透緑閃石 | 少ない | 運しだいですね |
| 蛇紋岩 | 多い | 3種類ありますか |
新潟県糸魚川市小滝 |
採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|---|---|
| 翡翠 | 少ない | 運しだいですね |
| 軟玉 | 少ない | 運しだいですね |
| 曹長岩 | 多い | 狐石の代表です |
| 石灰岩 | 多い | 山一つ全部ですから |
| 透緑閃石 | 少ない | 運しだいですね |
| 蛇紋岩 | 多い | 3種類ありますか |
出発は朝7時だった。天気予報は良くないと言っていた。(とりわけ日本海側)しかし、奈良や大阪・京都は小雨で西名阪・近畿自動車道・名神・北陸自動車道と順調な滑り出しであった。途中、朝食のために、サービスエリアに立ち寄ったが、心の焦りはみじんもなかった。それよりも、初めて行く糸魚川への期待が否が応でも膨らんできて、どんなところだろうか。翡翠は採れるだろうかとそればかりが気がかりであった。サービスエリアで小一時間過ごしたが、別に気にもならなかった。何せ2泊3日である。時間は十分にある。ここであわてて事故でも起こせば元もこもない。
しかし、八日市インターをすぎるあたりから雨足が強くなってきた。今までは順調だったが、車の調子が妙におかしい。道路一面に雨水が浮き出してきて、タイヤが変な感触である。ハンドルの方も言うことを聞いてくれない時がある。これぞまさしく、うわさに聞いていたハイドロプレーン現象である。すぐにパーキングエリアに車を入れタイヤを見てみると、前のタイヤの溝が全くない。つるつるとはこのことである。(さわってみたら本当につるつるだった。)しかし、ここではどうすることもできない。何とか次の大きな町まで走って、タイヤを新品に交換するしかなさそうだった。とりあえず、スピードを抑え、先に進むことにした。
そして、雲行きが怪しくなってきたのは木之元インターを過ぎたあたりからであった。賤ケ岳サービスエリアまでの登り道の横に雪が積もっているのがちらほら見え始め、道が下りにさしかかった頃、何と雨が雪に変わってきたのである。
前方には白いマーク・ツーと2・3台の普通車が見えていただけであったが、みんなあわててスピードを落とし始めた。坂の真ん中まできたとき雪がさらに強くなり、もう、道路上にもうっすら雪が積もっていることが見えだした。前輪のタイヤはつるつるである。これではまともに運転できるわけがない。シフトをD(ドライブ)から2(セカンド)へ落とし、ブレーキを踏まないように変えた。ところがすごく不安定である。考えて見ればこの車はFFでエンジンブレーキをかけると前輪にだけ制動がかかり、ふらつくのである。あわててDに戻し、ブレーキを薄くかけながら、30Km/hまでスピードを落としてから、2に落とした。幸い雪の抵抗と下りがゆるくなってきたことで、スピードがそれ以上あがることはなかったのでそのまま走って行くことにした。
ちょうどその時、生まれて初めてのものを見ることができた。なんと前を走っていたマーク・ツーが回っているのである。回りながらまっすぐ走っている。非常に奇妙な光景であった。と思った瞬間、360度以上回った後でお尻の方から、左の鉄線のガードレールに突っ込んで行った。しかし、すぐ後ろ(といっても北陸自動車道は通行量が少ないうえに、雪とタイヤの怖さが手伝って、車間距離は300m以上あったと思う。)を走っていた私は肝を冷やした。やがてどこかにぶつかって止まるだろう2000ccの車と、雪と、つるつるのタイヤと、下り道である。実際には車が止まるまで数秒であったろうが、数分に感じられた。ただ、不幸中の幸いで、その車もスピードは30Km/hくらいだったので、ブレーキランプのカバーが割れただけで、怪我はなさそうであった。胸をなで下ろして、再出発したが、あの電話の若い女性の声が妙に頭の中にこだましていたのを覚えている。「いくら新潟でも12月に雪なんて心配いりませんよ!」ここはまだ滋賀県である。
仕方がないので福井インターで降り、タイヤ屋さん(そんなものがあるのか知らないが。)を探して福井市の方に向かって国道を進むと200mほど行ったところにブリジストンの「タイヤ館」があった。私たちの目的にぴったりのネーミングである。前輪2つ分のタイヤを新品に交換してもらい待つ間は休憩とした。しかし福井でタイヤを交換するとは夢にも思わなかった。人生はいろいろあるものである。そんなこんなで30分がつぶれた。しかし、そこからは雪も小雨に変わり、ホイールバランスもばっちりで順調に先を進むことができた。倶利伽藍峠あたりで小さなヒョウが降ったがそれくらいで何もなかった。(と言っても昼食で息子がカレーをたのんだが、大人用のカレーはさすがに辛く食べられなかったようで、私のカツ丼と交換されてしまったり、トイレ事件やお菓子事件など小さいものはいっぱいあったが・・・。)ただ、有磯海パーキングエリアは日本海がすごくきれいで一度は行ってみたかったが、うっかり見逃してしまった。(帰りでは海側でないので見えないのだ。)
朝日から一車線になったが、通行量がさほど多くないので、スムーズに通れ、5Kmにも及ぶ長いトンネルを抜けてようやく親不知インターチェンジに着くことができた。奈良を出て8時間半、怖い思いをしてようやくたどり着いた。(6時間もあれば到着できる距離である。)
ピア・パークでトイレをかねて休憩をすることになった。怖い思いをして長時間の運転はつらかったので、いつもの元気はなかった。時間はもう3時30分であるが、本当に休みたかった。食堂はまだ少しはきれいだが、トイレのところがちょっと汚い、サービスエリアのようなおみやげ物やさんを少し見て回り、翡翠ラーメンまであることに感心しながら、食堂のコーナーの方の扉の横に翡翠の塊(80Cm×60Cmくらい)があることに気づいた。肉眼で見る初めてのヒスイであった。なめ回すように眺め、なで回し、一歳半の娘を上に載せて写真に収めた。初めて翡翠というものを見たが、今まで写真やその他で見ていたものとかなり違うと思った。やはり標本や写真になっているものは一級品であり、今目の前にある、風化面の多い、質の良くない所もたくさんある、この翡翠を見ているとフィールドで見つけられるかどうか心配になった。
とりあえず、海岸に降りてみることにした。名前も翡翠海岸である。東(海を見て右)に亀の像があって、その向こうに海に下りられる広い道があった。その向こうにユンボが一台置いてあって、土砂崩れの補修をしていた。ユンボの方に足が向いてしまうのは、石屋の癖のようなもので、ユンボの引っかいている地肌は黒く、翡翠は採れそうにないのだが、新しい掘り跡を見るとつい足がそっちを向いてしまった。(専門用語?で言うパブロフの犬状態である。)石は片岩のようなものに白い方解石の脈が走っているだけのもので、得るようなものはなかった。
ふと、海岸の方を見るとユンボで海岸の小石をほじくった跡が見える。慌ててその窪んだ所に入ってみると、3つほどの緑の石が見つかった。これぞまさしく本で見た色・艶のヒスイである。先ほどの翡翠とは似もつかなかったが、その時は感激の方が先で全く気づかなかった。(着いて3分で見つけたのである。採りに行った人の話を聞くと、とても難しいらしいのに。)
後は波打ち際でと思ったが、今日は天気が悪く波が荒い。10回に1回は1m以上ある波もやってくる。うっかり波に飲まれたら浜に戻れる自信はない。すぐに助けてくれそうな人もおらず、息子も波のすごさに圧倒され、後ずさりしている有様である。もちろん私も恐怖を覚えるほどである。とりあえず波を遠巻きにしながら30分ほど探したが、先ほどの4Cmくらいの3個の石以外は見つけることはできなかった。そして、先ほどから退屈そうにしていた愛娘と妻の視線に耐えきれずに予約してあるホテルに行くことにした。ここからは国道で糸魚川まで下見をかねて行くことにした。今回は青海の方は回らないつもりだったので、少しでも様子を見ておこうというつもりであった。
「ホテル糸魚川」には5時少し前に着いた。雪は少し降っていたが、本降りというほどでもなかった。しかし、夜中にどれくらい積もるかわからない。息子だけを誘ってホテルのすぐ後ろに見えている姫川の河原で、少しばかり採集を試みることにした。とは言っても雪の日の日暮れである。河原へは出たものの、周り一面薄暗く、石の色の判別もあまり着かなかった。しかし、明日足止めを食らっては何もできない。何しろ石の採集の一番の敵は雪である。一面の銀世界では何も採ることはできない。独身の頃、12月31日に石を採りに行ってひどい目にあったことがある。
そこで、緑色の石らしきものと変わった色の石を片っ端からスーパーの袋に詰めてかかった。ところが、ものの10分ほどで雪が本降りと化し、見る見る河原の石の上に積もっていくのである。一瞬の出来事のようであった。あっと言う間に1Cmを越えた雪は翡翠の夢を跡形もなく粉々にしてしまった。シャーベット状になった雪を通して、下の石の色が見えなくなっていたのである。しかたがないので、今まで採った30個ほどの7Cmくらいの石を、ホテルに持って帰ることにした。しかしホテルの中まで持って入るには忍びないし、エレベーターを上るのは恥ずかしすぎる。(部屋は704号室である。したがって7階まで上らなければならない。)そのまま駐車場に回ってトランクに放り込むことにした。そこで、目にしたものは、愛車の上に5Cm以上積もった雪の山であった。奈良では見たことのない光景である。愛車もさぞびっくりしたことであろう。かわいそうに思って、積もった雪を払ってやり、トランクに重い石を積み込んで、お風呂に行くことにして部屋に戻った。ただ、翡翠らしき三つの石と肉眼鑑定が難しそうな物だけはじっくり眺めるために部屋に持ち込み、舐めるように見ていた。(特にこの翡翠は頬ずりするほどの眺めようで妻もあきれていた。)
リゾート気分を満喫したいという妻の願いで、1泊、2万1000円のホテル代を出して思い切ってこのホテルを予約したのである。露天風呂と温水プールのついたこのホテルで夜はゆっくりと過ごそうと思った。しかし、露天風呂のあるお風呂への通路に糸魚川の地質説明のプレートが6枚ほど張ってあるのを見てさすが糸魚川だなと変な感心をしながら、読みながら歩いていった。フォッサマグナという言葉がナウマン博士のつけた名前であることなどを勉強しながら、息子に手を引かれて風呂場に入った。息子は露天風呂に入るのが初めてで、期待していたようだった。しかし、あの時代に地質を調べゾウの化石が新種の化石であることを見抜くなどナウマン先生もよっぽどのマニアであったのだろう。などと思いながら、露天風呂に行ってびっくりした。翡翠の湯である。浴槽の周りの大きな岩がほとんど翡翠なのである。これにはびっくりした。そういえばホテルの玄関にもびっくりするほど大きな翡翠が鎮座していた。おそるべし糸魚川である。
料理もすごく美味しかった。
次の日は朝6時に起きて外の様子をうかがった。いや、うかがう前から何となく様子が変である。いやに外が静かで白い。見て驚いた。一面の銀世界である。白以外は全く見えない。30Cmは積もっているようだ。今日の翡翠取りはどうなるのだろうと自分に問いかけるまでもなく中止は決定であった。こういうことになるかもしれないと、雪の北陸自動車道を走っている間に考えていた行程に切り替えることにした。今回は第一回目でもあるし、翡翠に目を慣らすために、博物館や物産展を回ろうということであった。外とは打って変わって快適なホテルで朝食をゆっくりとって満喫し、8時近くに出発することにした。
まず最初はフォッサマグナミュージアムである。さすが雪国だけあってホテルの駐車場にも国道にも融雪用のパイプが引いてあって水が出され雪を溶かしてはいた。だが、轍だけは雪の量は少なかったが、所々アイスバーンになっている所や雪の積もっている所も多かった。車はみんな、できるだけ雪の少ないところを走ろうとするので、電車の単線の線路のようになっていて、車は一台分しか通ることができないようになって、なかなか前に進めなかった。やっとの事でミュージアムの看板が見え、左折してまた驚いた。ほとんど車が通った跡がないのだ。雪は30Cmは積もっている。何とか前に進もうともがいたが、少し前に進んであきらめた。なぜなら、くねったすごい坂が見えてきて、フォッサマグナミュージアムに行くにはそれを上らないと行けないのだ。おまけに、雪の重みで竹が何本も道に倒れこんでいる。これではとうてい上れそうにない。またもや予定通りにはいかなくなってしまった。この危機を何とか脱する方法はただ一つ、タイヤチェーンを買うことである。またもや耳の奥に、あの電話の若い女性の声が聞こえてきた。「いくら新潟でも12月に雪なんて心配いりませんよ!」今日はまだ12月2日である。おとといまでは11月だったのだ。
駅前に行けばチェーンくらい売っている店があるだろうとたかをくくっていたが、駅までの道のりの中にはそんな店は見あたらなかった。それでなくても雪で滑りやすいのである。もうイヤになってきた。結局、糸魚川駅の正面まで来たが、どうにもならなかったので、車を駅前に止め近くの商店街でお話を伺うと、駅の裏にナルスというホームセンターがあることがわかった。駅の東の細いガードレールをくぐり、ナルスはすぐに見えた。しかし、雪はその間も少しではあるが降り続いていた。やっとの思いでチェーンは手に入れたが、これからそれをタイヤに付けなければならない。初めて買ったチェーンはやっかいで、雪の降る中、説明書とにらめっこをしながら、30分はかかっただろうか。その間家族は車の中でぬくぬくしていたが、私は一人で凍える手で一人寂しくチェーンと格闘していた。(父という生き物は寂しいものである。)そして、またまた耳の奥に、あの電話の若い女性の声が聞こえてきた。「いくら新潟でも12月に雪なんて心配いりませんよ!」私は今チェーンと格闘しているのである。
ようやく今日の予定のめどがつき、まずは翡翠園に行くことになった。大阪芸術大学の先生の設計だそうで、巨大な翡翠の塊が印象的でまた雪とのコントラストもよかった。よい思い出となった。
次に玉翠園に行った。谷村美術館とともに併設されてあるのだが、ここの食堂のテーブルが、翡翠の薄板でできており、なかなかきれいであった。そこで軽い昼食を取り、次の行程に移った。
午後はフォッサマグナミュージアムである。朝は雪で通れなかったが、今はラッセル車が雪をかいてくれた後であったので先ほどよりは上りやすかったが、まだ雪は降り続いており、何度か休憩しながらでないと上れなかった。この博物館は必見で、テーマ別になかなかうまく展示してあった。石に興味のない者でも楽しめる工夫がしてあり、家族で行っても退屈せずに済んだ。展示してある量もかなりの物で、広い館内にうまく配置されていた。販売のコーナーも充実し、初心者から上級者までが楽しめる物であった。日が良かったというか天気が悪かったことが幸いして、館内の見学者は少なく、ほか一組の家族連れと、中年の男性が一人だけであった。おかげで広い館内は自分の物のように自由に見ることができた。最後には学芸員の方まで登場していただき、糸魚川の地質の説明から、取ってきた石の同定までしていただいたが、残念なことに肉眼鑑定の難しそうな石だけをホテルに置いてきてしまい、見ていただくことができなかった。無謀な肉眼鑑定はやめれば良かったと悔やんだが後の祭りであった。もう一つ残念なことがあった。それは、ここの石と比べて判ったのだが、どうも昨日海岸で拾った三つの緑の石はどれも、クロムを含む曹長岩のようで、翡翠ではないようだった。俗に言う「狐石」というヤツで、私もどうやらこのキツネにだまされていたらしい。昨日の晩の私の頬ずりはいったい何だったのだろう。ふと自分が情けなくなってきた。また、えらい姿を妻に見られたもので、あの石が翡翠でないことが妻に知れたら私の面目は丸つぶれである。とんだところで窮地に立たされたものである。
帰るときになってまた問題が持ち上がった。私たちが、館内でゆっくり見学している2時間の間にも、雪は深々と降り続け、その勢いを増していたようで、駐車場に戻るのに一苦労し、自分の車を見て愕然とした。
車がないのである。
置いてあったはずの場所に大きな雪だるまが一つあった。どうもその下に愛車が埋もれているらしい。最後には見学者は私たちだけだったが、やっとその理由が判った。しかし、何とか脱出しなければならない。道具は何もないので手で(腕でといった方がいいかもしれない。)雪をかき分けかき分け15分はかかったと思うが、何とか車を掘りあげることができた。大人はしんどいが、子ども達は楽しそうで、思わぬ雪合戦にすごく楽しそうであったのが唯一の慰めであった。しかし、帰りの坂はほんとに怖かった。道は雪でわからず何度も側溝に落ちそうになり、雪で何度も滑ってしまった。
またもやへとへとになりながら、連泊のホテルに帰った。
ホテルへ帰るなりロビーで人々が北陸自動車道の通行止めのことをうわさし合っていて、話を聞いてみると、この雪が続く限り高速道路は使えないようである。夕食は連泊の客には別メニューらしく昨日とは違った料理でとても満足のいくものであったが、明日の雪のことを思うと気分ははれなかった。お風呂にも行ったが、雪が10階ほどもあるホテルの屋上から落ちてきて危ないと言うことで入浴禁止であったので入れなかった。おかげでその夜はテレビのニュースをずっと見ていなければならなくなった。しかし、いくら見ていても通行止めの解除はなりそうになかった。
朝になったが、する事も行く所もなく、途方に暮れてしまった。大雪で地面は全く見えず翡翠は見えそうにないし、海は荒れて海岸には近づけない。小滝や青海の翡翠産地にはこの車では行けそうにない。ホテルの中でチェックアウトの時間までゆっくりしている以外に方法はなさそうである。
朝から天気はまずまずで、太陽もたまには見えていたので9時頃にやっと北陸自動車道の通行止め解除の知らせを聞き、帰路につくことになった。私としては残念で仕方がなかったが、北陸自動車道の帰路には倶利伽藍峠近くと賤ヶ岳の難所が控えている。今の情報ではそのあたりでも通行止めが行われているらしい。明日は仕事に出なくては行けないし、ここで足止めを食ってしまうわけには行かなかった。ここに来るまでのことを思い出すと、帰らねば仕方なさそうだった。また雪が降ったら、どこでまた通行止めになるやも知れなかった。ホテルから糸魚川インターまで直行し、そのまま家路についた。途中やはり雪やヒョウに悩まされながら、帰ることになったが、幸いなことに通行止めはすべて解除され、速度規制はあったものの何とか通ることができた。ただ、前を走っていた、赤いスープラが私の車の500m前で2回転し、ガードレールにぶつかり、ラジエーターから湯気を噴きだしはじめた。その横をゆっくり通り過ぎたが、幸い速度規制中であったので、運転手にけがはなさそうであった。賤ヶ岳サービスエリアに入ると先ほどの事故のあたりがまた通行止めになってしまったようで、早くに出てきたことを初めて良かったと思った。普通なら6時間で帰ることができるところを9時間もかけてようやく家に着いた。計算してみると使ったお金は20万円を少し超えていた。翡翠は一つも採れなかった。もう泣きそうである。何のために新潟まで行ったのか全く分からなかった。妻や子ども達はホテルや雪にわりと満足しているようであるが、私の目的は何も達成されなかった。悲しい限りである。
しかし、天は我を見放してはいなかった。トランクから着替えのバッグや初日に採った石を出して整理にかかって発見した。雪で見えないながら採ってきた緑の石のほとんどは蛇紋岩であったが、中に一つだけ翡翠が混ざり込んでいたのである。はじめに気づかなかったのは、蛇紋岩の薄い層が裏に張り付いていたからだった。確か拾ったときは裏向きになっていて、これは翡翠とは違うなとは思いながら袋に入れた記憶がある石である。奴奈川姫が余りにもかわいそうと思ったのであろう。そして私に憐憫をたれてくれたようだ。深く感謝しなければならないと思った。
半年後の1998年7月に今度は息子だけを連れて雪のリベンジのため、またも糸魚川チャレンジを決行した。今度も2泊である。安くあげるためにキャンプにした。「ルネス金沢」という健康スパ・ランドのような所で一泊し、糸魚川に向かった。
しかし、今度は台風が接近し雨が降ってくるという予報であった。雨も降り出してきた。急いでホームセンターの「ナルス」に飛び込んでカッパを調達し(やはり12月の旅行は無駄ではなかった。)、姫川の河原で採集をはじめた。めぼしい石を採り、運良く翡翠も3つほど採ることができた。小滝の翡翠産地を見学し終わった頃から雨足が強くなり、今回も中断を余儀なくされた。ラジオで聴いてみると、新潟に直撃のコースでやってきているらしい。妻からも携帯電話に避難命令がかかって来た。
またもや、半ばで帰路につく羽目になってしまった。金沢あたりで台風の中心に入ってしまい、またもルネス金沢に避難することにした。台風が去った午前4時に出発し9時には我が家に到着していたが、台風一過、すばらしい天気であった。どうも私は新潟には運がないらしい。しかし、採れないと言われていた翡翠がいとも簡単に手に入り、うれしい限りであった。
今回も、雨で大変だったが、濡れた石が本来の色を出してくれ、翡翠その他の鉱物の鑑定は非常に楽だった。本当に何が幸運をもたらすか分からないものである。(専門用語?で棚からぼた餅とでも言うのだろうか。)