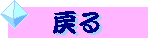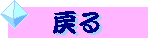採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|
| 電気石 | 少ない | 運しだいですね |
| ガーネット | 少ない | 灰磐柘榴石でクラックがすごいです |
| 苦灰石 | 少ない | 岩の隙間に成長しています |
| 石英 | 多い | 山ペグマタイトですから |
| 長石 | 少ない | 文象花崗岩もあります |
| 雲母 | 多い | 白黒両方あります |
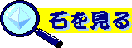
1987年11月22日
K氏からお誘いがあって、三重県大山田村におもしろい石があるので見に行こうと言われるので案内していただくことにした。それだけではもったいないので、そのまま峠を越えて榊原温泉の近くの化石を見て帰る計画になった。おもしろい石が何かは全く分からなかったが、疑問も感じずについていった。この頃はまだ駆け出しの頃で、この石のことを私は「でんきいし」とずっと言っていた。ところが最近、図鑑で「でんきせき」とあるのでようやく「せき」であることが分かった。10年以上はそう思っていた。恥ずかしい限りである。
西名阪国道の中瀬インターで下りてそのまま服部川をさかのぼり広瀬という集落をすぎたあたりに道路の切り羽が見える。そこがこの産地である。手前に大きな採石場があるが、ダイナマイト云々と書いてあるし事務所が見あたらず、中には入ったことがない。この採石場からも同じものが出ると思われるが致し方ない。
ここは、閃緑岩を貫くペグマタイト脈でマグネシウムを含んでいるらしく、じっくり探すとマグネシウムを含む鉱物が多く見つかる。独身だったこの頃は時間も有り余るほどで、3時間以上も採っていたと思う。それでも平気だったし、それが楽しかった。
寒い中で採れた物は、電気石が主になるが、その大きさや産状もいろいろであった。大きな物は、直径4Cm長さ10Cmもある柱状の物であるが、残念なことに、電気石が晶出後に大きな圧力を受けたらしく、クラックが多くきれいな柱面があまり見えない。また、小さなペグマタイトの中心部に平行に晶出した直径5mm長さ4Cmくらいの、これぞペグマタイトといわんばかりの物も採れた。
また、3.5Cmくらいのクラックだらけではあるが結晶型のハッキリしたサイドもきっちり鋭いガーネットを採ることができた。
上の採集できる物の中には書かなかったが、薄いピンク色の石英(ローズクォーツ)が採れた。ただ、10年後には色があせて、普通の石英になってしまったが、採れた当時は確かに薄いピンク色であった。光の入らないところで保存していたのだが、ダメだったようだ。
また、1987年には何の石か分からなかったが、まれに岩の割れ目に沿って白い結晶の脈が走っていることがあるが、たぶん苦灰岩であろうと思う。しかし、たった二つだけ採れた自型結晶の見える標本は裏が赤く色づいている。赤といってもれんが色に近い。近くにマンガン鉱山もあることからこの赤色はそれによるものと思うがどうだろうか。
しかし、マンガンと苦灰岩が接するとどうなるのであろうか。新産鉱物でも出やしないかと思ってはいるのだが、確かめてはいない。
1995年の秋に妻と息子を連れて採りに行ったことがあった。10年ぶりであったので懐かしく思われた。ローソンで弁当を買い、切り羽の少し上流の河原にレジャーシートを引き、家族で弁当を食べながら秋を満喫しようと思っていた。石取りはどうしても家族サービスのついでになる。悲しいことであるが、それが楽しいときもあって複雑な思いである。
ようやく弁当を食べ終え、息子と河原を散歩していると、大きな石英が転がっている。どうもおかしい。ここは産地の上流である。ペグマタイトの脈は下流だ。石が川を泳いでくるわけがない。探していると長さ4Cm直径3mmくらいの電気石も見つけた。どうやらまだ上にも電気石ペグマタイトは存在しているようだ。(まだ確かめたわけではないが。)私は興奮しながら妻に、石の説明を始めたが、妻の方は一向に気乗りしない様子で私はがっかりしてしまった。(最近は少し興味を持ってくれているので嬉しいが、もしかしたらうまく操られているのではないかとも思っている。石を採りに行くと、外でご飯が食べられるから。)
食事の後、切り羽に向かった。最近は工事も進み、なかなか良いものに当たらなくなっていた。15分もするとみんなが退屈になり、引き返すことになった。
名阪国道に向かってゆっくり秋の紅葉を見ながら進み、きれいなところでは立ち止まっていった。ちょうど真泥橋を過ぎたあたりの、古琵琶湖層群の化石の産地の少し下流あたりでススキの穂が夕日に輝きすごくきれいな場所を見つけた。そこで写真撮影をすることになった。といっても「写るんです」しか持って来ていなかったが、それでもすばらしい写真を撮ることができた。ここはおすすめの場所である。逆光で写すのは難しいが、無理矢理フラッシュをたき、レンズに太陽光線を入れることで輪ができ、真ん中の被写体が強調され、バックの燃えるようなススキの穂がアクセントになって芸術的な作品に仕上がった。何をしに来たか目的がずれたが、すばらしい思い出の写真は撮れた。
ただ、ここには広瀬と書いたが、本当の地名は違うかもしれない。これも、1985年に行ったときの思いこみであるかもしれないと思う。場所は国道が川の流れに沿って大きく曲がっている所で、現在は曲がっていた道をまっすぐにするための工事をしている。その切り羽なのである。
しかし、なぜ川がここで大きく曲がったのかを考えると、ペグマタイトの脈が理由であるように思える。福岡の長垂のリチウムペグマタイトが、波に浸食されずに海に突き出ているようなものだと思うのだが、どうだろうか。
帰りの道の名阪国道は運転のやっかいなところで、一般国道なので時速60Km/hが最高速度であるが、信号がないこともあって、制限速度を守っている車はないと行って過言ではない。反対に守ってしまうと後ろからクラクションの嵐である。左車線は100Km/hで走り、右車線は70Km/hで走っている。私としては80Km/hくらいがちょうど良いのだが、右車線では遅すぎていらいらし左車線では早すぎて怖い。仕方がないので左車線で走っているが、どちらにいても心の安まるときがない、一番走りにくい道だと思っている。天理から関までの1時間30分はいつも疲れてしまう。何とかならないものだろうかと思っているのは私だけだろうか。