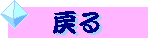奈良県奈良市菩提山 |
採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|---|---|
| 白雲母 | 多い | きらきら光ってきれいです |
| ガーネット | 少ない | 少し掘らないとないですね |
| 石英 | 多い | ペグマタイトですから |
| 長石 | 多い | 小さい産地なのですぐなくなるでしょう |
| 黒雲母 | 少ない | あまり見かけません |
奈良県奈良市菩提山 |
採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|---|---|
| 白雲母 | 多い | きらきら光ってきれいです |
| ガーネット | 少ない | 少し掘らないとないですね |
| 石英 | 多い | ペグマタイトですから |
| 長石 | 多い | 小さい産地なのですぐなくなるでしょう |
| 黒雲母 | 少ない | あまり見かけません |
|
峠越えの安全祈願? 古代の雲母片三片 奈良「柳生の里」阪原阪戸遺跡 祭祀具として使用か 「柳生の里」の一角で、古代の峠越えの際の祭祀(さいし)跡という説のある奈良市阪原町の阪原阪戸遣跡(五〜八世紀)で二十三日までに、五世紀(古墳時代中期)ごろの雲母の結晶片三点が見つかった。 薄片だが大きなものは三センチ近くもあり、元は一つの大きな結晶片だっだとみられる。鏡の単調な反射光とはひと味違い、角度によって微妙に変化する怪しい輝きに、峠での旅の安全祈願や外敵封じの願いを込めたとも推定される。 雲母片は、五世紀の遺構で採取された土砂を選別中に、ごく小さな滑石製臼玉(うすだま)多数と一緒に見つかった。 厚さ一ミリほどで、南西約十キロに雲母の産地が知られており、祭祀用に持ち込まれたとみられる。 調査を担当した奈良県文化財保存課の木下亘主査は「臼玉はビーズのように糸につないで使われたとみられることから、雲母片も穴を開けて糸を通し、キラキラ光る祭祀具として使ったのではないか」としている。 同遺跡は大和から東国への峠に当たる山間部に位置。石組み溝で引いた水を水槽で浄化するなど、五世紀から八世紀(奈良時代)にかけての大掛かりな「水の祭祀」跡が二年前に確認された。 峠越えのみそぎに使われたとする説のほか、在地豪族の豊作祈願の祭りとする見方なども出ている。 |