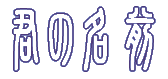 そんな必要はどこにもなかったけど、何となく彼女を部屋まで送っていった。 「じゃあ・・・おやすみ・・・フランソワーズ」 その深い翠の瞳が驚いたように、真っ直ぐに僕を見上げる・・・。 南極を離れ、北上を続けるドルフィン号。僕らはブラックゴーストのマッドマシン=M1号から受けたダメージを調べるため、順番にメディカル・チェックを受けていた。身体に取り付けられた様々な装置・・・。サイボーグに改造され初めて気がついた時のことを思い出す。かすかに吐き気を覚えた。 「・・・よし、どこもおかしいところはないようじゃな。良かった良かった・・・全員なんともなくて・・・」 ほっとしたように言うギルモア博士。濃い疲労の色が、彼の老いた顔を覆っている。 「・・・ありがとうございました」 不快な思いを、彼に悟られたくない・・・足早にメディカル・ルームを出て、水を飲もうとキッチンへ向かった。 「・・・003!」 キッチンのテーブルにひとりぽつんと彼女は座っていた。 僕を見て微笑む。 「009・・・どうだった?」 「ああ、だいじょうぶ・・・。それより、どうしたの? 今休憩中だろう、寝なかったのかい? ・・・もうすぐフランスだよ?」 彼女は、1日だけ休暇をもらっていた。生まれ育った場所に、どうしても行ってみたいのだと言って。 「・・・そうね・・」 呟いて、ふと気づいたように、僕にコーヒーは?と尋ねた。 淹れてもらったコーヒーを飲みながら、そっと彼女の様子を窺った。テーブルの上に置かれた白い指が、ぼんやりとあの時計をなぞっている。 「・・・その時計・・・」 ためらいがちに僕は口を開いた。 「いつも持ってるね・・・。ずいぶん古いものみたいけど・・・」 ふっと彼女が微笑む。 「古いわよ・・・。だって私のいた時代から持って来たんだもの」 「え?」 「・・・・この時計・・・私がブラックゴーストに捕まったときも持っていたの。大事なもので・・・・でも、もちろん気づいたときには無くなってた。それが・・・・」 遠くを見るような目で話す。 「・・・長い・・長い眠りから引き出された時、私、この時計をしっかり手に握っていたんですって・・・」 「・・・・・」 「ギルモア博士から聞いたとき、信じられなかったわ。だって・・・そうでしょう?」 ブラックゴーストから逃げ出した後で、ギルモア博士はそれまでひそかに隠し持っていたその時計を彼女に渡したという。 「・・・本当に、同じ時計なのかい?」 信じられない思いで、僕は尋ねた。 うなずいて、彼女は時計の蓋の内側に刻まれた文字を僕に示した。 「・・・なんて、書いてあるの?」 「・・・・最愛の妹、フランソワーズへ。15の誕生日に、さらなる愛を込めて・・・ジャン・アルヌール」 「フラン・・・ソワーズ・・・」 「ふふっ。私の名前よ・・・・でも・・・」 そういって、淋しげに瞳を伏せる。 「そう呼んでもらったのは、ずいぶん昔・・・。もう私の名前を呼ぶ兄の声も、思い出せないくらい・・・・」 「・・・・・」 なんと言えばいいか分からなかった。彼女の顔を見ているのが辛い。そんな僕に、 「009・・・聞いていいかしら。あなたの名前は・・・?」 「・・・ジョー。島村ジョー」 「ジョー・・・」 小さく呟く。 「・・・忘れないでね。あなたの名前を呼んでくれた人のこと」 そう言うと、ふいに、さあ!と明るい声を出して立ち上がった。 「もう夜明けね。降りる準備をしなきゃ・・・」 「・・・送っていくよ」 思わず言っていた。 そして、パリの街は君に何を見せたのだろう。今にも崩れ落ちそうな古い建物のテラスで、憑かれたように踊る君。連れ戻さなきゃ・・・それだけを思っていた。そうしないと、君はとんでもない所へ行ってしまう・・・。 「003!やめるんだ!!・・003!」 どんなに叫んでも、僕の声は届かない。僕の手を振り払い、そして、銃を向け・・・。思わず口をついて出た、君の名前。 「フランソワーズ・・・フランソワーズ!!」 君を愛した人が呼んだ名前。 そう、この街では君は003じゃない。いや、どこでだって君は、003である前にフランソワーズというひとりの女の子なんだ。 そして、僕も・・・・。 確かに、君が僕の名を呼ぶのが聞こえた。 「おやすみ・・・フランソワーズ」 僕を見上げた翠色の瞳が、一瞬ゆらめいた。 「・・・・忘れていたわ」 「・・・?」 「ありがとう、ジョー・・・・メリー・クリスマス」 「!」 ドアの向こうに消えた彼女を見送って、僕はたった今キスされた頬を思わず押さえた。顔が赤くなるのが自分でも分かる。みんなの所へ戻る前に何とかしなきゃ・・・そう思って歩きながら、ふと思った。 ・・・今日は朝からずっと、彼女の事ばかり考えてたな・・・。 ―――また頬が熱くなった。 《おわり》 |