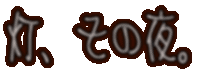 君がこんなに飲めるなんて知らなかった。 突然フランスからやってきて、ビックリしたけど僕は嬉しかった。 一年ぶりに会うフランソワーズ。 「・・・・でね、ジェットのハガキったらね・・・・」 頬がピンク色に染まって、大きな瞳が潤んだようになっている。ワインは2本目の赤がもう、 残りわずか。 (ほとんど彼女が飲んでるよなぁ・・・) 僕らは暖炉の前の敷物に小さな足の低いテーブルを持ってきて、そこで夕食を食べた。 僕には残りくずにしか見えなかった野菜のきれっぱしや干からびたチーズが、ちゃんといくつかの 料理になって。 (すごいな・・・・女の子って) 床に座り込んでグラスを合わすと、なんだか秘密のパーティーでもしているような気がして、僕は とても楽しくなった。そして、多分彼女も。 「なんにも書いてないのよ。マンハッタンの夜景の絵葉書にね、”元気か!”ってそれだけ。 名前も書いてないの!」 くつくつと笑いながら言いつける。 「すぐにジェットだって分かったけど・・・・でも名前くらい書いてあってもいいと思わない?」 間近で僕を覗きこむ瞳にちょっとドキドキする。 テーブルの角をはさんで座っている彼女の肘が 時々僕の肘と触れ合う。 「アルベルトは結構筆まめね。やっぱり絵葉書なんだけど、仕事で行った先の様子なんかとっても ステキに書いてくれて・・・・無口な人だけど、結構ロマンティストなのね。ココにも届いてるでしょう?」 「え?いや・・・・そうでもないかな」 1度か2度、アルベルトからはハガキが来ていた。簡単な近況報告。ジェットに至っては電話1本 来ていない。そうか、彼女のところにはみんな結構連絡を入れてるんだ・・・・・。 分かるような気がするな・・・・・・僕は微笑んで言った。 「みんなからはあまり連絡はないよ・・・・君だってずいぶん前に手紙をくれただけで、そのあとは 電話もくれなかったじゃないか」 ちょっとだけ間があいた。 けれどすぐに彼女は僕にボトルを持ち上げながら口を尖らせる。 「そうね・・・・でもジョーだって1度も連絡くれなかったでしょ」 そのまま自分のグラスにも、もう何杯目か分からなくなった紅い液体を注ぐ。 「それは・・・・」 だって、博士宛にきた手紙だったし・・・・最後に ”ジョーにもよろしく” とはあったけど。 「あ、あとグレートはね・・・・・・・」 知る限りの仲間の消息。僕のこと、イワンのこと、博士のこと・・・・僕の知ってた彼女より、少し 早口ではずんだ口調。とても楽しそう・・・・なんだけど。 「ねえ・・・そんなに飲んで大丈夫?」 2本目のボトルが空になる。 びっくりした・・・・みんなが知ったらなんて言うだろう。飲むほどに陽気になって、声を上げて笑って。 「平気平気! こう見えてもフランス人だもの! もう1本持ってくるわね」 分かるような分からないようなことを言って、立ち上がろうとした彼女がよろめいた。 「危ない・・・!」 とっさに抱きとめる。 ・・・・・柔らかい。セーターごしに伝わる彼女の柔らかな感触。防護服の時には分からない、華奢で それでいてしなやかな体―――。 !! 僕は今何を・・・・? 思わず、抱きしめた、彼女を・・・・・ほんの一呼吸分。 「あっ・・! あの・・もう止めた方がいいよ! 飲みすぎだよ、こんなフラフラして・・・・」 慌てて言ったけど、君は何だかぼんやりとして、僕のしたことなんてあまり気にしていないようだった。 「・・・・そう・・・かな」 「そうだよ! 後片付けは僕がやるから・・・そこで休んでて」 「・・・・うん」 テーブルの上を片付けている間、彼女はぼんやりと暖炉の火を眺めていた。 さっきまでとはうってかわって、ひっそりと。 「・・・・水、持ってこようか?」 聞いた僕に、かすかに微笑んで首を振った。 (飲みすぎ・・・・だよな、やっぱり・・・・・) 彼女の様子を気に掛けながらキッチンで食器を洗う。 そうしながら、また彼女の柔らかな感触を思い出していた。 (ダメだダメだ・・・! 何を考えてるんだ? 最低だぞ! 酔った彼女にあんな・・・・・・) 頭を振って、さっきの自分に腹を立ててみる。 戦闘中に庇って抱きかかえたり、何かで落ち込んだ彼女の肩を抱いたりしたことはあったけど、それは みんな彼女を思いやってのことだった。だけどさっきのは・・・・・・。 (・・・・・ホント、最低だな) ワインの酔い。久しぶりのフランソワーズ。二人だけの夜・・・・・・二人きり? (ああっ、もう、どうかしてるぞ!) 冷たい水で乱暴に手を洗うと、しんと静まり返ったリビングを覗いた。 「フランソワーズ・・・? 大丈夫かい?」 ――――彼女は眠っていた。テーブルの上に顔を伏せて。 (あ〜あ・・・・・あんな姿勢で眠ってたら気持ち悪くなっちゃうよ・・・・) そばに行って肩に手をかける。 「フランソワーズ、起きて・・・こんな所で寝ちゃダメだよ」 「う・・・ん」 少しだけ身じろぎして、でもちっとも起きる気配がない。 (仕方ないなぁ・・・・・) テーブルの向かい側で頬杖をついて、少しの間、その寝顔を見つめた。 君がここを出てから一年が過ぎた。もう会うこともないかもしれないと思っていた君と、こうしているなんて。 現実とは思えなかったあの戦闘の日々は忘れたかったけど、仲間のことはいつも懐かしく思い出していた。 なかでも君のことを想う時は、泣きたいほどの懐かしさと、わずかな胸の痛みが伴って。 会いたかったんだ・・・・・とても。 なんだか変だった、今夜のフランソワーズ。僕の知ってる彼女とちょっと違う。 でも、あのブラックゴーストとの戦いからもう一年。 故郷に戻って、夢だったエトワール目指してまた踊り始めて、平和な街でごく普通の女の子として 過ごしてきたんだもの。これが本当のフランソワーズなのかもしれない。 心のどこかで違和感を覚えながらも、そう思った。 乱れた髪を直してやるふりをして、彼女の頬に手を伸ばす。 触れていたかった。今夜は僕も、ただの若い男だった。 (・・・・・やっぱり部屋に連れていこう) 大きく一つ息を吐いて、立ち上がった。 フランソワーズは起きそうにないし、このままここに一人置いておくわけにはいかない。 かといって、一晩中、彼女と一緒にいて・・・・心穏やかでいる自信が、今夜の僕にはない。 「起きて・・・フランソワーズ!」 身動き一つしない。少し深い、規則正しい息遣いが聞こえる。 (・・・・・・・・・・・部屋を暖めてこなきゃ) 階段を上がり、フランソワーズの部屋のドアを開ける。 やはり部屋はひんやりとしていた。 手探りで明かりのスイッチと、エアコンのスイッチを同時に入れる。 そして、僕の眼に飛び込んできたのは。 ――――ベッドに投げ出された、見慣れた赤い服。 たった今脱ぎ捨てられたかのように、黄色い布地もふわりと広がって、ベッドからこぼれ落ちている。 ――――なぜ彼女は突然帰ってきたんだろう。 ふいに大きく湧きあがる疑問。 浮ついた感情などあっという間に消え去って、僕は防護服をそっと手にとった。 久しぶりで目にしたそれは、僕のものより一回りも小さくて、身につける彼女のかぼそさを、 今さらのように僕に突きつけた。 ―――――一体、何があったの? この服を見て、何を想っていたの? そして、ようやく気づいた。今夜、フランソワーズがちっとも自分の話をしなかったことに。 僕が尋ねてもすぐはぐらかしてしまって・・・・。 眠ったままの彼女を抱き上げる。 かすかに眉を寄せたけど、やっぱり目は覚まさない。 腕が覚えていた記憶より、フランソワーズは軽かった。 くたりとすべてを僕に預けて眠る君。こんな風に無防備な君は初めてかもしれない。 ベッドにそっと下ろした時、彼女が何かつぶやいた。そして、長い睫毛の間にしずくがひとつ。 「・・・・え? 何?」 顔を寄せたけれど、もう唇は閉じて、また規則正しい寝息に戻る。 フランス語・・・・? 僕の翻訳機では捉えられなった、吐息交じりのかすかなつぶやき。 しばらく彼女の寝顔を見つめて、それから少しためらったけど、額に静かに口づけた。 言葉に出来ない分、心を込めて、彼女のために。 おやすみ・・・・・フランソワーズ。 《おわり》 <あとがき> 『灯ともして。』の一応続編ですが、これだけ読んでも大丈夫だと思います。 そしてまた続きそうな気配ですが、一応これはこれでおわり・・・の予定。 続きは、またいつか機会があったらまとめてみたいです。 それにしてもこのジョーはやけにナイーブくんだなぁ。ゴメンなさい・・・・。 |