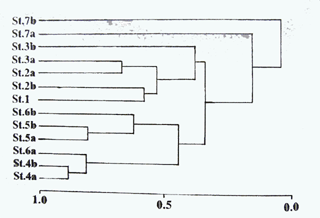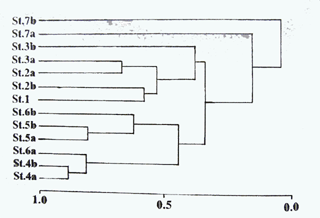富士山のカマアシムシ類とコムシ類
今回の富士山北麓で生物多様性調査が行われた。その調査で、カマアシムシ類では2科7属13種が、コムシ類では1科1属2種が確認された。確認された種は次のとおりである。
1.確認種
カマアシムシ目 Protura
- クシカマアシムシ科 Acerentomidae
- モリカワカマアシムシ Baculentulus morikawai (Imadaté et Yosii, 1956)
本種には、頭部に付加毛を持つものと持たないものが知られているが、今回得られた個体はすべて付加毛がない個体であった。
- トサカマアシムシ Baculentulus tosanus (Imadaté et Yosii, 1959)
- タカナワカマアシムシ Filientomon takanawanum (Imadaté, 1956)
- フタフシカマアシムシ属の一種 Kenyentulus sp.
フタフシカマアシムシ K. japonicus によく似るが、前肢ふ節の感覚毛b'がt2と同列に位置する点で異なる。日本各地から記録されている。
- ヨシイムシ Nipponentomon nippon (Yoshii,
1938)
- ウエノカマアシムシ Nipponentomon uenoi paucisetosum Imadaté, 1965
ウエノカマアシムシN. uenoiには、今立(1988)により6つの型が認められている。今回記録されたのはB型、従来の東日本型亜種であった。
- コブクシカマアシムシ Verrucoentomon shirampa (Imadaté, 1964)
- ヤマトカマアシムシ Yamatentomon yamato (Imadaté et Yosii, 1956)
- カマアシムシ科 Eosentomidae
- アサヒカマアシムシ Eosentomon asahi Imadaté, 1961
- オオカマアシムシ Eosentomon asakawaense Imadaté, 1961
- カマアシムシ Eosentomon sakura Imadaté et Yosii, 1959
- ウダガワカマアシムシ Eosentomon udagawai Imadaté, 1961
- ウダガワカマアシムシの近似種 Eosenotmon sp. cf. udagawai
ウダガワカマアシムシによく似るが、後肢の爪間体(empodium)が爪の1/5より短いので、
ここでは別種として扱った。日本各地から見いだされている。
コムシ目 Diplura
- ナガコムシ科 Campodeidae
- マツムラナガコムシ Metriocampa matsumurae
Silvestri, 1931
- クワヤマナガコムシ属の一種 Metriocampa sp.
2.特徴
カマアシムシ類
記録された種をみると、ヨシイムシやモリカワカマアシムシは普通種で,広く分布している。
今回も広い範囲わたって出現した。トサカマアシムシ、タカナワカマアシムシ、カマアシムシ、
ウダガワカマアシムシは、本州の温帯・暖温帯圏で普通に見いだされるものであり、
今回は低標高域からのみ記録された。一方、アサヒカマアシムシ、ヤマトカマアシムシ、
コブクシクシカマアシムシは冷温帯から亜寒帯を主たる分布圏とする山地性の種である。
特に、コブクシカマアシムシは岐阜県を南限とし、本州中部域では山地でのみ記録され
ている(Imadatée,1994)。今回もSt.3からのみ記録された。オオカマアシムシ
は本州東部から北部にのみ分布し、貧弱な植生からは得られていない(Imadaté,
1974)。これまでの最西端の記録は神奈川県山北町であり(Imadaté,1974)、
今回の記録は最も西の地点となる。
全体としては、山地性や本州東部・北部に限定される種が多く見いだされ
ているところに特徴がある。これは、高標高域での調査を反映しているものと考えられる。
今回、ウエノカマアシムシのB型(メス1個体)がSt.6より記録された。これ
までの調査で、富士吉田市滝沢林道(カラマツ、1520m
alt.、1996年8月29日採集)と馬返し(シラビソ、1450m
alt.、1996年8月29日採集)からはC型と思われる個体が採集されている
(中村、未発表)。B型は本州中央部より東部・北部に分布し、C型は
関東西部から中部地方東部で見いだされているが、B型は他の型との共存は報告さ
れていない(今立、1988)。富士山での両型の分布については今後の調査が必要である。
コムシ類
コムシ目には、尾角が糸状のナガコムシ科とハサミ状のハサミコムシ科・ニセハ
サミコムシ科があるが、今回の調査ではナガコムシ科のクワヤマナガコムシ属の2
種しか確認できなかった。今後の調査により他の種も見いだされる可能性は高い。
日本でのコムシ類の分類並びに分布の解明はきわめて不十分で、富士山のコムシ類の特徴
を述べられる段階に達していない。
3.群集構造
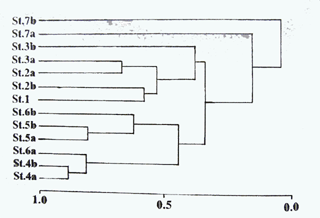 |
| Sørensenの類似係数によるデンドログラム |
各地点の種構成の類似性を比較するために、Sørensenの類似係数を用い郡平均法よりデン
ドログラムでグルーピングした。その結果、St.1〜St.3の地点とSt.4〜St.6の地
点がそれぞれまとまり、やや類似性が高いことを示した。St.1〜3は標高2100m以上の地点
であり、St.4〜6は1060〜1130mの間にある。それらの間には、1000m以上の高さの違いがあ
り、これが影響していることが考えられる。さらに、St.4〜6は火山地形でもあり、これ
も影響しているのかもしれない。植生はそれぞれの地点で異なっており,大きな影響を与えていないと思われる.
St.7の標高はSt.4〜St.6のそれの範囲に含まれるが,いずれともグルーピングされなか
った.これは、ススキ草原という環境が影響しているのだろう。さらに、2001年と2002
年に同一地点で調査を行っているが、それらがお互いにグルーピングされなかったのは、採
集による誤差等によるものと思われる。
4.文献
Imadaté, G. 1974. Protura, Fauna Japonica.
Keigaku Publishing Co., Tokyo. 351 pp
今立源太良、1988。ウエノカマアシムシの諸型。 Edaphologia,
(38): 17-26.
Imadaté, G. 1994. Contributions towaqrds
a Revision of the Proturan Fauna of Japan
(IX) Collecting Data of Acetentomid and Sinentomid
Species in the Japanese Islands. Bull. gen.
Educ. Tokyo med. dent. Univ., (24): 45-70.
| top| japanese protura
| my note | miscellany
| other animals |