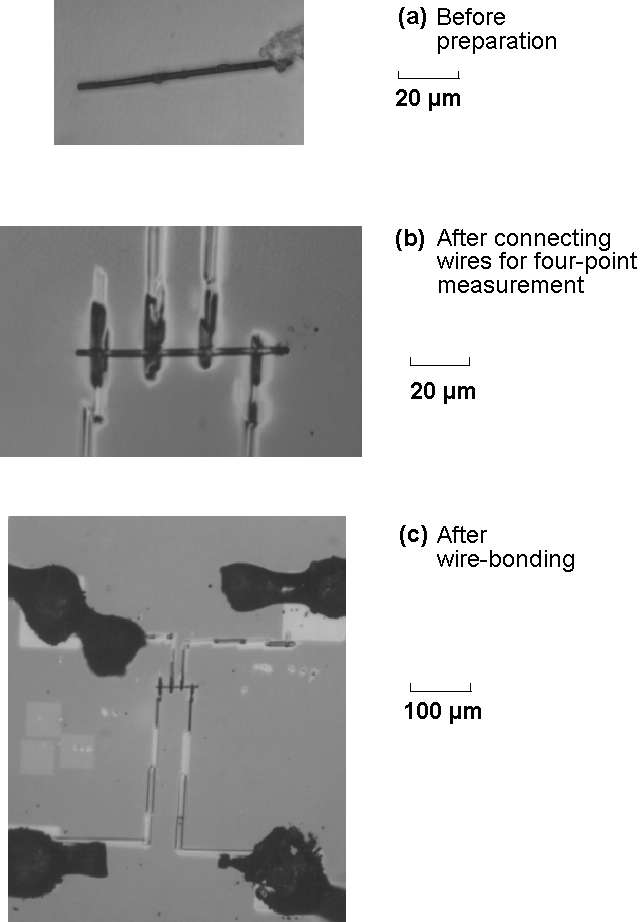
5−7.微小試料に対する電極形成
微小な試料に対する電極形成も集束イオンビーム直接蒸着法に期待される代表的な応用方法である。微小な試料の電気特性を計測するには、探針あるいはそれに代わるものを試料に当てなければならない。試料が数mm程度の大きさでありかつ探針を直接当てられる程度の剛性を持つものであるなら、たとえばプローバ(prober)を用いてそのままで探針を当て計測することが可能である。脆弱な材料で探針を直接当てられない場合には、金ペーストあるいは銀ペーストを用いて細い金属線を試料上に接着し、計測をおこなう手法が用いられる。特別な治具を用いて長さが0.2mmの試料に4探針の電極を接着したという報告はあるが14)、通常はこの手法は長さが1mm程度の試料測定にしか用いることはできない。試料がもっと小さい場合、リソグラフィーの手法により4探針の電極を付けることは可能である。たとえば絶縁物基板上に試料をおき、金属を試料の厚みと同程度以上の厚みで蒸着する。次にレジストを塗布し電子ビームで望みのパターン形状を露光する。このマスクを用いてエッチングすることにより4探針の電極および探針を当てるための電極を試料上に作製することができる。しかし、試料自体がエッチングの工程にさらされるために、エッチングの工程により試料が損傷を受けないという前提が存在する。現実には、そのような前提を満足するような試料、電極金属、エッチング方法の組み合わせはむしろまれである。
集束イオンビーム直接蒸着法により、長さが数μm以上の脆弱な試料に対する4探針の電極作製が可能となる。条件としては数10eVのエネルギーによる損傷(1〜数原子層の界面混合層が形成されるものと予想される)が電気特性の測定に決定的な影響を与えないということがある。この手法が有効であることが確立できれば、電気的な特性の測定のためにいかにして測定可能な大きさの試料を作製するかに腐心している新材料分野の研究において有用な手段となるものと予想される。その有効性を確立するために、有機物の結晶に対する電極作製を試みた。未だ損傷の影響が電気特性の妨げにはならないという結論には至っていないが、電極の形成が可能であることは確認できている。
有機物の結晶として、電荷移動錯体と呼ばれる範疇に属する導電性の結晶を用いた。電荷移動錯体の代表的なものの中に、DCQNI(Dicyanoquinonediimines)塩がある。(DMe−DCQNI)2Cuが低温まで安定な金属状態を保つことが発見15)されて以来、導電性有機結晶研究の大きなテーマとして、その金属に近い特性、半導体に近い特性あるいは絶縁物に近い特性が調べられている。試料として用いた(DI−DCQNI)2LiはそのようなDCQNI塩の1種であり、その電気的な特性は現在も明らかにはなっていない。図5−23に加工の経過を示す。(a)は電極加工をおこなう前の(DI−DCQNI)2Li試料(半径〜2μm、長さ72μmの六角柱状)を示す。54eVのAu+ビームによる4探針の電極加工(電極の厚さは試料の直径と同程度にする)後、Au+ビームにより電極を延ばしていく。この状態が(b)に示されている。引き続き、ボンディング用のパッド状電極を同じくAu+ビームにより作製し、IC用のパッケージに基板を接着した後、ワイヤボンディングによりパッド状電極とICパッケージの端子間を接続する。この状態の試料の様子は(c)に示されている。このようにして他の手段では測定が不可能であった試料の電気特性の測定をICパッケージの端子よりおこなうことが可能となる。この試料により、室温から冷却した場合に220K付近で急激に抵抗値が増大する結果が得られている。この結果が真の結晶の特性を示すものか何らかの熱的な損傷を示すものなのかは現在のところまだ明らかではない。
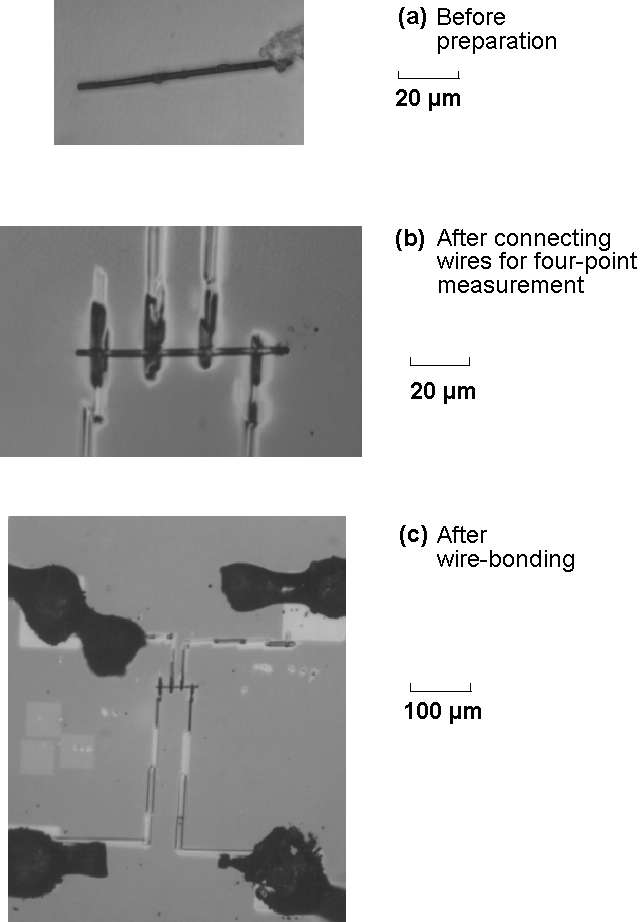
図5−23.有機導電体結晶に対する電極作製例
このような試料に電極加工をおこなう上で制限になるのは、試料の大きさと形状である。試料と基板間に大きな隙間が生じるような形状であったり、段差があまりに大きいと接続が困難になる。また、試料が大きくなると減速電界に影響をおよぼし、イオンビームが段差部分から基板側に偏向されるために段差部分の接続が困難になる。経験的にいえば、細い柱状(直径数μm以下)の試料はこの手法に適している。この手法が試料の電気的な特性を損なわないことが証明されれば、導電性の新材料研究用の強力な手法として実用化されるものと思われる。
5−8.結言
集束イオンビーム直接蒸着法の特長を生かした応用に関して、絶縁物上、曲面上への蒸着、回路修正への応用、弾性表面波素子への応用、SQUIDへの応用、磁気多層膜への応用および微小試料に対する電極形成を試みた。その結果、絶縁物上への蒸着は、有限な抵抗値で接地された金属パターンから蒸着を始め、電荷の逃げ道を自身で作製しながら絶縁物上にパターンを延長する手法を確立した。曲面上への蒸着に関しては、ビーム位置が補正可能な範囲であれば、可能であることを確認した。回路修正への応用では、保護膜に覆われているICの配線パターン間の接続(修正)をおこない、集束イオンビーム直接蒸着法を用いることにより低抵抗で結線可能であることを確認した。弾性表面波素子への応用では、絶縁物上への蒸着手法をもちいて圧電体上に伝送型フィルターを作製し、複数の金属により電極の作製が可能であり、その基本的な特性に関してリソグラフィーの工程を用いて作製されたフィルターと比較して遜色のないものであることを確認した。SQUIDへの応用では、準平面型ジョセフソン接合のマイクロブリッジ部分を集束イオンビーム直接蒸着法により作製し、DC−SQUID磁力計を構成してそれが遜色のない性能を持つことを確認した。磁気多層膜への応用においては、合金イオン源と質量分離器による金属多層膜作製の手法を確立し、GMR効果の発現を確認した。同時に、膜厚、平坦度等の制御において原子層程度の精度が可能であることが明らかになった。微小試料に対する電極形成においては、他の方法では電極の形成が不可能であるような微小で脆弱な試料に対して電極の形成が可能であることを明らかにした。
これらの結果は、真に実用的な段階にまで達しているものではないが、集束イオンビーム直接蒸着法の特長を生かす上で、その前提として基本的な問題がないことをそれぞれの応用例に対して示すと同時に、今後の応用研究に展望をもたらすものである。
第5章の参考文献
1) 長町信治、上田雅弘、山蔭康弘、丸野浩昌、浅利正敏:”集束イオンビーム直接蒸着法とその応用”、島津評論 51 (1994) 237.
2) J.Ishikawa and S.Nagamachi : "Bio-medical applicability of focused ion beam direct deposition", Proc. of BEAMS93 (1993) 219.
3) K.Nikawa : "Application of focused ion beam technique to falure analysis of very large scale integrations: A review", J.Vac.Sci.Technol. B9 (1991) 2566.
4) M.G.Holland and L.T.Claiborne : "Practical surface acoustic wave devices", Proc. of IEEE 62 (1974) 582.
5) M.Ueda, S.Nagamachi, T.Hata, K.Totani and J.Ishikawa : "Fabrication of surface acoustic wave device by focused ion beam direct deposition", Proc. of BEAMS96 (1996) 169.
6) K.K.Likharev : "Superconducting weak links", Rev.Mod.Phys. 51 (1979) 101.
7) H.Ohta : "A new Josephson Junction with a very short barrier length and a very low capacitance", IEEE Trans.Electron Devices ED-27 (1980) 2027.
8) D.Drung : "DC SQUID system overview", Supercond.Sci.Technol. 4 (1991) 377.
9) M.N.Baibich, J.M.Broto, A.Fert, F.Nguyen Van Dau, F.Petroff, P.Eitenne, G.Creuzet, A.Friederich and J.Chazelas : "Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices", Phys.Rev.Lett. 61 (1988) 2472.
10) S.S.P.Parkin, N.More and K.P.Roche : "Oscillations in exchange coupling and magnetoresistance in metallic superlattice structures: Co/Ru, Co/Cr and Fe/Cr", Phys.Rev.Lett. 64 (1990) 2304.
11) S.S.P.Parkin, Z.G.Li and D.J.Smith : "Giant magnetoresistance in antiferromagnetic Co/Cu multilayers", Appl.Phys.Lett. 58 (1991) 2710.
12) S.Nagamachi, M.Ueda, H.Sakakima, M.Satomi and J.Ishikawa : "Giant magnetoresistance in Co/Cu multilayers fabricated by focused ion-beam direct deposition", J.Appl.Phys. 80 (1996) 4217.
13) H.Sakakima, M.Satomi, Y.Irie and Y.Kawawake : "Magnetoresistance in metallic multilayers", Trans.Mat.Res.Soc.Jpn. 15B (1994) 1083.
14) S.Matsuzaki : "A new method to attach electrical leads on a single crystal of a submillimeter size", Rev.Sci.Instrum. 65 (1994) 221.
15) A.Aumuller, P.E.G.Klebe, S.Hunig, J.U. von Schutz and H.P.Werner : "A radical anion salt of 2,5-dimethyl-N,N'-dicyanoquinonediimine with extremely high electrical conductivity", Angew.Chem.Int.Ed.Engl. 25 (1986) 740.