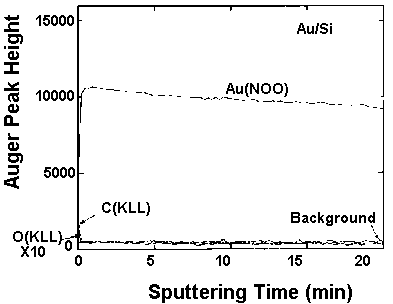
4−3.蒸着膜の純度
成膜した薄膜の純度に関しては、第1章において述べたように、イオンビーム蒸着法に対して集束イオンビーム直接蒸着法が持つ非常に際立った特長が期待される点である。Si基板上に大きさ100μm×100μm、厚さ0.4μmのパターンを54eVのAu+ビームを用いて作製し、オージェ電子分光法(Auger Electron Spectroscopy)および2次イオン質量分析法により組成の分析をおこなった。
図4−6は、Ar+ビームによりスパッタエッチングをおこないながら測定したオージェ電子分光の測定結果である3)。横軸のスパッタリング時間は、深さに対応する。縦軸は、Au、C、Oの各元素に対応するオージェ電子のピーク高さを示す。残留ガスに起因するものと予想されるC、Oの混入は最表面への付着とみられる有意値以外はバックグラウンド程度であった。しかし、オージェ電子分光法における検出限界は一般に0.1%〜1%程度であるため、オージェ電子分光法よりも検出限界が数桁小さい2次イオン質量分析法による測定をおこなった。
図4−7は、オージェ電子分光法に用いたものと同じ条件で作製した試料を2次イオン質量分析法で分析した結果を示す3)。分析に用いた1次イオンはCs+、検出した2次イオンはAu−、O−、C−、およびSi−である。C、Oは最表面、およびSi基板とAu層の界面でAuより2桁程度少ない量が計測されているが、Au層の中では最表面からのテイル以上の有意な量は検出されていない。定量的な分析をするためには、標準試料を用いて2次イオンの生成効率を補正する必要があるが、標準試料は用いていない。そのため、この結果より定量的な議論をすることは出来ないが、もしAu−、O−、C−の生成確率が同じであると仮定すると、O、Cともおよそ100ppm以下となる。
第1章において述べたように、残留ガスからの不純物の取り込みは、真空度、電流密度、残留ガスおよびイオンビームの付着確率が与えられれば、式(1−6)により評価することができる。残留ガス圧を試料作製時の真空度1×10−6Pa、電流密度を200A/m2(20mA/cm2)、残留ガスおよびイオンビームの付着確率を1とおくとき、求められる不純物濃度は3×10−5(30ppm)であり、オージェ電子分光法および2次イオン質量分析法により測定した結果と矛盾しない。
このように、集束イオンビーム直接蒸着法の最大の特長である高純度成膜が予想通りに実現することを証明した。
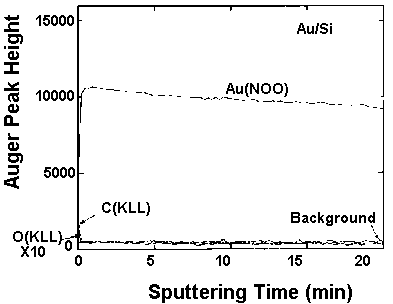
図4−6.オージェ電子分光法により測定した金試料の組成(深さ方向の分布)
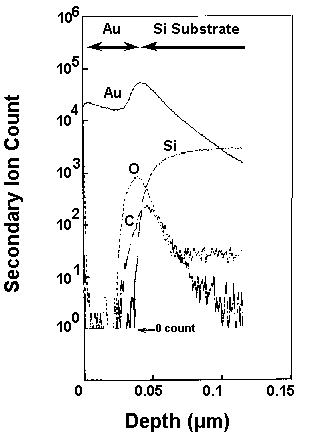
図4−7.2次イオン質量分析法により測定した金試料の組成(深さ方向の分布)