第4章 集束イオンビーム直接蒸着法で成膜した薄膜の評価
4−1.緒言
第2章、第3章において低エネルギー集束イオンビームの発生、直接蒸着法に用いるイオンの発生について述べてきた。本章では、そのようにして発生させたイオンビームを用いて薄膜を成膜し、イオンビーム蒸着(集束イオンビーム直接蒸着)に関する基礎的な物理量の取得とそれらの薄膜の基本的な特性の測定に関して述べる。
イオンビーム蒸着に関して、報告されている基礎的な物理量の測定結果はあまりにも少ない。たとえば、入射したイオンの数に対する成膜した原子数の比(これをイオンビーム蒸着における付着確率と定義した)という、最も基礎的な物理量さえ、エネルギーの関数として実験的に求められている報告例はほとんどない状態である。したがって、基礎的な物理量の取得が、まず最初の課題であった。
集束イオンビーム直接蒸着法の特長の一つである微細なビーム径は、同時に作製が可能な試料の大きさに制限があることを示している。例えば、50eVのAu+ビームの場合、ビーム電流密度が低下しない最大電流は10nAであることは、第2章において述べた。この電流値は入射したイオンがすべて蒸着すると仮定すると、1秒間あたりおよそ1μm3の蒸着速度に対応する。100μm角で厚さが0.1μmのパターンを作製するために必要な時間は17分程度であるが、10mm角で厚さが0.1μmのパターンを作製しようとすると116日という非現実的な時間が必要になる。したがって、評価するために必要な試料の大きさがmm単位である評価手段は使用できない。しかし、100μm程度の大きさで評価できるものであれば、同一基板上で条件を変えながら複数の評価用試料を連続して作製することが出来る。これは、基板毎に条件を変えながらおこなう評価と比較して実験条件の制御性、再現性および信頼性の点で優れている。つまり、基板の表面状態とか基板交換時における装置状態の変化に起因するような再現性上の問題点がないために、信頼性の高い測定結果を得ることが出来る。また、評価に要する手数、時間の点でもはるかに効率の良いものとなる。
本章では、直接蒸着法の付着確率のほか、直接蒸着法の最大の特長として期待される直接蒸着膜の純度、高純度の結果として期待されるバルク並の電気的特性、超伝導特性、およびイオンビーム蒸着において特異的な性質が期待される構造に関する評価結果について述べる。
4−2.付着確率
付着確率、すなわち入射したイオンビームの数に対する成膜した薄膜を構成する原子数の比は、前節で述べたようにイオンビーム蒸着においてイオンの電荷量から堆積された原子数を求めるために必要な、最も基本的な物理量である。蒸着膜の評価に先立ち、付着確率の測定をおこなった。
付着確率をSibdとおくとき、次のようにあらわされる。
![]() (4−1)
(4−1)
ここで、Nionは基板上に入射したイオン数、Natomは基板上に成膜した原子数である。さらにこれらは、Vfilmを成膜した薄膜の体積[m3]、Dfilmを薄膜の原子密度[atoms/m3]、Iをイオン電流値[A]、tをイオン照射時間[s]、qをイオンの電荷[C]とおくとき、次のようにあらわされる。
![]() (4−2)
(4−2)
![]() (4−3)
(4−3)
付着確率の測定のために、大きさがおよそ30μm角、厚みが0.1〜1μmのパッド状の試料を蒸着エネルギーを変えて作製した。体積は、面積を光学顕微鏡像より読みとり、厚みを段差計(Dektak)により測定し、両者を掛け合わせて求めた。蒸着した薄膜の原子密度にはバルク金属の値を代入した。後に述べるように、この仮定は厳密な物理量としての付着確率を求めるためには精度を落とすものであるが、照射した電荷量より成膜した体積を求めるためには不都合が生じない、むしろ実用的な目的に添うものである。図4−1に、実際に作製した試料の光学顕微鏡写真を示す。このように蒸着エネルギーのみを変えた複数の試料を連続して同じ基板上に作製することが出来る。
このようにして測定したAu+、Cu+の付着確率測定結果を図4−2に、Al+、Nb2+の測定結果を図4−3に示す1〜3)。蒸着エネルギーに対して付着確率はほぼ単調に減少している。付着確率が0になるエネルギーを、イオンビーム蒸着における臨界エネルギーと呼ぶが、Au+では〜210eV、Cu+については〜230eV、Al+については〜800eV、Nb2+については〜1300eVという結果が得られた。他のイオン種については、測定点が少ないため、粗い傾向しかわかっていないが、Si+はAl+に近く、Co2+はNb2+とAl+の間であった。
50〜1000eVのエネルギー領域においては、蒸着とスパッタリングの競合により付着確率が決定されるものと考えられる。したがって、自己スパッタリング収率(入射した1個のイオンに対して同種原子がスパッタリングされる原子数)をYSSとおくとき、付着確率(Sibd)は次のようにあらわされると考えられる。
![]() (4−4)
(4−4)
すなわち、臨界エネルギーは、YSSが1となるエネルギーに対応する。スパッタリング収率として報告されている実測値4、5)によれば、臨界エネルギーは、Au+では150〜170eV、Cu+については180〜200eV、Al+については550〜800eVであり、著者の測定値に近い結果となっている。Nbについては10keV以上の実測値に対する外挿値4)として2.2keVしかないため、比較は意味がなく、むしろ得られた結果が初めての実測値であると言うべきであろう。スパッタリング収率の測定には通常ターゲットの重量変化を計測するため2)その精度には限界があり、また低エネルギー領域における残留ガスの取り込みには考慮を払っていないため、低エネルギー領域においてより確度の高いと思われる計測結果が得られた。なお、これらの測定にはSi基板を用いている。厳密にはこれらの測定値はSi上に第1層が付着する確率と第2層以後が付着する確率(これが求める付着確率である)が分離されず重畳されたものである。しかし、試料は充分な厚さをもつために第1層の影響は薄められているものと思われる。
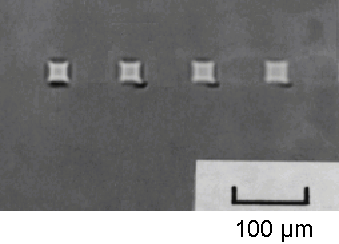
図4−1.付着確率測定のために作製した試料例
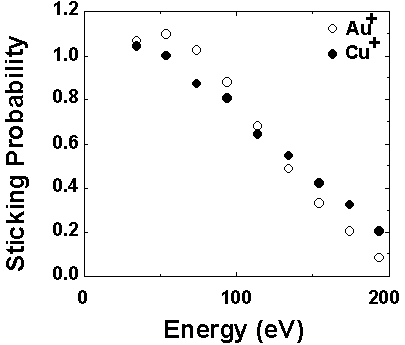
図4−2.金および銅の付着確率測定結果
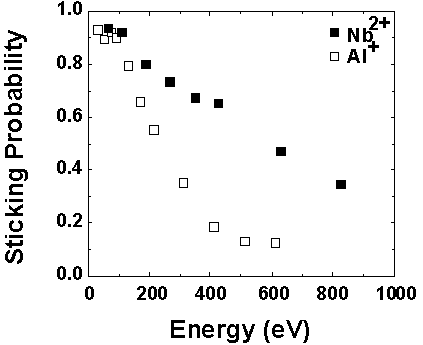
図4−3.アルミニウムおよびニオブの付着確率測定結果
図4−2において見られるように、低エネルギー側で付着確率が1を超えている結果が得られている。たとえば54eVのAu+ビームの付着確率は最も大きく、1.09である。その原因は、付着確率を求める過程において、バルク金属の原子密度を仮定したことにあるものと考えられる。その証明のために、54eVのAu+ビームを用いて成膜した試料の原子密度の測定をおこなった。原子密度は、単位面積当たりの原子数と試料の厚さが正確にわかれば求めることができる。そこで、単位面積当たりの原子数(重さ)をラザフォード後方散乱( Rutherford Back Scattering )法により、厚さを透過電子顕微鏡像により測定した。ラザフォード後方散乱法において得られた測定結果を図4−4に示す。横軸は後方散乱イオンのエネルギーに対応し、縦軸は散乱イオンの計数値を示す。用いたイオン種はHe+でエネルギーは2MeV、測定した散乱角は170゜である。図4−4で計測されているAuの測定結果を、単位面積あたりの原子数を仮定した弾性散乱に基づく理論計算で合わし、求められた単位面積あたりの重さは、5.0×10−4g/cm2であった。同じ試料により測定した透過電子顕微鏡像を図4−5に示す。これにより求められたAu膜の厚さは、280±10nmであった。この厚さで単位面積あたりの重さを割ると、17.9±0.6g/cm3が得られた。この値はバルクAuの値である19.28よりも4〜11%小さい。この補正を54eVのAu+ビームの付着確率におこなうと、1.01±0.04となり、誤差の範囲で1になる。
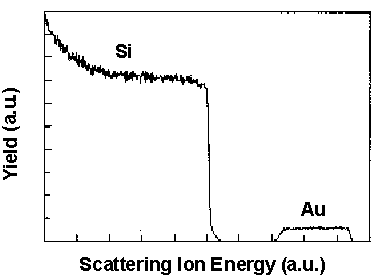
図4−4.ラザフォード後方散乱法において得られたAu試料のスペクトル
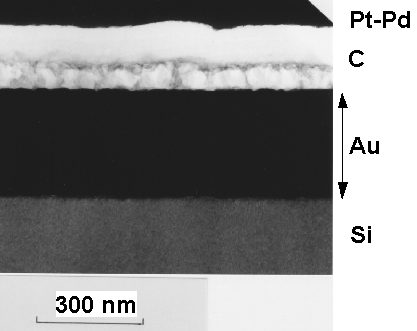
図4−5.Au試料の透過電子顕微鏡像