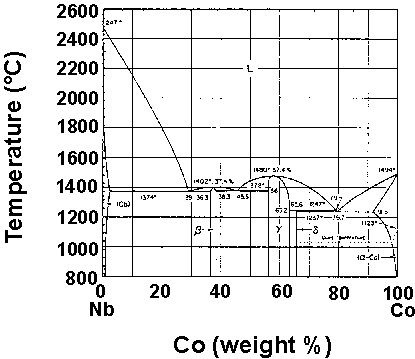
3−5.超伝導体用液体金属イオン源
超伝導体用液体金属イオン源として、Nb合金イオン源を開発した。Nbは単体では融点は2471℃であるのでイオン源の運転温度からはかけ離れており、そのままではイオン源に利用できない。Nb−Au合金の状態図は図3−3に示すように液相線固相線ともAuの融点以下にはならない。したがって、Au単体よりも高温で運転する必要があり、Nbの含有量が少ない領域であっても実用的なイオン源を構成することは困難である。Nb−Au合金にもう1元素(Co、Ni、Cu)を混合して、実用的な温度範囲で運転できる3元合金イオン源を試みた29〜31)。
CoはNbとの間で図3−19に示すように二つの中間相をはさんでそれぞれの領域で共晶点はあまり低くはないが共晶型を示す。また、Auとの間においても共晶点996℃の共晶型を示す。したがってNb−Au−Co合金は、運転可能な温度においてNb含有量の多いイオン源を構成可能な候補の一つとなり得る。NiもCoに近い性質を持ち、Nb−Ni合金は図3−20に示すように中間相をはさんで共晶型、包晶型を示す。Au−Ni合金は液相線が950℃付近で極小値を示す全率固溶型であるので、Nb−Au−Ni合金はNb−Au−Co合金よりも若干液相面の温度が下げられる可能性がある。CuはNbと図3−21に示すように明らかでない部分を含むが包晶型を示しており、Cuの多い領域において固相線はCuの融点に近い値(1060℃)をとる。Au−Cu合金は図3−4に示すように液相面が889℃の極小値をもつ全率固溶型であるので、Nb−Au−Cu合金は最も低温で運転できる可能性がある。しかし、Au、CuともNbとは共晶型にならないために、運転温度によりNbの含有量が大きく左右されることが予想される。
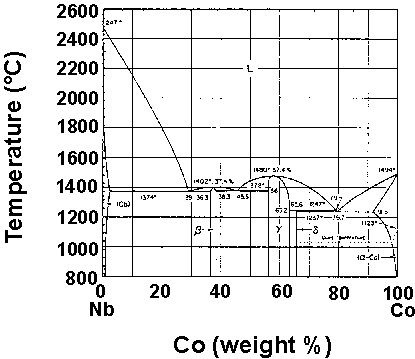
図3−19.Nb−Co合金の状態図32)(横軸は重量%を示す)
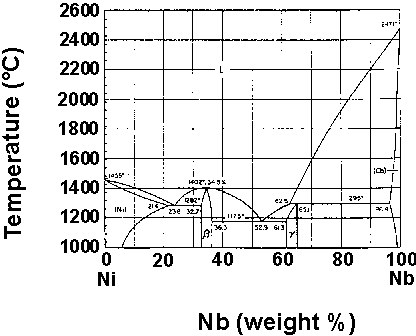
図3−20.Nb−Ni合金の状態図32)(横軸は重量%を示す)
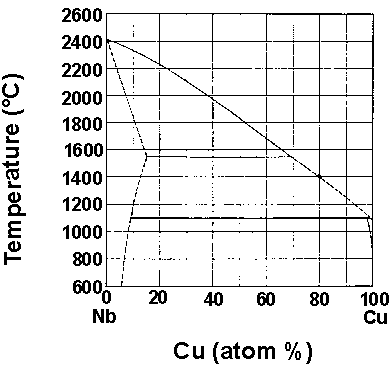
図3−21.Nb−Cu合金の状態図26)
Nb20−Au50−Co30合金を原料として使用したNb−Au−Coイオン源より引き出したビームの質量スペクトルの例を、図3−22に示す30)。引き出しビーム電流値中のNb2+ビーム電流値の割合は20%におよび、量的には優れたNbイオン源であるが、運転温度は1230℃にも達する。このイオン源の問題点は、運転時間とともに液体金属がグラファイトの発熱体に付着し、運転条件が変動するために安定なビームの取り出しがごく短時間しかおこなえず、また寿命そのものも20〜50時間程度であることである。そのため、現状では実用に耐えるには至っていない。
Nb−Au−Ni合金イオン源も同様な傾向を示す。Nb20−Au40−Ni40合金を原料として使用したNb−Au−Niイオン源の引き出しビームの質量スペクトル例を図3−23に示す31)。Nb2+ビーム電流値の割合は14%程度あり量的には問題ない。しかし、運転温度は1200℃程度であり、発熱体に対する付着の問題とそれにともなう不安定性、寿命の制限はNb−Au−Co合金イオン源と全く同様であった。これらのイオン源は、Nbイオン源としてNbイオンの発生量においては優れていたが安定性、寿命において実用領域に達しなかったため、採用に至らなかった。しかし、次節において述べる磁性体用イオン源の開発に生かされた。
Nbイオン源として実用領域に達したのはNb−Au−Cu合金イオン源である。原料としてNb10−Au50−Cu40合金を使用したイオン源の引き出しビームの質量スペクトルを図3−24に示す29、30)。運転温度1040℃においてNb2+ビーム電流値は引き出しビーム電流値のおよそ5%を占めている。イオン源の運転が可能な温度範囲は、900〜1100℃であるが、Nb2+の占める割合は図3−25(図3−24で用いたイオン源とは別のイオン源により測定した結果である)に示すように運転温度により1桁以上変化する。これは浸みだしてきた金属の局所的な組成が運転温度により変化することを示している。運転温度がNb−Au−Co合金イオン源よりも低いために、発熱体に対する金属の付着は顕著でなく、またビームの引き出しも安定であり、比較的低温(〜1000℃)で運転することにより200〜300時間の寿命が得られている。しかし、浸みだし時の温度(1200〜1300℃)と比較して運転温度が低いために、引き出しビーム中にしめるNb2+ビームの割合は長期的には減少する傾向がある。
第4章以降に述べるNb2+ビームを用いた実験には、Nb−Au−Cu合金イオン源を使用した。
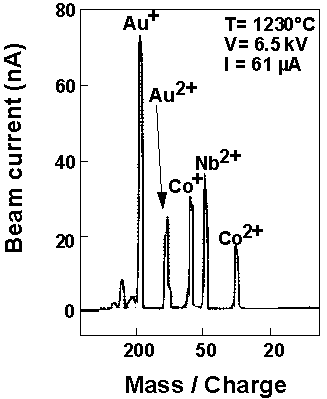
図3−22.Nb−Au−Co合金イオン源の質量スペクトル例
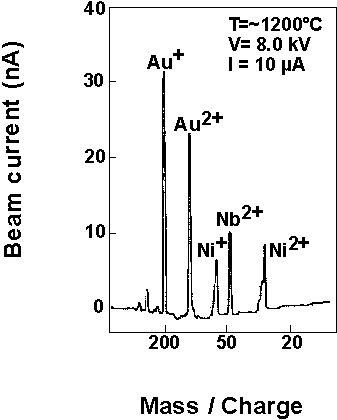
図3−23.Nb−Au−Ni合金イオン源の質量スペクトル例
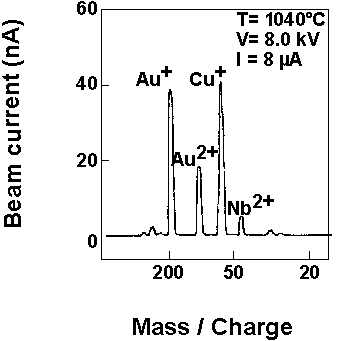
図3−24.Nb−Au−Cu合金イオン源の質量スペクトル例
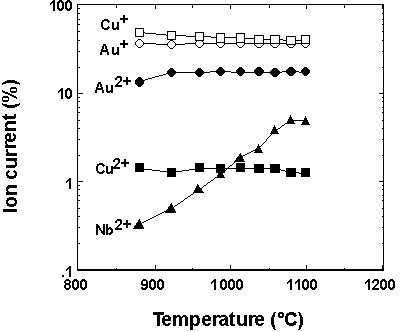
図3−25.Nb−Au−Cu合金イオン源のイオン組成と運転温度の関係