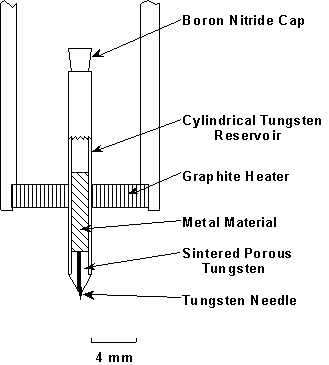
3−3.イオン源の構造(含浸電極型液体金属イオン源)
液体金属イオン源には、構造の異なるいくつかの形式がある。液体金属イオン源の黎明期にはキャピラリー型と呼ばれる液体金属溜に細い中空の針が取り付けられた形式のものが用いられた3〜5)。この形式は、テイラーコーンが形成されイオンが発生する部分が不安定で位置が定まりにくく、また小電流運転が困難であるため、集束イオンビーム用のイオン源としてはあまり用いられていない。液体金属イオン源の開発が盛んになると、ニードル型と呼ばれる形式が主流になった7〜12)。ニードル型は、タングステン、モリブデン、タンタル等の電熱線をループ状に折り曲げ、その中点にタングステン等の先端を鋭く尖らせた針(ニードル)を溶接したものである。この構造体を液体金属に一度浸して引き上げ、イオン源を作製する。キャピラリー型と比較して、イオン発生位置がニードル先端形状により決まる狭い範囲に限定することが可能であり、また小電流運転に適しているために、実効的な線源径が小さくエネルギー幅の小さな微小ビームの形成に適したビームを得ることができる。しかし、液体金属溜がないために装填できる液体金属の量は限られ、また蒸発に対しても無防備であるため、イオン源の寿命は限られており、イオン源開発の時期が過ぎ、実用に供せられるようになると、次に述べるキャピラリーニードル型が主流になるようになった16〜19)。キャピラリーニードル型は、液体金属溜を持つキャピラリーにニードルが取り付けられたものであり、ニードル型の長所を生かして、かつ液体金属溜により長寿命のイオン源を実現するものである。現在商用で販売されている液体金属イオン源はほとんどがこの形式である。
著者が採用したイオン源は、ニードル付きの含浸電極型液体金属イオン源と呼ばれる形式である28)。図3−5にこのイオン源の構造を示す。タングステンのパイプの先端にタングステンの微粒子を焼結し、タングステンのニードルを焼結部分に埋め込んである。キャピラリーニードル型と比較して、イオン発生位置が安定であり小電流運転に適しているニードル型の長所は同じであるが、ニードルに供給する液体金属の流量の制御性において優れている。この特性は、微小電流運転によりさらに実効的線源径、エネルギー幅の小さなビームを得ようとするときに有利に働くものと期待できる。また、蒸気圧の高い元素の利用を可能とすると同時に、蒸発量そのものを抑えることができる。
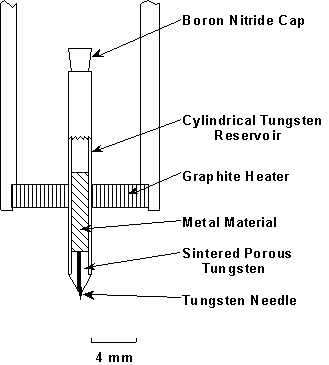
図3−5.含浸電極型液体金属イオン源の構造
次に、含浸電極型液体金属イオン源の作製法について述べる。材料のタングステンパイプは外形〜2mm、内径〜1.5mm、長さ18mmである。銅の細い棒(外形はタングステンパイプの内径に相当する)にCVD装置でタングステンを厚く成膜し、銅部分を化学的なエッチングで取り除き成型したものである。粒径が10μmと100μmのタングステン粉末をニトロセルロースを20%含むアセトン溶液で充分練り、タングステンパイプの一方に盛る。外径が250μmのタングステン針を盛り上げた粉末に刺し、図3−5に示すような形状を形成する。乾燥させた後、1300℃の水素炉に1〜2分入れ、軽く焼結する。次に、0.1〜1NのNaOH水溶液に先端の針(ニードル)を入れ、水溶液中の銅電極とイオン源構造体間にAC2〜10V程度を印加し、電解エッチングによりニードル先端を0.1μm以下の曲率半径になるように加工した。このようにして作製したイオン源構造体の先端部分の写真を図3−6に示す。
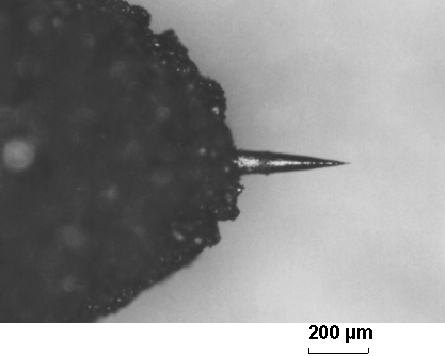
図3−6.イオン源構造体の先端部分
イオン源を作製するには、上記イオン源構造体に原料とすべき金属を充填し、真空中で加熱し、焼結体部分を浸みださせ、ニードルの先端まで供給しなくてはならない。このような浸みだしの工程と、電界をかけてビームを引き出し、イオン源の評価をおこなうために図3−7に示す液体金属イオン源用の真空装置を使用した。イオン源には最大で15kVまでの電位を印加することが可能であり、高圧側に加熱用の電源が設置されている。引き出し電極は接地電位である。対称型静電レンズとE×B形式の質量分離器を備え、質量スペクトルをとることができる。真空度は2〜4×10−5Pa程度である。
イオン源構造体に充填可能な金属の量は100mg程度かそれ以下である。合金を充填する場合と、合金の原料を充填しイオン源中で合金化する場合がある。原料を充填する場合には必ずしもすべての原料が均一に溶けあった状態で浸みだしが始まるわけではないことに注意する必要がある。合金を充填する場合においても、合金がすべて溶けあった状態で浸みだしが始まることはむしろまれである。したがってイオン化部分(ニードル先端部)の合金組成と充填した合金あるいは原料金属組成は区別して考える必要がある。このことを充分考慮することも合金開発において必要である。このような理由から、本論文においてはイオン源の合金組成は明記せず、充填した合金の組成および合金原料として充填した金属組成のみを記述している。
原料充填後、窒化硼素製のふたをした後、積層グラファイト製の発熱体でイオン源を挟み、支持電極に取り付ける。このイオン源支持体の構造を図3−8に示す29)。無充填のイオン源構造体を支持電極に取り付け、入力した電力と放射温度計により測定したイオン源表面温度の関係を図3−9に示す。以下に述べるイオン源運転温度は、すべてこの関係により入力電力より換算したものを採用している。
支持電極に取り付けたイオン源は、上述したイオン源調整評価用真空装置に取り付け、真空に引く。その後、発熱体に徐々に電力を供給し、イオン源構造体を加熱する。ある温度に達したところで原料金属が焼結体部分を浸みだし、ニードル部分に達する。原料金属が浸みだして来たかどうかは、放射温度計で焼結体部分を連続的に観測していると、その温度変化として知ることができる。浸みだしが確認できたら、引き出し電極との間に5〜10kVの電位を印加し、ビームの引き出しを試みる。ビームが出始めたら温度、印加電位とも少し下げ、安定に動作する条件を探る。また、質量スペクトルを計測して引き出しビーム中のイオンの組成を測定する。性質のわかっているイオン源の場合には若干の安定性試験の後、保管して使用する。イオン源自体の開発の場合には、安定性、寿命の測定をおこなう。
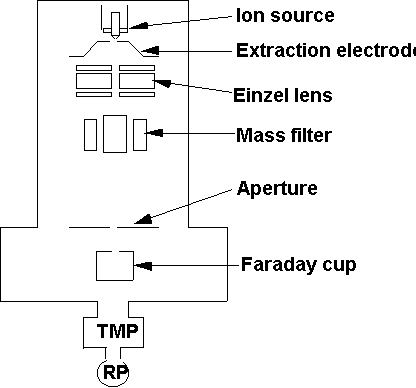
図3−7.液体金属イオン源調整評価用真空装置の概念図
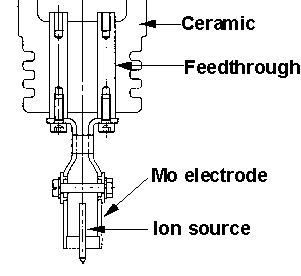
図3−8.液体金属イオン源支持体の構造
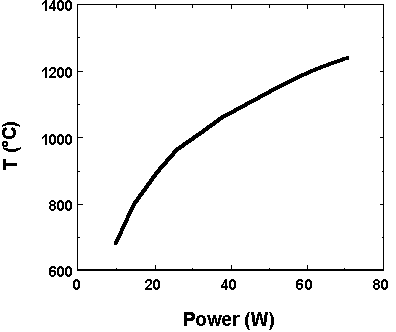
図3−9.イオン源に供給する電力とイオン源温度の関係