
2−5.低エネルギービームの特性
2−5−1.ビーム径、ビーム電流密度
以上述べてきた低エネルギー集束イオンビーム装置を用いて、低エネルギーの集束イオンビームを基板上に走査し、蒸着した金属パターンの形状観察により減速ビーム径の評価をおこなった5〜7)。金属パターンの形状観察には光学顕微鏡、走査電子顕微鏡および原子間力顕微鏡を用いた。計測するビーム径には、真のビーム径のほか、鏡筒とステージの機械的な振動、偏向電位のリップル、アスペクト比の大きなパターンの成膜の場合にマイグレーションおよび成膜パターン自身が電界に与える影響によるパターン幅のひろがりなどが含まれる。
Au+ビームの場合、レンズ系の光軸調整を充分おこなった後、30〜200eVのエネルギーにおいて得られるビーム径は、ビーム電流40pAから10nAに対して半値幅で0.4〜7μmであった。その間のビーム電流密度はほぼ一定で半値幅の範囲において300A/m2(30mA/cm2)である。この電流密度は、入射したイオンがすべて成膜すると仮定すると、〜30nm/sの蒸着速度に対応する。ビーム電流値をそれ以上小さくしても、最小ビーム径は0.35μm程度が限度でそれ以下にはならず、ビーム電流密度が急速に低下する。また、10nAよりもビーム電流値を増やしてもビーム電流密度は急速に低下する。この傾向は、図2−9で示した電流密度とビーム電流の関係と定性的に良く一致している。したがって、ビーム電流密度が一定値をとる40pAから10nAにおいてはビーム径は色収差によって決まっており、10nA以上では球面収差の項、40pA以下では線源径と倍率の項により決まっているものと思われる。しかし、定量的には図2−9におけるエネルギー幅30eVの計算結果と比べて1/4程度である。最小ビーム径も計算値と比べ2.5倍程度である。これは、計算においておこなった条件の設定および仮定のうちAu+ビームに関して不適当であったものがあることを示しているが、詳細は後に議論する。
図2−12は、ビーム電流値が40pA、エネルギーが54eVのAu+ビームを用いて100μm/sの走査速度で600回繰り返しSi基板上に走査して作製した、集束イオンビーム直接蒸着法の頭文字(FIBDD)を走査電子顕微鏡観察した像である。線幅として0.5μm程度であることがわかる。しかし、走査電子顕微鏡像は表面原子に敏感なので、線幅としては通常ビーム径を表現するときに用いられる半値幅よりも大きいものと思われる。同じくビーム電流値40pA、エネルギー32eVのAu+ビームを用いて作製したラインアンドスペースのパターンを原子間力顕微鏡で観察した例の鳥瞰図を図2−13に、同じ試料の断面図を図2−14に示す。ガウス分布に近いビーム分布を反映していると思われる断面形状を持ち、半値幅が0.4〜0.45μm程度であることがわかる。厚みは、30nm弱である。厚みを線幅に対して無視できない程度に(アスペクト比を大きく)すると、断面形状は、三角形に近いものとなる。例として、図2−15に、ビーム電流10nA、エネルギー104eVのAu+ビームを用いてSi基板上に作製した線状パターンのSEM像を示す。0.6μm程度の段差に交差して蒸着している。段差の両側数μmは20keVのAu+イオンで短時間スパッタエッチングしてあり、断面形状が観察しやすくなっている。スパッタエッチングされていない領域では、蒸着時にスパッタされた金原子の再付着とおもわれる層が線パターンの両側に拡がっている。また、ビームを走査せず、一点上で成膜すると、円錐状のパターンが得られる。例として、図2−16に、ビーム電流10nA、エネルギー32eVのAu+ビームを用いて作製した円錐状パターンの走査電子顕微鏡像を示す。
Cu+についても、同様な傾向が得られているが、数10nm以下の薄い成膜の場合、基板原子と反応してしまい、島状に再結晶するため、最小ビーム径の評価はできなかった。

図2−12.54eVのAu+ビームによる直接蒸着例(走査電子顕微鏡像)
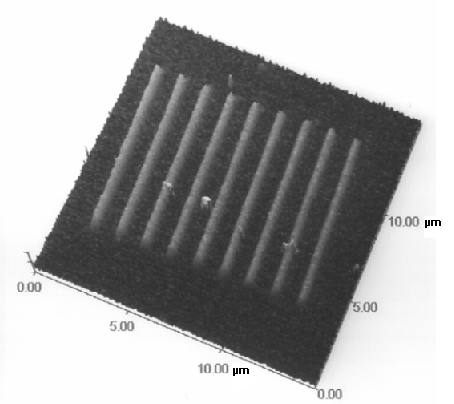
図2−13.32eVのAu+ビームによる直接蒸着例(原子間力顕微鏡像)
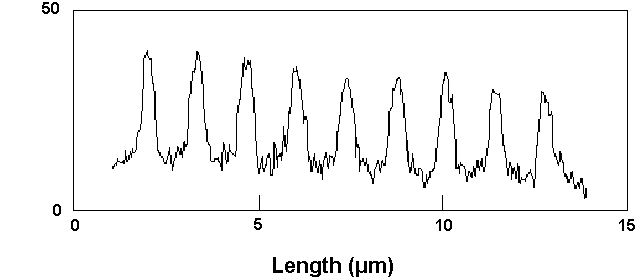
図2−14.32eVのAu+ビームによる直接蒸着例(原子間力顕微鏡断面図)
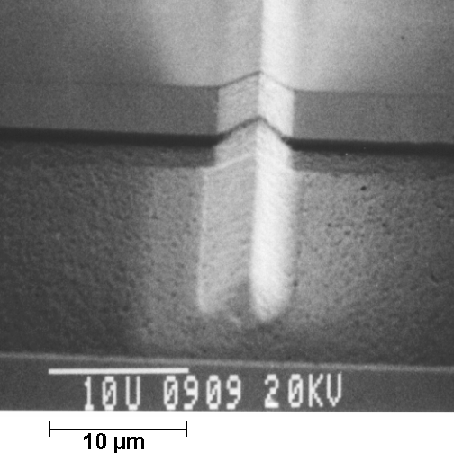
図2−15.104eVの大電流Au+ビームによる直接蒸着例(走査電子顕微鏡像)
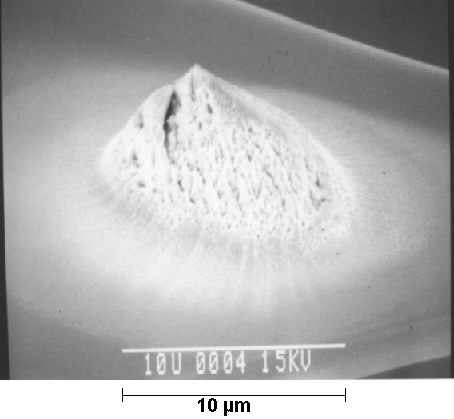
図2−16.32eVの大電流Au+ビームによるポイント蒸着例(走査電子顕微鏡像)
Au+の非減速ビーム(20keV)については、小電流において線状にスパッタエッチングした溝幅を観察した結果、その幅は〜0.2μm程度であった。ビーム径もほぼこの程度であろうと思われる。なお、同じイオン源から引き出されたCu+の非減速ビームによる溝幅(ビーム径)は〜0.14μm程度であった。
2−5−2.ビーム位置
前述したように、2重偏向電極を第2静電レンズの上流に配置することにより、レンズ電位によりビーム位置が影響されることはないが、減速場は偏向電極の走査範囲に影響を与える。すなわち、減速時には同じ偏向電位に対して偏向する距離が長くなる。たとえば減速長L=10mmのとき、実測で50eVにおける偏向距離は20keV(非減速時)の場合のおよそ1.9倍となっている。
また、減速場は第2静電レンズの外面とターゲット基板間に生じるが、これらの平行性が良くないとき、減速時と非減速時における位置ずれが生じる。たいていの場合には非減速ビームを用いた走査イオン顕微鏡による位置確認のみで、減速ビームの位置合わせをするのは無理であり、一度位置合わせのために試験的に蒸着してその位置を光学顕微鏡か走査イオン顕微鏡により確認し、その位置ずれを補正しながら蒸着する必要がある。また、試料自体が平坦でない場合にも減速電場の乱れによる位置ずれが生じる。しかし、それらも偏向位置を補正することによりパターニング可能である。逆に非平面上への蒸着も位置補正がきく範囲であるかぎり可能である。
合金イオン源の組成の範囲で、イオン種の切り替えが質量分離器のみの設定でおこなえ、それ以上の調整が不要なことは前述したが、ビーム位置に関してもイオン種を変更しても変わらない。したがって、パターン化された積層薄膜を成膜することが可能である。たとえば、後に第5章において詳細は述べるが、Co-Cu-Au-Nbイオン源から得られるCu+とCo2+ビームによりCo/Cu磁気多層膜を作製し、巨大磁気抵抗効果の発現を確認している。
2−5−3.実測結果と計算結果との比較と考察
図2−17に減速したAu+ビームの実測値と計算結果の比較を示す。定性的には、両者はよく一致している。すなわち低電流領域でビーム径一定、中間電流領域でビーム電流密度一定、大電流領域でビーム電流密度が急激に減少する減速ビームの実測結果の傾向は、計算結果とよく一致している。しかし、Au+ビームにおける測定したビーム径の絶対値は計算結果と幾分の開きがある。低電流領域における50eVビームの最小ビーム径0.35μmは計算結果の2.5倍である。また、中電流領域における電流密度もAu+ビームのエネルギー幅を30eV程度と考えても計算結果の1/4となっている。このような計算結果と実測結果の差を生じさせた原因について、議論をおこなう。
低電流領域においては、ビーム電流値、あるいはビームの半角によらずビーム径が一定値をとることから、式(2−7)に示されている最初の項、すなわち線源径と倍率により決まる項によりビーム径が決定されているものと考えられる。その他、ビーム径の観察の精度を落とす様々な項目のうち、ビーム電流値に依存しない項目、すなわち機械的な振動、偏向電位のリップルの影響、蒸着パターン自体の電界に対する影響、成膜時のイオンのマイグレーションの影響などが可能性としてあり得る。しかし、機械的な振動はエネルギー、イオン種にかかわりなくビーム径に常に一定の影響を与えるものであるが、減速ビームと非減速ビームで2倍程度のビーム径の差が生じている事実と矛盾するために、可能性としては除外することができる。蒸着パターン自体の電界に対する影響、およびマイグレーションの影響は、アスペクト比の大きなパターン(例えば図2−15)を想定しているが、アスペクト比が充分小さな領域における実測値なので、これについても可能性としては除外できる。偏向電位のリップルの影響は減速ビーム径と非減速ビーム径の比を説明できるため、可能性として充分あり得る。そこで、直接偏向電位(駆動回路の増幅器出力)を実測した結果、その影響は非減速ビームに対して0.08μm、減速ビームに対して0.16μmの影響を与え得るものであった。しかしこの影響はイオン種による差は生じないため、Au+とCu+の非減速ビーム径の差は説明できない。したがって、ビーム径にある程度の効果は与えているものと考えられるが、決定的な要因とはなっていないと思われる。したがって、測定値と計算値の差を説明できるものは、計算における設定、仮定に現実を反映していないことがあるのではないかという点にしぼられてくる。倍率は、レンズ系の幾何的な配置により決定されるものであり、不確定な結果を生じさせる可能性は小さい。その結果、最後まで残る可能性は、実効的な線源径の仮定(50nm)が妥当であるかどうかである。小電流運転におけるGaイオン源の線源径については40〜50μmという報告があるが10、13)、金を主成分としたイオン源の実効的な線源径に関する報告値はない。一般的に液体金属イオン源において、軽いイオンの方がエネルギー幅が小さいことが観測されており、その理由が引き出し直後の空間電荷効果により説明されている。それと全く同じ理由により、重いイオンの実効的な線源径が大きくなるであろうことは容易に推定できる。引き出し条件、質量とも極端な例ではあるが、金の液体金属イオン源から大電流ビーム引き出しにより、クラスターイオンを発生させた実験があり、実効的な線源径として8μmが報告されている14)。この報告は、上記の推定が充分あり得るものであることを示している。したがって、Au+イオンの場合には線源径が計算において仮定した50nmよりも大きく、計算結果と実測結果の差の主な原因となっている可能性が大きい。もし、最小ビーム径が線源径により決定されていると仮定すると、およそ0.13μm程度のとき、減速ビーム、非減速ビームの実測値をほぼ再現する計算結果が得られる。以上の議論より、Au+ビームの最小ビーム径は、線源径により決定されており、線源径は0.13μmであると推測している。
中電流領域においては、ビーム電流密度がほぼ一定値をとることから色収差によってビーム径が決定されていることは明らかである。しかし、図2−5のエネルギー幅10eVの計算値は実測値の30倍程度、エネルギー幅をたとえ30eV(Au+ビームにおける著者等の実測値である)としても、なお実測値の4倍程度であり、なお有意な差が存在する。イオン源引き出し時の角電流密度を20μA/srと仮定しているが、合金イオン源の場合、イオン種の成分比に比例して角電流密度を分配する必要が生じるものと思われる。使用したNb−Au−Cuイオン源について、Au+ビームの角電流密度を実測した結果、およそ10μA/srという結果が得られた。この値を用いて計算をおこなうと、計算結果として得られるビーム電流密度は実測値の2倍程度、すなわちビーム径に関しては実測値の1.4倍程度が再現できる。色収差の評価は、計算手法自体の信頼性がこの程度であり、むしろ良い一致が得られたのではないかと考えている。
もし、線源径に0.13μm、エネルギー幅に30eV、角電流密度に10μA/srを用いて計算をおこなうならば、実測結果として得られているAu+ビームの特性をほぼ(中電流領域においてビーム径で1.4倍程度の誤差は生じるが)再現することができる。図2−18は、このようにして計算したエネルギー50eVのときのビーム電流とビーム径の関係および線源径と倍率、色収差、および球面収差の寄与を示す。図2−19は、エネルギー50eVにおけるビーム電流値とビーム電流密度の関係を示す。
エネルギー幅30eVと角電流密度10μA/srに関しては、実測に基づいた値を代入しているので疑問の余地はなく、線源径のみ0.13μmであると仮定すれば実測値が再現できるという結果を得たわけであるが、これはむしろ、このような評価手法により、Au+ビームの線源径が実測できたと言うべきであろう。また、著者のおこなった光学系の評価手法が、設計の手法としてかなり現実に近い結果を与える確度の高い手法であることが確認されたということができよう。
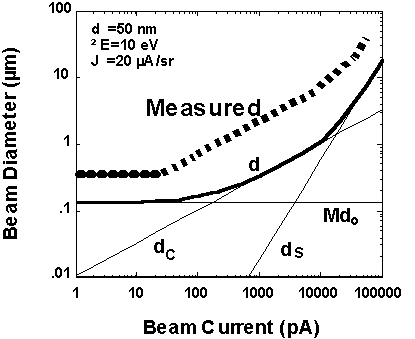
図2−17.減速したAu+ビーム実測値と計算結果の比較
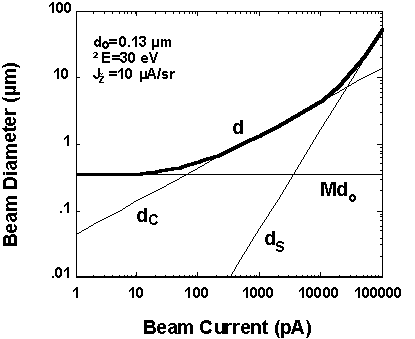
図2−18.50eVビームの電流値とビーム径の関係
(Au+ビームにおける実測値を再現する計算結果)
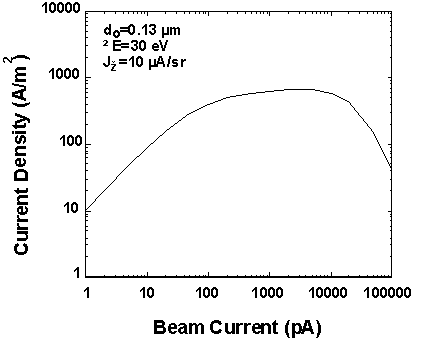
図2−19.50eVビームの電流値とビーム電流密度の関係
(Au+ビームにおける実測値をほぼ再現する計算結果)