 (2-14)
(2-14)2-3.光学系の探索と評価
前節において述べた手法により、想定したいくつかのレンズ系に対して低エネルギービームの集束特性の評価をおこない、著者の要求する性能を満たすと期待できるレンズ形状とその配置に関して探索をおこなった。要求する性能としては、最小ビーム径とビーム電流密度について設定した。最小ビーム径は、微細加工の手法としての集束イオンビーム直接蒸着法の価値を決定する最も重要な要因であり、またビーム電流密度は第1章において述べたように成膜手法としての集束イオンビーム直接蒸着法における高純度成膜という最大の特長を決定する要因である。最小ビーム径については0.1μmにできる限り近い値をとること、電流密度については104A/m2(1A/cm2)にできるだけ近い値をとることを目標とした。
前節において式(2-8)より示されているように、ビーム径は線源径と倍率の項、球面収差の項、および色収差の項であらわされる。線源径と倍率の項は完全に定数であり、ビーム電流値に依存しない。この項はビーム電流値を極限までしぼったときのビーム径に対応し、ビーム径の最小値をあらわす。色収差の項は焦点面でのビーム半角(αi)の1乗、すなわちビーム電流値の1/2乗で寄与し、球面収差の項はビーム半角の3乗、すなわちビーム電流値の3/2乗でビーム径に寄与する。したがって、低電流領域では線源径と倍率の項によりビーム径が決定され、ある範囲の中電流領域で色収差の項によりビーム径が決定され、その領域を超えた大電流領域においては球面収差の項によりビーム径が決定されるであろうことが定性的に予想できる。低電流領域(d~Mdo)においては電流密度(JI)は次のようにあらわされる。
 (2-14)
(2-14)
この領域では、電流密度は電流値に対して直線的に増加する。中電流領域(d~dC)においては、次のようにあらわされる。
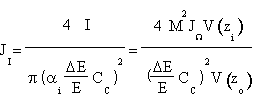 (2-15)
(2-15)
これは、ビーム半角(ビーム電流値)に依存しない定数となる。また、大電流領域(d~dS)においては、次のようにあらわされる。
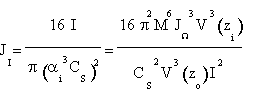 (2-16)
(2-16)
この領域では電流密度は電流値に対しては(逆2乗で)単調に減少する。これらの3領域を連結すると、中電流領域でビーム電流密度は一定値をとり、それが全電流領域における最大値であり、その両側では単調に増加/減少する傾向が明らかになる。したがって、ビーム電流密度の最大値を決定するのは色収差であり、色収差の小さな光学系の設計によってより大きなビーム電流密度を得ることが求められている課題である。また、ビーム電流密度が低下しない範囲で最小のビーム径を持つことが、実用的な最小ビーム径を得るために必要な条件である。
探索を開始するにあたって、Pease等がGa+の減速ビームを報告した2段の非対称型静電レンズから構成される光学系1、2)を前述した手法により評価した。Pease等の装置が低エネルギービームにどの程度最適化しているかは不明であり、また合金イオン源と質量分離器による多種のイオン種使用を可能とする機能、偏向電極と試料ステージを組み合わせた広範囲な描画機能、高純度成膜を可能とする超高真空雰囲気、光学顕微鏡による試料観察機能等、直接蒸着法の研究に不可欠な機能を備えていない。しかし、評価手法自体の機能確認と得られたレンズ系の評価のための参照用として利用した。このレンズ系の構成を図2-1に示す。第1レンズにより引き出し、集束、加速をおこない、第2レンズにより集束、減速をおこなう。評価にあたっては、以下に示す条件の設定および仮定をおこなった。
①初期条件としてイオン源位置に引き出しエネルギー(6keV)に相当する初速を持ち、大きさが実効的線源径doである線源があると仮定する。
②加速エネルギーは20keVとする。
③基準軌道は、第1レンズと第2レンズの中点で中心軸と交差する。
④エネルギー幅は10eVと仮定する。
⑤角電流密度は20μA/srと仮定する。
エネルギー幅ΔEはイオン化の過程における真のエネルギー幅と引き出し、加速、減速電位のリップルの和であらわされる。一般にGaイオン源において小電流引き出しにおけるエネルギー幅は10eV程度であると言われている10)。エネルギー幅はイオンの質量が大きいほど大きくなり、また引き出し電流値が大きくなればなるほど大きくなる傾向があり、Au+イオンの場合、引き出し電流値5~20μAにおいて20~40eVのエネルギー幅が報告されている10)。著者の実測においても電源系のリップル込みで同様な結果が得られている。したがって、計算にあたってはイオン種および引き出し条件を考慮して、エネルギー幅を代入することが必要になる。この計算においては、10eV(Ga+の値)を標準値として代入することにする。
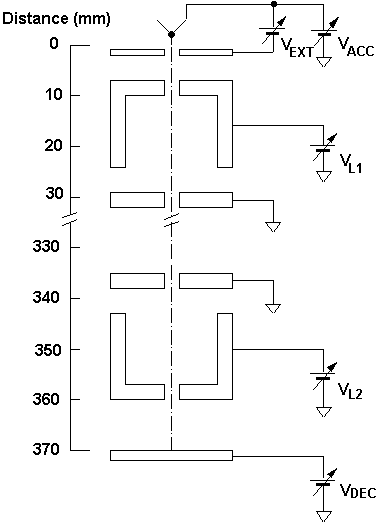
図2-1.Pease等が報告したレンズ系の形状1、2)
イオン源からの引き出しビームの角電流密度(JΩ)は、Gaイオン源の場合、およそ20μA/srであることが知られている11)。この値は著者等の合金イオン源の実測においてもほぼ同じ値が得られている。合金イオン源の場合には、全電流の合計がこの値になるので、各イオン種の角電流密度はそれぞれの成分比に相当する値となる。
このようにして得たPease等のレンズ系に対する著者の評価手法による評価結果を、図2-2~図2-4に示す。図2-2は、電流値10pA~100nAにおける最終エネルギーとビーム径の関係を示す。非減速時(20keV)のビーム径と比較して、減速時(50eV)におけるビーム径は4.1~5.2倍になっている。図2-3は最終エネルギーが50eVのときのビーム電流値とビーム径(d)、線源径と倍率の項(Mdo)、色収差の項(dC)、および球面収差の項(dS)の関係を示す。10pA~100nAにわたって色収差によりビーム径が決定されている結果が示されている。図2-4は最終エネルギーが50eVのときのビーム電流値とビーム電流密度の関係を示す。図で示すほとんどのビーム電流領域において色収差の項によりビーム径が決定されているために、およそ一定値となっており、最大値は600A/m2程度である。
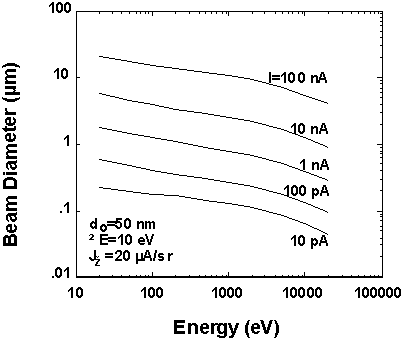
図2-2.Pease等のレンズ系における最終エネルギーとビーム径の関係(計算値)
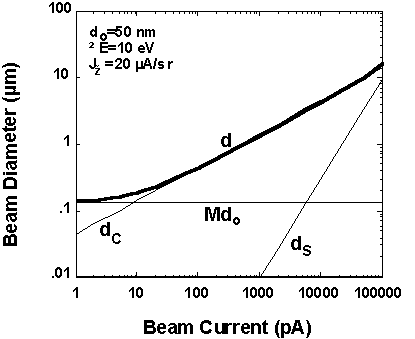
図2-3.Pease等のレンズ系における50eVビームのビーム電流値とビーム径(d)、
線源径の項(Md0)、球面収差の項(dS)、および色収差(dC)の項の関係(計算値)
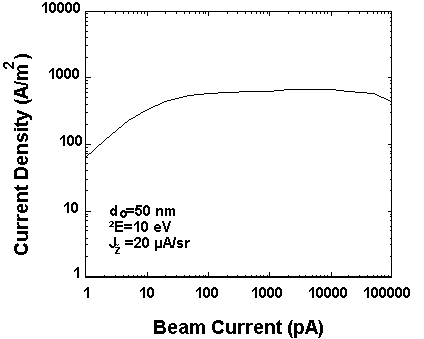
図2-4.Pease等のレンズ系における50eVビームのビーム電流値と
ビーム電流密度の関係(計算値)
Pease等の光学系の計算結果は、最小ビーム径(線源径と倍率の項)は0.14μmと目標値に近いが、それが実現するビーム電流値は1pAと小さく、ビーム電流密度も1pAにおいては100A/m2以下である。これは色収差が大きいことが原因である。 10pA~100nAの電流領域においてビーム径は色収差の項により決定されているが、この電流領域におけるビーム電流密度は600A/m2であり、目標とする104A/m2からはほど遠い。非減速ビームにおける集束特性はかなり良いようであるが(10pAのビーム電流値においてビーム径は50nm以下となっている)、集束イオンビーム直接蒸着法に用いる光学系としては色収差の効果が大きすぎる、というのがこの光学系に対する結論である。
著者の光学系は、これに対して低エネルギー領域において色収差の効果が小さいことが特長である。主な相違点は、Pease等のレンズが厚い(光軸方向に対して長い)非対称型の静電レンズであるのに対し、薄い(光軸方向に対して短い)対称型静電レンズを用いたことである。その結果、減速時の色収差はかなり改善することができた。しかし、減速時の倍率はあまり変わらないが、非減速時の倍率は大きくなり、非減速時の光学特性はかなり悪くなったということができる。また、薄いレンズの使用は、レンズ中心軸と光学系中心軸(光軸)間に生じる傾きの効果が小さいために(傾きをそれぞれの電極の位置誤差に変換した場合、その値は薄いレンズの方が小さくなる)、光軸調整が容易になるといった利点が生じる。
このようにして集束イオンビーム直接蒸着法に適した光学系の探索をおこない、目標値に近い性能が期待されるレンズ系を得ることができた。著者が採用したレンズ系の形状を図2-5に示す。レンズ系は二つの対称型静電レンズおよび引き出し後の加速電界、最後の減速電界によって構成される。実際の光学系には質量分離器、偏向電極等が加わる。引き出しビームはまず加速電位(加速電位と引き出し電位の差分)により1価イオンについて20keVまで加速され、第1静電レンズにより集束された後、第2静電レンズにより再び集束される。第2静電レンズを出るまでは、20keVに加速されたままである。最後に第2静電レンズとターゲット基板間の間隙で、基板に与えられた減速電位により0~20keVの最終エネルギーまで減速される。図2-5に示すレンズ系形状、配置のうち減速長(第2静電レンズと基板間の距離)Lは、基板が乗るXYZステージのz軸の調整により4~14mmの範囲で調整可能であるが、標準的には10mmで使用するように設計されており、評価においても10mmを用いている。
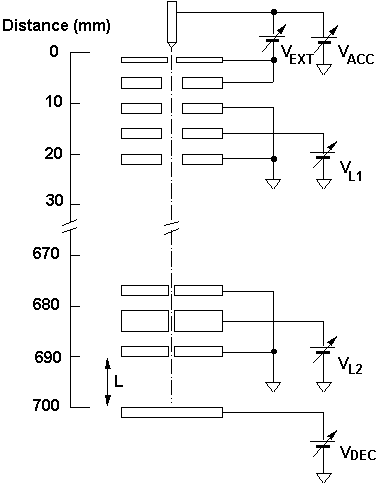
図2-5.低エネルギー集束イオンビーム装置に採用したレンズ系の形状
計算においておこなった条件の設定および仮定は、Pease等の光学系評価において述べた①~⑤と同じである。線源径、角電流密度、エネルギー幅はいずれもGaイオン源について報告された値を用いているので、もしそれらがイオン種により別の値をとるとしたら、これらの計算結果はGa+に関するものであると言わなくてはならない。このレンズ系に対する評価結果を図2-6~図2-9に示す。
図2-6は、最終エネルギーとビーム径の関係を10pA~100nAのビーム電流に対して示す。図2-2と比較して、減速ビーム径が10pA~10nAの電流領域において著しく改善されていることがわかる。また、減速ビームと非減速ビームの差が1.6~1.9倍程度と小さくなっている。図2-7は、非減速ビーム(20keV:a)と減速ビーム(50eV:b)において、線源径と倍率の項(Mdo)、球面収差の項(dS)、および色収差の項(dC)のビーム電流値に対する効果を示す。減速ビーム、非減速ビームともほぼ同じ傾向を示しており、低電流領域(<100pA)においては線源径と倍率の項、中電流領域(100pA~10nA)においては色収差の項、大電流領域(>10nA)においては球面収差の項によりビーム径が決定されている。図2-3と比較して、減速ビームに対する倍率はほぼ同じ、色収差の項はほぼ1/4になっており、逆に球面収差の項は2倍程度になっていることがわかる。図2-8は、減速ビーム(50eV)においてエネルギー幅を10~40eVにとったときのビーム電流値とビーム径の関係を示している。色収差によりビーム径が決定される中電流領域はエネルギー幅の値によって拡大、あるいは縮小する。図2-9は減速ビームのビーム電流密度を示す。エネルギー幅10eVに対して中電流領域で104A/m2の目標値が達成されていることが示されている。
これらの計算結果は、想定した光学系に対して、Ga+ビームに対して報告されているエネルギー幅、線源径を代入するとき、20~200eV程度の低エネルギー領域において目標である0.1μmにせまる0.14μmの最小ビーム径(ビーム電流密度は800A/m2)、および目標値である104A/m2の最大ビーム電流密度を持つ集束イオンビームの可能性を示すものである。この評価結果に基づき、低エネルギー集束イオンビームを実現するための実験装置の設計にとりかかった。
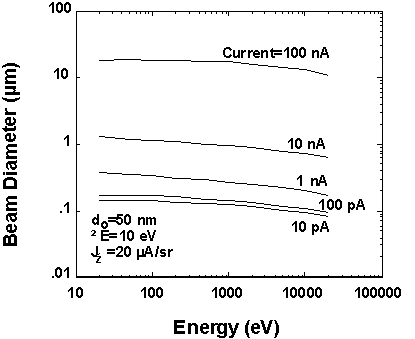
図2-6.著者等の光学系における最終エネルギーとビーム径の関係(計算値)
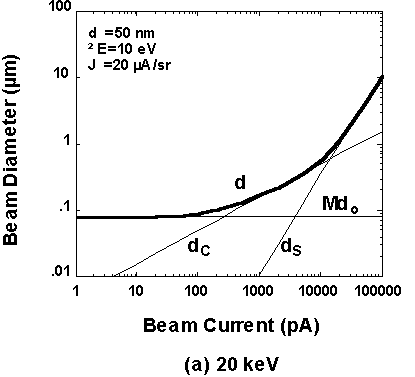
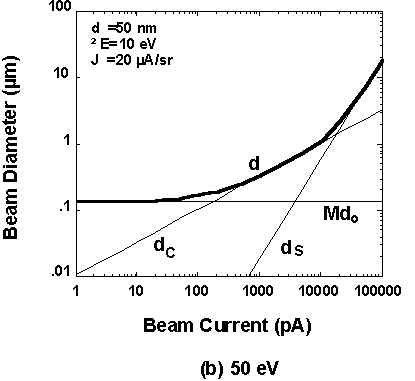
図2-7.非減速ビーム(20keV)と減速ビーム(50eV)におけるビーム径(d)と
線源径の項(Md0)、球面収差の項(dS)、および色収差(dC)の項の関係(計算値)
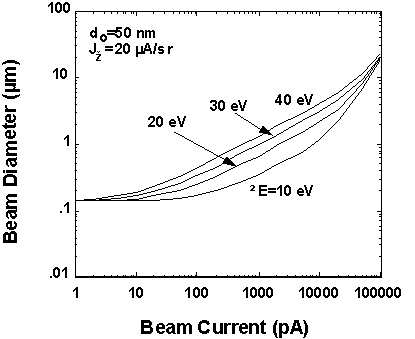
図2-8.エネルギー幅が10~40eVにおける減速ビーム(50eV)の
ビーム電流とビーム径の関係(計算値)
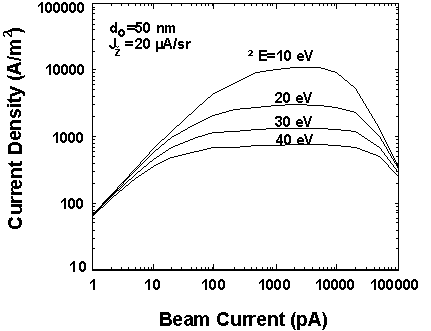
図2-9.減速ビーム(50eV)のビーム電流とビーム電流密度の関係(計算値)