つれづれ2008
後半
Logs
Dec.31 今年の総括
今年も終わり。時がたつのが早いと感じるのは30代だからなのか。今年もいろいろあったけど、趣味の総括です。
買ったCD :クラシック501枚、その他のジャンル142枚で計643枚。ここ数年の傾向として、クラシックのほうが圧倒的に多く買っている。ジャズ系はコンスタントに買っているが、ロックで面白い新譜がそうそうでないというのもあるかもしれない。新しく興味を持つバンドやミュージシャンもあんまりいないということかな。今年も、昨年と引き続きオペラと声楽がブームでした。
買ったDVD :119枚。今年もオペラのDVDを買い続けたせいか、多い。
行ったクラシックのコンサート :22回。2月に旅行に行ったときに7回もコンサートに行ったのが大きい。来日オケではナガノとモントリオール響がすばらしかった(遅れて行ったけど)。小澤とオペラ塾のこうもりも良かった。あと、印象に残るのは、岡田博美のゴールドベルク。
行ったライブ :15回。一番多く行ったのは去年と同じくunbeltipoのライブだが、2回。バンドは異なるが、鬼怒無月が5回。どれも印象に残るが、Zappa Plays Zappaはやはり完成度が高かった。ドームでのThe Policeは音がほとんど聴けなかったことが印象的。ジャズ系のライブはRichard BonaもJohn ScofieldもMike Sternも相変わらずいい感じだった。
行った展覧会 :4回。
読んだ本 :75冊 (音楽の本、グルメ・お酒の本、コンピュータの本、仕事の本、雑誌を除く)。昨年と大体同じくらい。シェークスピア全集読破計画が終了した。今年、はまったのはポール・オースター。
海外 :1回。プライベートで2月に旅行で行ったフランスとドイツ。ミュンヘンに住んでいた時もフランスだけにはいくことができず、ルーブルにはぜひ行きたいと思っていたので。ついでに行ったベルリンで、ラトル + ベルリン・フィルを聴くことができて、いい旅行だった。
その他 :ついにアンプとスピーカーを買い替えた。今まで使っていたものは大学2年生の頃に買ったものなので、14〜15年くらい使っていたことになる。
Dec.30 帰省 + 同窓会
帰省する。なんとなく、帰れるだろうと甘く見ていたが失敗した。14時ころ、東京駅まで出たのだが、自由席にすら座れない。新幹線のホームに人があふれている。おまけに、品川や新横浜で人が乗ってきて、朝の通勤電車のように満員だ。名古屋でなんとか座ることができたが、2時間たちっぱなし。せっかく駅弁を買ったのだが、立って食べる羽目になってしまった。16時半ころ新大阪駅で降りると、小田原で人身事故があって、16時以降の新幹線は止まっているらしい。昨日まで東北方面に行く新幹線もダイヤが乱れていたし、今年の年末の新幹線はめちゃめちゃだ。事故じゃないからまだいいけど。
夜は、毎年恒例高校の同窓会。昨年は出ていないので2年ぶりだ。25人ほどオッサンが集まる。関西圏内に住む医者が半分くらいだが、母校の先生になったやつもいれば、政治家めざしているやつもいれば、プロ棋士もいる。マスコミ系は、僕を含めて3人だが、不況の話題。在阪民放は、もろに影響を受けているらしい。2次会がプールバーで、久々にビリヤードをした。3次会まで飲んで、健康的に(?)日付が変わる頃に解散。1年に1回しか会わないやつがほとんどだが、それでも会えばなんとなく話が通じるし、気もあまり使わないし、楽しいもんだ。
新年に飲む約束をしようと、会社の同期にメールをしたら、そいつはみごと新横浜駅で足止めを食らったらしい。
Dec.29 ベルリン・フィル 最高のハーモニーを求めて
「Trip to ASIA」、邦題「ベルリン・フィル 最高のハーモニーを求めて」を、渋谷のユーロスペースへ見に行く。ベルリン・フィルハーモニーとラトルが。、2005年に行ったアジアツアーにあわせて、仮採用の団員、昔からいる団員、若い団員、定年間際の団員、のコメントと合わせて、このオケがどういう組織なのか、というのを見せ付けてくれる映画だった。音楽と生活の兼ね合い、ベルリンフィルの団員あることのストレス、組織のありようなど、オーケストラだけでなくどこの組織にでも起こりうる問題をメンバーが語っていくのはかなり面白い。「春の祭典」の映画は、ラトルが就任して間もなくの時期であり、またベルリン・フィルが公務員ではなく、独立行政法人のような組織に変わらなければいけない時期ということもあって、新しい試みをいっぱいいっぱいで頑張っています、といった雰囲気だったが、それよりも成熟した感じがする。そして、「春の祭典」のときと違うのは、ラトルが団員と付き添っている雰囲気になっているところです。練習風景でオーケストラ、しかも仮採用君に間違っているといわれるシーンなど意外です。リハで英語とドイツ語がちゃんぽんなのがもっと意外。印象的なのは、語る人がみんな、子供のころ友達がいない変わり者だと言い切るところですかね。
ベルリン・フィルはベルリンという都市だから、ああいうオケが出来上がったんだろうなと改めて感じた。ベルリンというのは、昔から首都だったわけではないし、音楽の伝統もあまりない。政治的には翻弄される。戦争でぶっ壊されるし、半分に分かれていた上に、周りは東に囲まれる。豊かさで言えばフランクフルトやミュンヘンのほうが圧倒的に上。なのに、人が集まる。そういう都市で最高のものを作るという意識と、過剰なまでの民主的なものへのこだわりがあのオケを作ってるんだろう。しかもフルトヴェングラーの後、実はドイツの人が監督になったことがない。ハイドン以来の音楽の都で、伝統のほうが重圧になるウィーン・フィルは、血や伝統、音楽するのが仕事ではなく生きざまだというような人ばかりなので、出てくる音が違うのは仕方ないわけだ。
メインで流れる曲が、英雄の生涯とベートーベンのエロイカなんだけど、とてもダメで変な演奏。変なアーティキュレーションをラトルがつけたがっているのだが、オケがイヤイヤな感じで、上っ面な演奏に聴こえる。今年の3月にベルリンで聴いたものと、解釈は似ているのだが、その時はベルリン・フィルの轟音のような弦のサウンドと、流れるような音楽だったので、3年で進化したってことなのだろうか?だとすると、長い時間をかけて素晴らしい仕事をしているということだ。
オーボエのマイヤーが語るシーンが多いのだが、肝心の英雄の生涯では乗っていない…つうか、語ってる人のほとんどが乗っていないとか、メンバーの顔を気にしながら見るともっと楽しい。ゼーガースが蝶について語るシーンとか、香港でコンサートの様子をパブリックビューで数万人が見た後、ロックスター並みに興奮しているシーンとか、コンサートやレコードだけではわからない側面、文化、時代のようなものが記録されているので、音楽が好きな人は見るべきところが多いと思う。
Dec.29 Lars Hollmer RIP
Samla Mammas MannaやAccordion Tribeで活躍していたラーシュ・ホルメルが27日になくなったそうだ。90年代後半は精力的に活動しており、アルバムやライブも多く、来日も何度かしていたのに、ここのところあまりニュースを聞かなくなっていたなとは思っていたのだが、体調がすぐれなかったようだ。今まで、再結成サムラ、Sola、向島ゆり子とのデュオの3回、来日公演を見ることができたが、Accordion Tribeとかもっと見てみたかったものだ。サムラのイメージが強いせいか、アヴァンギャルドな面やライブでのメチャメチャな雰囲気のイメージが強いが、とてもいいメロディを書く人だったと思う。もっとメジャーになってもいい人だったと思うが、これから他の人が彼の作品をもっと演奏してくれればとも思う。日本のファインサイトはここ。
Dec.25 CD : Return to Forever
 Return to Forever / Returns : チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴェーが再結成してツアーを行ったらしく、そのライブ録音がCDで発売された。DVDもそのうち出るようだ。このバンド、実はChick CoreaとStanley Clarke以外はメンバーの入れ替わりが多いのだが、黄金期と言われる第2期の3番目のメンバーでの再結成(第3期まで)。ギターがAl Di Meolaで、ドラムがLenny White。オープニングの曲だけ、新曲。ロックバンドの再結成とは違って、演奏に衰えというものは全く感じない。なんだか、余裕すら感じる。70年代の頃は、もっとせっついた感じだったんだろうけど、無茶をしなくても音が出せている感じがする。特にディメオラとホワイトの演奏に感じる。ホワイトのドラムは重くなった印象だ。あいかわらず、Stanley Clarkeのベースは音域がフラフラしていて、僕の好みのベースではない。もっとベースはうねるように、地盤を支えるようなラインを弾かないと。音楽に新規性はないし、ソロの応酬で手に汗を握る、という雰囲気の演奏ではないが、曲やメンバーに愛着があれば楽しく聴ける。
Return to Forever / Returns : チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴェーが再結成してツアーを行ったらしく、そのライブ録音がCDで発売された。DVDもそのうち出るようだ。このバンド、実はChick CoreaとStanley Clarke以外はメンバーの入れ替わりが多いのだが、黄金期と言われる第2期の3番目のメンバーでの再結成(第3期まで)。ギターがAl Di Meolaで、ドラムがLenny White。オープニングの曲だけ、新曲。ロックバンドの再結成とは違って、演奏に衰えというものは全く感じない。なんだか、余裕すら感じる。70年代の頃は、もっとせっついた感じだったんだろうけど、無茶をしなくても音が出せている感じがする。特にディメオラとホワイトの演奏に感じる。ホワイトのドラムは重くなった印象だ。あいかわらず、Stanley Clarkeのベースは音域がフラフラしていて、僕の好みのベースではない。もっとベースはうねるように、地盤を支えるようなラインを弾かないと。音楽に新規性はないし、ソロの応酬で手に汗を握る、という雰囲気の演奏ではないが、曲やメンバーに愛着があれば楽しく聴ける。
 Return to Forever / Returns : チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴェーが再結成してツアーを行ったらしく、そのライブ録音がCDで発売された。DVDもそのうち出るようだ。このバンド、実はChick CoreaとStanley Clarke以外はメンバーの入れ替わりが多いのだが、黄金期と言われる第2期の3番目のメンバーでの再結成(第3期まで)。ギターがAl Di Meolaで、ドラムがLenny White。オープニングの曲だけ、新曲。ロックバンドの再結成とは違って、演奏に衰えというものは全く感じない。なんだか、余裕すら感じる。70年代の頃は、もっとせっついた感じだったんだろうけど、無茶をしなくても音が出せている感じがする。特にディメオラとホワイトの演奏に感じる。ホワイトのドラムは重くなった印象だ。あいかわらず、Stanley Clarkeのベースは音域がフラフラしていて、僕の好みのベースではない。もっとベースはうねるように、地盤を支えるようなラインを弾かないと。音楽に新規性はないし、ソロの応酬で手に汗を握る、という雰囲気の演奏ではないが、曲やメンバーに愛着があれば楽しく聴ける。
Return to Forever / Returns : チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴェーが再結成してツアーを行ったらしく、そのライブ録音がCDで発売された。DVDもそのうち出るようだ。このバンド、実はChick CoreaとStanley Clarke以外はメンバーの入れ替わりが多いのだが、黄金期と言われる第2期の3番目のメンバーでの再結成(第3期まで)。ギターがAl Di Meolaで、ドラムがLenny White。オープニングの曲だけ、新曲。ロックバンドの再結成とは違って、演奏に衰えというものは全く感じない。なんだか、余裕すら感じる。70年代の頃は、もっとせっついた感じだったんだろうけど、無茶をしなくても音が出せている感じがする。特にディメオラとホワイトの演奏に感じる。ホワイトのドラムは重くなった印象だ。あいかわらず、Stanley Clarkeのベースは音域がフラフラしていて、僕の好みのベースではない。もっとベースはうねるように、地盤を支えるようなラインを弾かないと。音楽に新規性はないし、ソロの応酬で手に汗を握る、という雰囲気の演奏ではないが、曲やメンバーに愛着があれば楽しく聴ける。Dec.25 CD : Dido
 Dido / Safe Trip Home : ダイドの3作目。1作目は買ったんだけど、家に見当たらない。ブライアン・イーノとの共作があるとのことなので、なんとなく買ってしまった。僕の頭の中では、スザンヌ・ヴェガとかと同じようなジャンルの音楽だ。完成度はとても高く、耳にして疲れない女性ヴォーカル。
Dido / Safe Trip Home : ダイドの3作目。1作目は買ったんだけど、家に見当たらない。ブライアン・イーノとの共作があるとのことなので、なんとなく買ってしまった。僕の頭の中では、スザンヌ・ヴェガとかと同じようなジャンルの音楽だ。完成度はとても高く、耳にして疲れない女性ヴォーカル。
 Dido / Safe Trip Home : ダイドの3作目。1作目は買ったんだけど、家に見当たらない。ブライアン・イーノとの共作があるとのことなので、なんとなく買ってしまった。僕の頭の中では、スザンヌ・ヴェガとかと同じようなジャンルの音楽だ。完成度はとても高く、耳にして疲れない女性ヴォーカル。
Dido / Safe Trip Home : ダイドの3作目。1作目は買ったんだけど、家に見当たらない。ブライアン・イーノとの共作があるとのことなので、なんとなく買ってしまった。僕の頭の中では、スザンヌ・ヴェガとかと同じようなジャンルの音楽だ。完成度はとても高く、耳にして疲れない女性ヴォーカル。Dec.23 CD : Stefan Dohr
 Stefan Dohr : Mozart / Horn Concerto : ベルリン・フィルの首席ホルン奏者のひとりであるシュテファン・ドールがソロを吹く、モーツァルトのホルン協奏曲。彼がソロの協奏曲録音はこれが初めてみたいだ。バックは、シュルツ室内管弦楽団といい、ウィーン・フィルでフルートを吹くヴォルフガング・シュルツが一族や弟子を集めて作ったオケのようだ。アンサンブル・ウィーン・ベルリンつながりで、カメラータらしい企画だな。収録曲としては、4曲のホルン協奏曲なんだけど、第1番がジュスマイアの補筆による番だけでなくロバート・レヴィンによる補筆盤も録音されている。そして、ニーノ・ロータがこの第1番の第2楽章にと作曲したAndante Sostenutoも録音されている。オケが小編成なこともあると思うが、テンポははやめできびきびしている。ギュンター・ヘーグナーやペーター・ダムなどドイツ系のホルン吹きだと、レンジが狭めでちょっと間延びしたサウンドが印象に残るんだけど、ドールのホルンはもう少し機敏で(機能的?)颯爽としている。デニス・ブレインに近い印象なのかな。録音はとてもいいし、いいディスクだ。
Stefan Dohr : Mozart / Horn Concerto : ベルリン・フィルの首席ホルン奏者のひとりであるシュテファン・ドールがソロを吹く、モーツァルトのホルン協奏曲。彼がソロの協奏曲録音はこれが初めてみたいだ。バックは、シュルツ室内管弦楽団といい、ウィーン・フィルでフルートを吹くヴォルフガング・シュルツが一族や弟子を集めて作ったオケのようだ。アンサンブル・ウィーン・ベルリンつながりで、カメラータらしい企画だな。収録曲としては、4曲のホルン協奏曲なんだけど、第1番がジュスマイアの補筆による番だけでなくロバート・レヴィンによる補筆盤も録音されている。そして、ニーノ・ロータがこの第1番の第2楽章にと作曲したAndante Sostenutoも録音されている。オケが小編成なこともあると思うが、テンポははやめできびきびしている。ギュンター・ヘーグナーやペーター・ダムなどドイツ系のホルン吹きだと、レンジが狭めでちょっと間延びしたサウンドが印象に残るんだけど、ドールのホルンはもう少し機敏で(機能的?)颯爽としている。デニス・ブレインに近い印象なのかな。録音はとてもいいし、いいディスクだ。
 Stefan Dohr : Mozart / Horn Concerto : ベルリン・フィルの首席ホルン奏者のひとりであるシュテファン・ドールがソロを吹く、モーツァルトのホルン協奏曲。彼がソロの協奏曲録音はこれが初めてみたいだ。バックは、シュルツ室内管弦楽団といい、ウィーン・フィルでフルートを吹くヴォルフガング・シュルツが一族や弟子を集めて作ったオケのようだ。アンサンブル・ウィーン・ベルリンつながりで、カメラータらしい企画だな。収録曲としては、4曲のホルン協奏曲なんだけど、第1番がジュスマイアの補筆による番だけでなくロバート・レヴィンによる補筆盤も録音されている。そして、ニーノ・ロータがこの第1番の第2楽章にと作曲したAndante Sostenutoも録音されている。オケが小編成なこともあると思うが、テンポははやめできびきびしている。ギュンター・ヘーグナーやペーター・ダムなどドイツ系のホルン吹きだと、レンジが狭めでちょっと間延びしたサウンドが印象に残るんだけど、ドールのホルンはもう少し機敏で(機能的?)颯爽としている。デニス・ブレインに近い印象なのかな。録音はとてもいいし、いいディスクだ。
Stefan Dohr : Mozart / Horn Concerto : ベルリン・フィルの首席ホルン奏者のひとりであるシュテファン・ドールがソロを吹く、モーツァルトのホルン協奏曲。彼がソロの協奏曲録音はこれが初めてみたいだ。バックは、シュルツ室内管弦楽団といい、ウィーン・フィルでフルートを吹くヴォルフガング・シュルツが一族や弟子を集めて作ったオケのようだ。アンサンブル・ウィーン・ベルリンつながりで、カメラータらしい企画だな。収録曲としては、4曲のホルン協奏曲なんだけど、第1番がジュスマイアの補筆による番だけでなくロバート・レヴィンによる補筆盤も録音されている。そして、ニーノ・ロータがこの第1番の第2楽章にと作曲したAndante Sostenutoも録音されている。オケが小編成なこともあると思うが、テンポははやめできびきびしている。ギュンター・ヘーグナーやペーター・ダムなどドイツ系のホルン吹きだと、レンジが狭めでちょっと間延びしたサウンドが印象に残るんだけど、ドールのホルンはもう少し機敏で(機能的?)颯爽としている。デニス・ブレインに近い印象なのかな。録音はとてもいいし、いいディスクだ。Dec.22 DVD : Fabio Luisi
 Fabio Luisi + Staatsoper Dresden : R.Strauss / Der Rosenkavalier : 2007年のザクセン州立歌劇場、通称ゼンパー・オーパ、日本向けにはドレスデン歌劇場の引越し公演のDVD。NHKで放送されたものと同じ内容。この2007年は、ばらの騎士が流行っていた年で、ばら戦争なんて言われていた。新国立劇場、ウェルザー・メストのチューリッヒ歌劇場、そして最後がファビオ・ルイージのドレスデン歌劇場だった。でも残念なことに僕はどれも見ていない。この公演は、キャストがコロコロ変わって不評だった。もともと指揮は準メルクルだったはずなのだが、ルイージがタンホイザーの指揮から外れ、このばらを振ることになった。噂ではルイージはタンホイザーを振ったことがないとかいう話だった。メルクルの方がレパートリーが多かったってことですかね。タンホイザーは見に行っている。さらに、元帥夫人はもともとアンゲラ・デノケだったが、体調不良で来日せず、タンホイザーでもうたったアンネ・シュヴァンネヴィルムスが歌うことになった。また、森麻季が出演することがやたらクローズアップされていたように思う。
DVDをかけてまず驚いたのが録音のレベルがやたらと低い。録音が悪い、という意味ではなく収録されている音量がやたらと小さく、アンプのボリュームを大きく上げなければならなかった。オーケストラの演奏自体はいいんじゃないですかね。ルイージの指揮も、歌が絡むといい感じになっている。
演出はすこしセットがさびしい。20世紀あたりに時代を読み替えており、衣装もセットも19世紀の豪勢な雰囲気がないのが原因かもしれない。演出自体はオーソドックスなもの。第3幕も、変わった設定はしていない。
タンホイザーから中1日で歌っているのに、疲れすら見せないシュヴァンネヴィルムスの演じる、枯れと憂いのある元帥婦人がいい。ほんとうに急に代役を頼まれたとしたのなら、すばらしいとしか言いようがない。オクタビアンのアンケ・ヴォンドゥングも、初めて見る歌手だが、いいズボン役を演じていると思う。同じ時期のNHK音楽祭のコンサートで歌ったときは、イマイチだと思ったクルト・リドルのオックスもいい味を出している。問題はやはりゾフィー。練習会で歌っているかの如く、表情と歌い方が固定されている。しかも歌詞を覚えていないようで、常にプロンプターのほうを見つめうつむきがち。第2幕とオクタビアンとの二重唱のところでも顔を合わせることなく、同じ姿勢、同じ表情、同じような口もと。学校で習ったお手本どおりの姿勢と口の動きしか歌うことができないんですかね。オペラって演技しないといけないわけだから、話すように歌い、食べながらでも歌わなければならない。それでもいい発声や声量を求められるわけだ。レジーテアターが流行って演技が重視され、デ・ニースのようにボリウッドのようなダンスをしながら歌うことを要求されることだってあるのに、これではダメでしょう。ほんとにここだけが残念だ。
Fabio Luisi + Staatsoper Dresden : R.Strauss / Der Rosenkavalier : 2007年のザクセン州立歌劇場、通称ゼンパー・オーパ、日本向けにはドレスデン歌劇場の引越し公演のDVD。NHKで放送されたものと同じ内容。この2007年は、ばらの騎士が流行っていた年で、ばら戦争なんて言われていた。新国立劇場、ウェルザー・メストのチューリッヒ歌劇場、そして最後がファビオ・ルイージのドレスデン歌劇場だった。でも残念なことに僕はどれも見ていない。この公演は、キャストがコロコロ変わって不評だった。もともと指揮は準メルクルだったはずなのだが、ルイージがタンホイザーの指揮から外れ、このばらを振ることになった。噂ではルイージはタンホイザーを振ったことがないとかいう話だった。メルクルの方がレパートリーが多かったってことですかね。タンホイザーは見に行っている。さらに、元帥夫人はもともとアンゲラ・デノケだったが、体調不良で来日せず、タンホイザーでもうたったアンネ・シュヴァンネヴィルムスが歌うことになった。また、森麻季が出演することがやたらクローズアップされていたように思う。
DVDをかけてまず驚いたのが録音のレベルがやたらと低い。録音が悪い、という意味ではなく収録されている音量がやたらと小さく、アンプのボリュームを大きく上げなければならなかった。オーケストラの演奏自体はいいんじゃないですかね。ルイージの指揮も、歌が絡むといい感じになっている。
演出はすこしセットがさびしい。20世紀あたりに時代を読み替えており、衣装もセットも19世紀の豪勢な雰囲気がないのが原因かもしれない。演出自体はオーソドックスなもの。第3幕も、変わった設定はしていない。
タンホイザーから中1日で歌っているのに、疲れすら見せないシュヴァンネヴィルムスの演じる、枯れと憂いのある元帥婦人がいい。ほんとうに急に代役を頼まれたとしたのなら、すばらしいとしか言いようがない。オクタビアンのアンケ・ヴォンドゥングも、初めて見る歌手だが、いいズボン役を演じていると思う。同じ時期のNHK音楽祭のコンサートで歌ったときは、イマイチだと思ったクルト・リドルのオックスもいい味を出している。問題はやはりゾフィー。練習会で歌っているかの如く、表情と歌い方が固定されている。しかも歌詞を覚えていないようで、常にプロンプターのほうを見つめうつむきがち。第2幕とオクタビアンとの二重唱のところでも顔を合わせることなく、同じ姿勢、同じ表情、同じような口もと。学校で習ったお手本どおりの姿勢と口の動きしか歌うことができないんですかね。オペラって演技しないといけないわけだから、話すように歌い、食べながらでも歌わなければならない。それでもいい発声や声量を求められるわけだ。レジーテアターが流行って演技が重視され、デ・ニースのようにボリウッドのようなダンスをしながら歌うことを要求されることだってあるのに、これではダメでしょう。ほんとにここだけが残念だ。
 Fabio Luisi + Staatsoper Dresden : R.Strauss / Der Rosenkavalier : 2007年のザクセン州立歌劇場、通称ゼンパー・オーパ、日本向けにはドレスデン歌劇場の引越し公演のDVD。NHKで放送されたものと同じ内容。この2007年は、ばらの騎士が流行っていた年で、ばら戦争なんて言われていた。新国立劇場、ウェルザー・メストのチューリッヒ歌劇場、そして最後がファビオ・ルイージのドレスデン歌劇場だった。でも残念なことに僕はどれも見ていない。この公演は、キャストがコロコロ変わって不評だった。もともと指揮は準メルクルだったはずなのだが、ルイージがタンホイザーの指揮から外れ、このばらを振ることになった。噂ではルイージはタンホイザーを振ったことがないとかいう話だった。メルクルの方がレパートリーが多かったってことですかね。タンホイザーは見に行っている。さらに、元帥夫人はもともとアンゲラ・デノケだったが、体調不良で来日せず、タンホイザーでもうたったアンネ・シュヴァンネヴィルムスが歌うことになった。また、森麻季が出演することがやたらクローズアップされていたように思う。
DVDをかけてまず驚いたのが録音のレベルがやたらと低い。録音が悪い、という意味ではなく収録されている音量がやたらと小さく、アンプのボリュームを大きく上げなければならなかった。オーケストラの演奏自体はいいんじゃないですかね。ルイージの指揮も、歌が絡むといい感じになっている。
演出はすこしセットがさびしい。20世紀あたりに時代を読み替えており、衣装もセットも19世紀の豪勢な雰囲気がないのが原因かもしれない。演出自体はオーソドックスなもの。第3幕も、変わった設定はしていない。
タンホイザーから中1日で歌っているのに、疲れすら見せないシュヴァンネヴィルムスの演じる、枯れと憂いのある元帥婦人がいい。ほんとうに急に代役を頼まれたとしたのなら、すばらしいとしか言いようがない。オクタビアンのアンケ・ヴォンドゥングも、初めて見る歌手だが、いいズボン役を演じていると思う。同じ時期のNHK音楽祭のコンサートで歌ったときは、イマイチだと思ったクルト・リドルのオックスもいい味を出している。問題はやはりゾフィー。練習会で歌っているかの如く、表情と歌い方が固定されている。しかも歌詞を覚えていないようで、常にプロンプターのほうを見つめうつむきがち。第2幕とオクタビアンとの二重唱のところでも顔を合わせることなく、同じ姿勢、同じ表情、同じような口もと。学校で習ったお手本どおりの姿勢と口の動きしか歌うことができないんですかね。オペラって演技しないといけないわけだから、話すように歌い、食べながらでも歌わなければならない。それでもいい発声や声量を求められるわけだ。レジーテアターが流行って演技が重視され、デ・ニースのようにボリウッドのようなダンスをしながら歌うことを要求されることだってあるのに、これではダメでしょう。ほんとにここだけが残念だ。
Fabio Luisi + Staatsoper Dresden : R.Strauss / Der Rosenkavalier : 2007年のザクセン州立歌劇場、通称ゼンパー・オーパ、日本向けにはドレスデン歌劇場の引越し公演のDVD。NHKで放送されたものと同じ内容。この2007年は、ばらの騎士が流行っていた年で、ばら戦争なんて言われていた。新国立劇場、ウェルザー・メストのチューリッヒ歌劇場、そして最後がファビオ・ルイージのドレスデン歌劇場だった。でも残念なことに僕はどれも見ていない。この公演は、キャストがコロコロ変わって不評だった。もともと指揮は準メルクルだったはずなのだが、ルイージがタンホイザーの指揮から外れ、このばらを振ることになった。噂ではルイージはタンホイザーを振ったことがないとかいう話だった。メルクルの方がレパートリーが多かったってことですかね。タンホイザーは見に行っている。さらに、元帥夫人はもともとアンゲラ・デノケだったが、体調不良で来日せず、タンホイザーでもうたったアンネ・シュヴァンネヴィルムスが歌うことになった。また、森麻季が出演することがやたらクローズアップされていたように思う。
DVDをかけてまず驚いたのが録音のレベルがやたらと低い。録音が悪い、という意味ではなく収録されている音量がやたらと小さく、アンプのボリュームを大きく上げなければならなかった。オーケストラの演奏自体はいいんじゃないですかね。ルイージの指揮も、歌が絡むといい感じになっている。
演出はすこしセットがさびしい。20世紀あたりに時代を読み替えており、衣装もセットも19世紀の豪勢な雰囲気がないのが原因かもしれない。演出自体はオーソドックスなもの。第3幕も、変わった設定はしていない。
タンホイザーから中1日で歌っているのに、疲れすら見せないシュヴァンネヴィルムスの演じる、枯れと憂いのある元帥婦人がいい。ほんとうに急に代役を頼まれたとしたのなら、すばらしいとしか言いようがない。オクタビアンのアンケ・ヴォンドゥングも、初めて見る歌手だが、いいズボン役を演じていると思う。同じ時期のNHK音楽祭のコンサートで歌ったときは、イマイチだと思ったクルト・リドルのオックスもいい味を出している。問題はやはりゾフィー。練習会で歌っているかの如く、表情と歌い方が固定されている。しかも歌詞を覚えていないようで、常にプロンプターのほうを見つめうつむきがち。第2幕とオクタビアンとの二重唱のところでも顔を合わせることなく、同じ姿勢、同じ表情、同じような口もと。学校で習ったお手本どおりの姿勢と口の動きしか歌うことができないんですかね。オペラって演技しないといけないわけだから、話すように歌い、食べながらでも歌わなければならない。それでもいい発声や声量を求められるわけだ。レジーテアターが流行って演技が重視され、デ・ニースのようにボリウッドのようなダンスをしながら歌うことを要求されることだってあるのに、これではダメでしょう。ほんとにここだけが残念だ。Dec.16 CD : It's a Musical
 It's a Musical / The Music Makes me Sick : 例によってタワレコで視聴買い。エレクトロニカのコーナーに置いてあったが、まあフォークトロニカといえそうなポップス。スウェーデンのElla Blixtという女性が、ドイツ人のRobert Kretzschmarと組んだユニットらしい。ジャケットからしてそうだが、キュートでポップ。安っぽい書き方だけど、それ以外何物でもない。ピアノの音がとても耳に残るサウンドだ。アルバムタイトルにもなっている3曲目の"The Music Makes me Sick"は、キラーチューン。これほどよくできた曲もめずらしい。ちょっと影がある感じも含めて、良いのかもしれない。オフィシャルサイトはここ。PVはこんな感じ。
It's a Musical / The Music Makes me Sick : 例によってタワレコで視聴買い。エレクトロニカのコーナーに置いてあったが、まあフォークトロニカといえそうなポップス。スウェーデンのElla Blixtという女性が、ドイツ人のRobert Kretzschmarと組んだユニットらしい。ジャケットからしてそうだが、キュートでポップ。安っぽい書き方だけど、それ以外何物でもない。ピアノの音がとても耳に残るサウンドだ。アルバムタイトルにもなっている3曲目の"The Music Makes me Sick"は、キラーチューン。これほどよくできた曲もめずらしい。ちょっと影がある感じも含めて、良いのかもしれない。オフィシャルサイトはここ。PVはこんな感じ。
 It's a Musical / The Music Makes me Sick : 例によってタワレコで視聴買い。エレクトロニカのコーナーに置いてあったが、まあフォークトロニカといえそうなポップス。スウェーデンのElla Blixtという女性が、ドイツ人のRobert Kretzschmarと組んだユニットらしい。ジャケットからしてそうだが、キュートでポップ。安っぽい書き方だけど、それ以外何物でもない。ピアノの音がとても耳に残るサウンドだ。アルバムタイトルにもなっている3曲目の"The Music Makes me Sick"は、キラーチューン。これほどよくできた曲もめずらしい。ちょっと影がある感じも含めて、良いのかもしれない。オフィシャルサイトはここ。PVはこんな感じ。
It's a Musical / The Music Makes me Sick : 例によってタワレコで視聴買い。エレクトロニカのコーナーに置いてあったが、まあフォークトロニカといえそうなポップス。スウェーデンのElla Blixtという女性が、ドイツ人のRobert Kretzschmarと組んだユニットらしい。ジャケットからしてそうだが、キュートでポップ。安っぽい書き方だけど、それ以外何物でもない。ピアノの音がとても耳に残るサウンドだ。アルバムタイトルにもなっている3曲目の"The Music Makes me Sick"は、キラーチューン。これほどよくできた曲もめずらしい。ちょっと影がある感じも含めて、良いのかもしれない。オフィシャルサイトはここ。PVはこんな感じ。Dec.13 Mozart "Don Giovanni" / Constantin Trinks @ 新国立劇場 (Tokyo Philharmony Orchestra)
リゴレットに引き続き、新国でオペラを見ようねプロジェクト。本日はドン・ジョヴァンニ。家を出るのがちょっと遅い上に、バスが来なくて、時間に間に合わず、着いた時には序曲が終わっていた。第1場が終わるまで1階でまたされ、そのあと3階の立ち見席にほりこまれる。演出は基本的にはオーソドックスなもの。だが、視覚的にはきれいなのかもしれないが、チェスのコマとかイメージをあまりかきたてられないオブジェがいくつかあった。
指揮はコンスタンティン・トリンクスという人。非常にオペラ叩き上げの感じがする指揮者で、色付けがうまい人だった。第1幕の最後でテンポを急速に上げるなどと、意外な処理もあったのだが、流れがいい指揮だった。チェンバロも彼が弾いていたのだが即興性があり、とても巧かった。基本的にはビブラート控えめのオーデンティックな奏法を意識した演奏なんだが、問題はオーケストラ。その指揮者の面白みが台無しになるような技術力だった。あいかわらずですな。
ドン・ジョバンニのルチオ・ガッロは、シャンパンの歌も息切れなく歌いきっていたし全般的に良かった。逆に、レポレロのアンドレア・コンチェッティはちょっと物足りなかった。もう少し押しが強くてトンチが効いてる方が個人的には好き。
ドンナアンナのモシュクが本公演の聴きどころだと思うのだが、個人的にはそれほどピンとこなかった。確かにテクはあるんですけど、ちょっと吠えすぎで周りとのバランスが悪いですかね。エリヴィーラのアガ・ミコライという人も、飛びぬけて素晴らしい印象は受けませんでしたが、バランスが良かったでした。あと良かったのは、アニメ声系のツェルリーナを歌っていた高橋薫子。
全体的には、まずまずといったところかなと思うが、モーツァルトの面白さを初めてオペラを見た人に伝えられるほどのステージではないとも思う。
Dec.13 CD : Marc-Andre Hamelin
 Marc-Andre Hamelin : Chopin / Piano Sonata : アムランの新譜は、Hyperionに録音することはないだろうなと思っていたショパン。ソナタ2曲と、子守唄と舟歌。ついにアムランもメジャーなピアノ曲を弾くのかと勘違いしそうだが、実は昔から弾いていて、ソナタは2曲とも録音がすでに出ている。第2番は、 Port Royalから出ているし、第3番は、Ruhr音楽祭のDVDがある。第2番の旧録は、あまりにストレートに弾きすぎて、色彩感がないように感じる演奏だった。良いか悪いかは別にして、まあアムランらしいなと思わせる演奏だった。今回の録音は、その色彩感をつけようとして中途半端になってしまった感じがしてならない。来日公演のベートーヴェンの31番で、鼻息荒く悪戦苦闘しながら弾いていた姿を思い出してしまう演奏なのだ。相性が悪いのかな。第3番は、基本的な解釈はDVDと同じだと思う。ここに収められた曲の中では第3番が一番聴けるかな…
Marc-Andre Hamelin : Chopin / Piano Sonata : アムランの新譜は、Hyperionに録音することはないだろうなと思っていたショパン。ソナタ2曲と、子守唄と舟歌。ついにアムランもメジャーなピアノ曲を弾くのかと勘違いしそうだが、実は昔から弾いていて、ソナタは2曲とも録音がすでに出ている。第2番は、 Port Royalから出ているし、第3番は、Ruhr音楽祭のDVDがある。第2番の旧録は、あまりにストレートに弾きすぎて、色彩感がないように感じる演奏だった。良いか悪いかは別にして、まあアムランらしいなと思わせる演奏だった。今回の録音は、その色彩感をつけようとして中途半端になってしまった感じがしてならない。来日公演のベートーヴェンの31番で、鼻息荒く悪戦苦闘しながら弾いていた姿を思い出してしまう演奏なのだ。相性が悪いのかな。第3番は、基本的な解釈はDVDと同じだと思う。ここに収められた曲の中では第3番が一番聴けるかな…
 Marc-Andre Hamelin : Chopin / Piano Sonata : アムランの新譜は、Hyperionに録音することはないだろうなと思っていたショパン。ソナタ2曲と、子守唄と舟歌。ついにアムランもメジャーなピアノ曲を弾くのかと勘違いしそうだが、実は昔から弾いていて、ソナタは2曲とも録音がすでに出ている。第2番は、 Port Royalから出ているし、第3番は、Ruhr音楽祭のDVDがある。第2番の旧録は、あまりにストレートに弾きすぎて、色彩感がないように感じる演奏だった。良いか悪いかは別にして、まあアムランらしいなと思わせる演奏だった。今回の録音は、その色彩感をつけようとして中途半端になってしまった感じがしてならない。来日公演のベートーヴェンの31番で、鼻息荒く悪戦苦闘しながら弾いていた姿を思い出してしまう演奏なのだ。相性が悪いのかな。第3番は、基本的な解釈はDVDと同じだと思う。ここに収められた曲の中では第3番が一番聴けるかな…
Marc-Andre Hamelin : Chopin / Piano Sonata : アムランの新譜は、Hyperionに録音することはないだろうなと思っていたショパン。ソナタ2曲と、子守唄と舟歌。ついにアムランもメジャーなピアノ曲を弾くのかと勘違いしそうだが、実は昔から弾いていて、ソナタは2曲とも録音がすでに出ている。第2番は、 Port Royalから出ているし、第3番は、Ruhr音楽祭のDVDがある。第2番の旧録は、あまりにストレートに弾きすぎて、色彩感がないように感じる演奏だった。良いか悪いかは別にして、まあアムランらしいなと思わせる演奏だった。今回の録音は、その色彩感をつけようとして中途半端になってしまった感じがしてならない。来日公演のベートーヴェンの31番で、鼻息荒く悪戦苦闘しながら弾いていた姿を思い出してしまう演奏なのだ。相性が悪いのかな。第3番は、基本的な解釈はDVDと同じだと思う。ここに収められた曲の中では第3番が一番聴けるかな…Dec.10 CD : Yellow Magic Orchestra

 Londonymo + Gijonymo : YMOのライブ盤。もうだまされないぞ、と思って買わないつもりだったのだが、CDショップで視聴したところ、みごとにだまされて買ってしまった。2008年、ヨーロッパでの公演のライブ盤。一つは6月15日のロンドン。Meltdown Festivalでのライブ。もう一つは6月19日、スペインのヒホンでの音楽祭のライブ。サポートは、高田漣、クリスチャン・フェネス、権藤知彦という最近のYMOファミリー。Sketch Showに坂本龍一がゲスト参加してから、Human Audio Sponge、HASYMOといった名義で3人が集まっていたが、このライブ盤でついにYMOの名義になってしまった。セットリストは、YMOの曲、Sketch Showの曲、坂本龍一のソロ、HASYMOの曲とまんべんなく選曲されている。"Tibetan Dance"がこの3人のライブで演奏されたのは初めてではないだろうか。
たった4日違いのライブなので、ほとんど違いがないだろう、あくどい商法だ、と思わされるが、実はかなり違う。どちらも最近の3人らしくエレクトロニカを前面に出した、音数の少ない、しかし生楽器の音が印象的な、へんな言葉を使えばオーガニックな演奏だ。そしてLondonの方はクールだ。Sketch Showのライブでも感じたクールさ。そしてこちらの方が2曲多く、"Fly me to the River"と細野のソロ曲だった"Sportsmen"が収録されている。なぜGijonの方がホットかというと、幸宏が後半、生ドラムを真剣に叩いているのだ。この点でLondonとGijonの録音のイメージが全然異なる。"Liot in Lagos"はあおられたのか細野のベースも素晴らしい演奏。昔のYMOの曲が少ないなんて野暮なことを言う人は聴かない方がいいかもしれない。今は全然違うプロジェクトなのだから。
Londonymo + Gijonymo : YMOのライブ盤。もうだまされないぞ、と思って買わないつもりだったのだが、CDショップで視聴したところ、みごとにだまされて買ってしまった。2008年、ヨーロッパでの公演のライブ盤。一つは6月15日のロンドン。Meltdown Festivalでのライブ。もう一つは6月19日、スペインのヒホンでの音楽祭のライブ。サポートは、高田漣、クリスチャン・フェネス、権藤知彦という最近のYMOファミリー。Sketch Showに坂本龍一がゲスト参加してから、Human Audio Sponge、HASYMOといった名義で3人が集まっていたが、このライブ盤でついにYMOの名義になってしまった。セットリストは、YMOの曲、Sketch Showの曲、坂本龍一のソロ、HASYMOの曲とまんべんなく選曲されている。"Tibetan Dance"がこの3人のライブで演奏されたのは初めてではないだろうか。
たった4日違いのライブなので、ほとんど違いがないだろう、あくどい商法だ、と思わされるが、実はかなり違う。どちらも最近の3人らしくエレクトロニカを前面に出した、音数の少ない、しかし生楽器の音が印象的な、へんな言葉を使えばオーガニックな演奏だ。そしてLondonの方はクールだ。Sketch Showのライブでも感じたクールさ。そしてこちらの方が2曲多く、"Fly me to the River"と細野のソロ曲だった"Sportsmen"が収録されている。なぜGijonの方がホットかというと、幸宏が後半、生ドラムを真剣に叩いているのだ。この点でLondonとGijonの録音のイメージが全然異なる。"Liot in Lagos"はあおられたのか細野のベースも素晴らしい演奏。昔のYMOの曲が少ないなんて野暮なことを言う人は聴かない方がいいかもしれない。今は全然違うプロジェクトなのだから。

 Londonymo + Gijonymo : YMOのライブ盤。もうだまされないぞ、と思って買わないつもりだったのだが、CDショップで視聴したところ、みごとにだまされて買ってしまった。2008年、ヨーロッパでの公演のライブ盤。一つは6月15日のロンドン。Meltdown Festivalでのライブ。もう一つは6月19日、スペインのヒホンでの音楽祭のライブ。サポートは、高田漣、クリスチャン・フェネス、権藤知彦という最近のYMOファミリー。Sketch Showに坂本龍一がゲスト参加してから、Human Audio Sponge、HASYMOといった名義で3人が集まっていたが、このライブ盤でついにYMOの名義になってしまった。セットリストは、YMOの曲、Sketch Showの曲、坂本龍一のソロ、HASYMOの曲とまんべんなく選曲されている。"Tibetan Dance"がこの3人のライブで演奏されたのは初めてではないだろうか。
たった4日違いのライブなので、ほとんど違いがないだろう、あくどい商法だ、と思わされるが、実はかなり違う。どちらも最近の3人らしくエレクトロニカを前面に出した、音数の少ない、しかし生楽器の音が印象的な、へんな言葉を使えばオーガニックな演奏だ。そしてLondonの方はクールだ。Sketch Showのライブでも感じたクールさ。そしてこちらの方が2曲多く、"Fly me to the River"と細野のソロ曲だった"Sportsmen"が収録されている。なぜGijonの方がホットかというと、幸宏が後半、生ドラムを真剣に叩いているのだ。この点でLondonとGijonの録音のイメージが全然異なる。"Liot in Lagos"はあおられたのか細野のベースも素晴らしい演奏。昔のYMOの曲が少ないなんて野暮なことを言う人は聴かない方がいいかもしれない。今は全然違うプロジェクトなのだから。
Londonymo + Gijonymo : YMOのライブ盤。もうだまされないぞ、と思って買わないつもりだったのだが、CDショップで視聴したところ、みごとにだまされて買ってしまった。2008年、ヨーロッパでの公演のライブ盤。一つは6月15日のロンドン。Meltdown Festivalでのライブ。もう一つは6月19日、スペインのヒホンでの音楽祭のライブ。サポートは、高田漣、クリスチャン・フェネス、権藤知彦という最近のYMOファミリー。Sketch Showに坂本龍一がゲスト参加してから、Human Audio Sponge、HASYMOといった名義で3人が集まっていたが、このライブ盤でついにYMOの名義になってしまった。セットリストは、YMOの曲、Sketch Showの曲、坂本龍一のソロ、HASYMOの曲とまんべんなく選曲されている。"Tibetan Dance"がこの3人のライブで演奏されたのは初めてではないだろうか。
たった4日違いのライブなので、ほとんど違いがないだろう、あくどい商法だ、と思わされるが、実はかなり違う。どちらも最近の3人らしくエレクトロニカを前面に出した、音数の少ない、しかし生楽器の音が印象的な、へんな言葉を使えばオーガニックな演奏だ。そしてLondonの方はクールだ。Sketch Showのライブでも感じたクールさ。そしてこちらの方が2曲多く、"Fly me to the River"と細野のソロ曲だった"Sportsmen"が収録されている。なぜGijonの方がホットかというと、幸宏が後半、生ドラムを真剣に叩いているのだ。この点でLondonとGijonの録音のイメージが全然異なる。"Liot in Lagos"はあおられたのか細野のベースも素晴らしい演奏。昔のYMOの曲が少ないなんて野暮なことを言う人は聴かない方がいいかもしれない。今は全然違うプロジェクトなのだから。Dec.8 Unbeltipo @ 新宿Pit Inn
久々のウンベルティポのライブ。半年ぶりくらいかな。ライブ盤のCDも出ているが、やはり生で聴くと気持ちのいいバンドだ。そしてシリアスな演奏と、だらだらとしたMC。数年前のライブは、メンバーが演奏に対して緊張していたのか構えていたのかほとんどMCがなかったのに、最近のUnbeltipoのライブはMCが長い。今堀もナスノのMCを楽しんでいるようにも見える。セットリストはUBT 20 / Method of Panic / UBT 18 / The grid of the window // UBT 21 / Dash Freezing / The Tape Eater / UBT 19 // Pheasantism。UBT20、UBT18あたりはこなれてきていて流れが自然だ。後半の1曲目、新曲のUBT 21だが、やる前にナスノがゴネだし「インプロにしよう。そのほうが楽しい」と言いだす。今堀が「インプロの気持ちで」とか「インプロから入ろう」とかなだめすかしていたのが笑えた。この21はとてもかっこよくて、前半がテクノ風のカッティングコード、中間部がプログレ。そろそろ録音、みたいな話も出ているようだ。演奏もMCも長かったため、前半が終わった段階で22時近かったのだが、終了したら23時を過ぎていた。
Dec.6 Speaker
 8月にアンプを買ったが、スピーカーも買い替えることにした。ほとんど衝動買いなんだけど、タイミングの問題だけで、買ったスピーカーはアンプと同じく何年も前から目をつけていたもの。Monitor Audio(日本の代理店はここ)のSilver Reference RS6。色が何種類かあって、ローズナットと黒はある程度、日本に在庫があるようだが、僕がほしいウォルナットは、受注生産。頼んだのが10月の末なので、一か月ちょっとで納品された。ためしにアンプにつなげてみたが、音はまだバラバラで、これから楽しみだ。
8月にアンプを買ったが、スピーカーも買い替えることにした。ほとんど衝動買いなんだけど、タイミングの問題だけで、買ったスピーカーはアンプと同じく何年も前から目をつけていたもの。Monitor Audio(日本の代理店はここ)のSilver Reference RS6。色が何種類かあって、ローズナットと黒はある程度、日本に在庫があるようだが、僕がほしいウォルナットは、受注生産。頼んだのが10月の末なので、一か月ちょっとで納品された。ためしにアンプにつなげてみたが、音はまだバラバラで、これから楽しみだ。
 8月にアンプを買ったが、スピーカーも買い替えることにした。ほとんど衝動買いなんだけど、タイミングの問題だけで、買ったスピーカーはアンプと同じく何年も前から目をつけていたもの。Monitor Audio(日本の代理店はここ)のSilver Reference RS6。色が何種類かあって、ローズナットと黒はある程度、日本に在庫があるようだが、僕がほしいウォルナットは、受注生産。頼んだのが10月の末なので、一か月ちょっとで納品された。ためしにアンプにつなげてみたが、音はまだバラバラで、これから楽しみだ。
8月にアンプを買ったが、スピーカーも買い替えることにした。ほとんど衝動買いなんだけど、タイミングの問題だけで、買ったスピーカーはアンプと同じく何年も前から目をつけていたもの。Monitor Audio(日本の代理店はここ)のSilver Reference RS6。色が何種類かあって、ローズナットと黒はある程度、日本に在庫があるようだが、僕がほしいウォルナットは、受注生産。頼んだのが10月の末なので、一か月ちょっとで納品された。ためしにアンプにつなげてみたが、音はまだバラバラで、これから楽しみだ。Dec.6 Charles Dutoit + NHK Symphony Orchestra @ NHK Hall
N響の土曜日の公演って昼からだと思っていたんだが、いつのまにか夕方からに変わっていた。N響を聴くのは2年ぶり。指揮はデュトワ。2年前に行ったのも実はデュトワ。もっと聴いてもいいオケなんだけど、なかなか食指が…。今日のプログラムはストラヴィンスキーの「アポロ」と「エディプス王」。このプログラムはあまり聴けないなと思って行ってきた。客の入りはいまいち。驚いたことに開演前にオケが練習していた。ヨーロッパのオケは開演前によくステージ上で練習してるけれども、N響でこういうシーンを見たのは初めてかもしれない。デュトワは厳しいんだろうな。まず「アポロ」。編成は弦楽器のみの曲。カラヤン + ベルリン・フィルの筋肉質な演奏で耳が慣れているので、N響ではちょっとものたりなかった。技術的にはうまかったんだけど、ちょっと音量が小さかったかな。この曲、耳障りがいいですが、録音が少ないような気もする。聴いたことがあるのはラトルとムラヴィンスキーくらいで、どちらも重厚で筋肉質な演奏だ。ストラヴィンスキーの曲をほとんど録音しているようなブーレーズも録音がないのではないか。
メインは、エディプス王。これは非常によかった。この曲は、現地語でのナレーターとラテン語の歌曲とでなっているが、当然日本語。そして語るのが平幹二朗。あのヒラミキです。濃いいし、声は通るし、威厳もあるし、ぴったりだ。歌手が軒並みよかったのも勝因か。エディプス王を歌っているのが、ザルツブルグ2006の魔笛でタミーノを歌っているポール・グローブズ。王様にしてはちょっと甘い声ですが、それを抜きにすれば、最後まで歌いきっていましたし、エエ声でした。ぺトラ・ラングも良い声だが、この曲ではほとんど歌うパートがない。ちょっともったいない気もする。彼女は、シャイーのマーラーや、ティーレマンのトリスタンの録音でも歌っていて、大物扱いだと思うのだが。日本人が一人混じっていて、大槻孝志というひとだったのですが、声量もがっちりとあり、いい歌手だと思った。
今日のオケは金管があまりミスをしていなかったのが、ポイントが高い。音量が出ないけど、今日はうまかったです。しかし、久々に聴いてみて思ったのだが、このオケの木管はまずい。フルートとか何を吹いているのか。音が裏返るほど強く吹いたって良いことないですよ。きれいな音で吹こうとは思わないのかな。
Nov.30 Mozart "Die Zauberfloete" / 東京アマデウス管弦楽団 @ ミューザ川崎ホール
東京アマデウス管弦楽団の定期公演。友人がのっているので聴きに行く。今回は記念公演で、なんと魔笛全曲。ステージセットなしで、動きだけあるコンサート形式。まあ、トータルとしての感想はモーツァルト最高!かな。
演出はかなり凝ったもので、会場やピットに歌手が動いて行ったり、P席の1列目がコーラスだったり、飽きないものでした。読み替えとかはほとんどないのですが、ドイツ流ムジーク・テアターの流れですね。夜の女王メジャーキーのアリアのところで、ザラストロが会場の後ろを横切るとか、わかりにくい、というか、あの客層だとたいてい気づかないぞ?というような演出もあり。冒頭の蛇は演出が難しいところですが、ボディコンのおねえさん。本職は子供の振り付け師のようでしたが。セットはなくてもなんとなく意味はわかる演出。
セリフは、流れがわかるのに必要な最低限のもののみで、あとはカット。字幕も、流れが把握できる範囲のものだけだった。
歌手で一番良かったのはパパゲーノ。演技も良かったし、声の通りも発音も良かった。でも笛のチューニングが違うのが気になった…これはキーを合わせてもらわないと気持ち悪いんですよ。タミーノもいい声をしたテノールでした。パミーナは歌というより、かわいげがないのが残念でした。もちろん、見た目も込みで。夜の女王は、生であれだけ歌えたら合格点でしょうね。モノスタトスは風邪ですかね。可哀そうなことに全然声が出ていなかった。ザラストロは、ちと風格に欠けましたかね。
指揮は、東大オケでも有名な(?)三石精一。序曲の頭が重すぎたので、ぉぃぉぃこのテンポで行くのかよ、と思ったのだが、序奏以外はテンポはかなり速めで軽快に進んでいき、気持ちのいいものだった。ただ、指揮のくせなのか、オケの融通の利かなさを配慮したのか、歌手の歌い回しより、オケのテンポを維持する方を重視していたようで、夜の女王一つ目とか、タミーノのアリアとか息継ぎなどで歌手が苦労していたところが見受けられた。あと、フルートなんかの重要なフレーズが埋もれたまま進んで行ったりするのは、ちょっと残念。
客は結構入っていて、座るところを見つけるのが大変。モノスタトスの「なんてきれいな鈴の音」のところの動物と、2幕最後のパパゲーノとパパゲーナのところの子供の役で、大量の子供が出てきて、それは可愛かったのですが、その家族が客にいっぱいいたみたいでした。子供が退場する時にずっと拍手をするもんで、音楽が聞こえない…孫がかわいいのはわかるんですが、音楽やステージに配慮してほしいところだった。
Nov.29 CD : Terry Bozzio
 Terry Bozzio / Four from Ten Twenty Nine : ライブ会場で購入したCD。Bozzioを招へいしている&Forest Musicのレーベルのようだ。昨年来日した時のソロライブの演奏を4曲収録している。"djon don"は「Drawing the Circle」、"Klangfarben Melodie"は「Solo Drum Music Vol.3」に収録されている曲なので、残りの2曲も曲として作曲されているものなのかもしれない。ドラムが好きな人なら聴いていても飽きないだろうが、一人で延々と演奏しているので、聴きとおすのはつらい。演奏のクオリティはとても高いのだけど、聴く方に集中力が持たない。映像があればまだ楽しいんだろうけどね。ネットの情報によると、2007年の録音で14枚組のBOXも出すそうで。
Terry Bozzio / Four from Ten Twenty Nine : ライブ会場で購入したCD。Bozzioを招へいしている&Forest Musicのレーベルのようだ。昨年来日した時のソロライブの演奏を4曲収録している。"djon don"は「Drawing the Circle」、"Klangfarben Melodie"は「Solo Drum Music Vol.3」に収録されている曲なので、残りの2曲も曲として作曲されているものなのかもしれない。ドラムが好きな人なら聴いていても飽きないだろうが、一人で延々と演奏しているので、聴きとおすのはつらい。演奏のクオリティはとても高いのだけど、聴く方に集中力が持たない。映像があればまだ楽しいんだろうけどね。ネットの情報によると、2007年の録音で14枚組のBOXも出すそうで。
 Terry Bozzio / Four from Ten Twenty Nine : ライブ会場で購入したCD。Bozzioを招へいしている&Forest Musicのレーベルのようだ。昨年来日した時のソロライブの演奏を4曲収録している。"djon don"は「Drawing the Circle」、"Klangfarben Melodie"は「Solo Drum Music Vol.3」に収録されている曲なので、残りの2曲も曲として作曲されているものなのかもしれない。ドラムが好きな人なら聴いていても飽きないだろうが、一人で延々と演奏しているので、聴きとおすのはつらい。演奏のクオリティはとても高いのだけど、聴く方に集中力が持たない。映像があればまだ楽しいんだろうけどね。ネットの情報によると、2007年の録音で14枚組のBOXも出すそうで。
Terry Bozzio / Four from Ten Twenty Nine : ライブ会場で購入したCD。Bozzioを招へいしている&Forest Musicのレーベルのようだ。昨年来日した時のソロライブの演奏を4曲収録している。"djon don"は「Drawing the Circle」、"Klangfarben Melodie"は「Solo Drum Music Vol.3」に収録されている曲なので、残りの2曲も曲として作曲されているものなのかもしれない。ドラムが好きな人なら聴いていても飽きないだろうが、一人で延々と演奏しているので、聴きとおすのはつらい。演奏のクオリティはとても高いのだけど、聴く方に集中力が持たない。映像があればまだ楽しいんだろうけどね。ネットの情報によると、2007年の録音で14枚組のBOXも出すそうで。Nov.29 Terry Bozzio @ STB139
 昨年の2回の来日に続いて、今年も来日。ドラムセットを日本にも置いたのが大きいのかな。セットの移動費が高いのが理由といわれた、Bozzio Levin Stevensの来日中止は昔の話ということか。今回の来日ツアーは様々なフォーマットで行われている。逆の見方をすれば、初めての顔合わせが多いので、ほとんどインプロビゼーション一発勝負ということか。今日のメンバーは、Terry Bozzio、Pat Mastelotto、Tony LevinにAllan Holdsworthが加わる形。Allan以外の3人では、東京以外の土地でライブを何回かやってこなれているだろう。BozzioとMastelottはDuoでツアーもやっており、アルバムも出ている。LevinとMastelottoはKrimsonのメンバー、BozzioとLevinもBozzio Levin Stevensで共演済みなので、何かしら関係がある。でもAllan Holdsworthってどの3人とも共演したことがないんじゃないのかな。BozzioはUKでニアミスだし、彼が尊敬するTony Williamsのバンドにもいたことがあるので、よくは聴いているんだろうけど。いつもの会社の同僚の人たち4人組で観戦(?)。
前半、後半、アンコールの3曲で、ぜんぶインプロヴィゼーション。時間も45分、45分、15分。やはりAllanが浮ぎみだが、LevinやMastelottoがいい感じでキューを出してAllanが入り込めるスペースを作ってあげていた。どちらかといえば、3人ともAllanに気遣いすぎ。Allanのソロは最近のソロアルバムに多い、もあっとしたコードを多用した、雲のかたまりのような印象の音が多く、曲を引っ張ったり他の演奏者をあおったりするようなものではなかった。全体的な印象としては、Terryが基本的にはおとなしかった。Levinはスティックとアップライトのみで、2回ともスティック→アップライトの指弾き→アップライトの弓弾き→アップライトの指弾き→スティックと持ち替えるパターンだった。Patがあおって、Levinが乗せていくクリムゾンのような形が多かった。Levinが曲の流れを決めているシーンが多かったように感じた。相変わらず大人な雰囲気のいいプレーヤーだ。MastelottはBozzioと被るのを避けるように、Korgのパットを叩くシーンが多かった。見てくれは野人だけど、つぼを心得ていて、Levinとの相性もいいし、いい演奏が多かった。アンコールでは、MastelottoはTerryのセットのPercを叩いていた。Allan抜きで、もうちょっとテーマのある曲を演奏してくれると面白いかも知れない。
昨年の2回の来日に続いて、今年も来日。ドラムセットを日本にも置いたのが大きいのかな。セットの移動費が高いのが理由といわれた、Bozzio Levin Stevensの来日中止は昔の話ということか。今回の来日ツアーは様々なフォーマットで行われている。逆の見方をすれば、初めての顔合わせが多いので、ほとんどインプロビゼーション一発勝負ということか。今日のメンバーは、Terry Bozzio、Pat Mastelotto、Tony LevinにAllan Holdsworthが加わる形。Allan以外の3人では、東京以外の土地でライブを何回かやってこなれているだろう。BozzioとMastelottはDuoでツアーもやっており、アルバムも出ている。LevinとMastelottoはKrimsonのメンバー、BozzioとLevinもBozzio Levin Stevensで共演済みなので、何かしら関係がある。でもAllan Holdsworthってどの3人とも共演したことがないんじゃないのかな。BozzioはUKでニアミスだし、彼が尊敬するTony Williamsのバンドにもいたことがあるので、よくは聴いているんだろうけど。いつもの会社の同僚の人たち4人組で観戦(?)。
前半、後半、アンコールの3曲で、ぜんぶインプロヴィゼーション。時間も45分、45分、15分。やはりAllanが浮ぎみだが、LevinやMastelottoがいい感じでキューを出してAllanが入り込めるスペースを作ってあげていた。どちらかといえば、3人ともAllanに気遣いすぎ。Allanのソロは最近のソロアルバムに多い、もあっとしたコードを多用した、雲のかたまりのような印象の音が多く、曲を引っ張ったり他の演奏者をあおったりするようなものではなかった。全体的な印象としては、Terryが基本的にはおとなしかった。Levinはスティックとアップライトのみで、2回ともスティック→アップライトの指弾き→アップライトの弓弾き→アップライトの指弾き→スティックと持ち替えるパターンだった。Patがあおって、Levinが乗せていくクリムゾンのような形が多かった。Levinが曲の流れを決めているシーンが多かったように感じた。相変わらず大人な雰囲気のいいプレーヤーだ。MastelottはBozzioと被るのを避けるように、Korgのパットを叩くシーンが多かった。見てくれは野人だけど、つぼを心得ていて、Levinとの相性もいいし、いい演奏が多かった。アンコールでは、MastelottoはTerryのセットのPercを叩いていた。Allan抜きで、もうちょっとテーマのある曲を演奏してくれると面白いかも知れない。
 昨年の2回の来日に続いて、今年も来日。ドラムセットを日本にも置いたのが大きいのかな。セットの移動費が高いのが理由といわれた、Bozzio Levin Stevensの来日中止は昔の話ということか。今回の来日ツアーは様々なフォーマットで行われている。逆の見方をすれば、初めての顔合わせが多いので、ほとんどインプロビゼーション一発勝負ということか。今日のメンバーは、Terry Bozzio、Pat Mastelotto、Tony LevinにAllan Holdsworthが加わる形。Allan以外の3人では、東京以外の土地でライブを何回かやってこなれているだろう。BozzioとMastelottはDuoでツアーもやっており、アルバムも出ている。LevinとMastelottoはKrimsonのメンバー、BozzioとLevinもBozzio Levin Stevensで共演済みなので、何かしら関係がある。でもAllan Holdsworthってどの3人とも共演したことがないんじゃないのかな。BozzioはUKでニアミスだし、彼が尊敬するTony Williamsのバンドにもいたことがあるので、よくは聴いているんだろうけど。いつもの会社の同僚の人たち4人組で観戦(?)。
前半、後半、アンコールの3曲で、ぜんぶインプロヴィゼーション。時間も45分、45分、15分。やはりAllanが浮ぎみだが、LevinやMastelottoがいい感じでキューを出してAllanが入り込めるスペースを作ってあげていた。どちらかといえば、3人ともAllanに気遣いすぎ。Allanのソロは最近のソロアルバムに多い、もあっとしたコードを多用した、雲のかたまりのような印象の音が多く、曲を引っ張ったり他の演奏者をあおったりするようなものではなかった。全体的な印象としては、Terryが基本的にはおとなしかった。Levinはスティックとアップライトのみで、2回ともスティック→アップライトの指弾き→アップライトの弓弾き→アップライトの指弾き→スティックと持ち替えるパターンだった。Patがあおって、Levinが乗せていくクリムゾンのような形が多かった。Levinが曲の流れを決めているシーンが多かったように感じた。相変わらず大人な雰囲気のいいプレーヤーだ。MastelottはBozzioと被るのを避けるように、Korgのパットを叩くシーンが多かった。見てくれは野人だけど、つぼを心得ていて、Levinとの相性もいいし、いい演奏が多かった。アンコールでは、MastelottoはTerryのセットのPercを叩いていた。Allan抜きで、もうちょっとテーマのある曲を演奏してくれると面白いかも知れない。
昨年の2回の来日に続いて、今年も来日。ドラムセットを日本にも置いたのが大きいのかな。セットの移動費が高いのが理由といわれた、Bozzio Levin Stevensの来日中止は昔の話ということか。今回の来日ツアーは様々なフォーマットで行われている。逆の見方をすれば、初めての顔合わせが多いので、ほとんどインプロビゼーション一発勝負ということか。今日のメンバーは、Terry Bozzio、Pat Mastelotto、Tony LevinにAllan Holdsworthが加わる形。Allan以外の3人では、東京以外の土地でライブを何回かやってこなれているだろう。BozzioとMastelottはDuoでツアーもやっており、アルバムも出ている。LevinとMastelottoはKrimsonのメンバー、BozzioとLevinもBozzio Levin Stevensで共演済みなので、何かしら関係がある。でもAllan Holdsworthってどの3人とも共演したことがないんじゃないのかな。BozzioはUKでニアミスだし、彼が尊敬するTony Williamsのバンドにもいたことがあるので、よくは聴いているんだろうけど。いつもの会社の同僚の人たち4人組で観戦(?)。
前半、後半、アンコールの3曲で、ぜんぶインプロヴィゼーション。時間も45分、45分、15分。やはりAllanが浮ぎみだが、LevinやMastelottoがいい感じでキューを出してAllanが入り込めるスペースを作ってあげていた。どちらかといえば、3人ともAllanに気遣いすぎ。Allanのソロは最近のソロアルバムに多い、もあっとしたコードを多用した、雲のかたまりのような印象の音が多く、曲を引っ張ったり他の演奏者をあおったりするようなものではなかった。全体的な印象としては、Terryが基本的にはおとなしかった。Levinはスティックとアップライトのみで、2回ともスティック→アップライトの指弾き→アップライトの弓弾き→アップライトの指弾き→スティックと持ち替えるパターンだった。Patがあおって、Levinが乗せていくクリムゾンのような形が多かった。Levinが曲の流れを決めているシーンが多かったように感じた。相変わらず大人な雰囲気のいいプレーヤーだ。MastelottはBozzioと被るのを避けるように、Korgのパットを叩くシーンが多かった。見てくれは野人だけど、つぼを心得ていて、Levinとの相性もいいし、いい演奏が多かった。アンコールでは、MastelottoはTerryのセットのPercを叩いていた。Allan抜きで、もうちょっとテーマのある曲を演奏してくれると面白いかも知れない。Nov.29 フェルメール展 @ 東京都美術館
東京都美術館の「フェルメール展」を見に行く。フェルメール数枚と、フランドル系の画家の作品、計40点で1600円とちょっと割高。やっぱりフェルメールは人気があるようで、土曜日の夕方でもけっこう混んでいた。土曜日は20時まで開いているということで遅めに行ったのだが。フェルメール作品をスタンプラリーのように見続けている僕のような人にとっては、スコットランドやアイルランドの美術館所蔵のフェルメールの作品が展示されているところがいいが、一般人からしてみればマイナーな作品が多いような気もする。そういう意味では、来る予定だったが、作品が痛みそうという理由で来なかったウィーンの「絵画芸術」がないのは残念だったのかもしれない。人が多かったのも理由だが、1時間もかからずに見終わってしまった。
ピカソとは違ってフェルメールは作品数が少ないので、スタンプラリーのように見て回る人が多いと思うし、「フェルメール全点踏破の旅」という本あるくらいだ。僕も頻繁に見てきたが、所蔵の美術館を訪れてみたものと日本で見たものと複数回見ているものもあるので、ここでまとめてみる。やはりアメリカの美術館が所蔵している作品はほとんど見ていませんね…
| 牛乳を注ぐ女 | Amsterdam / 国立美術館 | 2003 / アムステルダム 2007 / 国立新美術館 |
| 青衣の女 | Amsterdam / 国立美術館 | 2003 / アムステルダム |
| 小路 | Amsterdam / 国立美術館 | 2003 / アムステルダム 2008 / 東京都美術館 |
| 恋文 | Amsterdam / 国立美術館 | 2003 / アムステルダム |
| 真珠の耳飾りの少女 | Den Haag / マウリッツハイス | 2000 / 大阪市立美術館 2003 / アムステルダム |
| デルフト眺望 | Den Haag / マウリッツハイス | 2003 / アムステルダム |
| ディアナとニンフたち | Den Haag / マウリッツハイス | 2003 / アムステルダム 2008 / 東京都美術館 |
| ぶどう酒のグラス | Berlin / 絵画館 | 2006 / ベルリン 2008 / ベルリン |
| 真珠の首飾り | Berlin / 絵画館 | 2006 / ベルリン 2008 / ベルリン |
| 取り持ち女 | Dresden / 国立美術館 | 2006 / ドレスデン |
| 窓辺で手紙を読む女 | Dresden / 国立美術館 | 2005 / 国立西洋美術館 2006 / ドレスデン |
| 地理学者 | Frankfurt am Main / シュテーデル美術館 | 2000 / 大阪市立美術館 2006 / フランクフルト |
| ワイングラスを持つ娘 | Braunschweig / アントン・ウルリッヒ美術館 | 2008 / 東京都美術館 |
| 絵画芸術 | Wien / 美術史美術館 | 2004 / 東京都美術館 2005 / ウィーン |
| 天文学者 | Paris / ルーヴル美術館 | 2008 / パリ |
| レースを編む女 | Paris / ルーヴル美術館 | 2008 / パリ |
| ヴァージナルの前に立つ女 | London / ナショナルギャラリー | 2001 / ロンドン 2003 / ロンドン 2005 / ロンドン 2006 / ロンドン |
| ヴァージナルの前に座る女 | London / ナショナルギャラリー | 2001 / ロンドン 2003 / ロンドン 2005 / ロンドン 2006 / ロンドン |
| 音楽の稽古 | London / バッキンガム宮殿王室コレクション | |
| ギターを弾く女 | London / ケンウッドハウス | 2006 / ロンドン |
| 手紙を書く女と召使 | Dublin / ナショナルギャラリー | 2008 / 東京都美術館 |
| マリアとマルタの家のキリスト | Edinburgh / スコットランド国立絵画館 | 2008 / 東京都美術館 |
| 眠る女 | New York / メトロポリタン美術館 | |
| 水差しを持つ女 | New York / メトロポリタン美術館 | |
| リュートを調弦する女 | New York / メトロポリタン美術館 | 2000 / 大阪市立美術館 2008 / 東京都美術館 |
| 少女 | New York / メトロポリタン美術館 | |
| 信仰の寓意 | New York / メトロポリタン美術館 | |
| 兵士と笑う娘 | New York / フリックコレクション | |
| 中断された音楽の稽古 | New York / フリックコレクション | |
| 婦人と召使 | New York / フリックコレクション | |
| 天秤を持つ女 | Washington D.C. / ナショナルギャラリー | 2000 / 大阪市立美術館 |
| 赤い帽子の女 | Washington D.C. / ナショナルギャラリー | |
| 手紙を書く女 | Washington D.C. / ナショナルギャラリー | |
| フルートを持つ女 | Washington D.C. / ナショナルギャラリー | |
| 聖女プラクセデス | Prinston / バーバラ・ピアセッカ・ジョンソン・コレクション | 2000 / 大阪市立美術館 |
| 合奏 | 盗難 | |
| ヴァージナルの前に座る女 | 個人蔵 | 2008 / 東京都美術館 |
Nov.25 CD : Vadim Repin + Riccardo Chailly
 Vadim Repin + Riccardo Chailly : Brahms / Violin Concerto : レーピンの新譜。レーピンはグラモフォンに移籍するまで、ベートーヴェンとブラームスの協奏曲の録音は控えていたらしく、この歳になって満を持しての録音ということらしい。ベートーヴェンはムーティとウィーンフィルがつけていたが、このブラームスはシャイーとゲバントハウスがつけている。レーピンのヴァイオリンは文句のつけようがなく、多少歌い回しが濃く、引き崩したように聞こえるところがあるものの、テクニック上不安定なところは全くない。2月に聴いたシベリウスも素晴らしかったし、ヴェンゲーロフがソリストとして引退してしまったようなので、レーピンはこれからもがんばってほしい。シャイーとゲバントハウスも素晴らしい鳴りっぷり。ルイージの録音で聴けるシュターツカペレ・ドレスデンでも感じたが、ゲバントハウスも旧東ドイツのくすんだ暗い感じがあまりしない。実演で聴いた時も抜けがいいと書いていますね。カップリングはモルクがチェロで、ブラームスのダブル・コンチェルト。ヴァイオリン協奏曲と同じくすばらしい演奏なんだけど、曲がイマイチですね…
Vadim Repin + Riccardo Chailly : Brahms / Violin Concerto : レーピンの新譜。レーピンはグラモフォンに移籍するまで、ベートーヴェンとブラームスの協奏曲の録音は控えていたらしく、この歳になって満を持しての録音ということらしい。ベートーヴェンはムーティとウィーンフィルがつけていたが、このブラームスはシャイーとゲバントハウスがつけている。レーピンのヴァイオリンは文句のつけようがなく、多少歌い回しが濃く、引き崩したように聞こえるところがあるものの、テクニック上不安定なところは全くない。2月に聴いたシベリウスも素晴らしかったし、ヴェンゲーロフがソリストとして引退してしまったようなので、レーピンはこれからもがんばってほしい。シャイーとゲバントハウスも素晴らしい鳴りっぷり。ルイージの録音で聴けるシュターツカペレ・ドレスデンでも感じたが、ゲバントハウスも旧東ドイツのくすんだ暗い感じがあまりしない。実演で聴いた時も抜けがいいと書いていますね。カップリングはモルクがチェロで、ブラームスのダブル・コンチェルト。ヴァイオリン協奏曲と同じくすばらしい演奏なんだけど、曲がイマイチですね…
 Vadim Repin + Riccardo Chailly : Brahms / Violin Concerto : レーピンの新譜。レーピンはグラモフォンに移籍するまで、ベートーヴェンとブラームスの協奏曲の録音は控えていたらしく、この歳になって満を持しての録音ということらしい。ベートーヴェンはムーティとウィーンフィルがつけていたが、このブラームスはシャイーとゲバントハウスがつけている。レーピンのヴァイオリンは文句のつけようがなく、多少歌い回しが濃く、引き崩したように聞こえるところがあるものの、テクニック上不安定なところは全くない。2月に聴いたシベリウスも素晴らしかったし、ヴェンゲーロフがソリストとして引退してしまったようなので、レーピンはこれからもがんばってほしい。シャイーとゲバントハウスも素晴らしい鳴りっぷり。ルイージの録音で聴けるシュターツカペレ・ドレスデンでも感じたが、ゲバントハウスも旧東ドイツのくすんだ暗い感じがあまりしない。実演で聴いた時も抜けがいいと書いていますね。カップリングはモルクがチェロで、ブラームスのダブル・コンチェルト。ヴァイオリン協奏曲と同じくすばらしい演奏なんだけど、曲がイマイチですね…
Vadim Repin + Riccardo Chailly : Brahms / Violin Concerto : レーピンの新譜。レーピンはグラモフォンに移籍するまで、ベートーヴェンとブラームスの協奏曲の録音は控えていたらしく、この歳になって満を持しての録音ということらしい。ベートーヴェンはムーティとウィーンフィルがつけていたが、このブラームスはシャイーとゲバントハウスがつけている。レーピンのヴァイオリンは文句のつけようがなく、多少歌い回しが濃く、引き崩したように聞こえるところがあるものの、テクニック上不安定なところは全くない。2月に聴いたシベリウスも素晴らしかったし、ヴェンゲーロフがソリストとして引退してしまったようなので、レーピンはこれからもがんばってほしい。シャイーとゲバントハウスも素晴らしい鳴りっぷり。ルイージの録音で聴けるシュターツカペレ・ドレスデンでも感じたが、ゲバントハウスも旧東ドイツのくすんだ暗い感じがあまりしない。実演で聴いた時も抜けがいいと書いていますね。カップリングはモルクがチェロで、ブラームスのダブル・コンチェルト。ヴァイオリン協奏曲と同じくすばらしい演奏なんだけど、曲がイマイチですね…Nov.25 CD : Jeff Beck
 Jeff Beck / Performing This Week : ジェフ・ベックのオフィシャル・ブートレグ・シリーズの第3弾。昨年のライブ。前の2作と違って、これは初めから発売することを念頭において録音されているようで、音質がかなりいい。オフィシャル・ブートレグというよりは、ライブ盤です。選曲も最近作の曲も含めてBeckのベスト曲ばかりで、聴き飽きない。2005年の来日公演のときとベース以外はメンバーがおなじで、キーボードはJason Rebello、ドラムはカリウタ。ベースは、話題の女の子Tal Wilkenfeld。レベロのキーボードもいいのだが、一番耳が行くのはやはりカリウタ。いつもの彼に比べればおとなしいんだけど、そのおとなしさも含めてジェフ・ベックのギターに合っている。うまいなぁ。金物系が特にいい。ジェフのギターはもう言うことがありません。この世代ではピカイチですね。昔から何も変わってないのかもしれないけれども、機材の進化もあって、シャープさとサウンドの細やかさが増しています。ほんとに神がかり的。もともとあまり仕事をしないという評価が高かった(?)人ですが、21世紀に入ってからの仕事ぶりは信じられない。この録音は1週間ほど、ロニースコッツ・クラブで演奏をして収録したらしいが、来年DVDもでるらしいので、そちらも買っちゃうんだろうね。
Jeff Beck / Performing This Week : ジェフ・ベックのオフィシャル・ブートレグ・シリーズの第3弾。昨年のライブ。前の2作と違って、これは初めから発売することを念頭において録音されているようで、音質がかなりいい。オフィシャル・ブートレグというよりは、ライブ盤です。選曲も最近作の曲も含めてBeckのベスト曲ばかりで、聴き飽きない。2005年の来日公演のときとベース以外はメンバーがおなじで、キーボードはJason Rebello、ドラムはカリウタ。ベースは、話題の女の子Tal Wilkenfeld。レベロのキーボードもいいのだが、一番耳が行くのはやはりカリウタ。いつもの彼に比べればおとなしいんだけど、そのおとなしさも含めてジェフ・ベックのギターに合っている。うまいなぁ。金物系が特にいい。ジェフのギターはもう言うことがありません。この世代ではピカイチですね。昔から何も変わってないのかもしれないけれども、機材の進化もあって、シャープさとサウンドの細やかさが増しています。ほんとに神がかり的。もともとあまり仕事をしないという評価が高かった(?)人ですが、21世紀に入ってからの仕事ぶりは信じられない。この録音は1週間ほど、ロニースコッツ・クラブで演奏をして収録したらしいが、来年DVDもでるらしいので、そちらも買っちゃうんだろうね。
 Jeff Beck / Performing This Week : ジェフ・ベックのオフィシャル・ブートレグ・シリーズの第3弾。昨年のライブ。前の2作と違って、これは初めから発売することを念頭において録音されているようで、音質がかなりいい。オフィシャル・ブートレグというよりは、ライブ盤です。選曲も最近作の曲も含めてBeckのベスト曲ばかりで、聴き飽きない。2005年の来日公演のときとベース以外はメンバーがおなじで、キーボードはJason Rebello、ドラムはカリウタ。ベースは、話題の女の子Tal Wilkenfeld。レベロのキーボードもいいのだが、一番耳が行くのはやはりカリウタ。いつもの彼に比べればおとなしいんだけど、そのおとなしさも含めてジェフ・ベックのギターに合っている。うまいなぁ。金物系が特にいい。ジェフのギターはもう言うことがありません。この世代ではピカイチですね。昔から何も変わってないのかもしれないけれども、機材の進化もあって、シャープさとサウンドの細やかさが増しています。ほんとに神がかり的。もともとあまり仕事をしないという評価が高かった(?)人ですが、21世紀に入ってからの仕事ぶりは信じられない。この録音は1週間ほど、ロニースコッツ・クラブで演奏をして収録したらしいが、来年DVDもでるらしいので、そちらも買っちゃうんだろうね。
Jeff Beck / Performing This Week : ジェフ・ベックのオフィシャル・ブートレグ・シリーズの第3弾。昨年のライブ。前の2作と違って、これは初めから発売することを念頭において録音されているようで、音質がかなりいい。オフィシャル・ブートレグというよりは、ライブ盤です。選曲も最近作の曲も含めてBeckのベスト曲ばかりで、聴き飽きない。2005年の来日公演のときとベース以外はメンバーがおなじで、キーボードはJason Rebello、ドラムはカリウタ。ベースは、話題の女の子Tal Wilkenfeld。レベロのキーボードもいいのだが、一番耳が行くのはやはりカリウタ。いつもの彼に比べればおとなしいんだけど、そのおとなしさも含めてジェフ・ベックのギターに合っている。うまいなぁ。金物系が特にいい。ジェフのギターはもう言うことがありません。この世代ではピカイチですね。昔から何も変わってないのかもしれないけれども、機材の進化もあって、シャープさとサウンドの細やかさが増しています。ほんとに神がかり的。もともとあまり仕事をしないという評価が高かった(?)人ですが、21世紀に入ってからの仕事ぶりは信じられない。この録音は1週間ほど、ロニースコッツ・クラブで演奏をして収録したらしいが、来年DVDもでるらしいので、そちらも買っちゃうんだろうね。Nov.24 CD : Phil Manzanera
 Phil Manzanera / Firebird V11 : フィル・マンザネラの新作。前回はラテン系だったので買わなかったのだが、今作はインストルメンタルばっかりのロックアルバム。空港でたまたま会ったCharles Haywardと共演する話が進み、アルバムにまでなったらしい。来年はこのメンバーでライブもあるようだ。この二人は学生時代の友達でQuiet Sunというバンドを組んでいた。1975年にマンザネラのファーストアルバム「Diamond Head」で共演をし、同時期にそのクワイエット・サンの曲を元のメンバー「メインストリーム」として録音している。内容は、予想以上にいい。今のクリアなマンザネラのギターの音で、カンタベリー系のようにじわじわと盛り上がる。耳はどうしてもギターとシャープなドラムに行ってしまうが、キーボードがいいアクセントになっていて、2曲目のようにピアノが印象的な場面も多い。1曲目の作曲者をよく見るとBill MacCormickになっているでの、昔の曲なのかもしれないが、これがいきなりいい。2曲目も後半、ベースがぐっと曲を引っ張るようにアップテンポになるところなどもかっこいい。3曲目はフリーっぽい感じからじわじわと盛り上がっていくSoft Machineみたいな曲。Enoっぽいヘイワードの掛け声もGood。Quiet Sunのアルバムよりインプロヴィゼーションっぽいところが少ないように感じる。8曲目はヘイワードの曲。確かにドラムトラックが先にできてそうな曲で、シンバルワークが決まっています。プログレ好きにはたまらないアルバム。
Phil Manzanera / Firebird V11 : フィル・マンザネラの新作。前回はラテン系だったので買わなかったのだが、今作はインストルメンタルばっかりのロックアルバム。空港でたまたま会ったCharles Haywardと共演する話が進み、アルバムにまでなったらしい。来年はこのメンバーでライブもあるようだ。この二人は学生時代の友達でQuiet Sunというバンドを組んでいた。1975年にマンザネラのファーストアルバム「Diamond Head」で共演をし、同時期にそのクワイエット・サンの曲を元のメンバー「メインストリーム」として録音している。内容は、予想以上にいい。今のクリアなマンザネラのギターの音で、カンタベリー系のようにじわじわと盛り上がる。耳はどうしてもギターとシャープなドラムに行ってしまうが、キーボードがいいアクセントになっていて、2曲目のようにピアノが印象的な場面も多い。1曲目の作曲者をよく見るとBill MacCormickになっているでの、昔の曲なのかもしれないが、これがいきなりいい。2曲目も後半、ベースがぐっと曲を引っ張るようにアップテンポになるところなどもかっこいい。3曲目はフリーっぽい感じからじわじわと盛り上がっていくSoft Machineみたいな曲。Enoっぽいヘイワードの掛け声もGood。Quiet Sunのアルバムよりインプロヴィゼーションっぽいところが少ないように感じる。8曲目はヘイワードの曲。確かにドラムトラックが先にできてそうな曲で、シンバルワークが決まっています。プログレ好きにはたまらないアルバム。
 Phil Manzanera / Firebird V11 : フィル・マンザネラの新作。前回はラテン系だったので買わなかったのだが、今作はインストルメンタルばっかりのロックアルバム。空港でたまたま会ったCharles Haywardと共演する話が進み、アルバムにまでなったらしい。来年はこのメンバーでライブもあるようだ。この二人は学生時代の友達でQuiet Sunというバンドを組んでいた。1975年にマンザネラのファーストアルバム「Diamond Head」で共演をし、同時期にそのクワイエット・サンの曲を元のメンバー「メインストリーム」として録音している。内容は、予想以上にいい。今のクリアなマンザネラのギターの音で、カンタベリー系のようにじわじわと盛り上がる。耳はどうしてもギターとシャープなドラムに行ってしまうが、キーボードがいいアクセントになっていて、2曲目のようにピアノが印象的な場面も多い。1曲目の作曲者をよく見るとBill MacCormickになっているでの、昔の曲なのかもしれないが、これがいきなりいい。2曲目も後半、ベースがぐっと曲を引っ張るようにアップテンポになるところなどもかっこいい。3曲目はフリーっぽい感じからじわじわと盛り上がっていくSoft Machineみたいな曲。Enoっぽいヘイワードの掛け声もGood。Quiet Sunのアルバムよりインプロヴィゼーションっぽいところが少ないように感じる。8曲目はヘイワードの曲。確かにドラムトラックが先にできてそうな曲で、シンバルワークが決まっています。プログレ好きにはたまらないアルバム。
Phil Manzanera / Firebird V11 : フィル・マンザネラの新作。前回はラテン系だったので買わなかったのだが、今作はインストルメンタルばっかりのロックアルバム。空港でたまたま会ったCharles Haywardと共演する話が進み、アルバムにまでなったらしい。来年はこのメンバーでライブもあるようだ。この二人は学生時代の友達でQuiet Sunというバンドを組んでいた。1975年にマンザネラのファーストアルバム「Diamond Head」で共演をし、同時期にそのクワイエット・サンの曲を元のメンバー「メインストリーム」として録音している。内容は、予想以上にいい。今のクリアなマンザネラのギターの音で、カンタベリー系のようにじわじわと盛り上がる。耳はどうしてもギターとシャープなドラムに行ってしまうが、キーボードがいいアクセントになっていて、2曲目のようにピアノが印象的な場面も多い。1曲目の作曲者をよく見るとBill MacCormickになっているでの、昔の曲なのかもしれないが、これがいきなりいい。2曲目も後半、ベースがぐっと曲を引っ張るようにアップテンポになるところなどもかっこいい。3曲目はフリーっぽい感じからじわじわと盛り上がっていくSoft Machineみたいな曲。Enoっぽいヘイワードの掛け声もGood。Quiet Sunのアルバムよりインプロヴィゼーションっぽいところが少ないように感じる。8曲目はヘイワードの曲。確かにドラムトラックが先にできてそうな曲で、シンバルワークが決まっています。プログレ好きにはたまらないアルバム。Nov.24 DVD : Eric Johnson
 Eric Johnson / Anaheim : こっそりと発売されていたエリック・ジョンソンのDVD。新しいアルバムもめったに出さないのに。メンバーは、Chris MareshとTommy Taylorととてもシンプル。収録は2006年5月。音質はいいが、DVカメラで収録したようで映像はイマイチ。本編が50分程度と非常に短い。おまけで、アコースティックツアーの曲が3曲収録されている。カバーを何曲か演奏しているが、セットリストはいつもと同じ。昔の映像に比べると、ちょっとだけライブパフォーマンスを意識したふるまいをしている気もするが、基本的には淡々と演奏をする素朴なステージ。巧いんだけど、昔に比べると、ここのフレーズの息がちょっと短くなったかな。ヴォーカルもさすがに衰えているし。機材や演奏は進化しているのかもしれないが、演奏している曲も演奏も基本的に変わらないので、衰えているところも目についちゃうのが残念だ。この前年、2005年10月に同じメンバーで来日していて、見に行ってるんだけど、おそろしいほど記憶にない。同時期のKeith Emersonは良いステージだった印象が残っているのに。よっぽど波長が合っていなかったのかな。
Eric Johnson / Anaheim : こっそりと発売されていたエリック・ジョンソンのDVD。新しいアルバムもめったに出さないのに。メンバーは、Chris MareshとTommy Taylorととてもシンプル。収録は2006年5月。音質はいいが、DVカメラで収録したようで映像はイマイチ。本編が50分程度と非常に短い。おまけで、アコースティックツアーの曲が3曲収録されている。カバーを何曲か演奏しているが、セットリストはいつもと同じ。昔の映像に比べると、ちょっとだけライブパフォーマンスを意識したふるまいをしている気もするが、基本的には淡々と演奏をする素朴なステージ。巧いんだけど、昔に比べると、ここのフレーズの息がちょっと短くなったかな。ヴォーカルもさすがに衰えているし。機材や演奏は進化しているのかもしれないが、演奏している曲も演奏も基本的に変わらないので、衰えているところも目についちゃうのが残念だ。この前年、2005年10月に同じメンバーで来日していて、見に行ってるんだけど、おそろしいほど記憶にない。同時期のKeith Emersonは良いステージだった印象が残っているのに。よっぽど波長が合っていなかったのかな。
 Eric Johnson / Anaheim : こっそりと発売されていたエリック・ジョンソンのDVD。新しいアルバムもめったに出さないのに。メンバーは、Chris MareshとTommy Taylorととてもシンプル。収録は2006年5月。音質はいいが、DVカメラで収録したようで映像はイマイチ。本編が50分程度と非常に短い。おまけで、アコースティックツアーの曲が3曲収録されている。カバーを何曲か演奏しているが、セットリストはいつもと同じ。昔の映像に比べると、ちょっとだけライブパフォーマンスを意識したふるまいをしている気もするが、基本的には淡々と演奏をする素朴なステージ。巧いんだけど、昔に比べると、ここのフレーズの息がちょっと短くなったかな。ヴォーカルもさすがに衰えているし。機材や演奏は進化しているのかもしれないが、演奏している曲も演奏も基本的に変わらないので、衰えているところも目についちゃうのが残念だ。この前年、2005年10月に同じメンバーで来日していて、見に行ってるんだけど、おそろしいほど記憶にない。同時期のKeith Emersonは良いステージだった印象が残っているのに。よっぽど波長が合っていなかったのかな。
Eric Johnson / Anaheim : こっそりと発売されていたエリック・ジョンソンのDVD。新しいアルバムもめったに出さないのに。メンバーは、Chris MareshとTommy Taylorととてもシンプル。収録は2006年5月。音質はいいが、DVカメラで収録したようで映像はイマイチ。本編が50分程度と非常に短い。おまけで、アコースティックツアーの曲が3曲収録されている。カバーを何曲か演奏しているが、セットリストはいつもと同じ。昔の映像に比べると、ちょっとだけライブパフォーマンスを意識したふるまいをしている気もするが、基本的には淡々と演奏をする素朴なステージ。巧いんだけど、昔に比べると、ここのフレーズの息がちょっと短くなったかな。ヴォーカルもさすがに衰えているし。機材や演奏は進化しているのかもしれないが、演奏している曲も演奏も基本的に変わらないので、衰えているところも目についちゃうのが残念だ。この前年、2005年10月に同じメンバーで来日していて、見に行ってるんだけど、おそろしいほど記憶にない。同時期のKeith Emersonは良いステージだった印象が残っているのに。よっぽど波長が合っていなかったのかな。Nov.23 CD : Queyras
 Queyras : Poulenc, Debussy / Cello Sonata : ジャン=ギアン・ケラスとアレクサンドル・タローのドビュッシーとプーランクのチェロ作品集。タローは時々気になっているピアニストなので試聴してみたら、チェロのほうも気に入ってしまった。一つのロングトーンの中で、表情をつけるのがとてもうまいチェリストのようだ。ロストロポーヴィッチのように力強さを出す弾き方も好きだが、あくまでヲサレに。しかし、軽くなりすぎず、鳴らすところは目いっぱい鳴らす。重音を引く時もぐっと弦を押さえ込まずに、濁らないとおとで軽く聞かせる。「レントより遅く」のテーマの歌い回しなんて、ほんとにイロケがある。ドビュッシーもよいが、録音のあまりないプーランクのチェロ・ソナタやフランス組曲なども楽しい。良いチェリストだな、と思ったら、パユ様のモーツァルトのフルート四重奏曲でもチェロを弾いていた。
Queyras : Poulenc, Debussy / Cello Sonata : ジャン=ギアン・ケラスとアレクサンドル・タローのドビュッシーとプーランクのチェロ作品集。タローは時々気になっているピアニストなので試聴してみたら、チェロのほうも気に入ってしまった。一つのロングトーンの中で、表情をつけるのがとてもうまいチェリストのようだ。ロストロポーヴィッチのように力強さを出す弾き方も好きだが、あくまでヲサレに。しかし、軽くなりすぎず、鳴らすところは目いっぱい鳴らす。重音を引く時もぐっと弦を押さえ込まずに、濁らないとおとで軽く聞かせる。「レントより遅く」のテーマの歌い回しなんて、ほんとにイロケがある。ドビュッシーもよいが、録音のあまりないプーランクのチェロ・ソナタやフランス組曲なども楽しい。良いチェリストだな、と思ったら、パユ様のモーツァルトのフルート四重奏曲でもチェロを弾いていた。
 Queyras : Poulenc, Debussy / Cello Sonata : ジャン=ギアン・ケラスとアレクサンドル・タローのドビュッシーとプーランクのチェロ作品集。タローは時々気になっているピアニストなので試聴してみたら、チェロのほうも気に入ってしまった。一つのロングトーンの中で、表情をつけるのがとてもうまいチェリストのようだ。ロストロポーヴィッチのように力強さを出す弾き方も好きだが、あくまでヲサレに。しかし、軽くなりすぎず、鳴らすところは目いっぱい鳴らす。重音を引く時もぐっと弦を押さえ込まずに、濁らないとおとで軽く聞かせる。「レントより遅く」のテーマの歌い回しなんて、ほんとにイロケがある。ドビュッシーもよいが、録音のあまりないプーランクのチェロ・ソナタやフランス組曲なども楽しい。良いチェリストだな、と思ったら、パユ様のモーツァルトのフルート四重奏曲でもチェロを弾いていた。
Queyras : Poulenc, Debussy / Cello Sonata : ジャン=ギアン・ケラスとアレクサンドル・タローのドビュッシーとプーランクのチェロ作品集。タローは時々気になっているピアニストなので試聴してみたら、チェロのほうも気に入ってしまった。一つのロングトーンの中で、表情をつけるのがとてもうまいチェリストのようだ。ロストロポーヴィッチのように力強さを出す弾き方も好きだが、あくまでヲサレに。しかし、軽くなりすぎず、鳴らすところは目いっぱい鳴らす。重音を引く時もぐっと弦を押さえ込まずに、濁らないとおとで軽く聞かせる。「レントより遅く」のテーマの歌い回しなんて、ほんとにイロケがある。ドビュッシーもよいが、録音のあまりないプーランクのチェロ・ソナタやフランス組曲なども楽しい。良いチェリストだな、と思ったら、パユ様のモーツァルトのフルート四重奏曲でもチェロを弾いていた。Nov.21 是巨人 + 内橋和久 @ 秋葉原 Goodman
幕張に用があったので、帰りに秋葉原でライブ。是巨人と内橋和久。到着したときには始まっていて、まず鬼怒無月+内橋和久。内橋はステージ下手でイスに着席。即興2曲。意外とアンビエントなサウンドが多く、内橋のギターカットの上に鬼怒がソロを弾く、という流れが多かったような。
次は、内橋和久+吉田達也。これはうって変わって、ハードコアな演奏。彼らのアルバムで聴けるような音。一気に5曲演奏して「まだ30分経ってない?」「もう一曲やる?」みたいな雰囲気でした。
是巨人は、DVD撮影ということで、鬼怒が緊張気味。1曲目のLebanonはめずらしく端正でソリッドな演奏。ここで吉田が新しく作ったという是巨人Tシャツにわざわざ着替える。続けて"Isotope"、"Nervecell"。ここから新曲S、Tと続くが、ナスノが疲れてきたのかMCが長くなってくる。昨日までPitInnでAlterd States3連続だったようで、シカゴのコピーの話など。MCで、「最後に内橋をいれてJacksonをする」と言うが、これがアンコールであることが判明し、あわてる。最後の「U」で、ナスノは完全に落ちちゃってるとろこがあったように見えた。DVD録り直してくださいとコメント。最後の"Poet And Peasant"は復活してましたが、ナスノは不本意そう。S、T、Uの3曲は聴くの2回目だけど、良い曲ですね。はやくアルバムで聴きたい。最後は、是巨人 + 内橋和久。即興で2セットだが、手堅い。アンコールが、ばらしたとおりジャクソン。内橋はリハをしていなかったようで、「キド、この曲のキーはになんや?」と聴く。鬼怒が「B…、タカナカみたいなところがB」。イントロ後の夏向けフュージョンみたいなところが高中正義ですか。内橋はキーまで訊いたくせに、エフェクトのみ一発勝負のような音をかぶせていただけでした。面白かった。
Nov.21 CD : Sanhedrin
 Sanhedrin / さあ真ん中だ どんな感じ : 灰野敬二、吉田達也、ナスノミツルのサンヘドリンのアルバム。どうやらライブ会場かネットでしか売っていないようだ。2007年のライブ録音。インプロヴィゼーション一発録音を編集したものだろう。ナスノと吉田のコンビのユニットは多いが、やはり灰野敬二のギターの凶暴さが耳につくユニットだ。一瞬の緩みもない。灰野に引っ張られるように、吉田もナスノもかっこいいフレーズを紡ぎだしている。とくにナスノさんのベースはいいな。
Sanhedrin / さあ真ん中だ どんな感じ : 灰野敬二、吉田達也、ナスノミツルのサンヘドリンのアルバム。どうやらライブ会場かネットでしか売っていないようだ。2007年のライブ録音。インプロヴィゼーション一発録音を編集したものだろう。ナスノと吉田のコンビのユニットは多いが、やはり灰野敬二のギターの凶暴さが耳につくユニットだ。一瞬の緩みもない。灰野に引っ張られるように、吉田もナスノもかっこいいフレーズを紡ぎだしている。とくにナスノさんのベースはいいな。
 Sanhedrin / さあ真ん中だ どんな感じ : 灰野敬二、吉田達也、ナスノミツルのサンヘドリンのアルバム。どうやらライブ会場かネットでしか売っていないようだ。2007年のライブ録音。インプロヴィゼーション一発録音を編集したものだろう。ナスノと吉田のコンビのユニットは多いが、やはり灰野敬二のギターの凶暴さが耳につくユニットだ。一瞬の緩みもない。灰野に引っ張られるように、吉田もナスノもかっこいいフレーズを紡ぎだしている。とくにナスノさんのベースはいいな。
Sanhedrin / さあ真ん中だ どんな感じ : 灰野敬二、吉田達也、ナスノミツルのサンヘドリンのアルバム。どうやらライブ会場かネットでしか売っていないようだ。2007年のライブ録音。インプロヴィゼーション一発録音を編集したものだろう。ナスノと吉田のコンビのユニットは多いが、やはり灰野敬二のギターの凶暴さが耳につくユニットだ。一瞬の緩みもない。灰野に引っ張られるように、吉田もナスノもかっこいいフレーズを紡ぎだしている。とくにナスノさんのベースはいいな。Nov.20 CD : David Byrne + Brian Eno
 David Byrne + Brian Eno / Everything that happen will happen today : デヴィッド・バーンとブライアン・イーノのコラボレーションアルバム。1か月も前から、オフィシャルサイトでは、ダウンロードで購入でき、おまけにストリームでは全曲試聴することができたが、CDでも発売になったので購入した。二十数年ぶりの共作で、二人名義のものは「My Life In The Bush Of Ghosts」以来となる。このアルバムが最近リマスターして発売されたのが、このアルバムの制作につながったらしい。「My Life〜」は、流行っていたダブと、Talking Headsが好んでいたアフリカっぽい原始的でミニマルなリズムが前面に出たインストアルバムで、リアルタイムでは体験していないけれども、当時もっともとんがっていたアルバムの一つだろう。洗練されていないクリムゾンみたいで、今聴いてもかっこいいアルバムだ。
しかし、このアルバムのメインは歌だ。イーノがインタビューでこのアルバムは現代のゴスペルだ、と言っていたが、フォークやポップな歌ばかりだ。曲はイーノが作りためていたもので、バーンが作詞したらしいが、サウンドはどこを切ってもイーノの作るポップ。最近では、「Another Day On Earth」がポップだったが、やはりイーノとジョン・ケールの「Wrong Way Up」を思い出してしまう。これらのアルバムが好きな人はこのアルバムもたまらなく好きだろう。ただ、あまりひねくれてはいなくて、このアルバムの歌はとても素朴だ。その素朴さを指してイーノは「ゴススペル」と言ってるのかもしれない。フィル・マンザネラやロバート・ワイアットがこっそり参加しているのも聴きどころか。
オフィシャルサイトでは、高音質で全曲聴くことができるうえ、ダウンロードで購入したものもDRMはかかっておらず、販売に関しても自主制作、という姿勢に彼らの今の業界に対する批判精神が出ていると思う。かっこいいおじさんたちだ。
David Byrne + Brian Eno / Everything that happen will happen today : デヴィッド・バーンとブライアン・イーノのコラボレーションアルバム。1か月も前から、オフィシャルサイトでは、ダウンロードで購入でき、おまけにストリームでは全曲試聴することができたが、CDでも発売になったので購入した。二十数年ぶりの共作で、二人名義のものは「My Life In The Bush Of Ghosts」以来となる。このアルバムが最近リマスターして発売されたのが、このアルバムの制作につながったらしい。「My Life〜」は、流行っていたダブと、Talking Headsが好んでいたアフリカっぽい原始的でミニマルなリズムが前面に出たインストアルバムで、リアルタイムでは体験していないけれども、当時もっともとんがっていたアルバムの一つだろう。洗練されていないクリムゾンみたいで、今聴いてもかっこいいアルバムだ。
しかし、このアルバムのメインは歌だ。イーノがインタビューでこのアルバムは現代のゴスペルだ、と言っていたが、フォークやポップな歌ばかりだ。曲はイーノが作りためていたもので、バーンが作詞したらしいが、サウンドはどこを切ってもイーノの作るポップ。最近では、「Another Day On Earth」がポップだったが、やはりイーノとジョン・ケールの「Wrong Way Up」を思い出してしまう。これらのアルバムが好きな人はこのアルバムもたまらなく好きだろう。ただ、あまりひねくれてはいなくて、このアルバムの歌はとても素朴だ。その素朴さを指してイーノは「ゴススペル」と言ってるのかもしれない。フィル・マンザネラやロバート・ワイアットがこっそり参加しているのも聴きどころか。
オフィシャルサイトでは、高音質で全曲聴くことができるうえ、ダウンロードで購入したものもDRMはかかっておらず、販売に関しても自主制作、という姿勢に彼らの今の業界に対する批判精神が出ていると思う。かっこいいおじさんたちだ。
 David Byrne + Brian Eno / Everything that happen will happen today : デヴィッド・バーンとブライアン・イーノのコラボレーションアルバム。1か月も前から、オフィシャルサイトでは、ダウンロードで購入でき、おまけにストリームでは全曲試聴することができたが、CDでも発売になったので購入した。二十数年ぶりの共作で、二人名義のものは「My Life In The Bush Of Ghosts」以来となる。このアルバムが最近リマスターして発売されたのが、このアルバムの制作につながったらしい。「My Life〜」は、流行っていたダブと、Talking Headsが好んでいたアフリカっぽい原始的でミニマルなリズムが前面に出たインストアルバムで、リアルタイムでは体験していないけれども、当時もっともとんがっていたアルバムの一つだろう。洗練されていないクリムゾンみたいで、今聴いてもかっこいいアルバムだ。
しかし、このアルバムのメインは歌だ。イーノがインタビューでこのアルバムは現代のゴスペルだ、と言っていたが、フォークやポップな歌ばかりだ。曲はイーノが作りためていたもので、バーンが作詞したらしいが、サウンドはどこを切ってもイーノの作るポップ。最近では、「Another Day On Earth」がポップだったが、やはりイーノとジョン・ケールの「Wrong Way Up」を思い出してしまう。これらのアルバムが好きな人はこのアルバムもたまらなく好きだろう。ただ、あまりひねくれてはいなくて、このアルバムの歌はとても素朴だ。その素朴さを指してイーノは「ゴススペル」と言ってるのかもしれない。フィル・マンザネラやロバート・ワイアットがこっそり参加しているのも聴きどころか。
オフィシャルサイトでは、高音質で全曲聴くことができるうえ、ダウンロードで購入したものもDRMはかかっておらず、販売に関しても自主制作、という姿勢に彼らの今の業界に対する批判精神が出ていると思う。かっこいいおじさんたちだ。
David Byrne + Brian Eno / Everything that happen will happen today : デヴィッド・バーンとブライアン・イーノのコラボレーションアルバム。1か月も前から、オフィシャルサイトでは、ダウンロードで購入でき、おまけにストリームでは全曲試聴することができたが、CDでも発売になったので購入した。二十数年ぶりの共作で、二人名義のものは「My Life In The Bush Of Ghosts」以来となる。このアルバムが最近リマスターして発売されたのが、このアルバムの制作につながったらしい。「My Life〜」は、流行っていたダブと、Talking Headsが好んでいたアフリカっぽい原始的でミニマルなリズムが前面に出たインストアルバムで、リアルタイムでは体験していないけれども、当時もっともとんがっていたアルバムの一つだろう。洗練されていないクリムゾンみたいで、今聴いてもかっこいいアルバムだ。
しかし、このアルバムのメインは歌だ。イーノがインタビューでこのアルバムは現代のゴスペルだ、と言っていたが、フォークやポップな歌ばかりだ。曲はイーノが作りためていたもので、バーンが作詞したらしいが、サウンドはどこを切ってもイーノの作るポップ。最近では、「Another Day On Earth」がポップだったが、やはりイーノとジョン・ケールの「Wrong Way Up」を思い出してしまう。これらのアルバムが好きな人はこのアルバムもたまらなく好きだろう。ただ、あまりひねくれてはいなくて、このアルバムの歌はとても素朴だ。その素朴さを指してイーノは「ゴススペル」と言ってるのかもしれない。フィル・マンザネラやロバート・ワイアットがこっそり参加しているのも聴きどころか。
オフィシャルサイトでは、高音質で全曲聴くことができるうえ、ダウンロードで購入したものもDRMはかかっておらず、販売に関しても自主制作、という姿勢に彼らの今の業界に対する批判精神が出ていると思う。かっこいいおじさんたちだ。
Nov.20 CD : Will Bernard
 Will Bernard / Blue Plate Special : タワレコでかかっていて、ハモンド・オルガンがかっこいいなあと思い、見てみるとジョン・メデスキが弾いていたので購入。ウィル・バーナードというギタリストのアルバム。何も知らない状態で購入。いわゆるジャム系なんですかね?他のメンバーは、スタントン・ムーアという人がドラムで、アンディ・ヘスという人がベース。お勉強不足でどちらの方も知りませんが、どちらもかっこいい音を出しています。たぶんジャム系では有名な人なんでしょうね。ギターは、ほとんどリフやカッティングかなのかなと思ってたのですが、4曲目の引っ掻いてぶっ壊れたようなソロとか、8曲目のソロとか巧いですね。
Will Bernard / Blue Plate Special : タワレコでかかっていて、ハモンド・オルガンがかっこいいなあと思い、見てみるとジョン・メデスキが弾いていたので購入。ウィル・バーナードというギタリストのアルバム。何も知らない状態で購入。いわゆるジャム系なんですかね?他のメンバーは、スタントン・ムーアという人がドラムで、アンディ・ヘスという人がベース。お勉強不足でどちらの方も知りませんが、どちらもかっこいい音を出しています。たぶんジャム系では有名な人なんでしょうね。ギターは、ほとんどリフやカッティングかなのかなと思ってたのですが、4曲目の引っ掻いてぶっ壊れたようなソロとか、8曲目のソロとか巧いですね。
 Will Bernard / Blue Plate Special : タワレコでかかっていて、ハモンド・オルガンがかっこいいなあと思い、見てみるとジョン・メデスキが弾いていたので購入。ウィル・バーナードというギタリストのアルバム。何も知らない状態で購入。いわゆるジャム系なんですかね?他のメンバーは、スタントン・ムーアという人がドラムで、アンディ・ヘスという人がベース。お勉強不足でどちらの方も知りませんが、どちらもかっこいい音を出しています。たぶんジャム系では有名な人なんでしょうね。ギターは、ほとんどリフやカッティングかなのかなと思ってたのですが、4曲目の引っ掻いてぶっ壊れたようなソロとか、8曲目のソロとか巧いですね。
Will Bernard / Blue Plate Special : タワレコでかかっていて、ハモンド・オルガンがかっこいいなあと思い、見てみるとジョン・メデスキが弾いていたので購入。ウィル・バーナードというギタリストのアルバム。何も知らない状態で購入。いわゆるジャム系なんですかね?他のメンバーは、スタントン・ムーアという人がドラムで、アンディ・ヘスという人がベース。お勉強不足でどちらの方も知りませんが、どちらもかっこいい音を出しています。たぶんジャム系では有名な人なんでしょうね。ギターは、ほとんどリフやカッティングかなのかなと思ってたのですが、4曲目の引っ掻いてぶっ壊れたようなソロとか、8曲目のソロとか巧いですね。Nov.20 CD : Herbert von Karajan
 Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1988 : カラヤンとベルリンフィルの、最後のイギリス公演のライブ録音。1988年10月5日、ロイヤル・フェスティバルホールでの演奏で、BBCによる収録。プログラムはシェーンベルクの浄夜と、ブラームスの交響曲第1番。シェーンベルクはとても色っぽい演奏で聴きやすい。カラヤンってこんな晩年に、これをプログラムに取り込んでいるとは。ブラ1は、この数ヶ月前の日本公演における演奏が、グラモフォンから発売されている(こちらはNHK収録)。解釈としてはあまり変わらないように感じるので、あとは録音から受ける印象のほうが大きいかもしれない。エコー多いのはホールのせいなんか、録音のせいなのか。ロイヤル・フェスティヴァル・ホールって、僕のイメージでは、けっこうNHKホールに近いけれども。ブラームスの遅いのだが、厚くてベルリンフィルのサウンド、とくに弦をたっぷり聴かせる演奏となっている。ここまで分厚い音は、とくに今ではなかなか聴けない音だ。第4楽章の推進力と流れの調和が素晴らしい。
Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1988 : カラヤンとベルリンフィルの、最後のイギリス公演のライブ録音。1988年10月5日、ロイヤル・フェスティバルホールでの演奏で、BBCによる収録。プログラムはシェーンベルクの浄夜と、ブラームスの交響曲第1番。シェーンベルクはとても色っぽい演奏で聴きやすい。カラヤンってこんな晩年に、これをプログラムに取り込んでいるとは。ブラ1は、この数ヶ月前の日本公演における演奏が、グラモフォンから発売されている(こちらはNHK収録)。解釈としてはあまり変わらないように感じるので、あとは録音から受ける印象のほうが大きいかもしれない。エコー多いのはホールのせいなんか、録音のせいなのか。ロイヤル・フェスティヴァル・ホールって、僕のイメージでは、けっこうNHKホールに近いけれども。ブラームスの遅いのだが、厚くてベルリンフィルのサウンド、とくに弦をたっぷり聴かせる演奏となっている。ここまで分厚い音は、とくに今ではなかなか聴けない音だ。第4楽章の推進力と流れの調和が素晴らしい。
 Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1988 : カラヤンとベルリンフィルの、最後のイギリス公演のライブ録音。1988年10月5日、ロイヤル・フェスティバルホールでの演奏で、BBCによる収録。プログラムはシェーンベルクの浄夜と、ブラームスの交響曲第1番。シェーンベルクはとても色っぽい演奏で聴きやすい。カラヤンってこんな晩年に、これをプログラムに取り込んでいるとは。ブラ1は、この数ヶ月前の日本公演における演奏が、グラモフォンから発売されている(こちらはNHK収録)。解釈としてはあまり変わらないように感じるので、あとは録音から受ける印象のほうが大きいかもしれない。エコー多いのはホールのせいなんか、録音のせいなのか。ロイヤル・フェスティヴァル・ホールって、僕のイメージでは、けっこうNHKホールに近いけれども。ブラームスの遅いのだが、厚くてベルリンフィルのサウンド、とくに弦をたっぷり聴かせる演奏となっている。ここまで分厚い音は、とくに今ではなかなか聴けない音だ。第4楽章の推進力と流れの調和が素晴らしい。
Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1988 : カラヤンとベルリンフィルの、最後のイギリス公演のライブ録音。1988年10月5日、ロイヤル・フェスティバルホールでの演奏で、BBCによる収録。プログラムはシェーンベルクの浄夜と、ブラームスの交響曲第1番。シェーンベルクはとても色っぽい演奏で聴きやすい。カラヤンってこんな晩年に、これをプログラムに取り込んでいるとは。ブラ1は、この数ヶ月前の日本公演における演奏が、グラモフォンから発売されている(こちらはNHK収録)。解釈としてはあまり変わらないように感じるので、あとは録音から受ける印象のほうが大きいかもしれない。エコー多いのはホールのせいなんか、録音のせいなのか。ロイヤル・フェスティヴァル・ホールって、僕のイメージでは、けっこうNHKホールに近いけれども。ブラームスの遅いのだが、厚くてベルリンフィルのサウンド、とくに弦をたっぷり聴かせる演奏となっている。ここまで分厚い音は、とくに今ではなかなか聴けない音だ。第4楽章の推進力と流れの調和が素晴らしい。Nov.20 CD : Mariss Jansons
 Mariss Jansons + Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : Haydn / Symphony No.100,104 : 時々SONYから出る、ヤンソンスとバイエルン放送響のコンビの最新録音。ハイドンの交響曲第100番、第104番、協奏交響曲。ヤンソンスとハイドンは合わないだろうなとおもったら、やっぱり気に入らなかった。個人的に、ハイドンはモーツァルトと同じで、スピード感、優雅さ、清潔感などが演奏から感じられた方がよく、節度のある色づけと、正確なリズム感と音の粒立ちのよさが必要だと思う。最近は、古楽器を使ったり、古楽器を意識した演奏が多く、そこが聴きどころにもなる。ラトルの演奏はベルリン・フィルのものもいいし、バーミンガム響との録音も面白い。そのような演奏でなく、編成の大きなオケでの古いタイプの演奏でも、カラヤンの録音のように素晴らしい演奏がたくさんある。80年代のパリ交響曲集なんてとても素晴らしいし、若いころのデッカに録音された104番の演奏も優雅でいい。ヨッフムのように編成の大きいオケで激しくつきすすむハイドンのスタイルもあるし、アダム・フィッシャーの全集で早い時期に録音されたものもウィーンや南ドイツ系の香りが少しする古いスタイルの演奏だ。オーセンティックな演奏を意識しているからいい演奏というわけではない、と思う。このヤンソンスの演奏も、大編成オケのスタイルをとっているが、清潔感も優雅さもスピード感もない。節度がなく、ロマンティックに崩しているところが多すぎ、品がなく感じられる。協奏交響曲のソロなどを聴いていると、バイエルン放送響の能力の高さが感じられて惜しくもある。オケのピッチも高めで、弦のきらびやかなサウンドがとてもいいのだが、スタイルが悪い。ティンパニの音を聴く限りではもしかしたら、木のマレットを使っているかもしれないが、ドカドカ鳴るだけで、スマートさやスピード感にはつながっていない。その妙な古楽器の利用に、センスが感じられず、ラトルのような演奏に対する意識も感じられない。ほんとに、この指揮者、褒めることが少なくて残念だ。
Mariss Jansons + Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : Haydn / Symphony No.100,104 : 時々SONYから出る、ヤンソンスとバイエルン放送響のコンビの最新録音。ハイドンの交響曲第100番、第104番、協奏交響曲。ヤンソンスとハイドンは合わないだろうなとおもったら、やっぱり気に入らなかった。個人的に、ハイドンはモーツァルトと同じで、スピード感、優雅さ、清潔感などが演奏から感じられた方がよく、節度のある色づけと、正確なリズム感と音の粒立ちのよさが必要だと思う。最近は、古楽器を使ったり、古楽器を意識した演奏が多く、そこが聴きどころにもなる。ラトルの演奏はベルリン・フィルのものもいいし、バーミンガム響との録音も面白い。そのような演奏でなく、編成の大きなオケでの古いタイプの演奏でも、カラヤンの録音のように素晴らしい演奏がたくさんある。80年代のパリ交響曲集なんてとても素晴らしいし、若いころのデッカに録音された104番の演奏も優雅でいい。ヨッフムのように編成の大きいオケで激しくつきすすむハイドンのスタイルもあるし、アダム・フィッシャーの全集で早い時期に録音されたものもウィーンや南ドイツ系の香りが少しする古いスタイルの演奏だ。オーセンティックな演奏を意識しているからいい演奏というわけではない、と思う。このヤンソンスの演奏も、大編成オケのスタイルをとっているが、清潔感も優雅さもスピード感もない。節度がなく、ロマンティックに崩しているところが多すぎ、品がなく感じられる。協奏交響曲のソロなどを聴いていると、バイエルン放送響の能力の高さが感じられて惜しくもある。オケのピッチも高めで、弦のきらびやかなサウンドがとてもいいのだが、スタイルが悪い。ティンパニの音を聴く限りではもしかしたら、木のマレットを使っているかもしれないが、ドカドカ鳴るだけで、スマートさやスピード感にはつながっていない。その妙な古楽器の利用に、センスが感じられず、ラトルのような演奏に対する意識も感じられない。ほんとに、この指揮者、褒めることが少なくて残念だ。
 Mariss Jansons + Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : Haydn / Symphony No.100,104 : 時々SONYから出る、ヤンソンスとバイエルン放送響のコンビの最新録音。ハイドンの交響曲第100番、第104番、協奏交響曲。ヤンソンスとハイドンは合わないだろうなとおもったら、やっぱり気に入らなかった。個人的に、ハイドンはモーツァルトと同じで、スピード感、優雅さ、清潔感などが演奏から感じられた方がよく、節度のある色づけと、正確なリズム感と音の粒立ちのよさが必要だと思う。最近は、古楽器を使ったり、古楽器を意識した演奏が多く、そこが聴きどころにもなる。ラトルの演奏はベルリン・フィルのものもいいし、バーミンガム響との録音も面白い。そのような演奏でなく、編成の大きなオケでの古いタイプの演奏でも、カラヤンの録音のように素晴らしい演奏がたくさんある。80年代のパリ交響曲集なんてとても素晴らしいし、若いころのデッカに録音された104番の演奏も優雅でいい。ヨッフムのように編成の大きいオケで激しくつきすすむハイドンのスタイルもあるし、アダム・フィッシャーの全集で早い時期に録音されたものもウィーンや南ドイツ系の香りが少しする古いスタイルの演奏だ。オーセンティックな演奏を意識しているからいい演奏というわけではない、と思う。このヤンソンスの演奏も、大編成オケのスタイルをとっているが、清潔感も優雅さもスピード感もない。節度がなく、ロマンティックに崩しているところが多すぎ、品がなく感じられる。協奏交響曲のソロなどを聴いていると、バイエルン放送響の能力の高さが感じられて惜しくもある。オケのピッチも高めで、弦のきらびやかなサウンドがとてもいいのだが、スタイルが悪い。ティンパニの音を聴く限りではもしかしたら、木のマレットを使っているかもしれないが、ドカドカ鳴るだけで、スマートさやスピード感にはつながっていない。その妙な古楽器の利用に、センスが感じられず、ラトルのような演奏に対する意識も感じられない。ほんとに、この指揮者、褒めることが少なくて残念だ。
Mariss Jansons + Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : Haydn / Symphony No.100,104 : 時々SONYから出る、ヤンソンスとバイエルン放送響のコンビの最新録音。ハイドンの交響曲第100番、第104番、協奏交響曲。ヤンソンスとハイドンは合わないだろうなとおもったら、やっぱり気に入らなかった。個人的に、ハイドンはモーツァルトと同じで、スピード感、優雅さ、清潔感などが演奏から感じられた方がよく、節度のある色づけと、正確なリズム感と音の粒立ちのよさが必要だと思う。最近は、古楽器を使ったり、古楽器を意識した演奏が多く、そこが聴きどころにもなる。ラトルの演奏はベルリン・フィルのものもいいし、バーミンガム響との録音も面白い。そのような演奏でなく、編成の大きなオケでの古いタイプの演奏でも、カラヤンの録音のように素晴らしい演奏がたくさんある。80年代のパリ交響曲集なんてとても素晴らしいし、若いころのデッカに録音された104番の演奏も優雅でいい。ヨッフムのように編成の大きいオケで激しくつきすすむハイドンのスタイルもあるし、アダム・フィッシャーの全集で早い時期に録音されたものもウィーンや南ドイツ系の香りが少しする古いスタイルの演奏だ。オーセンティックな演奏を意識しているからいい演奏というわけではない、と思う。このヤンソンスの演奏も、大編成オケのスタイルをとっているが、清潔感も優雅さもスピード感もない。節度がなく、ロマンティックに崩しているところが多すぎ、品がなく感じられる。協奏交響曲のソロなどを聴いていると、バイエルン放送響の能力の高さが感じられて惜しくもある。オケのピッチも高めで、弦のきらびやかなサウンドがとてもいいのだが、スタイルが悪い。ティンパニの音を聴く限りではもしかしたら、木のマレットを使っているかもしれないが、ドカドカ鳴るだけで、スマートさやスピード感にはつながっていない。その妙な古楽器の利用に、センスが感じられず、ラトルのような演奏に対する意識も感じられない。ほんとに、この指揮者、褒めることが少なくて残念だ。Nov.20 CD : Paavo Jarvi
 Paavo Jarvi : Mussorgsky / Pictures at an Exhibition : パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団の新譜。ムソルグスキー3曲で、「はげ山の一夜」「展覧会の絵」「ホヴァンシチーナ前奏曲」。好きかどうかは別として、どれも筋肉質で金属的でアメリカのオーケストラの機能的な演奏を楽しめる。オケの技術もヤルヴィのコントロールもすばらしいです。録音もいいし。「はげ山」が一番楽しめたかな。
Paavo Jarvi : Mussorgsky / Pictures at an Exhibition : パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団の新譜。ムソルグスキー3曲で、「はげ山の一夜」「展覧会の絵」「ホヴァンシチーナ前奏曲」。好きかどうかは別として、どれも筋肉質で金属的でアメリカのオーケストラの機能的な演奏を楽しめる。オケの技術もヤルヴィのコントロールもすばらしいです。録音もいいし。「はげ山」が一番楽しめたかな。
 Paavo Jarvi : Mussorgsky / Pictures at an Exhibition : パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団の新譜。ムソルグスキー3曲で、「はげ山の一夜」「展覧会の絵」「ホヴァンシチーナ前奏曲」。好きかどうかは別として、どれも筋肉質で金属的でアメリカのオーケストラの機能的な演奏を楽しめる。オケの技術もヤルヴィのコントロールもすばらしいです。録音もいいし。「はげ山」が一番楽しめたかな。
Paavo Jarvi : Mussorgsky / Pictures at an Exhibition : パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団の新譜。ムソルグスキー3曲で、「はげ山の一夜」「展覧会の絵」「ホヴァンシチーナ前奏曲」。好きかどうかは別として、どれも筋肉質で金属的でアメリカのオーケストラの機能的な演奏を楽しめる。オケの技術もヤルヴィのコントロールもすばらしいです。録音もいいし。「はげ山」が一番楽しめたかな。Nov.17 クリスタルガイザー
クリスタルガイザーというのはアメリカのミネラルウォーターで、会社の自販機にミネラルウォーターはこれしかない。僕は1日1.5リットルくらい水を飲むので、朝、コンビニで買わなかったときは、この水を飲むことになる。今朝も買おうと思ったら、どの自販機も水が売り切れ。どういうことかと思ったら、異臭がして回収ですか。この夏だけでも100本以上飲んでるんだと思うけどな…まあ、身体に影響がないそうなのでいいか。
Nov.16 DVD : Pierre Boulez
 Pierre Boulez + Mahler Chamber Orchestra / Patrice Chereau : Janacek / From the House of the Dead : ヤナーチェクのオペラ「死の家から」の映像。ヤナーチェクのオペラの映像は珍しく、しかも日本語字幕つきで発売されているし、ブーレーズの指揮だしということで購入した。話題の舞台だったし。ブーレーズが指揮で、演出がパトリス・シェロー。このコンビは、この演目をもって最後となるらしい。というか、ブーレーズがオペラを振るのがもうしんどいのではないだろうか?最近、オペラの新演出はお金がかかるので、複数のオペラハウスが共同で新演出を制作することが多いが、これもそう。収録は、2007年のエクサン・プロヴァンス音楽祭でのもの。オケはマーラー室内管弦楽団。この作品は初めて聴いたのだが、ぱっと聴いたら響きがドビュッシーみたいに聴こえる暗めのフランス音楽。そして、ショスタコーヴィッチまでもう少し、と感じる音楽。歌っているのはほとんど男。女声のパートもあるのだが、たった数小節で終わり。他の演奏は聴いたことがないが、オケの透明感のある響きと、ブーレーズの整理された指揮で、かなり聴きやすくなってるのではないかなと感じた。ブーレーズのライナーノートが、「ヤナーチェクなんて田舎のドヴォルザークだと思っていたが考えを改めた」とか、「振るのに難しいところがあって、ノイマンとマッケラスの録音も聴いてみたが、やっぱり苦労していた」とか非常に面白い。
演出としては、非常にまっとうな印象を受けた。ダムが出てきたりレーザーが飛び交ったりはしない。岩は落ちてきたけど。よく作りこまれた演出と舞台装置だと思う。手を抜いている感じが全くしない。
映像作品としても、カメラワークが凝っている。だいたいオペラの映像はステージ正面からのカメラショットばっかりなのだが、これは舞台袖からのハンディカメラの映像が多くつかわれいている。ステージを生で見に来ているお客さんには、袖でカメラがちらちら見えるので、普通はこういうカメラワークを嫌がると思うのだが、収録も込みで作品と考えているのかもしれない。
Pierre Boulez + Mahler Chamber Orchestra / Patrice Chereau : Janacek / From the House of the Dead : ヤナーチェクのオペラ「死の家から」の映像。ヤナーチェクのオペラの映像は珍しく、しかも日本語字幕つきで発売されているし、ブーレーズの指揮だしということで購入した。話題の舞台だったし。ブーレーズが指揮で、演出がパトリス・シェロー。このコンビは、この演目をもって最後となるらしい。というか、ブーレーズがオペラを振るのがもうしんどいのではないだろうか?最近、オペラの新演出はお金がかかるので、複数のオペラハウスが共同で新演出を制作することが多いが、これもそう。収録は、2007年のエクサン・プロヴァンス音楽祭でのもの。オケはマーラー室内管弦楽団。この作品は初めて聴いたのだが、ぱっと聴いたら響きがドビュッシーみたいに聴こえる暗めのフランス音楽。そして、ショスタコーヴィッチまでもう少し、と感じる音楽。歌っているのはほとんど男。女声のパートもあるのだが、たった数小節で終わり。他の演奏は聴いたことがないが、オケの透明感のある響きと、ブーレーズの整理された指揮で、かなり聴きやすくなってるのではないかなと感じた。ブーレーズのライナーノートが、「ヤナーチェクなんて田舎のドヴォルザークだと思っていたが考えを改めた」とか、「振るのに難しいところがあって、ノイマンとマッケラスの録音も聴いてみたが、やっぱり苦労していた」とか非常に面白い。
演出としては、非常にまっとうな印象を受けた。ダムが出てきたりレーザーが飛び交ったりはしない。岩は落ちてきたけど。よく作りこまれた演出と舞台装置だと思う。手を抜いている感じが全くしない。
映像作品としても、カメラワークが凝っている。だいたいオペラの映像はステージ正面からのカメラショットばっかりなのだが、これは舞台袖からのハンディカメラの映像が多くつかわれいている。ステージを生で見に来ているお客さんには、袖でカメラがちらちら見えるので、普通はこういうカメラワークを嫌がると思うのだが、収録も込みで作品と考えているのかもしれない。
 Pierre Boulez + Mahler Chamber Orchestra / Patrice Chereau : Janacek / From the House of the Dead : ヤナーチェクのオペラ「死の家から」の映像。ヤナーチェクのオペラの映像は珍しく、しかも日本語字幕つきで発売されているし、ブーレーズの指揮だしということで購入した。話題の舞台だったし。ブーレーズが指揮で、演出がパトリス・シェロー。このコンビは、この演目をもって最後となるらしい。というか、ブーレーズがオペラを振るのがもうしんどいのではないだろうか?最近、オペラの新演出はお金がかかるので、複数のオペラハウスが共同で新演出を制作することが多いが、これもそう。収録は、2007年のエクサン・プロヴァンス音楽祭でのもの。オケはマーラー室内管弦楽団。この作品は初めて聴いたのだが、ぱっと聴いたら響きがドビュッシーみたいに聴こえる暗めのフランス音楽。そして、ショスタコーヴィッチまでもう少し、と感じる音楽。歌っているのはほとんど男。女声のパートもあるのだが、たった数小節で終わり。他の演奏は聴いたことがないが、オケの透明感のある響きと、ブーレーズの整理された指揮で、かなり聴きやすくなってるのではないかなと感じた。ブーレーズのライナーノートが、「ヤナーチェクなんて田舎のドヴォルザークだと思っていたが考えを改めた」とか、「振るのに難しいところがあって、ノイマンとマッケラスの録音も聴いてみたが、やっぱり苦労していた」とか非常に面白い。
演出としては、非常にまっとうな印象を受けた。ダムが出てきたりレーザーが飛び交ったりはしない。岩は落ちてきたけど。よく作りこまれた演出と舞台装置だと思う。手を抜いている感じが全くしない。
映像作品としても、カメラワークが凝っている。だいたいオペラの映像はステージ正面からのカメラショットばっかりなのだが、これは舞台袖からのハンディカメラの映像が多くつかわれいている。ステージを生で見に来ているお客さんには、袖でカメラがちらちら見えるので、普通はこういうカメラワークを嫌がると思うのだが、収録も込みで作品と考えているのかもしれない。
Pierre Boulez + Mahler Chamber Orchestra / Patrice Chereau : Janacek / From the House of the Dead : ヤナーチェクのオペラ「死の家から」の映像。ヤナーチェクのオペラの映像は珍しく、しかも日本語字幕つきで発売されているし、ブーレーズの指揮だしということで購入した。話題の舞台だったし。ブーレーズが指揮で、演出がパトリス・シェロー。このコンビは、この演目をもって最後となるらしい。というか、ブーレーズがオペラを振るのがもうしんどいのではないだろうか?最近、オペラの新演出はお金がかかるので、複数のオペラハウスが共同で新演出を制作することが多いが、これもそう。収録は、2007年のエクサン・プロヴァンス音楽祭でのもの。オケはマーラー室内管弦楽団。この作品は初めて聴いたのだが、ぱっと聴いたら響きがドビュッシーみたいに聴こえる暗めのフランス音楽。そして、ショスタコーヴィッチまでもう少し、と感じる音楽。歌っているのはほとんど男。女声のパートもあるのだが、たった数小節で終わり。他の演奏は聴いたことがないが、オケの透明感のある響きと、ブーレーズの整理された指揮で、かなり聴きやすくなってるのではないかなと感じた。ブーレーズのライナーノートが、「ヤナーチェクなんて田舎のドヴォルザークだと思っていたが考えを改めた」とか、「振るのに難しいところがあって、ノイマンとマッケラスの録音も聴いてみたが、やっぱり苦労していた」とか非常に面白い。
演出としては、非常にまっとうな印象を受けた。ダムが出てきたりレーザーが飛び交ったりはしない。岩は落ちてきたけど。よく作りこまれた演出と舞台装置だと思う。手を抜いている感じが全くしない。
映像作品としても、カメラワークが凝っている。だいたいオペラの映像はステージ正面からのカメラショットばっかりなのだが、これは舞台袖からのハンディカメラの映像が多くつかわれいている。ステージを生で見に来ているお客さんには、袖でカメラがちらちら見えるので、普通はこういうカメラワークを嫌がると思うのだが、収録も込みで作品と考えているのかもしれない。Nov.15 岡田博美 @ 東京文化会館 小ホール
19時から東京文化会館の小ホールで岡田博美のコンサート「ふらんすplus」。前半がシューマンで、後半がフローラン・シュミット。まず、子供の情景。子供の情景は甘くならない加減がよく、とてもクリアで美しい。曲によって音色の違いがたくさん出せるところが素晴らしい。トロイメライみたいな有名曲を聴いて引きつけられてしまう。交響的練習曲は、とても音が大きくて力の入った演奏だった。テンポは速め。遺作の5曲はナシ。若い時のポリーニってこんな感じだったのだろうか。後半のフローラン・シュミットは「ちぎれた鎖」と「幻影」。どちらも録音がほしいほどいい演奏だった。「幻影」はオグドンの録音があるが、オグドンにくらべてリズミックで鮮明な演奏。オグドンの演奏はちょっとオドロオドロしすぎだ。アンコールはフォーレの「シチリアーノ」とシューマンの「予言の鳥」。いつも完璧な演奏だ。
Nov.15 巨匠ピカソ 愛と想像の軌跡 @ 新国立美術館
せっかく上野に行く用があるので、都美術館のフェルメール展を見ようかと思ったのだが、時間上の都合により、新国立美術館で「巨匠ピカソ 愛と想像の軌跡」を見ることにした。パリのピカソ美術館の改装のため、作品を世界中に回しているらしいが、この美術館のコレクションは、所蔵数が多いというのもあるのかもしれないが、しょっちゅう見ている気がする。調べてみると、03年9月に上野の森美術館で「ピカソクラシック」で180点、04年11月に東京都現代美術館で「ピカソ展−躰とエロス」、06年1月にベルリンの新ナショナルギャラリー(Neue Nationalgalerie)でピカソ展。これらすべてパリのピカソ美術館所蔵のコレクションで、「村の踊り」や「海辺を走る二人の女」など何回も見た。好きな絵だからいいんだけど。これらに加えて、04年9月に東郷青児でジャクリーヌコレクションを見ている。結構ピカソはたくさん見る機会があるのだ。
今回も170点と展示数が多い上に、オブジェが多い。これらの作品がほぼ年代順に並んでいるので、わかりやすい。「アヴィニヨンの娘たち」の習作がやたらとたくさんあるのだが、本物がないのがちょっと欲求不満にさせられる。キュービズムで「マンドリンを持つ男」、新古典では「肘掛け椅子に座るオルガの肖像」、「手紙を読む」あたりが良いかな。有名な絵だけど。「朝鮮の虐殺」を見たことがあったのかどうか記憶があやふや。オリジナル(?)である、プラド美術館のゴヤの「1808年5月3日、マドリード」と記憶が混ざってるのかも。
Nov.14 Marris Jansons + Royal Concertgebouw Orchestra @ 横浜みなとみらいホール
芸術の秋、食欲の秋。横浜までコンセルトヘボウを聴きに行ってきた。19時からみなとみらいホール。客は半分ちょっとしか入っていない。平日で都内でないのに値段設定高すぎなんでしょうね。S〜Bの席がガラガラ。今日のプログラムなら、20時からという時間設定にすればもっと客が入るかもしれないのに。ヤンソンスはこれまで5回聴いているが、コンセルトヘボウとの組合せは聴いたことがない。
- 05年12月:ウィーンでニューイヤーコンサート
- 06年3月:バイエルン放送響@ガスタイク、ポリーニとのブラームスの協奏曲2番、マーラーの5番
- 06年3月:バイエルン放送響@ヘラクレス、ヴェンゲーロフとのベートーヴェンの協奏曲、ブラームスの2番
- 06年4月:バイエルン放送響@ヘラクレス、ヴェルディのレクイエム
- 06年4月:バイエルン放送響@ガスタイク、バイエルン放送合唱団60周年コンサート
Nov.13 CD : Herbert von Karajan
 Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1985 : カラヤン + BPOの英国ツアーの録音。1985年4月で、場所はロイヤル・フェスティヴァル・ホール。曲はベートーヴェンの4番と英雄の生涯。BBCのライブ録音のようだが、音はとてもよく、右側から低弦のうなりなど、ベルリンフィルらしい響きが気持ちいい。85年は、グラモフォンのスタジオ録音と、それと同時期のDVDがあるが、この演奏はそれらにもまして生き生きとした何かがある。ライブ感なんだろうけど、このコンビのすばらしさがあってのことなんだろう。このように正規録音で出たことを喜ぶべきだ。
この演奏はこの曲の演奏の中でも格段にすばらしい記録だと思われる。英雄の戦いのところでテンポがかっくし落ちるのがちょっと気になるが。
Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1985 : カラヤン + BPOの英国ツアーの録音。1985年4月で、場所はロイヤル・フェスティヴァル・ホール。曲はベートーヴェンの4番と英雄の生涯。BBCのライブ録音のようだが、音はとてもよく、右側から低弦のうなりなど、ベルリンフィルらしい響きが気持ちいい。85年は、グラモフォンのスタジオ録音と、それと同時期のDVDがあるが、この演奏はそれらにもまして生き生きとした何かがある。ライブ感なんだろうけど、このコンビのすばらしさがあってのことなんだろう。このように正規録音で出たことを喜ぶべきだ。
この演奏はこの曲の演奏の中でも格段にすばらしい記録だと思われる。英雄の戦いのところでテンポがかっくし落ちるのがちょっと気になるが。
 Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1985 : カラヤン + BPOの英国ツアーの録音。1985年4月で、場所はロイヤル・フェスティヴァル・ホール。曲はベートーヴェンの4番と英雄の生涯。BBCのライブ録音のようだが、音はとてもよく、右側から低弦のうなりなど、ベルリンフィルらしい響きが気持ちいい。85年は、グラモフォンのスタジオ録音と、それと同時期のDVDがあるが、この演奏はそれらにもまして生き生きとした何かがある。ライブ感なんだろうけど、このコンビのすばらしさがあってのことなんだろう。このように正規録音で出たことを喜ぶべきだ。
この演奏はこの曲の演奏の中でも格段にすばらしい記録だと思われる。英雄の戦いのところでテンポがかっくし落ちるのがちょっと気になるが。
Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1985 : カラヤン + BPOの英国ツアーの録音。1985年4月で、場所はロイヤル・フェスティヴァル・ホール。曲はベートーヴェンの4番と英雄の生涯。BBCのライブ録音のようだが、音はとてもよく、右側から低弦のうなりなど、ベルリンフィルらしい響きが気持ちいい。85年は、グラモフォンのスタジオ録音と、それと同時期のDVDがあるが、この演奏はそれらにもまして生き生きとした何かがある。ライブ感なんだろうけど、このコンビのすばらしさがあってのことなんだろう。このように正規録音で出たことを喜ぶべきだ。
この演奏はこの曲の演奏の中でも格段にすばらしい記録だと思われる。英雄の戦いのところでテンポがかっくし落ちるのがちょっと気になるが。Nov.13 CD : Natalie Dessay
 Natalie Dessay : Bach / Cantatas : ナタリー・デセイが歌うバッハのカンタータ集。取り上げられているのは、BWV51、BWV82a、BWV199の3曲。バックにつけるのは、ヘンデルのイタリア語カンタータ集と同じく、エマニュエル・アイムとル・コンセール・ダストレエ。バッハのカンタータというと厳粛な演奏になりがちだが、このアルバムはそういう印象がほとんどない。上品で適度な派手さを持っている。演奏しているのがゲルマン系ではないというのもあるのかもしれない。特にBWV51では、ソロで吹きまくるトランペットとあいまって派手さが増す。どの曲も、テクニック的に難しいんだろうけど、下品にならずに、やわらかく歌いきるのが良い。
Natalie Dessay : Bach / Cantatas : ナタリー・デセイが歌うバッハのカンタータ集。取り上げられているのは、BWV51、BWV82a、BWV199の3曲。バックにつけるのは、ヘンデルのイタリア語カンタータ集と同じく、エマニュエル・アイムとル・コンセール・ダストレエ。バッハのカンタータというと厳粛な演奏になりがちだが、このアルバムはそういう印象がほとんどない。上品で適度な派手さを持っている。演奏しているのがゲルマン系ではないというのもあるのかもしれない。特にBWV51では、ソロで吹きまくるトランペットとあいまって派手さが増す。どの曲も、テクニック的に難しいんだろうけど、下品にならずに、やわらかく歌いきるのが良い。
 Natalie Dessay : Bach / Cantatas : ナタリー・デセイが歌うバッハのカンタータ集。取り上げられているのは、BWV51、BWV82a、BWV199の3曲。バックにつけるのは、ヘンデルのイタリア語カンタータ集と同じく、エマニュエル・アイムとル・コンセール・ダストレエ。バッハのカンタータというと厳粛な演奏になりがちだが、このアルバムはそういう印象がほとんどない。上品で適度な派手さを持っている。演奏しているのがゲルマン系ではないというのもあるのかもしれない。特にBWV51では、ソロで吹きまくるトランペットとあいまって派手さが増す。どの曲も、テクニック的に難しいんだろうけど、下品にならずに、やわらかく歌いきるのが良い。
Natalie Dessay : Bach / Cantatas : ナタリー・デセイが歌うバッハのカンタータ集。取り上げられているのは、BWV51、BWV82a、BWV199の3曲。バックにつけるのは、ヘンデルのイタリア語カンタータ集と同じく、エマニュエル・アイムとル・コンセール・ダストレエ。バッハのカンタータというと厳粛な演奏になりがちだが、このアルバムはそういう印象がほとんどない。上品で適度な派手さを持っている。演奏しているのがゲルマン系ではないというのもあるのかもしれない。特にBWV51では、ソロで吹きまくるトランペットとあいまって派手さが増す。どの曲も、テクニック的に難しいんだろうけど、下品にならずに、やわらかく歌いきるのが良い。Nov.09 CD : Fabio Luisi
 Fabio Luisi + Staatskapelle Dresden : Bruckner / Symphony No.9 : ファビオ・ルイージとシュターツカペレ・ドレスデンの新譜はブルックナーの9番。これまでこのコンビの録音はR.シュトラウスばっかりだったが、やっと異なる作曲家の録音が登場した。全体的な印象としては、オケが良く鳴っている。ときにはうるさいくらい。ライブ録音のせいもあるのか、第1主題の最後など、きっちり揃っていないところも多くみられる。しかし、ルイージは精密さを犠牲にしてでも大きく鳴らしたいという方を優先してるようだ。このオケのサウンドを評して「燻し銀のような」なんていうインチキな表現を使うことが多いが(いぶし銀のような、という言葉は色や音色を表現する言葉ではない…)、その言葉が表現したいのであろう旧東ドイツ時代の録音で聴けるような枯れた木管のサウンドは、すでにこのオケにはない。ベルリンフィルのような分厚さやウィーンフィルのような派手な弦のサウンドとは違う、ドレスデンらしい弦の音はあるのだが、ドイツが統合したせいなのか時代のせいなのか、金管も木管も音が断然明るくなっている。この曲で聴くとそれがよく感じられる。
個人的な好みでいえば、9番はもっとストイックに、バッハのオルガン曲のように演奏してほしい。ルイージの演奏は小細工が少ないのはいいのだが、歌いすぎたり鳴らしすぎたり色気があったりする部分が多いかな。視点を変えれば、イタリア人でオペラが得意なルイージのカラーに、このオケが合わせているということになるんだろうけど。ルイージが得意なマーラーも聴いてみたいものだ。
Fabio Luisi + Staatskapelle Dresden : Bruckner / Symphony No.9 : ファビオ・ルイージとシュターツカペレ・ドレスデンの新譜はブルックナーの9番。これまでこのコンビの録音はR.シュトラウスばっかりだったが、やっと異なる作曲家の録音が登場した。全体的な印象としては、オケが良く鳴っている。ときにはうるさいくらい。ライブ録音のせいもあるのか、第1主題の最後など、きっちり揃っていないところも多くみられる。しかし、ルイージは精密さを犠牲にしてでも大きく鳴らしたいという方を優先してるようだ。このオケのサウンドを評して「燻し銀のような」なんていうインチキな表現を使うことが多いが(いぶし銀のような、という言葉は色や音色を表現する言葉ではない…)、その言葉が表現したいのであろう旧東ドイツ時代の録音で聴けるような枯れた木管のサウンドは、すでにこのオケにはない。ベルリンフィルのような分厚さやウィーンフィルのような派手な弦のサウンドとは違う、ドレスデンらしい弦の音はあるのだが、ドイツが統合したせいなのか時代のせいなのか、金管も木管も音が断然明るくなっている。この曲で聴くとそれがよく感じられる。
個人的な好みでいえば、9番はもっとストイックに、バッハのオルガン曲のように演奏してほしい。ルイージの演奏は小細工が少ないのはいいのだが、歌いすぎたり鳴らしすぎたり色気があったりする部分が多いかな。視点を変えれば、イタリア人でオペラが得意なルイージのカラーに、このオケが合わせているということになるんだろうけど。ルイージが得意なマーラーも聴いてみたいものだ。
 Fabio Luisi + Staatskapelle Dresden : Bruckner / Symphony No.9 : ファビオ・ルイージとシュターツカペレ・ドレスデンの新譜はブルックナーの9番。これまでこのコンビの録音はR.シュトラウスばっかりだったが、やっと異なる作曲家の録音が登場した。全体的な印象としては、オケが良く鳴っている。ときにはうるさいくらい。ライブ録音のせいもあるのか、第1主題の最後など、きっちり揃っていないところも多くみられる。しかし、ルイージは精密さを犠牲にしてでも大きく鳴らしたいという方を優先してるようだ。このオケのサウンドを評して「燻し銀のような」なんていうインチキな表現を使うことが多いが(いぶし銀のような、という言葉は色や音色を表現する言葉ではない…)、その言葉が表現したいのであろう旧東ドイツ時代の録音で聴けるような枯れた木管のサウンドは、すでにこのオケにはない。ベルリンフィルのような分厚さやウィーンフィルのような派手な弦のサウンドとは違う、ドレスデンらしい弦の音はあるのだが、ドイツが統合したせいなのか時代のせいなのか、金管も木管も音が断然明るくなっている。この曲で聴くとそれがよく感じられる。
個人的な好みでいえば、9番はもっとストイックに、バッハのオルガン曲のように演奏してほしい。ルイージの演奏は小細工が少ないのはいいのだが、歌いすぎたり鳴らしすぎたり色気があったりする部分が多いかな。視点を変えれば、イタリア人でオペラが得意なルイージのカラーに、このオケが合わせているということになるんだろうけど。ルイージが得意なマーラーも聴いてみたいものだ。
Fabio Luisi + Staatskapelle Dresden : Bruckner / Symphony No.9 : ファビオ・ルイージとシュターツカペレ・ドレスデンの新譜はブルックナーの9番。これまでこのコンビの録音はR.シュトラウスばっかりだったが、やっと異なる作曲家の録音が登場した。全体的な印象としては、オケが良く鳴っている。ときにはうるさいくらい。ライブ録音のせいもあるのか、第1主題の最後など、きっちり揃っていないところも多くみられる。しかし、ルイージは精密さを犠牲にしてでも大きく鳴らしたいという方を優先してるようだ。このオケのサウンドを評して「燻し銀のような」なんていうインチキな表現を使うことが多いが(いぶし銀のような、という言葉は色や音色を表現する言葉ではない…)、その言葉が表現したいのであろう旧東ドイツ時代の録音で聴けるような枯れた木管のサウンドは、すでにこのオケにはない。ベルリンフィルのような分厚さやウィーンフィルのような派手な弦のサウンドとは違う、ドレスデンらしい弦の音はあるのだが、ドイツが統合したせいなのか時代のせいなのか、金管も木管も音が断然明るくなっている。この曲で聴くとそれがよく感じられる。
個人的な好みでいえば、9番はもっとストイックに、バッハのオルガン曲のように演奏してほしい。ルイージの演奏は小細工が少ないのはいいのだが、歌いすぎたり鳴らしすぎたり色気があったりする部分が多いかな。視点を変えれば、イタリア人でオペラが得意なルイージのカラーに、このオケが合わせているということになるんだろうけど。ルイージが得意なマーラーも聴いてみたいものだ。Nov.08 Minetti Quartett @ 町田 Art Space O
ミネッティ弦楽四重奏団というカルテットのライブに行ってきた。決め手はズバリ見た目です。オフィシャルサイトを参照。Violinの2人がとても美人で、チェロがイタリア系の堀の深い顔。Violaがアーリア系。1st Vnがヨーロッパ系美人で、2nd Vnはアジア系の美人。ぱっと見ると、1stの方のほうに目が行くが、じっくり見るとセカンドの方が日本人受けする美人かな。会場は、町田のArt Space Oというところ。これが、陶芸品を売っている店の2階にあるスタジオのようなところ。らせん階段を上っていかないといけない場所で、あまり老人向けではない。客は60人くらいいて、常連客みたいな方が多かった。
まずハイドンの74番(op.74-3、騎士)。これの音が響かない。はじめは、ホールのせいかなと思った。演奏としてはテンポが速めの突っ込んだ演奏。チェロがリーダーシップをとっているようで、やたらとアイコンタクトを取っている。メンバー全員、技術的にはとてもうまい。ただ、1stヴァイオリンは体調が悪いようで、時々ミスやピッチの不安定な音を弾いてしまう。雰囲気としては、若い時のAlban Berg Qや、Artis Qを思い浮かべてもらえばいい感じ。Hagen QやArtemis Qのように低音、特にチェロ強調型のバランス。
2曲目はベルクの弦楽四重奏曲。この曲になったとたん、ホールが変わったのかと思うほど艶っぽい弦の音が。Haydnはピリオドも考慮してか、ビブラート少なめで演奏していたようです。第2楽章に入ってしばらくしたところで、チェロの弦が切れてしまう。ふつうはこういうことがあると熱くなるパターンが多いのだが、逆に抑制がかかってしまったかように聴こえた。大人だ…。この曲だけは、1st vnがリードを取っていたようにも聴こえた。
後半はベートーヴェンの10番。これはBergとおなじ艶っぽい音で、切れ味が鋭い。テクニックは安定しているが、演奏はアグレッシブと、若くないとできない演奏でした。
アンコールは、2nd Vnのお姉さんが日本語で「こんにちは、アンコールはハイドン、74番」と日本語で案内。ハイドンの74番の4楽章をもう一度。これはいいカルテットだ。MozartもHaydnももっと聴いてみたい。再来日と録音を期待します。
Nov.03 CD : Annette Dasch
 Annette Dasch : Mozart / Arias : アネッテ・ダッシュのモーツァルト・アリア集。SONYから発売されているのだが、あまり見かけないので、ドイツローカル限定かもしれない。実は、アネッテ・ダッシュは生で2回聴いていて、ミュンヘンで「魔笛」のパミーナ、昨年のベルリン州立歌劇場の来日公演の「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを聴いている。今気づいたが、どちらもモーツァルトだ。「ドン・ジョヴァンニ」のときは声が細いように感じたが、このアルバムを通して聴いみて、やっぱり高い音がちょっと安定していないように感じた。ドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナのアリア"Non mi dir, bell'idol mio"などを聴くとそう思ってしまう。メゾ・ソプラノの音域のアリアは安心して楽しめる。つけているオーケストラは、Harmonia Mundiから出ているバロック・アリア集と同じく、Akademie fuer Alte Musik Berlin (ベルリン古楽アカデミー)。木管の音が渋くていい。
Annette Dasch : Mozart / Arias : アネッテ・ダッシュのモーツァルト・アリア集。SONYから発売されているのだが、あまり見かけないので、ドイツローカル限定かもしれない。実は、アネッテ・ダッシュは生で2回聴いていて、ミュンヘンで「魔笛」のパミーナ、昨年のベルリン州立歌劇場の来日公演の「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを聴いている。今気づいたが、どちらもモーツァルトだ。「ドン・ジョヴァンニ」のときは声が細いように感じたが、このアルバムを通して聴いみて、やっぱり高い音がちょっと安定していないように感じた。ドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナのアリア"Non mi dir, bell'idol mio"などを聴くとそう思ってしまう。メゾ・ソプラノの音域のアリアは安心して楽しめる。つけているオーケストラは、Harmonia Mundiから出ているバロック・アリア集と同じく、Akademie fuer Alte Musik Berlin (ベルリン古楽アカデミー)。木管の音が渋くていい。
 Annette Dasch : Mozart / Arias : アネッテ・ダッシュのモーツァルト・アリア集。SONYから発売されているのだが、あまり見かけないので、ドイツローカル限定かもしれない。実は、アネッテ・ダッシュは生で2回聴いていて、ミュンヘンで「魔笛」のパミーナ、昨年のベルリン州立歌劇場の来日公演の「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを聴いている。今気づいたが、どちらもモーツァルトだ。「ドン・ジョヴァンニ」のときは声が細いように感じたが、このアルバムを通して聴いみて、やっぱり高い音がちょっと安定していないように感じた。ドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナのアリア"Non mi dir, bell'idol mio"などを聴くとそう思ってしまう。メゾ・ソプラノの音域のアリアは安心して楽しめる。つけているオーケストラは、Harmonia Mundiから出ているバロック・アリア集と同じく、Akademie fuer Alte Musik Berlin (ベルリン古楽アカデミー)。木管の音が渋くていい。
Annette Dasch : Mozart / Arias : アネッテ・ダッシュのモーツァルト・アリア集。SONYから発売されているのだが、あまり見かけないので、ドイツローカル限定かもしれない。実は、アネッテ・ダッシュは生で2回聴いていて、ミュンヘンで「魔笛」のパミーナ、昨年のベルリン州立歌劇場の来日公演の「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを聴いている。今気づいたが、どちらもモーツァルトだ。「ドン・ジョヴァンニ」のときは声が細いように感じたが、このアルバムを通して聴いみて、やっぱり高い音がちょっと安定していないように感じた。ドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナのアリア"Non mi dir, bell'idol mio"などを聴くとそう思ってしまう。メゾ・ソプラノの音域のアリアは安心して楽しめる。つけているオーケストラは、Harmonia Mundiから出ているバロック・アリア集と同じく、Akademie fuer Alte Musik Berlin (ベルリン古楽アカデミー)。木管の音が渋くていい。Nov.04 CD : Garaj Mahal
 Garaj Mahal / Woot : タワレコで試聴して購入。ジャム系らしい。マクラフリンの音楽でよくあるような、インド系のメロディやリフがよく現れるジャズ・ロックです。メンバーは、Tony Levinの参加したソロアルバムでアコースティックギターばっかりなので、このような音楽が演奏できるとは知らなかったFareed Haqueがギター。キーボードはEric Levyという人で、ドラムがAlan Hertz。ベースが、マクラフリンとトリロク・グルトゥとトリオを組んでいたKai Eckhardt。マクラフリンっぽさといい、この人のベースが前面に出ているところといい、彼がリーダーなのかもしれない。アルバムを通して、ベースがかっこいい。もうそれだけです。スラップではないんだけど、跳ねるようなベースが、ベース好きにはたまりません。5曲目など、変拍子のキメがぱしっと決まる曲(Kaiが書いている)などでとくにそれを感じます。ドラムもシャープでかなり巧い。ジャムな雰囲気で全部通すわけではなく、各メンバーがアコースティックにも持ちかえたりして、飽きないように作られている。他のアルバムにも興味が出てきた。2曲目のベースのリフが、Date Course Pentagon Royal Gardenの"Hey Joe"の冒頭のリフに似ているんですが、何か有名なリフだったりするのだろうか。
Garaj Mahal / Woot : タワレコで試聴して購入。ジャム系らしい。マクラフリンの音楽でよくあるような、インド系のメロディやリフがよく現れるジャズ・ロックです。メンバーは、Tony Levinの参加したソロアルバムでアコースティックギターばっかりなので、このような音楽が演奏できるとは知らなかったFareed Haqueがギター。キーボードはEric Levyという人で、ドラムがAlan Hertz。ベースが、マクラフリンとトリロク・グルトゥとトリオを組んでいたKai Eckhardt。マクラフリンっぽさといい、この人のベースが前面に出ているところといい、彼がリーダーなのかもしれない。アルバムを通して、ベースがかっこいい。もうそれだけです。スラップではないんだけど、跳ねるようなベースが、ベース好きにはたまりません。5曲目など、変拍子のキメがぱしっと決まる曲(Kaiが書いている)などでとくにそれを感じます。ドラムもシャープでかなり巧い。ジャムな雰囲気で全部通すわけではなく、各メンバーがアコースティックにも持ちかえたりして、飽きないように作られている。他のアルバムにも興味が出てきた。2曲目のベースのリフが、Date Course Pentagon Royal Gardenの"Hey Joe"の冒頭のリフに似ているんですが、何か有名なリフだったりするのだろうか。
 Garaj Mahal / Woot : タワレコで試聴して購入。ジャム系らしい。マクラフリンの音楽でよくあるような、インド系のメロディやリフがよく現れるジャズ・ロックです。メンバーは、Tony Levinの参加したソロアルバムでアコースティックギターばっかりなので、このような音楽が演奏できるとは知らなかったFareed Haqueがギター。キーボードはEric Levyという人で、ドラムがAlan Hertz。ベースが、マクラフリンとトリロク・グルトゥとトリオを組んでいたKai Eckhardt。マクラフリンっぽさといい、この人のベースが前面に出ているところといい、彼がリーダーなのかもしれない。アルバムを通して、ベースがかっこいい。もうそれだけです。スラップではないんだけど、跳ねるようなベースが、ベース好きにはたまりません。5曲目など、変拍子のキメがぱしっと決まる曲(Kaiが書いている)などでとくにそれを感じます。ドラムもシャープでかなり巧い。ジャムな雰囲気で全部通すわけではなく、各メンバーがアコースティックにも持ちかえたりして、飽きないように作られている。他のアルバムにも興味が出てきた。2曲目のベースのリフが、Date Course Pentagon Royal Gardenの"Hey Joe"の冒頭のリフに似ているんですが、何か有名なリフだったりするのだろうか。
Garaj Mahal / Woot : タワレコで試聴して購入。ジャム系らしい。マクラフリンの音楽でよくあるような、インド系のメロディやリフがよく現れるジャズ・ロックです。メンバーは、Tony Levinの参加したソロアルバムでアコースティックギターばっかりなので、このような音楽が演奏できるとは知らなかったFareed Haqueがギター。キーボードはEric Levyという人で、ドラムがAlan Hertz。ベースが、マクラフリンとトリロク・グルトゥとトリオを組んでいたKai Eckhardt。マクラフリンっぽさといい、この人のベースが前面に出ているところといい、彼がリーダーなのかもしれない。アルバムを通して、ベースがかっこいい。もうそれだけです。スラップではないんだけど、跳ねるようなベースが、ベース好きにはたまりません。5曲目など、変拍子のキメがぱしっと決まる曲(Kaiが書いている)などでとくにそれを感じます。ドラムもシャープでかなり巧い。ジャムな雰囲気で全部通すわけではなく、各メンバーがアコースティックにも持ちかえたりして、飽きないように作られている。他のアルバムにも興味が出てきた。2曲目のベースのリフが、Date Course Pentagon Royal Gardenの"Hey Joe"の冒頭のリフに似ているんですが、何か有名なリフだったりするのだろうか。Nov.04 CD : Squarepusher
 Squarepusher / Just a Souvenier : スクエアプッシャーの新譜。11枚目だそうだ。大学生のころに出たデビュー作から、人から借りたり試聴したりしてなんとなく聴いてはいるのだが、買ったのはこれが初めて。買った理由はブレイクビーツというよりはロックに聴こえたから。1曲目からテクノ・ポップに激しいベースが乗っている変な曲。良く聴くとロックというよりはテクノポップ。アンビエントな曲とのバランスがいい。4曲目はDEVOのようなテクノポップ。ところが、5曲目は一転してRUINSになっている。吉田達也+スクエアプッシャーってちょっとだけ面白そう。8曲目もRUINSっぽいなと思っていたら、スペースロック。思い出波止場っぽい。このアルバムは、そういうテクノ+ベース一直線というよりは、テクノポップやプログレ、アンビエント、ロックぽいところが雑多に混じってるところが良い。
Squarepusher / Just a Souvenier : スクエアプッシャーの新譜。11枚目だそうだ。大学生のころに出たデビュー作から、人から借りたり試聴したりしてなんとなく聴いてはいるのだが、買ったのはこれが初めて。買った理由はブレイクビーツというよりはロックに聴こえたから。1曲目からテクノ・ポップに激しいベースが乗っている変な曲。良く聴くとロックというよりはテクノポップ。アンビエントな曲とのバランスがいい。4曲目はDEVOのようなテクノポップ。ところが、5曲目は一転してRUINSになっている。吉田達也+スクエアプッシャーってちょっとだけ面白そう。8曲目もRUINSっぽいなと思っていたら、スペースロック。思い出波止場っぽい。このアルバムは、そういうテクノ+ベース一直線というよりは、テクノポップやプログレ、アンビエント、ロックぽいところが雑多に混じってるところが良い。
 Squarepusher / Just a Souvenier : スクエアプッシャーの新譜。11枚目だそうだ。大学生のころに出たデビュー作から、人から借りたり試聴したりしてなんとなく聴いてはいるのだが、買ったのはこれが初めて。買った理由はブレイクビーツというよりはロックに聴こえたから。1曲目からテクノ・ポップに激しいベースが乗っている変な曲。良く聴くとロックというよりはテクノポップ。アンビエントな曲とのバランスがいい。4曲目はDEVOのようなテクノポップ。ところが、5曲目は一転してRUINSになっている。吉田達也+スクエアプッシャーってちょっとだけ面白そう。8曲目もRUINSっぽいなと思っていたら、スペースロック。思い出波止場っぽい。このアルバムは、そういうテクノ+ベース一直線というよりは、テクノポップやプログレ、アンビエント、ロックぽいところが雑多に混じってるところが良い。
Squarepusher / Just a Souvenier : スクエアプッシャーの新譜。11枚目だそうだ。大学生のころに出たデビュー作から、人から借りたり試聴したりしてなんとなく聴いてはいるのだが、買ったのはこれが初めて。買った理由はブレイクビーツというよりはロックに聴こえたから。1曲目からテクノ・ポップに激しいベースが乗っている変な曲。良く聴くとロックというよりはテクノポップ。アンビエントな曲とのバランスがいい。4曲目はDEVOのようなテクノポップ。ところが、5曲目は一転してRUINSになっている。吉田達也+スクエアプッシャーってちょっとだけ面白そう。8曲目もRUINSっぽいなと思っていたら、スペースロック。思い出波止場っぽい。このアルバムは、そういうテクノ+ベース一直線というよりは、テクノポップやプログレ、アンビエント、ロックぽいところが雑多に混じってるところが良い。Nov.03 CD : Joyce DiDonato
 Joyce DiDonato : Handel / Furore : モーツァルトとヘンデルのアリア集が流行ってるような気がする。世間ではやってるのか、僕の中ではやっていて目がつきやすいのかわからない。けれども。これもCDショップでジャケ買い。ジョイス・ディドナートのヘンデル・アリア集。「デセオ」「ヘラクレス」「アドメート」と僕があまり知らない作品からのアリアが多い。怨念のこもったような激しいアリアが多く、ディドナート自体も情をこめてうたっている。呪われそうです。つけているクリストフ・ルーセが指揮したオケで、当然ピリオド奏法の団体。
Joyce DiDonato : Handel / Furore : モーツァルトとヘンデルのアリア集が流行ってるような気がする。世間ではやってるのか、僕の中ではやっていて目がつきやすいのかわからない。けれども。これもCDショップでジャケ買い。ジョイス・ディドナートのヘンデル・アリア集。「デセオ」「ヘラクレス」「アドメート」と僕があまり知らない作品からのアリアが多い。怨念のこもったような激しいアリアが多く、ディドナート自体も情をこめてうたっている。呪われそうです。つけているクリストフ・ルーセが指揮したオケで、当然ピリオド奏法の団体。
 Joyce DiDonato : Handel / Furore : モーツァルトとヘンデルのアリア集が流行ってるような気がする。世間ではやってるのか、僕の中ではやっていて目がつきやすいのかわからない。けれども。これもCDショップでジャケ買い。ジョイス・ディドナートのヘンデル・アリア集。「デセオ」「ヘラクレス」「アドメート」と僕があまり知らない作品からのアリアが多い。怨念のこもったような激しいアリアが多く、ディドナート自体も情をこめてうたっている。呪われそうです。つけているクリストフ・ルーセが指揮したオケで、当然ピリオド奏法の団体。
Joyce DiDonato : Handel / Furore : モーツァルトとヘンデルのアリア集が流行ってるような気がする。世間ではやってるのか、僕の中ではやっていて目がつきやすいのかわからない。けれども。これもCDショップでジャケ買い。ジョイス・ディドナートのヘンデル・アリア集。「デセオ」「ヘラクレス」「アドメート」と僕があまり知らない作品からのアリアが多い。怨念のこもったような激しいアリアが多く、ディドナート自体も情をこめてうたっている。呪われそうです。つけているクリストフ・ルーセが指揮したオケで、当然ピリオド奏法の団体。Nov.02 児玉桃 @ フィリアホール
14時からフィリアホールで、児玉桃のメシアン演奏会。「まなざし」に続いて2回目で、今日は「鳥のカタログ」全曲。まず、この曲が全曲演奏される機会ってそうないだろう。ウゴルスキとか安田正昭とか、全曲録音がある人くらいではないだろうか。さて、客は「まなざし」のときより若干少なめ。ステージ上にスクリーンがあり、鳥の絵と簡単な解説が出る。しかし、30分もある「ヨーロッパヨシキリ」なのに解説は3行とか、不満な点は多い。あのスクリーンだけだと、この曲は1曲につき1種類の鳥しか出てこず、しかも鳥の鳴き声しか出てこないような印象を与えてしまう恐れがあると思うのだが。休憩は2回で、演奏が終わったのが17時20分ころ。演奏は前回よりも力が入っていて、ミスも少なそうに感じた。楽譜を見たことがないので、完全に印象であるが。彼女は、か弱そうな風貌なのにピアノを叩きつけるようにフォルテを演奏する。音色よりも印象を優先しているのか?休憩時間中は、朝の早稲田祭でメシアンを弾いてきた西村さんと歓談。なんで、この曲を聴きに来ているのか分からない人が多いのと、純粋に児玉桃のファンという人が何割かいるようだ。前の席のおじさんがうるさく、杖を倒したり、集中力がない。妻らしきおばさんと一緒に来ており、おばさんの方は集中して曲を聴いてるのだが、ちょっと咳込んだりすると、おじさんがやたらと話しかける。うっとおしいなと思っていたら、最後の曲が終わる、ほんの数小節前におばさんが切れて「うるさい」と言ってしまう。もうすぐ終わるのに…。聴く方も体力勝負の演奏会だった。
Oct.26 CD : Ingo Metzmacher
 Metzmacher : Pfitzner / Von Deutscher Seele : メッツマッハーとベルリン・ドイツ交響楽団の録音。メッツマッハーは、ケント・ナガノの後任として2007年か芸術監督のポジションにいて、カジュアルコンサートなど積極的にプロジェクトを行っている。録音が出るのはこれが初めてのはず(iTune向けのダウンロードで「英雄の生涯」があったが)。シーズンごとにテーマを決めているようで、1年目の2007-2008年のシーズンは「ドイツの魂について」というテーマだったようだ。9月はR.シュトラウスの「英雄の生涯」、マーラーの4番、ブラームスのピアノ協奏曲2番などが演奏されていて、10月の東西ドイツ統一の日と次の日の定期公演で、このプフィッツナーの「ドイツの精神について」が演奏されている。テキストの内容や、プフィッツナーの政治館などから、この作品をこの日に取り上げることで話題になったようだ。メッツマッハーといいティーレマンといい、この世代の指揮者はプフィッツナーを取り上げるのが好きなようだ。おまけにメッツマッハーはドイツの現代作曲家を幅広く演奏しているので、政治的意図が強いとも思えないのだが。曲は、R.シュトラウスをダサくしたような、ドイツ後期ロマン派風の作品。演奏については、この曲では何とも言えない。「英雄の生涯」とか「春の祭典」とか、バブゼと原田節がソロの「トゥランガリーラ交響曲」とかCD化しませんかね。
Metzmacher : Pfitzner / Von Deutscher Seele : メッツマッハーとベルリン・ドイツ交響楽団の録音。メッツマッハーは、ケント・ナガノの後任として2007年か芸術監督のポジションにいて、カジュアルコンサートなど積極的にプロジェクトを行っている。録音が出るのはこれが初めてのはず(iTune向けのダウンロードで「英雄の生涯」があったが)。シーズンごとにテーマを決めているようで、1年目の2007-2008年のシーズンは「ドイツの魂について」というテーマだったようだ。9月はR.シュトラウスの「英雄の生涯」、マーラーの4番、ブラームスのピアノ協奏曲2番などが演奏されていて、10月の東西ドイツ統一の日と次の日の定期公演で、このプフィッツナーの「ドイツの精神について」が演奏されている。テキストの内容や、プフィッツナーの政治館などから、この作品をこの日に取り上げることで話題になったようだ。メッツマッハーといいティーレマンといい、この世代の指揮者はプフィッツナーを取り上げるのが好きなようだ。おまけにメッツマッハーはドイツの現代作曲家を幅広く演奏しているので、政治的意図が強いとも思えないのだが。曲は、R.シュトラウスをダサくしたような、ドイツ後期ロマン派風の作品。演奏については、この曲では何とも言えない。「英雄の生涯」とか「春の祭典」とか、バブゼと原田節がソロの「トゥランガリーラ交響曲」とかCD化しませんかね。
 Metzmacher : Pfitzner / Von Deutscher Seele : メッツマッハーとベルリン・ドイツ交響楽団の録音。メッツマッハーは、ケント・ナガノの後任として2007年か芸術監督のポジションにいて、カジュアルコンサートなど積極的にプロジェクトを行っている。録音が出るのはこれが初めてのはず(iTune向けのダウンロードで「英雄の生涯」があったが)。シーズンごとにテーマを決めているようで、1年目の2007-2008年のシーズンは「ドイツの魂について」というテーマだったようだ。9月はR.シュトラウスの「英雄の生涯」、マーラーの4番、ブラームスのピアノ協奏曲2番などが演奏されていて、10月の東西ドイツ統一の日と次の日の定期公演で、このプフィッツナーの「ドイツの精神について」が演奏されている。テキストの内容や、プフィッツナーの政治館などから、この作品をこの日に取り上げることで話題になったようだ。メッツマッハーといいティーレマンといい、この世代の指揮者はプフィッツナーを取り上げるのが好きなようだ。おまけにメッツマッハーはドイツの現代作曲家を幅広く演奏しているので、政治的意図が強いとも思えないのだが。曲は、R.シュトラウスをダサくしたような、ドイツ後期ロマン派風の作品。演奏については、この曲では何とも言えない。「英雄の生涯」とか「春の祭典」とか、バブゼと原田節がソロの「トゥランガリーラ交響曲」とかCD化しませんかね。
Metzmacher : Pfitzner / Von Deutscher Seele : メッツマッハーとベルリン・ドイツ交響楽団の録音。メッツマッハーは、ケント・ナガノの後任として2007年か芸術監督のポジションにいて、カジュアルコンサートなど積極的にプロジェクトを行っている。録音が出るのはこれが初めてのはず(iTune向けのダウンロードで「英雄の生涯」があったが)。シーズンごとにテーマを決めているようで、1年目の2007-2008年のシーズンは「ドイツの魂について」というテーマだったようだ。9月はR.シュトラウスの「英雄の生涯」、マーラーの4番、ブラームスのピアノ協奏曲2番などが演奏されていて、10月の東西ドイツ統一の日と次の日の定期公演で、このプフィッツナーの「ドイツの精神について」が演奏されている。テキストの内容や、プフィッツナーの政治館などから、この作品をこの日に取り上げることで話題になったようだ。メッツマッハーといいティーレマンといい、この世代の指揮者はプフィッツナーを取り上げるのが好きなようだ。おまけにメッツマッハーはドイツの現代作曲家を幅広く演奏しているので、政治的意図が強いとも思えないのだが。曲は、R.シュトラウスをダサくしたような、ドイツ後期ロマン派風の作品。演奏については、この曲では何とも言えない。「英雄の生涯」とか「春の祭典」とか、バブゼと原田節がソロの「トゥランガリーラ交響曲」とかCD化しませんかね。Oct.25 Verdi "Rigoletto" / Daniele Callegari @ 新国立劇場 (Tokyo Philharmony Orchestra)
新国立劇場で「リゴレット」をみた。実は新国は初めて。今劇場ができたのは僕が大学の時だったが、その頃はオペラにまるで興味がなかったので、今まで来たことがなかったのだろう。今シーズンからちょくちょく来てみたいと思っている。3階の左ドアそばの席で、オケピットは見えず、ステージも少し影ぎみ。場所のせいもあるのか音が遠く聞こえる。オケは東京フィルであいかわらずイマイチだが、指揮者のダニエレ・カッレガーリのコントロールがいいのか、歌にはついていっていた。演出は非常にオーソドックスなもので、第1幕では回転舞台まで利用していた。平土間で見れば奥行感の感じられる演出だっただろう。一番気に入ったのはマントヴァ公爵のシャルヴァ・ムケリア。抜けのいい軽さが良かったのかな。第1幕では多少危なかったが、後半は特に良かった。ジルダのアニック・マッシスは美人で歌もよいし、リゴレットのラード・アタネッリもいい。このオペラは第2幕から第3幕の頭までが面白いところだと思うし、今日の公演でも盛り上がったのは第2幕じゃないかな。第1幕は、ところどころ記憶がない。
Oct.25 CD : Carlos Kleiber
 Carlos Kleiber : R.Strauss / Der Rosenkavalier : カルロス・クライバーのばらの騎士のライブCD。以前から海賊盤では出回っていたものであるが、Orfeoから放送録音の正規盤発売。おまけにSACDだ。1973年のミュンヘン、バイエルン州立歌劇場でのライブ。クライバーは、ばらの騎士はすでに映像で2種類録音があり、一つは79年のバイエルン州立歌劇場のもの、もう一つは94年のウィーンのものである。CDで公式録音が出たのはこれが初めてということだ。79年の録音と結構配役が被っていて、オクタヴィアンのブリギッテ・ファスベンダー、ゾフィーのルチア・ポップ、ファーニナルのベンノ・クッシェが、このCDと79年の映像と同じだ。79年の映像は、マルシャリンのギネス・ジョーンズの存在感が大きいが、この録音はクレア・ワトソン。
とにかく、拍手をさえぎるように振り下ろす冒頭のホルンからクライバー節で、これがたまらなくいい。バイエルンのオケとの相性もいいというか、オケが楽しそう。僕は、CDでオペラを聴くと、けっこうすぐ飽きてしまうのだが、これは音楽が退屈になる瞬間がない。躍動感、艶っぽさ、ウィーンの雰囲気などが見えてきそうな(もちろん想像と結びつくだけなんですが)演奏だ。アリアの途中でひとりだけタイミングを外した拍手が生々しく入っていたり、ライブだというのも大きいだろう。歌手は、ファスベンダーもポップも良いですね。オックスをカール・リッダーブッシュが歌っているが、これがすばらしい。歌も声もいい上に、必要以上に下品ではない。
録音としては、オンマイクぎみで、各楽器のバランスもきっちり取れているわけではないが、音質はいいので良しとすべきでしょう。こんなこといっても仕方ないんだけど、こういう公演を生で見ることができた人たちがうらやましい。
Carlos Kleiber : R.Strauss / Der Rosenkavalier : カルロス・クライバーのばらの騎士のライブCD。以前から海賊盤では出回っていたものであるが、Orfeoから放送録音の正規盤発売。おまけにSACDだ。1973年のミュンヘン、バイエルン州立歌劇場でのライブ。クライバーは、ばらの騎士はすでに映像で2種類録音があり、一つは79年のバイエルン州立歌劇場のもの、もう一つは94年のウィーンのものである。CDで公式録音が出たのはこれが初めてということだ。79年の録音と結構配役が被っていて、オクタヴィアンのブリギッテ・ファスベンダー、ゾフィーのルチア・ポップ、ファーニナルのベンノ・クッシェが、このCDと79年の映像と同じだ。79年の映像は、マルシャリンのギネス・ジョーンズの存在感が大きいが、この録音はクレア・ワトソン。
とにかく、拍手をさえぎるように振り下ろす冒頭のホルンからクライバー節で、これがたまらなくいい。バイエルンのオケとの相性もいいというか、オケが楽しそう。僕は、CDでオペラを聴くと、けっこうすぐ飽きてしまうのだが、これは音楽が退屈になる瞬間がない。躍動感、艶っぽさ、ウィーンの雰囲気などが見えてきそうな(もちろん想像と結びつくだけなんですが)演奏だ。アリアの途中でひとりだけタイミングを外した拍手が生々しく入っていたり、ライブだというのも大きいだろう。歌手は、ファスベンダーもポップも良いですね。オックスをカール・リッダーブッシュが歌っているが、これがすばらしい。歌も声もいい上に、必要以上に下品ではない。
録音としては、オンマイクぎみで、各楽器のバランスもきっちり取れているわけではないが、音質はいいので良しとすべきでしょう。こんなこといっても仕方ないんだけど、こういう公演を生で見ることができた人たちがうらやましい。
 Carlos Kleiber : R.Strauss / Der Rosenkavalier : カルロス・クライバーのばらの騎士のライブCD。以前から海賊盤では出回っていたものであるが、Orfeoから放送録音の正規盤発売。おまけにSACDだ。1973年のミュンヘン、バイエルン州立歌劇場でのライブ。クライバーは、ばらの騎士はすでに映像で2種類録音があり、一つは79年のバイエルン州立歌劇場のもの、もう一つは94年のウィーンのものである。CDで公式録音が出たのはこれが初めてということだ。79年の録音と結構配役が被っていて、オクタヴィアンのブリギッテ・ファスベンダー、ゾフィーのルチア・ポップ、ファーニナルのベンノ・クッシェが、このCDと79年の映像と同じだ。79年の映像は、マルシャリンのギネス・ジョーンズの存在感が大きいが、この録音はクレア・ワトソン。
とにかく、拍手をさえぎるように振り下ろす冒頭のホルンからクライバー節で、これがたまらなくいい。バイエルンのオケとの相性もいいというか、オケが楽しそう。僕は、CDでオペラを聴くと、けっこうすぐ飽きてしまうのだが、これは音楽が退屈になる瞬間がない。躍動感、艶っぽさ、ウィーンの雰囲気などが見えてきそうな(もちろん想像と結びつくだけなんですが)演奏だ。アリアの途中でひとりだけタイミングを外した拍手が生々しく入っていたり、ライブだというのも大きいだろう。歌手は、ファスベンダーもポップも良いですね。オックスをカール・リッダーブッシュが歌っているが、これがすばらしい。歌も声もいい上に、必要以上に下品ではない。
録音としては、オンマイクぎみで、各楽器のバランスもきっちり取れているわけではないが、音質はいいので良しとすべきでしょう。こんなこといっても仕方ないんだけど、こういう公演を生で見ることができた人たちがうらやましい。
Carlos Kleiber : R.Strauss / Der Rosenkavalier : カルロス・クライバーのばらの騎士のライブCD。以前から海賊盤では出回っていたものであるが、Orfeoから放送録音の正規盤発売。おまけにSACDだ。1973年のミュンヘン、バイエルン州立歌劇場でのライブ。クライバーは、ばらの騎士はすでに映像で2種類録音があり、一つは79年のバイエルン州立歌劇場のもの、もう一つは94年のウィーンのものである。CDで公式録音が出たのはこれが初めてということだ。79年の録音と結構配役が被っていて、オクタヴィアンのブリギッテ・ファスベンダー、ゾフィーのルチア・ポップ、ファーニナルのベンノ・クッシェが、このCDと79年の映像と同じだ。79年の映像は、マルシャリンのギネス・ジョーンズの存在感が大きいが、この録音はクレア・ワトソン。
とにかく、拍手をさえぎるように振り下ろす冒頭のホルンからクライバー節で、これがたまらなくいい。バイエルンのオケとの相性もいいというか、オケが楽しそう。僕は、CDでオペラを聴くと、けっこうすぐ飽きてしまうのだが、これは音楽が退屈になる瞬間がない。躍動感、艶っぽさ、ウィーンの雰囲気などが見えてきそうな(もちろん想像と結びつくだけなんですが)演奏だ。アリアの途中でひとりだけタイミングを外した拍手が生々しく入っていたり、ライブだというのも大きいだろう。歌手は、ファスベンダーもポップも良いですね。オックスをカール・リッダーブッシュが歌っているが、これがすばらしい。歌も声もいい上に、必要以上に下品ではない。
録音としては、オンマイクぎみで、各楽器のバランスもきっちり取れているわけではないが、音質はいいので良しとすべきでしょう。こんなこといっても仕方ないんだけど、こういう公演を生で見ることができた人たちがうらやましい。Oct.25 CD : Max Tundra
 Max Tundra / Parallax Error Beheads You : 新宿タワレコの7階はクラシックのフロアだが、現代音楽のコーナーの近くにある、アヴァンギャルドやエレクトロニカのコーナーには必ず寄る。そしてそこで、かかっているものを衝動買いする。もともと興味があった、レコメン系やアンビエントやドイツ系はなんとなく情報を体系的に持っているが、エレクトロニカの知識が蓄積されない。どれも衝動買いなのだ。これもその一つ。でも超大当たり。なにがって、まずブリティッシュ・ポップ。純英国産。英国産じゃないとこれはできませんな。XTCやTodd Rundgren、カンタベリー系がエレクトロニカをやったみたいなアルバムだ。でも4曲目なんて聴いてるとYESみたいに聴こえるし、Mats and Morganが演奏したら面白そうな曲もある。あ、プログレだから気に入っているのか。ネットで調べると6年ぶりのアルバムらしいが、昔のアルバムも聴いてみたい。
Max Tundra / Parallax Error Beheads You : 新宿タワレコの7階はクラシックのフロアだが、現代音楽のコーナーの近くにある、アヴァンギャルドやエレクトロニカのコーナーには必ず寄る。そしてそこで、かかっているものを衝動買いする。もともと興味があった、レコメン系やアンビエントやドイツ系はなんとなく情報を体系的に持っているが、エレクトロニカの知識が蓄積されない。どれも衝動買いなのだ。これもその一つ。でも超大当たり。なにがって、まずブリティッシュ・ポップ。純英国産。英国産じゃないとこれはできませんな。XTCやTodd Rundgren、カンタベリー系がエレクトロニカをやったみたいなアルバムだ。でも4曲目なんて聴いてるとYESみたいに聴こえるし、Mats and Morganが演奏したら面白そうな曲もある。あ、プログレだから気に入っているのか。ネットで調べると6年ぶりのアルバムらしいが、昔のアルバムも聴いてみたい。
 Max Tundra / Parallax Error Beheads You : 新宿タワレコの7階はクラシックのフロアだが、現代音楽のコーナーの近くにある、アヴァンギャルドやエレクトロニカのコーナーには必ず寄る。そしてそこで、かかっているものを衝動買いする。もともと興味があった、レコメン系やアンビエントやドイツ系はなんとなく情報を体系的に持っているが、エレクトロニカの知識が蓄積されない。どれも衝動買いなのだ。これもその一つ。でも超大当たり。なにがって、まずブリティッシュ・ポップ。純英国産。英国産じゃないとこれはできませんな。XTCやTodd Rundgren、カンタベリー系がエレクトロニカをやったみたいなアルバムだ。でも4曲目なんて聴いてるとYESみたいに聴こえるし、Mats and Morganが演奏したら面白そうな曲もある。あ、プログレだから気に入っているのか。ネットで調べると6年ぶりのアルバムらしいが、昔のアルバムも聴いてみたい。
Max Tundra / Parallax Error Beheads You : 新宿タワレコの7階はクラシックのフロアだが、現代音楽のコーナーの近くにある、アヴァンギャルドやエレクトロニカのコーナーには必ず寄る。そしてそこで、かかっているものを衝動買いする。もともと興味があった、レコメン系やアンビエントやドイツ系はなんとなく情報を体系的に持っているが、エレクトロニカの知識が蓄積されない。どれも衝動買いなのだ。これもその一つ。でも超大当たり。なにがって、まずブリティッシュ・ポップ。純英国産。英国産じゃないとこれはできませんな。XTCやTodd Rundgren、カンタベリー系がエレクトロニカをやったみたいなアルバムだ。でも4曲目なんて聴いてるとYESみたいに聴こえるし、Mats and Morganが演奏したら面白そうな曲もある。あ、プログレだから気に入っているのか。ネットで調べると6年ぶりのアルバムらしいが、昔のアルバムも聴いてみたい。Oct.21 CD : Aaron Parks
 Aaron Parks / Invisible Cinema : タワレコで視聴して購入、、最近このパターンばっかりだ。このところ、e.s.t.やAvishai Cohen Trioなど、個人的にピアノトリオブームだ。Cholet Kanzig Papaux TrioやAvishai Cohenがベースを弾いているChick Corea New Trioなんかまで購入してしまった。このアーロン・パークスは、このアルバムがデビュー盤らしいが、メジャーレーベルでのデビューということで、インディペンデントなレーベルには4枚ほど録音があるらしい。基本的にはピアノトリオだが、半数以上の曲でギターが加わっている。ベースは先日のジョン・スコフィールドのライブでも弾いていたMatt Penman、ドラムはジョシュア・レッドマンのSF JAZZ COLLECTIVEでドラムを叩いてた(これもブルーノート東京で見たな)Eric Harland。全員、演奏技術はとても高いのだが、派手な演奏より曲をしっかり聴かせるタイプのアルバムで、即興のパートも少ない。純粋な4ビートのジャズも少なく、e.s.t.やBrad Mehldauのアルバムに近い。Mike Morenoのギターの入った曲では、ロックぽいアプローチが多く、8曲目なんて、ディストーションのかかったギターのバックをピアノトリオがつけているようにも聴こえる。どちらがメインなんだか。メルドーなどに比べるとピアノの音が甘いかな。変に熱くならないので、何回も聴きなおして楽しめた。
Aaron Parks / Invisible Cinema : タワレコで視聴して購入、、最近このパターンばっかりだ。このところ、e.s.t.やAvishai Cohen Trioなど、個人的にピアノトリオブームだ。Cholet Kanzig Papaux TrioやAvishai Cohenがベースを弾いているChick Corea New Trioなんかまで購入してしまった。このアーロン・パークスは、このアルバムがデビュー盤らしいが、メジャーレーベルでのデビューということで、インディペンデントなレーベルには4枚ほど録音があるらしい。基本的にはピアノトリオだが、半数以上の曲でギターが加わっている。ベースは先日のジョン・スコフィールドのライブでも弾いていたMatt Penman、ドラムはジョシュア・レッドマンのSF JAZZ COLLECTIVEでドラムを叩いてた(これもブルーノート東京で見たな)Eric Harland。全員、演奏技術はとても高いのだが、派手な演奏より曲をしっかり聴かせるタイプのアルバムで、即興のパートも少ない。純粋な4ビートのジャズも少なく、e.s.t.やBrad Mehldauのアルバムに近い。Mike Morenoのギターの入った曲では、ロックぽいアプローチが多く、8曲目なんて、ディストーションのかかったギターのバックをピアノトリオがつけているようにも聴こえる。どちらがメインなんだか。メルドーなどに比べるとピアノの音が甘いかな。変に熱くならないので、何回も聴きなおして楽しめた。
 Aaron Parks / Invisible Cinema : タワレコで視聴して購入、、最近このパターンばっかりだ。このところ、e.s.t.やAvishai Cohen Trioなど、個人的にピアノトリオブームだ。Cholet Kanzig Papaux TrioやAvishai Cohenがベースを弾いているChick Corea New Trioなんかまで購入してしまった。このアーロン・パークスは、このアルバムがデビュー盤らしいが、メジャーレーベルでのデビューということで、インディペンデントなレーベルには4枚ほど録音があるらしい。基本的にはピアノトリオだが、半数以上の曲でギターが加わっている。ベースは先日のジョン・スコフィールドのライブでも弾いていたMatt Penman、ドラムはジョシュア・レッドマンのSF JAZZ COLLECTIVEでドラムを叩いてた(これもブルーノート東京で見たな)Eric Harland。全員、演奏技術はとても高いのだが、派手な演奏より曲をしっかり聴かせるタイプのアルバムで、即興のパートも少ない。純粋な4ビートのジャズも少なく、e.s.t.やBrad Mehldauのアルバムに近い。Mike Morenoのギターの入った曲では、ロックぽいアプローチが多く、8曲目なんて、ディストーションのかかったギターのバックをピアノトリオがつけているようにも聴こえる。どちらがメインなんだか。メルドーなどに比べるとピアノの音が甘いかな。変に熱くならないので、何回も聴きなおして楽しめた。
Aaron Parks / Invisible Cinema : タワレコで視聴して購入、、最近このパターンばっかりだ。このところ、e.s.t.やAvishai Cohen Trioなど、個人的にピアノトリオブームだ。Cholet Kanzig Papaux TrioやAvishai Cohenがベースを弾いているChick Corea New Trioなんかまで購入してしまった。このアーロン・パークスは、このアルバムがデビュー盤らしいが、メジャーレーベルでのデビューということで、インディペンデントなレーベルには4枚ほど録音があるらしい。基本的にはピアノトリオだが、半数以上の曲でギターが加わっている。ベースは先日のジョン・スコフィールドのライブでも弾いていたMatt Penman、ドラムはジョシュア・レッドマンのSF JAZZ COLLECTIVEでドラムを叩いてた(これもブルーノート東京で見たな)Eric Harland。全員、演奏技術はとても高いのだが、派手な演奏より曲をしっかり聴かせるタイプのアルバムで、即興のパートも少ない。純粋な4ビートのジャズも少なく、e.s.t.やBrad Mehldauのアルバムに近い。Mike Morenoのギターの入った曲では、ロックぽいアプローチが多く、8曲目なんて、ディストーションのかかったギターのバックをピアノトリオがつけているようにも聴こえる。どちらがメインなんだか。メルドーなどに比べるとピアノの音が甘いかな。変に熱くならないので、何回も聴きなおして楽しめた。Oct.21 CD : Juana Molina
 Juana Molina / Un Dia : アルゼンチン音響派でくくられるファナ・モリーナの新作。5作目らしい。これまでの作品は、わかりやすく言えばフォーク+エレクトロニカだったのだが、このアルバムはビートが強調されていて、ミニマルな展開が多くて、すこしロックしている。冒頭の曲が一番刺激が強い。ヴォーカルの多重録音で、土着的なビートが繰り返される。ビヨークとか上野洋子とかVarttinaがやっているような曲に近い。楽器はほとんどがファナが演奏している。気が狂いそうになるくらい、引き込まれる。
Juana Molina / Un Dia : アルゼンチン音響派でくくられるファナ・モリーナの新作。5作目らしい。これまでの作品は、わかりやすく言えばフォーク+エレクトロニカだったのだが、このアルバムはビートが強調されていて、ミニマルな展開が多くて、すこしロックしている。冒頭の曲が一番刺激が強い。ヴォーカルの多重録音で、土着的なビートが繰り返される。ビヨークとか上野洋子とかVarttinaがやっているような曲に近い。楽器はほとんどがファナが演奏している。気が狂いそうになるくらい、引き込まれる。
 Juana Molina / Un Dia : アルゼンチン音響派でくくられるファナ・モリーナの新作。5作目らしい。これまでの作品は、わかりやすく言えばフォーク+エレクトロニカだったのだが、このアルバムはビートが強調されていて、ミニマルな展開が多くて、すこしロックしている。冒頭の曲が一番刺激が強い。ヴォーカルの多重録音で、土着的なビートが繰り返される。ビヨークとか上野洋子とかVarttinaがやっているような曲に近い。楽器はほとんどがファナが演奏している。気が狂いそうになるくらい、引き込まれる。
Juana Molina / Un Dia : アルゼンチン音響派でくくられるファナ・モリーナの新作。5作目らしい。これまでの作品は、わかりやすく言えばフォーク+エレクトロニカだったのだが、このアルバムはビートが強調されていて、ミニマルな展開が多くて、すこしロックしている。冒頭の曲が一番刺激が強い。ヴォーカルの多重録音で、土着的なビートが繰り返される。ビヨークとか上野洋子とかVarttinaがやっているような曲に近い。楽器はほとんどがファナが演奏している。気が狂いそうになるくらい、引き込まれる。Oct.21 CD : Patricia Petibon
 Patricia Petibon + Daniel Harding : Amoureuses : パトリシア・プティボンの新譜。古典派のオペラアリア集なので購入した。彼女の前のアルバムはデッカから出ていたが、グラモフォンに移籍したようだ。ハイドン、グルック、モーツァルトのアリア。役どころはバラバラで、最近のダムラウのアルバムと張り合う形となってしまっているのかな。ところが、歌手としての傾向は全然違う。ポリーニとグールド、カラヤンとサヴァリッシュくらい違う。とにかく歌い方が濃いい。彼女が歌うオペラをぜひ見てみたい、と思わせるくらい芸が濃いのだ。"夜の女王のアリア" (2つめ)も収められているが、ダムラウやグルベローヴァに比べると、素直に歌えていない気がする。例のハイFのところも、ごまかしぎみ。この曲だけちょっと浮いている気もするのだが、メジャーな曲をということで収録したのかもしれない。真面目にハイドンのアリアを聴いたのは初めてなのだが、オペラとしても面白そう。これも勉強しないと。
バックは、ハーディングとコンチェルト・ケルン。これがクールな演奏をするのだ。"Tiger"やアルミードのフィナーレのなど、激情的なものはとてもカッコいい。この組み合わせでモーツァルトやハイドンの交響曲を録音してくれないかな。
グラモフォンのサイトに録音時の映像がPVとして掲載されている。映像を見たとき、ハーディングの方に目が行ってしまったのは内緒だ。
Patricia Petibon + Daniel Harding : Amoureuses : パトリシア・プティボンの新譜。古典派のオペラアリア集なので購入した。彼女の前のアルバムはデッカから出ていたが、グラモフォンに移籍したようだ。ハイドン、グルック、モーツァルトのアリア。役どころはバラバラで、最近のダムラウのアルバムと張り合う形となってしまっているのかな。ところが、歌手としての傾向は全然違う。ポリーニとグールド、カラヤンとサヴァリッシュくらい違う。とにかく歌い方が濃いい。彼女が歌うオペラをぜひ見てみたい、と思わせるくらい芸が濃いのだ。"夜の女王のアリア" (2つめ)も収められているが、ダムラウやグルベローヴァに比べると、素直に歌えていない気がする。例のハイFのところも、ごまかしぎみ。この曲だけちょっと浮いている気もするのだが、メジャーな曲をということで収録したのかもしれない。真面目にハイドンのアリアを聴いたのは初めてなのだが、オペラとしても面白そう。これも勉強しないと。
バックは、ハーディングとコンチェルト・ケルン。これがクールな演奏をするのだ。"Tiger"やアルミードのフィナーレのなど、激情的なものはとてもカッコいい。この組み合わせでモーツァルトやハイドンの交響曲を録音してくれないかな。
グラモフォンのサイトに録音時の映像がPVとして掲載されている。映像を見たとき、ハーディングの方に目が行ってしまったのは内緒だ。
 Patricia Petibon + Daniel Harding : Amoureuses : パトリシア・プティボンの新譜。古典派のオペラアリア集なので購入した。彼女の前のアルバムはデッカから出ていたが、グラモフォンに移籍したようだ。ハイドン、グルック、モーツァルトのアリア。役どころはバラバラで、最近のダムラウのアルバムと張り合う形となってしまっているのかな。ところが、歌手としての傾向は全然違う。ポリーニとグールド、カラヤンとサヴァリッシュくらい違う。とにかく歌い方が濃いい。彼女が歌うオペラをぜひ見てみたい、と思わせるくらい芸が濃いのだ。"夜の女王のアリア" (2つめ)も収められているが、ダムラウやグルベローヴァに比べると、素直に歌えていない気がする。例のハイFのところも、ごまかしぎみ。この曲だけちょっと浮いている気もするのだが、メジャーな曲をということで収録したのかもしれない。真面目にハイドンのアリアを聴いたのは初めてなのだが、オペラとしても面白そう。これも勉強しないと。
バックは、ハーディングとコンチェルト・ケルン。これがクールな演奏をするのだ。"Tiger"やアルミードのフィナーレのなど、激情的なものはとてもカッコいい。この組み合わせでモーツァルトやハイドンの交響曲を録音してくれないかな。
グラモフォンのサイトに録音時の映像がPVとして掲載されている。映像を見たとき、ハーディングの方に目が行ってしまったのは内緒だ。
Patricia Petibon + Daniel Harding : Amoureuses : パトリシア・プティボンの新譜。古典派のオペラアリア集なので購入した。彼女の前のアルバムはデッカから出ていたが、グラモフォンに移籍したようだ。ハイドン、グルック、モーツァルトのアリア。役どころはバラバラで、最近のダムラウのアルバムと張り合う形となってしまっているのかな。ところが、歌手としての傾向は全然違う。ポリーニとグールド、カラヤンとサヴァリッシュくらい違う。とにかく歌い方が濃いい。彼女が歌うオペラをぜひ見てみたい、と思わせるくらい芸が濃いのだ。"夜の女王のアリア" (2つめ)も収められているが、ダムラウやグルベローヴァに比べると、素直に歌えていない気がする。例のハイFのところも、ごまかしぎみ。この曲だけちょっと浮いている気もするのだが、メジャーな曲をということで収録したのかもしれない。真面目にハイドンのアリアを聴いたのは初めてなのだが、オペラとしても面白そう。これも勉強しないと。
バックは、ハーディングとコンチェルト・ケルン。これがクールな演奏をするのだ。"Tiger"やアルミードのフィナーレのなど、激情的なものはとてもカッコいい。この組み合わせでモーツァルトやハイドンの交響曲を録音してくれないかな。
グラモフォンのサイトに録音時の映像がPVとして掲載されている。映像を見たとき、ハーディングの方に目が行ってしまったのは内緒だ。Oct.21 CD : Angelika Kirchschlager
 Angelika Kirchschlager : Sings Christmas Carols : まだちょっと時期が早いが、アンゲリカ・キルヒシュラーガーの「クリスマス・キャロルを歌う」。おそらく海外では昨年に発売されていたものだが、国内盤が最近発売された。半数がオケ伴奏で、ペーター・コルネリウスの作品などはヘルムート・ドイチェによるピアノ伴奏。"きよしこの夜"はアカペラ。偉大な母親に歌われているような気分になる声だ。有名な賛美歌の曲が多く収録されているので、楽しいが、やっぱりまだ季節が早いかな。
Angelika Kirchschlager : Sings Christmas Carols : まだちょっと時期が早いが、アンゲリカ・キルヒシュラーガーの「クリスマス・キャロルを歌う」。おそらく海外では昨年に発売されていたものだが、国内盤が最近発売された。半数がオケ伴奏で、ペーター・コルネリウスの作品などはヘルムート・ドイチェによるピアノ伴奏。"きよしこの夜"はアカペラ。偉大な母親に歌われているような気分になる声だ。有名な賛美歌の曲が多く収録されているので、楽しいが、やっぱりまだ季節が早いかな。
 Angelika Kirchschlager : Sings Christmas Carols : まだちょっと時期が早いが、アンゲリカ・キルヒシュラーガーの「クリスマス・キャロルを歌う」。おそらく海外では昨年に発売されていたものだが、国内盤が最近発売された。半数がオケ伴奏で、ペーター・コルネリウスの作品などはヘルムート・ドイチェによるピアノ伴奏。"きよしこの夜"はアカペラ。偉大な母親に歌われているような気分になる声だ。有名な賛美歌の曲が多く収録されているので、楽しいが、やっぱりまだ季節が早いかな。
Angelika Kirchschlager : Sings Christmas Carols : まだちょっと時期が早いが、アンゲリカ・キルヒシュラーガーの「クリスマス・キャロルを歌う」。おそらく海外では昨年に発売されていたものだが、国内盤が最近発売された。半数がオケ伴奏で、ペーター・コルネリウスの作品などはヘルムート・ドイチェによるピアノ伴奏。"きよしこの夜"はアカペラ。偉大な母親に歌われているような気分になる声だ。有名な賛美歌の曲が多く収録されているので、楽しいが、やっぱりまだ季節が早いかな。Oct.18 Richard Bona @ Blue Note 東京 2nd Set
昼間にコンサートを聴いておきながら、夜もライブ。ブルーノートで、リチャード・ボナのライブ。21時半からのセカンドセット。Bonaは、Mike Sternのライブと渡辺香津美のライブで見たことはあるが、ソロは初めて。ライブアルバムの「Bona Makes You Sweat」とおなじようなセットリスト。"Engingilaye"でつかみ、"Kalabancoro"の歌でしびれさせ、"O Sen Sen Sen"で客をあおってコーラスをさせ、"Te Dikalo"で盛り上げる。基本的にジャズのライブというよりは、アフリカ系シンガーソングライターのライブだ。ベース好きを黙らせるため、Jacoの"Liberty City"とWeatherの"Birdland"のメドレーを演奏した。もちろん、ボナのベースは言うことないが、他のメンバーのテクニックもかなりのものだ。メンバーは、Taylor Haskins (tp)、Etienne Stadwijk (key)、Adam Stoler (g)、Ernesto Simpson (ds)、Samuel Torres (per)。メンバー紹介のときに出身地を言うのはZawinulの影響かなんですかね。キーボードがオランダの出身で「警察がJointを吸ってるいいところだ」と紹介。ギターはNYのロングアイランド出身で18歳だとか。けっこうギンギンなギターを弾いていた。あと、ボナは自己紹介で「西宮出身だ」と言っていた。何が気に入ってそんなこと言ってるのかな。以前に比べると、少しお腹が出ていて貫禄がついている。アンコールはBonaは「私の歌を歌います。ボナボナボナ〜」とドナドナの替え歌を歌ってボケたあとに、マイク2本を使って、一人で多重録音ループを作りながら、コーラスをつけながら歌うという離れ業をやってくれた。単純に楽しいライブだった。
Oct.18 児玉桃 @ フィリアホール
14時からフィリアホールで、児玉桃のメシアン演奏会。実はフィリアホールは初めて。遠いイメージがあったのだが、最寄りの駅から15分でついてしまい、駅からも近くて便利なことが分かった。ただ、駅近辺の様子から察するに古い感じの住宅街(ベッドタウン)だ。さて、プログラムはメシアンの「みどり児イエスに注ぐ20のまなざし」全曲。曲の細かいところまでは勉強不足なので、語るほどではないのだが、曲を楽しめる演奏だった。6曲目の冒頭のリズムなどはかっこ悪いと思ったけど(ベロフだとカッコいいのですよ)。時々拍手が入り、演奏者が袖にひっこむ。さすがに休みなしだときついのかな。10曲目の後に休憩が入る。後半は予想どおり眠くなってきて、16曲目、17曲目あたりは記憶が飛んでいる。この曲を生で聴いたのが初めてだが、ライブだとさすがに大変そうな曲だ。次の鳥のカタログはどうなるのでしょうか。コンサートのあとは、後輩杉本、西村さん、高沖さんらと音楽話の濃い飲み会。
Oct.18 CD : The Duo (鬼怒無月 + 鈴木大介)
 The Duo / Cinema Voyage : 鬼怒無月と鈴木大介のThe DUOの新作が出!2作目。映画音楽集、ってことは鈴木の方の趣味なんだろうか。ファーストアルバムは、2人のギタリストの対比がおもしろかったのだが、この作品は2人が溶け合っているように聴こえる。ユニットとして演奏回数が増えたからかなと思ったのだが、何回か繰り返して聴いているうちに、アレンジが緻密にされているからだということに気がついた。ぼーとBGMにして聴いていても問題ないくらい緻密で美しい。選曲もとてもいい。普通なら"Libertango"に耳が行くのかな。"Over the Rainbow"〜"What a Wonderful World"がとてもいい。サッチモよりいい。"Both Sides Now"は、最近でた吉田美奈子と渡辺香津美のデュオアルバムでも取り上げられていたが、はやっているのかな。歌が入ってるなら、Joniのオリジナルの録音がいいなぁと思ってしまう。鬼怒の書いた"空の映写技師"は"Three Colors of the Sky"と同じくらい泣けてきそうないい曲。どこかで聴いたことがあるような覚えがあるのだが、気のせだろうか。初回限定版は3曲入った2枚目がついていて、"It's only Paper Moon"なんかとてもいいので、売ってたならこっちを買わないと損。3枚目は鬼怒色を出して、全曲即興演奏とかどうでしょう。この2人での"Crawler"なんていうのも聴いてみたいので、2枚組ライブアルバムにして1枚は完全即興にしちゃうとか。
The Duo / Cinema Voyage : 鬼怒無月と鈴木大介のThe DUOの新作が出!2作目。映画音楽集、ってことは鈴木の方の趣味なんだろうか。ファーストアルバムは、2人のギタリストの対比がおもしろかったのだが、この作品は2人が溶け合っているように聴こえる。ユニットとして演奏回数が増えたからかなと思ったのだが、何回か繰り返して聴いているうちに、アレンジが緻密にされているからだということに気がついた。ぼーとBGMにして聴いていても問題ないくらい緻密で美しい。選曲もとてもいい。普通なら"Libertango"に耳が行くのかな。"Over the Rainbow"〜"What a Wonderful World"がとてもいい。サッチモよりいい。"Both Sides Now"は、最近でた吉田美奈子と渡辺香津美のデュオアルバムでも取り上げられていたが、はやっているのかな。歌が入ってるなら、Joniのオリジナルの録音がいいなぁと思ってしまう。鬼怒の書いた"空の映写技師"は"Three Colors of the Sky"と同じくらい泣けてきそうないい曲。どこかで聴いたことがあるような覚えがあるのだが、気のせだろうか。初回限定版は3曲入った2枚目がついていて、"It's only Paper Moon"なんかとてもいいので、売ってたならこっちを買わないと損。3枚目は鬼怒色を出して、全曲即興演奏とかどうでしょう。この2人での"Crawler"なんていうのも聴いてみたいので、2枚組ライブアルバムにして1枚は完全即興にしちゃうとか。
 The Duo / Cinema Voyage : 鬼怒無月と鈴木大介のThe DUOの新作が出!2作目。映画音楽集、ってことは鈴木の方の趣味なんだろうか。ファーストアルバムは、2人のギタリストの対比がおもしろかったのだが、この作品は2人が溶け合っているように聴こえる。ユニットとして演奏回数が増えたからかなと思ったのだが、何回か繰り返して聴いているうちに、アレンジが緻密にされているからだということに気がついた。ぼーとBGMにして聴いていても問題ないくらい緻密で美しい。選曲もとてもいい。普通なら"Libertango"に耳が行くのかな。"Over the Rainbow"〜"What a Wonderful World"がとてもいい。サッチモよりいい。"Both Sides Now"は、最近でた吉田美奈子と渡辺香津美のデュオアルバムでも取り上げられていたが、はやっているのかな。歌が入ってるなら、Joniのオリジナルの録音がいいなぁと思ってしまう。鬼怒の書いた"空の映写技師"は"Three Colors of the Sky"と同じくらい泣けてきそうないい曲。どこかで聴いたことがあるような覚えがあるのだが、気のせだろうか。初回限定版は3曲入った2枚目がついていて、"It's only Paper Moon"なんかとてもいいので、売ってたならこっちを買わないと損。3枚目は鬼怒色を出して、全曲即興演奏とかどうでしょう。この2人での"Crawler"なんていうのも聴いてみたいので、2枚組ライブアルバムにして1枚は完全即興にしちゃうとか。
The Duo / Cinema Voyage : 鬼怒無月と鈴木大介のThe DUOの新作が出!2作目。映画音楽集、ってことは鈴木の方の趣味なんだろうか。ファーストアルバムは、2人のギタリストの対比がおもしろかったのだが、この作品は2人が溶け合っているように聴こえる。ユニットとして演奏回数が増えたからかなと思ったのだが、何回か繰り返して聴いているうちに、アレンジが緻密にされているからだということに気がついた。ぼーとBGMにして聴いていても問題ないくらい緻密で美しい。選曲もとてもいい。普通なら"Libertango"に耳が行くのかな。"Over the Rainbow"〜"What a Wonderful World"がとてもいい。サッチモよりいい。"Both Sides Now"は、最近でた吉田美奈子と渡辺香津美のデュオアルバムでも取り上げられていたが、はやっているのかな。歌が入ってるなら、Joniのオリジナルの録音がいいなぁと思ってしまう。鬼怒の書いた"空の映写技師"は"Three Colors of the Sky"と同じくらい泣けてきそうないい曲。どこかで聴いたことがあるような覚えがあるのだが、気のせだろうか。初回限定版は3曲入った2枚目がついていて、"It's only Paper Moon"なんかとてもいいので、売ってたならこっちを買わないと損。3枚目は鬼怒色を出して、全曲即興演奏とかどうでしょう。この2人での"Crawler"なんていうのも聴いてみたいので、2枚組ライブアルバムにして1枚は完全即興にしちゃうとか。Oct.18 CD : Gulda
 Gulda : Plays Bach : グルダの新譜「プレイズ・バッハ」。モーツァルトのお蔵出しテープに続き、バッハのライブ録音のお蔵だし。監修は息子のパウル・グルダ。55年から69年までのベルリンでのライブテープで、トッカータとカプリッチオがグルダの個人録音(モノラル)、残りがベルリンの放送局の録音。音質はどれもよく、どの演奏もグルダ好きなら感動できる演奏。
イギリス組曲の第2番は、これまで録音がなかったのではないだろうか。弟子(?)のアルゲリッチがめずらしく録音しているバッハの曲ではあるが。第3番は「グルダ・ワークス("The Complete Musician Gulda")」にサラバンドだけ録音がある。どちらも、グルダらしく躍動感のあるリズムを強調した演奏で、絶対踊れないスピード。第2番の方は少し弾き飛ばしている印象を受けるが、第3番の方は完成度が高い。こんなライブを聴いてみたかった。
イタリア協奏曲は、ピアノでのスタジオ録音があるが、それは意外とおとなしく、楷書的な演奏で、グールドの古いほうの刺激的な速さの演奏に比べると、ちと物足りない。グルダはもうひとつ「世界音楽物語」に、クラヴィコードで弾いた第3楽章の演奏が残っているが、このアルバムの録音はこちらに近い。第2楽章の歌わせ方にしても、このアルバムの演奏がいい。
トッカータ BWV911も、フーガの部分がデッカのモノラル録音が残っている。その丁寧な演奏に比べると、歌い回しなどライブならではのノリが出ていて、非常にいい。どうしてグルダはもっとバッハの録音を残してくれなかったのだろうか。
カプリッチオ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」は、あまり好きな曲ではないのだが、フーガの演奏がやはりグルダらしくて楽しめた。
最後はバッハと関係なく、自作の「プレリュードとフーガ」。「グルダ・ノンストップ」のころの演奏になると、シンコペーションを強調した崩した演奏になってしまうのだが、まだ丁寧にひかれている。タワレコのコメントも、HMVのサイトも、レコード会社であるユニバーサルの記事をそのまま引用して「グルダがジャズ風にアレンジした」と書いている。この曲は完全に自作なんだけどな。キース・エマーソンも弾いてるし、最近はアムランの録音もでたのに。レコード会社のくせに間違うのももってのほかだが、ショップの方も、ちょっと調べたり聴いてみればわかることなのに、書いている人や担当者の質が落ちてるな、と思うちょっとしたことだ。
Gulda : Plays Bach : グルダの新譜「プレイズ・バッハ」。モーツァルトのお蔵出しテープに続き、バッハのライブ録音のお蔵だし。監修は息子のパウル・グルダ。55年から69年までのベルリンでのライブテープで、トッカータとカプリッチオがグルダの個人録音(モノラル)、残りがベルリンの放送局の録音。音質はどれもよく、どの演奏もグルダ好きなら感動できる演奏。
イギリス組曲の第2番は、これまで録音がなかったのではないだろうか。弟子(?)のアルゲリッチがめずらしく録音しているバッハの曲ではあるが。第3番は「グルダ・ワークス("The Complete Musician Gulda")」にサラバンドだけ録音がある。どちらも、グルダらしく躍動感のあるリズムを強調した演奏で、絶対踊れないスピード。第2番の方は少し弾き飛ばしている印象を受けるが、第3番の方は完成度が高い。こんなライブを聴いてみたかった。
イタリア協奏曲は、ピアノでのスタジオ録音があるが、それは意外とおとなしく、楷書的な演奏で、グールドの古いほうの刺激的な速さの演奏に比べると、ちと物足りない。グルダはもうひとつ「世界音楽物語」に、クラヴィコードで弾いた第3楽章の演奏が残っているが、このアルバムの録音はこちらに近い。第2楽章の歌わせ方にしても、このアルバムの演奏がいい。
トッカータ BWV911も、フーガの部分がデッカのモノラル録音が残っている。その丁寧な演奏に比べると、歌い回しなどライブならではのノリが出ていて、非常にいい。どうしてグルダはもっとバッハの録音を残してくれなかったのだろうか。
カプリッチオ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」は、あまり好きな曲ではないのだが、フーガの演奏がやはりグルダらしくて楽しめた。
最後はバッハと関係なく、自作の「プレリュードとフーガ」。「グルダ・ノンストップ」のころの演奏になると、シンコペーションを強調した崩した演奏になってしまうのだが、まだ丁寧にひかれている。タワレコのコメントも、HMVのサイトも、レコード会社であるユニバーサルの記事をそのまま引用して「グルダがジャズ風にアレンジした」と書いている。この曲は完全に自作なんだけどな。キース・エマーソンも弾いてるし、最近はアムランの録音もでたのに。レコード会社のくせに間違うのももってのほかだが、ショップの方も、ちょっと調べたり聴いてみればわかることなのに、書いている人や担当者の質が落ちてるな、と思うちょっとしたことだ。
 Gulda : Plays Bach : グルダの新譜「プレイズ・バッハ」。モーツァルトのお蔵出しテープに続き、バッハのライブ録音のお蔵だし。監修は息子のパウル・グルダ。55年から69年までのベルリンでのライブテープで、トッカータとカプリッチオがグルダの個人録音(モノラル)、残りがベルリンの放送局の録音。音質はどれもよく、どの演奏もグルダ好きなら感動できる演奏。
イギリス組曲の第2番は、これまで録音がなかったのではないだろうか。弟子(?)のアルゲリッチがめずらしく録音しているバッハの曲ではあるが。第3番は「グルダ・ワークス("The Complete Musician Gulda")」にサラバンドだけ録音がある。どちらも、グルダらしく躍動感のあるリズムを強調した演奏で、絶対踊れないスピード。第2番の方は少し弾き飛ばしている印象を受けるが、第3番の方は完成度が高い。こんなライブを聴いてみたかった。
イタリア協奏曲は、ピアノでのスタジオ録音があるが、それは意外とおとなしく、楷書的な演奏で、グールドの古いほうの刺激的な速さの演奏に比べると、ちと物足りない。グルダはもうひとつ「世界音楽物語」に、クラヴィコードで弾いた第3楽章の演奏が残っているが、このアルバムの録音はこちらに近い。第2楽章の歌わせ方にしても、このアルバムの演奏がいい。
トッカータ BWV911も、フーガの部分がデッカのモノラル録音が残っている。その丁寧な演奏に比べると、歌い回しなどライブならではのノリが出ていて、非常にいい。どうしてグルダはもっとバッハの録音を残してくれなかったのだろうか。
カプリッチオ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」は、あまり好きな曲ではないのだが、フーガの演奏がやはりグルダらしくて楽しめた。
最後はバッハと関係なく、自作の「プレリュードとフーガ」。「グルダ・ノンストップ」のころの演奏になると、シンコペーションを強調した崩した演奏になってしまうのだが、まだ丁寧にひかれている。タワレコのコメントも、HMVのサイトも、レコード会社であるユニバーサルの記事をそのまま引用して「グルダがジャズ風にアレンジした」と書いている。この曲は完全に自作なんだけどな。キース・エマーソンも弾いてるし、最近はアムランの録音もでたのに。レコード会社のくせに間違うのももってのほかだが、ショップの方も、ちょっと調べたり聴いてみればわかることなのに、書いている人や担当者の質が落ちてるな、と思うちょっとしたことだ。
Gulda : Plays Bach : グルダの新譜「プレイズ・バッハ」。モーツァルトのお蔵出しテープに続き、バッハのライブ録音のお蔵だし。監修は息子のパウル・グルダ。55年から69年までのベルリンでのライブテープで、トッカータとカプリッチオがグルダの個人録音(モノラル)、残りがベルリンの放送局の録音。音質はどれもよく、どの演奏もグルダ好きなら感動できる演奏。
イギリス組曲の第2番は、これまで録音がなかったのではないだろうか。弟子(?)のアルゲリッチがめずらしく録音しているバッハの曲ではあるが。第3番は「グルダ・ワークス("The Complete Musician Gulda")」にサラバンドだけ録音がある。どちらも、グルダらしく躍動感のあるリズムを強調した演奏で、絶対踊れないスピード。第2番の方は少し弾き飛ばしている印象を受けるが、第3番の方は完成度が高い。こんなライブを聴いてみたかった。
イタリア協奏曲は、ピアノでのスタジオ録音があるが、それは意外とおとなしく、楷書的な演奏で、グールドの古いほうの刺激的な速さの演奏に比べると、ちと物足りない。グルダはもうひとつ「世界音楽物語」に、クラヴィコードで弾いた第3楽章の演奏が残っているが、このアルバムの録音はこちらに近い。第2楽章の歌わせ方にしても、このアルバムの演奏がいい。
トッカータ BWV911も、フーガの部分がデッカのモノラル録音が残っている。その丁寧な演奏に比べると、歌い回しなどライブならではのノリが出ていて、非常にいい。どうしてグルダはもっとバッハの録音を残してくれなかったのだろうか。
カプリッチオ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」は、あまり好きな曲ではないのだが、フーガの演奏がやはりグルダらしくて楽しめた。
最後はバッハと関係なく、自作の「プレリュードとフーガ」。「グルダ・ノンストップ」のころの演奏になると、シンコペーションを強調した崩した演奏になってしまうのだが、まだ丁寧にひかれている。タワレコのコメントも、HMVのサイトも、レコード会社であるユニバーサルの記事をそのまま引用して「グルダがジャズ風にアレンジした」と書いている。この曲は完全に自作なんだけどな。キース・エマーソンも弾いてるし、最近はアムランの録音もでたのに。レコード会社のくせに間違うのももってのほかだが、ショップの方も、ちょっと調べたり聴いてみればわかることなのに、書いている人や担当者の質が落ちてるな、と思うちょっとしたことだ。Oct.18 CD : Blechacz
 Blechacz : Haydn / Piano Sonata No.52 : ブレハッチの古典派ソナタ集。グラモフォンでの2枚目。1枚目はショパン集だったのでスルーしたが、このアルバムはとてもいいと後輩が勧めたので購入。ハイドンの52番、ベートーヴェンの2番、モーツァルトの9番。確かに巧いし、ピアノのコントロールもすばらしい。ハイドンは特に重厚さと堅さがあって、古典的な構築を前に出していて、休符も聴こえて聴くるような演奏だ。ベートーヴェンも同様の演奏。ただ、モーツァルトはもう少し聴かせどころがあってもいいんじゃないのかなという仕上がりになってしまっている。
Blechacz : Haydn / Piano Sonata No.52 : ブレハッチの古典派ソナタ集。グラモフォンでの2枚目。1枚目はショパン集だったのでスルーしたが、このアルバムはとてもいいと後輩が勧めたので購入。ハイドンの52番、ベートーヴェンの2番、モーツァルトの9番。確かに巧いし、ピアノのコントロールもすばらしい。ハイドンは特に重厚さと堅さがあって、古典的な構築を前に出していて、休符も聴こえて聴くるような演奏だ。ベートーヴェンも同様の演奏。ただ、モーツァルトはもう少し聴かせどころがあってもいいんじゃないのかなという仕上がりになってしまっている。
 Blechacz : Haydn / Piano Sonata No.52 : ブレハッチの古典派ソナタ集。グラモフォンでの2枚目。1枚目はショパン集だったのでスルーしたが、このアルバムはとてもいいと後輩が勧めたので購入。ハイドンの52番、ベートーヴェンの2番、モーツァルトの9番。確かに巧いし、ピアノのコントロールもすばらしい。ハイドンは特に重厚さと堅さがあって、古典的な構築を前に出していて、休符も聴こえて聴くるような演奏だ。ベートーヴェンも同様の演奏。ただ、モーツァルトはもう少し聴かせどころがあってもいいんじゃないのかなという仕上がりになってしまっている。
Blechacz : Haydn / Piano Sonata No.52 : ブレハッチの古典派ソナタ集。グラモフォンでの2枚目。1枚目はショパン集だったのでスルーしたが、このアルバムはとてもいいと後輩が勧めたので購入。ハイドンの52番、ベートーヴェンの2番、モーツァルトの9番。確かに巧いし、ピアノのコントロールもすばらしい。ハイドンは特に重厚さと堅さがあって、古典的な構築を前に出していて、休符も聴こえて聴くるような演奏だ。ベートーヴェンも同様の演奏。ただ、モーツァルトはもう少し聴かせどころがあってもいいんじゃないのかなという仕上がりになってしまっている。Oct.12 CD : Gulda + Boehm
 Gulda + Boehm + VPO : R.Strauss / Burleske : セルやカラヤンと引き続いて、ベームも1957年のザルツブルク音楽祭のライブ音源がOrfeoから出た。こうやって、毎年50年の著作権が切れたものから順番にCD化していくつもりなのだろうか。ベームは1枚だけで、グルダとのR.シュトラウスのブルレスケとベートヴェンの7番。オケはウィーン・フィル。モノラルだが、音質はいい。少し音量レベルが低い気がする。ブルレスケだが、グルダは非常に音質の悪い録音がデッカに残っているが、ベームはこの曲の録音は初めてではないだろうか。グルダのテンポ設定は快速ぎみなので、あまり面白くないこの曲も楽しく聴くことができた。グルダのピアノの音がいい。ベートーヴェンの交響曲第7番は、1958年にグラモフォンに録音されたベルリン・フィルとの録音があるが、基本的なテンポ設定、解釈は全く同じ。ベルリン・フィルの方はオーケストラが我慢できずに咆哮してしまったりゴリゴリ轟音を出してしまったりしているが、この演奏では適度の熱で抑えられている。特にリズムやビートを強調するわけでもなく、テンポを激しく揺らすわけでも熱くなるわけでもないが、しっかりとした構築感を感じる。70年代以降の弛緩したテンポではなく、ノイエザッハリヒカイトのお手本みたいな演奏。
Gulda + Boehm + VPO : R.Strauss / Burleske : セルやカラヤンと引き続いて、ベームも1957年のザルツブルク音楽祭のライブ音源がOrfeoから出た。こうやって、毎年50年の著作権が切れたものから順番にCD化していくつもりなのだろうか。ベームは1枚だけで、グルダとのR.シュトラウスのブルレスケとベートヴェンの7番。オケはウィーン・フィル。モノラルだが、音質はいい。少し音量レベルが低い気がする。ブルレスケだが、グルダは非常に音質の悪い録音がデッカに残っているが、ベームはこの曲の録音は初めてではないだろうか。グルダのテンポ設定は快速ぎみなので、あまり面白くないこの曲も楽しく聴くことができた。グルダのピアノの音がいい。ベートーヴェンの交響曲第7番は、1958年にグラモフォンに録音されたベルリン・フィルとの録音があるが、基本的なテンポ設定、解釈は全く同じ。ベルリン・フィルの方はオーケストラが我慢できずに咆哮してしまったりゴリゴリ轟音を出してしまったりしているが、この演奏では適度の熱で抑えられている。特にリズムやビートを強調するわけでもなく、テンポを激しく揺らすわけでも熱くなるわけでもないが、しっかりとした構築感を感じる。70年代以降の弛緩したテンポではなく、ノイエザッハリヒカイトのお手本みたいな演奏。
 Gulda + Boehm + VPO : R.Strauss / Burleske : セルやカラヤンと引き続いて、ベームも1957年のザルツブルク音楽祭のライブ音源がOrfeoから出た。こうやって、毎年50年の著作権が切れたものから順番にCD化していくつもりなのだろうか。ベームは1枚だけで、グルダとのR.シュトラウスのブルレスケとベートヴェンの7番。オケはウィーン・フィル。モノラルだが、音質はいい。少し音量レベルが低い気がする。ブルレスケだが、グルダは非常に音質の悪い録音がデッカに残っているが、ベームはこの曲の録音は初めてではないだろうか。グルダのテンポ設定は快速ぎみなので、あまり面白くないこの曲も楽しく聴くことができた。グルダのピアノの音がいい。ベートーヴェンの交響曲第7番は、1958年にグラモフォンに録音されたベルリン・フィルとの録音があるが、基本的なテンポ設定、解釈は全く同じ。ベルリン・フィルの方はオーケストラが我慢できずに咆哮してしまったりゴリゴリ轟音を出してしまったりしているが、この演奏では適度の熱で抑えられている。特にリズムやビートを強調するわけでもなく、テンポを激しく揺らすわけでも熱くなるわけでもないが、しっかりとした構築感を感じる。70年代以降の弛緩したテンポではなく、ノイエザッハリヒカイトのお手本みたいな演奏。
Gulda + Boehm + VPO : R.Strauss / Burleske : セルやカラヤンと引き続いて、ベームも1957年のザルツブルク音楽祭のライブ音源がOrfeoから出た。こうやって、毎年50年の著作権が切れたものから順番にCD化していくつもりなのだろうか。ベームは1枚だけで、グルダとのR.シュトラウスのブルレスケとベートヴェンの7番。オケはウィーン・フィル。モノラルだが、音質はいい。少し音量レベルが低い気がする。ブルレスケだが、グルダは非常に音質の悪い録音がデッカに残っているが、ベームはこの曲の録音は初めてではないだろうか。グルダのテンポ設定は快速ぎみなので、あまり面白くないこの曲も楽しく聴くことができた。グルダのピアノの音がいい。ベートーヴェンの交響曲第7番は、1958年にグラモフォンに録音されたベルリン・フィルとの録音があるが、基本的なテンポ設定、解釈は全く同じ。ベルリン・フィルの方はオーケストラが我慢できずに咆哮してしまったりゴリゴリ轟音を出してしまったりしているが、この演奏では適度の熱で抑えられている。特にリズムやビートを強調するわけでもなく、テンポを激しく揺らすわけでも熱くなるわけでもないが、しっかりとした構築感を感じる。70年代以降の弛緩したテンポではなく、ノイエザッハリヒカイトのお手本みたいな演奏。Oct.12 CD : Artemis Quartet
 Artemis Quartet : Beethoven / String Quartet No.4,8 : アルテミス・カルテットのベートーヴェン。メンバーが変わって2枚目かな。彼らはVirginに7番と11番の録音があり、その他に2番と14番の録音がある。今回は渋く4番と8番(ラズモフスキーの2番)。最近、カップリングのせいなのか、初期のカルテットを聴く機会が多い気がする。まず、4番だが熱気があってテンポが速い。ハーゲン・カルテットのものとタイミングはそれほど変わらないと思うが、ハーゲンより速い。メンバーが変わっても音楽的にリーダー格はチェロのスキンヘッドさんなので、低音が厚い。そのために、曲がとても立体的に聴こえる。8番も、終楽章なんて「フルトヴェングラーかよ」と思うようなテンポの揺らし方もある。東京カルテットの演奏の楷書的な演奏と聴き比べるとまるで違う印象を受ける。とてもドイツ的な印象で面白い。
Artemis Quartet : Beethoven / String Quartet No.4,8 : アルテミス・カルテットのベートーヴェン。メンバーが変わって2枚目かな。彼らはVirginに7番と11番の録音があり、その他に2番と14番の録音がある。今回は渋く4番と8番(ラズモフスキーの2番)。最近、カップリングのせいなのか、初期のカルテットを聴く機会が多い気がする。まず、4番だが熱気があってテンポが速い。ハーゲン・カルテットのものとタイミングはそれほど変わらないと思うが、ハーゲンより速い。メンバーが変わっても音楽的にリーダー格はチェロのスキンヘッドさんなので、低音が厚い。そのために、曲がとても立体的に聴こえる。8番も、終楽章なんて「フルトヴェングラーかよ」と思うようなテンポの揺らし方もある。東京カルテットの演奏の楷書的な演奏と聴き比べるとまるで違う印象を受ける。とてもドイツ的な印象で面白い。
 Artemis Quartet : Beethoven / String Quartet No.4,8 : アルテミス・カルテットのベートーヴェン。メンバーが変わって2枚目かな。彼らはVirginに7番と11番の録音があり、その他に2番と14番の録音がある。今回は渋く4番と8番(ラズモフスキーの2番)。最近、カップリングのせいなのか、初期のカルテットを聴く機会が多い気がする。まず、4番だが熱気があってテンポが速い。ハーゲン・カルテットのものとタイミングはそれほど変わらないと思うが、ハーゲンより速い。メンバーが変わっても音楽的にリーダー格はチェロのスキンヘッドさんなので、低音が厚い。そのために、曲がとても立体的に聴こえる。8番も、終楽章なんて「フルトヴェングラーかよ」と思うようなテンポの揺らし方もある。東京カルテットの演奏の楷書的な演奏と聴き比べるとまるで違う印象を受ける。とてもドイツ的な印象で面白い。
Artemis Quartet : Beethoven / String Quartet No.4,8 : アルテミス・カルテットのベートーヴェン。メンバーが変わって2枚目かな。彼らはVirginに7番と11番の録音があり、その他に2番と14番の録音がある。今回は渋く4番と8番(ラズモフスキーの2番)。最近、カップリングのせいなのか、初期のカルテットを聴く機会が多い気がする。まず、4番だが熱気があってテンポが速い。ハーゲン・カルテットのものとタイミングはそれほど変わらないと思うが、ハーゲンより速い。メンバーが変わっても音楽的にリーダー格はチェロのスキンヘッドさんなので、低音が厚い。そのために、曲がとても立体的に聴こえる。8番も、終楽章なんて「フルトヴェングラーかよ」と思うようなテンポの揺らし方もある。東京カルテットの演奏の楷書的な演奏と聴き比べるとまるで違う印象を受ける。とてもドイツ的な印象で面白い。Oct.12 CD : Hilario Duran
 Hilario Duran / From the Heart : キューバのピアノスト、イラリオ・ドゥランの新作。ビッグバンド編成。前作「New Danzon」と同じく、ドラムをオラシオ・エルナンデスが叩いているので購入。オラシオは、一時期ほど日本に来なくなってしまったのでさびしい。いきなりチューチョ・ヴァルデスの曲だし、イラケレのようにわかりやすい全編ラテンサウンドで、前作ほど難しい感じがしない。といっても、無駄に盛り上がるわけではなく抑制された感じがあり、必要以上に熱くるしくならない。そこがオサレなのかな。ビッグバンドも、めちゃめちゃうまくて気持ちがいいほどそろっている。
Hilario Duran / From the Heart : キューバのピアノスト、イラリオ・ドゥランの新作。ビッグバンド編成。前作「New Danzon」と同じく、ドラムをオラシオ・エルナンデスが叩いているので購入。オラシオは、一時期ほど日本に来なくなってしまったのでさびしい。いきなりチューチョ・ヴァルデスの曲だし、イラケレのようにわかりやすい全編ラテンサウンドで、前作ほど難しい感じがしない。といっても、無駄に盛り上がるわけではなく抑制された感じがあり、必要以上に熱くるしくならない。そこがオサレなのかな。ビッグバンドも、めちゃめちゃうまくて気持ちがいいほどそろっている。
 Hilario Duran / From the Heart : キューバのピアノスト、イラリオ・ドゥランの新作。ビッグバンド編成。前作「New Danzon」と同じく、ドラムをオラシオ・エルナンデスが叩いているので購入。オラシオは、一時期ほど日本に来なくなってしまったのでさびしい。いきなりチューチョ・ヴァルデスの曲だし、イラケレのようにわかりやすい全編ラテンサウンドで、前作ほど難しい感じがしない。といっても、無駄に盛り上がるわけではなく抑制された感じがあり、必要以上に熱くるしくならない。そこがオサレなのかな。ビッグバンドも、めちゃめちゃうまくて気持ちがいいほどそろっている。
Hilario Duran / From the Heart : キューバのピアノスト、イラリオ・ドゥランの新作。ビッグバンド編成。前作「New Danzon」と同じく、ドラムをオラシオ・エルナンデスが叩いているので購入。オラシオは、一時期ほど日本に来なくなってしまったのでさびしい。いきなりチューチョ・ヴァルデスの曲だし、イラケレのようにわかりやすい全編ラテンサウンドで、前作ほど難しい感じがしない。といっても、無駄に盛り上がるわけではなく抑制された感じがあり、必要以上に熱くるしくならない。そこがオサレなのかな。ビッグバンドも、めちゃめちゃうまくて気持ちがいいほどそろっている。Oct.12 CD : 渡辺香津美 + 吉田美奈子
 渡辺香津美 + 吉田美奈子 / Nowadays : 吉田美奈子と渡辺香津美のデュオ。二人による声とギターのみで、他の楽器はナシ。すでにこの二人は、香津美のアコースティックギタープロジェクトの3作目「ギタールネッサンス3」の"翼"(武満の曲)で録音がある。全曲カバーで、1曲めがドアーズの"ハートに火をつけて"というのも意外でカッコいい。吉田の歌い方は独特なので、ストレートなロックやストレートなジャズを聴くと、ちょっと意外に感じるが、こういうものかと思えば慣れなくもない。"Come Sunday"がよくはまっているかな。ギターはエレキギターも使っているが、基本的には「ギタールネッサンス」の延長。、"I wish You Love"でのエフェクターの使い方が素晴らしい。あと、"Good Bye Pork Pie Hat"のエレキギターはちょっとカッコ悪いかな。特設サイトで、使っているギターの細かな解説がある。
渡辺香津美 + 吉田美奈子 / Nowadays : 吉田美奈子と渡辺香津美のデュオ。二人による声とギターのみで、他の楽器はナシ。すでにこの二人は、香津美のアコースティックギタープロジェクトの3作目「ギタールネッサンス3」の"翼"(武満の曲)で録音がある。全曲カバーで、1曲めがドアーズの"ハートに火をつけて"というのも意外でカッコいい。吉田の歌い方は独特なので、ストレートなロックやストレートなジャズを聴くと、ちょっと意外に感じるが、こういうものかと思えば慣れなくもない。"Come Sunday"がよくはまっているかな。ギターはエレキギターも使っているが、基本的には「ギタールネッサンス」の延長。、"I wish You Love"でのエフェクターの使い方が素晴らしい。あと、"Good Bye Pork Pie Hat"のエレキギターはちょっとカッコ悪いかな。特設サイトで、使っているギターの細かな解説がある。
 渡辺香津美 + 吉田美奈子 / Nowadays : 吉田美奈子と渡辺香津美のデュオ。二人による声とギターのみで、他の楽器はナシ。すでにこの二人は、香津美のアコースティックギタープロジェクトの3作目「ギタールネッサンス3」の"翼"(武満の曲)で録音がある。全曲カバーで、1曲めがドアーズの"ハートに火をつけて"というのも意外でカッコいい。吉田の歌い方は独特なので、ストレートなロックやストレートなジャズを聴くと、ちょっと意外に感じるが、こういうものかと思えば慣れなくもない。"Come Sunday"がよくはまっているかな。ギターはエレキギターも使っているが、基本的には「ギタールネッサンス」の延長。、"I wish You Love"でのエフェクターの使い方が素晴らしい。あと、"Good Bye Pork Pie Hat"のエレキギターはちょっとカッコ悪いかな。特設サイトで、使っているギターの細かな解説がある。
渡辺香津美 + 吉田美奈子 / Nowadays : 吉田美奈子と渡辺香津美のデュオ。二人による声とギターのみで、他の楽器はナシ。すでにこの二人は、香津美のアコースティックギタープロジェクトの3作目「ギタールネッサンス3」の"翼"(武満の曲)で録音がある。全曲カバーで、1曲めがドアーズの"ハートに火をつけて"というのも意外でカッコいい。吉田の歌い方は独特なので、ストレートなロックやストレートなジャズを聴くと、ちょっと意外に感じるが、こういうものかと思えば慣れなくもない。"Come Sunday"がよくはまっているかな。ギターはエレキギターも使っているが、基本的には「ギタールネッサンス」の延長。、"I wish You Love"でのエフェクターの使い方が素晴らしい。あと、"Good Bye Pork Pie Hat"のエレキギターはちょっとカッコ悪いかな。特設サイトで、使っているギターの細かな解説がある。Oct.12 CD : Giovanni Allevi
 Giovanni Allevi / Joy : 何カ月か前からタワレコのワールドミュージックのコーナーに並んでいて、そのジャケットの風貌は気になっていたが、ちらっと視聴してイージーリスニング系だと勘違いしたままになっていた。先日、Blue NoteにJohn Scofieldを聴きに行って待っている間、ここ数か月にBlue Noteに来日するアーチストのプロモーションのビデオをボーと見ていた。そのときに、けっこうプログレちっくなメロディでいいなぁと思うピアノの音が流れた。それが、このジョヴァンニ・アレヴィだった。イージーリスニングとか言ってすみませんでした。ぱっと聴くとBGMとして聞き流せそうなんだが、メロディやコード進行に癖があり、きれいに聴き心地良くまとめようというだけでないところがいいのかな。キース・エマーソンやパトリック・モラーツのピアノソロ曲といわれても(タッチは全然違うし、アレヴィの方がはるかにうまいが)おかしくない。Blue Noteで見た映像はもっと激しく弾いていたので、ライブではもっとエモーショナルな演奏をするのかもしれない。"Water Dance"や"Vento d'Europa"が好み。風景や青い空が見えるような南欧風の音が多い。
Giovanni Allevi / Joy : 何カ月か前からタワレコのワールドミュージックのコーナーに並んでいて、そのジャケットの風貌は気になっていたが、ちらっと視聴してイージーリスニング系だと勘違いしたままになっていた。先日、Blue NoteにJohn Scofieldを聴きに行って待っている間、ここ数か月にBlue Noteに来日するアーチストのプロモーションのビデオをボーと見ていた。そのときに、けっこうプログレちっくなメロディでいいなぁと思うピアノの音が流れた。それが、このジョヴァンニ・アレヴィだった。イージーリスニングとか言ってすみませんでした。ぱっと聴くとBGMとして聞き流せそうなんだが、メロディやコード進行に癖があり、きれいに聴き心地良くまとめようというだけでないところがいいのかな。キース・エマーソンやパトリック・モラーツのピアノソロ曲といわれても(タッチは全然違うし、アレヴィの方がはるかにうまいが)おかしくない。Blue Noteで見た映像はもっと激しく弾いていたので、ライブではもっとエモーショナルな演奏をするのかもしれない。"Water Dance"や"Vento d'Europa"が好み。風景や青い空が見えるような南欧風の音が多い。
 Giovanni Allevi / Joy : 何カ月か前からタワレコのワールドミュージックのコーナーに並んでいて、そのジャケットの風貌は気になっていたが、ちらっと視聴してイージーリスニング系だと勘違いしたままになっていた。先日、Blue NoteにJohn Scofieldを聴きに行って待っている間、ここ数か月にBlue Noteに来日するアーチストのプロモーションのビデオをボーと見ていた。そのときに、けっこうプログレちっくなメロディでいいなぁと思うピアノの音が流れた。それが、このジョヴァンニ・アレヴィだった。イージーリスニングとか言ってすみませんでした。ぱっと聴くとBGMとして聞き流せそうなんだが、メロディやコード進行に癖があり、きれいに聴き心地良くまとめようというだけでないところがいいのかな。キース・エマーソンやパトリック・モラーツのピアノソロ曲といわれても(タッチは全然違うし、アレヴィの方がはるかにうまいが)おかしくない。Blue Noteで見た映像はもっと激しく弾いていたので、ライブではもっとエモーショナルな演奏をするのかもしれない。"Water Dance"や"Vento d'Europa"が好み。風景や青い空が見えるような南欧風の音が多い。
Giovanni Allevi / Joy : 何カ月か前からタワレコのワールドミュージックのコーナーに並んでいて、そのジャケットの風貌は気になっていたが、ちらっと視聴してイージーリスニング系だと勘違いしたままになっていた。先日、Blue NoteにJohn Scofieldを聴きに行って待っている間、ここ数か月にBlue Noteに来日するアーチストのプロモーションのビデオをボーと見ていた。そのときに、けっこうプログレちっくなメロディでいいなぁと思うピアノの音が流れた。それが、このジョヴァンニ・アレヴィだった。イージーリスニングとか言ってすみませんでした。ぱっと聴くとBGMとして聞き流せそうなんだが、メロディやコード進行に癖があり、きれいに聴き心地良くまとめようというだけでないところがいいのかな。キース・エマーソンやパトリック・モラーツのピアノソロ曲といわれても(タッチは全然違うし、アレヴィの方がはるかにうまいが)おかしくない。Blue Noteで見た映像はもっと激しく弾いていたので、ライブではもっとエモーショナルな演奏をするのかもしれない。"Water Dance"や"Vento d'Europa"が好み。風景や青い空が見えるような南欧風の音が多い。Oct.11 John Scofield + Joe Lovano @ Blue Note 東京 2nd Set
ジョン・スコフィールドのライブに行ってきた。これまで、Uberjamの編成とMMWとのカルテットと2回見ているが、今回はジョー・ロヴァーノとの双頭バンド。ベースはMatt Penman、ドラムはMatt Wilsonと、若手。ブルーノートのセカンドセットで、この来日の最後の公演。曲としてはオーソドックスなジャズだが、スコフィールドのギターは相変わらずウネウネと宇宙人的なフレーズを湧き出していた。何を考えていたらあんなフレーズを思いつくのだろう。また、エフェクトを多用して、ギタープレイと音があっていないようなアンビエントなサウンドも出していたし、ほんとにわけがわからないがカッコいいギタリストだ。テーマ部で、ジョンソコとロヴァーノがメカニカルなフレーズをユニゾンでばっちり決めてしまうところもかっこいい。ロヴァーノは基本的にテナーだが、ソプラノサックスを2本合体させた楽器を吹いていた。ちょっと演奏は荒いと思ったけど、パワーもあったし良いです。ドラムのMatt Wilsonについてはよく知らないのだが、セットがとてもシンプル。シンプルなのだが、全然ワンパターンに陥らずにフロントの二人につけているところを見ると、とてもテクニシャンなのかも知れない。盛り上がったせいか、最終公演だったせいか、アンコールで"Keep in Mind"ともう1曲の2曲演奏してくれた("Big Fun"かな?)。元々ジョンスコは「Blue Matter」「Pick Hits Live」などのファンク期のアルバムが好きでファンになったのだが、「Meant to Be」「Time on my Hands」や「What We Do」などのBlue Noteに在籍していたころのアルバムは、買ってはいるもののピンと来ていなかった。ちょっとJazzすぎて、買った当時は聴きどころがわからなかったのかもしれない。また聴きなおさないといけないな。
Oct.11 CD : Damrau
 Dianna Damrau : Mozart / Arias : ディアナ・ダムラウのモーツァルト・アリア集。Virginからの2枚目。前作は、コロラトゥーラを前面に出した、モーツァルトとサリエリのアリア集だったが、今作は、幅広さを見せるアルバムだ。前作では夜の女王をうたっていた「魔笛」も、パミーナのアリアを、「フィガロ」では伯爵夫人とスザンナのアリアを、「後宮からの誘拐」もコンスタンツェとブロンデを、「ドン・ジョヴァンニ」ではドンナ・アンナとドンナ・エルヴィーラをうたっている。さすがに、ステージ上ではうたったことのない役柄もあるだろうが(レパートリーは確認できますね)、どれも素晴らしく聴こえる。役柄の違いを演じ分けてはいるのだろうが、彼女は技巧と声量が素晴らしすぎるので、どれもダムラウのすごさがまず耳についてしまう。変なたとえを使うならカラヤンとベルリンフィルみたいなものだ。オケも前作と同じピリオド系のオケ。総合すると、脇をみせたジャケット写真にひっかかるかどうかということかな。僕はかなりダマされています。
Dianna Damrau : Mozart / Arias : ディアナ・ダムラウのモーツァルト・アリア集。Virginからの2枚目。前作は、コロラトゥーラを前面に出した、モーツァルトとサリエリのアリア集だったが、今作は、幅広さを見せるアルバムだ。前作では夜の女王をうたっていた「魔笛」も、パミーナのアリアを、「フィガロ」では伯爵夫人とスザンナのアリアを、「後宮からの誘拐」もコンスタンツェとブロンデを、「ドン・ジョヴァンニ」ではドンナ・アンナとドンナ・エルヴィーラをうたっている。さすがに、ステージ上ではうたったことのない役柄もあるだろうが(レパートリーは確認できますね)、どれも素晴らしく聴こえる。役柄の違いを演じ分けてはいるのだろうが、彼女は技巧と声量が素晴らしすぎるので、どれもダムラウのすごさがまず耳についてしまう。変なたとえを使うならカラヤンとベルリンフィルみたいなものだ。オケも前作と同じピリオド系のオケ。総合すると、脇をみせたジャケット写真にひっかかるかどうかということかな。僕はかなりダマされています。
 Dianna Damrau : Mozart / Arias : ディアナ・ダムラウのモーツァルト・アリア集。Virginからの2枚目。前作は、コロラトゥーラを前面に出した、モーツァルトとサリエリのアリア集だったが、今作は、幅広さを見せるアルバムだ。前作では夜の女王をうたっていた「魔笛」も、パミーナのアリアを、「フィガロ」では伯爵夫人とスザンナのアリアを、「後宮からの誘拐」もコンスタンツェとブロンデを、「ドン・ジョヴァンニ」ではドンナ・アンナとドンナ・エルヴィーラをうたっている。さすがに、ステージ上ではうたったことのない役柄もあるだろうが(レパートリーは確認できますね)、どれも素晴らしく聴こえる。役柄の違いを演じ分けてはいるのだろうが、彼女は技巧と声量が素晴らしすぎるので、どれもダムラウのすごさがまず耳についてしまう。変なたとえを使うならカラヤンとベルリンフィルみたいなものだ。オケも前作と同じピリオド系のオケ。総合すると、脇をみせたジャケット写真にひっかかるかどうかということかな。僕はかなりダマされています。
Dianna Damrau : Mozart / Arias : ディアナ・ダムラウのモーツァルト・アリア集。Virginからの2枚目。前作は、コロラトゥーラを前面に出した、モーツァルトとサリエリのアリア集だったが、今作は、幅広さを見せるアルバムだ。前作では夜の女王をうたっていた「魔笛」も、パミーナのアリアを、「フィガロ」では伯爵夫人とスザンナのアリアを、「後宮からの誘拐」もコンスタンツェとブロンデを、「ドン・ジョヴァンニ」ではドンナ・アンナとドンナ・エルヴィーラをうたっている。さすがに、ステージ上ではうたったことのない役柄もあるだろうが(レパートリーは確認できますね)、どれも素晴らしく聴こえる。役柄の違いを演じ分けてはいるのだろうが、彼女は技巧と声量が素晴らしすぎるので、どれもダムラウのすごさがまず耳についてしまう。変なたとえを使うならカラヤンとベルリンフィルみたいなものだ。オケも前作と同じピリオド系のオケ。総合すると、脇をみせたジャケット写真にひっかかるかどうかということかな。僕はかなりダマされています。Oct.11 CD : Pahud
 Emmanuel Pahud : Bach / Sonatas : 数ヶ月前に出たアルバムは現代作曲家による協奏曲だったが、新録音はバッハ集。著名なフルート吹きには多いが、この幅の広さもパユ様のいいところ。2枚組で真作も偽作と言われているものも収録している。演奏はもう文句ないです。理想の演奏というものを想定すると、それ具現化する技術をパユは持っている。ブレスコントロール、トリルのタイミング、あらゆることがよく考えられていることが聴きとれ、それにより曲の良さを再認識することができる。音色は少し明るめで抜けがいいので、好みによっては気に入らないかもしれない。我が家にはニコレ、ゴールウェイの録音があり、パユのを聴くにあたり聴き返してみた。あー全員ベルリンフィルのトップだ…。ゴールウェイのものは少しクールで涼しい感じ。意外だったのはニコレのものが面白かったことだ。たぶん中学生のころ初めてバッハのフルートソナタを聴いたのもこのアルヒーフの録音のはずだが、当時は当たり前のようにつまらなく感じた気がする。おそらく曲がわからなかったんだろう。息づかい、息の切れ目、歌い回し、音の厚さ、どれもが素晴らしく聴こえる。ゴールウェイと比較するとよくわかるが、ドイツの音がするのも気に入った原因だろう。当分楽しめそうだ。
Emmanuel Pahud : Bach / Sonatas : 数ヶ月前に出たアルバムは現代作曲家による協奏曲だったが、新録音はバッハ集。著名なフルート吹きには多いが、この幅の広さもパユ様のいいところ。2枚組で真作も偽作と言われているものも収録している。演奏はもう文句ないです。理想の演奏というものを想定すると、それ具現化する技術をパユは持っている。ブレスコントロール、トリルのタイミング、あらゆることがよく考えられていることが聴きとれ、それにより曲の良さを再認識することができる。音色は少し明るめで抜けがいいので、好みによっては気に入らないかもしれない。我が家にはニコレ、ゴールウェイの録音があり、パユのを聴くにあたり聴き返してみた。あー全員ベルリンフィルのトップだ…。ゴールウェイのものは少しクールで涼しい感じ。意外だったのはニコレのものが面白かったことだ。たぶん中学生のころ初めてバッハのフルートソナタを聴いたのもこのアルヒーフの録音のはずだが、当時は当たり前のようにつまらなく感じた気がする。おそらく曲がわからなかったんだろう。息づかい、息の切れ目、歌い回し、音の厚さ、どれもが素晴らしく聴こえる。ゴールウェイと比較するとよくわかるが、ドイツの音がするのも気に入った原因だろう。当分楽しめそうだ。
 Emmanuel Pahud : Bach / Sonatas : 数ヶ月前に出たアルバムは現代作曲家による協奏曲だったが、新録音はバッハ集。著名なフルート吹きには多いが、この幅の広さもパユ様のいいところ。2枚組で真作も偽作と言われているものも収録している。演奏はもう文句ないです。理想の演奏というものを想定すると、それ具現化する技術をパユは持っている。ブレスコントロール、トリルのタイミング、あらゆることがよく考えられていることが聴きとれ、それにより曲の良さを再認識することができる。音色は少し明るめで抜けがいいので、好みによっては気に入らないかもしれない。我が家にはニコレ、ゴールウェイの録音があり、パユのを聴くにあたり聴き返してみた。あー全員ベルリンフィルのトップだ…。ゴールウェイのものは少しクールで涼しい感じ。意外だったのはニコレのものが面白かったことだ。たぶん中学生のころ初めてバッハのフルートソナタを聴いたのもこのアルヒーフの録音のはずだが、当時は当たり前のようにつまらなく感じた気がする。おそらく曲がわからなかったんだろう。息づかい、息の切れ目、歌い回し、音の厚さ、どれもが素晴らしく聴こえる。ゴールウェイと比較するとよくわかるが、ドイツの音がするのも気に入った原因だろう。当分楽しめそうだ。
Emmanuel Pahud : Bach / Sonatas : 数ヶ月前に出たアルバムは現代作曲家による協奏曲だったが、新録音はバッハ集。著名なフルート吹きには多いが、この幅の広さもパユ様のいいところ。2枚組で真作も偽作と言われているものも収録している。演奏はもう文句ないです。理想の演奏というものを想定すると、それ具現化する技術をパユは持っている。ブレスコントロール、トリルのタイミング、あらゆることがよく考えられていることが聴きとれ、それにより曲の良さを再認識することができる。音色は少し明るめで抜けがいいので、好みによっては気に入らないかもしれない。我が家にはニコレ、ゴールウェイの録音があり、パユのを聴くにあたり聴き返してみた。あー全員ベルリンフィルのトップだ…。ゴールウェイのものは少しクールで涼しい感じ。意外だったのはニコレのものが面白かったことだ。たぶん中学生のころ初めてバッハのフルートソナタを聴いたのもこのアルヒーフの録音のはずだが、当時は当たり前のようにつまらなく感じた気がする。おそらく曲がわからなかったんだろう。息づかい、息の切れ目、歌い回し、音の厚さ、どれもが素晴らしく聴こえる。ゴールウェイと比較するとよくわかるが、ドイツの音がするのも気に入った原因だろう。当分楽しめそうだ。Oct.5 ポイントカード 続
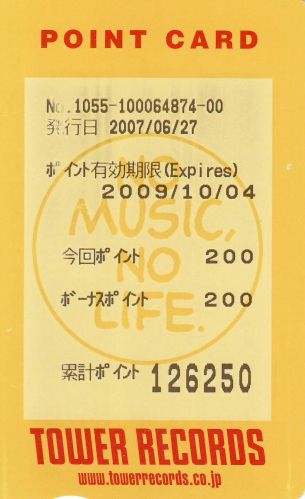 8月9日に、タワーレコードのポイントカードが10万円分たまってどうしよう、みたいなことを書いた。あれから特にポイントを使うこともなくだらだらとため続けていたら、12万5000円分もたまってしまった。タワレコで買い物をしたら「12万円分もたまってるのに、ポイントを使わないんですか?」と怒られた。100万円分くらいためて、一気に使ったら店の人もがっくりくるんだろうか。
8月9日に、タワーレコードのポイントカードが10万円分たまってどうしよう、みたいなことを書いた。あれから特にポイントを使うこともなくだらだらとため続けていたら、12万5000円分もたまってしまった。タワレコで買い物をしたら「12万円分もたまってるのに、ポイントを使わないんですか?」と怒られた。100万円分くらいためて、一気に使ったら店の人もがっくりくるんだろうか。
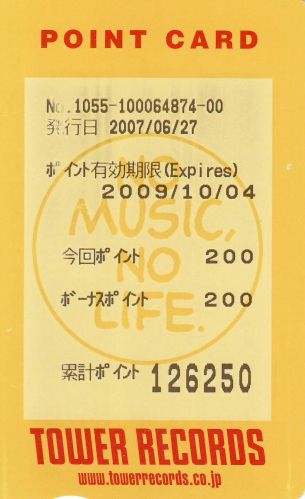 8月9日に、タワーレコードのポイントカードが10万円分たまってどうしよう、みたいなことを書いた。あれから特にポイントを使うこともなくだらだらとため続けていたら、12万5000円分もたまってしまった。タワレコで買い物をしたら「12万円分もたまってるのに、ポイントを使わないんですか?」と怒られた。100万円分くらいためて、一気に使ったら店の人もがっくりくるんだろうか。
8月9日に、タワーレコードのポイントカードが10万円分たまってどうしよう、みたいなことを書いた。あれから特にポイントを使うこともなくだらだらとため続けていたら、12万5000円分もたまってしまった。タワレコで買い物をしたら「12万円分もたまってるのに、ポイントを使わないんですか?」と怒られた。100万円分くらいためて、一気に使ったら店の人もがっくりくるんだろうか。Oct.5 CD : Karajan
 Karajan + BPO + Kempff : Mozart / Piano Concerto No.20 : カラヤン生誕100周年の企画でAuditeレーベルから3点発売された。いずれもDeutschlandradio Kulturの音源によるもので、とても音質がいい。第2弾が、モーツァルトで、ヴィルヘルム・ケンプをソロに迎えたピアノ協奏曲20番と、ジュピター。1956年1月21日の録音で、会場はベルリン・ツェーレンドルフのパウロ派教区信徒会館というところ。まだフィルハーモニーが再建されていない時期なので、会場が変わった場所が多くて面白い。協奏曲の20番だが、この曲は正規録音はないし、ライブでもクララ・ハスキルと演奏することが多かったようで、70年代以降ほとんど演奏されていないようだ。ここでソロを弾いているケンプだが、予想どおりにイマイチ。モーツァルトはエッジが立って粒がそろっている演奏が好きなので、この演奏はいただけない。カデンツなど非常にがっかりするタッチだ。交響曲第41番の方は、若き日のカラヤンがよく言われていたように、颯爽とした切れのいい演奏。ベルリンフィルの首席指揮者になってすぐの演奏であるが、よくコントロールされており気持ちのいい流れ方をする。第4楽章はすこし早すぎるかも。
Karajan + BPO + Kempff : Mozart / Piano Concerto No.20 : カラヤン生誕100周年の企画でAuditeレーベルから3点発売された。いずれもDeutschlandradio Kulturの音源によるもので、とても音質がいい。第2弾が、モーツァルトで、ヴィルヘルム・ケンプをソロに迎えたピアノ協奏曲20番と、ジュピター。1956年1月21日の録音で、会場はベルリン・ツェーレンドルフのパウロ派教区信徒会館というところ。まだフィルハーモニーが再建されていない時期なので、会場が変わった場所が多くて面白い。協奏曲の20番だが、この曲は正規録音はないし、ライブでもクララ・ハスキルと演奏することが多かったようで、70年代以降ほとんど演奏されていないようだ。ここでソロを弾いているケンプだが、予想どおりにイマイチ。モーツァルトはエッジが立って粒がそろっている演奏が好きなので、この演奏はいただけない。カデンツなど非常にがっかりするタッチだ。交響曲第41番の方は、若き日のカラヤンがよく言われていたように、颯爽とした切れのいい演奏。ベルリンフィルの首席指揮者になってすぐの演奏であるが、よくコントロールされており気持ちのいい流れ方をする。第4楽章はすこし早すぎるかも。
 Karajan + BPO : Beethoven / Symphony No.3,9 : これは第3弾で、演奏時期も異なるベートーヴェンが2曲で第3番と第9番。モーツァルトと同じくDeutschlandradio Kulturのアーカイブ。音はモノラルだが鮮明。
1枚目はエロイカ。1953年9月8日で、カラヤンが戦後初めてベルリンフィルを振った時の演奏会だそうだ。前半はバルトークのオケコンだったらしい。会場はフルトヴェングラーの戦後のライブ録音でおなじみの映画館、ティタニア・パラスト。まだ、フルトヴェングラーが生きていて、首席指揮者だった時期だ。フルトヴェングラーの録音で聴くことのできるベルリン・フィルと同じとは思えないほど、オーケストラの音が整理されており、カラヤン風味が出ている。しかし、第4楽章のコーダなどは、オーケストラがアッチェレランドしたくて仕方がないようで、カラヤンのスタジオ録音では聴けないような、テンポアップを聴くことができる。
第9の方は、1957年4月25日、ベルリン高等音楽院大ホールでのライブ録音。ベルリンフィル創立75周年記念演奏会ということで、気合が入っているのだろう。昨年、ラトルが創立125周年の記念演奏会を開いたので、50年前の演奏だ。テノールがヘフリガーなのもいい。第4楽章のダブルフーガのところをとても美しくレガート強調ぎみに演奏するので、リズムがなくなったように聴こえてしまい、個人的には気に入らない。アクセントが全くなくなって、ノンビートに聞こえるのだ。この演奏を聴いて気になったので、他の年代の録音も聴いてみたが、カラヤンの演奏は80年代に至るまで同じなので、彼の解釈なんだろう。
カラヤンはベルリン・フィルの首席指揮者になってからも、オーケストラの音を自分の好みに仕立て上げるまで録音をしたがらなかったようで、1958年にグラモフォンで「英雄の生涯」が録音されるまで、カラヤンとベルリンの正規の録音はなかった。これらの1958年までの録音が聴くことができるのは、カラヤンの本意ではないかもしれないが、彼やベルリン・フィルのファンがその歩みを知る上でとても貴重なことだ。
Karajan + BPO : Beethoven / Symphony No.3,9 : これは第3弾で、演奏時期も異なるベートーヴェンが2曲で第3番と第9番。モーツァルトと同じくDeutschlandradio Kulturのアーカイブ。音はモノラルだが鮮明。
1枚目はエロイカ。1953年9月8日で、カラヤンが戦後初めてベルリンフィルを振った時の演奏会だそうだ。前半はバルトークのオケコンだったらしい。会場はフルトヴェングラーの戦後のライブ録音でおなじみの映画館、ティタニア・パラスト。まだ、フルトヴェングラーが生きていて、首席指揮者だった時期だ。フルトヴェングラーの録音で聴くことのできるベルリン・フィルと同じとは思えないほど、オーケストラの音が整理されており、カラヤン風味が出ている。しかし、第4楽章のコーダなどは、オーケストラがアッチェレランドしたくて仕方がないようで、カラヤンのスタジオ録音では聴けないような、テンポアップを聴くことができる。
第9の方は、1957年4月25日、ベルリン高等音楽院大ホールでのライブ録音。ベルリンフィル創立75周年記念演奏会ということで、気合が入っているのだろう。昨年、ラトルが創立125周年の記念演奏会を開いたので、50年前の演奏だ。テノールがヘフリガーなのもいい。第4楽章のダブルフーガのところをとても美しくレガート強調ぎみに演奏するので、リズムがなくなったように聴こえてしまい、個人的には気に入らない。アクセントが全くなくなって、ノンビートに聞こえるのだ。この演奏を聴いて気になったので、他の年代の録音も聴いてみたが、カラヤンの演奏は80年代に至るまで同じなので、彼の解釈なんだろう。
カラヤンはベルリン・フィルの首席指揮者になってからも、オーケストラの音を自分の好みに仕立て上げるまで録音をしたがらなかったようで、1958年にグラモフォンで「英雄の生涯」が録音されるまで、カラヤンとベルリンの正規の録音はなかった。これらの1958年までの録音が聴くことができるのは、カラヤンの本意ではないかもしれないが、彼やベルリン・フィルのファンがその歩みを知る上でとても貴重なことだ。
 Karajan + BPO + Kempff : Mozart / Piano Concerto No.20 : カラヤン生誕100周年の企画でAuditeレーベルから3点発売された。いずれもDeutschlandradio Kulturの音源によるもので、とても音質がいい。第2弾が、モーツァルトで、ヴィルヘルム・ケンプをソロに迎えたピアノ協奏曲20番と、ジュピター。1956年1月21日の録音で、会場はベルリン・ツェーレンドルフのパウロ派教区信徒会館というところ。まだフィルハーモニーが再建されていない時期なので、会場が変わった場所が多くて面白い。協奏曲の20番だが、この曲は正規録音はないし、ライブでもクララ・ハスキルと演奏することが多かったようで、70年代以降ほとんど演奏されていないようだ。ここでソロを弾いているケンプだが、予想どおりにイマイチ。モーツァルトはエッジが立って粒がそろっている演奏が好きなので、この演奏はいただけない。カデンツなど非常にがっかりするタッチだ。交響曲第41番の方は、若き日のカラヤンがよく言われていたように、颯爽とした切れのいい演奏。ベルリンフィルの首席指揮者になってすぐの演奏であるが、よくコントロールされており気持ちのいい流れ方をする。第4楽章はすこし早すぎるかも。
Karajan + BPO + Kempff : Mozart / Piano Concerto No.20 : カラヤン生誕100周年の企画でAuditeレーベルから3点発売された。いずれもDeutschlandradio Kulturの音源によるもので、とても音質がいい。第2弾が、モーツァルトで、ヴィルヘルム・ケンプをソロに迎えたピアノ協奏曲20番と、ジュピター。1956年1月21日の録音で、会場はベルリン・ツェーレンドルフのパウロ派教区信徒会館というところ。まだフィルハーモニーが再建されていない時期なので、会場が変わった場所が多くて面白い。協奏曲の20番だが、この曲は正規録音はないし、ライブでもクララ・ハスキルと演奏することが多かったようで、70年代以降ほとんど演奏されていないようだ。ここでソロを弾いているケンプだが、予想どおりにイマイチ。モーツァルトはエッジが立って粒がそろっている演奏が好きなので、この演奏はいただけない。カデンツなど非常にがっかりするタッチだ。交響曲第41番の方は、若き日のカラヤンがよく言われていたように、颯爽とした切れのいい演奏。ベルリンフィルの首席指揮者になってすぐの演奏であるが、よくコントロールされており気持ちのいい流れ方をする。第4楽章はすこし早すぎるかも。 Karajan + BPO : Beethoven / Symphony No.3,9 : これは第3弾で、演奏時期も異なるベートーヴェンが2曲で第3番と第9番。モーツァルトと同じくDeutschlandradio Kulturのアーカイブ。音はモノラルだが鮮明。
1枚目はエロイカ。1953年9月8日で、カラヤンが戦後初めてベルリンフィルを振った時の演奏会だそうだ。前半はバルトークのオケコンだったらしい。会場はフルトヴェングラーの戦後のライブ録音でおなじみの映画館、ティタニア・パラスト。まだ、フルトヴェングラーが生きていて、首席指揮者だった時期だ。フルトヴェングラーの録音で聴くことのできるベルリン・フィルと同じとは思えないほど、オーケストラの音が整理されており、カラヤン風味が出ている。しかし、第4楽章のコーダなどは、オーケストラがアッチェレランドしたくて仕方がないようで、カラヤンのスタジオ録音では聴けないような、テンポアップを聴くことができる。
第9の方は、1957年4月25日、ベルリン高等音楽院大ホールでのライブ録音。ベルリンフィル創立75周年記念演奏会ということで、気合が入っているのだろう。昨年、ラトルが創立125周年の記念演奏会を開いたので、50年前の演奏だ。テノールがヘフリガーなのもいい。第4楽章のダブルフーガのところをとても美しくレガート強調ぎみに演奏するので、リズムがなくなったように聴こえてしまい、個人的には気に入らない。アクセントが全くなくなって、ノンビートに聞こえるのだ。この演奏を聴いて気になったので、他の年代の録音も聴いてみたが、カラヤンの演奏は80年代に至るまで同じなので、彼の解釈なんだろう。
カラヤンはベルリン・フィルの首席指揮者になってからも、オーケストラの音を自分の好みに仕立て上げるまで録音をしたがらなかったようで、1958年にグラモフォンで「英雄の生涯」が録音されるまで、カラヤンとベルリンの正規の録音はなかった。これらの1958年までの録音が聴くことができるのは、カラヤンの本意ではないかもしれないが、彼やベルリン・フィルのファンがその歩みを知る上でとても貴重なことだ。
Karajan + BPO : Beethoven / Symphony No.3,9 : これは第3弾で、演奏時期も異なるベートーヴェンが2曲で第3番と第9番。モーツァルトと同じくDeutschlandradio Kulturのアーカイブ。音はモノラルだが鮮明。
1枚目はエロイカ。1953年9月8日で、カラヤンが戦後初めてベルリンフィルを振った時の演奏会だそうだ。前半はバルトークのオケコンだったらしい。会場はフルトヴェングラーの戦後のライブ録音でおなじみの映画館、ティタニア・パラスト。まだ、フルトヴェングラーが生きていて、首席指揮者だった時期だ。フルトヴェングラーの録音で聴くことのできるベルリン・フィルと同じとは思えないほど、オーケストラの音が整理されており、カラヤン風味が出ている。しかし、第4楽章のコーダなどは、オーケストラがアッチェレランドしたくて仕方がないようで、カラヤンのスタジオ録音では聴けないような、テンポアップを聴くことができる。
第9の方は、1957年4月25日、ベルリン高等音楽院大ホールでのライブ録音。ベルリンフィル創立75周年記念演奏会ということで、気合が入っているのだろう。昨年、ラトルが創立125周年の記念演奏会を開いたので、50年前の演奏だ。テノールがヘフリガーなのもいい。第4楽章のダブルフーガのところをとても美しくレガート強調ぎみに演奏するので、リズムがなくなったように聴こえてしまい、個人的には気に入らない。アクセントが全くなくなって、ノンビートに聞こえるのだ。この演奏を聴いて気になったので、他の年代の録音も聴いてみたが、カラヤンの演奏は80年代に至るまで同じなので、彼の解釈なんだろう。
カラヤンはベルリン・フィルの首席指揮者になってからも、オーケストラの音を自分の好みに仕立て上げるまで録音をしたがらなかったようで、1958年にグラモフォンで「英雄の生涯」が録音されるまで、カラヤンとベルリンの正規の録音はなかった。これらの1958年までの録音が聴くことができるのは、カラヤンの本意ではないかもしれないが、彼やベルリン・フィルのファンがその歩みを知る上でとても貴重なことだ。Oct.5 CD : Fotheringay
 Fotheringay / 2 : サンディ・デニーがフェアポート・コンヴェンションを脱退して結成したフォザリンゲイのお蔵入りしたセカンドアルバムが発売された。幻の録音となっていたものを、存命中の、おそらくジェリー・ドナヒューとゲリー・コンウェイがアルバムとしてミックス、マスタリングされたもののようだ。このバンドの解散理由は、単純に売れなくてお金がなかったからだろう。サンディのソロでは、このメンバーは全員参加しているし、ベースのパット・ドナルドソン以外は、全員フェアポート・コンベンションに加入してしまうほどなので仲が悪いというとか音楽性の違いということはなさそうだ。このアルバムに収録されている曲は、のちに再利用されているものが多い。"Knights of the Road"はフェアポートの「Rosie」に、"Restless"はフェアポートの「Rising for the Moon」に、"John the Gun"と"Late November"はサンディーのソロアルバム「The North Star Grassman And The Ravens」で演奏されている("John the Gun"に至ってはフェアポートのレパートリーとして定着している)。サンディのソロの録音に慣れていると「ああギターソロがない」とか「なんか短い」とか感じてしまう。ファースト・アルバムはトレヴァー・ルーカスの志向か、アメリカのカントリーっぽいカラーが強かったのだが、このセカンドは、トラッドを4曲も取り上げている。サンディーがいると、トラッドを歌わないと売れなかったということなのか、サンディーや他のメンバーのカラーによるものなのかはよくわからない(ライナーをちゃんと読めばわかるのかもしれないが)。個人的にはトレヴァーの歌はフェアポートにおいてもイマイチなのだけど(ブリティッシュの香りがしないから)、こういう録音がきちんとした形で出るのはありがたいことなのかもしれない。秋はやはりサンディの声をステレオでかけると落ち着く(そしてちょっと寂しくなる)。夜が寒くなってくるとなぜか毎年"Rising for the Moon"を聴きたくなるのだが、ちょうどいいタイミングで出てくれたアルバムだ。
Fotheringay / 2 : サンディ・デニーがフェアポート・コンヴェンションを脱退して結成したフォザリンゲイのお蔵入りしたセカンドアルバムが発売された。幻の録音となっていたものを、存命中の、おそらくジェリー・ドナヒューとゲリー・コンウェイがアルバムとしてミックス、マスタリングされたもののようだ。このバンドの解散理由は、単純に売れなくてお金がなかったからだろう。サンディのソロでは、このメンバーは全員参加しているし、ベースのパット・ドナルドソン以外は、全員フェアポート・コンベンションに加入してしまうほどなので仲が悪いというとか音楽性の違いということはなさそうだ。このアルバムに収録されている曲は、のちに再利用されているものが多い。"Knights of the Road"はフェアポートの「Rosie」に、"Restless"はフェアポートの「Rising for the Moon」に、"John the Gun"と"Late November"はサンディーのソロアルバム「The North Star Grassman And The Ravens」で演奏されている("John the Gun"に至ってはフェアポートのレパートリーとして定着している)。サンディのソロの録音に慣れていると「ああギターソロがない」とか「なんか短い」とか感じてしまう。ファースト・アルバムはトレヴァー・ルーカスの志向か、アメリカのカントリーっぽいカラーが強かったのだが、このセカンドは、トラッドを4曲も取り上げている。サンディーがいると、トラッドを歌わないと売れなかったということなのか、サンディーや他のメンバーのカラーによるものなのかはよくわからない(ライナーをちゃんと読めばわかるのかもしれないが)。個人的にはトレヴァーの歌はフェアポートにおいてもイマイチなのだけど(ブリティッシュの香りがしないから)、こういう録音がきちんとした形で出るのはありがたいことなのかもしれない。秋はやはりサンディの声をステレオでかけると落ち着く(そしてちょっと寂しくなる)。夜が寒くなってくるとなぜか毎年"Rising for the Moon"を聴きたくなるのだが、ちょうどいいタイミングで出てくれたアルバムだ。
 Fotheringay / 2 : サンディ・デニーがフェアポート・コンヴェンションを脱退して結成したフォザリンゲイのお蔵入りしたセカンドアルバムが発売された。幻の録音となっていたものを、存命中の、おそらくジェリー・ドナヒューとゲリー・コンウェイがアルバムとしてミックス、マスタリングされたもののようだ。このバンドの解散理由は、単純に売れなくてお金がなかったからだろう。サンディのソロでは、このメンバーは全員参加しているし、ベースのパット・ドナルドソン以外は、全員フェアポート・コンベンションに加入してしまうほどなので仲が悪いというとか音楽性の違いということはなさそうだ。このアルバムに収録されている曲は、のちに再利用されているものが多い。"Knights of the Road"はフェアポートの「Rosie」に、"Restless"はフェアポートの「Rising for the Moon」に、"John the Gun"と"Late November"はサンディーのソロアルバム「The North Star Grassman And The Ravens」で演奏されている("John the Gun"に至ってはフェアポートのレパートリーとして定着している)。サンディのソロの録音に慣れていると「ああギターソロがない」とか「なんか短い」とか感じてしまう。ファースト・アルバムはトレヴァー・ルーカスの志向か、アメリカのカントリーっぽいカラーが強かったのだが、このセカンドは、トラッドを4曲も取り上げている。サンディーがいると、トラッドを歌わないと売れなかったということなのか、サンディーや他のメンバーのカラーによるものなのかはよくわからない(ライナーをちゃんと読めばわかるのかもしれないが)。個人的にはトレヴァーの歌はフェアポートにおいてもイマイチなのだけど(ブリティッシュの香りがしないから)、こういう録音がきちんとした形で出るのはありがたいことなのかもしれない。秋はやはりサンディの声をステレオでかけると落ち着く(そしてちょっと寂しくなる)。夜が寒くなってくるとなぜか毎年"Rising for the Moon"を聴きたくなるのだが、ちょうどいいタイミングで出てくれたアルバムだ。
Fotheringay / 2 : サンディ・デニーがフェアポート・コンヴェンションを脱退して結成したフォザリンゲイのお蔵入りしたセカンドアルバムが発売された。幻の録音となっていたものを、存命中の、おそらくジェリー・ドナヒューとゲリー・コンウェイがアルバムとしてミックス、マスタリングされたもののようだ。このバンドの解散理由は、単純に売れなくてお金がなかったからだろう。サンディのソロでは、このメンバーは全員参加しているし、ベースのパット・ドナルドソン以外は、全員フェアポート・コンベンションに加入してしまうほどなので仲が悪いというとか音楽性の違いということはなさそうだ。このアルバムに収録されている曲は、のちに再利用されているものが多い。"Knights of the Road"はフェアポートの「Rosie」に、"Restless"はフェアポートの「Rising for the Moon」に、"John the Gun"と"Late November"はサンディーのソロアルバム「The North Star Grassman And The Ravens」で演奏されている("John the Gun"に至ってはフェアポートのレパートリーとして定着している)。サンディのソロの録音に慣れていると「ああギターソロがない」とか「なんか短い」とか感じてしまう。ファースト・アルバムはトレヴァー・ルーカスの志向か、アメリカのカントリーっぽいカラーが強かったのだが、このセカンドは、トラッドを4曲も取り上げている。サンディーがいると、トラッドを歌わないと売れなかったということなのか、サンディーや他のメンバーのカラーによるものなのかはよくわからない(ライナーをちゃんと読めばわかるのかもしれないが)。個人的にはトレヴァーの歌はフェアポートにおいてもイマイチなのだけど(ブリティッシュの香りがしないから)、こういう録音がきちんとした形で出るのはありがたいことなのかもしれない。秋はやはりサンディの声をステレオでかけると落ち着く(そしてちょっと寂しくなる)。夜が寒くなってくるとなぜか毎年"Rising for the Moon"を聴きたくなるのだが、ちょうどいいタイミングで出てくれたアルバムだ。Oct.1 CD : Figueiredo
 Figueiredo : Soler : Sonatas : フィゲイレドが弾くソレルのソナタ集。フィゲレイドはスカルラッティ集を聴いて気に入り、目白バ・ロック音楽祭にライブも聴きに行った。彼のの弾くチェンバロはなんとなくロックを感じさせるところが好きだ。感情や熱のほとばしり方がロックなのだ。新しい録音はソレールの作品集。ソレールはスカルラッティの弟子で、スペインの作曲家。ラローチャが数曲録音しており、個人的にはハフのStephen Hough's Spanish Album に1曲だけ録音されているのを聴いてとても気に入っていた。まずまとめて作品が聴けるというのがうれしいし、どの曲も熱が入った演奏で飽きない。文句のつけどころがないです。夜、聴いていたら寝れなくなります。最後のファンタンゴは、フィゲレイドがアンコールでよく弾く曲のようで、すばらしい演奏だ。ハフのアルバムに入っていた曲(R90)も収録されているが、楽器が違うこともあり印象がかなり異なる。誰かピアノで作品集を録音してくれないものかな。
Figueiredo : Soler : Sonatas : フィゲイレドが弾くソレルのソナタ集。フィゲレイドはスカルラッティ集を聴いて気に入り、目白バ・ロック音楽祭にライブも聴きに行った。彼のの弾くチェンバロはなんとなくロックを感じさせるところが好きだ。感情や熱のほとばしり方がロックなのだ。新しい録音はソレールの作品集。ソレールはスカルラッティの弟子で、スペインの作曲家。ラローチャが数曲録音しており、個人的にはハフのStephen Hough's Spanish Album に1曲だけ録音されているのを聴いてとても気に入っていた。まずまとめて作品が聴けるというのがうれしいし、どの曲も熱が入った演奏で飽きない。文句のつけどころがないです。夜、聴いていたら寝れなくなります。最後のファンタンゴは、フィゲレイドがアンコールでよく弾く曲のようで、すばらしい演奏だ。ハフのアルバムに入っていた曲(R90)も収録されているが、楽器が違うこともあり印象がかなり異なる。誰かピアノで作品集を録音してくれないものかな。
 Figueiredo : Soler : Sonatas : フィゲイレドが弾くソレルのソナタ集。フィゲレイドはスカルラッティ集を聴いて気に入り、目白バ・ロック音楽祭にライブも聴きに行った。彼のの弾くチェンバロはなんとなくロックを感じさせるところが好きだ。感情や熱のほとばしり方がロックなのだ。新しい録音はソレールの作品集。ソレールはスカルラッティの弟子で、スペインの作曲家。ラローチャが数曲録音しており、個人的にはハフのStephen Hough's Spanish Album に1曲だけ録音されているのを聴いてとても気に入っていた。まずまとめて作品が聴けるというのがうれしいし、どの曲も熱が入った演奏で飽きない。文句のつけどころがないです。夜、聴いていたら寝れなくなります。最後のファンタンゴは、フィゲレイドがアンコールでよく弾く曲のようで、すばらしい演奏だ。ハフのアルバムに入っていた曲(R90)も収録されているが、楽器が違うこともあり印象がかなり異なる。誰かピアノで作品集を録音してくれないものかな。
Figueiredo : Soler : Sonatas : フィゲイレドが弾くソレルのソナタ集。フィゲレイドはスカルラッティ集を聴いて気に入り、目白バ・ロック音楽祭にライブも聴きに行った。彼のの弾くチェンバロはなんとなくロックを感じさせるところが好きだ。感情や熱のほとばしり方がロックなのだ。新しい録音はソレールの作品集。ソレールはスカルラッティの弟子で、スペインの作曲家。ラローチャが数曲録音しており、個人的にはハフのStephen Hough's Spanish Album に1曲だけ録音されているのを聴いてとても気に入っていた。まずまとめて作品が聴けるというのがうれしいし、どの曲も熱が入った演奏で飽きない。文句のつけどころがないです。夜、聴いていたら寝れなくなります。最後のファンタンゴは、フィゲレイドがアンコールでよく弾く曲のようで、すばらしい演奏だ。ハフのアルバムに入っていた曲(R90)も収録されているが、楽器が違うこともあり印象がかなり異なる。誰かピアノで作品集を録音してくれないものかな。Oct.1 CD : Grimaud
 Grimaud : Bach : グリモーのバッハ集。ブーレーズがつけたバルトークの協奏曲を除けば、彼女のディスクを買うのはこれが初めて。曲は、平均律から5曲、ピアノ協奏曲第1番、ブゾーニ編のシャコンヌ、リスト編のプレリュードとフーガ、ラフマニノフ編の無伴奏パルティータ第3番のプレリュード。マイナーキーの曲が多すぎて、続けて聴くと気がめいってきてしまう。タッチもいいし、パワーもあるし、演奏は悪くないが、バッハにほしいと思っている清廉さが足りないかな。シャコンヌも適度にロマンティックでいいんだけど、メジャーキーに転調するところでの天に向かって抜けていく感じが少ないんですよね。最後の無伴奏パルティータ第3番からの前奏曲も、悪い演奏ではない。しかし、もっと軽やかさと華やかさがほしいかな。個人的に一番好きなのは今だにThomas Labeのものです。
Grimaud : Bach : グリモーのバッハ集。ブーレーズがつけたバルトークの協奏曲を除けば、彼女のディスクを買うのはこれが初めて。曲は、平均律から5曲、ピアノ協奏曲第1番、ブゾーニ編のシャコンヌ、リスト編のプレリュードとフーガ、ラフマニノフ編の無伴奏パルティータ第3番のプレリュード。マイナーキーの曲が多すぎて、続けて聴くと気がめいってきてしまう。タッチもいいし、パワーもあるし、演奏は悪くないが、バッハにほしいと思っている清廉さが足りないかな。シャコンヌも適度にロマンティックでいいんだけど、メジャーキーに転調するところでの天に向かって抜けていく感じが少ないんですよね。最後の無伴奏パルティータ第3番からの前奏曲も、悪い演奏ではない。しかし、もっと軽やかさと華やかさがほしいかな。個人的に一番好きなのは今だにThomas Labeのものです。
 Grimaud : Bach : グリモーのバッハ集。ブーレーズがつけたバルトークの協奏曲を除けば、彼女のディスクを買うのはこれが初めて。曲は、平均律から5曲、ピアノ協奏曲第1番、ブゾーニ編のシャコンヌ、リスト編のプレリュードとフーガ、ラフマニノフ編の無伴奏パルティータ第3番のプレリュード。マイナーキーの曲が多すぎて、続けて聴くと気がめいってきてしまう。タッチもいいし、パワーもあるし、演奏は悪くないが、バッハにほしいと思っている清廉さが足りないかな。シャコンヌも適度にロマンティックでいいんだけど、メジャーキーに転調するところでの天に向かって抜けていく感じが少ないんですよね。最後の無伴奏パルティータ第3番からの前奏曲も、悪い演奏ではない。しかし、もっと軽やかさと華やかさがほしいかな。個人的に一番好きなのは今だにThomas Labeのものです。
Grimaud : Bach : グリモーのバッハ集。ブーレーズがつけたバルトークの協奏曲を除けば、彼女のディスクを買うのはこれが初めて。曲は、平均律から5曲、ピアノ協奏曲第1番、ブゾーニ編のシャコンヌ、リスト編のプレリュードとフーガ、ラフマニノフ編の無伴奏パルティータ第3番のプレリュード。マイナーキーの曲が多すぎて、続けて聴くと気がめいってきてしまう。タッチもいいし、パワーもあるし、演奏は悪くないが、バッハにほしいと思っている清廉さが足りないかな。シャコンヌも適度にロマンティックでいいんだけど、メジャーキーに転調するところでの天に向かって抜けていく感じが少ないんですよね。最後の無伴奏パルティータ第3番からの前奏曲も、悪い演奏ではない。しかし、もっと軽やかさと華やかさがほしいかな。個人的に一番好きなのは今だにThomas Labeのものです。Oct.1 CD : Szell
 Szell + BPO : Salzburger Orchesterkonzerte 1957 : セルがザルツブルク音楽祭に出演した時のライブ録音。これまで何種類も発売されているが、これはベルリン・フィルと共演したものを集めたもの。録音著作権の保護される50年が過ぎたものから発売していっているのかな。1枚目はモーツァルト。最近、海賊版に近い録音の形で発売されたものと全く同じ内容。音質はこちらの方が上で、とてもクリア。フライシャーとの協奏曲第25番がとてもいい演奏。交響曲の29番は筋肉質でセルらしい演奏だが、オケがついてきていないところが若干あり。というか、ホルンがいまいちで、第4楽章など出があっていない気がする。40番の方はとてもいい演奏。個人的には40番は好きではないのだが、セルの演奏だと聴き入ってしまう。彼と40番は相性がいいのかもしれない。
2枚目のドビュッシー「海」とメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の感想はパス。
3枚目はエロイカ。2枚目と同じく1957年8月9日のライブ。もう文句が付けようがないです。セルのエロイカをベルリン・フィルのサウンドで堪能できるってだけで満足です。モーツァルトでは感じられなかったが、この演奏では、セルらしさがオーケストラに浸透している。
Szell + BPO : Salzburger Orchesterkonzerte 1957 : セルがザルツブルク音楽祭に出演した時のライブ録音。これまで何種類も発売されているが、これはベルリン・フィルと共演したものを集めたもの。録音著作権の保護される50年が過ぎたものから発売していっているのかな。1枚目はモーツァルト。最近、海賊版に近い録音の形で発売されたものと全く同じ内容。音質はこちらの方が上で、とてもクリア。フライシャーとの協奏曲第25番がとてもいい演奏。交響曲の29番は筋肉質でセルらしい演奏だが、オケがついてきていないところが若干あり。というか、ホルンがいまいちで、第4楽章など出があっていない気がする。40番の方はとてもいい演奏。個人的には40番は好きではないのだが、セルの演奏だと聴き入ってしまう。彼と40番は相性がいいのかもしれない。
2枚目のドビュッシー「海」とメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の感想はパス。
3枚目はエロイカ。2枚目と同じく1957年8月9日のライブ。もう文句が付けようがないです。セルのエロイカをベルリン・フィルのサウンドで堪能できるってだけで満足です。モーツァルトでは感じられなかったが、この演奏では、セルらしさがオーケストラに浸透している。
 Szell + BPO : Salzburger Orchesterkonzerte 1957 : セルがザルツブルク音楽祭に出演した時のライブ録音。これまで何種類も発売されているが、これはベルリン・フィルと共演したものを集めたもの。録音著作権の保護される50年が過ぎたものから発売していっているのかな。1枚目はモーツァルト。最近、海賊版に近い録音の形で発売されたものと全く同じ内容。音質はこちらの方が上で、とてもクリア。フライシャーとの協奏曲第25番がとてもいい演奏。交響曲の29番は筋肉質でセルらしい演奏だが、オケがついてきていないところが若干あり。というか、ホルンがいまいちで、第4楽章など出があっていない気がする。40番の方はとてもいい演奏。個人的には40番は好きではないのだが、セルの演奏だと聴き入ってしまう。彼と40番は相性がいいのかもしれない。
2枚目のドビュッシー「海」とメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の感想はパス。
3枚目はエロイカ。2枚目と同じく1957年8月9日のライブ。もう文句が付けようがないです。セルのエロイカをベルリン・フィルのサウンドで堪能できるってだけで満足です。モーツァルトでは感じられなかったが、この演奏では、セルらしさがオーケストラに浸透している。
Szell + BPO : Salzburger Orchesterkonzerte 1957 : セルがザルツブルク音楽祭に出演した時のライブ録音。これまで何種類も発売されているが、これはベルリン・フィルと共演したものを集めたもの。録音著作権の保護される50年が過ぎたものから発売していっているのかな。1枚目はモーツァルト。最近、海賊版に近い録音の形で発売されたものと全く同じ内容。音質はこちらの方が上で、とてもクリア。フライシャーとの協奏曲第25番がとてもいい演奏。交響曲の29番は筋肉質でセルらしい演奏だが、オケがついてきていないところが若干あり。というか、ホルンがいまいちで、第4楽章など出があっていない気がする。40番の方はとてもいい演奏。個人的には40番は好きではないのだが、セルの演奏だと聴き入ってしまう。彼と40番は相性がいいのかもしれない。
2枚目のドビュッシー「海」とメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の感想はパス。
3枚目はエロイカ。2枚目と同じく1957年8月9日のライブ。もう文句が付けようがないです。セルのエロイカをベルリン・フィルのサウンドで堪能できるってだけで満足です。モーツァルトでは感じられなかったが、この演奏では、セルらしさがオーケストラに浸透している。Sept.29 ペイリン
最近、ネットでニュースを見ているとペイリンという文字が目に付く。パイソン好きの僕としては、ランバージャックやスペインの司教やガンビーが頭に浮かんでクリックしてしまうのだが、メガネマニアが喜びそうな白人のお姉さま(熟女?)である。アメリカの共和党の副大統領候補だ。まぎらわしいなぁ、と思っていたが、YAMDAS現更新履歴を読んで、やっぱりこういうことを言い出す人がいるのかと。
guardian : Michael Palin for president?
Michael Palin for president
YouTubeに映像がアップされているのだが、よくできている。だいたい、サラ・ペイリンのほうは副大統領候補なのに、こちらはすでに「大統領に!」である。がんばれマイケル。
Sept.28 CD : Rene Pape
 Rene Pape : Gods Kings and Demons : 今、もっともメジャーなバス歌手といえば、ルネ・パーペ。残念ながら生ではまだ一度も聴いたことがないのだが。録音や映像で聴くと、安定した歌に、まだ40代前半とは思えない貫禄と演技力、そして極悪な面構え、どれも印象的な歌手である。彼が初めてのソロアルバムをグラモフォンから出した。タイトルは「神々、王と魔王」ということで、彼がよく歌う神と王様と魔王の役柄ばかり集めたアルバムだ。グノー、ベルリオーズ(オペラじゃない)、ヴェルディ、ルービンシュテイン、ドヴォルザークといったオペラから選曲されている。個人的に一番気になるのは、ワーグナー。トリスタンのマルケ王の歌と、ラインの黄金のフィナーレが取り上げられている。このラインの黄金のフィナーレはオケも良く気に入った。全曲ほしいくらい。あと、気に入ったのは、、ムソルグスキー「ボリス・ゴドノフ」。このオペラ、全体的に暗くてあまり好きではないのだが、くわしく勉強しないとダメなのかな。パーペはドレスデン出身だそうで、ペーター・シュライヤーのようにドレスデン聖十字架教会合唱団出身らしい。このアルバムで伴奏しているのは、セバスティアン・ヴァイグレ指揮のシュターツカペレ・ドレスデン。録音場所もドレスデンのルカ教会ということで、パーペにとっていい環境でセッション録音されている。シュターツカペレ・ドレスデンは、最近グラモフォンの録音では伴奏に使われてしまうことが多いのだが(グリモーのエンペラーや、ガランチャのアルバムなど)、このアルバムでもヴァイグレのつけ方がとてもよく、オケの音もすばらしい。
Rene Pape : Gods Kings and Demons : 今、もっともメジャーなバス歌手といえば、ルネ・パーペ。残念ながら生ではまだ一度も聴いたことがないのだが。録音や映像で聴くと、安定した歌に、まだ40代前半とは思えない貫禄と演技力、そして極悪な面構え、どれも印象的な歌手である。彼が初めてのソロアルバムをグラモフォンから出した。タイトルは「神々、王と魔王」ということで、彼がよく歌う神と王様と魔王の役柄ばかり集めたアルバムだ。グノー、ベルリオーズ(オペラじゃない)、ヴェルディ、ルービンシュテイン、ドヴォルザークといったオペラから選曲されている。個人的に一番気になるのは、ワーグナー。トリスタンのマルケ王の歌と、ラインの黄金のフィナーレが取り上げられている。このラインの黄金のフィナーレはオケも良く気に入った。全曲ほしいくらい。あと、気に入ったのは、、ムソルグスキー「ボリス・ゴドノフ」。このオペラ、全体的に暗くてあまり好きではないのだが、くわしく勉強しないとダメなのかな。パーペはドレスデン出身だそうで、ペーター・シュライヤーのようにドレスデン聖十字架教会合唱団出身らしい。このアルバムで伴奏しているのは、セバスティアン・ヴァイグレ指揮のシュターツカペレ・ドレスデン。録音場所もドレスデンのルカ教会ということで、パーペにとっていい環境でセッション録音されている。シュターツカペレ・ドレスデンは、最近グラモフォンの録音では伴奏に使われてしまうことが多いのだが(グリモーのエンペラーや、ガランチャのアルバムなど)、このアルバムでもヴァイグレのつけ方がとてもよく、オケの音もすばらしい。
 Rene Pape : Gods Kings and Demons : 今、もっともメジャーなバス歌手といえば、ルネ・パーペ。残念ながら生ではまだ一度も聴いたことがないのだが。録音や映像で聴くと、安定した歌に、まだ40代前半とは思えない貫禄と演技力、そして極悪な面構え、どれも印象的な歌手である。彼が初めてのソロアルバムをグラモフォンから出した。タイトルは「神々、王と魔王」ということで、彼がよく歌う神と王様と魔王の役柄ばかり集めたアルバムだ。グノー、ベルリオーズ(オペラじゃない)、ヴェルディ、ルービンシュテイン、ドヴォルザークといったオペラから選曲されている。個人的に一番気になるのは、ワーグナー。トリスタンのマルケ王の歌と、ラインの黄金のフィナーレが取り上げられている。このラインの黄金のフィナーレはオケも良く気に入った。全曲ほしいくらい。あと、気に入ったのは、、ムソルグスキー「ボリス・ゴドノフ」。このオペラ、全体的に暗くてあまり好きではないのだが、くわしく勉強しないとダメなのかな。パーペはドレスデン出身だそうで、ペーター・シュライヤーのようにドレスデン聖十字架教会合唱団出身らしい。このアルバムで伴奏しているのは、セバスティアン・ヴァイグレ指揮のシュターツカペレ・ドレスデン。録音場所もドレスデンのルカ教会ということで、パーペにとっていい環境でセッション録音されている。シュターツカペレ・ドレスデンは、最近グラモフォンの録音では伴奏に使われてしまうことが多いのだが(グリモーのエンペラーや、ガランチャのアルバムなど)、このアルバムでもヴァイグレのつけ方がとてもよく、オケの音もすばらしい。
Rene Pape : Gods Kings and Demons : 今、もっともメジャーなバス歌手といえば、ルネ・パーペ。残念ながら生ではまだ一度も聴いたことがないのだが。録音や映像で聴くと、安定した歌に、まだ40代前半とは思えない貫禄と演技力、そして極悪な面構え、どれも印象的な歌手である。彼が初めてのソロアルバムをグラモフォンから出した。タイトルは「神々、王と魔王」ということで、彼がよく歌う神と王様と魔王の役柄ばかり集めたアルバムだ。グノー、ベルリオーズ(オペラじゃない)、ヴェルディ、ルービンシュテイン、ドヴォルザークといったオペラから選曲されている。個人的に一番気になるのは、ワーグナー。トリスタンのマルケ王の歌と、ラインの黄金のフィナーレが取り上げられている。このラインの黄金のフィナーレはオケも良く気に入った。全曲ほしいくらい。あと、気に入ったのは、、ムソルグスキー「ボリス・ゴドノフ」。このオペラ、全体的に暗くてあまり好きではないのだが、くわしく勉強しないとダメなのかな。パーペはドレスデン出身だそうで、ペーター・シュライヤーのようにドレスデン聖十字架教会合唱団出身らしい。このアルバムで伴奏しているのは、セバスティアン・ヴァイグレ指揮のシュターツカペレ・ドレスデン。録音場所もドレスデンのルカ教会ということで、パーペにとっていい環境でセッション録音されている。シュターツカペレ・ドレスデンは、最近グラモフォンの録音では伴奏に使われてしまうことが多いのだが(グリモーのエンペラーや、ガランチャのアルバムなど)、このアルバムでもヴァイグレのつけ方がとてもよく、オケの音もすばらしい。Sept.28 CD : I am robot and proud
 I am robot and proud / uphill city : 前作の「Electricity in Your House Wants to Sing」は、タワレコでたまたま視聴して気に入って買った。その後、エレクトロニカ系ではとても人気のあるミュージシャンだということを知った。前のアルバムの気に入ったポイントはピアノっぽい音やエレピのような音の感触だったのだが、彼はトロント音楽院でクラシックピアノを学んでいたらしい。そのあたりが、気に入った原因か。このアルバムも
、同じようにピアノに近い音が気持ちいアルバムだ。ただ、エレクトロニカというよりは、ロックのダイナミックさを感じる部分が多い。メロディはあいかわらずポップなのだが。"Making a Case for Magic"や"Storm of the Century"なんて、とてもロックだ。テクノロック。YMOが演奏しててもおかしくなさそう。とてもいいアルバムだ。
I am robot and proud / uphill city : 前作の「Electricity in Your House Wants to Sing」は、タワレコでたまたま視聴して気に入って買った。その後、エレクトロニカ系ではとても人気のあるミュージシャンだということを知った。前のアルバムの気に入ったポイントはピアノっぽい音やエレピのような音の感触だったのだが、彼はトロント音楽院でクラシックピアノを学んでいたらしい。そのあたりが、気に入った原因か。このアルバムも
、同じようにピアノに近い音が気持ちいアルバムだ。ただ、エレクトロニカというよりは、ロックのダイナミックさを感じる部分が多い。メロディはあいかわらずポップなのだが。"Making a Case for Magic"や"Storm of the Century"なんて、とてもロックだ。テクノロック。YMOが演奏しててもおかしくなさそう。とてもいいアルバムだ。
 I am robot and proud / uphill city : 前作の「Electricity in Your House Wants to Sing」は、タワレコでたまたま視聴して気に入って買った。その後、エレクトロニカ系ではとても人気のあるミュージシャンだということを知った。前のアルバムの気に入ったポイントはピアノっぽい音やエレピのような音の感触だったのだが、彼はトロント音楽院でクラシックピアノを学んでいたらしい。そのあたりが、気に入った原因か。このアルバムも
、同じようにピアノに近い音が気持ちいアルバムだ。ただ、エレクトロニカというよりは、ロックのダイナミックさを感じる部分が多い。メロディはあいかわらずポップなのだが。"Making a Case for Magic"や"Storm of the Century"なんて、とてもロックだ。テクノロック。YMOが演奏しててもおかしくなさそう。とてもいいアルバムだ。
I am robot and proud / uphill city : 前作の「Electricity in Your House Wants to Sing」は、タワレコでたまたま視聴して気に入って買った。その後、エレクトロニカ系ではとても人気のあるミュージシャンだということを知った。前のアルバムの気に入ったポイントはピアノっぽい音やエレピのような音の感触だったのだが、彼はトロント音楽院でクラシックピアノを学んでいたらしい。そのあたりが、気に入った原因か。このアルバムも
、同じようにピアノに近い音が気持ちいアルバムだ。ただ、エレクトロニカというよりは、ロックのダイナミックさを感じる部分が多い。メロディはあいかわらずポップなのだが。"Making a Case for Magic"や"Storm of the Century"なんて、とてもロックだ。テクノロック。YMOが演奏しててもおかしくなさそう。とてもいいアルバムだ。Sept.28 CD : Albrecht Mayer
 Albrecht Mayer : In Venice : ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者でもあるアルブレヒト・マイヤーの新作。モーツァルト、バッハ、ヘンデルとグラモフォンから出ていたのだが、この作品はデッカから。移籍したのかな。これは、イタリアのバロック協奏曲集。イタリア・バロックはオーボエ(オーボエダモーレ)協奏曲の作品が大量にあり、ホリガーやシェレンベルガーなどのソロ奏者はいろいろ録音を残している。タイトルが「In Venice」だが、ジャケットもヴェニスで撮影されており、まるで映画のシーンのような写真だ。選ばれている曲も映画音楽になりそうな曲が多い。マイヤーは、鋭さの少ないなめらかな音色で弾いていて、風景にひたれそうな音が流れてくる。ニュー・シーズンズ・アンサンブルというオーケストラであるが、先日購入したダントーネのバッハの協奏曲集のオーケストラのように一楽器につき一人づつという編成。古楽アンサンブルであるが、ノンビブラートのアクセントが強いため、マイヤーの音とはちょっと合わないかもしれない。マルチェロの有名な協奏曲はちょっと激しいかな。ロッティという作曲家の協奏曲がいい。
Albrecht Mayer : In Venice : ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者でもあるアルブレヒト・マイヤーの新作。モーツァルト、バッハ、ヘンデルとグラモフォンから出ていたのだが、この作品はデッカから。移籍したのかな。これは、イタリアのバロック協奏曲集。イタリア・バロックはオーボエ(オーボエダモーレ)協奏曲の作品が大量にあり、ホリガーやシェレンベルガーなどのソロ奏者はいろいろ録音を残している。タイトルが「In Venice」だが、ジャケットもヴェニスで撮影されており、まるで映画のシーンのような写真だ。選ばれている曲も映画音楽になりそうな曲が多い。マイヤーは、鋭さの少ないなめらかな音色で弾いていて、風景にひたれそうな音が流れてくる。ニュー・シーズンズ・アンサンブルというオーケストラであるが、先日購入したダントーネのバッハの協奏曲集のオーケストラのように一楽器につき一人づつという編成。古楽アンサンブルであるが、ノンビブラートのアクセントが強いため、マイヤーの音とはちょっと合わないかもしれない。マルチェロの有名な協奏曲はちょっと激しいかな。ロッティという作曲家の協奏曲がいい。
 Albrecht Mayer : In Venice : ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者でもあるアルブレヒト・マイヤーの新作。モーツァルト、バッハ、ヘンデルとグラモフォンから出ていたのだが、この作品はデッカから。移籍したのかな。これは、イタリアのバロック協奏曲集。イタリア・バロックはオーボエ(オーボエダモーレ)協奏曲の作品が大量にあり、ホリガーやシェレンベルガーなどのソロ奏者はいろいろ録音を残している。タイトルが「In Venice」だが、ジャケットもヴェニスで撮影されており、まるで映画のシーンのような写真だ。選ばれている曲も映画音楽になりそうな曲が多い。マイヤーは、鋭さの少ないなめらかな音色で弾いていて、風景にひたれそうな音が流れてくる。ニュー・シーズンズ・アンサンブルというオーケストラであるが、先日購入したダントーネのバッハの協奏曲集のオーケストラのように一楽器につき一人づつという編成。古楽アンサンブルであるが、ノンビブラートのアクセントが強いため、マイヤーの音とはちょっと合わないかもしれない。マルチェロの有名な協奏曲はちょっと激しいかな。ロッティという作曲家の協奏曲がいい。
Albrecht Mayer : In Venice : ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者でもあるアルブレヒト・マイヤーの新作。モーツァルト、バッハ、ヘンデルとグラモフォンから出ていたのだが、この作品はデッカから。移籍したのかな。これは、イタリアのバロック協奏曲集。イタリア・バロックはオーボエ(オーボエダモーレ)協奏曲の作品が大量にあり、ホリガーやシェレンベルガーなどのソロ奏者はいろいろ録音を残している。タイトルが「In Venice」だが、ジャケットもヴェニスで撮影されており、まるで映画のシーンのような写真だ。選ばれている曲も映画音楽になりそうな曲が多い。マイヤーは、鋭さの少ないなめらかな音色で弾いていて、風景にひたれそうな音が流れてくる。ニュー・シーズンズ・アンサンブルというオーケストラであるが、先日購入したダントーネのバッハの協奏曲集のオーケストラのように一楽器につき一人づつという編成。古楽アンサンブルであるが、ノンビブラートのアクセントが強いため、マイヤーの音とはちょっと合わないかもしれない。マルチェロの有名な協奏曲はちょっと激しいかな。ロッティという作曲家の協奏曲がいい。Sept.28 DVD : Kent Nagano
 Kent Nagano + Bayerische Staatsoper : Chin / Alice in Wonderland : ケント・ナガノとバイエルン州立歌劇場の映像。チン・ウンスクの「不思議の国のアリス」という作品で、初演時の映像。日本語字幕はついていないが、歌詞は英語だし、あの「不思議の国のアリス」なのでプロットはそのまま。チン・ウンスクは韓国系の現代作曲家でリゲティの弟子らしいが、曲の作風は、特殊な響きのする現代音楽というわけではなく、耳当たりのいいカラフルだ。折衷的というか、いろんな様式を取り入れて用いる多様的な作品。アリスはフィナーレまで被り物をしているが、これがかわいくない。出てくるキャラクターがみなホラーっぽくてかわいくないのだ。ファンタジーなんだから、もっとアニメキャラっぽくていいんだとおもうのだが、日本人が作らないと、かわいいキャラクターにはならないのかな。バイエルン歌劇場のオーケストラは、こんなにうまかったっけ?とおもうほどナガノの棒についていっています。やっぱりR.Straussとか聴いてみたいな。収録は2007年6月27日の世界初演時のものと書いてあるのだが、公式サイトを見ても6月27日に公演はなく、6月30日が世界初演。映像では客が入っているのだが、27日にシークレットで演奏したものなのか、たんに書き間違っただけなのか、非常に気になる。
Kent Nagano + Bayerische Staatsoper : Chin / Alice in Wonderland : ケント・ナガノとバイエルン州立歌劇場の映像。チン・ウンスクの「不思議の国のアリス」という作品で、初演時の映像。日本語字幕はついていないが、歌詞は英語だし、あの「不思議の国のアリス」なのでプロットはそのまま。チン・ウンスクは韓国系の現代作曲家でリゲティの弟子らしいが、曲の作風は、特殊な響きのする現代音楽というわけではなく、耳当たりのいいカラフルだ。折衷的というか、いろんな様式を取り入れて用いる多様的な作品。アリスはフィナーレまで被り物をしているが、これがかわいくない。出てくるキャラクターがみなホラーっぽくてかわいくないのだ。ファンタジーなんだから、もっとアニメキャラっぽくていいんだとおもうのだが、日本人が作らないと、かわいいキャラクターにはならないのかな。バイエルン歌劇場のオーケストラは、こんなにうまかったっけ?とおもうほどナガノの棒についていっています。やっぱりR.Straussとか聴いてみたいな。収録は2007年6月27日の世界初演時のものと書いてあるのだが、公式サイトを見ても6月27日に公演はなく、6月30日が世界初演。映像では客が入っているのだが、27日にシークレットで演奏したものなのか、たんに書き間違っただけなのか、非常に気になる。
 Kent Nagano + Bayerische Staatsoper : Chin / Alice in Wonderland : ケント・ナガノとバイエルン州立歌劇場の映像。チン・ウンスクの「不思議の国のアリス」という作品で、初演時の映像。日本語字幕はついていないが、歌詞は英語だし、あの「不思議の国のアリス」なのでプロットはそのまま。チン・ウンスクは韓国系の現代作曲家でリゲティの弟子らしいが、曲の作風は、特殊な響きのする現代音楽というわけではなく、耳当たりのいいカラフルだ。折衷的というか、いろんな様式を取り入れて用いる多様的な作品。アリスはフィナーレまで被り物をしているが、これがかわいくない。出てくるキャラクターがみなホラーっぽくてかわいくないのだ。ファンタジーなんだから、もっとアニメキャラっぽくていいんだとおもうのだが、日本人が作らないと、かわいいキャラクターにはならないのかな。バイエルン歌劇場のオーケストラは、こんなにうまかったっけ?とおもうほどナガノの棒についていっています。やっぱりR.Straussとか聴いてみたいな。収録は2007年6月27日の世界初演時のものと書いてあるのだが、公式サイトを見ても6月27日に公演はなく、6月30日が世界初演。映像では客が入っているのだが、27日にシークレットで演奏したものなのか、たんに書き間違っただけなのか、非常に気になる。
Kent Nagano + Bayerische Staatsoper : Chin / Alice in Wonderland : ケント・ナガノとバイエルン州立歌劇場の映像。チン・ウンスクの「不思議の国のアリス」という作品で、初演時の映像。日本語字幕はついていないが、歌詞は英語だし、あの「不思議の国のアリス」なのでプロットはそのまま。チン・ウンスクは韓国系の現代作曲家でリゲティの弟子らしいが、曲の作風は、特殊な響きのする現代音楽というわけではなく、耳当たりのいいカラフルだ。折衷的というか、いろんな様式を取り入れて用いる多様的な作品。アリスはフィナーレまで被り物をしているが、これがかわいくない。出てくるキャラクターがみなホラーっぽくてかわいくないのだ。ファンタジーなんだから、もっとアニメキャラっぽくていいんだとおもうのだが、日本人が作らないと、かわいいキャラクターにはならないのかな。バイエルン歌劇場のオーケストラは、こんなにうまかったっけ?とおもうほどナガノの棒についていっています。やっぱりR.Straussとか聴いてみたいな。収録は2007年6月27日の世界初演時のものと書いてあるのだが、公式サイトを見ても6月27日に公演はなく、6月30日が世界初演。映像では客が入っているのだが、27日にシークレットで演奏したものなのか、たんに書き間違っただけなのか、非常に気になる。Sept.27 CD : Magma
 Magma / Bourges 1979 : MAGMAのライブアーカイブを出しているAKTシリーズ。このシリーズが出るのは、「Korusz」以来だと思うのでかなり久々のことだと思う。今回は正規録音では耳にすることができなかった「Attahk」発売後の時期のライブ。メンバーは、Christian、Stella、Klaus Blasquizの3人に、Andre Herve (k)、Michel Herve (b)の兄弟、Jean-Luc Chevalier (g,b)、 そしてコーラスでMaria PopkiewiczとLisa Deluxeが加わっている。音質はいいほうで、これまでのAKTシリーズの中でもダイナミックレンジが広い方だ。MAGMAがファンク化していく途中で、しかもChevalierとHerveのツインベース体制なので、かなりダンサブルな演奏。曲も"Retrovision"、"Urgon Gorgo"、"Nono"という70年代後半のものが収められている。"Korusz"ではなぜかMDK期のメンバーであるRene Garberがサックスを吹いている。"The Last Seven Minutes"がとてもかっこイイ。後半のアレンジはしまりがなくていまいちだが、このライブヴァージョンが聴けるだけでも大きい(神話と伝説のBussonettヴァージョンの方が完成度は高いが)。"MDK"はやたらテンポが速い。後半のソロも短くとても圧縮された印象を受ける。とてもかっこいいのだが、コンサートのすべてのプログラムを納めているわけではないらしいので、なんとなくバランスが悪いが、ファンなら買わないとしかたがない。
Magma / Bourges 1979 : MAGMAのライブアーカイブを出しているAKTシリーズ。このシリーズが出るのは、「Korusz」以来だと思うのでかなり久々のことだと思う。今回は正規録音では耳にすることができなかった「Attahk」発売後の時期のライブ。メンバーは、Christian、Stella、Klaus Blasquizの3人に、Andre Herve (k)、Michel Herve (b)の兄弟、Jean-Luc Chevalier (g,b)、 そしてコーラスでMaria PopkiewiczとLisa Deluxeが加わっている。音質はいいほうで、これまでのAKTシリーズの中でもダイナミックレンジが広い方だ。MAGMAがファンク化していく途中で、しかもChevalierとHerveのツインベース体制なので、かなりダンサブルな演奏。曲も"Retrovision"、"Urgon Gorgo"、"Nono"という70年代後半のものが収められている。"Korusz"ではなぜかMDK期のメンバーであるRene Garberがサックスを吹いている。"The Last Seven Minutes"がとてもかっこイイ。後半のアレンジはしまりがなくていまいちだが、このライブヴァージョンが聴けるだけでも大きい(神話と伝説のBussonettヴァージョンの方が完成度は高いが)。"MDK"はやたらテンポが速い。後半のソロも短くとても圧縮された印象を受ける。とてもかっこいいのだが、コンサートのすべてのプログラムを納めているわけではないらしいので、なんとなくバランスが悪いが、ファンなら買わないとしかたがない。
 Magma / Bourges 1979 : MAGMAのライブアーカイブを出しているAKTシリーズ。このシリーズが出るのは、「Korusz」以来だと思うのでかなり久々のことだと思う。今回は正規録音では耳にすることができなかった「Attahk」発売後の時期のライブ。メンバーは、Christian、Stella、Klaus Blasquizの3人に、Andre Herve (k)、Michel Herve (b)の兄弟、Jean-Luc Chevalier (g,b)、 そしてコーラスでMaria PopkiewiczとLisa Deluxeが加わっている。音質はいいほうで、これまでのAKTシリーズの中でもダイナミックレンジが広い方だ。MAGMAがファンク化していく途中で、しかもChevalierとHerveのツインベース体制なので、かなりダンサブルな演奏。曲も"Retrovision"、"Urgon Gorgo"、"Nono"という70年代後半のものが収められている。"Korusz"ではなぜかMDK期のメンバーであるRene Garberがサックスを吹いている。"The Last Seven Minutes"がとてもかっこイイ。後半のアレンジはしまりがなくていまいちだが、このライブヴァージョンが聴けるだけでも大きい(神話と伝説のBussonettヴァージョンの方が完成度は高いが)。"MDK"はやたらテンポが速い。後半のソロも短くとても圧縮された印象を受ける。とてもかっこいいのだが、コンサートのすべてのプログラムを納めているわけではないらしいので、なんとなくバランスが悪いが、ファンなら買わないとしかたがない。
Magma / Bourges 1979 : MAGMAのライブアーカイブを出しているAKTシリーズ。このシリーズが出るのは、「Korusz」以来だと思うのでかなり久々のことだと思う。今回は正規録音では耳にすることができなかった「Attahk」発売後の時期のライブ。メンバーは、Christian、Stella、Klaus Blasquizの3人に、Andre Herve (k)、Michel Herve (b)の兄弟、Jean-Luc Chevalier (g,b)、 そしてコーラスでMaria PopkiewiczとLisa Deluxeが加わっている。音質はいいほうで、これまでのAKTシリーズの中でもダイナミックレンジが広い方だ。MAGMAがファンク化していく途中で、しかもChevalierとHerveのツインベース体制なので、かなりダンサブルな演奏。曲も"Retrovision"、"Urgon Gorgo"、"Nono"という70年代後半のものが収められている。"Korusz"ではなぜかMDK期のメンバーであるRene Garberがサックスを吹いている。"The Last Seven Minutes"がとてもかっこイイ。後半のアレンジはしまりがなくていまいちだが、このライブヴァージョンが聴けるだけでも大きい(神話と伝説のBussonettヴァージョンの方が完成度は高いが)。"MDK"はやたらテンポが速い。後半のソロも短くとても圧縮された印象を受ける。とてもかっこいいのだが、コンサートのすべてのプログラムを納めているわけではないらしいので、なんとなくバランスが悪いが、ファンなら買わないとしかたがない。Sept.24 CD : smv
 smv / Thunder : Tone Centerレーベルが出してくるような超絶技巧演奏系のアルバムは飽きたので買わないようにしているのだが、このアルバムは視聴したところ、よく作りこまれているように感じたので購入。スタンリー・クラーク、マーカス・ミラー、ヴィクター・ウッテンの3人のベーシストによるプロジェクト。単にテーマを決めて弾きまくります、というわけではなく、音楽的に聞かせるようにアレンジして作りこまれている。アップで激しい曲よりも、ミドルテンポで重いビートの曲が多いのはメインプロデューサーのマーカスの嗜好なんでしょうかね。チック・コリアがピアノで参加している曲が1曲ある。70年代のフュージョンぽい曲でキーボードを弾いているのがほとんどマーカスだというのは、クレジットを見て驚いた。
smv / Thunder : Tone Centerレーベルが出してくるような超絶技巧演奏系のアルバムは飽きたので買わないようにしているのだが、このアルバムは視聴したところ、よく作りこまれているように感じたので購入。スタンリー・クラーク、マーカス・ミラー、ヴィクター・ウッテンの3人のベーシストによるプロジェクト。単にテーマを決めて弾きまくります、というわけではなく、音楽的に聞かせるようにアレンジして作りこまれている。アップで激しい曲よりも、ミドルテンポで重いビートの曲が多いのはメインプロデューサーのマーカスの嗜好なんでしょうかね。チック・コリアがピアノで参加している曲が1曲ある。70年代のフュージョンぽい曲でキーボードを弾いているのがほとんどマーカスだというのは、クレジットを見て驚いた。
 smv / Thunder : Tone Centerレーベルが出してくるような超絶技巧演奏系のアルバムは飽きたので買わないようにしているのだが、このアルバムは視聴したところ、よく作りこまれているように感じたので購入。スタンリー・クラーク、マーカス・ミラー、ヴィクター・ウッテンの3人のベーシストによるプロジェクト。単にテーマを決めて弾きまくります、というわけではなく、音楽的に聞かせるようにアレンジして作りこまれている。アップで激しい曲よりも、ミドルテンポで重いビートの曲が多いのはメインプロデューサーのマーカスの嗜好なんでしょうかね。チック・コリアがピアノで参加している曲が1曲ある。70年代のフュージョンぽい曲でキーボードを弾いているのがほとんどマーカスだというのは、クレジットを見て驚いた。
smv / Thunder : Tone Centerレーベルが出してくるような超絶技巧演奏系のアルバムは飽きたので買わないようにしているのだが、このアルバムは視聴したところ、よく作りこまれているように感じたので購入。スタンリー・クラーク、マーカス・ミラー、ヴィクター・ウッテンの3人のベーシストによるプロジェクト。単にテーマを決めて弾きまくります、というわけではなく、音楽的に聞かせるようにアレンジして作りこまれている。アップで激しい曲よりも、ミドルテンポで重いビートの曲が多いのはメインプロデューサーのマーカスの嗜好なんでしょうかね。チック・コリアがピアノで参加している曲が1曲ある。70年代のフュージョンぽい曲でキーボードを弾いているのがほとんどマーカスだというのは、クレジットを見て驚いた。Sept.24 CD : Boehm
 Karl Boehm + Bayreuth Festspiel : Wagner / Die Meistersinger von Nuernberg : ベームの「マイスタージンガー」。Orfeoからステレオで出た。トリスタン、オランダ人、指輪とバイロイトでベームの振ったワーグナーは、たいてい正規ライブ録音としてリリースされているが、マイスタージンガーだけはなかった。ザックス役の歌手(ヴァルター・ベリー)が直前にキャンセルして、テオ・アダムになったため契約上発売できなかったらしい。この公演はマイスタージンガーができて100年を記念したものだったらしい。「オランダ人」と同じく、ベームは推進力のある指揮ぶりで、しかも第1幕のフィナーレなど盛り上がるところでは思いっきり盛り上がる。ライブで見たら気持ちいいだろうな。前奏曲から、ミキサーがうまくないのか、本番で金管が急に大きい音を出しすぎたのか、金管のバランスが大きすぎて気持ち悪い。指揮のせいというより録音のせいのような気がする。第1幕後半になれば気にならなくなるので、いいとしよう。ダイナミックレンジはそれほど広くなく、全体的にちょっとのっぺりしたライブ録音だが、ステレオでこれだけ分離がよければいい方だろう。テオ・アダムは、カラヤンの録音でもうたっているが、とてもいい。第3幕は引き締まった感じで進んでいき、とてもいい(いいとしか書いていないが)。エファがギネス・ジョーンズ、夜警がクルト・モルというのも豪華な配役。今後、ライブ録音ならこれを押すな。
Karl Boehm + Bayreuth Festspiel : Wagner / Die Meistersinger von Nuernberg : ベームの「マイスタージンガー」。Orfeoからステレオで出た。トリスタン、オランダ人、指輪とバイロイトでベームの振ったワーグナーは、たいてい正規ライブ録音としてリリースされているが、マイスタージンガーだけはなかった。ザックス役の歌手(ヴァルター・ベリー)が直前にキャンセルして、テオ・アダムになったため契約上発売できなかったらしい。この公演はマイスタージンガーができて100年を記念したものだったらしい。「オランダ人」と同じく、ベームは推進力のある指揮ぶりで、しかも第1幕のフィナーレなど盛り上がるところでは思いっきり盛り上がる。ライブで見たら気持ちいいだろうな。前奏曲から、ミキサーがうまくないのか、本番で金管が急に大きい音を出しすぎたのか、金管のバランスが大きすぎて気持ち悪い。指揮のせいというより録音のせいのような気がする。第1幕後半になれば気にならなくなるので、いいとしよう。ダイナミックレンジはそれほど広くなく、全体的にちょっとのっぺりしたライブ録音だが、ステレオでこれだけ分離がよければいい方だろう。テオ・アダムは、カラヤンの録音でもうたっているが、とてもいい。第3幕は引き締まった感じで進んでいき、とてもいい(いいとしか書いていないが)。エファがギネス・ジョーンズ、夜警がクルト・モルというのも豪華な配役。今後、ライブ録音ならこれを押すな。
 Karl Boehm + Bayreuth Festspiel : Wagner / Die Meistersinger von Nuernberg : ベームの「マイスタージンガー」。Orfeoからステレオで出た。トリスタン、オランダ人、指輪とバイロイトでベームの振ったワーグナーは、たいてい正規ライブ録音としてリリースされているが、マイスタージンガーだけはなかった。ザックス役の歌手(ヴァルター・ベリー)が直前にキャンセルして、テオ・アダムになったため契約上発売できなかったらしい。この公演はマイスタージンガーができて100年を記念したものだったらしい。「オランダ人」と同じく、ベームは推進力のある指揮ぶりで、しかも第1幕のフィナーレなど盛り上がるところでは思いっきり盛り上がる。ライブで見たら気持ちいいだろうな。前奏曲から、ミキサーがうまくないのか、本番で金管が急に大きい音を出しすぎたのか、金管のバランスが大きすぎて気持ち悪い。指揮のせいというより録音のせいのような気がする。第1幕後半になれば気にならなくなるので、いいとしよう。ダイナミックレンジはそれほど広くなく、全体的にちょっとのっぺりしたライブ録音だが、ステレオでこれだけ分離がよければいい方だろう。テオ・アダムは、カラヤンの録音でもうたっているが、とてもいい。第3幕は引き締まった感じで進んでいき、とてもいい(いいとしか書いていないが)。エファがギネス・ジョーンズ、夜警がクルト・モルというのも豪華な配役。今後、ライブ録音ならこれを押すな。
Karl Boehm + Bayreuth Festspiel : Wagner / Die Meistersinger von Nuernberg : ベームの「マイスタージンガー」。Orfeoからステレオで出た。トリスタン、オランダ人、指輪とバイロイトでベームの振ったワーグナーは、たいてい正規ライブ録音としてリリースされているが、マイスタージンガーだけはなかった。ザックス役の歌手(ヴァルター・ベリー)が直前にキャンセルして、テオ・アダムになったため契約上発売できなかったらしい。この公演はマイスタージンガーができて100年を記念したものだったらしい。「オランダ人」と同じく、ベームは推進力のある指揮ぶりで、しかも第1幕のフィナーレなど盛り上がるところでは思いっきり盛り上がる。ライブで見たら気持ちいいだろうな。前奏曲から、ミキサーがうまくないのか、本番で金管が急に大きい音を出しすぎたのか、金管のバランスが大きすぎて気持ち悪い。指揮のせいというより録音のせいのような気がする。第1幕後半になれば気にならなくなるので、いいとしよう。ダイナミックレンジはそれほど広くなく、全体的にちょっとのっぺりしたライブ録音だが、ステレオでこれだけ分離がよければいい方だろう。テオ・アダムは、カラヤンの録音でもうたっているが、とてもいい。第3幕は引き締まった感じで進んでいき、とてもいい(いいとしか書いていないが)。エファがギネス・ジョーンズ、夜警がクルト・モルというのも豪華な配役。今後、ライブ録音ならこれを押すな。Sept.23 CD : Joe Zawinul
 Joe Zawinul / 75th : 2007年7月7日、ザヴィヌルの75歳の誕生日に行われたライブ。この年の9月に亡くなってしまったのでラストの誕生日だ。しばらくドラムをたたいていたナサニエル・タウンスレーではなく、ボナが在籍していたころのドラマーであったパコ・セリーが復帰している。ザヴィヌルはインタビューで、いつも「ベストドラマーはパコだ」と言っていたので、この編成で見てみたかったのだが、かなわなくなってしまった。あとのメンバーは、最後の来日の時と同じで、アレグレ・コレア、アジズ・サーマウィ、ホルヘ・ベセーラ、リンレイ・マルテ、そして産休から復帰したサビーネ・カボンゴ。とても病気だったとは思えないほどエネルギッシュでパワーのあるライブだ。ファンだから贔屓めな発言かもしれないが、75になってまでこれだけの音楽を生み出せるミュージシャンってそうそういないものだ。収録曲はこれまでのライブアルバムと重ならないように選曲されているのかもしれない。たまたまかもしれないが、"Madagascar"、"Scarlet Woman"、"Badia / Boogie Woogie Waltz"、"Fast City / Two Lines"とWeather Reportの曲がとても多く収められている。"Badia"と"Fast City"はいつも演奏していたので、前の2曲が珍しいのか。"In a Silent Way"だけは8月のハンガリーでの録音。これはゲストのWayne Shorterとの演奏。この曲だし、何も変わらないので、何も言うことはない。"Orient Express"を聴くと、ヴォコーダーのマイクをグーで猫パンチするザヴィヌルの姿(毎回ライブでは恒例のシーン)を思い出して、ちょっと悲しくなってしまった。
Joe Zawinul / 75th : 2007年7月7日、ザヴィヌルの75歳の誕生日に行われたライブ。この年の9月に亡くなってしまったのでラストの誕生日だ。しばらくドラムをたたいていたナサニエル・タウンスレーではなく、ボナが在籍していたころのドラマーであったパコ・セリーが復帰している。ザヴィヌルはインタビューで、いつも「ベストドラマーはパコだ」と言っていたので、この編成で見てみたかったのだが、かなわなくなってしまった。あとのメンバーは、最後の来日の時と同じで、アレグレ・コレア、アジズ・サーマウィ、ホルヘ・ベセーラ、リンレイ・マルテ、そして産休から復帰したサビーネ・カボンゴ。とても病気だったとは思えないほどエネルギッシュでパワーのあるライブだ。ファンだから贔屓めな発言かもしれないが、75になってまでこれだけの音楽を生み出せるミュージシャンってそうそういないものだ。収録曲はこれまでのライブアルバムと重ならないように選曲されているのかもしれない。たまたまかもしれないが、"Madagascar"、"Scarlet Woman"、"Badia / Boogie Woogie Waltz"、"Fast City / Two Lines"とWeather Reportの曲がとても多く収められている。"Badia"と"Fast City"はいつも演奏していたので、前の2曲が珍しいのか。"In a Silent Way"だけは8月のハンガリーでの録音。これはゲストのWayne Shorterとの演奏。この曲だし、何も変わらないので、何も言うことはない。"Orient Express"を聴くと、ヴォコーダーのマイクをグーで猫パンチするザヴィヌルの姿(毎回ライブでは恒例のシーン)を思い出して、ちょっと悲しくなってしまった。
 Joe Zawinul / 75th : 2007年7月7日、ザヴィヌルの75歳の誕生日に行われたライブ。この年の9月に亡くなってしまったのでラストの誕生日だ。しばらくドラムをたたいていたナサニエル・タウンスレーではなく、ボナが在籍していたころのドラマーであったパコ・セリーが復帰している。ザヴィヌルはインタビューで、いつも「ベストドラマーはパコだ」と言っていたので、この編成で見てみたかったのだが、かなわなくなってしまった。あとのメンバーは、最後の来日の時と同じで、アレグレ・コレア、アジズ・サーマウィ、ホルヘ・ベセーラ、リンレイ・マルテ、そして産休から復帰したサビーネ・カボンゴ。とても病気だったとは思えないほどエネルギッシュでパワーのあるライブだ。ファンだから贔屓めな発言かもしれないが、75になってまでこれだけの音楽を生み出せるミュージシャンってそうそういないものだ。収録曲はこれまでのライブアルバムと重ならないように選曲されているのかもしれない。たまたまかもしれないが、"Madagascar"、"Scarlet Woman"、"Badia / Boogie Woogie Waltz"、"Fast City / Two Lines"とWeather Reportの曲がとても多く収められている。"Badia"と"Fast City"はいつも演奏していたので、前の2曲が珍しいのか。"In a Silent Way"だけは8月のハンガリーでの録音。これはゲストのWayne Shorterとの演奏。この曲だし、何も変わらないので、何も言うことはない。"Orient Express"を聴くと、ヴォコーダーのマイクをグーで猫パンチするザヴィヌルの姿(毎回ライブでは恒例のシーン)を思い出して、ちょっと悲しくなってしまった。
Joe Zawinul / 75th : 2007年7月7日、ザヴィヌルの75歳の誕生日に行われたライブ。この年の9月に亡くなってしまったのでラストの誕生日だ。しばらくドラムをたたいていたナサニエル・タウンスレーではなく、ボナが在籍していたころのドラマーであったパコ・セリーが復帰している。ザヴィヌルはインタビューで、いつも「ベストドラマーはパコだ」と言っていたので、この編成で見てみたかったのだが、かなわなくなってしまった。あとのメンバーは、最後の来日の時と同じで、アレグレ・コレア、アジズ・サーマウィ、ホルヘ・ベセーラ、リンレイ・マルテ、そして産休から復帰したサビーネ・カボンゴ。とても病気だったとは思えないほどエネルギッシュでパワーのあるライブだ。ファンだから贔屓めな発言かもしれないが、75になってまでこれだけの音楽を生み出せるミュージシャンってそうそういないものだ。収録曲はこれまでのライブアルバムと重ならないように選曲されているのかもしれない。たまたまかもしれないが、"Madagascar"、"Scarlet Woman"、"Badia / Boogie Woogie Waltz"、"Fast City / Two Lines"とWeather Reportの曲がとても多く収められている。"Badia"と"Fast City"はいつも演奏していたので、前の2曲が珍しいのか。"In a Silent Way"だけは8月のハンガリーでの録音。これはゲストのWayne Shorterとの演奏。この曲だし、何も変わらないので、何も言うことはない。"Orient Express"を聴くと、ヴォコーダーのマイクをグーで猫パンチするザヴィヌルの姿(毎回ライブでは恒例のシーン)を思い出して、ちょっと悲しくなってしまった。Sept.23 CD : Metzmacher
 Metzmacher + VPO : Messiaen / Eclairs sur l'Au-Dela : 今年の1月20日に、メッツメッハーがウィーンフィルの定期公演を振ったときのライブ録音。Kairosという現代曲のレーベルから発売。ウィーンフィルがメシアンを演奏するということでも話題になった。インターネットラジオの演奏で聴いたが、録音はCDの方が当然よい。この曲はラトルとベルリン・フィルのものを持っているが、実は、メシアンの管弦楽曲で、トゥランガリーラ交響曲以外気に入ったものがない。ラトルの演奏でもいまいちだった。しかし、この録音はそこそこ楽しめた。楽しめた原因は、ウィーンフィルの音だと思う。弦も管も、ウィーンらしい色気があり、録音のよさもあってカラフルなのだ。第7楽章のフルートのソロなどとても気持ちがいい。フランスの作曲家の曲なんだから、色気がないとダメだ。ラトルの演奏は、あのベルリンを振っているのに、色彩の幅が少なくて、色気がないと感じる。これはやはりメッツマッハーの腕なんだろう。コンサートの前半に演奏されたモーツァルトの交響曲29番がとても好みの演奏だった。また、このコンサートの次の週もメッツマッハーはザルツブルク公演で、エマールがソロでモーツァルトのピアノ協奏曲23番、メシアンの鳥たちの目覚め、モーツァルトの交響曲39番という、メシアンとモーツァルトを組み合わせたプログラムを振っているのだが、これら録音として出してほしいんだけど、現代曲でないとメッツマッハーの録音を売るのは無理ですかね。
Metzmacher + VPO : Messiaen / Eclairs sur l'Au-Dela : 今年の1月20日に、メッツメッハーがウィーンフィルの定期公演を振ったときのライブ録音。Kairosという現代曲のレーベルから発売。ウィーンフィルがメシアンを演奏するということでも話題になった。インターネットラジオの演奏で聴いたが、録音はCDの方が当然よい。この曲はラトルとベルリン・フィルのものを持っているが、実は、メシアンの管弦楽曲で、トゥランガリーラ交響曲以外気に入ったものがない。ラトルの演奏でもいまいちだった。しかし、この録音はそこそこ楽しめた。楽しめた原因は、ウィーンフィルの音だと思う。弦も管も、ウィーンらしい色気があり、録音のよさもあってカラフルなのだ。第7楽章のフルートのソロなどとても気持ちがいい。フランスの作曲家の曲なんだから、色気がないとダメだ。ラトルの演奏は、あのベルリンを振っているのに、色彩の幅が少なくて、色気がないと感じる。これはやはりメッツマッハーの腕なんだろう。コンサートの前半に演奏されたモーツァルトの交響曲29番がとても好みの演奏だった。また、このコンサートの次の週もメッツマッハーはザルツブルク公演で、エマールがソロでモーツァルトのピアノ協奏曲23番、メシアンの鳥たちの目覚め、モーツァルトの交響曲39番という、メシアンとモーツァルトを組み合わせたプログラムを振っているのだが、これら録音として出してほしいんだけど、現代曲でないとメッツマッハーの録音を売るのは無理ですかね。
 Metzmacher + VPO : Messiaen / Eclairs sur l'Au-Dela : 今年の1月20日に、メッツメッハーがウィーンフィルの定期公演を振ったときのライブ録音。Kairosという現代曲のレーベルから発売。ウィーンフィルがメシアンを演奏するということでも話題になった。インターネットラジオの演奏で聴いたが、録音はCDの方が当然よい。この曲はラトルとベルリン・フィルのものを持っているが、実は、メシアンの管弦楽曲で、トゥランガリーラ交響曲以外気に入ったものがない。ラトルの演奏でもいまいちだった。しかし、この録音はそこそこ楽しめた。楽しめた原因は、ウィーンフィルの音だと思う。弦も管も、ウィーンらしい色気があり、録音のよさもあってカラフルなのだ。第7楽章のフルートのソロなどとても気持ちがいい。フランスの作曲家の曲なんだから、色気がないとダメだ。ラトルの演奏は、あのベルリンを振っているのに、色彩の幅が少なくて、色気がないと感じる。これはやはりメッツマッハーの腕なんだろう。コンサートの前半に演奏されたモーツァルトの交響曲29番がとても好みの演奏だった。また、このコンサートの次の週もメッツマッハーはザルツブルク公演で、エマールがソロでモーツァルトのピアノ協奏曲23番、メシアンの鳥たちの目覚め、モーツァルトの交響曲39番という、メシアンとモーツァルトを組み合わせたプログラムを振っているのだが、これら録音として出してほしいんだけど、現代曲でないとメッツマッハーの録音を売るのは無理ですかね。
Metzmacher + VPO : Messiaen / Eclairs sur l'Au-Dela : 今年の1月20日に、メッツメッハーがウィーンフィルの定期公演を振ったときのライブ録音。Kairosという現代曲のレーベルから発売。ウィーンフィルがメシアンを演奏するということでも話題になった。インターネットラジオの演奏で聴いたが、録音はCDの方が当然よい。この曲はラトルとベルリン・フィルのものを持っているが、実は、メシアンの管弦楽曲で、トゥランガリーラ交響曲以外気に入ったものがない。ラトルの演奏でもいまいちだった。しかし、この録音はそこそこ楽しめた。楽しめた原因は、ウィーンフィルの音だと思う。弦も管も、ウィーンらしい色気があり、録音のよさもあってカラフルなのだ。第7楽章のフルートのソロなどとても気持ちがいい。フランスの作曲家の曲なんだから、色気がないとダメだ。ラトルの演奏は、あのベルリンを振っているのに、色彩の幅が少なくて、色気がないと感じる。これはやはりメッツマッハーの腕なんだろう。コンサートの前半に演奏されたモーツァルトの交響曲29番がとても好みの演奏だった。また、このコンサートの次の週もメッツマッハーはザルツブルク公演で、エマールがソロでモーツァルトのピアノ協奏曲23番、メシアンの鳥たちの目覚め、モーツァルトの交響曲39番という、メシアンとモーツァルトを組み合わせたプログラムを振っているのだが、これら録音として出してほしいんだけど、現代曲でないとメッツマッハーの録音を売るのは無理ですかね。Sept.21 Wagner "Tristan und Isolde" / Taijiro Iimori @ ティアラこうとう
飯守泰次郎のWagnerを聴きに行ってきた。前々から評判を聞いていて、ぜひ聴いてみたいと思っていたのだ。オーケストラは東京シティ・フィル。在京オーケストラはたいてい聴いているが、実はシティフィルは聴いたことがない。たぶんあまりうまくないだろと思い込んでいたからだ。ちなみに、新星日響はリヒテルの伴奏で聴いたことがあるが、読響は聴いたことがない。場所はティアラこうとう。このホールも初めて。だいたい、江東区に足を踏み入れるのなんて、現代美術館に行ったときくらいじゃないだろうか。それで、演目はトリスタンとイゾルデのコンサート形式。当日券で入れた。ホールは1000人ちょっとくらいの大きさ。当日券で取った席がU列だったので、ステージから遠いかと思ったが、小さめのホールでちょうど良い。14時からスタート。ゆったりめのテンポの前奏曲を聴き始めて、オーケストラが下手だと思い込んでいたことを反省した。指揮者の意思が浸透していて、よくコントロールされている。第1幕の後半にかけては上り調子で良かった。フルートは強く吹くと音が裏返るし、ホルンはシャープさに欠けるが、弦はうまい。特にチェロの音が深くてまろやか。このパートだけならドイツのオケと言われてもおかしくないかな。でも、全体としては音色にまとまりがなく、中庸さが日本のオケっぽい。オーケストラの後ろに高めのステージがあり、歌手はそこで、かるい振りをつけながら歌う。また、照明と、ステージ後ろに映し出される映像の演出はある。しかし、映像がイマイチで、演奏されている曲や風景のイメージを喚起しないような絵、しかもえぐい絵が多い。
イゾルデの緑川マリは飯守とよく演奏しているので、期待していたのだが、ちょっと期待外れ。やたらと絶叫するが。音程がのっぺりしている上に、息が続かない。そして、ドイツ語の響きが全くしない。ワーグナーの楽劇の魅力の一つはドイツ語の響きだと思うのだが(それを僕がきちんと理解しているかどうかは別として)、はきはきと音が切れるドイツ語の雰囲気がしない。これまで、ワーグナーのオペラはドイツ語圏のオペラハウスのものばかり見ていたので、あまり気にならなかっのだが(うたっているのがドイツ語圏内の人ではなくてもね)。おまけに、第1幕の2か所ほどと第2幕の冒頭の高音程のところは声が全く出ておらず、オケでフォロー。フィナーレの愛の死は、全然息が持たず、飯守はおそらくもっと歌わせる濃い演奏をしたそうだったが、歌手に合わせてせかせかしたテンポになってしまっていた。一番気に入ったのはクルヴェナールの島村武男。音程もしっかりしていて、息も長く、なによりドイツ語の発音がよかった。ブランげーネの福原寿美枝は第1幕は、イゾルデにかき消されていたのかイマイチだと思ったが、第2幕以降は良かった。トリスタンの成田勝美も、第3幕では座りながら歌うのがつらいのか、持たなかったのか、かなり平凡な歌で抑揚がない。
第1幕の途中から、プロンプターの歌詞をリードする声がやたらとホールに響き、興ざめだった。70年代のフォーク歌手が、客に歌わせようとして小節間で先に歌詞を言うみたいな感じになっていた。ホールが小さめで、よく響くところだっただけになおさら。オーケストラだけならかなり満足。第3幕では、舞台裏でホルツ・トランペットの演奏もあって、この音も良かった。
Sept.20 CD : Pollini
 Maurizio Pollini : Chopin Piano Sonata No.2 : ポリーニのショパン集が出た。作品番号が30番台の作品を集めている。バラードの2番とソナタの2番が再録音で、ワルツとマズルカが初録音。最近はこのようなプログラムでコンサートを行っているようで、これもライブ録音。なんかワルツを聴いていて悲しくなった。2年ほど前に生で聴いたときも感じたことなので改めて感じることでもないのだが。微妙に走ったり、指が音価の最後まで抑えられていなかったり、昔のポリーニでは考えられないくらいコントロールが効いていないように聞こえる。ポリーニの魅力はクールさと揺らぎのない構築ときらきらした音色なんだと思っているのだが、もうそれを表現するテクニックと体力がないんだろう。特に体力かな。これをもって人間味があるとか温かさがあるとか巨匠風とかいうことはできるが、僕がポリーニに魅力を感じる部分はそこではない。
Maurizio Pollini : Chopin Piano Sonata No.2 : ポリーニのショパン集が出た。作品番号が30番台の作品を集めている。バラードの2番とソナタの2番が再録音で、ワルツとマズルカが初録音。最近はこのようなプログラムでコンサートを行っているようで、これもライブ録音。なんかワルツを聴いていて悲しくなった。2年ほど前に生で聴いたときも感じたことなので改めて感じることでもないのだが。微妙に走ったり、指が音価の最後まで抑えられていなかったり、昔のポリーニでは考えられないくらいコントロールが効いていないように聞こえる。ポリーニの魅力はクールさと揺らぎのない構築ときらきらした音色なんだと思っているのだが、もうそれを表現するテクニックと体力がないんだろう。特に体力かな。これをもって人間味があるとか温かさがあるとか巨匠風とかいうことはできるが、僕がポリーニに魅力を感じる部分はそこではない。
 Maurizio Pollini : Chopin Piano Sonata No.2 : ポリーニのショパン集が出た。作品番号が30番台の作品を集めている。バラードの2番とソナタの2番が再録音で、ワルツとマズルカが初録音。最近はこのようなプログラムでコンサートを行っているようで、これもライブ録音。なんかワルツを聴いていて悲しくなった。2年ほど前に生で聴いたときも感じたことなので改めて感じることでもないのだが。微妙に走ったり、指が音価の最後まで抑えられていなかったり、昔のポリーニでは考えられないくらいコントロールが効いていないように聞こえる。ポリーニの魅力はクールさと揺らぎのない構築ときらきらした音色なんだと思っているのだが、もうそれを表現するテクニックと体力がないんだろう。特に体力かな。これをもって人間味があるとか温かさがあるとか巨匠風とかいうことはできるが、僕がポリーニに魅力を感じる部分はそこではない。
Maurizio Pollini : Chopin Piano Sonata No.2 : ポリーニのショパン集が出た。作品番号が30番台の作品を集めている。バラードの2番とソナタの2番が再録音で、ワルツとマズルカが初録音。最近はこのようなプログラムでコンサートを行っているようで、これもライブ録音。なんかワルツを聴いていて悲しくなった。2年ほど前に生で聴いたときも感じたことなので改めて感じることでもないのだが。微妙に走ったり、指が音価の最後まで抑えられていなかったり、昔のポリーニでは考えられないくらいコントロールが効いていないように聞こえる。ポリーニの魅力はクールさと揺らぎのない構築ときらきらした音色なんだと思っているのだが、もうそれを表現するテクニックと体力がないんだろう。特に体力かな。これをもって人間味があるとか温かさがあるとか巨匠風とかいうことはできるが、僕がポリーニに魅力を感じる部分はそこではない。Sept.20 CD : Tilson Thomas
 Michael Tilson Thomas + San Francisco Symphony : Mahler / Das Lied von der Erde : ティルソン・トーマスとサンフランシスコ交響楽団のマーラーシリーズ、前回はRCAで出ていた嘆きの歌の再発と、ちょっとすかされたが、無事、大地の歌が発売された。これで残すは8番のみ。バーンスタインやラトルと同じく、バリトンを用いる編成。あいかわらず精緻な演奏で、木管のソロなど、非常に美しい。癖も、神経質さも、変な枯れもなく、純度の高い演奏で、聴いていてもあまり疲れを感じない演奏。録音に関しては、このシリーズの特徴なので改めて言うことでもないが、驚くほどよい。
Michael Tilson Thomas + San Francisco Symphony : Mahler / Das Lied von der Erde : ティルソン・トーマスとサンフランシスコ交響楽団のマーラーシリーズ、前回はRCAで出ていた嘆きの歌の再発と、ちょっとすかされたが、無事、大地の歌が発売された。これで残すは8番のみ。バーンスタインやラトルと同じく、バリトンを用いる編成。あいかわらず精緻な演奏で、木管のソロなど、非常に美しい。癖も、神経質さも、変な枯れもなく、純度の高い演奏で、聴いていてもあまり疲れを感じない演奏。録音に関しては、このシリーズの特徴なので改めて言うことでもないが、驚くほどよい。
 Michael Tilson Thomas + San Francisco Symphony : Mahler / Das Lied von der Erde : ティルソン・トーマスとサンフランシスコ交響楽団のマーラーシリーズ、前回はRCAで出ていた嘆きの歌の再発と、ちょっとすかされたが、無事、大地の歌が発売された。これで残すは8番のみ。バーンスタインやラトルと同じく、バリトンを用いる編成。あいかわらず精緻な演奏で、木管のソロなど、非常に美しい。癖も、神経質さも、変な枯れもなく、純度の高い演奏で、聴いていてもあまり疲れを感じない演奏。録音に関しては、このシリーズの特徴なので改めて言うことでもないが、驚くほどよい。
Michael Tilson Thomas + San Francisco Symphony : Mahler / Das Lied von der Erde : ティルソン・トーマスとサンフランシスコ交響楽団のマーラーシリーズ、前回はRCAで出ていた嘆きの歌の再発と、ちょっとすかされたが、無事、大地の歌が発売された。これで残すは8番のみ。バーンスタインやラトルと同じく、バリトンを用いる編成。あいかわらず精緻な演奏で、木管のソロなど、非常に美しい。癖も、神経質さも、変な枯れもなく、純度の高い演奏で、聴いていてもあまり疲れを感じない演奏。録音に関しては、このシリーズの特徴なので改めて言うことでもないが、驚くほどよい。Sept.20 CD : Pahud
 Emmanuel Pahud : Dalbavie / Flite Concerto : パユ様の最新録音。現代作曲家の協奏曲が3曲。作曲家に曲を委嘱する、現代で活動する最高の音楽家の使命の一つであり、作曲家もどんな複雑なパッセージでも吹いてくれる可能性を想定して曲を書くのは楽しいだろう。そしてこうやって録音が残れば、楽譜だけ残るよりも、後世に作品を聴いてもらえる可能性が多いわけだ。はっきりいって売れないだろう録音を、こうやって残すことができるのもパユ様の人気のおかげだろう。取り上げられている作曲家は、ダルバヴィ、ヤレル、ピンチャーの3人。どの人もよく知らない。オーケストラは3曲とも同じだが、指揮者はエトヴェシュ、ロフェ、作曲家の自演と曲によって異なる。初演はジンマンやハーディングなどが振ったらしいが、さすがにその人たちを呼ぶとお金がかかりすぎるか?ダルバヴィは冒頭からミニマルなフレーズのオンパレード。パユ様じゃなったら弾けないですよ。フランス系の流麗な感じの曲で、最後まで聞ける。しかし後の2曲はいわゆるゲンダイオンガクなきわどい響きが多く、あまり楽しめない。フルートの曲だからやはり華やかな方がいいと思うんですけどね。
Emmanuel Pahud : Dalbavie / Flite Concerto : パユ様の最新録音。現代作曲家の協奏曲が3曲。作曲家に曲を委嘱する、現代で活動する最高の音楽家の使命の一つであり、作曲家もどんな複雑なパッセージでも吹いてくれる可能性を想定して曲を書くのは楽しいだろう。そしてこうやって録音が残れば、楽譜だけ残るよりも、後世に作品を聴いてもらえる可能性が多いわけだ。はっきりいって売れないだろう録音を、こうやって残すことができるのもパユ様の人気のおかげだろう。取り上げられている作曲家は、ダルバヴィ、ヤレル、ピンチャーの3人。どの人もよく知らない。オーケストラは3曲とも同じだが、指揮者はエトヴェシュ、ロフェ、作曲家の自演と曲によって異なる。初演はジンマンやハーディングなどが振ったらしいが、さすがにその人たちを呼ぶとお金がかかりすぎるか?ダルバヴィは冒頭からミニマルなフレーズのオンパレード。パユ様じゃなったら弾けないですよ。フランス系の流麗な感じの曲で、最後まで聞ける。しかし後の2曲はいわゆるゲンダイオンガクなきわどい響きが多く、あまり楽しめない。フルートの曲だからやはり華やかな方がいいと思うんですけどね。
 Emmanuel Pahud : Dalbavie / Flite Concerto : パユ様の最新録音。現代作曲家の協奏曲が3曲。作曲家に曲を委嘱する、現代で活動する最高の音楽家の使命の一つであり、作曲家もどんな複雑なパッセージでも吹いてくれる可能性を想定して曲を書くのは楽しいだろう。そしてこうやって録音が残れば、楽譜だけ残るよりも、後世に作品を聴いてもらえる可能性が多いわけだ。はっきりいって売れないだろう録音を、こうやって残すことができるのもパユ様の人気のおかげだろう。取り上げられている作曲家は、ダルバヴィ、ヤレル、ピンチャーの3人。どの人もよく知らない。オーケストラは3曲とも同じだが、指揮者はエトヴェシュ、ロフェ、作曲家の自演と曲によって異なる。初演はジンマンやハーディングなどが振ったらしいが、さすがにその人たちを呼ぶとお金がかかりすぎるか?ダルバヴィは冒頭からミニマルなフレーズのオンパレード。パユ様じゃなったら弾けないですよ。フランス系の流麗な感じの曲で、最後まで聞ける。しかし後の2曲はいわゆるゲンダイオンガクなきわどい響きが多く、あまり楽しめない。フルートの曲だからやはり華やかな方がいいと思うんですけどね。
Emmanuel Pahud : Dalbavie / Flite Concerto : パユ様の最新録音。現代作曲家の協奏曲が3曲。作曲家に曲を委嘱する、現代で活動する最高の音楽家の使命の一つであり、作曲家もどんな複雑なパッセージでも吹いてくれる可能性を想定して曲を書くのは楽しいだろう。そしてこうやって録音が残れば、楽譜だけ残るよりも、後世に作品を聴いてもらえる可能性が多いわけだ。はっきりいって売れないだろう録音を、こうやって残すことができるのもパユ様の人気のおかげだろう。取り上げられている作曲家は、ダルバヴィ、ヤレル、ピンチャーの3人。どの人もよく知らない。オーケストラは3曲とも同じだが、指揮者はエトヴェシュ、ロフェ、作曲家の自演と曲によって異なる。初演はジンマンやハーディングなどが振ったらしいが、さすがにその人たちを呼ぶとお金がかかりすぎるか?ダルバヴィは冒頭からミニマルなフレーズのオンパレード。パユ様じゃなったら弾けないですよ。フランス系の流麗な感じの曲で、最後まで聞ける。しかし後の2曲はいわゆるゲンダイオンガクなきわどい響きが多く、あまり楽しめない。フルートの曲だからやはり華やかな方がいいと思うんですけどね。Sept.20 CD : Ottavio Dantone
 Ottavio Dantone : Bach / Harpsichord Concerto : よく読ませていただいている#Credoや庭は夏の日ざかりといったBlogでほめられていたので購入した1枚。グールドやガブリーロフ、カツァリスといったピアノ協奏曲として聴き慣れているので、ピアノの派手な音じゃないと耳になじまないのが残念。しかし、オーケストラは面白いと思う。一つの楽器につきメンバーが一人しかいないという室内楽のような編成だが、ぱっと聴いただけではそれを感じさせないくらい音の広がりがある。録音がいいというのもあるのかもしれない。チェンバロの音がオーケストラに埋もれてしまわないというだけでも重要なのか。古楽器演奏にありがちな理論ずくめのところや、妙なアグレッシブさがなく、非常にエッジの立った切れ味があり、安定したテンポ感のある演奏だ。
Ottavio Dantone : Bach / Harpsichord Concerto : よく読ませていただいている#Credoや庭は夏の日ざかりといったBlogでほめられていたので購入した1枚。グールドやガブリーロフ、カツァリスといったピアノ協奏曲として聴き慣れているので、ピアノの派手な音じゃないと耳になじまないのが残念。しかし、オーケストラは面白いと思う。一つの楽器につきメンバーが一人しかいないという室内楽のような編成だが、ぱっと聴いただけではそれを感じさせないくらい音の広がりがある。録音がいいというのもあるのかもしれない。チェンバロの音がオーケストラに埋もれてしまわないというだけでも重要なのか。古楽器演奏にありがちな理論ずくめのところや、妙なアグレッシブさがなく、非常にエッジの立った切れ味があり、安定したテンポ感のある演奏だ。
 Ottavio Dantone : Bach / Harpsichord Concerto : よく読ませていただいている#Credoや庭は夏の日ざかりといったBlogでほめられていたので購入した1枚。グールドやガブリーロフ、カツァリスといったピアノ協奏曲として聴き慣れているので、ピアノの派手な音じゃないと耳になじまないのが残念。しかし、オーケストラは面白いと思う。一つの楽器につきメンバーが一人しかいないという室内楽のような編成だが、ぱっと聴いただけではそれを感じさせないくらい音の広がりがある。録音がいいというのもあるのかもしれない。チェンバロの音がオーケストラに埋もれてしまわないというだけでも重要なのか。古楽器演奏にありがちな理論ずくめのところや、妙なアグレッシブさがなく、非常にエッジの立った切れ味があり、安定したテンポ感のある演奏だ。
Ottavio Dantone : Bach / Harpsichord Concerto : よく読ませていただいている#Credoや庭は夏の日ざかりといったBlogでほめられていたので購入した1枚。グールドやガブリーロフ、カツァリスといったピアノ協奏曲として聴き慣れているので、ピアノの派手な音じゃないと耳になじまないのが残念。しかし、オーケストラは面白いと思う。一つの楽器につきメンバーが一人しかいないという室内楽のような編成だが、ぱっと聴いただけではそれを感じさせないくらい音の広がりがある。録音がいいというのもあるのかもしれない。チェンバロの音がオーケストラに埋もれてしまわないというだけでも重要なのか。古楽器演奏にありがちな理論ずくめのところや、妙なアグレッシブさがなく、非常にエッジの立った切れ味があり、安定したテンポ感のある演奏だ。Sept.20 CD : Jansons
 Mariss Jansons + Royal Concertogebouw : R.Strauss / Eine Alpensinfonie : コンセルトヘボウのレーベルから出ている、ヤンソンスとコンセルトヘボウの新録音。R.シュトラウスの「ドン・ファン」と「アルプス交響曲」なので購入した。ヤンソンスらしい抜けの良い音がオーケストラからでいている。しかし、シャープさに欠けると感じた。どこかのっぺりとした印象を受けるのだ。R.シュトラウスは、とりあえず冒頭で聴き手を驚かせてなんぼ、と思っていたわけだが、「ドン・ファン」の冒頭の上昇音階のテーマからしてキレがない。アルプス交響曲の方も、場面に応じた曲想の見せ方というのがあると思うのだが、どこもピシッと決まらない。山に登るところの張り切った感じとか、嵐の前の不安な感じとか、はっきりいって映画音楽なんだからもっと楽しく聴かせてくれてもいいのではないかと思う。ライブ録音なので仕方ないが、金管で不安定に聴こえるところもある。相変わらずオーケストラビルダーとしての腕は認めるが、音楽の奏で方がイマイチ僕と合わない指揮者だ。
Mariss Jansons + Royal Concertogebouw : R.Strauss / Eine Alpensinfonie : コンセルトヘボウのレーベルから出ている、ヤンソンスとコンセルトヘボウの新録音。R.シュトラウスの「ドン・ファン」と「アルプス交響曲」なので購入した。ヤンソンスらしい抜けの良い音がオーケストラからでいている。しかし、シャープさに欠けると感じた。どこかのっぺりとした印象を受けるのだ。R.シュトラウスは、とりあえず冒頭で聴き手を驚かせてなんぼ、と思っていたわけだが、「ドン・ファン」の冒頭の上昇音階のテーマからしてキレがない。アルプス交響曲の方も、場面に応じた曲想の見せ方というのがあると思うのだが、どこもピシッと決まらない。山に登るところの張り切った感じとか、嵐の前の不安な感じとか、はっきりいって映画音楽なんだからもっと楽しく聴かせてくれてもいいのではないかと思う。ライブ録音なので仕方ないが、金管で不安定に聴こえるところもある。相変わらずオーケストラビルダーとしての腕は認めるが、音楽の奏で方がイマイチ僕と合わない指揮者だ。
 Mariss Jansons + Royal Concertogebouw : R.Strauss / Eine Alpensinfonie : コンセルトヘボウのレーベルから出ている、ヤンソンスとコンセルトヘボウの新録音。R.シュトラウスの「ドン・ファン」と「アルプス交響曲」なので購入した。ヤンソンスらしい抜けの良い音がオーケストラからでいている。しかし、シャープさに欠けると感じた。どこかのっぺりとした印象を受けるのだ。R.シュトラウスは、とりあえず冒頭で聴き手を驚かせてなんぼ、と思っていたわけだが、「ドン・ファン」の冒頭の上昇音階のテーマからしてキレがない。アルプス交響曲の方も、場面に応じた曲想の見せ方というのがあると思うのだが、どこもピシッと決まらない。山に登るところの張り切った感じとか、嵐の前の不安な感じとか、はっきりいって映画音楽なんだからもっと楽しく聴かせてくれてもいいのではないかと思う。ライブ録音なので仕方ないが、金管で不安定に聴こえるところもある。相変わらずオーケストラビルダーとしての腕は認めるが、音楽の奏で方がイマイチ僕と合わない指揮者だ。
Mariss Jansons + Royal Concertogebouw : R.Strauss / Eine Alpensinfonie : コンセルトヘボウのレーベルから出ている、ヤンソンスとコンセルトヘボウの新録音。R.シュトラウスの「ドン・ファン」と「アルプス交響曲」なので購入した。ヤンソンスらしい抜けの良い音がオーケストラからでいている。しかし、シャープさに欠けると感じた。どこかのっぺりとした印象を受けるのだ。R.シュトラウスは、とりあえず冒頭で聴き手を驚かせてなんぼ、と思っていたわけだが、「ドン・ファン」の冒頭の上昇音階のテーマからしてキレがない。アルプス交響曲の方も、場面に応じた曲想の見せ方というのがあると思うのだが、どこもピシッと決まらない。山に登るところの張り切った感じとか、嵐の前の不安な感じとか、はっきりいって映画音楽なんだからもっと楽しく聴かせてくれてもいいのではないかと思う。ライブ録音なので仕方ないが、金管で不安定に聴こえるところもある。相変わらずオーケストラビルダーとしての腕は認めるが、音楽の奏で方がイマイチ僕と合わない指揮者だ。Sept.20 エクトル・ザズー
タワレコでCDを眺めているときに知ったのだが、Hector Zazouが亡くなったらしい。彼の代表作といえばZNRなんだろうけど、個人的にはあまり好きではない。やはり、豪華なミュージシャンを集めているのに、各ミュージシャンの個性が強く出ていないアンビエントな「Song from Cold Seas」や「Light in the Dark」といったアルバムが好きだ。とてもひんやりとした肌触りでちょっとポップなの音楽を作ることができた人だと思う。
Sept.16 リック・ライト
Pink FloydのRichard (Rick) Wrightが亡くなったそうだ。ちなみに、メジャーなプログレのバンドで僕が一番聴かないのがピンク・フロイドだ。理由は疾走感が足りないから。でも、70年代のアルバムにはすべて耳を通しているし、一部のアルバムを除いてちゃんと持っている。リック・ライトは、「Wall」のときにバンドの覇権争いのあおりを食らって解雇。「Final Cut」のときにはおらず、Roger Watersのいない再結成フロイドではまた呼ばれるという、なんだか芯の弱い人生を歩んでこられたので、メンバーの中では一番目立たない存在だったような気がする。音楽的にも、フロイドのよくわからない、しかし一番重要な「雰囲気を醸しだす」芯のない音を担当をしているため、Rick WakemanやKeith Emersonのようなヒーロー扱いのプレーヤーにもなれず、地味だった。2005年のLive 8のときの再結成が最後のピンク・フロイドになってしまったが、1回こっきりとはいえ、あんな仲の悪いバンドで、亡くなる前に4人で演奏できたのは良いことだったのだろう。感動的だったし。RIP。
Sept.15 CD : Fleming + Thielemann
 Rene Fleming + Christian Thielemann : R.Strauss / Four Last Songs : 最近見た、ウェルザー・メストの振るアラベラで主役を歌っていたルネ・フレミングによる、R.シュトラウスの歌曲とアリア集。つけているのはティーレマンとミュンヘンフィル。収録されているのは4つの最後の歌、「アリアドネ」のアリア、「エジプトのヘレナ」というあまり聴くことができないオペラのアリア、歌曲集から4曲。4つの最後の歌は、個人的な好みからすると中音域が豊かすぎて、もっさりした印象を受けた。アリアドネのアリアと4曲の歌曲、とくに「冬の聖化」が気に入った。オーケストラもおおむね同じで、4つの最後の歌がピンとこなかった。デッカの録音のせいだと思うが、ミュンヘン・フィルにしては線が細めでシャープな音がする。
Rene Fleming + Christian Thielemann : R.Strauss / Four Last Songs : 最近見た、ウェルザー・メストの振るアラベラで主役を歌っていたルネ・フレミングによる、R.シュトラウスの歌曲とアリア集。つけているのはティーレマンとミュンヘンフィル。収録されているのは4つの最後の歌、「アリアドネ」のアリア、「エジプトのヘレナ」というあまり聴くことができないオペラのアリア、歌曲集から4曲。4つの最後の歌は、個人的な好みからすると中音域が豊かすぎて、もっさりした印象を受けた。アリアドネのアリアと4曲の歌曲、とくに「冬の聖化」が気に入った。オーケストラもおおむね同じで、4つの最後の歌がピンとこなかった。デッカの録音のせいだと思うが、ミュンヘン・フィルにしては線が細めでシャープな音がする。
 Rene Fleming + Christian Thielemann : R.Strauss / Four Last Songs : 最近見た、ウェルザー・メストの振るアラベラで主役を歌っていたルネ・フレミングによる、R.シュトラウスの歌曲とアリア集。つけているのはティーレマンとミュンヘンフィル。収録されているのは4つの最後の歌、「アリアドネ」のアリア、「エジプトのヘレナ」というあまり聴くことができないオペラのアリア、歌曲集から4曲。4つの最後の歌は、個人的な好みからすると中音域が豊かすぎて、もっさりした印象を受けた。アリアドネのアリアと4曲の歌曲、とくに「冬の聖化」が気に入った。オーケストラもおおむね同じで、4つの最後の歌がピンとこなかった。デッカの録音のせいだと思うが、ミュンヘン・フィルにしては線が細めでシャープな音がする。
Rene Fleming + Christian Thielemann : R.Strauss / Four Last Songs : 最近見た、ウェルザー・メストの振るアラベラで主役を歌っていたルネ・フレミングによる、R.シュトラウスの歌曲とアリア集。つけているのはティーレマンとミュンヘンフィル。収録されているのは4つの最後の歌、「アリアドネ」のアリア、「エジプトのヘレナ」というあまり聴くことができないオペラのアリア、歌曲集から4曲。4つの最後の歌は、個人的な好みからすると中音域が豊かすぎて、もっさりした印象を受けた。アリアドネのアリアと4曲の歌曲、とくに「冬の聖化」が気に入った。オーケストラもおおむね同じで、4つの最後の歌がピンとこなかった。デッカの録音のせいだと思うが、ミュンヘン・フィルにしては線が細めでシャープな音がする。Sept.14 帰省と兵庫県立芸術文化センター
実家で法事があるので、金曜日から帰省している。ここ最近、実家に長期滞在することも少ないので、休暇をつけて何泊かすることにした。といっても、阪神間に住んでいる友人はほとんどなく、会社の同期も東京に転勤しているか、会社を辞めて違うところで働いているので会いたい人もいない。なんかないかと調べてみたところ、兵庫県立芸術文化センターでコンサートがあるではないか。社会人になってから3年間、西宮北口駅から歩いて5分のところに住んでいたが、このホールのあるあたりは再開発中だったので(モデルハウスとかジャスコがあったのかな)、このホールにはお目にかかったことがない。この週末は同じプログラムを3日演奏しており、指揮は佐渡裕。しかし、曲はハチャトリアンのヴァイオリン協奏曲とバーンスタインのカディッシュと、おおよそ一般受けのしない曲なのでチケットはあるだろうと思ってホールに向かった。ところが、完売。キャンセルのチケットもなく完売。マチネということもあって、カジュアルな雰囲気で年齢層の広いお客がわんさかと列をなして入場していく。バーンスタインの交響曲第3番ですよ?これが、佐渡裕の人気や、クラシックの裾野を広げたいという戦略によるものだったらうらやましいくらい大成功なんじゃないかな。なんで、僕が住んでいたころになかったのか、と思わせるくらい。今日のところは諦めるけど、やっぱり聴いてみたいので、この勢いで続けてください。今度は事前にチケット取ってから帰省します。
ちなみに、15日はフェスティバルホールで、ムーティ様指揮のウィーン・フィルのコンサートがあった、これもオークションで当日渡しのチケットがとれそうだったのだが、あえなく失敗。コンサート運のない連休でした。
Sept.12 ウィーン美術史美術館所蔵 静物画の秘密展 @ 国立新美術館
帰省のため休暇をとった。せっかくなので、もうすぐ展示が終わりそうなウィーン美術史美術館所蔵 静物画の秘密展に行ってきた。場所は国立新美術館。平日なためか客は少なめ。美術史美術館 (Kunsthistorisches Museum)は2回行ったので、目を引く絵は覚えている。ここの美術館で印象的なのは、バベルの塔とかフェルメールとかであって、静物画ではないように思う。。展示物はルーベンス、ブリューゲルなどフランドル派が中心。僕にとって、印象派の静物の絵は面白いけど、この時代の静物画は興味を引くところが少ない。つらつらと見て回ると、最後の方で突如ベラスケスの「マルガリータ王女」が現れる。この企画はこれがメインかな。
Sept.10 ナスノミツル+吉田達也×3 @ 秋葉原グッドマン
最近、ライブ見ていない気がしたので、仕事の後、わざわざ秋葉原に出撃。19時半ころついたらすでに始まっていた。このライブハウスは初めて来た。生活圏から遠いということを除けば、適度な広さだし、ディスプレイに出る映像もマルチカメラだし、いい小屋だ。「ナスノミツル+吉田達也×3」というタイトルだが、吉田達也叩きっぱなし+ナスノミツル弾きっぱなし、ということ。まず、ホッピー神山との大文字。着いた時には1曲目が終わっていて、MC中だった。このユニットは、ZAOの前座で見ているから2回目かな。2曲演奏。ホッピさんは話し始めると長い。なんか訴えたいことが多い人に違いない。演奏も、持っている引出しが多い感じで、即興なのに飽きが来ない。2つ目は、鬼怒無月との是巨人。気分的には、これがメイン。鬼怒はサル・ガヴォのヨーロッパ公演から帰ってきたばかりで、時差ボケなのか、冒頭からいきなりミス(?)。"Jackson"などで、ソロの音色など乗り切れず、残念なところがいくつかあり。しかし、新曲は良かった。とくに"S"。おそらく、残りの2曲の新曲は"T"と"U"だろうが、どれもアメリカのプログレのようにポップで、パワーコードが多く、メカニカルなフレーズの多い曲で気持ちがいい。「是巨人」の由来であるThis Heatの影は薄れて、Gentle Giantの複雑でポップなところが前面に出たバンドになっている感がある。最後は、坂田明との原寸大。これがデビューだそうだ。以前に、吉田と坂田が揃ったところを見たことがあったような気がしたが、Bill Laswellと山下洋輔とのセッションかな。このユニットも即興で3曲。ナスノが恐縮してMC。坂田との掛け合いが面白かった。2曲目で坂田は歌いだす。このライブのはじめから客席真ん中あたりで、携帯のカメラでステージを頻繁に撮影している奴が気になっていたのだが、坂田は即興の歌で警告していて面白かった。最後のアンコールはホッピー、鬼怒、坂田と5人でインプロ。
Sept.6 CD : Bireli Lagrene
 Bireli Lagrene / Electric Side : ビレリ・ラグレーンのアルバム。このギタリストは、今までジャコとのアルバムとか、ラリー・コリエルとの「Spaces Revisited」とか、とりあえず巧いという印象しかなく、リーダー作を聴いたことはなかった。タイトル通り、エレクトリックなFusionの作品で、マクラフリンのエレクトリックな編成のアルバムと印象が近い。マクラフリンの「Industrial Zen」で有名になったアドリアン・フェロー (Hadrien Feraud)がベースで、曲も提供している。ラグレーンとフェローの双頭バンドのアルバムといっても悪くない。ドラムもフェローと共演が多いダミアン・シュミット (Damien Schmitt)。この2人とサックスのフランク・ウルフ (Franck Wolf)が固定メンバー。ダミアンは、歌わせるような叩き方はあまりしないが、テクニックは抜群。特に高速な金物系の入れ方は素晴らしい。これで泣けるような歌いっぷりができれば最高なのだが、これだけ叩ければ文句はないか。ギターはとにかく巧いが、ギターを前面に押し出すわけではなく、曲としてのバランスを重視して演奏しているように聴こえる。時々フィルっぽく入れる高速なフレーズがかっこいい。どちらかといえばベースの方が目立つプレイが多いかも。1曲目、4曲目(ハンコックの"Jack Rabbit")などのヒップホップ風味の曲がいい。このバンドでライブが見てみたい。
Bireli Lagrene / Electric Side : ビレリ・ラグレーンのアルバム。このギタリストは、今までジャコとのアルバムとか、ラリー・コリエルとの「Spaces Revisited」とか、とりあえず巧いという印象しかなく、リーダー作を聴いたことはなかった。タイトル通り、エレクトリックなFusionの作品で、マクラフリンのエレクトリックな編成のアルバムと印象が近い。マクラフリンの「Industrial Zen」で有名になったアドリアン・フェロー (Hadrien Feraud)がベースで、曲も提供している。ラグレーンとフェローの双頭バンドのアルバムといっても悪くない。ドラムもフェローと共演が多いダミアン・シュミット (Damien Schmitt)。この2人とサックスのフランク・ウルフ (Franck Wolf)が固定メンバー。ダミアンは、歌わせるような叩き方はあまりしないが、テクニックは抜群。特に高速な金物系の入れ方は素晴らしい。これで泣けるような歌いっぷりができれば最高なのだが、これだけ叩ければ文句はないか。ギターはとにかく巧いが、ギターを前面に押し出すわけではなく、曲としてのバランスを重視して演奏しているように聴こえる。時々フィルっぽく入れる高速なフレーズがかっこいい。どちらかといえばベースの方が目立つプレイが多いかも。1曲目、4曲目(ハンコックの"Jack Rabbit")などのヒップホップ風味の曲がいい。このバンドでライブが見てみたい。
 Bireli Lagrene / Electric Side : ビレリ・ラグレーンのアルバム。このギタリストは、今までジャコとのアルバムとか、ラリー・コリエルとの「Spaces Revisited」とか、とりあえず巧いという印象しかなく、リーダー作を聴いたことはなかった。タイトル通り、エレクトリックなFusionの作品で、マクラフリンのエレクトリックな編成のアルバムと印象が近い。マクラフリンの「Industrial Zen」で有名になったアドリアン・フェロー (Hadrien Feraud)がベースで、曲も提供している。ラグレーンとフェローの双頭バンドのアルバムといっても悪くない。ドラムもフェローと共演が多いダミアン・シュミット (Damien Schmitt)。この2人とサックスのフランク・ウルフ (Franck Wolf)が固定メンバー。ダミアンは、歌わせるような叩き方はあまりしないが、テクニックは抜群。特に高速な金物系の入れ方は素晴らしい。これで泣けるような歌いっぷりができれば最高なのだが、これだけ叩ければ文句はないか。ギターはとにかく巧いが、ギターを前面に押し出すわけではなく、曲としてのバランスを重視して演奏しているように聴こえる。時々フィルっぽく入れる高速なフレーズがかっこいい。どちらかといえばベースの方が目立つプレイが多いかも。1曲目、4曲目(ハンコックの"Jack Rabbit")などのヒップホップ風味の曲がいい。このバンドでライブが見てみたい。
Bireli Lagrene / Electric Side : ビレリ・ラグレーンのアルバム。このギタリストは、今までジャコとのアルバムとか、ラリー・コリエルとの「Spaces Revisited」とか、とりあえず巧いという印象しかなく、リーダー作を聴いたことはなかった。タイトル通り、エレクトリックなFusionの作品で、マクラフリンのエレクトリックな編成のアルバムと印象が近い。マクラフリンの「Industrial Zen」で有名になったアドリアン・フェロー (Hadrien Feraud)がベースで、曲も提供している。ラグレーンとフェローの双頭バンドのアルバムといっても悪くない。ドラムもフェローと共演が多いダミアン・シュミット (Damien Schmitt)。この2人とサックスのフランク・ウルフ (Franck Wolf)が固定メンバー。ダミアンは、歌わせるような叩き方はあまりしないが、テクニックは抜群。特に高速な金物系の入れ方は素晴らしい。これで泣けるような歌いっぷりができれば最高なのだが、これだけ叩ければ文句はないか。ギターはとにかく巧いが、ギターを前面に押し出すわけではなく、曲としてのバランスを重視して演奏しているように聴こえる。時々フィルっぽく入れる高速なフレーズがかっこいい。どちらかといえばベースの方が目立つプレイが多いかも。1曲目、4曲目(ハンコックの"Jack Rabbit")などのヒップホップ風味の曲がいい。このバンドでライブが見てみたい。Sept.6 CD : Alejandro Franov
 Alejandro Franov / aixa : アルゼンチン音響派といわれるジャンルで扱われているアレハンドロ・フラノフのソロ作。前作「Khali」もよく聴いたので購入。音楽、ではなく。気持ちよく「音が置いてある」ような作品。前作に比べるとキーボードによるアンビエントな音が多く、民族音楽っぽさが薄れている。ペンギン・カフェからイーノに戻った、みたいな印象。自分の精神状態もあるんだと思うが、夜にぼーっとかけていると気持ちいいです。
Alejandro Franov / aixa : アルゼンチン音響派といわれるジャンルで扱われているアレハンドロ・フラノフのソロ作。前作「Khali」もよく聴いたので購入。音楽、ではなく。気持ちよく「音が置いてある」ような作品。前作に比べるとキーボードによるアンビエントな音が多く、民族音楽っぽさが薄れている。ペンギン・カフェからイーノに戻った、みたいな印象。自分の精神状態もあるんだと思うが、夜にぼーっとかけていると気持ちいいです。
 Alejandro Franov / aixa : アルゼンチン音響派といわれるジャンルで扱われているアレハンドロ・フラノフのソロ作。前作「Khali」もよく聴いたので購入。音楽、ではなく。気持ちよく「音が置いてある」ような作品。前作に比べるとキーボードによるアンビエントな音が多く、民族音楽っぽさが薄れている。ペンギン・カフェからイーノに戻った、みたいな印象。自分の精神状態もあるんだと思うが、夜にぼーっとかけていると気持ちいいです。
Alejandro Franov / aixa : アルゼンチン音響派といわれるジャンルで扱われているアレハンドロ・フラノフのソロ作。前作「Khali」もよく聴いたので購入。音楽、ではなく。気持ちよく「音が置いてある」ような作品。前作に比べるとキーボードによるアンビエントな音が多く、民族音楽っぽさが薄れている。ペンギン・カフェからイーノに戻った、みたいな印象。自分の精神状態もあるんだと思うが、夜にぼーっとかけていると気持ちいいです。Sept.3 CD : Esbjorn Svensson Trio
 est / Leucocyte : スヴェンソンは今年の6月に事故で亡くなったので、これがおそらく遺作になる。スヴェンソン本人はこのあと死ぬなんて全く思っていなかったに違いないので、死を思わせるようなものは何もない。即興演奏の一発どりを編集したアルバムなので、ひたすらスネアの連打でキーボードが聞こえないパートが延々と続いたりして、曲としての完成度が高いとは決して言えない。それよりも何かを追い求めるエネルギーのようなものを感じるアルバムだ。彼らの最高作では決してなく、過渡期のアルバムになるのだと思う。この後がないので過渡期にはなりえないのだが。King Crimsonでいえば「Earthbound」、Chick CoreaでいえばCircleなわけで、このあとに「太陽と戦慄」や「RED」、「Return to Forever」のような素晴らしいアルバムが作られたはずなのに、という残念な気分にさせられるアルバムだ。
est / Leucocyte : スヴェンソンは今年の6月に事故で亡くなったので、これがおそらく遺作になる。スヴェンソン本人はこのあと死ぬなんて全く思っていなかったに違いないので、死を思わせるようなものは何もない。即興演奏の一発どりを編集したアルバムなので、ひたすらスネアの連打でキーボードが聞こえないパートが延々と続いたりして、曲としての完成度が高いとは決して言えない。それよりも何かを追い求めるエネルギーのようなものを感じるアルバムだ。彼らの最高作では決してなく、過渡期のアルバムになるのだと思う。この後がないので過渡期にはなりえないのだが。King Crimsonでいえば「Earthbound」、Chick CoreaでいえばCircleなわけで、このあとに「太陽と戦慄」や「RED」、「Return to Forever」のような素晴らしいアルバムが作られたはずなのに、という残念な気分にさせられるアルバムだ。
 est / Leucocyte : スヴェンソンは今年の6月に事故で亡くなったので、これがおそらく遺作になる。スヴェンソン本人はこのあと死ぬなんて全く思っていなかったに違いないので、死を思わせるようなものは何もない。即興演奏の一発どりを編集したアルバムなので、ひたすらスネアの連打でキーボードが聞こえないパートが延々と続いたりして、曲としての完成度が高いとは決して言えない。それよりも何かを追い求めるエネルギーのようなものを感じるアルバムだ。彼らの最高作では決してなく、過渡期のアルバムになるのだと思う。この後がないので過渡期にはなりえないのだが。King Crimsonでいえば「Earthbound」、Chick CoreaでいえばCircleなわけで、このあとに「太陽と戦慄」や「RED」、「Return to Forever」のような素晴らしいアルバムが作られたはずなのに、という残念な気分にさせられるアルバムだ。
est / Leucocyte : スヴェンソンは今年の6月に事故で亡くなったので、これがおそらく遺作になる。スヴェンソン本人はこのあと死ぬなんて全く思っていなかったに違いないので、死を思わせるようなものは何もない。即興演奏の一発どりを編集したアルバムなので、ひたすらスネアの連打でキーボードが聞こえないパートが延々と続いたりして、曲としての完成度が高いとは決して言えない。それよりも何かを追い求めるエネルギーのようなものを感じるアルバムだ。彼らの最高作では決してなく、過渡期のアルバムになるのだと思う。この後がないので過渡期にはなりえないのだが。King Crimsonでいえば「Earthbound」、Chick CoreaでいえばCircleなわけで、このあとに「太陽と戦慄」や「RED」、「Return to Forever」のような素晴らしいアルバムが作られたはずなのに、という残念な気分にさせられるアルバムだ。Aug.26 CD : Jonathan Nott
 Jonathan Nott + Bamberger Symphoniker : Mahler / Symphony No.4 : ジョナサン・ノットとバンベルク響のマーラー、第3段。演奏時間も短いし、構成もマーラーにしては古典的な交響曲に近いので人気が高い曲だと思うが、個人的には苦手。第1番と同じく全体的にゆっくりとしたテンポ。丁寧で、音色はとてもやわらかい演奏。このような演奏をするなら木管はもっと柔らかく吹ければいいのにと思うが、これはオケの技量なので仕方がない。弦はあいかわらず南ドイツっぽいふくよかな音がする。とにかく丁寧で過不足がなく、無理に誇張した点や無理がない。逆を言えばそれほど面白くないということになるが、録音がいいので充分だ。第3楽章の終りの方で、破たんなく盛り上がるあたりなどすばらしい。第4楽章のソロを歌うのはモイカ・エルドマン。
Jonathan Nott + Bamberger Symphoniker : Mahler / Symphony No.4 : ジョナサン・ノットとバンベルク響のマーラー、第3段。演奏時間も短いし、構成もマーラーにしては古典的な交響曲に近いので人気が高い曲だと思うが、個人的には苦手。第1番と同じく全体的にゆっくりとしたテンポ。丁寧で、音色はとてもやわらかい演奏。このような演奏をするなら木管はもっと柔らかく吹ければいいのにと思うが、これはオケの技量なので仕方がない。弦はあいかわらず南ドイツっぽいふくよかな音がする。とにかく丁寧で過不足がなく、無理に誇張した点や無理がない。逆を言えばそれほど面白くないということになるが、録音がいいので充分だ。第3楽章の終りの方で、破たんなく盛り上がるあたりなどすばらしい。第4楽章のソロを歌うのはモイカ・エルドマン。
 Jonathan Nott + Bamberger Symphoniker : Mahler / Symphony No.4 : ジョナサン・ノットとバンベルク響のマーラー、第3段。演奏時間も短いし、構成もマーラーにしては古典的な交響曲に近いので人気が高い曲だと思うが、個人的には苦手。第1番と同じく全体的にゆっくりとしたテンポ。丁寧で、音色はとてもやわらかい演奏。このような演奏をするなら木管はもっと柔らかく吹ければいいのにと思うが、これはオケの技量なので仕方がない。弦はあいかわらず南ドイツっぽいふくよかな音がする。とにかく丁寧で過不足がなく、無理に誇張した点や無理がない。逆を言えばそれほど面白くないということになるが、録音がいいので充分だ。第3楽章の終りの方で、破たんなく盛り上がるあたりなどすばらしい。第4楽章のソロを歌うのはモイカ・エルドマン。
Jonathan Nott + Bamberger Symphoniker : Mahler / Symphony No.4 : ジョナサン・ノットとバンベルク響のマーラー、第3段。演奏時間も短いし、構成もマーラーにしては古典的な交響曲に近いので人気が高い曲だと思うが、個人的には苦手。第1番と同じく全体的にゆっくりとしたテンポ。丁寧で、音色はとてもやわらかい演奏。このような演奏をするなら木管はもっと柔らかく吹ければいいのにと思うが、これはオケの技量なので仕方がない。弦はあいかわらず南ドイツっぽいふくよかな音がする。とにかく丁寧で過不足がなく、無理に誇張した点や無理がない。逆を言えばそれほど面白くないということになるが、録音がいいので充分だ。第3楽章の終りの方で、破たんなく盛り上がるあたりなどすばらしい。第4楽章のソロを歌うのはモイカ・エルドマン。Aug.26 CD : Pieter Wispelwey
 Pieter Wispelwey : Shostakovich / Cello Concerto No.2 : これもコンスタントに録音が出るペーター・ウィスペルウェイの新譜。 ショスタコーヴィチの協奏曲第2番とブリテンの組曲第3番。この2人の関係の深さは言うまでもないが、両作品とも初演はロストロポーヴィチだ。ただ、無伴奏チェロ組曲は、ロストロポーヴィッチは第3番の録音はなかったはず(放送録音などが正規発売されているかもしれないので明言できないが)。どちらも陰のある作品なのでなかなか聴こうと思わないのが難点。演奏評もできません。ウィスペルウェイのチェロの音の良さ、テクニックの素晴らしさは相変わらずで、録音もいい。
Pieter Wispelwey : Shostakovich / Cello Concerto No.2 : これもコンスタントに録音が出るペーター・ウィスペルウェイの新譜。 ショスタコーヴィチの協奏曲第2番とブリテンの組曲第3番。この2人の関係の深さは言うまでもないが、両作品とも初演はロストロポーヴィチだ。ただ、無伴奏チェロ組曲は、ロストロポーヴィッチは第3番の録音はなかったはず(放送録音などが正規発売されているかもしれないので明言できないが)。どちらも陰のある作品なのでなかなか聴こうと思わないのが難点。演奏評もできません。ウィスペルウェイのチェロの音の良さ、テクニックの素晴らしさは相変わらずで、録音もいい。
 Pieter Wispelwey : Shostakovich / Cello Concerto No.2 : これもコンスタントに録音が出るペーター・ウィスペルウェイの新譜。 ショスタコーヴィチの協奏曲第2番とブリテンの組曲第3番。この2人の関係の深さは言うまでもないが、両作品とも初演はロストロポーヴィチだ。ただ、無伴奏チェロ組曲は、ロストロポーヴィッチは第3番の録音はなかったはず(放送録音などが正規発売されているかもしれないので明言できないが)。どちらも陰のある作品なのでなかなか聴こうと思わないのが難点。演奏評もできません。ウィスペルウェイのチェロの音の良さ、テクニックの素晴らしさは相変わらずで、録音もいい。
Pieter Wispelwey : Shostakovich / Cello Concerto No.2 : これもコンスタントに録音が出るペーター・ウィスペルウェイの新譜。 ショスタコーヴィチの協奏曲第2番とブリテンの組曲第3番。この2人の関係の深さは言うまでもないが、両作品とも初演はロストロポーヴィチだ。ただ、無伴奏チェロ組曲は、ロストロポーヴィッチは第3番の録音はなかったはず(放送録音などが正規発売されているかもしれないので明言できないが)。どちらも陰のある作品なのでなかなか聴こうと思わないのが難点。演奏評もできません。ウィスペルウェイのチェロの音の良さ、テクニックの素晴らしさは相変わらずで、録音もいい。Aug.25 ブログ通信簿
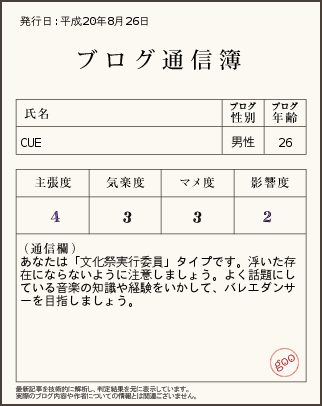
数週間話題に遅れているが、ブログ通信簿を試してみたpingの設定は初期設定から全くいじっていないのに、うまくgooに送れていっていなかったようで、何回やっても「あなたの最近のブログが見つかりません」と出ていたのだが、何かの拍子にうまくいったみたい。年齢が実年齢より約10歳も若いので、一瞬をぉっと喜んでしまったが、よくよく考えれば「表現が幼稚」っていわれてるのかな。主張度が高いのに影響度が低いのも「あまり読まれてないよ」って言われてるみたいでウツです。
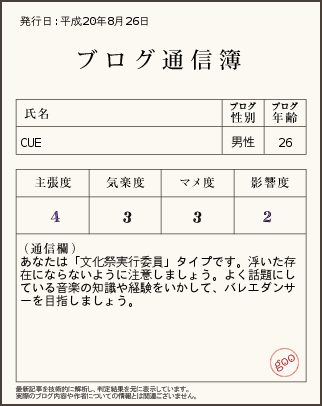
数週間話題に遅れているが、ブログ通信簿を試してみたpingの設定は初期設定から全くいじっていないのに、うまくgooに送れていっていなかったようで、何回やっても「あなたの最近のブログが見つかりません」と出ていたのだが、何かの拍子にうまくいったみたい。年齢が実年齢より約10歳も若いので、一瞬をぉっと喜んでしまったが、よくよく考えれば「表現が幼稚」っていわれてるのかな。主張度が高いのに影響度が低いのも「あまり読まれてないよ」って言われてるみたいでウツです。
Aug.23 CD : Francois Leleux
 Francois Leleux : Mozart / Alles Fuehhlt der liebe Freuden : フランソワ・ルルーのモーツァルト集。オーボエ協奏曲、フルート協奏曲の編曲、ロンド、フィガロのアリアを編曲したものが4曲、ドン・ジョヴァンニのアリアを編曲したものが4曲である。アリアの編曲はルルー自身。オーボエもオーケストラも、とても音色が気持ちいアルバム。ルルーの音色はとても甘くて柔らかい。といって音が細いわけではなく、印象が近いのはシェレンベルガーだろうか。シェレンベルガーの録音はバックがベルリン・フィル(指揮はレヴァイン)のせいか、彼の音色の柔らかさに比べれば全体的に筋肉質に聴こえる演奏。アルブレヒト・マイヤーのモーツァルト・アルバムと交互にかけてみたが、どちらも良い…優劣をつけるのはあまり意味がありません。吹き振りなのだが、カメラータ・ザルツブルクの音も素晴らしい。もちろん古楽奏法なのだが、編成が小さく統制がとれていて音が美しい。また、ドン・ジョヴァンニの"手を取り合って"のアリアでのチェロのソロがすばらしい。ジャケットに書いていあるルルーのプロフィールを読むと、ヨーロッパ室内管でソロを取っていると書いてあるが、バイエルン放送響のトップだったことは書いていない。一番大きなキャリアだと思うんだけど。
Francois Leleux : Mozart / Alles Fuehhlt der liebe Freuden : フランソワ・ルルーのモーツァルト集。オーボエ協奏曲、フルート協奏曲の編曲、ロンド、フィガロのアリアを編曲したものが4曲、ドン・ジョヴァンニのアリアを編曲したものが4曲である。アリアの編曲はルルー自身。オーボエもオーケストラも、とても音色が気持ちいアルバム。ルルーの音色はとても甘くて柔らかい。といって音が細いわけではなく、印象が近いのはシェレンベルガーだろうか。シェレンベルガーの録音はバックがベルリン・フィル(指揮はレヴァイン)のせいか、彼の音色の柔らかさに比べれば全体的に筋肉質に聴こえる演奏。アルブレヒト・マイヤーのモーツァルト・アルバムと交互にかけてみたが、どちらも良い…優劣をつけるのはあまり意味がありません。吹き振りなのだが、カメラータ・ザルツブルクの音も素晴らしい。もちろん古楽奏法なのだが、編成が小さく統制がとれていて音が美しい。また、ドン・ジョヴァンニの"手を取り合って"のアリアでのチェロのソロがすばらしい。ジャケットに書いていあるルルーのプロフィールを読むと、ヨーロッパ室内管でソロを取っていると書いてあるが、バイエルン放送響のトップだったことは書いていない。一番大きなキャリアだと思うんだけど。
 Francois Leleux : Mozart / Alles Fuehhlt der liebe Freuden : フランソワ・ルルーのモーツァルト集。オーボエ協奏曲、フルート協奏曲の編曲、ロンド、フィガロのアリアを編曲したものが4曲、ドン・ジョヴァンニのアリアを編曲したものが4曲である。アリアの編曲はルルー自身。オーボエもオーケストラも、とても音色が気持ちいアルバム。ルルーの音色はとても甘くて柔らかい。といって音が細いわけではなく、印象が近いのはシェレンベルガーだろうか。シェレンベルガーの録音はバックがベルリン・フィル(指揮はレヴァイン)のせいか、彼の音色の柔らかさに比べれば全体的に筋肉質に聴こえる演奏。アルブレヒト・マイヤーのモーツァルト・アルバムと交互にかけてみたが、どちらも良い…優劣をつけるのはあまり意味がありません。吹き振りなのだが、カメラータ・ザルツブルクの音も素晴らしい。もちろん古楽奏法なのだが、編成が小さく統制がとれていて音が美しい。また、ドン・ジョヴァンニの"手を取り合って"のアリアでのチェロのソロがすばらしい。ジャケットに書いていあるルルーのプロフィールを読むと、ヨーロッパ室内管でソロを取っていると書いてあるが、バイエルン放送響のトップだったことは書いていない。一番大きなキャリアだと思うんだけど。
Francois Leleux : Mozart / Alles Fuehhlt der liebe Freuden : フランソワ・ルルーのモーツァルト集。オーボエ協奏曲、フルート協奏曲の編曲、ロンド、フィガロのアリアを編曲したものが4曲、ドン・ジョヴァンニのアリアを編曲したものが4曲である。アリアの編曲はルルー自身。オーボエもオーケストラも、とても音色が気持ちいアルバム。ルルーの音色はとても甘くて柔らかい。といって音が細いわけではなく、印象が近いのはシェレンベルガーだろうか。シェレンベルガーの録音はバックがベルリン・フィル(指揮はレヴァイン)のせいか、彼の音色の柔らかさに比べれば全体的に筋肉質に聴こえる演奏。アルブレヒト・マイヤーのモーツァルト・アルバムと交互にかけてみたが、どちらも良い…優劣をつけるのはあまり意味がありません。吹き振りなのだが、カメラータ・ザルツブルクの音も素晴らしい。もちろん古楽奏法なのだが、編成が小さく統制がとれていて音が美しい。また、ドン・ジョヴァンニの"手を取り合って"のアリアでのチェロのソロがすばらしい。ジャケットに書いていあるルルーのプロフィールを読むと、ヨーロッパ室内管でソロを取っていると書いてあるが、バイエルン放送響のトップだったことは書いていない。一番大きなキャリアだと思うんだけど。Aug.23 CD : Bychkov
 Semyon Bychkov + WDR Sinfonieorchester Koeln : Verdi / Requiem : コンスタントに録音が出るビシュコフ+ケルン放送響 (WDR Sinfonieorchester Koeln)の新譜。このコンビの録音はAvie Recordsというレーベルのものと、Profilからのものがあるが、これはProfilから。しかも、ライブ録音ではなく、セッションでの録音。メジャーレーベルでもなかなかセッション録音を行うことができないのに、いくら放送局付きオーケストラとはいえ、なかなか贅沢で力が入っている。録音を通して、耳に残るのは音の空気の感触だ。SACDでマルチチャンネル録音なのだが、うちの再生機ではステレオでしか聴くことができない。それでも、ティンパニの残響のリアルさ、空気感がとても耳に残る。基本的に派手な曲なのだが、ビシュコフは無理にハデハデしくすることなく、カッコよく決めている。この曲のハイライトだと勝手に思っているDies Iraeの部分だけでも楽しめる。アバド + ベルリン・フィルのような筋肉質なカッコよさは足りないのだけれども、これはオケの特色なので仕方がない。Sanctusのオペラじみたところも演出過剰にならず、嫌みなく聴こえる。あと、コーラスにとてもパワーのある録音だ。
Semyon Bychkov + WDR Sinfonieorchester Koeln : Verdi / Requiem : コンスタントに録音が出るビシュコフ+ケルン放送響 (WDR Sinfonieorchester Koeln)の新譜。このコンビの録音はAvie Recordsというレーベルのものと、Profilからのものがあるが、これはProfilから。しかも、ライブ録音ではなく、セッションでの録音。メジャーレーベルでもなかなかセッション録音を行うことができないのに、いくら放送局付きオーケストラとはいえ、なかなか贅沢で力が入っている。録音を通して、耳に残るのは音の空気の感触だ。SACDでマルチチャンネル録音なのだが、うちの再生機ではステレオでしか聴くことができない。それでも、ティンパニの残響のリアルさ、空気感がとても耳に残る。基本的に派手な曲なのだが、ビシュコフは無理にハデハデしくすることなく、カッコよく決めている。この曲のハイライトだと勝手に思っているDies Iraeの部分だけでも楽しめる。アバド + ベルリン・フィルのような筋肉質なカッコよさは足りないのだけれども、これはオケの特色なので仕方がない。Sanctusのオペラじみたところも演出過剰にならず、嫌みなく聴こえる。あと、コーラスにとてもパワーのある録音だ。
 Semyon Bychkov + WDR Sinfonieorchester Koeln : Verdi / Requiem : コンスタントに録音が出るビシュコフ+ケルン放送響 (WDR Sinfonieorchester Koeln)の新譜。このコンビの録音はAvie Recordsというレーベルのものと、Profilからのものがあるが、これはProfilから。しかも、ライブ録音ではなく、セッションでの録音。メジャーレーベルでもなかなかセッション録音を行うことができないのに、いくら放送局付きオーケストラとはいえ、なかなか贅沢で力が入っている。録音を通して、耳に残るのは音の空気の感触だ。SACDでマルチチャンネル録音なのだが、うちの再生機ではステレオでしか聴くことができない。それでも、ティンパニの残響のリアルさ、空気感がとても耳に残る。基本的に派手な曲なのだが、ビシュコフは無理にハデハデしくすることなく、カッコよく決めている。この曲のハイライトだと勝手に思っているDies Iraeの部分だけでも楽しめる。アバド + ベルリン・フィルのような筋肉質なカッコよさは足りないのだけれども、これはオケの特色なので仕方がない。Sanctusのオペラじみたところも演出過剰にならず、嫌みなく聴こえる。あと、コーラスにとてもパワーのある録音だ。
Semyon Bychkov + WDR Sinfonieorchester Koeln : Verdi / Requiem : コンスタントに録音が出るビシュコフ+ケルン放送響 (WDR Sinfonieorchester Koeln)の新譜。このコンビの録音はAvie Recordsというレーベルのものと、Profilからのものがあるが、これはProfilから。しかも、ライブ録音ではなく、セッションでの録音。メジャーレーベルでもなかなかセッション録音を行うことができないのに、いくら放送局付きオーケストラとはいえ、なかなか贅沢で力が入っている。録音を通して、耳に残るのは音の空気の感触だ。SACDでマルチチャンネル録音なのだが、うちの再生機ではステレオでしか聴くことができない。それでも、ティンパニの残響のリアルさ、空気感がとても耳に残る。基本的に派手な曲なのだが、ビシュコフは無理にハデハデしくすることなく、カッコよく決めている。この曲のハイライトだと勝手に思っているDies Iraeの部分だけでも楽しめる。アバド + ベルリン・フィルのような筋肉質なカッコよさは足りないのだけれども、これはオケの特色なので仕方がない。Sanctusのオペラじみたところも演出過剰にならず、嫌みなく聴こえる。あと、コーラスにとてもパワーのある録音だ。Aug.23 CD : pupa
 pupa / floating pupa : 高橋幸宏が原田知世らと作ったユニットpupaのアルバム。他のメンバーは高野寛、権藤知彦、堀江博久、高田漣と、YMOファミリーで固められている。Sketch Showの頃から見られる「チリチリ」な音が支配的で、mumのようなエレクトロニカのサウンドと、ユキヒロが元々好んでいるヨーロッパっぽいクールなテクノポップさがうまく融合している。5曲目や6曲目は、残念なほど高野寛のソロで彼らしさが出てしまっているのだが、違和感を感じないのはアレンジのせいなのかな。11曲目が日本のフォークっぽい曲で、逆に目立ってしまっているかな。原田知世は作詞もしているが、ボーカルを取っている曲は3曲程度。スチールギターっぽい音の入りが気持ちいい曲が何曲かある。耳触りがいいのでぼーっと聞けてしまうが、音がとても作りこまれていて、よくい考えて音を選んで制作しているのがよくわかる。とてもいいアルバムだ。
pupa / floating pupa : 高橋幸宏が原田知世らと作ったユニットpupaのアルバム。他のメンバーは高野寛、権藤知彦、堀江博久、高田漣と、YMOファミリーで固められている。Sketch Showの頃から見られる「チリチリ」な音が支配的で、mumのようなエレクトロニカのサウンドと、ユキヒロが元々好んでいるヨーロッパっぽいクールなテクノポップさがうまく融合している。5曲目や6曲目は、残念なほど高野寛のソロで彼らしさが出てしまっているのだが、違和感を感じないのはアレンジのせいなのかな。11曲目が日本のフォークっぽい曲で、逆に目立ってしまっているかな。原田知世は作詞もしているが、ボーカルを取っている曲は3曲程度。スチールギターっぽい音の入りが気持ちいい曲が何曲かある。耳触りがいいのでぼーっと聞けてしまうが、音がとても作りこまれていて、よくい考えて音を選んで制作しているのがよくわかる。とてもいいアルバムだ。
 pupa / floating pupa : 高橋幸宏が原田知世らと作ったユニットpupaのアルバム。他のメンバーは高野寛、権藤知彦、堀江博久、高田漣と、YMOファミリーで固められている。Sketch Showの頃から見られる「チリチリ」な音が支配的で、mumのようなエレクトロニカのサウンドと、ユキヒロが元々好んでいるヨーロッパっぽいクールなテクノポップさがうまく融合している。5曲目や6曲目は、残念なほど高野寛のソロで彼らしさが出てしまっているのだが、違和感を感じないのはアレンジのせいなのかな。11曲目が日本のフォークっぽい曲で、逆に目立ってしまっているかな。原田知世は作詞もしているが、ボーカルを取っている曲は3曲程度。スチールギターっぽい音の入りが気持ちいい曲が何曲かある。耳触りがいいのでぼーっと聞けてしまうが、音がとても作りこまれていて、よくい考えて音を選んで制作しているのがよくわかる。とてもいいアルバムだ。
pupa / floating pupa : 高橋幸宏が原田知世らと作ったユニットpupaのアルバム。他のメンバーは高野寛、権藤知彦、堀江博久、高田漣と、YMOファミリーで固められている。Sketch Showの頃から見られる「チリチリ」な音が支配的で、mumのようなエレクトロニカのサウンドと、ユキヒロが元々好んでいるヨーロッパっぽいクールなテクノポップさがうまく融合している。5曲目や6曲目は、残念なほど高野寛のソロで彼らしさが出てしまっているのだが、違和感を感じないのはアレンジのせいなのかな。11曲目が日本のフォークっぽい曲で、逆に目立ってしまっているかな。原田知世は作詞もしているが、ボーカルを取っている曲は3曲程度。スチールギターっぽい音の入りが気持ちいい曲が何曲かある。耳触りがいいのでぼーっと聞けてしまうが、音がとても作りこまれていて、よくい考えて音を選んで制作しているのがよくわかる。とてもいいアルバムだ。Aug.23 CD : Keith Emerson
 Keith Emerson Band featuring Marc Bonilla : キース・エマーソンの新作。ソロ名義でここまでロックなアルバムは初めてなのかな。腕の故障などでパッとしなかったし、ピアノソロのアルバムなどは出していたけれど。2005年の来日公演はそこそこ良かったので、いい流れなんだろう。どこを聴いてもエマーソン節。ELPの時から何も変わっていないといってしまえばそのままだが、ロック、とくにハードロックとはそういうものだ。あと、エマーソンはやはりいいサポートをするミュージシャンと一緒に仕事をしないとダメなんだろうな。一人じゃいい仕事ができない。このアルバムでは、マーク・ボニーラが的確なギターとエマーソン好みの甘いボーカルを取っていて、いいサポートをしている。そして、このアルバムを良くしているのはボニーラではなく、実はドラムのグレッグ・ビゾネットなのではないだろうか。彼のビートが重くて安定したリズムが、走りやすいエマーソンをコントロールして、いい録音にしていると思う。カール・パーマーではこうなりません。そういえばビゾネットはスティーブ・ヴァイのレーベルからソロアルバムを出したり、Joe SatrianiやAndy Summersのアルバムに参加したりと、よく録音で楽しめたが、最近あまり活動状況が網に引っ掛かってこないな。
Keith Emerson Band featuring Marc Bonilla : キース・エマーソンの新作。ソロ名義でここまでロックなアルバムは初めてなのかな。腕の故障などでパッとしなかったし、ピアノソロのアルバムなどは出していたけれど。2005年の来日公演はそこそこ良かったので、いい流れなんだろう。どこを聴いてもエマーソン節。ELPの時から何も変わっていないといってしまえばそのままだが、ロック、とくにハードロックとはそういうものだ。あと、エマーソンはやはりいいサポートをするミュージシャンと一緒に仕事をしないとダメなんだろうな。一人じゃいい仕事ができない。このアルバムでは、マーク・ボニーラが的確なギターとエマーソン好みの甘いボーカルを取っていて、いいサポートをしている。そして、このアルバムを良くしているのはボニーラではなく、実はドラムのグレッグ・ビゾネットなのではないだろうか。彼のビートが重くて安定したリズムが、走りやすいエマーソンをコントロールして、いい録音にしていると思う。カール・パーマーではこうなりません。そういえばビゾネットはスティーブ・ヴァイのレーベルからソロアルバムを出したり、Joe SatrianiやAndy Summersのアルバムに参加したりと、よく録音で楽しめたが、最近あまり活動状況が網に引っ掛かってこないな。
 Keith Emerson Band featuring Marc Bonilla : キース・エマーソンの新作。ソロ名義でここまでロックなアルバムは初めてなのかな。腕の故障などでパッとしなかったし、ピアノソロのアルバムなどは出していたけれど。2005年の来日公演はそこそこ良かったので、いい流れなんだろう。どこを聴いてもエマーソン節。ELPの時から何も変わっていないといってしまえばそのままだが、ロック、とくにハードロックとはそういうものだ。あと、エマーソンはやはりいいサポートをするミュージシャンと一緒に仕事をしないとダメなんだろうな。一人じゃいい仕事ができない。このアルバムでは、マーク・ボニーラが的確なギターとエマーソン好みの甘いボーカルを取っていて、いいサポートをしている。そして、このアルバムを良くしているのはボニーラではなく、実はドラムのグレッグ・ビゾネットなのではないだろうか。彼のビートが重くて安定したリズムが、走りやすいエマーソンをコントロールして、いい録音にしていると思う。カール・パーマーではこうなりません。そういえばビゾネットはスティーブ・ヴァイのレーベルからソロアルバムを出したり、Joe SatrianiやAndy Summersのアルバムに参加したりと、よく録音で楽しめたが、最近あまり活動状況が網に引っ掛かってこないな。
Keith Emerson Band featuring Marc Bonilla : キース・エマーソンの新作。ソロ名義でここまでロックなアルバムは初めてなのかな。腕の故障などでパッとしなかったし、ピアノソロのアルバムなどは出していたけれど。2005年の来日公演はそこそこ良かったので、いい流れなんだろう。どこを聴いてもエマーソン節。ELPの時から何も変わっていないといってしまえばそのままだが、ロック、とくにハードロックとはそういうものだ。あと、エマーソンはやはりいいサポートをするミュージシャンと一緒に仕事をしないとダメなんだろうな。一人じゃいい仕事ができない。このアルバムでは、マーク・ボニーラが的確なギターとエマーソン好みの甘いボーカルを取っていて、いいサポートをしている。そして、このアルバムを良くしているのはボニーラではなく、実はドラムのグレッグ・ビゾネットなのではないだろうか。彼のビートが重くて安定したリズムが、走りやすいエマーソンをコントロールして、いい録音にしていると思う。カール・パーマーではこうなりません。そういえばビゾネットはスティーブ・ヴァイのレーベルからソロアルバムを出したり、Joe SatrianiやAndy Summersのアルバムに参加したりと、よく録音で楽しめたが、最近あまり活動状況が網に引っ掛かってこないな。Aug.23 DVD : 高円寺百景
 高円寺百景 / 070531 : ライブDVD。タイトル通り2007月5月31日に吉祥寺Star Pine's Cafeで行われたライブの映像。PA席からのワンカメ映像だが、比較的きれいに撮れている。金澤美也子が脱退して、矢吹卓が加入したものの、この日は不参加だったために、吉田達也 (d,vo)、坂元健吾 (b,vo)、小森慶子 (sax,cl) , 久保田安紀 (vo)のメンバーに、ホッピー神山と石橋英子がキーボードで加わり、おまけに今堀恒雄 (g)と壷井彰久 (vn)がゲスト参加という豪華キャスティングのライブだった。前半がデュオ→トリオ→カルテットとメンバー構成を変えての即興演奏で、後半が百景の曲というプログラムだった。この日のライブは生で見ているので、感想はこれを変わるものではない。そう、梅雨入りかなぁと思わせる豪雨の日だった。
高円寺百景 / 070531 : ライブDVD。タイトル通り2007月5月31日に吉祥寺Star Pine's Cafeで行われたライブの映像。PA席からのワンカメ映像だが、比較的きれいに撮れている。金澤美也子が脱退して、矢吹卓が加入したものの、この日は不参加だったために、吉田達也 (d,vo)、坂元健吾 (b,vo)、小森慶子 (sax,cl) , 久保田安紀 (vo)のメンバーに、ホッピー神山と石橋英子がキーボードで加わり、おまけに今堀恒雄 (g)と壷井彰久 (vn)がゲスト参加という豪華キャスティングのライブだった。前半がデュオ→トリオ→カルテットとメンバー構成を変えての即興演奏で、後半が百景の曲というプログラムだった。この日のライブは生で見ているので、感想はこれを変わるものではない。そう、梅雨入りかなぁと思わせる豪雨の日だった。
 高円寺百景 / 070531 : ライブDVD。タイトル通り2007月5月31日に吉祥寺Star Pine's Cafeで行われたライブの映像。PA席からのワンカメ映像だが、比較的きれいに撮れている。金澤美也子が脱退して、矢吹卓が加入したものの、この日は不参加だったために、吉田達也 (d,vo)、坂元健吾 (b,vo)、小森慶子 (sax,cl) , 久保田安紀 (vo)のメンバーに、ホッピー神山と石橋英子がキーボードで加わり、おまけに今堀恒雄 (g)と壷井彰久 (vn)がゲスト参加という豪華キャスティングのライブだった。前半がデュオ→トリオ→カルテットとメンバー構成を変えての即興演奏で、後半が百景の曲というプログラムだった。この日のライブは生で見ているので、感想はこれを変わるものではない。そう、梅雨入りかなぁと思わせる豪雨の日だった。
高円寺百景 / 070531 : ライブDVD。タイトル通り2007月5月31日に吉祥寺Star Pine's Cafeで行われたライブの映像。PA席からのワンカメ映像だが、比較的きれいに撮れている。金澤美也子が脱退して、矢吹卓が加入したものの、この日は不参加だったために、吉田達也 (d,vo)、坂元健吾 (b,vo)、小森慶子 (sax,cl) , 久保田安紀 (vo)のメンバーに、ホッピー神山と石橋英子がキーボードで加わり、おまけに今堀恒雄 (g)と壷井彰久 (vn)がゲスト参加という豪華キャスティングのライブだった。前半がデュオ→トリオ→カルテットとメンバー構成を変えての即興演奏で、後半が百景の曲というプログラムだった。この日のライブは生で見ているので、感想はこれを変わるものではない。そう、梅雨入りかなぁと思わせる豪雨の日だった。Aug.23 CD : Jannick Top
 Jannick Top / Infernal Machina : MAGMAのベーシストとして有名な、ヤニック・トップのソロ作。ソロ名義のアルバムは初めてなのではないだろうか。パート1からパート11の部分とコーダの"resolutio"の12部に分かれる。邦題が「呪われし機械」…MAGMAにも"Mekanik Machine "って曲があったし、こういう響きの言葉が好きなのかな。全体的な印象は、今までのトップの作曲を追っかけていたら「なんだか聴いたことがあるな」と思う、過去の
Jannick Top / Infernal Machina : MAGMAのベーシストとして有名な、ヤニック・トップのソロ作。ソロ名義のアルバムは初めてなのではないだろうか。パート1からパート11の部分とコーダの"resolutio"の12部に分かれる。邦題が「呪われし機械」…MAGMAにも"Mekanik Machine "って曲があったし、こういう響きの言葉が好きなのかな。全体的な印象は、今までのトップの作曲を追っかけていたら「なんだか聴いたことがあるな」と思う、過去の焼きなおし 集大成。ドラムは、Hadrien FeraudのソロやEric La LennとJannick Topとの連作アルバム「Le Lann Top」で叩いているDamien Schmitt。この人は、ほんとにうまい。アンビエント〜呪術的な声から、トップらしいリフがパート3から現れる。そのままパート4でKlaus Blasquizの声が。ここでMAGMA風を感じさせたと思ったら、パート5で"De Futura"のリフが。そのまま"De Futura"でパート6まで進む。後半でJames McGaw (g)と思われる鋭いギターソロが入る。ピアノがきれいで一瞬Mike Oldfieldっぽくも聴こえる7曲目からはドラムがChristian Vanderに変わる。パート8はMDKっぽいピアノのコードにVanderのドラムと地鳴りのするトップのベース。演奏としてはここからパート9が一番聴きどころかも。激しいソロも特になく、呪術的なヴォーカルが戻ってきてパート11が終わる。Stella Vander (vo)、Himiko Paganotti (vo)、Antoine Paganotti (vo)といったMAGMA組も参加しているらしいが細かなクレジットはない。あのヤニック・トップのソロ作が、と過剰に期待してしまうと肩透かしを食らうが、完成度は高いし、MAGMAファンなら聞いておくべき作品かな。
 Jannick Top / Infernal Machina : MAGMAのベーシストとして有名な、ヤニック・トップのソロ作。ソロ名義のアルバムは初めてなのではないだろうか。パート1からパート11の部分とコーダの"resolutio"の12部に分かれる。邦題が「呪われし機械」…MAGMAにも"Mekanik Machine "って曲があったし、こういう響きの言葉が好きなのかな。全体的な印象は、今までのトップの作曲を追っかけていたら「なんだか聴いたことがあるな」と思う、過去の
Jannick Top / Infernal Machina : MAGMAのベーシストとして有名な、ヤニック・トップのソロ作。ソロ名義のアルバムは初めてなのではないだろうか。パート1からパート11の部分とコーダの"resolutio"の12部に分かれる。邦題が「呪われし機械」…MAGMAにも"Mekanik Machine "って曲があったし、こういう響きの言葉が好きなのかな。全体的な印象は、今までのトップの作曲を追っかけていたら「なんだか聴いたことがあるな」と思う、過去のAug.19 DVD : Welser-Moest
 Welser-Moest + Zurich Opera House : R.Strauss / Arabella : ウェルザー・メスト指揮、チューリッヒ歌劇場のコンビの映像。このコンビの映像はEMIから発売されていたが、主役のフレミングの契約のためかDeccaから発売されている。演目はR.シュトラウスの「アラベラ」。この作品はミュンヘンで見たことがあるが(指揮はペーター・シュナイダー、主役はカミラ・ニュールンド)、そのときみたプロダクションの印象からすると、オーソドックスな演出。しかも、舞踏会のシーンなどはお金がかかっていて、画的にも美しく派手で、青色が印象的な演出。意外なことにゲッツ・フリードリッヒの演出だそうだ。ばらの騎士と同じく、ウィーン世紀末の雰囲気の出たオペラで、プロットもそれほど悪くないのに、ワルツが少ないせいか、重唱が少ないせいか、ばらほど人気がないような気がする。さっきも書いたが、アラベラはシュトラウスのオペラをいろいろ歌っているレネ・フレミング。もっと若くていろんな男をふらふらする感じが出ててもいいと思いますが。でも、このオペラって冷静に見るとズデンカの方が主役に見えるんですけどね。ズデンカ役のユリア・クライターという人だが、声も動きもいい。ウェルザーメストの指揮は、いつものごとくシャープで気持ちのいいものです。
Welser-Moest + Zurich Opera House : R.Strauss / Arabella : ウェルザー・メスト指揮、チューリッヒ歌劇場のコンビの映像。このコンビの映像はEMIから発売されていたが、主役のフレミングの契約のためかDeccaから発売されている。演目はR.シュトラウスの「アラベラ」。この作品はミュンヘンで見たことがあるが(指揮はペーター・シュナイダー、主役はカミラ・ニュールンド)、そのときみたプロダクションの印象からすると、オーソドックスな演出。しかも、舞踏会のシーンなどはお金がかかっていて、画的にも美しく派手で、青色が印象的な演出。意外なことにゲッツ・フリードリッヒの演出だそうだ。ばらの騎士と同じく、ウィーン世紀末の雰囲気の出たオペラで、プロットもそれほど悪くないのに、ワルツが少ないせいか、重唱が少ないせいか、ばらほど人気がないような気がする。さっきも書いたが、アラベラはシュトラウスのオペラをいろいろ歌っているレネ・フレミング。もっと若くていろんな男をふらふらする感じが出ててもいいと思いますが。でも、このオペラって冷静に見るとズデンカの方が主役に見えるんですけどね。ズデンカ役のユリア・クライターという人だが、声も動きもいい。ウェルザーメストの指揮は、いつものごとくシャープで気持ちのいいものです。
 Welser-Moest + Zurich Opera House : R.Strauss / Arabella : ウェルザー・メスト指揮、チューリッヒ歌劇場のコンビの映像。このコンビの映像はEMIから発売されていたが、主役のフレミングの契約のためかDeccaから発売されている。演目はR.シュトラウスの「アラベラ」。この作品はミュンヘンで見たことがあるが(指揮はペーター・シュナイダー、主役はカミラ・ニュールンド)、そのときみたプロダクションの印象からすると、オーソドックスな演出。しかも、舞踏会のシーンなどはお金がかかっていて、画的にも美しく派手で、青色が印象的な演出。意外なことにゲッツ・フリードリッヒの演出だそうだ。ばらの騎士と同じく、ウィーン世紀末の雰囲気の出たオペラで、プロットもそれほど悪くないのに、ワルツが少ないせいか、重唱が少ないせいか、ばらほど人気がないような気がする。さっきも書いたが、アラベラはシュトラウスのオペラをいろいろ歌っているレネ・フレミング。もっと若くていろんな男をふらふらする感じが出ててもいいと思いますが。でも、このオペラって冷静に見るとズデンカの方が主役に見えるんですけどね。ズデンカ役のユリア・クライターという人だが、声も動きもいい。ウェルザーメストの指揮は、いつものごとくシャープで気持ちのいいものです。
Welser-Moest + Zurich Opera House : R.Strauss / Arabella : ウェルザー・メスト指揮、チューリッヒ歌劇場のコンビの映像。このコンビの映像はEMIから発売されていたが、主役のフレミングの契約のためかDeccaから発売されている。演目はR.シュトラウスの「アラベラ」。この作品はミュンヘンで見たことがあるが(指揮はペーター・シュナイダー、主役はカミラ・ニュールンド)、そのときみたプロダクションの印象からすると、オーソドックスな演出。しかも、舞踏会のシーンなどはお金がかかっていて、画的にも美しく派手で、青色が印象的な演出。意外なことにゲッツ・フリードリッヒの演出だそうだ。ばらの騎士と同じく、ウィーン世紀末の雰囲気の出たオペラで、プロットもそれほど悪くないのに、ワルツが少ないせいか、重唱が少ないせいか、ばらほど人気がないような気がする。さっきも書いたが、アラベラはシュトラウスのオペラをいろいろ歌っているレネ・フレミング。もっと若くていろんな男をふらふらする感じが出ててもいいと思いますが。でも、このオペラって冷静に見るとズデンカの方が主役に見えるんですけどね。ズデンカ役のユリア・クライターという人だが、声も動きもいい。ウェルザーメストの指揮は、いつものごとくシャープで気持ちのいいものです。Aug.19 CD : Rattle
 Simon Rattle + Berlin Philharmoniker : Berlioz / Symphonie Fantastique : ラトルとベルリン・フィルの新譜はベルリオーズ。幻想交響曲と「クレオパトラの死」から2曲。もともとライブ録音の予定だったが、フィルハーモニー(カラヤン・サーカス)が火事になったため、コンサートはもうすぐなくなるテンペルホフ空港で行われた。さすがに、空港の倉庫ではライブ録音ができなかったようで、この録音はベルリン・イエス・キリスト教会でのスタジオ収録となっている。この教会での幻想の録音といえば、カラヤンやマルケヴィッチのものがあるが、どちらもグラモフォン。これらの比べると、このディスクはやはりEMIっぽい音像の遠さを感じる。演奏の方だが、第1楽章ではそれほど感じなかったのだが、後ろの楽章に進むほどボヤけた演奏になっている。各楽器がうまく融合していないのと、リズムが単調に機械的に進んでいく。第4楽章でテーマを吹くトランペットの力のなさって何なんだろう。それぞれの楽器はやはりうまいし、弦の音も素晴らしい。第5楽章も、鐘がなんか遠いところでなっているし、結末に向かっての推進力に欠ける。…ドホナーニとかティルソン=トーマスとかの演奏で耳が慣れすぎたか。
Simon Rattle + Berlin Philharmoniker : Berlioz / Symphonie Fantastique : ラトルとベルリン・フィルの新譜はベルリオーズ。幻想交響曲と「クレオパトラの死」から2曲。もともとライブ録音の予定だったが、フィルハーモニー(カラヤン・サーカス)が火事になったため、コンサートはもうすぐなくなるテンペルホフ空港で行われた。さすがに、空港の倉庫ではライブ録音ができなかったようで、この録音はベルリン・イエス・キリスト教会でのスタジオ収録となっている。この教会での幻想の録音といえば、カラヤンやマルケヴィッチのものがあるが、どちらもグラモフォン。これらの比べると、このディスクはやはりEMIっぽい音像の遠さを感じる。演奏の方だが、第1楽章ではそれほど感じなかったのだが、後ろの楽章に進むほどボヤけた演奏になっている。各楽器がうまく融合していないのと、リズムが単調に機械的に進んでいく。第4楽章でテーマを吹くトランペットの力のなさって何なんだろう。それぞれの楽器はやはりうまいし、弦の音も素晴らしい。第5楽章も、鐘がなんか遠いところでなっているし、結末に向かっての推進力に欠ける。…ドホナーニとかティルソン=トーマスとかの演奏で耳が慣れすぎたか。
 Simon Rattle + Berlin Philharmoniker : Berlioz / Symphonie Fantastique : ラトルとベルリン・フィルの新譜はベルリオーズ。幻想交響曲と「クレオパトラの死」から2曲。もともとライブ録音の予定だったが、フィルハーモニー(カラヤン・サーカス)が火事になったため、コンサートはもうすぐなくなるテンペルホフ空港で行われた。さすがに、空港の倉庫ではライブ録音ができなかったようで、この録音はベルリン・イエス・キリスト教会でのスタジオ収録となっている。この教会での幻想の録音といえば、カラヤンやマルケヴィッチのものがあるが、どちらもグラモフォン。これらの比べると、このディスクはやはりEMIっぽい音像の遠さを感じる。演奏の方だが、第1楽章ではそれほど感じなかったのだが、後ろの楽章に進むほどボヤけた演奏になっている。各楽器がうまく融合していないのと、リズムが単調に機械的に進んでいく。第4楽章でテーマを吹くトランペットの力のなさって何なんだろう。それぞれの楽器はやはりうまいし、弦の音も素晴らしい。第5楽章も、鐘がなんか遠いところでなっているし、結末に向かっての推進力に欠ける。…ドホナーニとかティルソン=トーマスとかの演奏で耳が慣れすぎたか。
Simon Rattle + Berlin Philharmoniker : Berlioz / Symphonie Fantastique : ラトルとベルリン・フィルの新譜はベルリオーズ。幻想交響曲と「クレオパトラの死」から2曲。もともとライブ録音の予定だったが、フィルハーモニー(カラヤン・サーカス)が火事になったため、コンサートはもうすぐなくなるテンペルホフ空港で行われた。さすがに、空港の倉庫ではライブ録音ができなかったようで、この録音はベルリン・イエス・キリスト教会でのスタジオ収録となっている。この教会での幻想の録音といえば、カラヤンやマルケヴィッチのものがあるが、どちらもグラモフォン。これらの比べると、このディスクはやはりEMIっぽい音像の遠さを感じる。演奏の方だが、第1楽章ではそれほど感じなかったのだが、後ろの楽章に進むほどボヤけた演奏になっている。各楽器がうまく融合していないのと、リズムが単調に機械的に進んでいく。第4楽章でテーマを吹くトランペットの力のなさって何なんだろう。それぞれの楽器はやはりうまいし、弦の音も素晴らしい。第5楽章も、鐘がなんか遠いところでなっているし、結末に向かっての推進力に欠ける。…ドホナーニとかティルソン=トーマスとかの演奏で耳が慣れすぎたか。Aug.19 CD : Avishai Cohen
 Avishai Cohen / Gently Disturbed : タワレコで試聴機にかかっているのを見かけたのだが、ピアノトリオという気分でもなかったので見ないふりをしていた。アヴィシャイ・コーエンといえば、チック・コリアのOriginでの演奏は聴いたことがあるが、Originというユニット自体あまり好きではなく、ベースもそれほど印象に残っていなかったというのもある。後輩の家で飲んでいるとき、彼がこのアルバムを買っており、聴かせてもらった。変拍子だらけでめちゃめちゃカッコいい上に、ピアノの音がとてもいい!すぐに買ってきた。ベース弾きらしい拍子へのこだわりと、マイナーが主体のコードの動きがとてもカッコいいアルバムだ。曲は熱いんだけど、演奏と音がクール。個人的にはベースのフレーズがカッコいい2曲目が気に入った。6曲目なんかはe.s.t(Esbjörn Svensson Trio)っぽくも聴こえる。8曲目の中盤以降の弾けるような曲もいい。あとは4曲目が好みか。このトリオのピアニスト、名前が変わっていてShai Maestroという。「シャイ・マエストロ」…シャイな巨匠ですよ。このトリオ、もうすこしアルバムを買ってみよう。
Avishai Cohen / Gently Disturbed : タワレコで試聴機にかかっているのを見かけたのだが、ピアノトリオという気分でもなかったので見ないふりをしていた。アヴィシャイ・コーエンといえば、チック・コリアのOriginでの演奏は聴いたことがあるが、Originというユニット自体あまり好きではなく、ベースもそれほど印象に残っていなかったというのもある。後輩の家で飲んでいるとき、彼がこのアルバムを買っており、聴かせてもらった。変拍子だらけでめちゃめちゃカッコいい上に、ピアノの音がとてもいい!すぐに買ってきた。ベース弾きらしい拍子へのこだわりと、マイナーが主体のコードの動きがとてもカッコいいアルバムだ。曲は熱いんだけど、演奏と音がクール。個人的にはベースのフレーズがカッコいい2曲目が気に入った。6曲目なんかはe.s.t(Esbjörn Svensson Trio)っぽくも聴こえる。8曲目の中盤以降の弾けるような曲もいい。あとは4曲目が好みか。このトリオのピアニスト、名前が変わっていてShai Maestroという。「シャイ・マエストロ」…シャイな巨匠ですよ。このトリオ、もうすこしアルバムを買ってみよう。
 Avishai Cohen / Gently Disturbed : タワレコで試聴機にかかっているのを見かけたのだが、ピアノトリオという気分でもなかったので見ないふりをしていた。アヴィシャイ・コーエンといえば、チック・コリアのOriginでの演奏は聴いたことがあるが、Originというユニット自体あまり好きではなく、ベースもそれほど印象に残っていなかったというのもある。後輩の家で飲んでいるとき、彼がこのアルバムを買っており、聴かせてもらった。変拍子だらけでめちゃめちゃカッコいい上に、ピアノの音がとてもいい!すぐに買ってきた。ベース弾きらしい拍子へのこだわりと、マイナーが主体のコードの動きがとてもカッコいいアルバムだ。曲は熱いんだけど、演奏と音がクール。個人的にはベースのフレーズがカッコいい2曲目が気に入った。6曲目なんかはe.s.t(Esbjörn Svensson Trio)っぽくも聴こえる。8曲目の中盤以降の弾けるような曲もいい。あとは4曲目が好みか。このトリオのピアニスト、名前が変わっていてShai Maestroという。「シャイ・マエストロ」…シャイな巨匠ですよ。このトリオ、もうすこしアルバムを買ってみよう。
Avishai Cohen / Gently Disturbed : タワレコで試聴機にかかっているのを見かけたのだが、ピアノトリオという気分でもなかったので見ないふりをしていた。アヴィシャイ・コーエンといえば、チック・コリアのOriginでの演奏は聴いたことがあるが、Originというユニット自体あまり好きではなく、ベースもそれほど印象に残っていなかったというのもある。後輩の家で飲んでいるとき、彼がこのアルバムを買っており、聴かせてもらった。変拍子だらけでめちゃめちゃカッコいい上に、ピアノの音がとてもいい!すぐに買ってきた。ベース弾きらしい拍子へのこだわりと、マイナーが主体のコードの動きがとてもカッコいいアルバムだ。曲は熱いんだけど、演奏と音がクール。個人的にはベースのフレーズがカッコいい2曲目が気に入った。6曲目なんかはe.s.t(Esbjörn Svensson Trio)っぽくも聴こえる。8曲目の中盤以降の弾けるような曲もいい。あとは4曲目が好みか。このトリオのピアニスト、名前が変わっていてShai Maestroという。「シャイ・マエストロ」…シャイな巨匠ですよ。このトリオ、もうすこしアルバムを買ってみよう。Aug.19 CD : Boulez
 Pierre Boulez + Uchida : Berg / Chamber Symphony : 今月はブーレーズの新譜が2枚。まず、内田光子とテツラフがソロを弾いたベルクの室内協奏曲と、モーツァルトのグラン・パルティータ。これが同じアルバムに入ってるのはどちらも13管楽器の作品だからだろうな。ベルクの室内協奏曲はブーレーズにとっては3回目の録音ですかね。グラモフォンに、バレンボイムとズッカーマンと、今回と同じくアンサンブル・アンテルコンタンポランとの録音がある。比較して聴いてみたが、この曲、面白くないですね。今回の録音は緊張感もありとてもいい演奏だと思うけど、いい曲じゃない。グラン・パルティータは「ブーレーズ初のモーツァルト録音」のように書いてある記事も見たが、ピリスとのピアノ協奏曲(第20番)の映像などがある。全体的にしゃきしゃきとしてストレートな演奏。最終楽章などは快速で気持ちいいが、モーツァルトっぽい色彩感には乏しいかもしれない。
Pierre Boulez + Uchida : Berg / Chamber Symphony : 今月はブーレーズの新譜が2枚。まず、内田光子とテツラフがソロを弾いたベルクの室内協奏曲と、モーツァルトのグラン・パルティータ。これが同じアルバムに入ってるのはどちらも13管楽器の作品だからだろうな。ベルクの室内協奏曲はブーレーズにとっては3回目の録音ですかね。グラモフォンに、バレンボイムとズッカーマンと、今回と同じくアンサンブル・アンテルコンタンポランとの録音がある。比較して聴いてみたが、この曲、面白くないですね。今回の録音は緊張感もありとてもいい演奏だと思うけど、いい曲じゃない。グラン・パルティータは「ブーレーズ初のモーツァルト録音」のように書いてある記事も見たが、ピリスとのピアノ協奏曲(第20番)の映像などがある。全体的にしゃきしゃきとしてストレートな演奏。最終楽章などは快速で気持ちいいが、モーツァルトっぽい色彩感には乏しいかもしれない。
 Pierre Boulez + London SO , Berlin Philharmoniker , Kremer , Bashmet : Bartok / Concertos : ブーレーズのバルトーク録音はこれで終了らしい。"2台のピアノと打楽器のための協奏曲"のみオーケストラがロンドン交響楽団。これはソナタをそのまま管弦楽にアレンジしたものだが、編成が大きくなるせいか、ソナタに比べてシャープさが欠ける曲だと思う。この録音もリズムのシャープさに欠ける感がある。残りの2曲のオーケストラはベルリン・フィル。まずヴァイオリン協奏曲第1番の方だが、クレーメルがしんどい。もちろん下手なわけではないのだが、妙に力んだり歌いまわしたりしているように聴こえる。オーケストラの方は、気持ちいいくらい機動性を発揮して伴奏しているのだが。最後はヴィオラ協奏曲。この演奏も、伴奏の機動力が気持ちい演奏だ。ソロのバシュメットもすばらしい。バシュメットのソロはクレーメルと同じく演出過剰に聴こえるところもあるが、クレーメルほど気にならないのは音色に艶があり耳触りがいいからなのかもしれない。
Pierre Boulez + London SO , Berlin Philharmoniker , Kremer , Bashmet : Bartok / Concertos : ブーレーズのバルトーク録音はこれで終了らしい。"2台のピアノと打楽器のための協奏曲"のみオーケストラがロンドン交響楽団。これはソナタをそのまま管弦楽にアレンジしたものだが、編成が大きくなるせいか、ソナタに比べてシャープさが欠ける曲だと思う。この録音もリズムのシャープさに欠ける感がある。残りの2曲のオーケストラはベルリン・フィル。まずヴァイオリン協奏曲第1番の方だが、クレーメルがしんどい。もちろん下手なわけではないのだが、妙に力んだり歌いまわしたりしているように聴こえる。オーケストラの方は、気持ちいいくらい機動性を発揮して伴奏しているのだが。最後はヴィオラ協奏曲。この演奏も、伴奏の機動力が気持ちい演奏だ。ソロのバシュメットもすばらしい。バシュメットのソロはクレーメルと同じく演出過剰に聴こえるところもあるが、クレーメルほど気にならないのは音色に艶があり耳触りがいいからなのかもしれない。
 Pierre Boulez + Uchida : Berg / Chamber Symphony : 今月はブーレーズの新譜が2枚。まず、内田光子とテツラフがソロを弾いたベルクの室内協奏曲と、モーツァルトのグラン・パルティータ。これが同じアルバムに入ってるのはどちらも13管楽器の作品だからだろうな。ベルクの室内協奏曲はブーレーズにとっては3回目の録音ですかね。グラモフォンに、バレンボイムとズッカーマンと、今回と同じくアンサンブル・アンテルコンタンポランとの録音がある。比較して聴いてみたが、この曲、面白くないですね。今回の録音は緊張感もありとてもいい演奏だと思うけど、いい曲じゃない。グラン・パルティータは「ブーレーズ初のモーツァルト録音」のように書いてある記事も見たが、ピリスとのピアノ協奏曲(第20番)の映像などがある。全体的にしゃきしゃきとしてストレートな演奏。最終楽章などは快速で気持ちいいが、モーツァルトっぽい色彩感には乏しいかもしれない。
Pierre Boulez + Uchida : Berg / Chamber Symphony : 今月はブーレーズの新譜が2枚。まず、内田光子とテツラフがソロを弾いたベルクの室内協奏曲と、モーツァルトのグラン・パルティータ。これが同じアルバムに入ってるのはどちらも13管楽器の作品だからだろうな。ベルクの室内協奏曲はブーレーズにとっては3回目の録音ですかね。グラモフォンに、バレンボイムとズッカーマンと、今回と同じくアンサンブル・アンテルコンタンポランとの録音がある。比較して聴いてみたが、この曲、面白くないですね。今回の録音は緊張感もありとてもいい演奏だと思うけど、いい曲じゃない。グラン・パルティータは「ブーレーズ初のモーツァルト録音」のように書いてある記事も見たが、ピリスとのピアノ協奏曲(第20番)の映像などがある。全体的にしゃきしゃきとしてストレートな演奏。最終楽章などは快速で気持ちいいが、モーツァルトっぽい色彩感には乏しいかもしれない。 Pierre Boulez + London SO , Berlin Philharmoniker , Kremer , Bashmet : Bartok / Concertos : ブーレーズのバルトーク録音はこれで終了らしい。"2台のピアノと打楽器のための協奏曲"のみオーケストラがロンドン交響楽団。これはソナタをそのまま管弦楽にアレンジしたものだが、編成が大きくなるせいか、ソナタに比べてシャープさが欠ける曲だと思う。この録音もリズムのシャープさに欠ける感がある。残りの2曲のオーケストラはベルリン・フィル。まずヴァイオリン協奏曲第1番の方だが、クレーメルがしんどい。もちろん下手なわけではないのだが、妙に力んだり歌いまわしたりしているように聴こえる。オーケストラの方は、気持ちいいくらい機動性を発揮して伴奏しているのだが。最後はヴィオラ協奏曲。この演奏も、伴奏の機動力が気持ちい演奏だ。ソロのバシュメットもすばらしい。バシュメットのソロはクレーメルと同じく演出過剰に聴こえるところもあるが、クレーメルほど気にならないのは音色に艶があり耳触りがいいからなのかもしれない。
Pierre Boulez + London SO , Berlin Philharmoniker , Kremer , Bashmet : Bartok / Concertos : ブーレーズのバルトーク録音はこれで終了らしい。"2台のピアノと打楽器のための協奏曲"のみオーケストラがロンドン交響楽団。これはソナタをそのまま管弦楽にアレンジしたものだが、編成が大きくなるせいか、ソナタに比べてシャープさが欠ける曲だと思う。この録音もリズムのシャープさに欠ける感がある。残りの2曲のオーケストラはベルリン・フィル。まずヴァイオリン協奏曲第1番の方だが、クレーメルがしんどい。もちろん下手なわけではないのだが、妙に力んだり歌いまわしたりしているように聴こえる。オーケストラの方は、気持ちいいくらい機動性を発揮して伴奏しているのだが。最後はヴィオラ協奏曲。この演奏も、伴奏の機動力が気持ちい演奏だ。ソロのバシュメットもすばらしい。バシュメットのソロはクレーメルと同じく演出過剰に聴こえるところもあるが、クレーメルほど気にならないのは音色に艶があり耳触りがいいからなのかもしれない。Aug.17 KENSO @ 川崎クラブチッタ
KENSOのライブに行ってきた。昨年の5月のライブは仕事とバッティングして行けなかったので、一昨年の10月以来。気分的なものもあるのだが、最近はあまりロックを聴かずにクラシックばかり聴いている。ここ1年くらいCDでもKENSOを真剣に聴いた覚えはあまりない。なので、あまり期待感もなく、どちらかといえば義務感のようなもので行ってしまった。いつ聴けなくなるかわからないしな…というのも含めて義務感。当日券ですんなり入れる。座席は500くらい用意されていると思うが、後ろ5列は真ん中しか埋まっていない。一番後ろの席に堂々と座る。始めに答えを書いてしまえば、とてもよかったのだ。冒頭が"Good Days Bad Days"〜"願いをかなえる子供をつれていこう"といきなりハイライトで演奏されるような曲のメドレー。休みを入れずに"麻酔"〜"精武門"のメドレー。このメドレーがとても気持ちよくつながるアレンジになっていた思う。2年前のライブの感想に「ライブ用メドレーアレンジをすることもなく、唐突に曲が終わったりするのも残念」と書いているが、やっぱりKENSOのライブの楽しみの一つは、この絶妙のメドレーだ。ここで清水さんより自ら「飛ばしすぎ」というコメントが。MCが少なかったのも緊張感が途切れなくて良かったのかな。MCが少ないは、演奏に対して気合いが入っていたからなのかもしれない。ステージも良く、なんかヴァリライトみたいなのを使っているし照明がやたらと凝っていた。新曲が4曲あったが(僕が初めて聴いた曲が4曲、昨年のライブで演奏した曲もあったのかもしれない)、妙な講釈や民族音楽への頑なな傾倒が感じられず、GENSISやPFMが好きなんだなぁということを感じさせるKENSOらしい広がりを感じるロックな曲になっていた。新しいアルバムも近いのでしょうか。光田のソロの時、美深のキーボードソロアレンジを弾いていて、心にしみました。そのあとの小口ソロ(with 小森)〜"GOS"〜"Tjandi Bentar"も小口ワールド全開。"Echi dal Foro Romano"は何回聴いてもいい曲なので、いいと書くだけバカらしい。このライブで一番いい演奏は冒頭の2つのメドレーと"氷島"だったと思う。アンコールは"月の位相II"〜"月の位相I"。やっぱり「夢の丘」の曲は個人的に好きなんだな。お約束のように2回目のアンコールがあって、美深のグループでの演奏と憎たらしい演出。今年のライブはプログラムの構成が素晴らしかったのではないだろうか。
Aug.16 オーディオアンプ

 今使っているアンプは、Marantz PM44SEで、大学2年か3年の時に購入したもの。6〜7年前からアンプとスピーカーを買い替えようと計画していたのだが、特にきっかけもなくそのままになっていた。その当時、オーディオショップをいろいろ周って試聴して、Musical FidelityのアンプA3.2CRが欲しいなと思っていた。ところがそのうち、そのアンプは品切れになり、Musical Fidelityのアンプ自体、日本であまり取扱いされることがなくなったようだ。ネットで海外から購入することは簡単だが、アンプのようなオーディオ製品の場合、電圧が違うので使うのは簡単ではない。こういったことも、買い替える気がなくなった理由の一つだろう。しかし、今使っているアンプがもう15年近く使っているためガリが多く、ときどき片方のチャンネルの音が出なくなったりしていた。他のブランドのアンプを見たり聴いたりしてもピンとこない(アキュフェーズが良いのはわかるが、普通すぎてつまらない)。最近、musicFieldというオークションサイトにMusical Fidelity A3.2の中古品が出品されており、価格も妥当だったので、入札してみることにした。結局入札者が誰もいず、最低価格で落札。出品者はaudio unionで、商品に問題は何もなかった。とりあえずつないで見て、ちょっとだけ音を出してみた。エージングもしていないし、スピーカーはYAMAHAのNS-10Mのままだが、音の立ち上がりの良さと空間解像度の良さは実感できた。クラシックの弦の音がいい。ジャズをかけたら、ちょっと紙っぽい音がしたが、スピーカーのせいだ。スピーカーも買い変えたくなってきた……。当然アンプに、ヘッドホンコネクタはついていないので、ヘッドホンアンプも購入。Audio TechnicaのAT-HA20。ちょっとエコーがかかっているように聞こえるのは気のせいかな。
今使っているアンプは、Marantz PM44SEで、大学2年か3年の時に購入したもの。6〜7年前からアンプとスピーカーを買い替えようと計画していたのだが、特にきっかけもなくそのままになっていた。その当時、オーディオショップをいろいろ周って試聴して、Musical FidelityのアンプA3.2CRが欲しいなと思っていた。ところがそのうち、そのアンプは品切れになり、Musical Fidelityのアンプ自体、日本であまり取扱いされることがなくなったようだ。ネットで海外から購入することは簡単だが、アンプのようなオーディオ製品の場合、電圧が違うので使うのは簡単ではない。こういったことも、買い替える気がなくなった理由の一つだろう。しかし、今使っているアンプがもう15年近く使っているためガリが多く、ときどき片方のチャンネルの音が出なくなったりしていた。他のブランドのアンプを見たり聴いたりしてもピンとこない(アキュフェーズが良いのはわかるが、普通すぎてつまらない)。最近、musicFieldというオークションサイトにMusical Fidelity A3.2の中古品が出品されており、価格も妥当だったので、入札してみることにした。結局入札者が誰もいず、最低価格で落札。出品者はaudio unionで、商品に問題は何もなかった。とりあえずつないで見て、ちょっとだけ音を出してみた。エージングもしていないし、スピーカーはYAMAHAのNS-10Mのままだが、音の立ち上がりの良さと空間解像度の良さは実感できた。クラシックの弦の音がいい。ジャズをかけたら、ちょっと紙っぽい音がしたが、スピーカーのせいだ。スピーカーも買い変えたくなってきた……。当然アンプに、ヘッドホンコネクタはついていないので、ヘッドホンアンプも購入。Audio TechnicaのAT-HA20。ちょっとエコーがかかっているように聞こえるのは気のせいかな。

 今使っているアンプは、Marantz PM44SEで、大学2年か3年の時に購入したもの。6〜7年前からアンプとスピーカーを買い替えようと計画していたのだが、特にきっかけもなくそのままになっていた。その当時、オーディオショップをいろいろ周って試聴して、Musical FidelityのアンプA3.2CRが欲しいなと思っていた。ところがそのうち、そのアンプは品切れになり、Musical Fidelityのアンプ自体、日本であまり取扱いされることがなくなったようだ。ネットで海外から購入することは簡単だが、アンプのようなオーディオ製品の場合、電圧が違うので使うのは簡単ではない。こういったことも、買い替える気がなくなった理由の一つだろう。しかし、今使っているアンプがもう15年近く使っているためガリが多く、ときどき片方のチャンネルの音が出なくなったりしていた。他のブランドのアンプを見たり聴いたりしてもピンとこない(アキュフェーズが良いのはわかるが、普通すぎてつまらない)。最近、musicFieldというオークションサイトにMusical Fidelity A3.2の中古品が出品されており、価格も妥当だったので、入札してみることにした。結局入札者が誰もいず、最低価格で落札。出品者はaudio unionで、商品に問題は何もなかった。とりあえずつないで見て、ちょっとだけ音を出してみた。エージングもしていないし、スピーカーはYAMAHAのNS-10Mのままだが、音の立ち上がりの良さと空間解像度の良さは実感できた。クラシックの弦の音がいい。ジャズをかけたら、ちょっと紙っぽい音がしたが、スピーカーのせいだ。スピーカーも買い変えたくなってきた……。当然アンプに、ヘッドホンコネクタはついていないので、ヘッドホンアンプも購入。Audio TechnicaのAT-HA20。ちょっとエコーがかかっているように聞こえるのは気のせいかな。
今使っているアンプは、Marantz PM44SEで、大学2年か3年の時に購入したもの。6〜7年前からアンプとスピーカーを買い替えようと計画していたのだが、特にきっかけもなくそのままになっていた。その当時、オーディオショップをいろいろ周って試聴して、Musical FidelityのアンプA3.2CRが欲しいなと思っていた。ところがそのうち、そのアンプは品切れになり、Musical Fidelityのアンプ自体、日本であまり取扱いされることがなくなったようだ。ネットで海外から購入することは簡単だが、アンプのようなオーディオ製品の場合、電圧が違うので使うのは簡単ではない。こういったことも、買い替える気がなくなった理由の一つだろう。しかし、今使っているアンプがもう15年近く使っているためガリが多く、ときどき片方のチャンネルの音が出なくなったりしていた。他のブランドのアンプを見たり聴いたりしてもピンとこない(アキュフェーズが良いのはわかるが、普通すぎてつまらない)。最近、musicFieldというオークションサイトにMusical Fidelity A3.2の中古品が出品されており、価格も妥当だったので、入札してみることにした。結局入札者が誰もいず、最低価格で落札。出品者はaudio unionで、商品に問題は何もなかった。とりあえずつないで見て、ちょっとだけ音を出してみた。エージングもしていないし、スピーカーはYAMAHAのNS-10Mのままだが、音の立ち上がりの良さと空間解像度の良さは実感できた。クラシックの弦の音がいい。ジャズをかけたら、ちょっと紙っぽい音がしたが、スピーカーのせいだ。スピーカーも買い変えたくなってきた……。当然アンプに、ヘッドホンコネクタはついていないので、ヘッドホンアンプも購入。Audio TechnicaのAT-HA20。ちょっとエコーがかかっているように聞こえるのは気のせいかな。Aug.9 ポイントカード
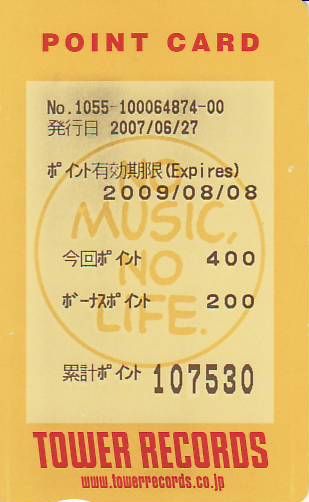 僕はあまりポイントカードに執着しないほうだと思う。あらゆる店のポイントカードを常備していて、飲みに行ったりするとさっとカードを出し、旅行や買い物でいかに組み合わせれば得なポイントがたまるかということに詳しい人が周りにもいる。しかし、僕は面倒くさがりで、財布が膨らむのが嫌いだ。しかし、クレジットカードのポイントと、飛行機のマイル、そしてタワーレコードのポイントカードだけは貯めている。タワーレコードのポイントカードは、以前は500円買うと1ポイントつき、100ポイントたまるとカードがいっぱいになって、そのカードを出せば3000円引いてもらえるというものだった。そのころは、CDを買い続けているとポイントカードが何枚も財布にたまり、うっとおしくなってきたころにカードを出して割引してもらうというようにしていた。ところが、何年か前にシステムが変わり、同じカードにずっとポイントが加算されるシステムになった。こちらから、ポイントを使って割り引いてください、といわないと貯まり続けるシステムになった。それから2年ほどたったのかな。「ポイント使ってください」といわずに買い続けていたら、これだけポイントが貯まってしまいました。100000。そう、このカードを使えばタワレコで10万円買い物ができるのだ………何を買ったらいいんだろう?
僕はあまりポイントカードに執着しないほうだと思う。あらゆる店のポイントカードを常備していて、飲みに行ったりするとさっとカードを出し、旅行や買い物でいかに組み合わせれば得なポイントがたまるかということに詳しい人が周りにもいる。しかし、僕は面倒くさがりで、財布が膨らむのが嫌いだ。しかし、クレジットカードのポイントと、飛行機のマイル、そしてタワーレコードのポイントカードだけは貯めている。タワーレコードのポイントカードは、以前は500円買うと1ポイントつき、100ポイントたまるとカードがいっぱいになって、そのカードを出せば3000円引いてもらえるというものだった。そのころは、CDを買い続けているとポイントカードが何枚も財布にたまり、うっとおしくなってきたころにカードを出して割引してもらうというようにしていた。ところが、何年か前にシステムが変わり、同じカードにずっとポイントが加算されるシステムになった。こちらから、ポイントを使って割り引いてください、といわないと貯まり続けるシステムになった。それから2年ほどたったのかな。「ポイント使ってください」といわずに買い続けていたら、これだけポイントが貯まってしまいました。100000。そう、このカードを使えばタワレコで10万円買い物ができるのだ………何を買ったらいいんだろう?
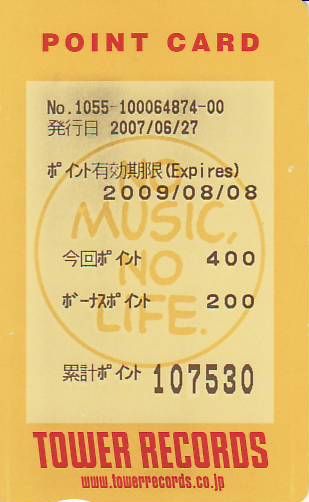 僕はあまりポイントカードに執着しないほうだと思う。あらゆる店のポイントカードを常備していて、飲みに行ったりするとさっとカードを出し、旅行や買い物でいかに組み合わせれば得なポイントがたまるかということに詳しい人が周りにもいる。しかし、僕は面倒くさがりで、財布が膨らむのが嫌いだ。しかし、クレジットカードのポイントと、飛行機のマイル、そしてタワーレコードのポイントカードだけは貯めている。タワーレコードのポイントカードは、以前は500円買うと1ポイントつき、100ポイントたまるとカードがいっぱいになって、そのカードを出せば3000円引いてもらえるというものだった。そのころは、CDを買い続けているとポイントカードが何枚も財布にたまり、うっとおしくなってきたころにカードを出して割引してもらうというようにしていた。ところが、何年か前にシステムが変わり、同じカードにずっとポイントが加算されるシステムになった。こちらから、ポイントを使って割り引いてください、といわないと貯まり続けるシステムになった。それから2年ほどたったのかな。「ポイント使ってください」といわずに買い続けていたら、これだけポイントが貯まってしまいました。100000。そう、このカードを使えばタワレコで10万円買い物ができるのだ………何を買ったらいいんだろう?
僕はあまりポイントカードに執着しないほうだと思う。あらゆる店のポイントカードを常備していて、飲みに行ったりするとさっとカードを出し、旅行や買い物でいかに組み合わせれば得なポイントがたまるかということに詳しい人が周りにもいる。しかし、僕は面倒くさがりで、財布が膨らむのが嫌いだ。しかし、クレジットカードのポイントと、飛行機のマイル、そしてタワーレコードのポイントカードだけは貯めている。タワーレコードのポイントカードは、以前は500円買うと1ポイントつき、100ポイントたまるとカードがいっぱいになって、そのカードを出せば3000円引いてもらえるというものだった。そのころは、CDを買い続けているとポイントカードが何枚も財布にたまり、うっとおしくなってきたころにカードを出して割引してもらうというようにしていた。ところが、何年か前にシステムが変わり、同じカードにずっとポイントが加算されるシステムになった。こちらから、ポイントを使って割り引いてください、といわないと貯まり続けるシステムになった。それから2年ほどたったのかな。「ポイント使ってください」といわずに買い続けていたら、これだけポイントが貯まってしまいました。100000。そう、このカードを使えばタワレコで10万円買い物ができるのだ………何を買ったらいいんだろう?Aug.9 CD : HASYMO
 HASYMO / The City of Light : HASYMO (= Human Audio Sponge + Yellow Magic Orchestra)の1年ぶりのEP。2曲。どちらもアコースティック楽器をメインとしたエレクトロニカな曲。変わったことをしようという意識はもうなく、いい音を作ろうという気持ちがよく伝わる。音のたたずまい、みたいなものに凝っていて、ピアノの残響やそれに被さるパッドの音に耳を惹かれる。いいオーディオで聴きたい。"体操"っぽいと言われればそうかもしれないけど、教授のソロ色が強いということなのかな。ユキヒロのドラムが気持ちいい。
HASYMO / The City of Light : HASYMO (= Human Audio Sponge + Yellow Magic Orchestra)の1年ぶりのEP。2曲。どちらもアコースティック楽器をメインとしたエレクトロニカな曲。変わったことをしようという意識はもうなく、いい音を作ろうという気持ちがよく伝わる。音のたたずまい、みたいなものに凝っていて、ピアノの残響やそれに被さるパッドの音に耳を惹かれる。いいオーディオで聴きたい。"体操"っぽいと言われればそうかもしれないけど、教授のソロ色が強いということなのかな。ユキヒロのドラムが気持ちいい。
 HASYMO / The City of Light : HASYMO (= Human Audio Sponge + Yellow Magic Orchestra)の1年ぶりのEP。2曲。どちらもアコースティック楽器をメインとしたエレクトロニカな曲。変わったことをしようという意識はもうなく、いい音を作ろうという気持ちがよく伝わる。音のたたずまい、みたいなものに凝っていて、ピアノの残響やそれに被さるパッドの音に耳を惹かれる。いいオーディオで聴きたい。"体操"っぽいと言われればそうかもしれないけど、教授のソロ色が強いということなのかな。ユキヒロのドラムが気持ちいい。
HASYMO / The City of Light : HASYMO (= Human Audio Sponge + Yellow Magic Orchestra)の1年ぶりのEP。2曲。どちらもアコースティック楽器をメインとしたエレクトロニカな曲。変わったことをしようという意識はもうなく、いい音を作ろうという気持ちがよく伝わる。音のたたずまい、みたいなものに凝っていて、ピアノの残響やそれに被さるパッドの音に耳を惹かれる。いいオーディオで聴きたい。"体操"っぽいと言われればそうかもしれないけど、教授のソロ色が強いということなのかな。ユキヒロのドラムが気持ちいい。Aug.9 CD : de Billy
 Bertrand de Billy : R.Strauss / Don Juan : ベルトラント・ド・ビリーとウィーン放送響のコンビの新録音。ド・ビリーはオペラ録音も含めて、録音が多すぎではないのか。R.シュトラウスのドン・ファンとイタリアから。ドン・ファンはやや突っ込みすぎじゃないのかと思う程度に速いテンポ。良い演奏だと思う。イタリアより、はやはり曲がぼやっとしている。高校生の頃は何がいいのかさっぱりわからなかったが、今ではそのイタリアらしいメロディの良さがなんとなくわかる。でも、大そうな曲だ。最終楽章のフニクニフニクラも昔はバカっぽいと思ったが、この演奏を聴くと、ここまでうまく曲にまとめられたものだと、シュトラウスのテクニックに感心してしまう。録音がとてもよく、ティンパニや弦のスタッカットの音が際立ってはじめるように聴こえる。弦の音にもっと艶があればいいのだが、それは求めすぎか。録音で繰り返し聴くほどスーパーオケではないが、このレベルのオーケストラを日常的にライブで聴ければ文句がない。日本の放送局オーケストラもこれくらいになってほしいところなんだけど、無理ですかね。
Bertrand de Billy : R.Strauss / Don Juan : ベルトラント・ド・ビリーとウィーン放送響のコンビの新録音。ド・ビリーはオペラ録音も含めて、録音が多すぎではないのか。R.シュトラウスのドン・ファンとイタリアから。ドン・ファンはやや突っ込みすぎじゃないのかと思う程度に速いテンポ。良い演奏だと思う。イタリアより、はやはり曲がぼやっとしている。高校生の頃は何がいいのかさっぱりわからなかったが、今ではそのイタリアらしいメロディの良さがなんとなくわかる。でも、大そうな曲だ。最終楽章のフニクニフニクラも昔はバカっぽいと思ったが、この演奏を聴くと、ここまでうまく曲にまとめられたものだと、シュトラウスのテクニックに感心してしまう。録音がとてもよく、ティンパニや弦のスタッカットの音が際立ってはじめるように聴こえる。弦の音にもっと艶があればいいのだが、それは求めすぎか。録音で繰り返し聴くほどスーパーオケではないが、このレベルのオーケストラを日常的にライブで聴ければ文句がない。日本の放送局オーケストラもこれくらいになってほしいところなんだけど、無理ですかね。
 Bertrand de Billy : R.Strauss / Don Juan : ベルトラント・ド・ビリーとウィーン放送響のコンビの新録音。ド・ビリーはオペラ録音も含めて、録音が多すぎではないのか。R.シュトラウスのドン・ファンとイタリアから。ドン・ファンはやや突っ込みすぎじゃないのかと思う程度に速いテンポ。良い演奏だと思う。イタリアより、はやはり曲がぼやっとしている。高校生の頃は何がいいのかさっぱりわからなかったが、今ではそのイタリアらしいメロディの良さがなんとなくわかる。でも、大そうな曲だ。最終楽章のフニクニフニクラも昔はバカっぽいと思ったが、この演奏を聴くと、ここまでうまく曲にまとめられたものだと、シュトラウスのテクニックに感心してしまう。録音がとてもよく、ティンパニや弦のスタッカットの音が際立ってはじめるように聴こえる。弦の音にもっと艶があればいいのだが、それは求めすぎか。録音で繰り返し聴くほどスーパーオケではないが、このレベルのオーケストラを日常的にライブで聴ければ文句がない。日本の放送局オーケストラもこれくらいになってほしいところなんだけど、無理ですかね。
Bertrand de Billy : R.Strauss / Don Juan : ベルトラント・ド・ビリーとウィーン放送響のコンビの新録音。ド・ビリーはオペラ録音も含めて、録音が多すぎではないのか。R.シュトラウスのドン・ファンとイタリアから。ドン・ファンはやや突っ込みすぎじゃないのかと思う程度に速いテンポ。良い演奏だと思う。イタリアより、はやはり曲がぼやっとしている。高校生の頃は何がいいのかさっぱりわからなかったが、今ではそのイタリアらしいメロディの良さがなんとなくわかる。でも、大そうな曲だ。最終楽章のフニクニフニクラも昔はバカっぽいと思ったが、この演奏を聴くと、ここまでうまく曲にまとめられたものだと、シュトラウスのテクニックに感心してしまう。録音がとてもよく、ティンパニや弦のスタッカットの音が際立ってはじめるように聴こえる。弦の音にもっと艶があればいいのだが、それは求めすぎか。録音で繰り返し聴くほどスーパーオケではないが、このレベルのオーケストラを日常的にライブで聴ければ文句がない。日本の放送局オーケストラもこれくらいになってほしいところなんだけど、無理ですかね。Aug.9 CD : Peter Gabriel
 Peter Gabriel / Big Blue Ball : ピーター・ガブリエルの新譜、ではないそうで、ピーターによるプロジェクト。15年越しのプロジェクト、という触れ込みだが、実際は91年、92年、95年のReal World Studioでのセッションからできたアルバム。Peter Gabrielのプロデュース、というよりは彼のWOMADやReal World Studioのコンセプトが生んだアルバムといったところか。民族音楽やワールドミュージック、ではなく、ヨーロッパの先進国がテクノロジーを多分に使って消化したPeter Gabriel色の強い音楽。やはり「Passion」や「US」に肌触りが似ている。Peterのファンなので"Burn You Up, Burn You Down"や"Exit through You"が気に入ったトラックでした。"Rivers"のマルタ・セバスチャンの声もいい。
Peter Gabriel / Big Blue Ball : ピーター・ガブリエルの新譜、ではないそうで、ピーターによるプロジェクト。15年越しのプロジェクト、という触れ込みだが、実際は91年、92年、95年のReal World Studioでのセッションからできたアルバム。Peter Gabrielのプロデュース、というよりは彼のWOMADやReal World Studioのコンセプトが生んだアルバムといったところか。民族音楽やワールドミュージック、ではなく、ヨーロッパの先進国がテクノロジーを多分に使って消化したPeter Gabriel色の強い音楽。やはり「Passion」や「US」に肌触りが似ている。Peterのファンなので"Burn You Up, Burn You Down"や"Exit through You"が気に入ったトラックでした。"Rivers"のマルタ・セバスチャンの声もいい。
 Peter Gabriel / Big Blue Ball : ピーター・ガブリエルの新譜、ではないそうで、ピーターによるプロジェクト。15年越しのプロジェクト、という触れ込みだが、実際は91年、92年、95年のReal World Studioでのセッションからできたアルバム。Peter Gabrielのプロデュース、というよりは彼のWOMADやReal World Studioのコンセプトが生んだアルバムといったところか。民族音楽やワールドミュージック、ではなく、ヨーロッパの先進国がテクノロジーを多分に使って消化したPeter Gabriel色の強い音楽。やはり「Passion」や「US」に肌触りが似ている。Peterのファンなので"Burn You Up, Burn You Down"や"Exit through You"が気に入ったトラックでした。"Rivers"のマルタ・セバスチャンの声もいい。
Peter Gabriel / Big Blue Ball : ピーター・ガブリエルの新譜、ではないそうで、ピーターによるプロジェクト。15年越しのプロジェクト、という触れ込みだが、実際は91年、92年、95年のReal World Studioでのセッションからできたアルバム。Peter Gabrielのプロデュース、というよりは彼のWOMADやReal World Studioのコンセプトが生んだアルバムといったところか。民族音楽やワールドミュージック、ではなく、ヨーロッパの先進国がテクノロジーを多分に使って消化したPeter Gabriel色の強い音楽。やはり「Passion」や「US」に肌触りが似ている。Peterのファンなので"Burn You Up, Burn You Down"や"Exit through You"が気に入ったトラックでした。"Rivers"のマルタ・セバスチャンの声もいい。Aug.6 CD : Medeski Martin and Wood (John Zorn)
 Medeski Martin and Wood / Book of Angels Vol.11 : メデスキ・マーティン &ウッドの新譜は、ジョン・ゾーンの書いたマサダ作品を演奏したもの。レーベルはもちろんTzadik。冒頭からいきなり凶悪なオルガンの音がする。ラフな音の雰囲気が完全にTzadikの音だ。曲調はもちろんジューイッシュ。ここまで変わってしまうのがわかるのも面白い。演奏自体も即興よりもアレンジで聴かせている部分が多い気がする。そのせいか、1曲目、5曲目、8曲目などベースがカッコいい場面が多い。また、オルガンや4曲目など、ピアノトリオ風で、これまた意外。
Medeski Martin and Wood / Book of Angels Vol.11 : メデスキ・マーティン &ウッドの新譜は、ジョン・ゾーンの書いたマサダ作品を演奏したもの。レーベルはもちろんTzadik。冒頭からいきなり凶悪なオルガンの音がする。ラフな音の雰囲気が完全にTzadikの音だ。曲調はもちろんジューイッシュ。ここまで変わってしまうのがわかるのも面白い。演奏自体も即興よりもアレンジで聴かせている部分が多い気がする。そのせいか、1曲目、5曲目、8曲目などベースがカッコいい場面が多い。また、オルガンや4曲目など、ピアノトリオ風で、これまた意外。
 Medeski Martin and Wood / Book of Angels Vol.11 : メデスキ・マーティン &ウッドの新譜は、ジョン・ゾーンの書いたマサダ作品を演奏したもの。レーベルはもちろんTzadik。冒頭からいきなり凶悪なオルガンの音がする。ラフな音の雰囲気が完全にTzadikの音だ。曲調はもちろんジューイッシュ。ここまで変わってしまうのがわかるのも面白い。演奏自体も即興よりもアレンジで聴かせている部分が多い気がする。そのせいか、1曲目、5曲目、8曲目などベースがカッコいい場面が多い。また、オルガンや4曲目など、ピアノトリオ風で、これまた意外。
Medeski Martin and Wood / Book of Angels Vol.11 : メデスキ・マーティン &ウッドの新譜は、ジョン・ゾーンの書いたマサダ作品を演奏したもの。レーベルはもちろんTzadik。冒頭からいきなり凶悪なオルガンの音がする。ラフな音の雰囲気が完全にTzadikの音だ。曲調はもちろんジューイッシュ。ここまで変わってしまうのがわかるのも面白い。演奏自体も即興よりもアレンジで聴かせている部分が多い気がする。そのせいか、1曲目、5曲目、8曲目などベースがカッコいい場面が多い。また、オルガンや4曲目など、ピアノトリオ風で、これまた意外。Aug.6 CD : Kasarova , Bolton , Dohnanyi
 Kasarova : Handel / Aria for Carestini : カサロヴァのヘンデルといえば、アーニャ・ハルテロスとのキャストで、ボルトンが振ったバイエルン州立歌劇場との「アルチーナ」の録音がとても気に入っていた。バロック・オペラも歌うのかとちょっと意外だったのだが、そのカサロヴァが歌うヘンデルのアリア集。「アリオダンテ」や「アルチーナ」は知ってる曲だが、よく知らない曲のアリアも収録されている。演奏の解釈について語れるほど、まだヘンデルに造詣が深いわけではないが、声の良さと品の良さについては文句のつけようがない。かなりカッコいい歌いっぷり。
Kasarova : Handel / Aria for Carestini : カサロヴァのヘンデルといえば、アーニャ・ハルテロスとのキャストで、ボルトンが振ったバイエルン州立歌劇場との「アルチーナ」の録音がとても気に入っていた。バロック・オペラも歌うのかとちょっと意外だったのだが、そのカサロヴァが歌うヘンデルのアリア集。「アリオダンテ」や「アルチーナ」は知ってる曲だが、よく知らない曲のアリアも収録されている。演奏の解釈について語れるほど、まだヘンデルに造詣が深いわけではないが、声の良さと品の良さについては文句のつけようがない。かなりカッコいい歌いっぷり。
 Ivor Bolton : Symphony No.9 / Bolton : アイヴォー・ボルトンとザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団によるブルックナーの録音第3弾。第7番や第5番と同じ方向性で、特におかしなことをしていない真っ当な演奏。オーケストラの規模はそれほど小編成でもないようだ。この曲ほど時代が降りてこれば、ピリオド奏法がどうとかいった話ではないだろう。第5番のように音を積み重ねて伽藍のように組み上げていく曲には、このコンビの演奏は非常に合っているように感じたが、第9番の場合はその素直さがちょっとマイナスポイントか。天に消え入るような(特に第3楽章)美しさがほしいと思っているので、もうちょっと柔軟さが欲しかった。この曲はクリアな音色で、ちょっと色気のある弦の方がいい。
Ivor Bolton : Symphony No.9 / Bolton : アイヴォー・ボルトンとザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団によるブルックナーの録音第3弾。第7番や第5番と同じ方向性で、特におかしなことをしていない真っ当な演奏。オーケストラの規模はそれほど小編成でもないようだ。この曲ほど時代が降りてこれば、ピリオド奏法がどうとかいった話ではないだろう。第5番のように音を積み重ねて伽藍のように組み上げていく曲には、このコンビの演奏は非常に合っているように感じたが、第9番の場合はその素直さがちょっとマイナスポイントか。天に消え入るような(特に第3楽章)美しさがほしいと思っているので、もうちょっと柔軟さが欲しかった。この曲はクリアな音色で、ちょっと色気のある弦の方がいい。
 Christoph von Dohnanyi : Brahms / Symphony No.2,4 : フィルハーモニア管弦楽団が、Signum Classicsというところからアーカイブ音源を出すようで、その第1弾。首席指揮者のドホナーニが振ったブラームスの交響曲第2番と第4番。1997年から首席のポジションにいるが、2007/08年のシーズンで退任する。ドホナーニはどのレコード会社とも契約していなかったのか、録音に対して前向きでなかっったのかわからないが、フィルハーモニアとの正式な録音はこれまで残していない。ブラームスの交響曲はクリーブランドと全集の録音を残しているが、彼の録音の中でも結構ピンとこない部類に入るものだった。ブルックナーやマーラーの録音に比較しても、彼らしいオケのコントロールと明晰さに欠けるように聴こえるからだ(解釈は別の問題です)。しかし、この2曲の録音はライブであるにもかかわらず、そのドホナーニらしい明晰さとバランス感覚の良さを聴くことができる。オーケストラ自体も状態がよく、フィルハーモニアらしいサウンドをしている。このシリーズでもっとドホナーニの録音を出してほしいものだ。昨年、日本で聴いたNDR放送響との演奏に比べてもはるかにレベルが高い。ちなみに、第2番は全集に比べてテンポは遅め、第4番は速め。
Christoph von Dohnanyi : Brahms / Symphony No.2,4 : フィルハーモニア管弦楽団が、Signum Classicsというところからアーカイブ音源を出すようで、その第1弾。首席指揮者のドホナーニが振ったブラームスの交響曲第2番と第4番。1997年から首席のポジションにいるが、2007/08年のシーズンで退任する。ドホナーニはどのレコード会社とも契約していなかったのか、録音に対して前向きでなかっったのかわからないが、フィルハーモニアとの正式な録音はこれまで残していない。ブラームスの交響曲はクリーブランドと全集の録音を残しているが、彼の録音の中でも結構ピンとこない部類に入るものだった。ブルックナーやマーラーの録音に比較しても、彼らしいオケのコントロールと明晰さに欠けるように聴こえるからだ(解釈は別の問題です)。しかし、この2曲の録音はライブであるにもかかわらず、そのドホナーニらしい明晰さとバランス感覚の良さを聴くことができる。オーケストラ自体も状態がよく、フィルハーモニアらしいサウンドをしている。このシリーズでもっとドホナーニの録音を出してほしいものだ。昨年、日本で聴いたNDR放送響との演奏に比べてもはるかにレベルが高い。ちなみに、第2番は全集に比べてテンポは遅め、第4番は速め。
 Kasarova : Handel / Aria for Carestini : カサロヴァのヘンデルといえば、アーニャ・ハルテロスとのキャストで、ボルトンが振ったバイエルン州立歌劇場との「アルチーナ」の録音がとても気に入っていた。バロック・オペラも歌うのかとちょっと意外だったのだが、そのカサロヴァが歌うヘンデルのアリア集。「アリオダンテ」や「アルチーナ」は知ってる曲だが、よく知らない曲のアリアも収録されている。演奏の解釈について語れるほど、まだヘンデルに造詣が深いわけではないが、声の良さと品の良さについては文句のつけようがない。かなりカッコいい歌いっぷり。
Kasarova : Handel / Aria for Carestini : カサロヴァのヘンデルといえば、アーニャ・ハルテロスとのキャストで、ボルトンが振ったバイエルン州立歌劇場との「アルチーナ」の録音がとても気に入っていた。バロック・オペラも歌うのかとちょっと意外だったのだが、そのカサロヴァが歌うヘンデルのアリア集。「アリオダンテ」や「アルチーナ」は知ってる曲だが、よく知らない曲のアリアも収録されている。演奏の解釈について語れるほど、まだヘンデルに造詣が深いわけではないが、声の良さと品の良さについては文句のつけようがない。かなりカッコいい歌いっぷり。 Ivor Bolton : Symphony No.9 / Bolton : アイヴォー・ボルトンとザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団によるブルックナーの録音第3弾。第7番や第5番と同じ方向性で、特におかしなことをしていない真っ当な演奏。オーケストラの規模はそれほど小編成でもないようだ。この曲ほど時代が降りてこれば、ピリオド奏法がどうとかいった話ではないだろう。第5番のように音を積み重ねて伽藍のように組み上げていく曲には、このコンビの演奏は非常に合っているように感じたが、第9番の場合はその素直さがちょっとマイナスポイントか。天に消え入るような(特に第3楽章)美しさがほしいと思っているので、もうちょっと柔軟さが欲しかった。この曲はクリアな音色で、ちょっと色気のある弦の方がいい。
Ivor Bolton : Symphony No.9 / Bolton : アイヴォー・ボルトンとザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団によるブルックナーの録音第3弾。第7番や第5番と同じ方向性で、特におかしなことをしていない真っ当な演奏。オーケストラの規模はそれほど小編成でもないようだ。この曲ほど時代が降りてこれば、ピリオド奏法がどうとかいった話ではないだろう。第5番のように音を積み重ねて伽藍のように組み上げていく曲には、このコンビの演奏は非常に合っているように感じたが、第9番の場合はその素直さがちょっとマイナスポイントか。天に消え入るような(特に第3楽章)美しさがほしいと思っているので、もうちょっと柔軟さが欲しかった。この曲はクリアな音色で、ちょっと色気のある弦の方がいい。 Christoph von Dohnanyi : Brahms / Symphony No.2,4 : フィルハーモニア管弦楽団が、Signum Classicsというところからアーカイブ音源を出すようで、その第1弾。首席指揮者のドホナーニが振ったブラームスの交響曲第2番と第4番。1997年から首席のポジションにいるが、2007/08年のシーズンで退任する。ドホナーニはどのレコード会社とも契約していなかったのか、録音に対して前向きでなかっったのかわからないが、フィルハーモニアとの正式な録音はこれまで残していない。ブラームスの交響曲はクリーブランドと全集の録音を残しているが、彼の録音の中でも結構ピンとこない部類に入るものだった。ブルックナーやマーラーの録音に比較しても、彼らしいオケのコントロールと明晰さに欠けるように聴こえるからだ(解釈は別の問題です)。しかし、この2曲の録音はライブであるにもかかわらず、そのドホナーニらしい明晰さとバランス感覚の良さを聴くことができる。オーケストラ自体も状態がよく、フィルハーモニアらしいサウンドをしている。このシリーズでもっとドホナーニの録音を出してほしいものだ。昨年、日本で聴いたNDR放送響との演奏に比べてもはるかにレベルが高い。ちなみに、第2番は全集に比べてテンポは遅め、第4番は速め。
Christoph von Dohnanyi : Brahms / Symphony No.2,4 : フィルハーモニア管弦楽団が、Signum Classicsというところからアーカイブ音源を出すようで、その第1弾。首席指揮者のドホナーニが振ったブラームスの交響曲第2番と第4番。1997年から首席のポジションにいるが、2007/08年のシーズンで退任する。ドホナーニはどのレコード会社とも契約していなかったのか、録音に対して前向きでなかっったのかわからないが、フィルハーモニアとの正式な録音はこれまで残していない。ブラームスの交響曲はクリーブランドと全集の録音を残しているが、彼の録音の中でも結構ピンとこない部類に入るものだった。ブルックナーやマーラーの録音に比較しても、彼らしいオケのコントロールと明晰さに欠けるように聴こえるからだ(解釈は別の問題です)。しかし、この2曲の録音はライブであるにもかかわらず、そのドホナーニらしい明晰さとバランス感覚の良さを聴くことができる。オーケストラ自体も状態がよく、フィルハーモニアらしいサウンドをしている。このシリーズでもっとドホナーニの録音を出してほしいものだ。昨年、日本で聴いたNDR放送響との演奏に比べてもはるかにレベルが高い。ちなみに、第2番は全集に比べてテンポは遅め、第4番は速め。Aug.3 DVD : Metzmacher
 Metzmacher + Netherland Opera : Mozart / Cosi fan tutte , Le nozze di Figaro , Don Giovanni : ネーデルランド・オペラとメッツマッハーのダ・ポンテ三部作の映像。モーツァルト生誕250年の2006年のプロダクション。おまけDVDもついて4枚組とボリュームがあるセットだ。コジとフィガロでは、ダニエレ・デ・ニースが歌っているのも気になるところ。しかし、コジのほうの歌はいまいちで見た目もあまりかわいくない。演出は、ヴィーラーとモラビト。全作品、現代風の読み替えが行われており、ドン・ジョバンニは大量のベッドがあるベッドルームだし、フィガロは自動車会社のショールーム。たまに見る分にはいいけど、始めてみたのがこの演出だったらいやだな。何度も繰り返して聴いているオペラだからこういうのもありかと認められるだけで。演奏はドンジョバンニは気に入ったが、あとの2作はピリッとしない。室内楽オーケストラというのもあるが、フィガロなど、音がばらけて聴こえるのだ。録音のせいなのかもしれないが。演奏はフィガロでの通奏低音でシンセが使われているのはちょっと違和感がある。
Metzmacher + Netherland Opera : Mozart / Cosi fan tutte , Le nozze di Figaro , Don Giovanni : ネーデルランド・オペラとメッツマッハーのダ・ポンテ三部作の映像。モーツァルト生誕250年の2006年のプロダクション。おまけDVDもついて4枚組とボリュームがあるセットだ。コジとフィガロでは、ダニエレ・デ・ニースが歌っているのも気になるところ。しかし、コジのほうの歌はいまいちで見た目もあまりかわいくない。演出は、ヴィーラーとモラビト。全作品、現代風の読み替えが行われており、ドン・ジョバンニは大量のベッドがあるベッドルームだし、フィガロは自動車会社のショールーム。たまに見る分にはいいけど、始めてみたのがこの演出だったらいやだな。何度も繰り返して聴いているオペラだからこういうのもありかと認められるだけで。演奏はドンジョバンニは気に入ったが、あとの2作はピリッとしない。室内楽オーケストラというのもあるが、フィガロなど、音がばらけて聴こえるのだ。録音のせいなのかもしれないが。演奏はフィガロでの通奏低音でシンセが使われているのはちょっと違和感がある。
 Metzmacher + Netherland Opera : Mozart / Cosi fan tutte , Le nozze di Figaro , Don Giovanni : ネーデルランド・オペラとメッツマッハーのダ・ポンテ三部作の映像。モーツァルト生誕250年の2006年のプロダクション。おまけDVDもついて4枚組とボリュームがあるセットだ。コジとフィガロでは、ダニエレ・デ・ニースが歌っているのも気になるところ。しかし、コジのほうの歌はいまいちで見た目もあまりかわいくない。演出は、ヴィーラーとモラビト。全作品、現代風の読み替えが行われており、ドン・ジョバンニは大量のベッドがあるベッドルームだし、フィガロは自動車会社のショールーム。たまに見る分にはいいけど、始めてみたのがこの演出だったらいやだな。何度も繰り返して聴いているオペラだからこういうのもありかと認められるだけで。演奏はドンジョバンニは気に入ったが、あとの2作はピリッとしない。室内楽オーケストラというのもあるが、フィガロなど、音がばらけて聴こえるのだ。録音のせいなのかもしれないが。演奏はフィガロでの通奏低音でシンセが使われているのはちょっと違和感がある。
Metzmacher + Netherland Opera : Mozart / Cosi fan tutte , Le nozze di Figaro , Don Giovanni : ネーデルランド・オペラとメッツマッハーのダ・ポンテ三部作の映像。モーツァルト生誕250年の2006年のプロダクション。おまけDVDもついて4枚組とボリュームがあるセットだ。コジとフィガロでは、ダニエレ・デ・ニースが歌っているのも気になるところ。しかし、コジのほうの歌はいまいちで見た目もあまりかわいくない。演出は、ヴィーラーとモラビト。全作品、現代風の読み替えが行われており、ドン・ジョバンニは大量のベッドがあるベッドルームだし、フィガロは自動車会社のショールーム。たまに見る分にはいいけど、始めてみたのがこの演出だったらいやだな。何度も繰り返して聴いているオペラだからこういうのもありかと認められるだけで。演奏はドンジョバンニは気に入ったが、あとの2作はピリッとしない。室内楽オーケストラというのもあるが、フィガロなど、音がばらけて聴こえるのだ。録音のせいなのかもしれないが。演奏はフィガロでの通奏低音でシンセが使われているのはちょっと違和感がある。Aug.3 CD : Gatti
 Daniele Gatti + Royal Concertgebouw : Berg / Lulu SUite : コンセルトヘボウの自主製作録音。ハイティンクやヤンソンスが多いのだが、ダニエレ・ガッティが登場。ガッティは、ヨーロッパで結構活躍している指揮者で、ウィーンのオペラでもいい演目を振っているのだが、日本ではあまり話題にならない。録音も首席指揮者をしているロイヤル・フィルのものがいくつかと、サンタ・チェチーリアとのレスピーギがあるくらいか。あとはウィーン国立歌劇場再建50周年記念ガラ・コンサート のDVDでヴェルディを振っているくらい。やっと最近の録音が出たと思って喜んでみたものの、曲がベルクでイマイチ盛り上がらない。おまけにあまり語れない。ベルクの3つの小品とルル組曲。指揮ぶりは悪くないのだが、オーケストラの音色があまり良くない。金管とかこんなくすんだ音色だったっけ?録音のせいかも知れないのでよくわからないけど。
Daniele Gatti + Royal Concertgebouw : Berg / Lulu SUite : コンセルトヘボウの自主製作録音。ハイティンクやヤンソンスが多いのだが、ダニエレ・ガッティが登場。ガッティは、ヨーロッパで結構活躍している指揮者で、ウィーンのオペラでもいい演目を振っているのだが、日本ではあまり話題にならない。録音も首席指揮者をしているロイヤル・フィルのものがいくつかと、サンタ・チェチーリアとのレスピーギがあるくらいか。あとはウィーン国立歌劇場再建50周年記念ガラ・コンサート のDVDでヴェルディを振っているくらい。やっと最近の録音が出たと思って喜んでみたものの、曲がベルクでイマイチ盛り上がらない。おまけにあまり語れない。ベルクの3つの小品とルル組曲。指揮ぶりは悪くないのだが、オーケストラの音色があまり良くない。金管とかこんなくすんだ音色だったっけ?録音のせいかも知れないのでよくわからないけど。
 Daniele Gatti + Royal Concertgebouw : Berg / Lulu SUite : コンセルトヘボウの自主製作録音。ハイティンクやヤンソンスが多いのだが、ダニエレ・ガッティが登場。ガッティは、ヨーロッパで結構活躍している指揮者で、ウィーンのオペラでもいい演目を振っているのだが、日本ではあまり話題にならない。録音も首席指揮者をしているロイヤル・フィルのものがいくつかと、サンタ・チェチーリアとのレスピーギがあるくらいか。あとはウィーン国立歌劇場再建50周年記念ガラ・コンサート のDVDでヴェルディを振っているくらい。やっと最近の録音が出たと思って喜んでみたものの、曲がベルクでイマイチ盛り上がらない。おまけにあまり語れない。ベルクの3つの小品とルル組曲。指揮ぶりは悪くないのだが、オーケストラの音色があまり良くない。金管とかこんなくすんだ音色だったっけ?録音のせいかも知れないのでよくわからないけど。
Daniele Gatti + Royal Concertgebouw : Berg / Lulu SUite : コンセルトヘボウの自主製作録音。ハイティンクやヤンソンスが多いのだが、ダニエレ・ガッティが登場。ガッティは、ヨーロッパで結構活躍している指揮者で、ウィーンのオペラでもいい演目を振っているのだが、日本ではあまり話題にならない。録音も首席指揮者をしているロイヤル・フィルのものがいくつかと、サンタ・チェチーリアとのレスピーギがあるくらいか。あとはウィーン国立歌劇場再建50周年記念ガラ・コンサート のDVDでヴェルディを振っているくらい。やっと最近の録音が出たと思って喜んでみたものの、曲がベルクでイマイチ盛り上がらない。おまけにあまり語れない。ベルクの3つの小品とルル組曲。指揮ぶりは悪くないのだが、オーケストラの音色があまり良くない。金管とかこんなくすんだ音色だったっけ?録音のせいかも知れないのでよくわからないけど。July.31 DVD : Belohlavek
 Belohlavek + London Philharmonic Orchestra : Wagner / Tristan und Isolde : トリスタンは生で聴いたことがあるものの、DVDを持っていなかったのでとりあえず最近でたこのDVDを買ってみた。グラインドボーン音楽祭での初ワーグナー上演の映像。演目はトリスタン。レーンホフの演出は特に悪くない。簡素な、というよりは丸以外ほとんど何もない舞台装置と印象付けをするような照明のみ。レーンホフが時々出してくる変なキャラクターづけされた空間もない。前奏曲がなっている間のテロップの入れかたが妙にかっこいい。目当ては、シュテンメのイゾルデ。クール・ビューティーです。透明感のある声で歌いあげていてとてもいい。あと、レネ・パーペのマルケ王は、やはり存在感があって、力強い声。この2人の声に耳が行く。ロバート・ギャンビルのトリスタンはともかく、スコウフスのクルナヴェルはいまいちかな。この前、こうもりのアイゼンシュタインを彼で見たばっかりなので、頼りなく見えてしまう。ビエロフラーヴェクの指揮は悪くないしオーケストラのサウンドも良いが、大胆な盛り上がりに欠け、エロくもない。フィナーレくらいはもっとうねりがあって良い曲なのに。
Belohlavek + London Philharmonic Orchestra : Wagner / Tristan und Isolde : トリスタンは生で聴いたことがあるものの、DVDを持っていなかったのでとりあえず最近でたこのDVDを買ってみた。グラインドボーン音楽祭での初ワーグナー上演の映像。演目はトリスタン。レーンホフの演出は特に悪くない。簡素な、というよりは丸以外ほとんど何もない舞台装置と印象付けをするような照明のみ。レーンホフが時々出してくる変なキャラクターづけされた空間もない。前奏曲がなっている間のテロップの入れかたが妙にかっこいい。目当ては、シュテンメのイゾルデ。クール・ビューティーです。透明感のある声で歌いあげていてとてもいい。あと、レネ・パーペのマルケ王は、やはり存在感があって、力強い声。この2人の声に耳が行く。ロバート・ギャンビルのトリスタンはともかく、スコウフスのクルナヴェルはいまいちかな。この前、こうもりのアイゼンシュタインを彼で見たばっかりなので、頼りなく見えてしまう。ビエロフラーヴェクの指揮は悪くないしオーケストラのサウンドも良いが、大胆な盛り上がりに欠け、エロくもない。フィナーレくらいはもっとうねりがあって良い曲なのに。
 Belohlavek + London Philharmonic Orchestra : Wagner / Tristan und Isolde : トリスタンは生で聴いたことがあるものの、DVDを持っていなかったのでとりあえず最近でたこのDVDを買ってみた。グラインドボーン音楽祭での初ワーグナー上演の映像。演目はトリスタン。レーンホフの演出は特に悪くない。簡素な、というよりは丸以外ほとんど何もない舞台装置と印象付けをするような照明のみ。レーンホフが時々出してくる変なキャラクターづけされた空間もない。前奏曲がなっている間のテロップの入れかたが妙にかっこいい。目当ては、シュテンメのイゾルデ。クール・ビューティーです。透明感のある声で歌いあげていてとてもいい。あと、レネ・パーペのマルケ王は、やはり存在感があって、力強い声。この2人の声に耳が行く。ロバート・ギャンビルのトリスタンはともかく、スコウフスのクルナヴェルはいまいちかな。この前、こうもりのアイゼンシュタインを彼で見たばっかりなので、頼りなく見えてしまう。ビエロフラーヴェクの指揮は悪くないしオーケストラのサウンドも良いが、大胆な盛り上がりに欠け、エロくもない。フィナーレくらいはもっとうねりがあって良い曲なのに。
Belohlavek + London Philharmonic Orchestra : Wagner / Tristan und Isolde : トリスタンは生で聴いたことがあるものの、DVDを持っていなかったのでとりあえず最近でたこのDVDを買ってみた。グラインドボーン音楽祭での初ワーグナー上演の映像。演目はトリスタン。レーンホフの演出は特に悪くない。簡素な、というよりは丸以外ほとんど何もない舞台装置と印象付けをするような照明のみ。レーンホフが時々出してくる変なキャラクターづけされた空間もない。前奏曲がなっている間のテロップの入れかたが妙にかっこいい。目当ては、シュテンメのイゾルデ。クール・ビューティーです。透明感のある声で歌いあげていてとてもいい。あと、レネ・パーペのマルケ王は、やはり存在感があって、力強い声。この2人の声に耳が行く。ロバート・ギャンビルのトリスタンはともかく、スコウフスのクルナヴェルはいまいちかな。この前、こうもりのアイゼンシュタインを彼で見たばっかりなので、頼りなく見えてしまう。ビエロフラーヴェクの指揮は悪くないしオーケストラのサウンドも良いが、大胆な盛り上がりに欠け、エロくもない。フィナーレくらいはもっとうねりがあって良い曲なのに。July.31 CD : Jochum
 Eugen Jochum + Staatskapelle Dresden : Brahms / Symphony No.4 : ヨッフムとドレスデン・シュターツカペレのライブ。このコンビはブルックナーの全集が録音として残っているが、ライブではあまり演奏したことがないらしい(ブルックナーの全集は、カラヤンのマイスタージンガーと同じようにEMIの企画らしい)。ブラームスが2曲。ベロフがソロを弾いたピアノ協奏曲第2番と、交響曲の第4番。ピアノ協奏曲の方は、特色のあるホルンの音など、オーケストラを楽しむことはできるが、ベロフの指周りが良くなくピアノをたたきつけるような音が多いため、総合的にはダメ。交響曲の方はヨッフムの他のスタジオ録音に比べてもテンポが遅めで、ねっとりとした演奏。オケのサウンドはとても気持ちがいい。しかし、ヨッフムの演奏に多い推進力のようなものはあまりない。こういう演奏もするのかとちょっと意外だった。
Eugen Jochum + Staatskapelle Dresden : Brahms / Symphony No.4 : ヨッフムとドレスデン・シュターツカペレのライブ。このコンビはブルックナーの全集が録音として残っているが、ライブではあまり演奏したことがないらしい(ブルックナーの全集は、カラヤンのマイスタージンガーと同じようにEMIの企画らしい)。ブラームスが2曲。ベロフがソロを弾いたピアノ協奏曲第2番と、交響曲の第4番。ピアノ協奏曲の方は、特色のあるホルンの音など、オーケストラを楽しむことはできるが、ベロフの指周りが良くなくピアノをたたきつけるような音が多いため、総合的にはダメ。交響曲の方はヨッフムの他のスタジオ録音に比べてもテンポが遅めで、ねっとりとした演奏。オケのサウンドはとても気持ちがいい。しかし、ヨッフムの演奏に多い推進力のようなものはあまりない。こういう演奏もするのかとちょっと意外だった。
 Eugen Jochum + Staatskapelle Dresden : Brahms / Symphony No.4 : ヨッフムとドレスデン・シュターツカペレのライブ。このコンビはブルックナーの全集が録音として残っているが、ライブではあまり演奏したことがないらしい(ブルックナーの全集は、カラヤンのマイスタージンガーと同じようにEMIの企画らしい)。ブラームスが2曲。ベロフがソロを弾いたピアノ協奏曲第2番と、交響曲の第4番。ピアノ協奏曲の方は、特色のあるホルンの音など、オーケストラを楽しむことはできるが、ベロフの指周りが良くなくピアノをたたきつけるような音が多いため、総合的にはダメ。交響曲の方はヨッフムの他のスタジオ録音に比べてもテンポが遅めで、ねっとりとした演奏。オケのサウンドはとても気持ちがいい。しかし、ヨッフムの演奏に多い推進力のようなものはあまりない。こういう演奏もするのかとちょっと意外だった。
Eugen Jochum + Staatskapelle Dresden : Brahms / Symphony No.4 : ヨッフムとドレスデン・シュターツカペレのライブ。このコンビはブルックナーの全集が録音として残っているが、ライブではあまり演奏したことがないらしい(ブルックナーの全集は、カラヤンのマイスタージンガーと同じようにEMIの企画らしい)。ブラームスが2曲。ベロフがソロを弾いたピアノ協奏曲第2番と、交響曲の第4番。ピアノ協奏曲の方は、特色のあるホルンの音など、オーケストラを楽しむことはできるが、ベロフの指周りが良くなくピアノをたたきつけるような音が多いため、総合的にはダメ。交響曲の方はヨッフムの他のスタジオ録音に比べてもテンポが遅めで、ねっとりとした演奏。オケのサウンドはとても気持ちがいい。しかし、ヨッフムの演奏に多い推進力のようなものはあまりない。こういう演奏もするのかとちょっと意外だった。July.30 Holst Stein 逝去
ホルスト・シュタインが亡くなったそうです。一度見たら忘れられない風貌、というよりおでこの指揮者。バイロイト出演も多いオペラ指揮者なので、ドイツでも大きな記事で扱われていますね。ここ10年くらいは病気で引退状態だったそうで。日本でも多く振っており、N響でも聴けた指揮者という意味では日本でも貴重な人でした。僕も、93年にこれもまた今は亡きヘルマン・プライとのシューベルト歌曲と英雄の生涯、同じ月にイモジェン・クーパーとモーツァルトのピアノ協奏曲20番とベートーヴェン、96年にシュテファン・ヴラダーとベートーヴェンの協奏曲3番とベートーヴェンの7番を聴いています。ヴラダーとの3番は良かった思い出が。どれもドイツドイツしたプログラムですが、もともとドイツ音楽が得意なN響と合っていたようで、そこそこドイツらしい響きをさせていたように思います。
July.29 ルパン
この時期のテレビといえば金曜ロードショーでのルパンSPだ。今年のルパン「魔法のランプは悪夢の予感」をやっと見た。正直言って面白くない。プロットはなんか散漫だし、キャラクター設定をワンパターンに使いすぎだ。有名なセリフや、シチュエーションは1回効果的に使うだけで十分なのだ。水戸黄門が何度も印籠を見せたらうっとうしいだろ。CGは手を抜いているので、静止画を処理したものが多い。時間とか予算がなかったのかな。ヒロインは可愛かったけど。ルパンといえば、今週、BS2がルパン祭り。今週3日かけて第1シリーズを全作品放映している。オープニング、次回予告、エンディングテーマも全部放送。なんか、70年代のルパンは渋くてヲサレ。キャラクターが白土三平みたいだけど。昔はわからなかったけど、バックにかかってる音楽がカコイイ。
July.27 CD : John McLaughlin
 John McLaughlin / Floating Point : ジョン・マクラフリンの新譜。休暇で行ったつもりのインドで、そのまま収録してしまった作品らしい。なので、参加メンバーはほとんどがインド人。ただ、ベースだけは最近のマクラフリンのお気に入りであるアドリアン・フェローが、あとからオーヴァーダビング。前作の「Industrial Zen」は、かなりいい作品だったが、今回も同じくらい緊張感があり良い。全般的にはエレクトリック化したShakti。4曲目や6曲目はそのイメージが顕著な曲。マクラフリンはギターシンセをメインで弾いており、今までのマハヴィシュヌやShakti、The Heart of Spiritsなどの要素がうまくミックスされている。キーボードの音色がちょっと古くて80年代っぽいが、マクラフリンのシンセギターの音とはよく合っている。このキーボードはJim Beardぽいかな。残念なのは、ドラムに品がなくてうるさい。タブラだと音も小さいのでちょうどいいのだが、タブラでたたくようなフレーズをひたすらドラムでたたき、音に変化がないので、うるさい。"1 4 u"のようなカリプソ風の曲でも(テーマのメロディはCapercaillieでMichael McGoldrickっぽい)、バタバタ叩くのはいただけない。
John McLaughlin / Floating Point : ジョン・マクラフリンの新譜。休暇で行ったつもりのインドで、そのまま収録してしまった作品らしい。なので、参加メンバーはほとんどがインド人。ただ、ベースだけは最近のマクラフリンのお気に入りであるアドリアン・フェローが、あとからオーヴァーダビング。前作の「Industrial Zen」は、かなりいい作品だったが、今回も同じくらい緊張感があり良い。全般的にはエレクトリック化したShakti。4曲目や6曲目はそのイメージが顕著な曲。マクラフリンはギターシンセをメインで弾いており、今までのマハヴィシュヌやShakti、The Heart of Spiritsなどの要素がうまくミックスされている。キーボードの音色がちょっと古くて80年代っぽいが、マクラフリンのシンセギターの音とはよく合っている。このキーボードはJim Beardぽいかな。残念なのは、ドラムに品がなくてうるさい。タブラだと音も小さいのでちょうどいいのだが、タブラでたたくようなフレーズをひたすらドラムでたたき、音に変化がないので、うるさい。"1 4 u"のようなカリプソ風の曲でも(テーマのメロディはCapercaillieでMichael McGoldrickっぽい)、バタバタ叩くのはいただけない。
 John McLaughlin / Floating Point : ジョン・マクラフリンの新譜。休暇で行ったつもりのインドで、そのまま収録してしまった作品らしい。なので、参加メンバーはほとんどがインド人。ただ、ベースだけは最近のマクラフリンのお気に入りであるアドリアン・フェローが、あとからオーヴァーダビング。前作の「Industrial Zen」は、かなりいい作品だったが、今回も同じくらい緊張感があり良い。全般的にはエレクトリック化したShakti。4曲目や6曲目はそのイメージが顕著な曲。マクラフリンはギターシンセをメインで弾いており、今までのマハヴィシュヌやShakti、The Heart of Spiritsなどの要素がうまくミックスされている。キーボードの音色がちょっと古くて80年代っぽいが、マクラフリンのシンセギターの音とはよく合っている。このキーボードはJim Beardぽいかな。残念なのは、ドラムに品がなくてうるさい。タブラだと音も小さいのでちょうどいいのだが、タブラでたたくようなフレーズをひたすらドラムでたたき、音に変化がないので、うるさい。"1 4 u"のようなカリプソ風の曲でも(テーマのメロディはCapercaillieでMichael McGoldrickっぽい)、バタバタ叩くのはいただけない。
John McLaughlin / Floating Point : ジョン・マクラフリンの新譜。休暇で行ったつもりのインドで、そのまま収録してしまった作品らしい。なので、参加メンバーはほとんどがインド人。ただ、ベースだけは最近のマクラフリンのお気に入りであるアドリアン・フェローが、あとからオーヴァーダビング。前作の「Industrial Zen」は、かなりいい作品だったが、今回も同じくらい緊張感があり良い。全般的にはエレクトリック化したShakti。4曲目や6曲目はそのイメージが顕著な曲。マクラフリンはギターシンセをメインで弾いており、今までのマハヴィシュヌやShakti、The Heart of Spiritsなどの要素がうまくミックスされている。キーボードの音色がちょっと古くて80年代っぽいが、マクラフリンのシンセギターの音とはよく合っている。このキーボードはJim Beardぽいかな。残念なのは、ドラムに品がなくてうるさい。タブラだと音も小さいのでちょうどいいのだが、タブラでたたくようなフレーズをひたすらドラムでたたき、音に変化がないので、うるさい。"1 4 u"のようなカリプソ風の曲でも(テーマのメロディはCapercaillieでMichael McGoldrickっぽい)、バタバタ叩くのはいただけない。July.21 J.Strauss "Die Fledermaus" / Seiji Ozawa @ 神奈川県民ホール
小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトIX「こうもり」を神奈川県民ホールで見る。チケットは掲示板で定価で入手。研究職でも芸術家でも歳をとると、教育に目が行ってしまうようで、この小澤征爾音楽塾も、オペラを演奏することによって若手の音楽家を教育したいという夏のプログラム。オケは若手で、歌手とプロダクションはプロ。もちろん指揮は小澤。ホールに入り、3階に上がって席を探して、座るべき場所を見つけると、いつもの後輩の横の席。チケットをまとめて取ったわけでもないのに隣だなんて。ちなみに、違う人から購入していたよう。小澤はヘルニアかなんかで、ここ数か月、いろんな公演をお休みしているのだが、ピットには小走りで元気に出てきた。序曲は颯爽と、小澤らしいテンポで進むのだが、やはり違和感ありますね。ウィンナワルツではない、なにか。香りが違う。オーケストラは若々しく、元気がいいのだが、やはり時々バランスが崩れる。しかし、小澤のコントロールでサッと直るあたりもさすが。同じ曲に対する練習量が違うので比較にはならないが、某都内オケとか放送局オケとかのプロよりは上手かった。歌手は総じて満足だった。アデーレのアンナ・クリスティはちょっと声量不足かな。冒頭のコロラトゥーラでガツンと見せつけてほしかったのですが、ちょっと弱め。ロザリンデのアンドレア・ロストが本公演の注目するところ。アデーレとのパワーの差が見えてしまい、ちょっとかわいそうだった。ロストは、あまりこの役になじんでいるとは思えなかったが、それでもうまい(08-09シーズンのミュンヘンでこの役を歌うようですが)。アルフレートはゴードン・キーツという人で陽気なイタリア人系。役どころと同じく、始終歌っている雰囲気。第1幕の1回目、ロザリンデの寝室から逃げるところで、プッチーニの誰も寝てはならぬを、アドリブのように歌ったのですが、そのあとオーケストラがいきなりそれの2小節ばかり伴奏をつけました。開始20分で、オペレッタ乗りです。一番感心したのは、アイゼンシュタインのボー・スコウフス。単純にうまいし、いい声で、ドイツ語の発音もいい。第2幕の冒頭のアデーレとイーダが会話して、イーダが踊るシーンはすべてカット。第1幕でアデーレに手紙を出したのが彼女ではないことがわかるシーンだが、ファルケにはめられたことはすぐにわかるので、テンポ感を出すためのカットだろう。各登場人物を紹介するセリフはおおむねカット、「蒙古人いわく〜」「xx人いわく〜」のことわざっぽいセリフも全部カット。かわりに、ロザリンデの歌うチャルダーシュの後に、ハンガリー人万歳が挿入されていた。言語の違いのせいで面白くなくなる言葉遊びなどをカットし、客を面白くさせる点を重視して演出しているのはプラスポイント。ウィーン国立歌劇場でのオットー・シェンクの演出がやはり偉大なのだろうか。今回の演出はデビッド・ニースによる、サンフランシスコ・オペラの演出なのだが、いたるところにシェンクの影響が。第2幕のダンスシーンは当然のように「雷鳴と電光」で踊り狂った後、全員床に倒れます。第3幕でも、監守は日本人で、日本語がメインでセリフを言うのですが、フランクがタバコを吸ったり、アイゼンシュタインとフランクが招待をばらすところで飲み物をぶーと吹くところなどは、シェンク演出と同じ。ここでは歌手も日本語を交えたり、小澤に語りかけてみたりと、笑わそうという意図は見える。第2幕の舞踏会シーンで女性コーラスが来ているオリエンタルな衣装は、逆にサンフランシスコ・オペラっぽいのかな。惜しいのはフィナーレ。ロザリンデが歌い出すところで、ロストが早く歌いだしてしまった。すぐに取り戻してはいましたけれどもちょっと残念。
ネットで見つけた新聞の記事で、「小沢征爾さんが久々に指揮棒、「こうもり」舞台げいこで復帰」とあった。「小沢」ではなく「小澤」だとか細かいところが問題なのではなく、小澤は指揮棒は持たずに振るのですよ。この公演でも指揮棒は使っていなかった。記者も思い込みやクリシェで記事を書いてはいけない。ある意味、「久々に指揮棒」を持ったら、音楽的なニュースなのかもしれないけど。
July.19 DVD : Welser-Moest
 Welser-Moest + Cleveland Orchestra : Bruckner / Symphony No.9 : 2007年11月、ウィーンのムジークフェラインでの録画。ウェルザー・メストとクリーブランドのコンビは、ブルックナーは第5番もDVDで出ている。このまま全集にならないかな。第5番と同じく、丁寧な演奏。オーケストラも統制が取れており、同じパートの人たちが同じ方向を向いて、一つ一つのフレーズをきっちり弾いている様子が映像から伝わる。第5番と同じく、木管のフルートやロータリーのトランペットを使っていて、ドイツ的な響きを持たせようとしているようだ。第1楽章は、収録側が響きのバランスをきっちり取ることができていないのか、弦の間で音がずれているように感じるところがあり、違和感がある。第2楽章の、荒々しいテーマはスタッカットをあまりせず、ひきずるような感じで、最近DVDでみたヨッフムの演奏と近い。ドイツ語圏の習慣的な演奏なのだろうか、いろんな演奏を比較してみたくなった。第3楽章は想像していたよりはねっとりとしたロマンティックな処理が多い。全体的に、ホールの残響もきっちり収録されており、黄金のホールの映像とあわせて、非常に楽しめるDVDだった。
Welser-Moest + Cleveland Orchestra : Bruckner / Symphony No.9 : 2007年11月、ウィーンのムジークフェラインでの録画。ウェルザー・メストとクリーブランドのコンビは、ブルックナーは第5番もDVDで出ている。このまま全集にならないかな。第5番と同じく、丁寧な演奏。オーケストラも統制が取れており、同じパートの人たちが同じ方向を向いて、一つ一つのフレーズをきっちり弾いている様子が映像から伝わる。第5番と同じく、木管のフルートやロータリーのトランペットを使っていて、ドイツ的な響きを持たせようとしているようだ。第1楽章は、収録側が響きのバランスをきっちり取ることができていないのか、弦の間で音がずれているように感じるところがあり、違和感がある。第2楽章の、荒々しいテーマはスタッカットをあまりせず、ひきずるような感じで、最近DVDでみたヨッフムの演奏と近い。ドイツ語圏の習慣的な演奏なのだろうか、いろんな演奏を比較してみたくなった。第3楽章は想像していたよりはねっとりとしたロマンティックな処理が多い。全体的に、ホールの残響もきっちり収録されており、黄金のホールの映像とあわせて、非常に楽しめるDVDだった。
 Welser-Moest + Cleveland Orchestra : Bruckner / Symphony No.9 : 2007年11月、ウィーンのムジークフェラインでの録画。ウェルザー・メストとクリーブランドのコンビは、ブルックナーは第5番もDVDで出ている。このまま全集にならないかな。第5番と同じく、丁寧な演奏。オーケストラも統制が取れており、同じパートの人たちが同じ方向を向いて、一つ一つのフレーズをきっちり弾いている様子が映像から伝わる。第5番と同じく、木管のフルートやロータリーのトランペットを使っていて、ドイツ的な響きを持たせようとしているようだ。第1楽章は、収録側が響きのバランスをきっちり取ることができていないのか、弦の間で音がずれているように感じるところがあり、違和感がある。第2楽章の、荒々しいテーマはスタッカットをあまりせず、ひきずるような感じで、最近DVDでみたヨッフムの演奏と近い。ドイツ語圏の習慣的な演奏なのだろうか、いろんな演奏を比較してみたくなった。第3楽章は想像していたよりはねっとりとしたロマンティックな処理が多い。全体的に、ホールの残響もきっちり収録されており、黄金のホールの映像とあわせて、非常に楽しめるDVDだった。
Welser-Moest + Cleveland Orchestra : Bruckner / Symphony No.9 : 2007年11月、ウィーンのムジークフェラインでの録画。ウェルザー・メストとクリーブランドのコンビは、ブルックナーは第5番もDVDで出ている。このまま全集にならないかな。第5番と同じく、丁寧な演奏。オーケストラも統制が取れており、同じパートの人たちが同じ方向を向いて、一つ一つのフレーズをきっちり弾いている様子が映像から伝わる。第5番と同じく、木管のフルートやロータリーのトランペットを使っていて、ドイツ的な響きを持たせようとしているようだ。第1楽章は、収録側が響きのバランスをきっちり取ることができていないのか、弦の間で音がずれているように感じるところがあり、違和感がある。第2楽章の、荒々しいテーマはスタッカットをあまりせず、ひきずるような感じで、最近DVDでみたヨッフムの演奏と近い。ドイツ語圏の習慣的な演奏なのだろうか、いろんな演奏を比較してみたくなった。第3楽章は想像していたよりはねっとりとしたロマンティックな処理が多い。全体的に、ホールの残響もきっちり収録されており、黄金のホールの映像とあわせて、非常に楽しめるDVDだった。June.19 Pasmo
PASMOが普及して、東京都の電車やバスのほとんどはPASMOやSUICAの非接触型カードで乗ることができるようになった。3つ以上の会社の路線を乗り継いでいるとかいう人を除けば、定期もPASMOやSUICAにしている人がほとんどだろう。駅の改札口でも、ほとんどの人がカードを取りだすことなく、財布のまま読み取る場所に財布をあてて電車に乗っている。リーダーの場所に「ピッ」、リーダーの場所に「ピッ」、リーダーの場所に「ピッ」。前の人につられてキップをリーダーにあてて、「キンコン」改札口が閉まってしまった人を見てしまった。
July.14 CD : Aimard
 Phillip-Laurent Aimard : Hommage e Messiaen : グラモフォンに移籍したエマールによる「メシアンへのオマージュ」。8つの前奏曲と、「鳥のカタログ」から2曲、リズムエチュードから2曲。メシアンの演奏を事細かに語るほどの知識と観賞力は持ち合わせていないのだが、鳥のカタログは、ウゴルスキのものに比べてテンポも速めで硬質な印象を受けた。メシアンのピアノ曲、しかも練習曲が普通に聴こえる。これを聴いた後に、「20のまなざし」の録音を聴きなおしたが、これほどの曲が普通に美しい曲であるかのように聴かせる技術は大したものだと思う。輸入盤で買ったのだが、SACDでもないのに、SACDのケースに入っていた。
Phillip-Laurent Aimard : Hommage e Messiaen : グラモフォンに移籍したエマールによる「メシアンへのオマージュ」。8つの前奏曲と、「鳥のカタログ」から2曲、リズムエチュードから2曲。メシアンの演奏を事細かに語るほどの知識と観賞力は持ち合わせていないのだが、鳥のカタログは、ウゴルスキのものに比べてテンポも速めで硬質な印象を受けた。メシアンのピアノ曲、しかも練習曲が普通に聴こえる。これを聴いた後に、「20のまなざし」の録音を聴きなおしたが、これほどの曲が普通に美しい曲であるかのように聴かせる技術は大したものだと思う。輸入盤で買ったのだが、SACDでもないのに、SACDのケースに入っていた。
 Phillip-Laurent Aimard : Hommage e Messiaen : グラモフォンに移籍したエマールによる「メシアンへのオマージュ」。8つの前奏曲と、「鳥のカタログ」から2曲、リズムエチュードから2曲。メシアンの演奏を事細かに語るほどの知識と観賞力は持ち合わせていないのだが、鳥のカタログは、ウゴルスキのものに比べてテンポも速めで硬質な印象を受けた。メシアンのピアノ曲、しかも練習曲が普通に聴こえる。これを聴いた後に、「20のまなざし」の録音を聴きなおしたが、これほどの曲が普通に美しい曲であるかのように聴かせる技術は大したものだと思う。輸入盤で買ったのだが、SACDでもないのに、SACDのケースに入っていた。
Phillip-Laurent Aimard : Hommage e Messiaen : グラモフォンに移籍したエマールによる「メシアンへのオマージュ」。8つの前奏曲と、「鳥のカタログ」から2曲、リズムエチュードから2曲。メシアンの演奏を事細かに語るほどの知識と観賞力は持ち合わせていないのだが、鳥のカタログは、ウゴルスキのものに比べてテンポも速めで硬質な印象を受けた。メシアンのピアノ曲、しかも練習曲が普通に聴こえる。これを聴いた後に、「20のまなざし」の録音を聴きなおしたが、これほどの曲が普通に美しい曲であるかのように聴かせる技術は大したものだと思う。輸入盤で買ったのだが、SACDでもないのに、SACDのケースに入っていた。July.14 CD : Ian Bostridge
 Ian Bostridge : Great Handel : ボストリッジが歌うヘンデルのアリア集。本当に最近ヘンデルが流行っているみたいですね。ボストリッジって、シューベルトを歌う時でも、ブリテンを歌う時でも、生真面目というか学究的というか、フィッシャー=ディースカウとかぶるキャラクターがあると思っていたのですが、このアルバムは非常にやわらかい。天から降り注ぐ音につつまれるような声だ。イギリス人だからヘンデルがとても好きなんだろうなというのと、英語の発音の問題なのだろうか。ただ、「アリオダンテ」のアリアは女声じゃないと違和感があるな。
Ian Bostridge : Great Handel : ボストリッジが歌うヘンデルのアリア集。本当に最近ヘンデルが流行っているみたいですね。ボストリッジって、シューベルトを歌う時でも、ブリテンを歌う時でも、生真面目というか学究的というか、フィッシャー=ディースカウとかぶるキャラクターがあると思っていたのですが、このアルバムは非常にやわらかい。天から降り注ぐ音につつまれるような声だ。イギリス人だからヘンデルがとても好きなんだろうなというのと、英語の発音の問題なのだろうか。ただ、「アリオダンテ」のアリアは女声じゃないと違和感があるな。
 Ian Bostridge : Great Handel : ボストリッジが歌うヘンデルのアリア集。本当に最近ヘンデルが流行っているみたいですね。ボストリッジって、シューベルトを歌う時でも、ブリテンを歌う時でも、生真面目というか学究的というか、フィッシャー=ディースカウとかぶるキャラクターがあると思っていたのですが、このアルバムは非常にやわらかい。天から降り注ぐ音につつまれるような声だ。イギリス人だからヘンデルがとても好きなんだろうなというのと、英語の発音の問題なのだろうか。ただ、「アリオダンテ」のアリアは女声じゃないと違和感があるな。
Ian Bostridge : Great Handel : ボストリッジが歌うヘンデルのアリア集。本当に最近ヘンデルが流行っているみたいですね。ボストリッジって、シューベルトを歌う時でも、ブリテンを歌う時でも、生真面目というか学究的というか、フィッシャー=ディースカウとかぶるキャラクターがあると思っていたのですが、このアルバムは非常にやわらかい。天から降り注ぐ音につつまれるような声だ。イギリス人だからヘンデルがとても好きなんだろうなというのと、英語の発音の問題なのだろうか。ただ、「アリオダンテ」のアリアは女声じゃないと違和感があるな。July.13 CD : Hamelin
 Marc-Andre Hamelin : Godowsky / Strauss Transcriptions and other Waltzes : アムランの新譜。ゴドフスキのシュトラウス・トランスクリプション集。3つの交響的変容を中心にして、仮面舞踏会(Walzermasken)とトリアコンタメロン(Traikontameron)からの抜粋、オスカー・シュトラウスの"The Last Waltz"が収められている。"The Last Waltz"はゴドフスキのピアノロールからアムラン・パパが採譜したものを弾いている。3つの交響的変容はどれも素晴らしい演奏で、どれもワルツのオシャレな雰囲気が漂う。普通の演奏だと、弾きこなすので精いっぱいで、流れも雰囲気もないものが多い。「芸術家の生涯」はショミン (Edvard Shomin)の演奏も素晴らしく、派手な演奏だが、ちょっとごつごつしい。アムランの演奏はソフトなように聴かせているところが、あいかわらず凄いところ。「こうもり」も「酒・女・歌」もあまり難しい曲と感じさせないところがアムランですな。彼の最近の録音は、リファレンスとなるような演奏を心がけているように見える。ので、ライブで聴けるような盛り上がりや疾走感は控えめになってしまう。そのためDukasのソナタ、やAlkanの協奏曲では物足りなさを感じてしまう(例外はAlkanの協奏曲)が、ゴドフスキのように盛り上がりやスピード感よりも構成や対位法処理に重きを置く作品の場合はこのように、他に勝てるものが居なくなってしまうような演奏になるのだと思う。すばらしい録音だ。
Marc-Andre Hamelin : Godowsky / Strauss Transcriptions and other Waltzes : アムランの新譜。ゴドフスキのシュトラウス・トランスクリプション集。3つの交響的変容を中心にして、仮面舞踏会(Walzermasken)とトリアコンタメロン(Traikontameron)からの抜粋、オスカー・シュトラウスの"The Last Waltz"が収められている。"The Last Waltz"はゴドフスキのピアノロールからアムラン・パパが採譜したものを弾いている。3つの交響的変容はどれも素晴らしい演奏で、どれもワルツのオシャレな雰囲気が漂う。普通の演奏だと、弾きこなすので精いっぱいで、流れも雰囲気もないものが多い。「芸術家の生涯」はショミン (Edvard Shomin)の演奏も素晴らしく、派手な演奏だが、ちょっとごつごつしい。アムランの演奏はソフトなように聴かせているところが、あいかわらず凄いところ。「こうもり」も「酒・女・歌」もあまり難しい曲と感じさせないところがアムランですな。彼の最近の録音は、リファレンスとなるような演奏を心がけているように見える。ので、ライブで聴けるような盛り上がりや疾走感は控えめになってしまう。そのためDukasのソナタ、やAlkanの協奏曲では物足りなさを感じてしまう(例外はAlkanの協奏曲)が、ゴドフスキのように盛り上がりやスピード感よりも構成や対位法処理に重きを置く作品の場合はこのように、他に勝てるものが居なくなってしまうような演奏になるのだと思う。すばらしい録音だ。
 Marc-Andre Hamelin : Godowsky / Strauss Transcriptions and other Waltzes : アムランの新譜。ゴドフスキのシュトラウス・トランスクリプション集。3つの交響的変容を中心にして、仮面舞踏会(Walzermasken)とトリアコンタメロン(Traikontameron)からの抜粋、オスカー・シュトラウスの"The Last Waltz"が収められている。"The Last Waltz"はゴドフスキのピアノロールからアムラン・パパが採譜したものを弾いている。3つの交響的変容はどれも素晴らしい演奏で、どれもワルツのオシャレな雰囲気が漂う。普通の演奏だと、弾きこなすので精いっぱいで、流れも雰囲気もないものが多い。「芸術家の生涯」はショミン (Edvard Shomin)の演奏も素晴らしく、派手な演奏だが、ちょっとごつごつしい。アムランの演奏はソフトなように聴かせているところが、あいかわらず凄いところ。「こうもり」も「酒・女・歌」もあまり難しい曲と感じさせないところがアムランですな。彼の最近の録音は、リファレンスとなるような演奏を心がけているように見える。ので、ライブで聴けるような盛り上がりや疾走感は控えめになってしまう。そのためDukasのソナタ、やAlkanの協奏曲では物足りなさを感じてしまう(例外はAlkanの協奏曲)が、ゴドフスキのように盛り上がりやスピード感よりも構成や対位法処理に重きを置く作品の場合はこのように、他に勝てるものが居なくなってしまうような演奏になるのだと思う。すばらしい録音だ。
Marc-Andre Hamelin : Godowsky / Strauss Transcriptions and other Waltzes : アムランの新譜。ゴドフスキのシュトラウス・トランスクリプション集。3つの交響的変容を中心にして、仮面舞踏会(Walzermasken)とトリアコンタメロン(Traikontameron)からの抜粋、オスカー・シュトラウスの"The Last Waltz"が収められている。"The Last Waltz"はゴドフスキのピアノロールからアムラン・パパが採譜したものを弾いている。3つの交響的変容はどれも素晴らしい演奏で、どれもワルツのオシャレな雰囲気が漂う。普通の演奏だと、弾きこなすので精いっぱいで、流れも雰囲気もないものが多い。「芸術家の生涯」はショミン (Edvard Shomin)の演奏も素晴らしく、派手な演奏だが、ちょっとごつごつしい。アムランの演奏はソフトなように聴かせているところが、あいかわらず凄いところ。「こうもり」も「酒・女・歌」もあまり難しい曲と感じさせないところがアムランですな。彼の最近の録音は、リファレンスとなるような演奏を心がけているように見える。ので、ライブで聴けるような盛り上がりや疾走感は控えめになってしまう。そのためDukasのソナタ、やAlkanの協奏曲では物足りなさを感じてしまう(例外はAlkanの協奏曲)が、ゴドフスキのように盛り上がりやスピード感よりも構成や対位法処理に重きを置く作品の場合はこのように、他に勝てるものが居なくなってしまうような演奏になるのだと思う。すばらしい録音だ。July.13 CD : Salle Gaveau
 Salle Gaveau / Strange Device : 鬼怒無月によるタンゴ・プロジェクトSalle Gaveauのセカンドアルバム。曲もアンサンブルもソロも緊張感もどれもよい。あまりにも良いので何度も聴いたが、どこがタンゴなのかすでにわからない。前作はレスポールっぽい音色で、アンサンブル重視のギターが多かったが、このアルバムではフェンダーでオーヴァードライブを利かせたギターソロが多い。鬼怒無月の作曲が減った分、ギターソロが増えたような感じ。"Weightless Zoo"のギターはFred FrithだとかCrimsonのBelewとか言われてもそうかと思ってしまうほどプログレ。ギターとピアノが張り合うところが多く、"800%"のギター→ピアノと流れるところなど非常にかっこいい。ラテン乗りの熱さじゃなくて、ロックとかジャズの熱さを感じるからタンゴっぽくないのかもしれない。またライブに行きたい。
Salle Gaveau / Strange Device : 鬼怒無月によるタンゴ・プロジェクトSalle Gaveauのセカンドアルバム。曲もアンサンブルもソロも緊張感もどれもよい。あまりにも良いので何度も聴いたが、どこがタンゴなのかすでにわからない。前作はレスポールっぽい音色で、アンサンブル重視のギターが多かったが、このアルバムではフェンダーでオーヴァードライブを利かせたギターソロが多い。鬼怒無月の作曲が減った分、ギターソロが増えたような感じ。"Weightless Zoo"のギターはFred FrithだとかCrimsonのBelewとか言われてもそうかと思ってしまうほどプログレ。ギターとピアノが張り合うところが多く、"800%"のギター→ピアノと流れるところなど非常にかっこいい。ラテン乗りの熱さじゃなくて、ロックとかジャズの熱さを感じるからタンゴっぽくないのかもしれない。またライブに行きたい。
 Salle Gaveau / Strange Device : 鬼怒無月によるタンゴ・プロジェクトSalle Gaveauのセカンドアルバム。曲もアンサンブルもソロも緊張感もどれもよい。あまりにも良いので何度も聴いたが、どこがタンゴなのかすでにわからない。前作はレスポールっぽい音色で、アンサンブル重視のギターが多かったが、このアルバムではフェンダーでオーヴァードライブを利かせたギターソロが多い。鬼怒無月の作曲が減った分、ギターソロが増えたような感じ。"Weightless Zoo"のギターはFred FrithだとかCrimsonのBelewとか言われてもそうかと思ってしまうほどプログレ。ギターとピアノが張り合うところが多く、"800%"のギター→ピアノと流れるところなど非常にかっこいい。ラテン乗りの熱さじゃなくて、ロックとかジャズの熱さを感じるからタンゴっぽくないのかもしれない。またライブに行きたい。
Salle Gaveau / Strange Device : 鬼怒無月によるタンゴ・プロジェクトSalle Gaveauのセカンドアルバム。曲もアンサンブルもソロも緊張感もどれもよい。あまりにも良いので何度も聴いたが、どこがタンゴなのかすでにわからない。前作はレスポールっぽい音色で、アンサンブル重視のギターが多かったが、このアルバムではフェンダーでオーヴァードライブを利かせたギターソロが多い。鬼怒無月の作曲が減った分、ギターソロが増えたような感じ。"Weightless Zoo"のギターはFred FrithだとかCrimsonのBelewとか言われてもそうかと思ってしまうほどプログレ。ギターとピアノが張り合うところが多く、"800%"のギター→ピアノと流れるところなど非常にかっこいい。ラテン乗りの熱さじゃなくて、ロックとかジャズの熱さを感じるからタンゴっぽくないのかもしれない。またライブに行きたい。July.6 CD : Xavier de Maistre
 Xavier de Maistre : Nuit d'Etoiles : グザヴィエ・ドゥ・メストレというハーピストの作品。彼はバイエルン放送響やウィーン・フィルのハーピストとして有名らしい(オフィシャル・サイト)。ドビュッシーの作品集。買った理由は歌曲集で、ディアナ・ダムラウが歌っているから。当然編曲物がほとんどなのだが、オリジナルのピアノ曲と同じく気持ちよく聴けるし、曲調とあっている。オーストリアのメンバーで固めているようで、神聖な舞曲と世俗的な舞曲に、ライナー・ホーネックを筆頭とするウィーン・フィルの弦メンバーが参加している。目当てのダムラウの歌曲は、とてもうまくていい声なのは相変わらずなのだが、ちょっと血の気が多すぎて音が分厚い。ドビュッシーなのでもう少しクールに歌ってもらえればいいんだけど。
Xavier de Maistre : Nuit d'Etoiles : グザヴィエ・ドゥ・メストレというハーピストの作品。彼はバイエルン放送響やウィーン・フィルのハーピストとして有名らしい(オフィシャル・サイト)。ドビュッシーの作品集。買った理由は歌曲集で、ディアナ・ダムラウが歌っているから。当然編曲物がほとんどなのだが、オリジナルのピアノ曲と同じく気持ちよく聴けるし、曲調とあっている。オーストリアのメンバーで固めているようで、神聖な舞曲と世俗的な舞曲に、ライナー・ホーネックを筆頭とするウィーン・フィルの弦メンバーが参加している。目当てのダムラウの歌曲は、とてもうまくていい声なのは相変わらずなのだが、ちょっと血の気が多すぎて音が分厚い。ドビュッシーなのでもう少しクールに歌ってもらえればいいんだけど。
 Xavier de Maistre : Nuit d'Etoiles : グザヴィエ・ドゥ・メストレというハーピストの作品。彼はバイエルン放送響やウィーン・フィルのハーピストとして有名らしい(オフィシャル・サイト)。ドビュッシーの作品集。買った理由は歌曲集で、ディアナ・ダムラウが歌っているから。当然編曲物がほとんどなのだが、オリジナルのピアノ曲と同じく気持ちよく聴けるし、曲調とあっている。オーストリアのメンバーで固めているようで、神聖な舞曲と世俗的な舞曲に、ライナー・ホーネックを筆頭とするウィーン・フィルの弦メンバーが参加している。目当てのダムラウの歌曲は、とてもうまくていい声なのは相変わらずなのだが、ちょっと血の気が多すぎて音が分厚い。ドビュッシーなのでもう少しクールに歌ってもらえればいいんだけど。
Xavier de Maistre : Nuit d'Etoiles : グザヴィエ・ドゥ・メストレというハーピストの作品。彼はバイエルン放送響やウィーン・フィルのハーピストとして有名らしい(オフィシャル・サイト)。ドビュッシーの作品集。買った理由は歌曲集で、ディアナ・ダムラウが歌っているから。当然編曲物がほとんどなのだが、オリジナルのピアノ曲と同じく気持ちよく聴けるし、曲調とあっている。オーストリアのメンバーで固めているようで、神聖な舞曲と世俗的な舞曲に、ライナー・ホーネックを筆頭とするウィーン・フィルの弦メンバーが参加している。目当てのダムラウの歌曲は、とてもうまくていい声なのは相変わらずなのだが、ちょっと血の気が多すぎて音が分厚い。ドビュッシーなのでもう少しクールに歌ってもらえればいいんだけど。July.6 「パリの100年展」@ 都美術館
2月にパリとベルリンに行って以来、絵を見ていない気がしていた。そういえば、都内の美術館で何をやっているのかなと調べたところ、この「パリの100年展」は見ておきたいなと思った。しかし、なんだか上野まで行く気がしなくて(というのとパリに行ったばっかりなので)今日まで引き延ばしてしまった。今日が展示の最終日。人もあんまり多くない。19世紀のパリの街並みとパリで活躍した画家の作品が中心の展覧会。あまりグッとくる作品がなかったのだが、ユトリロの何枚かと、セザンヌ「聖アントワーヌの誘惑」が良かった。ユトリロに「ベルリーズの家」という作品があったのだが、あまりに普通の家の描写でイマイチでした。
July.5 CD : Koroliov
 Koroliov : Handel / Suites : バッハが非常に良かったコロリオフの新譜はヘンデルの組曲。3番、4番、7番、8番。ヘンデルの組曲はロシアのピアニストはよく弾いていますね。ギレリス、リヒテル、ガヴリーロフ。基本的に遅めのテンポで、妙な歌い回しが少ない。リヒテルとガヴリーロフによる全集は、ライブということもあり、より性急で乱暴なところを感じるところがある。特にガヴリーロフが。彼らとコロリオフは、間の取り方など同じクセを持っているように聴こえるが、落ち着いていて音がきれいだ。第7番のパッサカリアはグルダの清潔感と威厳のある演奏がとても好きなのだが、それを越えるほど好きにはなれなかった。しかし、ペライアも一部しか録音しなかったし、ぜひ全曲録音してほしい。
Koroliov : Handel / Suites : バッハが非常に良かったコロリオフの新譜はヘンデルの組曲。3番、4番、7番、8番。ヘンデルの組曲はロシアのピアニストはよく弾いていますね。ギレリス、リヒテル、ガヴリーロフ。基本的に遅めのテンポで、妙な歌い回しが少ない。リヒテルとガヴリーロフによる全集は、ライブということもあり、より性急で乱暴なところを感じるところがある。特にガヴリーロフが。彼らとコロリオフは、間の取り方など同じクセを持っているように聴こえるが、落ち着いていて音がきれいだ。第7番のパッサカリアはグルダの清潔感と威厳のある演奏がとても好きなのだが、それを越えるほど好きにはなれなかった。しかし、ペライアも一部しか録音しなかったし、ぜひ全曲録音してほしい。
 Koroliov : Handel / Suites : バッハが非常に良かったコロリオフの新譜はヘンデルの組曲。3番、4番、7番、8番。ヘンデルの組曲はロシアのピアニストはよく弾いていますね。ギレリス、リヒテル、ガヴリーロフ。基本的に遅めのテンポで、妙な歌い回しが少ない。リヒテルとガヴリーロフによる全集は、ライブということもあり、より性急で乱暴なところを感じるところがある。特にガヴリーロフが。彼らとコロリオフは、間の取り方など同じクセを持っているように聴こえるが、落ち着いていて音がきれいだ。第7番のパッサカリアはグルダの清潔感と威厳のある演奏がとても好きなのだが、それを越えるほど好きにはなれなかった。しかし、ペライアも一部しか録音しなかったし、ぜひ全曲録音してほしい。
Koroliov : Handel / Suites : バッハが非常に良かったコロリオフの新譜はヘンデルの組曲。3番、4番、7番、8番。ヘンデルの組曲はロシアのピアニストはよく弾いていますね。ギレリス、リヒテル、ガヴリーロフ。基本的に遅めのテンポで、妙な歌い回しが少ない。リヒテルとガヴリーロフによる全集は、ライブということもあり、より性急で乱暴なところを感じるところがある。特にガヴリーロフが。彼らとコロリオフは、間の取り方など同じクセを持っているように聴こえるが、落ち着いていて音がきれいだ。第7番のパッサカリアはグルダの清潔感と威厳のある演奏がとても好きなのだが、それを越えるほど好きにはなれなかった。しかし、ペライアも一部しか録音しなかったし、ぜひ全曲録音してほしい。July.5 CD : Emily Smith
 Emily Smith / Too Long Away : タワレコで、ブリティッシュ・トラッドのコーナーを見ていた時にジャケット買い。調べてみると、エミリー・スミスはスコットランドのシンガーらしい。これが3枚目のようだ。内容は、自作とトラッドが半々くらい。声質はアン・ブリッグスに近く、声が伸びるところとポップさはマディ・プライアの感じ。アレンジは、がちがちのトラッドでもなく、ケイト・ラスビーやカーラ・ディロンの作品に近い。トラッドの歌う時の節回しが、ほどよくポップで良い。何回も聴いてしまった。2作目はジョン・マカスカーの一味が参加しているようなので聴いてみたいところだ。
Emily Smith / Too Long Away : タワレコで、ブリティッシュ・トラッドのコーナーを見ていた時にジャケット買い。調べてみると、エミリー・スミスはスコットランドのシンガーらしい。これが3枚目のようだ。内容は、自作とトラッドが半々くらい。声質はアン・ブリッグスに近く、声が伸びるところとポップさはマディ・プライアの感じ。アレンジは、がちがちのトラッドでもなく、ケイト・ラスビーやカーラ・ディロンの作品に近い。トラッドの歌う時の節回しが、ほどよくポップで良い。何回も聴いてしまった。2作目はジョン・マカスカーの一味が参加しているようなので聴いてみたいところだ。
 Emily Smith / Too Long Away : タワレコで、ブリティッシュ・トラッドのコーナーを見ていた時にジャケット買い。調べてみると、エミリー・スミスはスコットランドのシンガーらしい。これが3枚目のようだ。内容は、自作とトラッドが半々くらい。声質はアン・ブリッグスに近く、声が伸びるところとポップさはマディ・プライアの感じ。アレンジは、がちがちのトラッドでもなく、ケイト・ラスビーやカーラ・ディロンの作品に近い。トラッドの歌う時の節回しが、ほどよくポップで良い。何回も聴いてしまった。2作目はジョン・マカスカーの一味が参加しているようなので聴いてみたいところだ。
Emily Smith / Too Long Away : タワレコで、ブリティッシュ・トラッドのコーナーを見ていた時にジャケット買い。調べてみると、エミリー・スミスはスコットランドのシンガーらしい。これが3枚目のようだ。内容は、自作とトラッドが半々くらい。声質はアン・ブリッグスに近く、声が伸びるところとポップさはマディ・プライアの感じ。アレンジは、がちがちのトラッドでもなく、ケイト・ラスビーやカーラ・ディロンの作品に近い。トラッドの歌う時の節回しが、ほどよくポップで良い。何回も聴いてしまった。2作目はジョン・マカスカーの一味が参加しているようなので聴いてみたいところだ。
| 戦績記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classical Music CD |
Not Classical CD |
CD (Sum) |
DVD | Clssical Music Concert |
Live | |
| 2007 | 572 | 169 | 741 | 117 | 13 | 16 |
| 2008.Jan | 30 | 4 | 34 | 5 | 0 | 2 |
| 2008.Feb | 42 | 4 | 46 | 4 | 8 | 1 |
| 2008.Mar | 61 | 12 | 73 | 8 | 0 | 1 |
| 2008.Apr | 32 | 3 | 35 | 13 | 2 | 1 |
| 2008.May | 42 | 16 | 58 | 9 | 0 | 2 |
| 2008.Jun | 11 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 |
| 2008.Jul | 24 | 13 | 37 | 6 | 1 | 0 |
| 2008.Aug | 32 | 12 | 44 | 13 | 0 | 1 |
| 2008.Spt | 85 | 19 | 104 | 5 | 1 | 1 |
| 2008.Oct | 55 | 9 | 64 | 16 | 2 | 2 |
| 2008.Nov | 48 | 19 | 67 | 18 | 4 | 2 |
| 2008.Dec | 39 | 28 | 67 | 18 | 2 | 1 |
| 2008 | 501 | 142 | 643 | 119 | 22 | 15 |