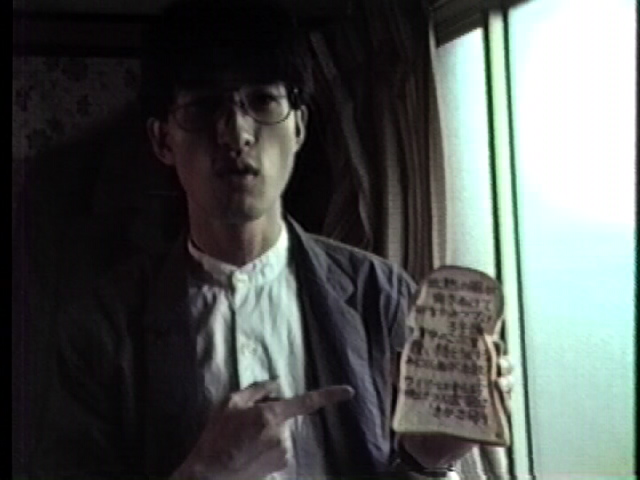

モーロー牛温泉
3分/8ʔ/2000
Moh-Roh-Ushi Hot Springs
[解説]
ナンセンス映画。俺の家の冷蔵庫にはバターがふたつあって上のバターと下のバターとして使い分けている、というところから始まり、なぜか思い出した「モーローウシ温泉」の探索となる。解説してもしょうがない。ただコメディは「間」が重要だが、ナンセンスは「飛躍の度合い」が重要だということだけ指摘しておきたい。
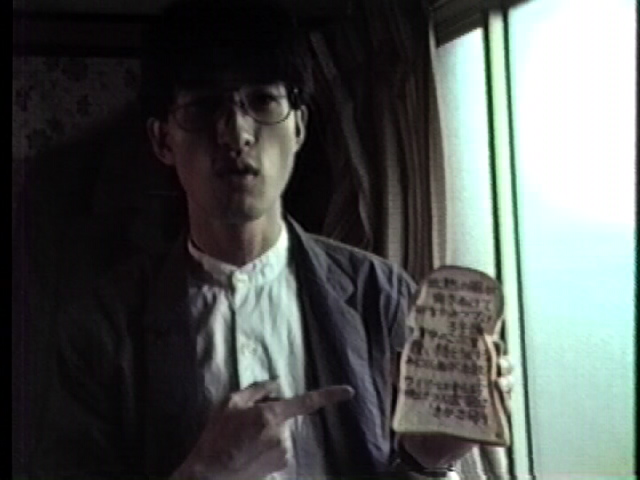
食パンへぼ詩人
29分/VTR/2000
A Poor Bread Poet
[解説]
大学時代、互いに影響しあった杉浦茂こと雑奇セルについてのドキュメンタリー。彼がやっていた食パンに詩をチョコレートで書くというパフォーマンスの記録ビデオを最初にたっぷりと引用し、そこから彼が後に入信してしまったオウム真理教での参議院選挙の政見放送映像、逮捕のニュース映像を引用して、最後に彼の詩を朗読する。
毛髪悲喜劇3分/8mm/2001
A Tragicomedy of my hair
[解説]
近頃、なぜか髪が薄くなってきたような。家系からして白髪になるタイプのはずなので変だ。プルトニウムを製造した覚えもないし。しかし朝起きると枕にはびっしりと抜けた毛髪がついている。もしかして自分でむしっているのか。だとしたら気味が悪いぞ。というわけで自分の寝ている姿をビデオ撮影することに。名付けてアンディ・ウォーホール作戦。そこで明らかになった意外な犯人の姿。(ホームコメディです)

こぼれる黄金の月
9分/8mm/2002
Spilling Golden Moon
[解説]
映像は走行する車の中からバルブ撮影したものと、銀河のようにまわる光点の群れのなかに、少年少女の戯れる映像がぼんやりと映っているものの2種類だけ。そこに短かめのモノローグと、安っぽいキーボードで作られた音楽、さらには古い日本映画の一シーンのサウンドトラックが添えられた作品。ことばにできるようなコンセプトではないので、解説が困難でスマン。
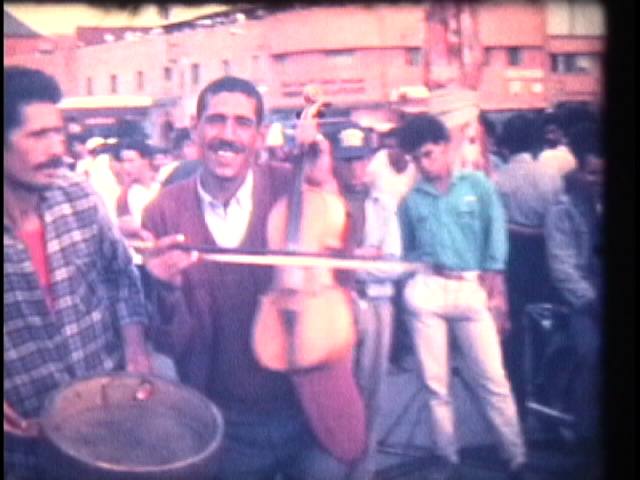
セル、眠っちゃだめだ
8分/8mm/2002
Sel, don't sleep
[解説]
食パンへぼ詩人、セル(杉浦茂)が1987年に北アフリカを旅した時の8ミリ映像に、旅先から送って来た私信というよりは作品に近い手紙を山崎が朗読する。解釈はいっさいはさまずに、この旅でセルがどんなことを感じ、どんなものが到来したのかを考察するきっかけになればそれでOKと考えて作った。
あいたい<2002年版>
11分/8mm/2002
AITAI<2002version>
[解説]
1988年に製作された『あいたい』という短編作品は、そのコンセプト上、1998年を過ぎるとわけがわからないことになってしまう。この作品の大半を撮影した神岡猟が病死したこともあって、映像には手をつけずに、モノローグだけを全面的に入れ替えることした。

遠くへ
16分/8mm/2003
Far Away
[解説]
新たに撮影した部分はなく、すべて保存してあった8ミリフィルムをつないだもの。これだけ長いこと8ミリをやっていると、どんなものを撮って、それを捨てずに保存してあったのかきれいさっぱり忘れていたりする。ふと取り出してヴューワーで見てみると、画面のなかではもう死んでしまった友人が、とても幸福そうに笑っている。生きているのかどうかわからない友人も微笑んでいる。毎日、汚辱にまみれていたはずの自分も、なんと幸福そうにカメラをまわしていることか。そうかこれは走馬灯なんだな、と思った。死ぬ直前に見るという人生のパラパラ漫画。

LetMeEndWithYou
12分/DV/2003
[解説]
タイトルはこの映像についている音楽の題。この音楽をつくった人から映像をつけてほしいと依頼され、すべて8ミリ素材の映像を編集してつくったもの。音楽と映像とが五分五分の関係でお互いを補完し合って叙情的気分を醸し出すことを狙いとした。ノンリニア編集をしたわけだが、映像へのエフェクトはできるだけ加えないように気をつけた。

8ミリシューターDQNオヤヂ
3分/8mm/2003
8mm-shooter Mr Yellow Trash
[解説]
8ミリシューターはシリーズ化することにした。いつものようにパーソナルフォーカス出品作品は「おもしろおかしく」が原則。今回はフジZC1000でできることを解説しつつ、アフォなことをするという作品。スチールは車を運転しながらバルブ撮影をして、それだけではおもしろくないからヘンな顔をしているというしょうもないカット。
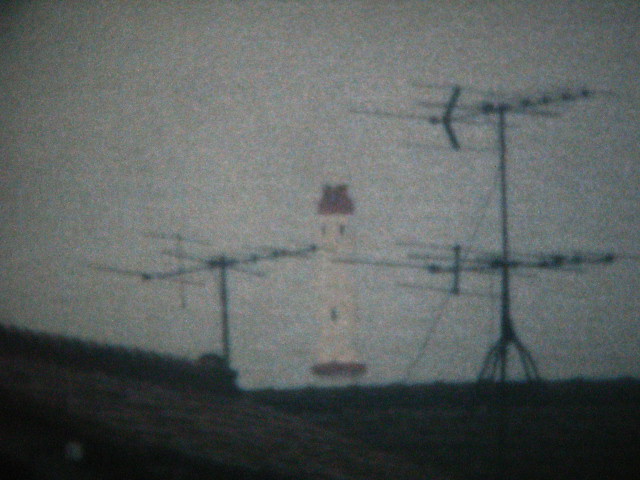
無翼の朝と夜
70分/8mm/2004
I have no wing through the night
[解説]
この作品は「ラ・カメラ全記録」の1995年1月のところを見てもらえばわかるように、いったん挫折してしまった作品。なぜ挫折したかと言えば、ただひたすら街の風景を撮り続けるというこの作品のコンセプトを貫徹するためには、心のなかのレンズを砕かなくてはならなかったからだ。砕けたらもとには戻れない。その覚悟が95年の段階ではなかったというわけ。カメラのレンズが砕けているわけではない。撮影者の心のレンズが砕けているのだ。そのうえで、なおも、街をさまよい歩き、撮り集められた風景の集積。それだけと言えばほんとうにそれだけしかない映画。