

僩儌偪傖傫僀儞僪傊偄偔
35暘乛VTR乛1995
Tomo-chan goes India
乵夝愢乶
丂搶懞嶳惵嬻妛峑偲偄偆丄壞偲搤偵巕偳傕偨偪偺僉儍儞僾傪庡嵜偡傞僌儖乕僾偑偁偭偰丄偦偙偱庰偺傒榖偱乽偄偮傕拋晝偲偐嶳棞偱偼偮傑傜側偄丅偄偭偦僀儞僪偵峴偙偆偐乿側傫偰尵偭偰傢偼偼偲徫偭偰偄偨偺偩偑丄庰偺傒榖偱廔傢傜偣側偄偲偙傠偑偙偙傪塣塩偟偰偄傞恖乆偺惁偄偲偙傠偱丄杮摉偵僀儞僪偵峴偔偙偲偵側偭偰偟傑偭偨丅偦偺庰偺傒榖偺応偵偄偰乽偄偄偧乕丄傗傟乕乿偲惙傝忋偑偭偰偄偨儚僞僔偼丄嶲壛偡傞愑擟偑偁傞偲巚偄丄價僨僆婰榐學偲偟偰帺旓偱嶲壛偟偨丅
丂偲偙傠偑嶲壛偟偨僌儖乕僾偵偄偨悪嶳朁巕偲偄偆侾俀嵨偺彮彈偺僉儍儔僋僞乕偑慺惏傜偟偔丄偙傟偼傕偆嶌昳偵偡傞偟偐側偄偲巚偭偰丄嶲壛幰偵攝晅偡傞僶乕僕儑儞偲偼暿偵曇廤偟偨傕偺丅

柌偺儔僀僆儞
14暘乛俉咢乛1996
Dreamed Lion Dreaming
乵夝愢乶
丂巕偳傕偺崰丄嬤強偱儔僀僆儞傪帞偭偰偄偨揦偑偁偭偨偲偄偆偺偼傑偭偨偔杮摉偺榖丅偦偺儔僀僆儞偑嬤偛傠帺暘偺柌偺拞偵搊応偡傞丅婥偵側傞丅曣恊偵僀儞僞價儏乕偟偨傝丄俁侽擭慜偺偦偺応強傪嵞朘偟偨傝偡傞丅傕偼傗偐偮偰偺柺塭側偳傑傞偱巆偭偰偄側偄奨丅
丂柌偺拞偵弌偰偔傞儔僀僆儞偼丄偦偺攚拞偵彈恄偝傑傪忔偣偰偄傞丅偁偒傜偐偵偦傟偼僸儞僪僁乕嫵偺僪僁儖僈乕彈恄偝傑偩丅崱搙偼僀儞僪偺恄條億僗僞乕傗丅僀儞僪塮夋偺堦僔乕儞丄偝傜偵偼僼傽儈僐儞僎乕儉夋柺傪堷梡偟偰丄柌偺僀儊乕僕偺弌強傪岅傞丅
丂嵟屻偵彮擭帪戙偺帺暘乮墶堜弐懢榊乯偑尰傟丄崱偺巹偵乽儔僀僆儞丄偳偙偄偭偪傖偭偨偺丠乿偲偟偮偙偔暦偔丅巹偼乽偍偲側偵側偭偨孨偺柌偺拞偱傑偨夛偊傞傛乿偲尵偆丅



嫊峘
80暘乛俉咢乛1996
A Port in Vain
乵夝愢乶
丂晛捠偺夝愢偵偮偄偰偼丄僼儘儞僩儁乕僕偵栠偭偰丄儔丒僇儊儔偺僐乕僫乕偱僠儔僔夝愢暥傪撉傫偱偔偩偝偄丅
丂偱丄傑偢偼儔丒僇儊儔忋塮偱偺僠儔僔偺夝摎丅巹埲奜偺俁恖偲偼丄厊帥杮榓惓丅偙傟偼娙扨丅乽嬌惎乿偱偼梒帣丅乽擫栭乿偱偼僇乕僐偺僷乕僩偱偺庡恖岞偺傛偆側傕偺丅乽嫊峘乿偱偼撍慠儈僯乕偲僎乕儉傪偟偰偄傞拞妛惗偱弌偰偔傞丅厎愳岥慞擵丅乽嬌惎乿偱偼侾侽暘偖傜偄偺帪揰偱丄恄壀偵乽偁偲俆暘偱偡傋偰偑傢偐傞乿偲尵偆抝丅傑偨屻傠巔偩偑丄嵟屻偵恄壀偑弌傞慜偺抧壓悈摴傪曕偄偰偄傞偺傕愳岥偱偁傞丅乽擫栭乿偱偼柤屆壆偱夛偆抝偲偟偰俁嶌偺拞偱偼偄偪偽傫偼偭偒傝弌偰偔傞丅乽嫊峘乿偱偼儈僯乕偺忣曬傪媮傔偰夛偆抝彈傆偨傝偺偆偪偺傂偲傝丅厏恄壀椔丅偙傟偑堦斣擄偟偄丅乽嬌惎乿偱偼摉弶偺庡恖岞丅乽擫栭乿偱偼僇儊儔傪帩偮俁恖偺撪偺侾恖丅偲偙傠偑乽嫊峘乿偺偳偙偵弌偰偄偨偐偑傢偐傜側偄偩傠偆丅偠偮偼丄愳岥偺僔乕儞偺朻摢丄愳岥偺嵗偭偰偄傞慜傪捠夁偡傞捠峴恖偑恄壀側偺偩丅傢偞偲僇儊儔偵婄傪岦偗偰捠夁偝偣偰偄傞偺偩偑丄偦偺偙偲偑媡偵帺慠偵尒偊傞偨傔丄傢偐傜側偄丅
丂偄傗丄偦傫側偙偲偼偳偆偱傕偄偄偙偲偩丅偣偭偐偔偙偙傪尒偰偔傟偨恖偺偨傔偵桳塿側夝愢傪偟側偔偰偼偄偗側偄丅
丂乽嫊峘乿偺偪傚偆偳帪娫揑偵傑傫拞偺晹暘偼丄乽僠儑乣僢僩丄儅僢僥僋僟僒乣僀乿抝偑乽儘僔傾恖偺寣偑俁暘偺侾乿偵偮偄偰夝愢偟偰偄傞晹暘偩丅寉偔尒棳偟偰偟傑偭偰偄傕偄偄偑丄偠偮偼偙偙偑娞怱側晹暘側偺偩丅偳偆偄偆偙偲偐偲尵偆偲丄抂揑偵尵偊偽擔杮恖偺寣偑侾侽侽亾側傫偰偙偲偼偁傝摼側偄丅偦傟偼擔杮恖偑崿寣柉懓偱偁傞偲尵偆庡挘偱偼側偔偰丄偳偺柉懓偱偁偭偰傕丄偦傟偑侾侽侽亾弮悎偱偁傞偲偄偆崻嫆偼偁傝摼側偄偐傜偩丅傢偐傞傛偹丅傢偐傜側偐偭偨傜丄偪傚偭偲帺暘偺傾僞儅偱峫偊傛偆丅偝偰丄偦偆偩偲偡傞偙偲偐傜偳偙偑偳偆偄偆偲偄偆峔憿傪扵嶕偡傋偔暥壢恖椶妛偑偼偠傑傞偺偩偑丄偦傟偼抲偄偰偍偄偔偙偲偵偟偰丄偙偲塮夋偵偮偄偰丄偙傟傪侾侽侽亾偺僼傿僋僔儑儞偐侾侽侽亾偺僲儞僼傿僋僔儑儞偐偲偄偆栤偄偵抲偒姺偊傞偲暘偐傝傗偡偄偩傠偆丅偦偆丄偦傫側傕偺偁傝偼偟側偄偺偩丅僼傿僋僔儑儞偲僲儞僼傿僋僔儑儞偺娫偵僌儗乕僝乕儞偑偁傞偺偱偼側偔偰丄偦傕偦傕尩枾偵傢偗傞偙偲側偳晄壜擻側偺偩丅
丂偠傖偁壗偑尵偄偨偄偺偐偲偄偊偽丄偦偺偙偲傪愊嬌揑偵嶌昳偵庢傝崬傫偩傝丄擔忢偵墳梡偟偰偄偗偽丄傕偭偲妝偟偔惗偒傞偙偲偑偱偒傞傫偠傖側偄偐偺偋丄偲偄偆偙偲偩丅偦傟偩偗丅戅孅偟偰偨傝丄柺敀偄偙偲偑側偄偲晄枮僽僞偵側偭偰偄傞傂偲偼丄憐憸椡偑側偔偰擔忢偵傂偦傓奜崙傪奐戱偱偒側偄恖娫側傫偩丅偙傟偼偒偭偲晄岾側偙偲偵堘偄側偄丅
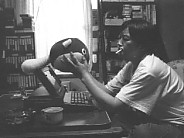
僐乕僕儑儖偺數
俁暘乛俉咢乛1996
A Pegeon of Kajol
乵夝愢乶
丂僐乕僕儑儖偲偼僀儞僪塮夋偺僗僞乕彈桪偝傫丅偦偺斵彈偑弌偰偄傞塮夋傪價僨僆偱尒偰偄偨傜晄巚媍側僔乕儞傪敪尒偟偨丅儈儏乕僕僇儖偺堦応柺偱丄僐乕僕儑儖偑戝嬻偵搳偘偨數偑丄偁偭偗側偔捘偪偰偟傑偆偺偩丅偙傟偼擔杮塮夋偺尰応偱偼OK偵偼側傜側偄丅偦傟偱擔杮塮夋偲僀儞僪塮夋偺堘偄傪峫偊偨傝偡傞丅偦偆偄偊偽僀儞僪偵偼塮夋偺彈恄偝傑偑偄傞偲杮偵彂偄偰偁傞丅偦偺彈恄偝傑偵僀儞僪塮夋偼斴岇偝傟偰偄傞偺偩傠偆丅偱偼擔杮偵偼塮夋偺恄條偼偄側偄偺偐丅偁丄塮夋偱偼側偄偗傟偳丄梮傝偺恄條偼偄傞丅偦偺傾儊僲僂僘儊偲偄偆彈恄偝傑傪庡恖岞偵丄僔僫儕僆傪彂偒巒傔傞偑丄崙憿傝偺埬撪栶偱偁傞儎僞僈儔僗偑捘偪偰偟傑偭偰擔杮偺崙偼惉棫偟側偄偲偄偆僆僠偱傔偱偨偟傔偨偟丅

倁丏俵.
80暘乛俉咢乛1997
乵夝愢乶
丂娙扨偵尵偆偲乽VM乿偲僞僀僩儖偁偨傑偵偮偄偰偄傞嶌昳傪慡晹偮側偘偨傕偺丅偨偩偟偦傟偱偼寍偑側偄偺偱丄怴偟偔侾俆暘傎偳偺僼僢僥乕僕傪嶣傝懌偟偰偄傞丅傑偨娙扨側塮憸僷僼僅乕儅儞僗傕偁傞偺偱丄巹偑峴偗側偄応偱偺忋塮偼偱偒側偄丅偮側偘偰傒傞偲丄偠偮偵攑毿庯枴偵枮偪偨嶌昳孮偩偭偨偙偲偑傢偐傞丅偳偆傗傜巹偵偲偭偰攑毿偲偼丄惗(V=VIDA)偲巰(M=MUERTE)偑梟夝偟丄梈崌偡傞応偱傕偁傞傛偆偩丅
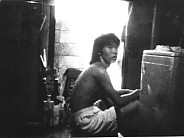
僌儕僓僀儐乮偡傋偰奃怓乯
俁暘乛俉咢乛1997
Grisaille (Gray over)
乵夝愢乶
乽嬌惎乿乽擫栭乿偱戝妶桇偺彮擭丄僇僘偑傂偝偟傇傝偵傾儊儕僇偐傜婣偭偰偒偰偆偪偵傗偭偰偒偨丅偦傟偱丄僇僘偵斵偺曣恊偺庒偄帪偺幨恀傪尒偣傞丅僇僘偲偺嫍棧傪應傝偐偹側偑傜儃乕儕儞僌偱梀傫偩傝丄怘帠傪偟偰偄傞偆偪偵丄斵偼乽偹偊丄偍傆偔傠偲怮偨偙偲偁傞偺丠乿偲暦偔丅偦偺尵梩偵摦梙偟側偑傜傕丄嶌幰偺棥偵嬯乆偟偄婰壇偑傛傒偑偊偭偰偔傞丅僇僘偺偍傕傝傪棅傑傟偨偙偲偑偁偭偨偑丄偦偺帪丄偠偮偼僇僘偺曣恊偼抝偲埀偭偰偄偨偺偩丅
丂屄恖塮夋僗僞僀儖偺拞偱丄埆堄傪娷傓嬯乆偟偄傕偺偑偁偭偰傕偄偄偲峫偊偰偮偔偭偨丅偟偐偟丄巹彫愢偱偼捒偟偔傕側偄曽朄偩偑丄塮夋偲偄偆恖傗暔偑媅帡揑偵尰慜偡傞儊僨傿傾偱偼丄柶塽偑側偄恖偑傎偲傫偳偱偁偭偨傛偆偱丄崱偺偲偙傠偙偺堄恾傪棟夛偟偨偲岅傞恖偵偼弌夛偭偰偄側偄丅巆擮丅
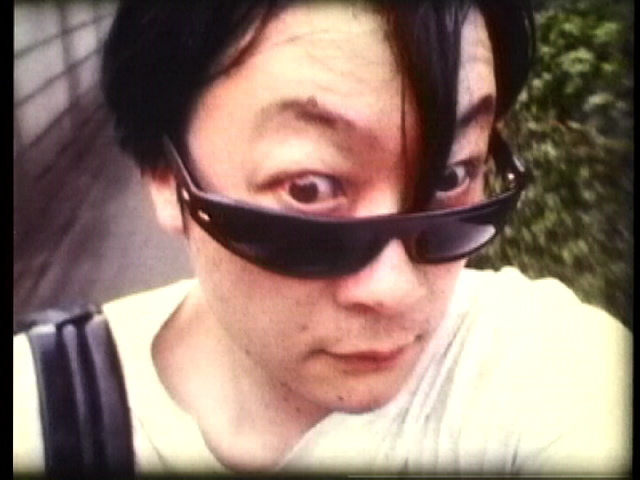
俉儈儕僔儏乕僞乕榑棟楾
俁暘乛俉咢乛1998
8mmfilm shooter Logical Lonely Wolf
乵夝愢乶
丂俉儈儕偺戝儀僥儔儞偱偁傞儘儞儕丒僂儖僼巵偑斵偺忢梡偡傞僇儊儔僶僢僋偺拞恎傪岞奐偟丄夝愢偡傞偲偄偆庯岦丅僶僢僋偐傜庢傝弌偝傟傞傕偺偼偄偪偄偪梡搑偑擺摼偱偒傞傕偺偽偐傝偩偑丄偳傟傕偱偒傞偐偓傝偐偝挘傞傕偺偵偟偨丅傑偨丄掁傝巺偺巊梡朄偲僐儞僪乕儉偵傛傞寣屝戃偺巊偄曽偼幚慔塮憸傕偁傝丄偄偔傇傫偐偼嶲峫偵側傞傛偆側攝椂傕偝傟偰偄傞丅

僌乕僞儕僾僩儔
56暘乛俉咢乛1999
GOOTARIPUTRA
乵夝愢乶
丂俁侽嵨戙屻敿偺帺嶌帺墘傜偟偒庡恖岞偺擔忢偑偨傫偨傫偲捲傜傟傞塮夋丅撈恎偺斵偼擔杮庰傪垽偟丄擫傪垽偟丄栭偺偆傠偮偒傪垽偟丄偦偟偰俉儈儕僇儊儔傪偍傕偪傖偺傛偆偵偟偰擔忢偺摴嬶偲偟偰偄傞丅暔岅揑側揥奐偼偄偭偝偄側偔丄偨偩傂偨偡傜抝偺晹壆偱偺偟偖偝傗峴摦丄奜偱偺偆傠偮偒傪昤偔丅
丂儌僩僱僞傪柧偐偣偽丄嶳揷桬抝偺乽栭憢乿傪帺暘側傝偵傗偭偰傒偨嶌昳丅嵟弶偵愝掕偟偨儖乕儖偼厊暔岅偼側偟厎戜帉傕側偟厏庡恖岞乮嶳嶈乯埲奜偺恖娫偺搊応恖暔側偟丅偙傟偼俁廳嬯偺傛偆側傕偺偩丅偟偐偟寛傔偨埲忋偼傗傠偆偲巚偭偨偺偱丄姰惉傑偱偵俁擭偐偐偭偰偟傑偭偨丅偙偺偙偲偼掚偵杽傔偨儈僢僉乕偲儈僯乕偺僆乕償傽乕儔僢僾偑弔偐傜搤傑偱懕偔偲偙傠偱姶偠庢偭偰傕傜偊傞偩傠偆丅俉儈儕偵偼僱僈偑側偄偐傜丄偙傟偼偢偭偲侾杮偺僼傿儖儉傪僇儊儔偵擖傟偨傑傑丄堦搙偺幐攕傕嫋偝傟偢偵偙偺嶌嬈傪偡傞偟偐側偄偺偩丅
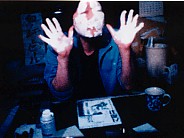
墲暅IV
63暘乛俉咢乛1999乮嶳揷桬抝偲嫟嶌乯
Filmletter仛oufuku IV
乵夝愢乶
丂侾丄俀丄俁偺偲偙傠偺夝愢偵傕偼傗晅偗懌偡傕偺偼側偄丅戞係嶌栚丅
丂偢偭偲儔丒僇儊儔偱偺忋塮夛傪偍偙側偭偰偄傞帪婜側偺偱丄寧偵堦搙偼夛偭偰偄傞丅偦傫側側偐偱棫偪偁傜傢傟偰偔傞偺偼乽搶嫗乿偲偄偆庡戣偲乽暔岅乿偲偄偆庡戣偩傠偆偐丅

栭偵僠儍僠儍僠儍
14暘乛俉咢乛1999
Cha-cha-cha for Night
乵夝愢乶
丂塮夋偼僑僟乕儖偑尵偆傛偆偵乽塮憸偲壒乿偱惉傝棫偭偰偄傞偑丄偳偆偟偰傕塮憸偺曽偑庡偱壒偼廬偲偄偆偒傜偄偑偁偭偨丅偦傟傪懪攋偟偰壒乮偙偺応崌偼尵梩乯偑庡偵側傞偨傔偵丄儗儞僘傪偼偢偟偰嶣塭偟偨塮憸傪巊梡偡傞偲偄偆曽朄傪巚偄偮偄偨丅僼僕僇ZC1000偩偗偑儗儞僘傪偼偢偡偙偲偺偱偒傞俉儈儕僇儊儔偩丅偙傟偼偦傟偱嶣塭偝傟偰偄傞丅儗儞僘傪偼偢偡偲塮憸偼寢偽側偄偑丄岝偺嫮搙偲崿熇偟偨怓崌偄偩偗偼弌傞丅偦傟傛傝傕偍傕偟傠偄偺偼丄岝偺擖幩妏偑僼儕乕偵側傞偙偲偱丄岝尮偵妏搙偵婎偯偔僼儗乕儉偑偦偺傑傑塮傝崬傫偱偔傞偙偲偩丅
丂庡懱偲側傞尵梩偼丄媑憹崉憿偝傫偺塭嬁偑嫮偄尵梩偵側偭偰偟傑偭偨丅偙傟偼巹偑挿傜偔媑憹偝傫傪價僨僆偵嶣偭偰偁乕偱傕側偄偙乕偱傕側偄偲曇廤偟偰偄偨偺偱偟偐偨側偄丅