

がむぜ3
GAMUZE 3
1989年、約30分、8mm、カラー
初公開:光が生まれるところ(東京・ラ・カメラ)
参加者:高島利行 酒井知彦 山崎幹夫 原達也 佐々木浩久 松井エリセ
小川智子 松本崇久 金子丈男 田村拓 神岡猟 七尾太佳史
[解説]
新宿と高田馬場の間にある、新宿スポーツセンターに集合。昭和天皇が死んで「大葬の礼」というのが行われる直前であり、警察の厳戒体制の中で決行された。まあ当然「不審な行動をしている」ということで、松井エリセが警察に引っ張っていかれてしまった。12名の参加者のうち、映像通り魔のメンバーだったものが6名。北海道出身者がやはり6名と、偏りのみられた実習であった。またワタシは二日酔いで午前中はトイレにこもって胃液を吐きまくり、ヒンシュクを買った。

VMの夢想
V/M. Dreaming
1989年、8分、16mm、白黒&カラー
初公開:イメージフォーラムフェスティバル89(東京・シードホール)
音楽:勝井祐二 出演:神岡猟
[解説]
VMシリーズ第1作。Vとはスペイン語のヴィダ(生)、Mは同じくムエルテ(死)のこと。撮影は北海道で行なった。現像済みフィルムをもういちど不完全に重ねて露光し、絵がゆらめいたり、フレームから逸脱する効果を狙った実験映画。
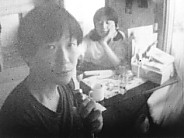
3時に集まって
Gather at 3pm
1989年、20分、8mm、カラー
初公開:映像ネットワークVIEWフェスティバル(札幌・イメージ・ガレリオ)
参加者:加藤到 佐々木健 黒川芳信 水由章 前田敏行 永野聖美 山崎幹夫
[解説]
参加者は20分ごとに15秒ずつ撮影しながら、最終的には新宿御苑に集合して出会うというコンセプトの作品。参加者のそれぞれ異なる特質が発揮され、観やすい作品となった。1989年ハンガリー国際実験映画祭〈レティナ89〉正式招待作品。

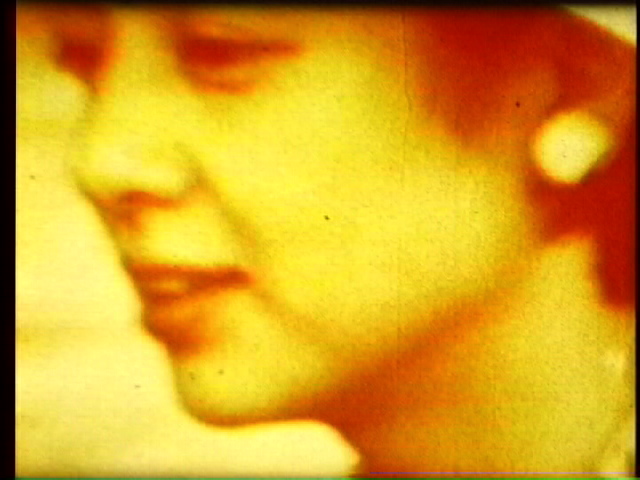
VMの漂流
V/M. Drifting
1990年、9分、16mm(8mm版もあり)、カラー
初公開:イメージフォーラムフェスティバル90(東京・シードホール)
音楽:勝井祐二 出演:神岡猟 寺本恵子
[解説]
シリーズ2作目では、さらに多重露光を試みた。川辺でイアリングをはずして投げ込むシーンは『泥のなかで生まれた』と重複している。
がむぜ4
GAMUZE 4
1990年、約30分、8mm、カラー
初公開:光が生まれるところ(東京・ラ・カメラ)
参加者:山崎幹夫 神岡猟 酒井知彦 石井秀人 小口詩子 鈴木章浩 金子丈男
松本崇久 岡本伊津子
[解説]
練馬区の石神井公園でおこなった。新趣向としてワタシがあらかじめルートのあちこちに落書きしたり、赤い星のシールを貼ったりした。まったく無視されたものもあったが、ちゃんと複数の参加者によって撮影されたものもあった。この実習では小道具が駆使されたのが特徴で、神岡は無線機、小口はリカちゃん人形、金子は液晶モニター付きのビデオカメラを持ち込んできた。また、鈴木はあらかじめ彼の子どもを前もってフィルムに写し込んできた。しかし秀逸だったのは石井で、他の参加者と同じようなものを撮っているのに、なぜか飛び抜けて美しい。彼にだけは8ミリ映画の女神さまが微笑んでいるのではないかと思ったのだった。

VMの脈動
V/M. Heartbeating
1991年、9分、8mm、カラー
初公開:イメージフォーラムフェスティバル91(東京・シードホール)
音楽:エマーソン北村
[解説]
平型のマイクを使って、街のあちこちの聴診を試みる。特に多く収録されたマンホールの音は、都市という生き物のたてる脈動のようにも聞こえる。

くねひと
Knecht
1991年、3分、8mm、カラー
初公開:VIEWフェスティバル(埼玉・名栗村営山の家)
[解説]
街を歩いていての気になるもの全集。古いビルの壁の亀裂が、なにげない落書きが、意味不明の突起物が「気になる」。それは日常から自分をずらすための手掛かりのように見えるからだ。

VMの地標
V/M. Landmarking
1992年、5分、8mm、カラー
初公開:イメージフォーラムフェスティバル92(東京・シードホール)
[解説]
街を解読するための赤い星大作戦(ムエン通信9号)。それを映像化してみた。与えられたものでなく、しかし現前する「街」を解読するための試み

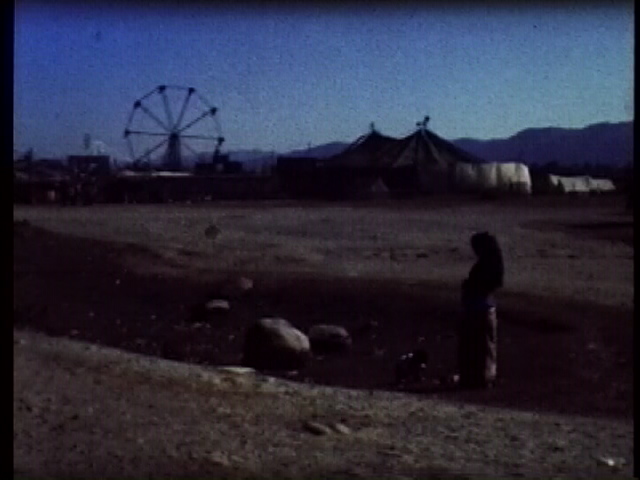

猫夜
The Cat Night
1992年、80分、8mm、カラー
初公開:猫夜/山崎幹夫作品集(東京・イメージフォーラム)
出演および撮影:山崎幹夫 神岡猟 寺本恵子 寺本和正 杉浦茂
音楽:勝井祐二(ヴァイオリン) 演奏:ヒゴヒロシ(ベース) カムラ(ボーカル)[解説]
『極星』でヤマザキが北陸で再会した女性、カーコは東京へ子どもを連れて出てくる。一方、ヤマザキは『極星』をユーロスペースで上映。相変わらず映写室でカメラを回していたりする。そして『極星』の札幌上映。今度はリョウも一緒だ。かつて撮影した場所を再訪したりする。札幌から戻ると、友人のセルがアフリカで撮った8ミリのフィルムが届いている。それにヒントを得て、ヤマザキはカーコとリョウに8ミリカメラを渡し、彼らの日常を彼らじしんの手で撮ってもらうことにする。3人それぞれの日記映画が平行して展開される。カーコはもっぱら息子のカズを写している。リョウは仕事と酒飲みにあけくれる日常。ヤマザキはじしんのさまよう夜の街の映像。やがてヤマザキはインドへ旅に出る。旅から帰ってこんどは国内を『極星』上映の旅にあけくれる。カーコは相変わらずカズを撮っている。保育園に通っていたカズも、いつのまにかランドセルを背負っている。一方、リョウは、しだいに8ミリカメラが重荷に感じてくる。意を決してヤマザキに8ミリカメラを突き返し、なじるヤマザキに背を向けて去る。ある朝、ヤマザキは子猫を拾う。夜にさまよい歩くのはやめて猫を育てるのに熱中する。そして唐突なラスト、緑深い林の中にいるカーコとカズ。カズはカーコに「お母さん、今度は僕が撮る」と言って、樹の下でカズを微笑んでみつめているカーコを8ミリフィルムにおさめる。
上記のストーリーでもわかるように、まるで物語的な結構(起承転結)がない映画だ。作者であるワタシじしんの「眼」を排して、編集においてもキメを極力排除した。なぜかと言うと、その方が気持ちよいからだ。時間だけがじわじわ流れる。物語が始まる以前の静けさで全編を統一したかった。ここにはホレたハレたも、キッタハッタもない。目玉(カメラ)は4つに分裂し、ついに交わることはない。映画の最初の方で出てきたセルという人物は、アフリカから8ミリフィルムを送ったまま、行方不明になってしまう。ヤマザキとリョウの男ふたりは、混迷するという自覚もとくになく、ただ風景をさまようだけ。カーコは徹頭徹尾、息子のカズを見つめ続ける。変化と言えばカズがすこしずつ成長していくことだけだ。
物語がなくても映画は成立する、という意見は間違いではないにしても、浅はかな見解でしかない。人間がスクリーン上に写し出される以上、物語は否応なく発生してしまう。例え話でもうしわけないが、これはオーディオの世界で言えば、真空管アンプのようなものだろう。効率が悪く、出力が驚くほど少なくても、真空管アンプの音はなぜか心なごむ。あるいは、思考速度が遅く、容量がバカ少なく、音が3つしか出せなかったファミコンでのゲームが、なぜこんなにもスーパーファミコンのゲームよりもおもしろかったのか。
表現には強度の限界が設定されているほうが想像力をかきたてる。これも間違いではないが、単細胞な見解だろう。しかし実際のところ、ワタシにもこれがどうして気持ちいいのかわからない。機械あるいはメディアは、それが原初形態にたちかえるたびに不可思議な色気をはなつ、とか、音楽の世界で、和音を全部出さないことや、雑音成分だけで主旋律を導き出す方が気持ちいいことと通じている、ということぐらいしか今はわからない。まあ、作者がしたり顔で解説するほどシラケることもないから、このくらいにしておこう。理屈をこねくりまわしてないで、さっさと新作を発表せんかい!という声が外野席から聞こえてきそうだから。

破壊市を探して
Looking for Destructive City
1992年、15分、8mm、カラー
初公開:映像ネットワークVIEWフェスティバル(長野・大日向公民館)
[解説]
札幌在住時代のいくつかの作品に出演してくれた犬飼久美子がこの年、故郷で病死した。それで、彼女を追悼するような作品をつくろうと単純に考えた。しかし、ただ悲しみにうちひしがれて、哀悼するだけの作品ではつまらない。どうせなら未来へ向かって開いていくような作品であるべきだろうと思ったのだった。それが、彼女の死という事実の報告と、彼女の主演した『散る、アウト。』の引用にからめて挿入される「筆ペンの冒険」の物語なのだ。なんで筆ペンなの? 筆ペンにどんな意味があるの? と、よく観客から聞かれた。ここはちょっとうかつだった。ワタシにとっては、筆ペンというのは葬式のときにだけ出くわす文具なので、筆ペンに葬式のイメージを重ねただけだったのだが、すんなり伝わらなかったようだ。もうしわけない。