
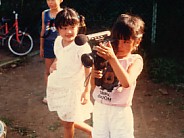

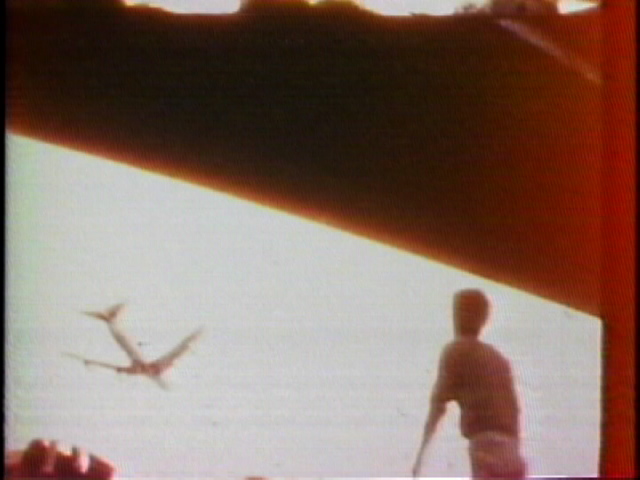

嬌惎
Guiding Star
侾俋俉俈擭丄俈俆暘丄俉mm丄僇儔乕仌敀崟
弶岞奐丗嶳嶈姴晇塮憸屄揥乽嬌惎乿乮搶嫗丒儐乕儘僗儁乕僗乯
丂弌墘丗恄壀椔丂帥杮宐巕丂帥杮榓惓丂愳岥慞擵丂娾熀嵤巕
丂壒妝丗彑堜桽擇乮僨僼僅儖儊乯
乵夝愢乶
丂1985擭係寧丄乻杔乼偼桭恖偺恄壀椔傪庡恖岞偵丄堦杮偺塮夋傪嶣傝巒傔傞丅偟偐偟嶰儢寧傪宱夁偟偰傕塮夋偺慡懱偼尒偊偰偙側偄丅攡塉偵側傝壵棫偪巒傔偨杔偼偙偺塮夋傪拞巭偵偟傛偆偐偲巚偆丅廐偵側傝丄杔偼傂偲傝偱僇儊儔傪傑傢偟巒傔傞丅枅擔丄擔杤偺晽宨傪僐儅嶣傝偟偨傝丄柊偭偰偄傞帺暘傪嶣偭偨傝偡傞丅偦偟偰搤丄傄偁偱塮幨媄巘偺傾儖僶僀僩傪偟側偑傜塮幨幒偱僇儊儔傪傑傢偡丅偦傫側偁傞擔丄壠偱帞偭偰偄傞偆偝偓偑巰嶻偟偨丅掚偺擁偺壓偵杽憭偟側偑傜丄杔偼堦嶐擭巰傫偩晝偺偙偲傪憐偄弌偡丅晝偑俉儈儕僇儊儔傪攦偭偨偺偼17擭慜偺偙偲偩丅壠偵巆偭偰偄傞僼傿儖儉偺拞偱丄梒偄杔偲枀偑梀傫偱偄傞丅晝偼傕偆偙偺悽偵偄側偄偗傟偳丄晝偺巆偟偨乹傑側偞偟乺偩偗偼巆偭偰偄傞丅偦偟偰杔偼椃偵弌傞丅杒棨偺偁傞挰偱丄愄丄杔偺塮夋偵弌偰偔傟偨彈惈偲夛偆丅斵彈偼傕偆偡偖係嵨偵側傞斵彈偺巕偳傕傪楢傟偰偒偨丅搶嫗偵岦偐偆楍幵偺拞偱偆偨偨偹傪偡傞偲丄柌偺拞偵斵彈偑弌偰偒偰乽傕偆偡偖弌岥偑傒偮偐傞傛乿偲尵偆丅搶嫗偵栠偭偨杔偼恄壀偵乽傑偨嶣塭傪巒傔傞偧乿偲尵偆丅暔岅偺敍傝偐傜夝偐傟偨恄壀偼丄僇儊儔傪偍偪傚偔傞偐偺傛偆偵丄偁傞偄偼媃傟傞偐偺傛偆偵栰尨傪憱傝夞傞丅傆偨偨傃晹壆偵栠偭偰偒偨杔偼丄儅僀僋偵壩傪偮偗丄墛傪儗儞僘偵墴偟摉偰傞丅
丂塅乆揷岞嶰偼偙偺塮夋傪乽巰偲夬暅乮嵞惗乯偺暔岅乿偲昡偟偨丅斵偵傛傞偲丄偙偺塮夋偺拞偵偼係偮偺乽巰偲夬暅乿偑偁傞偲尵偆丅厊嵟弶偵寁夋偟偨塮夋偼姠夝偡傞偑丄儔僗僩偱庡恖岞偺恄壀偑栶偐傜夝曻偝傟傞偙偲偱暔岅偼惉暓偟丄傕偭偲峀偄悽奅偑採帵偝傟傞丅厎巰嶻偡傞偆偝偓偑丄儔僗僩偱偼偪傖傫偲巕偳傕傪嶻傒丄尦婥傛偔巕偆偝偓偑彫壆偐傜旘傃弌偟偰偔傞丅厏晝偼巰傫偩偑丄偺偙偝傟偨晝偺傑側偞偟亖儂乕儉儉乕價乕偑偙偺塮夋偵庢傝崬傑傟傞偙偲偱怴偨側惗傪庴偗傞丅厐妛惗帪戙偵嶌偭偨塮夋偵弌墘偟偨彈惈傪嵞傃嶣傝偵峴偔偙偲偱丄暔岅偺榞傪墇偊偨娭學偑嵞惗偝傟傞丅
丂偁傞偄偼偙偺塮夋偺偁偪偙偪偱業掓偟偰偄傞乽塕乿偑巜揈偝傟傞偙偲傕懡偄丅旕擄偱側偔丄岲堄揑偵巜揈偝傟傞偺偩偑丄偮傑傝丄屄恖塮夋偩偐傜偲偄偭偰帠幚偵拤幚偱側偔偰偼側傜側偄偲偄偆婯懃偼側偄偲偄偆偙偲偩丅娤媞偵偲偭偰傕丄嶌幰偵偲偭偰傕丄婎杮揑偵偼偍傕偟傠偐偭偨傝丄怱偑摦梙偟偨傝偡傟偽丄偦傟偼偨偄偟偨傕傫偩偲峬掕揑偵偲傜偊傞傋偒偩偲偄偆偙偲側偺偩丅塮夋傕侾侽侽擭懕偄偰偒偨昞尰宍幃偩偐傜丄娤媞傕偄偄偐偘傫偡傟偭偐傜偟偵側偭偰偔傞丅曄摦偡傞乽儕傾儖姶乿偺憡応偼丄傛偆傗偔乽嫊幚旐枌乿偺椞堟偵庴偗庤偺懁偱傕摓払偟偨偲尵偆傋偒偐丅
丂嶌幰偱偁傝丄僇儊儔傪夞偟偰偄偨儚僞僔丄嶳嶈姴晇偑乽傎傫偲偆偵乿帥杮宐巕偵巚偄傪婑偣偰偄偨偐偳偆偐側傫偰丄偳偆偱傕偄偄偙偲側偺偩丅恄壀椔偑栶偐傜夝曻偝傟丄偳偙傊憱傝嫀傠偆偲偦傟傕偳偆偱傕偄偄偙偲側偺偩丅晝偺傑側偞偟偩偗偑巆偭偰偄傞側傫偰偄偆偙偲傕丄椻惷偵峫偊傟偽儗僩儕僢僋乮尵偄夞偟乯偵夁偓側偄丅偆偝偓偼傎偭偲偄偰傕彑庤偵巕偳傕傪嶻傓丅偆偝偓偵偟偰傒傝傖梋寁側偍悽榖偩丅撍弌偟偰偄偨偺偼僇儊儔偩偗偩丅僇儊儔偑棪愭偟偰偙偺塮夋傪堷偭挘偭偰偟傑偭偨偺偩丅僇儊儔偺嫵偊偵拤幚偵側傞偙偲丅偙偺塮夋傪巟偊偨偺偼偙傟偩偗丅弌岥側傫偰偦傕偦傕側偄丅偖傞偖傞夞偭偰偄偨偺偼僇儊儔偺拞偺俉儈儕僼傿儖儉偩偗偩丅
亀嬌惎亁偼丄俉儈儕僇儊儔偩偗偑悽奅傪廲墶柍恠偵旘傃夞偭偰憿傝忋偘偨塮夋側偺偱偁傞丅儚僞僔丄嶳嶈偑俉儈儕塮夋偲偄偆儊僨傿傾傪巊偭偰嶌偭偨悽奅偱偼側偔丄俉儈儕僇儊儔偑儚僞僔傪偟偰嶣傜偟傔偨塮夋側偺偩丅崱偲側偭偰偼偦傫側婥偑偡傞丅偦傟偱丄偔傗偟偄偐傜丄塮夋偺曽偵傕傂偲朅悂偐偣偰傗傠偆偲嶔傪楙傝丄偦偺屻亀擫栭亁偲偄偆嶌昳傪偮偔傞偙偲偵側傞丅

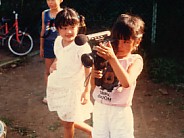
傝傝偔偠傘傫傃
Preparation to take off
侾俋俉俈擭丄侾侽暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗俹俥俥87僾儗僼僃僗僥傿僶儖乮搶嫗丒怴廻僔傾僞乕僩僢僾僗乯
丂嶣塭丗戝懶妛摱僋儔僽偺巕偳傕偨偪
乵夝愢乶
丂摉帪僶僀僩偟偰偄偨妛摱僋儔僽偱丄巕偳傕偨偪偵僇儊儔傪搉偟偰彑庤偵嶣傜偣偨丅彫妛峑堦擭惗偐傜嶰擭惗傑偱偺巕偳傕偨偪偺丄掅偄埵抲偐傜偺晄埨掕側堏摦嶣塭偑慡曇傪愯傔傞丅帺暘偺摢傛傝戝偒偄俉儈儕僇儊儔偱廳偨偦偆偵丄偟偐偟婌傫偱嶣塭偡傞巔偑偍偐偟偐偭偨偺偱偳傫偳傫嶣傜偣偨丅尰憸偟偰僼傿儖儉傪尒傞偲丄側傫偲傕旤偟偄乹傑側偞偟乺偵枮偪偰偄偨偺偱丄傊偨偵庤傪壛偊偢偦偺傑傑嶌昳偲偟偨丅搑拞丄僇儊儔傪帩偭偨彮擭偑丄彮彈偵堦敪墸傜傟傞偲偙傠偼丄壗搙尒偰傕徫偭偰偟傑偆丅峫偊偰傒傟偽丄巕偳傕偨偪偺悽奅偭偰偺偼丄偙傫側傆偆偵晄堄偵償傽僀僆儗儞僗偑朘傟傞傕偺側偺偩丅

偱傟偭偒
DEREKKI
侾俋俉俈擭丄俁暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗僷乕僜僫儖僼僅乕僇僗87乮暉壀丒暉壀導棫旤弍娰乯
乵夝愢乶
丂僞僀僩儖偼杒奀摴曎偱乽壩憕偒朹乿偺偙偲丅亀嬌惎亁傪俁暘偵嬅弅偟偨傕偺丄偲尵偭偰傕偄偄偐丅戝妛堦擭惗偺帪偵嶣偭偨僼傿儖儉偲丄尰嵼偺帺暘偺塭偺塮憸偵丄摉帪彂偄偨彫愢亀旝徫傒丄偦偟偰巰柵偡傞栭亁偺暔岅偑嬅弅偟偰岅傜傟傞丅僷乕僜僫儖僼僅乕僇僗偺俉mm俁暘偲偄偆尷掕偝傟偨榞偺拞偱丄偳傟偩偗暔岅傪崬傔傜傟傞偐偲巚偭偰嶌偭偨丅

偑傓偤侾
GAMUZE 1
侾俋俉俉擭丄俀侽暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗嶥杫塮憸僼僃僗僥傿僶儖1988乮嶥杫丒僀儊乕僕丒僈儗儕僆乯
嶲壛幰丗揷懞戱丂摗尨復丂嶳嶈姴晇丂幍旜懢壚巎丂恄壀椔丂庰堜抦旻
乵夝愢乶
丂埲壓偵昿弌偡傞乽偑傓偤乿乽側傑傜乿乽偩偼傫乿側傞嫟摨惢嶌嶌昳丅偙傟傜偼乽彑塝妚柦戝妛塮憸島嵗幚廗乿偲偄偆塮憸儚乕僋僔儑僢僾偵傛偭偰惗傑傟偨嶌昳孮側偺偩丅丂敪憐偺傕偲偵側偭偨偺偼亀塮憸楢壧亁偱丄偦偺懱尡偐傜丄傕偆偪偭偲柺敀偔偡傞偵偼丄傕偭偲忦審傪偒傃偟偔偟偨曽偑偄偄偺偱偼側偄偐偲偁傟偙傟峫偊偰丄俁僷僞乕儞偺僐儞僙僾僩傪栂憐偟丄偦傟偧傟乽偑傓偤乿嶌愴丄乽側傑傜乿嶌愴丄乽偩偼傫乿嶌愴偲柤偯偗偨丅娤傟偽堦栚椖慠偩偑丄偦傟偧傟偙偙偱傑偲傔偰夝愢偡傞丅
偑傓偤丗
丂偙傟偼擔偵偪偲廤崌応強傪寛傔偰屇傃偐偗丄嶰乆屲乆廤傑偭偨幚廗幰偵丄俉儈儕僇儊儔偲抧恾傪搉偡丅抧恾偵偼栴報偑彂偒崬傫偱偁偭偰丄偖傞傝偲傂偲傑傢傝偟偰傑偨廤崌応強偵栠傞傛偆偵側偭偰偄傞丅偙偺栴報偵廬偭偰曕偒側偑傜丄偦偺娫偵俉儈儕僼傿儖儉傪儚儞儘乕儖夞偟側偝偄丄偲偄偆僐儞僙僾僩丅摨偠応強傪曕偒側偑傜丄偳傟傎偳傑側偞偟偵嵎偑弌傞偐丄偲偄偆幚尡側偺偩丅
亀偑傓偤侾亁偼丄偲傝偁偊偢嵟弶偲偄偆偙偲偱丄儚僞僔偺帺戭偵廤傑偭偰傕傜偭偰丄偦偙偐傜攡娾帥偲偄偆帥傪嵟墦揰偲偟偰堦廃偟偰傕傜偭偨丅僇儊儔偺儗儞僘忋壓偵儅僗僉儞僌偟偰柍棟傗傝僔僱僗僐偵偟丄偍抧憼偝傫偲栤摎偡傞摗尨復偺僷乕僩偑廏堩偩偭偨丅
側傑傜丗
丂偙傟偼偁傞応強偵廤崌偟丄慡堳偑俉儈儕僇儊儔傪帩偭偰丄乽偄偭偣偺偣乿偱僼傿儖儉傪夞偟巒傔丄偦偺傑傑俁暘娫夞偟愗偭偰偟傑偆丄偲偄偆僐儞僙僾僩丅
丂僗僞乕僩偺帪揰偱堦弿偵偄傟偽丄偁偲偼偳傫側摦偒曽傪偟偰傕寢峔丅傑偭偨偔摨堦帪娫偵丄偆偛傔偔懡悢偺僇儊儔偺栚偑丄偳傫側岝宨傪偲傜偊傞偐丄偲偄偆偙偲偑慱偄偩丅忢乆乽俁暘偺塮夋偼俁暘偱嶣傟傞乿偲尵偄挘偭偰棃偨偺偩偑丄偙傟偼寢壥揑偵偼俁暘偺嶣塭帪娫偱丄嵟挿50暘偺塮夋偑抋惗偟偨丅乽嵟挿乿偲偄偆偺偼丄嶲壛幰慡堳偺嶣偭偨僼傿儖儉傪忋塮偡傟偽亀側傑傜侾亁偺応崌丄嵟戝偱50暘偲偄偆偙偲偱丄忋塮夛偺僾儘僌儔儉偵崌傢偣偰丄壗恖偐傪乽晄壜乿偲偟偰嶍偭偨傝偡傞偺偱帪娫偑妋掕偟偰偄側偄偲偄偆傢偗側偺偩丅
偩偼傫丗
乽慡崙摨帪懡敪僎儕儔曽幃乿偲柤偯偗偨偺偩偑丄偙傟偼寛傔傜傟偨擔偵丄偍拫偺俶俫俲偺帪曬偐傜20昩傎偳夋柺傪嶣偭偰丄偦偺傑傑俁暘娫僼傿儖儉傪夞偟愗傝側偝偄偲偄偆僷僞乕儞丅擔帪偩偗傪嫟桳偟丄嬻娫揑側峀偑傝傪帩偨偣偨帋傒丅
丂尰嵼偱偼塮憸幚廗偼偍媥傒拞丅亀俁帪偵廤傑偭偰亁傗亀捛搲僄僋僞僋儘乕儉亁側偳丄偄傢備傞廤崌塮夋偑偦偺屻丄偄偔偮偐尰傟偨偨傔丄敪揥揑夝徚偲徧偟偰偄傞偺偩偑丄傑偨怴偨側僐儞僙僾僩傪峫埬偟偰丄嵞奐偟偨偄偲峫偊偰偄傞丅
丂偲偙傠偱偦傟偧傟偺嶌愴柤偩偑丄偲偔偵怺偄堄枴偼側偔丄偡傋偰杒奀摴曽尵丅乽側傑傜乿偼乽偲偭偰傕乿偺堄丄乽偑傓偤乿偼杮摉偼乽偑傫偤乿偲敪壒偟偰乽偆偵乿偺堄丄乽偩偼傫乿偼乽偩偼傫偙偔偱側偄乿偲偄偆傆偆偵巊偭偰乽傢偑傑傑乿偺堄丄偩偦偆偩丅偙傟偼杒奀摴弌恎偺恄壀椔偐傜堷偒弌偟偨傕偺側偺偱丄忋愳抧曽偩偗偺傕偺偐傕偟傟側偄丅

側傑傜侾
NAMARA 1
侾俋俉俉擭丄俁侽暘乣俆侽暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗嶥杫傏傛傛傫揤崙乽塮憸偺婄柺僔儍儚乕乿乮嶥杫丒僀儊乕僕僈儗儕僆乯
嶲壛幰丗墍巕壏丂幍旜懢壚巎丂楅栘復峗丂戝愳屗梞夘丂懌棫惌揟丂嬥巕忎抝
丂丂丂丂壨惣岹旤丂帥杮榓惓丂帥杮宐巕丂嶳嶈姴晇丂彫栰岾惗丂彫岥帊巕丂抾暯帪晇乵夝愢乶
丂僐儞僙僾僩偵偮偄偰偼亀偑傓偤侾亁傪嶲徠偺偙偲丅廤崌偼抮戃墂惣岥丅懌棫惌揟偼偁傜偐偠傔俀恖偺栶幰傪巇崬傫偱僪僞僶僞僪儔儅傪揥奐丅彫岥帊巕偼壴偱忺偭偨儘乕儔乕僗働乕僩偵僇儊儔傪屌掕偟偰揮偑偟偨丅嶳嶈偲帥杮恊巕偼俁偮偺僇儊儔偲恖暔偺埵抲娭學偑岎嶖偟偰偦偙偦偙偍傕偟傠偄丅

偑傓偤俀
GAMUZE 2
侾俋俉俉擭丄栺俁侽暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗擫栭乧嶳嶈姴晇嶌昳廤乮搶嫗丒僀儊乕僕僼僅乕儔儉乯
嶲壛幰丗庰堜抦旻丂愇堜廏恖丂嶳嶈姴晇丂尨払栫丂暯栰彑擵丂幍旜懢壚巎丂恄壀椔
丂丂丂丂徏堜僄儕僙丂娾熀嵤巕丂楅栘戩帰丂彫嶁堜揙丂彫愳抭巕
乵夝愢乶
丂怴廻彫揷媫僨僷乕僩偺壆忋偵廤崌偟丄怴廻壧晳婈挰傪撍偒敳偗傞僐乕僗傪愝掕偟偨丅暯栰偼斵偺塮夋亀棆嫑亁偺庡墘幰丄悪嶳惓峅傪巊偭偰嶣傝丄愇堜廏恖偼岝傊偺偙偩傢傝傪尒偣傞丅傑偨幍旜偼側傫偲僒僢僋僗憈幰丄惣撪揙巵傪楢傟偰偒偰丄僸儞僔儏僋傪攦偄側偑傜奨偱悂偐偣傑偔偭偨丅側偍丄偙偺帪偺壆忋偱偺嶲壛幰偺條巕偑亀偁偄偨偄亁偱尒傜傟傞丅寢壥揑偵堦擔偱俀杮偺嶌昳偑偱偒偰偟傑偭偨傢偗偩丅

偠傚偭傄傫
JYOPPIN
侾俋俉俉擭丄俁暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗僷乕僜僫儖僼僅乕僇僗88乮暉壀丒暉壀導棫旤弍娰乯
乵夝愢乶
丂僞僀僩儖偼杒奀摴曎偱乽尞乿偺偙偲丅亀棨楬偼乣亁亀揇偺乣亁亀偆傑偆偍亁亀嬌惎亁偵楢側傞儅僀僋傪巊偭偨嶌昳丅晹壆傪旘傃弌偟偰梀傫偱偄傞巕偳傕偨偪偵廝偄偐偐傞偑丄儅僀僋偼彮彈偵扗傢傟偰偟傑偆丅儅僀僋偑抝崻偺徾挜偩偲偡傟偽丄嵟屻偵儅僀僋傪偔傢偊傞偺偼帺屓僼僃儔亊亊偐丠

偩偼傫俀
DAHAN 2
侾俋俉俉擭丄栺侾俆暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗擫栭乧嶳嶈姴晇嶌昳廤乮搶嫗丒僀儊乕僕僼僅乕儔儉乯
嶲壛幰丗媑梇岶婭乮杒奀摴乯丂嶳嶈姴晇乮搶嫗乯丂戝愳屗梞夘乮搶嫗乯
丂丂丂丂揷懞戱乮搶嫗乯丂媨揷桋巕仌暉娫椙晇乮暉壀乯
乵夝愢乶
丂嶲壛幰偼俆恖偲彮側偐偭偨偑丄杒奀摴偺媑梇孨偲嬨廈偺媨揷偝傫暉娫偝傫偑嶲壛偟偰偔傟偨偍偐偘偱嫍棧揑側暆偑峀偑偭偨丅側偤偐俆恖偑俆恖偲傕偺傫傃傝偲偟偨暤埻婥傪忴偟弌偟偰偄傞丅側偍亀偩偼傫侾亁偼側偄丅嶌愴傪寛峴偼偟偨偑丄儚僞僔偼嶣塭偵幐攕丅嶲壛幰傕彮側偐偭偨偨傔丄晄惉棫偲偟偨丅

偁偄偨偄
AITAI
侾俋俉俉擭丄侾侾暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗僯儏乕僀儊乕僕愰尵乮搶嫗丒僀儊乕僕僼僅乕儔儉乯
丂壒妝丗彑堜桽擇乮僨僼僅儖儊乯
乵夝愢乶
丂乽夛偄偨偄乿偲乽柰枋乮塤偺棳傟傞偝傑丄偁傞偄偼儗儞僘偺偙偲乯乿傪偐偗偨僞僀僩儖丅婜尷愗傟屻丄弉惉10擭傪宱偨僼傿儖儉傪巊偭偰偺堦庬偺僼僃僀僋嶌昳丅偗傟偳傕搑拞偵憓擖偝傟傞乽扤偺傕偺偐暘偐傜側偄僼傿儖儉乿偼杮摉偺偙偲偱偡丅僼傿儖儉偱側偔偰偼泂傓偙偲偑偱偒側偄惗偒偨暔岅偲偄偆偙偲傪丄偙偙偐傜峫偊巒傔偨乮尰嵼傕峫偊拞乯丅
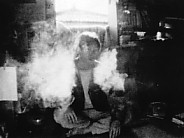
墲暅II
Filmletter仛Oufuku II
侾俋俉俉擭丄俋侽暘丄俉mm丄僇儔乕
弶岞奐丗俥俼俤俙俲俷倀俿丂俿俫俤俙俿俤俼乮嫗搒丒帺慠摪乯
僾儘僨儏乕僗丗惓栘婎
乵夝愢乶
丂嶳揷桬抝偝傫偲偺墲暅塮憸彂娙偺戞俀抏丅崱夞偼嵟弶偐傜壒乮壒妝偁傞偄偼僫儗乕僔儑儞乯傪晅偗丄傑偨慜夞偼側傫偲側偔姷椺偵側偭偨俁暘傪偄偆榞傕偼偢偟偰庢傝慻傫偩丅偦偺寢壥丄堦夞暘偺検偑懡偔側傝丄寢壥揑偵90暘偲偄偆戝嶌偵側偭偰偟傑偭偨丅嶣塭婜娫偼1986擭弔偐傜1988擭枛傑偱偺栺俀擭敿丅儚僞僔偑愭峌偱俆墲暅偟偨偺偱丄儁乕僗偲偟偰偼敿擭偵堦墲暅丅岅傝傗壒妝偑擖傞偙偲偱丄庤巻偭傐偔側傝丄寢壥揑偵偼亀厽亁偱偺偍屳偄偺帒幙偺懳棫偐傜曄傢偭偰丄梈崌傪傔偞偟偨傛偆側僯儏傾儞僗偑慜柺偵弌偨丅嵟屻偺曽偱丄夋柺偵偼弌側偄偑丄柀扟柌媑偝傫偑朣偔側傝丄偦偺偨傔偵傗傗埫偄姶偠偺嶌昳偵側偭偰偟傑偭偨丅