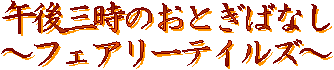
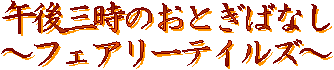
海洋堂フェアリーテイルズフィギュアコレクション全9種
Figure Producted by KAIYODO / Presented by HORIKO
ひとつひとつ精巧な作りをしていて、眺めているとそれぞれのストーリーが蘇ってくるようです。また、解説書の内容がストーリーのあらすじに留まらず、あらたな関心を引き出させるような書き方がなされているところがとても気に入ったので一部省略して載せてみました。お時間がありましたら読んでみてください。
| 01.白雪姫 〜Snow White | 02.ブレーメンの音楽師 〜The Bremen Town Musicians | 03.赤ずきん 〜Little Red Riding Hood |
|
|
|
|
|
その美しさのあまり、母親の嫉妬にあい、殺されそうになった白雪姫。森の奥で七人の小人たちのもとにかくまわれますが、母親は執拗に白雪姫の行方を追い求めます。…中略…それにしても、「鏡よ、鏡、この国で一番美しいのはだあれ?」という呼びかけは、不思議に心に迫ります。「シンデレラ」とともに継母物語の典型のように思われているこの物語ですが、初版では実の母親という設定になっており、それが本来の形であったと思われます。母と娘の美しさをめぐっての闘い、それは時代を超えた究極のテーマではないでしょうか。 |
年老いてそれまでのように働くことができず、飼い主に見捨てられそうになったロバ、音楽隊に雇ってもらおうとブレーメンを目指します。その道すがら、同じ境遇のイヌ、ネコ、オンドリと出会い、仲間が増えていくところは、日本の昔話「桃太郎」を思わせます。そして旅の途中、鬼退治ならぬ泥棒たちを四匹の協力で撃退し、そこを自分たちの終の住処とするのです。結局はブレーメンの町に着くことはなかったロバたちですが、今もブレーメン市庁の舎横の広場には、銅像になった四匹の動物たちが、中の良い姿を見せています。 |
…前略…さて、一般に知られているグリム童話の赤ずきんと違って、それより百年以上も前に書かれたフランスのペロー童話には、お話の後半部分がありません。つまり、赤ずきんはおおかみに食べられて、それでおしまいなのです。そして、お話のあとに、おおかみにはくれぐれも気を付けようという「若い娘さん」たちへの「教訓」がつけられています。 あなたは、グリムとペロー、どちらの赤ずきんがお好みでしょうか? |
|
04.長靴をはいた猫 〜Puss in Boots |
05.ライオンとネズミ 〜The Lion & the Mouse | 06.アリとキリギリス 〜The Ant & the Grasshopper |
|
|
||
|
…長男が粉ひき小屋を、次男はロバを、そして三番目の息子がもらいうけたのは猫一匹でした。一番の貧乏くじを引いたかに見えた三男に猫は長靴を作ってくれと頼みます。そして長靴をはいた猫の見事な計略と実行力で、三男は貴族の地位を手に入れることになるのです。…略…ちょっとのび太くんとドラえもんの関係を思い出しませんか。ところで、ヨーロッパでは古来奴隷の身分の者は靴をはくことを禁じられていたといいます。猫が三男に長靴を求めたのは、奴隷としてではなく、参謀役として三男の人生に関わることを意思表示したのだと解釈できるのではないでしょうか。 |
捕まえたネズミを食べようとすると、ネズミが懸命に命乞いをします。ここで助けてくれたら、必ずいつかたっぷりと恩返しをするからというのです。ばかばかしくてネズミを放してやったライオンですが、それからほどなくして、今度はライオンが狩人に捕らえられ、しばりつけられてしまいます。そこにやってきたネズミ、「あなたはあの時笑ったけど、どんな小さな生き物だって恩を忘れることはありません」と、縄を噛み切ってくれます。…略…ライオンはイソップ童話にしばしば登場してきますが、それはまさに強いものの代表という役柄。しかし、この話は、さすがの百獣の王も「反省」という一幕です。 |
…もっともポピュラーな話なのですが、原話では「セミとアリ」となっています。セミをしらないドイツ語圏にこの話が流布された時、夏に鳴く虫としてなじみのあるキリギリスに替えられたもののようです…子ども向けの本では、アリがキリギリスに同情して食べ物を分けてあげるというふうになっているものもありますが、原話でのアリの言葉は「夏の間歌っていたのなら、今度は踊っていたら」というすこぶるシビアなもの。自業自得といってしまえばそれまでですが、アリの対応がいささか冷たすぎると思うのは、現代人の甘さでしょうか。イソップは奴隷身分だったと伝えられており、働かないものにはがまんならなかったのかも知れません。 |
| 07.親指姫 〜Thumbelina | 08.人魚姫 〜The Little Mermaid | 09.王様の耳はロバの耳 〜King Has Donkey's Ears |
| 子どもがほしい女の人が、魔法使いのおばあさんからもらった大麦の種を植えると、チチューリップの花が咲き、その中から親指姫が生まれます。子どもがほしい親がとても小さな体の子を授かるということでは、グリム童話の「親指小僧」や日本の「一寸法師」を思わせますが、ここでは母親が「シングルマザー」であることが注目されます。…童話作家としての名声を確立しながらも、生涯結婚をせず、自分の家を持つこともなかったアンデルセンのいきざまが、親指姫の旅に投影されているのかもしれません。 | …悲劇的に彩られたドラマですが、しかしそれは誰かが悪をなした結果ということではありません。人魚姫にその美しい声と引き換えに、人間に変身する薬を与えた海の魔女はいかにも悪玉のイメージですが、それとても人魚姫から願ったこと。結局は初めて海の上に出たとき、人間の王子に恋をしてしまったことが、すべての始まりだったのでしょう。まさに命をかけて愛した王子に、それを伝えるすべがない人魚姫の姿に、生涯女性に対して消極的で失恋を繰り返した作者アンデルセンの姿が重なります。 | …なんと王様の耳がロバの耳そっくりの形をしていたのです。ついにこらえきれず…「王様の耳はロバの耳!」と叫び続ける床屋の姿は、こっけいでもあり、なにやら身につまされるようでもあります。この物語は、もともとはギリシャ神話の中のミダス王(手にさわるものをすべて金に変えるよう神に願った話も有名)にまつわる挿話の一つです。それがまるで民間に伝わる昔話のように広がったのは、「秘密」をもつことの苦しさや、いくら隠しても結局は発覚してしまうというほろ苦い事実を、この物語が巧みに言い当てているからではないでしょうか。 |