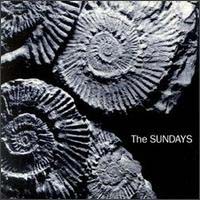 The Sundays / Reading, Writing and Arithmetic (1990)
The Sundays / Reading, Writing and Arithmetic (1990) The Sundays / Reading, Writing and Arithmetic (1990)
| 『 天使のささやき 』 | |
|
|
サンデイズのこのファースト・アルバム「天使のささやき(原題は『読み、書き、そろばん』?)」は、いろいろな意味で想い出深い作品。 アルバムの中に収められ、シングル曲にもなった「Here's Where The Story Ends(邦題は『物語の終りに』だったと思う)を初めて聴いたのが高校3年の時。卒業する少し前、90年代に入ってすぐのことで、開局してまもないJ-Waveでだった。 アコースティックなギターに優しいメロディ、そしてなんといってもその澄んだ歌声に魅了され、曲のハイライトになる後半部分では、まさにその声こそが、圧倒的な存在感を持っていた。 すっかり心を奪われてしまった、まではよかったのだが、なにぶん、誰の、何という歌か分らなかった。 その頃、「03」という雑誌があって、創刊したばかりだったが、ロンドンの音楽特集をした号が良くて(確か第3号)、それ以来ずっと購入していた。パラパラとページをめくっていると、音楽コーナーで新人バンドの紹介をしていて、その記事に何かしらピンとくるものがあった。サンデイズという、ラフ・トレードから出たギター・バンド(つまりあのスミスと同じ)というだけでも、可能性にかけてみるには十分だったが、天使のような歌声と形容されていたし、小さな写真に写っているヴォーカルの女性の、すっと射すくめるような瞳が魅力的だった。 そんなわけで、たぶんあの歌とこのバンドは一緒だろうと予想して、市街地のはずれの輸入盤店に買いにいった。 その輸入盤店である「Heat Wave」は、地元では数少ない輸入盤専門店で、マンションの一室を店舗にしていた。狭いしレコード中心でもあったので、お客は多いということはなかったが、ちょっと通好みを気取りたい少年にとってはうってつけのところだった。また実際、インディー・レーベルのレコードは、そこでしか手に入らなかった。 ほどなく、サンデイズのアルバムが見つかった。ジャケットを見たとき、予想は確信に変わった。その静かで印象的な感覚は、往年のスミスのシングル・ジャケットを彷彿とさせた。 家に帰って聴いてみた。やはり大当たりだった。A面の2曲目に入っていた。そして驚くべきことに、他のどの曲も素晴らしかった。 ナチュラルなギター中心の楽曲に文学的な歌詞、ささやきから高いところまですっと伸びるヴォイス。内省的でありながら、すごく研ぎ澄まされていた。 当時はちょうどストーン・ローゼズのファースト・アルバムが出て、シーンがひっくり返るような大騒ぎの時だった。暗く内向的で停滞であったとして、80年代の主要なバンドや音楽が、大批判を浴びている時だった。だからともすればサンデイズの音の在り方は、批判を浴びかねないものだった。 しかしシーンもリスナーも、サンデイズを好意的に受け入れたように思う。それは、あまりに内省さを突き詰めた結果、クオリティがある高みにまで達したこと、そして何よりも、ポップ・ソングとしてのメロディの良さと、魅力的な声が、内省さを吹き飛ばしてしまっていたからのように思う。 僕はこのアルバムを何度も聴いた。
それからずいぶんと時が流れた。高校を卒業し大学に全部落ち、次の年受かって東京で一人暮らしを始めた。長い休みに実家に帰って久し振りに「Heat Wave」に行ってみると、店はもうなかった。レコードはほとんど見かけなくなり、いつのまにか「03」は廃刊した。音楽シーンの中心はグランジに移っており、その後ブリット・ポップがやってきた。 僕はレコードだったサンデイズのアルバムを、CDで買い直した。その後彼らはどんどん音が内向的になっていき、静けさだけが目立つようになり、あのポップさと内向性の絶妙なバランスは見られなくなってしまった。今ではもう、ほとんどシーンで目立った活躍はしていない。 ナイーヴさゆえ、世界に初めて向き合ったときはパーンとはじけて内側から飛び出し、あのようなポップ性をもつに至ったのだろうか。そう思うと、ファースト・アルバムのあの瑞々しさは痛ましくもあり、逆に今のような音の世界こそ、彼らの場所なのかもしれない。「天使のささやき」は、少しの間地上に降りてきて、舞ってみただけなのかもしれない。
|