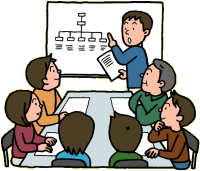|
グループ別情報交換会会議録 テーマ 「防災について」 H23,6,27
|
|
4グループに分かれて、防災に関する情報交換を行いました。
普段はなかなか見えない他事業所の実情や課題が分かり、有意義な情報の共有ができました。明らかになった課題を整理して、解決のための方策を検討していきたいと思います。 Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ
|
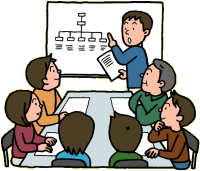
|
|
Aグループ
入所施設では24時間365日職員が常駐しているが、夜間帯等で災害が発生した場合の対応は難しい所が
たくさんある。
夜間は(21時以降)職員が一人体制になるため、もし災害が起きた時には30名近い利用者へ対応しなけれ
ばならなくなる事から一人での対応は厳しいものがある。
また、就寝してしまうと(睡眠薬等を服用)、朝までしっかりと眠っている人も多く、夜間の災害時にはみんなが
起きられるかが心配。
2年前に日中活動の場を開設。災害時には地域で暮らしている障害者も受け入れる事をイメージして開設。
また地域住民に開放する事も可能。
保育園の場合、子どもを預かっている時間帯や通園時等と時間帯によって対応を考えなければならなく、
保護者との連絡方法や乳児と幼児の対応が違ってくる等と様々な場面を想定しなければならない。
備蓄用品について
・ 備蓄は3日分のみで、施設利用者・職員分しかない状態。3日分以上の備蓄は必要。
・ 食料品(保存食)に関して、賞味期限が3年未満のものが多いので、年に1回は保存食を食べて、新しい
ものに換えている。
・
賞味期限が過ぎた飲料水は災害時にトイレの水用として残している。
・ 今回の震災で手回し式充電ラジオを購入。
薬について、利用者には「お薬手帳」は必ず保管しておくようにと言っている。実際に東日本大震災では
「お薬手帳」を持っている事でちゃんと薬が処方されたと聞いた。
避難訓練について
・ 3〜4ヶ月に1回行なっている。年に3回開催し地震時・火災時の対応、ビデオ学習を行なっている。
・
避難訓練を伝えても、利用者になかなか伝わらないことがあるのでビデオ学習をおこなっている。
・
施設前の道路は車の通行量が多い為、実際の災害時には、利用者が慌てて道路に飛び出すのではないか
と心配で気をつけなければならない。
避難場所での生活で周りの理解が得られるのか?
避難場所は公園をイメージしていたが、消防署に確認したところ、公園は一時避難場所であり、公園にいても
援助物資等は届かないと説明を受けた。
地域の人たちに施設がある事を知ってもらう事が大切で、施設のイベントがある時には町内会長を呼んでい
る。
|
|
|
|
Bグループ
■現在おこなっている対策
年間通して6回の避難訓練を行っている。秋におこなう訓練は5時から9時の間で実際の職員数で、男女職員
2名ずつ計4名で行っている。他の職員はいない想定で見ているだけ。またいろんな場所での訓練を行って
いる。(喫茶店。グループホーム)その他でAEDを4箇所に設置している。
消防署の方をよんで、利用者対象の講義と職員愛称の講義を行い、地域の防災訓練にも参加している。
地域の方と一緒に行う訓練にも利用者が積極的に参加することで、顔を知ってもらっている。実際に災害が
起こったときは助け合えるのではないか。
地域の消防団の手伝いとして、職員をだすこともある。
年間を通して4回の避難訓練を行っている。
テレビの固定や、居室の危険な箇所を点検し、荷物が落下しても危険のないような収納に変更した。
食料の備蓄や、防災訓練を行っているが、実際に避難所まで行ったことがない。
園として子どもの人数の備蓄だけだが、学院として、大学の食堂など、受け入れ体制を整えている。
交通の便が悪いところに施設があり、地域の人たちにしってもらうために、学区の民生委員さんや区役所の
方や保護者との交流の場をつくることで、顔を覚えてもらえるようにしている。
■不安点
精神障害の方の特性を考えると、震災が起きたときよりも、さらに日にちが経つにつれて、どのようになって
いくのか予想がつかず不安。
二次災害が起こると、こどもが落ち着かなくなるのではないかと心配で、どうやって落ち着かせれば良いのか
わからない。
水害が起こると道が遮断されてしまい孤立してしまうので心配。
■被災地に行って見えてきた問題点と対策案
お薬手帳が津波で流されてしまい、今までどのような薬をどれだけ飲んでいたのかがわからなくなって困って
いたとの話しがあった。精神の方は特に、薬の量によって状態も変わってくるので、実際に自分たちの地域で
起こった時を想定し、防災訓練のときに、お薬手帳を持参してもらうようにしたいと考えている。また、コピーを
とらせてもらい、作業所にも保管できるようにしようと思っている。
被災後1週間で、薬も何とか物資として届いているが、実際は市販薬が多く、てんかん薬や精神薬など一般
的でないものに関しては難しいと思う。
被災地にいって、災害ボランティアセンターの立ち上げを行ってきた。
福祉避難所は定員いっぱいだったのに、避難所で生活している様子はなかったため、家族が親戚などを
頼ってどうにか自分たちで生活しているのではないか。
福祉避難所に入らないといけない人がどれだけいて、どのような支援が必要かなどを把握しておく必要が
あるのではないか。
避難所で生活している人たちのニーズはあまりなく、運営スタッフからのニーズが多く、ボランティアをコーディ
ネートできる人が必要で、中心になって動ける人が必要になってくる。
レスキューストックヤードで被災地にいっているチームは同じ地域に何度も行くため、被災地の方とも信頼
関係ができており、顔を知ってもらえることが重要で、それは地域で生活している方にとっても同じ事がいえる
のではないか、知ってもらう事が本当に大切。
■今後の課題と対策案
守山区だけでなく、長久手や名東区から通園しているこどももいるため、子どもさんの迎えにかかる時間が
かかるため、地域の方との関わりが必要になってくる。また帰宅困難になった場合にも、地域の方の助けが
重要になってくると思う。
障害者の避場所の確保として、福祉避難所が少ない。一般の方と障害者が同じ避難所で生活することが
難しく、施設として地域の受け皿になっていかないといけないと考えている。
子どもは避難訓練を行っているが、保護者とどういった連絡をとるかが課題。
子どものアレルギーなど、知っておかないと対応できない部分もあり、地域の助けが必要なときに、正確に
伝えられないと助けられないので、日ごろから地域の方と関わる機会が必要だと思う。
薬は日ごろから、3日分常備して持ち歩いてもらえると、緊急時にも、どの薬が必要なのかもわかるし、なん
とか補充できるのではないか。
在宅で単身の方が、ヘルパーのいない時間帯に被災されたとき、隣近所の人たちが、助けてくれないと、
困ると思う。学区の民生委員さんがどこまで関わるかが重要になるのではないかと思う。
単身のかたは、身体障害なら自分では避難できないし、精神や知的なら、その場から動けないのではないか
と思う。誰がどうやって安否確認などをするのかを決めておく必要があると思う。
在宅にいると、避難所よりも情報が入ってこないし、近所の人が知らせてくれる環境は田舎より、都会の方が
難しいと思う。
県外より避難をしている人達のニーズにこたえるのも、自分たちの役目だと思う。
復興のための費用がかかり、結局止めてしまう事業所もでてくるのではないか、必要な介助を受けられない
状況を防がなければならないと思う。
身体障害や高齢者よりも知的障害や精神障害、発達障害をもっている方の避難所をつくるのが難しいと
いわれている。
守山区は3ヶ所福祉避難所があるが、3ヶ所合わせて定員120名で、120名以外の方の避難所の確保が問題
になってくる。環境をなるべく変えないことが良いといわれていることを考えると、擁護学校も福祉避難所として
受け入れてもらえないか、現在検討中。
災害ボランティアセンターを実際に立ち上げることになると予想される。核となるセンターが情報をいかに早く
正確に伝え、指示がだせるかが重要になる。
実際に守山区で災害ボランティアセンターを立ち上げるためのシュミレーションをした方が良いと思う。
夜間の安否確認など、どこに逃げるのか、実際にここなら大丈夫という場所を決めておく必要があるのでは
ないか。
被災したら、まずなにを把握しなければいけないのか、利用者の安否確認なのか、避難所の運営なのか。
誰が何をするのかなど、確認しておく必要がある。
|
|
|
|
Cグループ
■各事業所の現況と取り組みについて
入所施設の機能を活かして有事の際には開放していく必要性を感じている。
現在、福祉避難所の指定を受けている。しかし、いざとなった時にどのように動けばいいのかというマニュアル
がない。
養護学校だが、1食分の備蓄しかないことや自家発電機の能力が低いことが課題。地域への貢献という面
では、避難所としての受け入れ体制も課題である。
重複障害を持った人たちが集まる通所施設。聴覚障害者の場合、情報がなかなか入手できない。今回の
災害でも実際に情報が入らずに被害に遭った人もいた。地域の皆さんの協力が大切だと考えている。
行政窓口はどうしても受身的な業務になりがちで現場の声が届きにくい。その意味で協議会のような場は
大変重要だと考えている。
精神科の病院で閉鎖病棟や医療観察法で重大な犯罪行為を犯した患者の収容施設(34床)もある。今回の
大震災では医療スタッフを派遣し心のケアにあたった。災害時は精神科医療の専門性を活かした地域貢献を
していきたい。
訪問介護事業所だが、移動時の利用者とスタッフの安全を心がけている。
240名の子どもがいる保育園。小さな子どもだと避難所へ入ることは難しいと考えている。また、周辺住民が
園に集まって来た時の体制作りも課題である。
精神障害者の作業所を運営している。利用者のうち1/3が単身者で、いざという時の連絡体制や不安の
解消といった部分が未協議。家族単位での支援や他事業所との連携の必要性も痛感している。
就労支援施設。外での作業時の対応や帰宅困難者への対応、地域との連携が課題。
相談支援事業の中で集まった個人情報の活用の仕方。取り扱いは慎重にしなければならないが、いざと
いう時に役立てられるよう紙ベースでの保管が大切だと考えている。
■相互質疑と応答
重複障害の人への情報の伝え方はどうしているのか?
絵や写真で伝えている。避難所でも目で見せる情報提供が必要。
閉鎖病棟の避難訓練は行っているのか?また、震災の影響で心的ダメージを負った入院患者はいたか?
訓練は年に1回実施している。心的ダメージの点では特に大きな影響はない。
車椅子の人の避難はどのようにしていくのか?
特にマンションのような所でエレベーターが動かない場合だと階段を使う人は大変。車椅子のままだと4人は
必要になる。どうしても近隣の人の手助けが必要になる。また、避難所でのトイレの問題など環境的な面での
支援も必要。
重度の人への人数的な対応は?
マンツーマンでの対応が必要。中には二人で介助する人もいる。
入所のような施設で夜間などの対応はどうしているのか?
夜間想定の訓練はしているが、あくまでも居室数を限定したシュミレーション的なものしかできていない。
優先順位をつけて対応するしかないが、幸い消防署も近く、ボタン一つでつながる緊急通報システムもある
ので、それに頼るしかない。
火災と地震では指示が違うこともある。逃げるのか、待機するのかで違ってくる。
守山区に二つしかないという福祉避難所の機能とは?
マニュアルが整備されていないのが現状。施設が作るのか、行政が作るのか、また、指揮命令系統はどこが
担い、誰がコーディネートするのか、ということが未整備。
制度としては新しく周知されていないのが現状。最低学区に1つは必要ではないかと思う。
豊田市では福祉避難所に看護師を派遣するシステムがあり、学校の送迎バスもそこへ行くことがマニュアル
に載っているようである。
薬の確保などはどのようにしているのか?
学校の場合、必要分は持参しているが、1日で帰れない場合、保管できる設備が必要になる。
精神科の薬も重要だが、医師も初対面での処方は難しいし、複数種類の薬を飲んでいる人もいると思うので、
お薬手帳を携帯しているとよい。
福祉避難所にいろんな障害を持った人が集まっても、なかなか落ち着けない場合もある。普段通い慣れた
施設で過ごせればその方がよいが、その場合、行政からの情報漏れが心配になる。実際に避難所よりも
自宅を選んだ人に、物資が届かなかったということがあった。
ヘルパーの場合、各家庭でケアに入っている時は不安が大きい。利用者との防災に関する話し合いが
必要だと思う。
多くのヘルパーを利用している人は、ヘルパーが被災すると困ってしまう。連絡手段も使えない場合、その
支援体制を維持する必要がある。
■今回、学んだことや今後の抱負について
福祉避難所の存在。
福祉避難所のマニュアル整備の必要性。
薬手帳の作成と携帯。
長期間の受け入れ体制と連携の必要性。
施設の職員だけでなく、地域との連携が大切であること。
避難訓練や炊き出し訓練などを近隣住民と協力して行っている地域もある。
重度の人の支援体制の必要性。
持ち出し品をまとめておくこと。
写真等で情報を分かりやすく伝えること。
|
|
|
|
Dグループ
被災地のケアホームの情報を聞くと、世話人一人で24時間利用者の世話をしている状況になっており、事業
所自体で手一杯の状態にある。今一番ほしいのはマンパワー。
設立7年目の保育園 幼児のため自分では歩けない子もいるためどのように避難すればいいのか。実際に
どのようにすればいいのか分からないので皆さんの意見を参考にしたい。
被災地の保育園で保育していた子供が一人も亡くなっていないという事実がある。やはり常日頃からの訓練と
臨機応変な対応が大切であることをあらためて認識した。
建物の耐震診断や備蓄品の整備、家具等の転倒防止の方法などを確認する必要を感じている。N幼稚園は
避難所に指定されているが、市全体の保育園でマニュアルの見直しを行っているところである。
A型就労支援で今年から事業開始。現在10名の利用者がおり、高蔵寺や日進から公共交通機関で通勤して
いるため災害が発生した時、どのタイミングで返せばいいのか。また、知的障害者の場合、イレギュラーの
事態にどのように対処すればいいのか今後の課題となっている。
大人の日中部門を担当している。東日本の震災を受けて事業所内でも対応について協議している。逃げる
ことが出来なかった場合はどうするのか。親が迎えに来られない場合に、事業所としてどの位持ちこたえる
ことが出来るのか。
特別支援学級の担任をしている。突然、避難訓練を行うとパニックになってしまう。自閉症の子供にとっては
その時その時が、最初の出来事なので予め避難訓練があることを伝えておいてもパニックを起こしてしまう。
訓練一つ行うにしても課題が多い。
事業所が八剣から大森に転居し、建物も2階建ての建物になった。階段の避難訓練をどのように行うか検討
している。今回の東日本大震災の揺れでは、利用者よりもむしろ職員がパニックになってしまった。
当施設では、消防署の職員に実際来てもらい訓練を行っている。消防署の車や職員を実際に見ることで、
災害時に助けに来てくれる人との認識を持ってもらうために行っている。
実際に近い訓練を行いたいと思っているが、サイレンだけでパニックになってしまう園児もいると思われる
ので、一般的な訓練しか行っていない。実際に地震が起こった場合は、職員もパニックになってしまう可能性
も十分考えられる。
パトカーや消防車、救急車を見せても避難訓練の練習にはならない。特別支援学級の子供たちに地震を
説明しようとしても理解できない場合が多い。
教師になって6年経つが今回の震災で初めて生徒を机の下に避難させた。
居宅介護や児童ディサービスの事業所を行っている。知的障害者は、犯罪を疑われたり、犯罪に巻き込まれ
やすい。
消防署の職員に来てもらい訓練を行っている。バケツリレーや担架・ストレッチャーに乗ることを通して消防
署員が自分たちのことを守ってくれる存在であることを理解してもらう。避難訓練等を行うにあたり、聴覚
過敏の方やプレッシャーに弱い障害者については、配慮したり場合によっては、除外することが必要な場合
もある。
それぞれの職場や自宅にいる利用者の安否確認をどう行うのか今後の課題である。
災害時に利用者が事業所の建物にいない場合は、近くの公園に避難している。近くの公園にもいない場合
は、避難所になっている地域の体育館に避難しているということは予め家族には伝えている。地震だけでなく、
台風や大雨の時の営業をどうするのか。責任者が事業所に出てきて建物の安全確認をするようにしている。
より的確な情報を伝えることが大切。今回の震災から学ぶべきことが多い。横のつながりを作っていくことが
大切。
阪神・淡路大震災の「誰に助け出されましたか?」のアンケートに対し、近所の人60,5%、家族18,9%、
救助隊2,4%となっている結果を聞いて、地域とのつながりが如何に大切かあらためて認識できた。
|