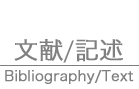|
「作間敏宏『colony』」(1999/9) [集積された時間がスパークする瞬間に立ち会う] 展覧会図録/山下里加(美術ライター)
"ソウル・フード※"、日本語に訳すると「魂の食物」でしょうか。記憶の奥底に刷り込まれた味覚の原風景というべきもの。幼い頃は好きだったのに、大人になるとすっかり忘れていることが多いようです。でも、時折、事故のようにその味にぶつかり、「ああ、これが私のソウル・フードなんだな」と気づくことがあります。…実は、私は、作間敏宏の作品は、"ソウル・フード"ではないか、と妄想しているのです。
なぜ美術展のカタログの序文に食べ物の話が出てくるのか、と怒られそうですね。ごめんなさい。もっと賢そうな、威厳のある文章を書きたかったのですが、結局、私は私の足で立っている場所から言葉を紡いでいくしかできないし、そうでなければ、作間敏宏という美術家と向き合えないでしょうから。もうしばらく私の妄想にお付き合いください。
さて、素材も手法もギリギリまで純化された作間敏宏の作品と、記憶の底にへばりついている食べ物がなぜ結びつくのか。「直観です」と開き直りたいところですが、ここはふんばって言葉に置き換えていきましょう。
作間の作品は、相反するふたつの時間で出来上がっているように思います。ひとつは、〔時間の集積〕。作間の作品には、たっぷり時間が含まれています。扱う素材でも、98年のニューヨークの個展で初登場したガーゼは、95年のリアス・アーク美術館でのワークショップをした時から気になっていたと言います。「colony」シリーズの主題である"名前"との出会いも、5,6年前にベトナム戦争の戦死者の名を刻んだ巨大な石碑を見た時に逆上るそう。その他、アトリエには、まだ作品にはならないけれど何か"力がある"と彼が直観したモノがたんまりあります。作間は、そんな諸々の物を手元に置いて眺めたり、電話帳を毎日めくったりしながら、時間をかけて身体の中で発酵させています。
実際の制作でも、作間は〔時間を集積〕させる手法を選んでいます。木札に名前を書いたり、ガーゼに名札を縫い付けたりすること自体は、日常にあふれている作業です。主婦の台所仕事に近いものかもしれません。誰にでも出来る作業をあきれるほど繰り返すことで、初めて作家の意図が目に見える形になっていきます。
でもまぁ、気になる素材を手元に置いておくのは、もの作り達には当たり前のことでしょう。単純な作業を繰り返す手法も、それほど珍しくありません。これだけなら、美味しい日常食であっても、"ソウル・フード"にはなりません。
ところが、完成した作品空間が観客を迎え入れた時、〔時間の集積〕がパンッと弾けるような、〔時間がスパークする〕ような現象が起こるのです。忘れていた"ソウル・フード"にぶちあたった時のように。
"ソウル・フード"は、食したとたん閃光のように幼い頃の記憶が鮮やかによみがえります。過去から現在に至る膨大な時間が圧縮され、全身を駆けめぐる。快感というより、呆然とするしかない一瞬…。
作間の「colony」の空間に足を踏み入れた者も、同じような現象に出くわします。物として見えるのは、4〜5つの漢字が書かれた木札やガーゼだけ。色も形も日常生活にありふれた、なんとも無愛想な代物の集積です。ところが、漢字が人名だと気づいたとたん、脳内にスパークが走ります。姓名という最小の情報から、年齢、職業、名前をつけた親の気持ち、隣の人名や同じ名字との関係、真向きの木札が暗示するこの世の不在者、ガーゼや消毒薬の匂いが喚起させる病や死、誕生……人間にまつわる様々な想像がふくらんでいきます。ハッとして全体を見渡すと、膨大な量の人名が人間となり、生と死に挟まれた人生となり、一挙に押し寄せてきます。言葉で説明すると失速してしまう、凝縮された時間のスパークが次々と身体を貫いていく……。この感覚は、美術作品を見る、鑑賞するというよりは、"食べる"に通じるほどの生々しい身体性を伴っているように思えます。
階段を一段ずつ登っていくような〔時間の集積〕と、その頂上から点のように小さく見える人間の集合体に飛び込むような〔時間がスパークする〕一瞬。作間敏宏の作品には、このふたつの時間が同居している。ひとつの作品空間でもそうですが、彼の仕事の軌跡の中に、既にこのふたつは内包されているようです。作間は、4〜5年間隔で作品の傾向を一変させます。ひとつのテーマにかかっている間、彼は徹底的に思考を突き詰めます。ですが、あらゆる可能性を検討した後は、惰性に入る前に潔く別のテーマに移行します。彼はこれを"ジャンプ"と呼び、「本質的には変わらないが、今までの手法ではあまかった部分をキチンと詰める決意表明のようなもの」と言います。私たち、観客が体感するふたつの時間は、作家の制作に対する姿勢から生まれてくるのでしょう。
最後に、もう一度"ソウル・フード"について。ふつう食べ物は生きていくために身体に取り入れます。では、"ソウル・フード"が最も切実に求められるのはいつか?私が思うに、死に瀕している時です。死に向かう最期の生の時間に、これを食べれば小さな喜怒哀楽を繰り返したどうしようもない人生を受け入れられる予感がするのです。作間敏宏の作品も、生と死が同列に並んでいます。「治癒」シリーズの電球の温かさ、ロマンティックさを削り取り、"人間"に焦点を絞った「colony」シリーズでは、永遠に癒されない死の気配が濃厚になったように思います。でも、それは嫌悪や恐怖を連想させるものではありません。生の最期に"ソウル・フード"を食するように、作間の作品に対時する時、癒されないこともまた、自分の身体の一部なのだと思えてくるのです。
※本来は、黒人家庭で食べられている伝統的な南部料理のこと。
|