新米防災士 「新潟・中越地震ボランティアレポート」
|
−防災士メモ− 防災士とは、「自助、互助、協働を原則として、社会の様々な場で、減災と社会の防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有するものとして認められた人」と定義がされています。 私の場合は2004年5月に資格を取りました。防災士の定義のまず第一番目にある「自助」。災害の時、まず自分の身は自分で守る。それができないとその後に続く「互助」「協働」つまり、人を助ける事はできないのです。 ですから、ボランティアで新潟に入っても余震等で自分が助けてもらう立場になれば迷惑がかかるという事で、その点だけは特に緊張しました。 12月に入ったばかりの中越地域に行きました。最初の地震からおよそ5週間たった小千谷、長岡、川口町をまわりました。 |
1.準備
大きい事は出来ないので、1人1人とふれあう事ができれば、という気持ちでクッキーを焼いて、持っていく準備をしました。
そして、小千谷のボランティアセンターによるボランティアに参加するために、長靴や軍手など。
 |
| ちょっと変わった塩クッキーを作ってみました。 お口に合えば良いのですが・・・。 |
 |
| ラッピングに意外と時間がかかり百個が限界でした。 |
2.被災地へ
 |
| 被害の大きかった小千谷駅前。 まだまだ物々しい雰囲気。 |
 |
 |
| 空き地などにはこういったゴミが集められています。 | |
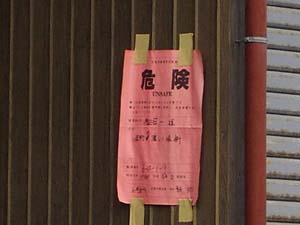 |
| 被害の多かった小千谷市の住宅地。 家屋の調査が進んでおり、 「調査済み」(居住OK) が緑、「要注意」が黄色、 「危険」の貼り紙が赤と 一目で識別できるようになっています。 |
 |
| 自然の猛威に対して私たち人間は本当に微力です。 |
−防災士メモ− 大規模災害の発生直後は、消防、警察、自衛隊などの公的機関による対応には限界があり、発生直後の初動では地域住民が自ら生命を守る事が重要です。 そこで重要な役割を果たすのが、隣り近所で助け合う「自主防災組織」の存在です。阪神・淡路大震災においても、倒壊家屋からの救助や、初期消火も近隣の住民が活躍したと言われます。 そこで都道府県の自主防災組織の結成率を見ると、静岡県が第一位の結成率で97.9%、沖縄が最下位の3.3%、新潟県は下から6番目の19.9%となっていました。(2002年の統計) 今後の結成率の上昇に期待します。 |
3.長岡大手高校の避難所
夕方に着いたので校庭では自衛隊の人たちが自分たちの食事の準備中。
ここの体育館には山古志村の住人の方が多く避難されているそう。中では多くの子供達がお遊び中。人なつこい子供達が多く、陽気に話しかけてくれて会話が弾みますが、話が地震の事になりますと、みんな一様に顔を曇らせます。
元気良く遊んでいましたが、心に受けたショックは相当大きいと感じます。
長岡の中心地なども風評被害で不況に追い討ちをかけられているそう。被災地からの毎日の報道も特異な事実を伝える事は極めて重要ですが、そこだけが大げさにクローズアップしてしまうというデメリットもあるという事を実感。
−防災士メモ− 大規模災害で深刻な被害を受け、精神的に動揺している場合には、正常な判断能力が失われやすく「流言」(事実の確証無しに語られる情報・うわさ)や「風評被害」が発生しやすい。 過去の災害においても流言などにより被災地の混乱にますます拍車がかかったケースがあります。 対策としてはまず、行政や避難所関係者、町内会役員、防災士(も含まれると思 平時、普段からいざというときに信頼できる情報を入手できる手段を確保する事が理想ですね。 |
4.小千谷市市民体育館
中は衛生面に細心の注意を払っているようで、病院のような匂いがしています。
子供専用の遊び部屋などが、開設されています。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 駐車場に設置されているお風呂からの帰り道の方と。 今日もさっぱりしたとの事です。 |
6.川口町仮設住宅開設
主に川口町で家を失った人たちの仮設住宅の入居がこの日から始まりました。
お話を伺ったご夫妻は「とにかくあれから一度も家を見にいけない状況なので、家がどうなっているか心配」「これから2年以上もここで暮らすと思うと・・・」大勢の人たちと同じ空間で寝食をともにする避難所から抜けてきた事で、やれやれ・・・という気持ちの様ですが、先の見えない不安がこちらにも痛いほど伝わってきます。
 |
 |
 |
いま阪神大震災で仮設住宅に住まれている高齢者の孤独死の問題や、PTSDの問題。これからこの地でも重要な課題となっていきます。
政府や自治体の対応をチェックしていくのが、私たちの国民の仕事という事を痛感。
7.小千谷ボランティアセンター
記入、受け付け、マッチング、ナビの順にボランティアをするまでの過程があります。
まずは「ボランティア受付カード」に記入。資格を書く欄などもあり 、医師や看護婦などを数多く必要としているため、ここでも資格社会なんだなという事を実感。
受付にカードを提出し、仕事が来るまで待機。ものの5分で、仕事内容の書いてある「ニーズ票」というファックスが届く。
 |
与えられたのは「図書館にて地震の記事のスクラップ」。掃除や片付けが大部分を占めているボランティア活動なので「こんな仕事もあるんだー」と少々驚きました。
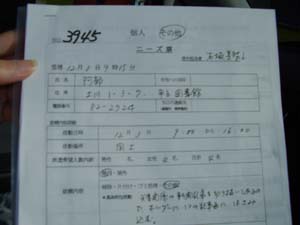 |
仕事が決まったところで次はナビ。目的地までの道のりを、地元の方が航空地図を使って丁寧に教えてくれます。
 |
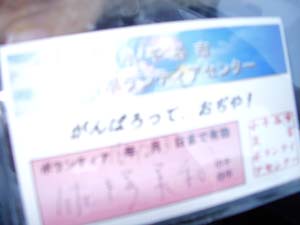 |
名前を書いたカードを首からかけていざ現地へ。
いよいよ現地の図書館へ。職員の方から作業の説明を受けます。作業開始。新潟日報をはじめとする各新聞の中越地震の記事の切り抜き&ファイルへのスクラップ。
このスクラップがこの街に半永久的に残るのだなと思うと、責任感を感じはさみの入れ方や、ファイルのレイアウトにも非常に気を使いますが、作業が進むにつれ要領を得て速くなっていく様です。
 |
時間内に効率良く終わるかがちょっと心配。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
この一か月と少しで本当にいろいろな事があったのだなと・・・。
終了 報告書を記入。
 |
センターへ戻る
 |
ぞくぞくとボランティアから帰ってきた人で活気づきます。
 |
ボランティアを終えた人たちにケンチンうどん?らしきものもふるまわれています。
新潟をあとにして・・・
ボランティアというものにどう関わってよいか解らない、という人はまだまだ多いと思います。
「ボランティアだからこうあるべき」という固定観念に縛られて、勇み足になりがちですが、少しでも何かを協力したいという気持ちがあれば、積極的に自分なりのやり方で手を差しのべる事がまずは大切だなと実感しました。
今回の新潟に関していえば、ボランティアだから、被災地だからといってあまり自粛ムードが強すぎると、今度は街に活気がなくなるという心配もあるのは事実です。人が百人いればボランティアのやり方も百通り、「気持ち」があれば必ず通じるという事を信じて常識の中で活動してはいかがでしょう。
 |
新潟の美味しい郷土料理も健在ですよ。のっ平にジンバソウ、菊の花・・・。心や身体に傷を負った方の一日も早い回復、被災地の復興、活気のある街づくりが進む事を期待しています!!