
 014
014
チャオの英語
チャオの最初の先生は、背が高くすらりとした若い女性で、名前はクロウ先生といった。いかにも優しそうなタイプで、一度父兄の面談であったことがある。丁度、先生が結婚して辞めるという時期だった。チャオが「ミス・クロウと離れるのはいやだ。結婚するならぼくも一緒に行く」としきりに迫ったという。「これには困りましたよ」と先生は嬉しそうに話してくれた。
次の年、1年生のクラスの先生はミセス・テスターという中年の女性だった。この先生は低学年を専門に教えていた。彼女は2人の息子とともに、ミネアポリスの北に住んでいたが、後年、マルティノーという丸々と太ったチャーミングな男性と再婚した。それでもブリムホールで教え続けた。マルティノー先生の話しでは、今ではブリムホール・スクールでの外国人の割合が30%を越えたそうだが、当時は、外国から来ている子供の数は少なく、日本人はチャオと他のクラスにもう1人いるだけだった。クラスの子供たちがチャオにどう対応していたのか、詳しい事はテスター先生との面談でしか分からないが、概して、偏見はなかったようだ。地域のせいかもしれないし、偏見を持たない子供たちかもしれない。低学年が幸したのかもしれない。日本人が小学校の高学年や中学・高校などに編入すれば話しは別だと思う。黒人やアジア人などの有色人種が少なく、クラスにはアジア人の子供はチャオだけで、黒人も男の子が1人いるだけだった。
外国で子供を学校に通わせると、言葉の問題が大変で、子供にも大きな負担がかかる。チャオは幼稚園からスタートしたが、日本で4月から幼稚園の経験があり、いってみれば、幼稚園を2度経験ことになるから、集団生活には慣れていた。最初の3ヶ月は、英語の単語を一つ一つ覚えて行く期間だ。但し、大人と違って、英語を知識として、概念として覚えるのではないから、覚えた単語は100%使うので無駄がない。
3ヶ月目のある夜だったろうか、先に寝かせておいたチャオが寝言をいっている。余り寝言はいわない方だが、この時ははっきりと喋っている。
「おや、英語で寝言をいっているぞ」
パパとママは顔を見合わせた。
「うん、もう大丈夫だ。明日から英語で話すようになるから」
そして、次の日から本当に英語が泉のように湧き出したのだ。丁度、空のタンクに3ヶ月間少しずつ溜めて置いた水が、入り切らなくなってあふれ出たように。容器のタンクが大きくなって行くスピードよりも、入ってくる水の量が速いのだ。それでも、覚えている単語の数といえば120〜150くらなのである。
先ず、動詞は、have, get, give, come, go, do, take, make, put, open, close, like, wantなど20個くらい、名詞が日常つかう言葉ばかり、形容詞・副詞はhot, cold, hungry, angryなど感覚的なものと、pretty, fast, slow, good, badなどの状態を示すものなど、前置詞がinとかatとかforとかonなどの必要最小限の単語だけだ。文章も定型文が殆どで、コミュニケーションをとることが中心で、これだけで意志の相通ができるという見本みたいなものである。英語の語順だけでなく、その発想の違いのために、英語の表現自体が日本で覚える英語と違ってくる。
 言葉の問題をクリアできれば、次に、学校で引っ込み思案にならないためには何が必要か。今は変わったかもしれないが、アメリカの父母は就学前の子供に読み方を教えるということは余りしないようだった。現在のホームスクールなどで母親が子供に勉強を教える場合でも、「学校では他人と競争することばかりだから、うち子には学校へ通わせない」というのが多い。これは今始まった事ではなく、既に、ミネソタ大学などでも、『パス』と『ノット・パス』の2分法でABCなどのグレーディグはしないという方式も選択できた。ところで、算数は日本の子供にとって有利な科目のはずだ。特に教えないのに、チャオは算数がクラスで一番だったから、クラスの全員から注目を集めた。得意な科目を増やせば、自然と自信がついてくる。
言葉の問題をクリアできれば、次に、学校で引っ込み思案にならないためには何が必要か。今は変わったかもしれないが、アメリカの父母は就学前の子供に読み方を教えるということは余りしないようだった。現在のホームスクールなどで母親が子供に勉強を教える場合でも、「学校では他人と競争することばかりだから、うち子には学校へ通わせない」というのが多い。これは今始まった事ではなく、既に、ミネソタ大学などでも、『パス』と『ノット・パス』の2分法でABCなどのグレーディグはしないという方式も選択できた。ところで、算数は日本の子供にとって有利な科目のはずだ。特に教えないのに、チャオは算数がクラスで一番だったから、クラスの全員から注目を集めた。得意な科目を増やせば、自然と自信がついてくる。
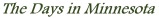
HOME 前頁へ 次頁へ
”遠い夏に想いを”- Click here(ヴィオさんの旅行ブログ) も一読ください。
ミネソタ大学留学のあと、パリ大学の夏期講座に妻が受講するためパリへ飛び、3ヶ月滞在したときの思い出を探してのブログ手記です。