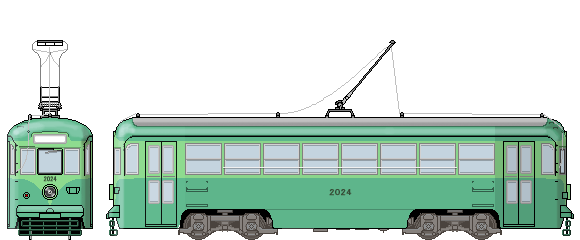
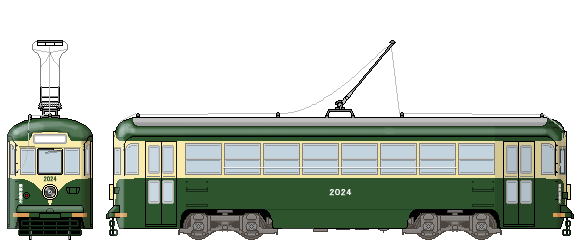
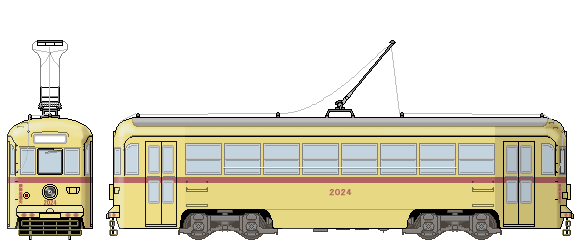
かつて日本最大規模を誇った都電の車両図鑑(モドキ)です。
2010年8月に久々のイラストとなる都電3000形の塗り絵をぽこぺん談話室やpixivなどで発表しました。
玉電よりも大きなサイズで描きました。色もそのうち塗ります。今後も都電の各形式を発表できればと思います。
| 2000形(鋼製)は、狭軌だった杉並線用に投入された形式です。ここでは新造された最終グループ(2018〜2024)を紹介します。 | |
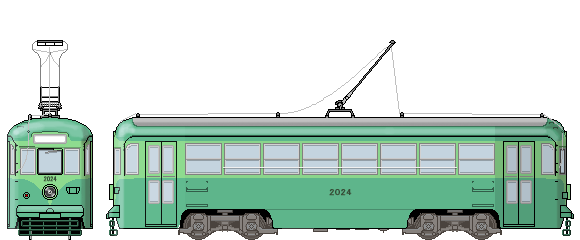 |
昭和30年12月22日に2018〜2021がナニワ工機製、26日に2022〜2024の東洋工機製が出場しました。台車はD-16N、塗装は同時期の7000形(7051〜73)と同じでした。 |
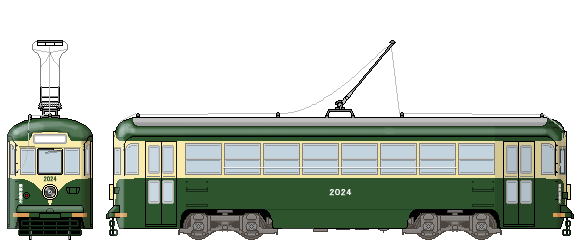 |
昭和31〜33年ごろの塗装を再現しました。「都電写真集」の149頁を参考にしました。 |
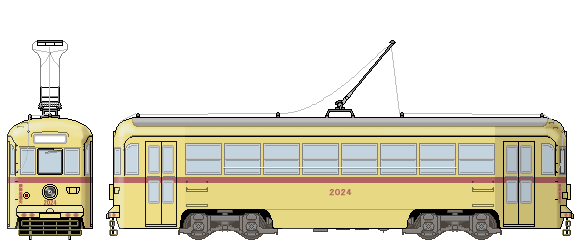 |
昭和34年以降の塗装を再現しました。34年以降と、オリンピック以降では塗装が違うようです。 |
| この車輌は杉並線廃止後、三田や広尾、目黒などの車庫へ転属し昭和44年に廃車になりました。この最終グループのうち6両(2018〜2022、2024)が長崎電気軌道へ譲渡され、700形として今も一部が現役です。 | |
| 3000形は、大正12年(1923年)に登場した木造車でした。関東大震災後にも、増備され610両いました。 ここでは、戦後鋼体化された3000形を紹介します。 |
|
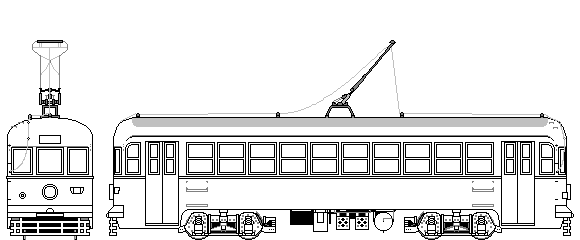 |
3001〜3213は昭和24年に登場しました。局工場と民間6社(汽車製造(支店)、日本車輌(本店)、日国工業、日立製作所、東急車輛、富士産業)で製造されました。 昭和25年に3214〜18が局工場の部品で新造され、昭和27年3月までに3226までが登場しました。これらは側面窓が10枚あります。 イラストは登場時からビューゲルのの3219〜3226を再現しました。 |
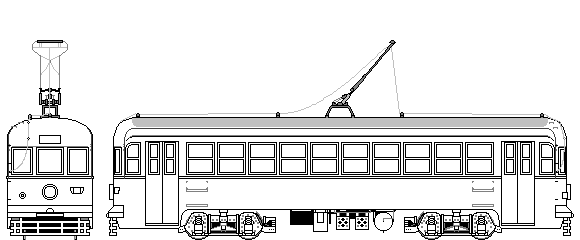 |
3000形は、6000形に良く似た形をしていますが、全長が11700mmと6000形よりも一回り小さく、幅も小さめです。 イラストは、雨樋を取り付けた姿を再現しました。 |
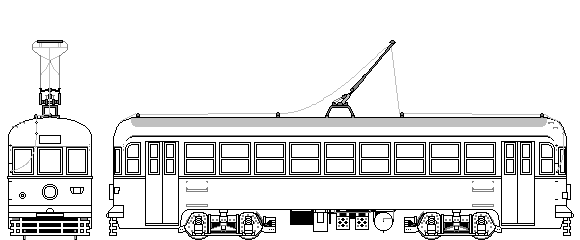 |
昭和26年4月に登場した3227以降は、幅が2000形と同じ2154mmとなり、側面窓も9枚になりました。3227〜3232までは登場時はロックフェンダーを付けていましたが、2年後に取り外されました。また都電初のドアエンジン装備車でした。 イラストは、ロックフェンダーを外した姿です。(登場時、排障器はストライカーでしたがイラストでは再現してません。m(_ _)m) |
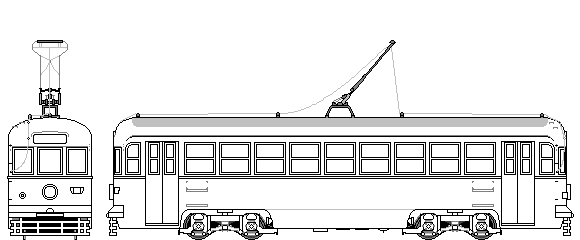 |
3236〜3240までは側面にスカートが取り付けられました。側面スカートは後に撤去されました。 3236以降は完全な新造車で台車もD-16になりました。また、方向幕も3233以降大型化されています。 イラストは、3236、3237、3240の登場時の姿を再現しました。 |
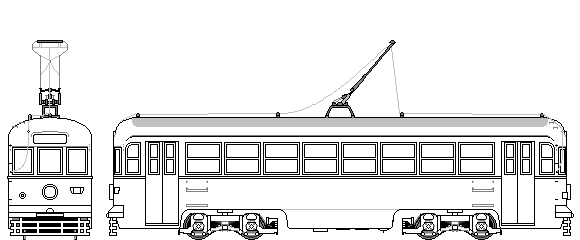 |
3238、3239は昭和28年(1953年)に日本鉄道自動車製で、側面窓が8枚になりました。 |
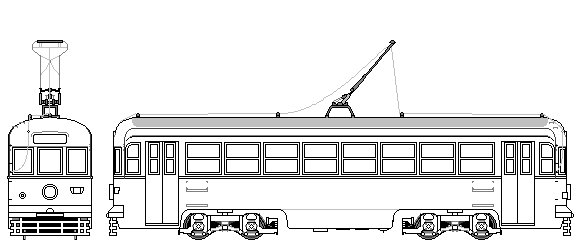 |
イラストは3238の昭和39年ごろを再現しました。晩年は側面スカートが撤去されてしまったようです。 |
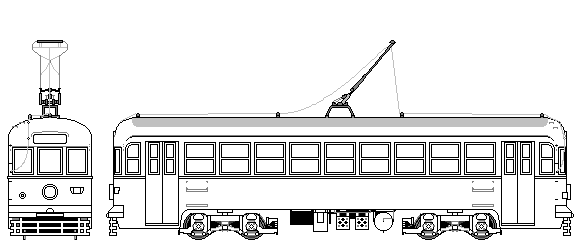 |
イラストは3241、3242を再現しました。側面スカートの無い大型方向幕車です。 |
3000形は9枚窓、8枚窓、側面スカートとそのバリエーションが豊富でした。今回は少数派の車両を中心に描きましたが、10枚窓車も雨樋の高さなど細かな違いはあります。この時代の電車は一両一両細かな個性があるので全部を再現するのは無理ですが、そうした違いを見つけるのも面白いです。数が多すぎて気が狂いそうになりますが…(苦笑) |
|