小学生の頃家の近くに住みついていた野良猫がいました。さわろうと人が近づくと逃げ出す三毛猫でした。
その猫が生んだ子猫が人なつこく、私はその猫とよくあそびました。
大人がそう呼ぶので私もちょんと呼んでいました。ちょんと私はとっても仲良しでした。猫の嫌いな祖母には近寄らないけれど私のそばには寄ってきます。
その猫が子猫を今にも産みそうな日、外は嵐のようでした。家の中で産みたそうに体を横たえていました。でも祖母が厳しくダメといい納屋に毛布を敷き詰めて産みやすいようにしてあげました。
ちょんは間もなく子どもを産みました。そして生まれたての赤ちゃんをくわえて私の部屋にやってきました。少しだけ窓を開けると窓枠をめがけて子猫をくわえてジャンプして・・。一匹、二匹、三匹、四匹と順々に・・・。まだ目もあいていない赤ちゃんの猫を・・。
私は祖母に怒られるのを承知で自分の洋服ダンスの中にかくまいました。見つからないように。
だけど翌日には見つかってまた納屋に連れ戻されました。それでも何度も何度も子猫を加えて私の部屋に戻ってくるのです。
私はそんなちょんのこどもをみんな飼いたいと言いました。
けれどこれからも子どもを産むちょんを家にはおいておけないということになりました。私はそのときどうやって納得したのか覚えていないのですが、子猫が生まれて50日ほどしてから、その子どものなかからちょんにいちばんよくにた子猫を選びました。
しっぽがみじかくて、さきっぽがちょっと曲がっているところまでそっくりなねこを・・。そのねこをちょんと名付けました。それからもう一匹の子猫がとなりの人にひきとられていきました。
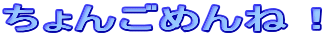
わたしの大好きだった親猫のちょんはそれからどうなったかというと、家から遠いところに連れて行かれたのです。それは祖母と両親とで出した結論でした。私は仔猫を家で飼えるということでそのときは納得させられたのでしょう(ちょんは家族の中では野良猫扱いでした)。
ちょんと別れる日私もついていきました。どんな場所に置いて行かれるか見届けておきたかったのです。戻ってくればいいのにとか、あとで迎えにいければどんなにいいかとおもったのです。
家からは10キロほど離れていたけど民家がさほど遠くない山の中でした。だけど猫が歩いて戻るには相当な距離がありました。
ちょんと子猫を二匹、缶詰をひとつおいて立ち去ったのです。私は何度も振り向きました。ちょんは悲しげな眼差しを見せたけどついてはきませんでした。なにかを悟ったように缶詰をおいしそうに食べる子猫のそばによりそっていました。
しばらく私は泣き続けちょんが見せた悲しそうな顔を忘れられなくて、親に迎えに連れて行ってほしいと頼み込む日が続きました。
そして日々が過ぎ、残された子ねことあそび、いつしか私は子猫だったちょんと親のちょんを同化していました。
別れたちょんと見分けがつかないくらいそっくりに大きくなりました。ちがうのは子どもを産むか産まないだけ。
私が高校を卒業して京都の学校に行くまでずっと一緒に過ごしました。
今もあの時別れた(捨てられた)ちょんの顔が脳裏に焼き付いてはなれません。あれからあの親子はどんなふうに生きていったのだろうかと。
私の大好きだったちょん・・・。
もどる
