 �u�E�N�����E�f���I�v
�u�E�N�����E�f���I�v
�I�[�^�T���i�n�[�u�E�I�I�^�j�����C���E���b�c
�r�N�^�[VICG-60452�i�Q�O�O�P�N�U���Q�P�������j
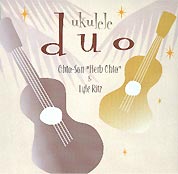 �@��������ƃI���`�����������ꂽ��n���C���y�̔��t�p�Ƃ��ẴC���[�W���������Ȃ������E�N�����Ƃ����y����A���h�ȃ\���y��Ƃ��Ă������n���C���y�݂̂Ȃ炸������W�������̊y��ƑΓ��Ɋ���y��Ƃ��Ă̒n��
�Ɏ����グ�����J�҂͉��ƌ����Ă��I�[�^�T���i�n�[�u�E�I�I�^�j�ł���A����ɂ̓I�[�^�T���قǒ��ڂ͂���܂���ł������W���Y�E�E�N�����Ƃ����W���������m���������C���E���b�c�̂ӂ���ł���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@��������ƃI���`�����������ꂽ��n���C���y�̔��t�p�Ƃ��ẴC���[�W���������Ȃ������E�N�����Ƃ����y����A���h�ȃ\���y��Ƃ��Ă������n���C���y�݂̂Ȃ炸������W�������̊y��ƑΓ��Ɋ���y��Ƃ��Ă̒n��
�Ɏ����グ�����J�҂͉��ƌ����Ă��I�[�^�T���i�n�[�u�E�I�I�^�j�ł���A����ɂ̓I�[�^�T���قǒ��ڂ͂���܂���ł������W���Y�E�E�N�����Ƃ����W���������m���������C���E���b�c�̂ӂ���ł���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@���̂ӂ���́A�������ƃn���C�ƕĖ{�y�Ƃ����ʁX�ȏꏊ�ʼn��t���������Ă���A���Ƀ��C���E���b�c�̓W���Y�E�E�N�����̃A���o�����Q�������[�X������͖{�Ƃ̃x�[�X�Ŋ��Ă������߂��݂��̐ړ_�͂���܂���ł����B�Ƃ��낪�P�X�X�O�N��ɖ{�Ƃ���u���ށv���ĕĖ{�y����n���C�ɈڏZ���Ă������C���E���b�c���A������I�[�^�T���̖��Ӊ��t���Ă������X�g�����Ƀx�[�X���Q�œo�ꂵ�ꏏ�ɉ��t�������Ƃłӂ���͂����ɈӋC�������A����Ȍ�̃I�[�^�T���̃��R�[�f�B���O�ɂ̓��C���E���b�c���K���x�[�X��e���Ƃ����t�������ɂȂ�A���ꂪ���݂܂ł������Ă���܂��B
�@�����������Ԃƈꏏ�ɉ��y���y���ނƂ��̍ŏ��P�ʂ͈�l�����t���đ��̐l���S���Ƃ����`�������̂ł����A�������E�N�������D�ғ��u�̏ꍇ�ł��ƁA��l�����t��������l���\����e���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�I�[�^�T���ƃ��C���E���b�c�̂ӂ�����v���C�x�[�g�̏�ł͂��̂悤�Ȋy���݂��������Ă���܂������A���̂ӂ���̑f���炵���Ƃ���͂��݂��Ƀ\�����Ƃ�A���������X�ƃA�h���u���������邱�Ƃ��ł��邱�ƂŁA���̑f���炵�����E�N�������D�҂݂̂Ȃ炸���Б����̉��y�t�@���ɒm���Ă������������Ƃ�����|�ō���̃A���o������悳��܂����B
�@�ߋ��ɂ��P���̃A���o�����ɃE�N�����E�f���I�̉��t�̋Ȃ��܂܂�Ă���Ղ͂���܂������A����̔Ղ̂悤�ɂ��ׂĂ̋Ȃ��E�N�����E�f���I�ɂ�鉉�t�Ƃ����A���o���͐��E�ŏ��߂Ă̊��Ǝv���܂��B���^����Ă���P�O�Ȃ͂�������X�^���_�[�h�E�W���Y����у{�T�m���@�̖��Ȃ���ł��̂ŁA��ϐe���݂₷���A�����W�Ƃ����܂��Ē����l�̐S�������b�N�X�����Ă����A���o���ɂȂ��Ă���܂��B�����ăX�^���_�[�h�E�E�N������e���I�[�^�T���̒���l�߂����̗����オ��ƁA�e�i�[�E�E�N������e�����C���E���b�c�̌��݂̂���܂�₩�ȉ��̑Δ�́A�E�N�����Ƃ����y��̉\���̍L���������Ă��āA�ق��̊y�킪�ȂɂЂƂ�����Ă��Ȃ��ɂ�������炸�R���{��r�b�O�o���h�̕��͋C�����������o���Ă���̂ɂ͋�������܂��B
�@�E�N�������D�҂̊F�l�͐��̂ӂ���̉��t���镵�͋C�̃R�s�[�ɒ��킵�Ă݂Ă��������B�K�������e�i�[�E�E�N�������K�v�Ȃ킯�ł͂Ȃ��A�Q�{�Ƃ��X�^���_�[�h�E�E�N�����ł����̕��͋C�̓R�s�[�ł���Ǝv���܂��B
| �X�e�[�W�l�[���u�I�[�^�T���v�̒a����b
|
�@�I�[�^�T���̉��y�o���͂���܂ł��Ȃ�ڂ����Љ��Ă��܂��̂ŁA�����ł͔ނ̃X�e�[�W�E�l�[���ł���u�I�[�^�T���v�i�p��ŏ����ꍇ��Ohta-San�j�̗R���ɂ��Ă��Љ�����܂��傤�B
�@�P�X�R�S�N�P�O�����܂�̃I�[�^�T���͎q���̂��납��E�N�������t�ɔM�����Ă��܂����B�����ĂP�Q�̂Ƃ��ɓ����ō��̃E�N�����t�҂ł������G�f�B�[�E�J�}�G�ƕl�ӂŋ��R�m�荇�����̂����������ƂȂ��ĔނɎt�������̂ł����A�����Ɏt�����āu�����ނɂ͋�������̂����������Ȃ����v�ƒQ������قǂ̘r�O�ɂȂ��������ł��B
�@���̃G�f�B�[�E�J�}�G�����������ہA�G�f�B�[�E�J�}�G�Ɛe���̂������D�c�L�I�F�Ɂu���̒�q�őf���炵���E�N�����E�v���C���[������v�ƏЉ���̂��I�[�^�T���ł����B�����Ă��܂��ܔނ��C�����̒�
��œ��{�ɒ������Ă������Ƃ�����A���̌�I�[�^�T���̍ݓ����͓��{�r�N�^�[�ł̃I�[�^�T���̃\���E�A���o���^���̋��n����������A���{�E�N��������i�m�t�`�j�Ŕނ̉��t������J�Â���ȂNJD�c�L�I�F�����낢��Ɣނ̖�
�|���݂Ă���܂����B
�@�P�X�U�R�N�ɏ������ăn���C�֖߂����I�[�^�T���͂��낢��ȐE�Ƃ�͍�����������E�N�����E�v���C���[�Ƃ��Ă̓���i�ނ��Ƃ����S���A�t���E���R�[�h�̃_���E�}�N�_�~�A�h�E�V�j�A�̃v���f���[�X�ŗ��P�X�U�S�N�ɃT�[�t�T�C�h�E���[�x������V���O���E�f�r���[�����邱�ƂƂȂ�܂����B���{�r�N�^�[�Ř^�������Q���̂k�o�����ē��{�O�����t�H�����烊���[�X���ꂽ�P���̂k�o���ɂ����鉉�t�Җ��Ƃ��Ắu�n�[�o�[�g���c�i���m�ɂ͑�c�j�v���g���Ă��܂����̂ŁA��������ނ�m���Ă���F�l�B�͔ނ̂��Ƃ����ł��u�n�[�o�[�g�v�ƌĂ�ł��܂����A�n���C�E�f�r���[�ɂ������ă_���E�}�N�_�~�A�h�E�V�j�A�͔ނ̃X�e�[�W�E�l�[�����uOhta-San�v�Ƃ��邱�Ƃɂ��܂����B����̓n���C�l�̂������ł́u�`����v�Ƃ����Ăт����͑�όh�ӂ����������t�Ƃ��Ď�����Ă��邱�ƂƁA�u�n�[�u�v��u�n�[�o�[�g�v�Ƃ������Ă���ȒZ���P��ŌŗL�̐l�����w�����Ƃ��ł��邱�Ƃ��˂�������̂ŁA���̌�u�I�[�^�T���v�̓_���E�}�N�_�~�A�h�E�V�j�A�̂�����݂ǂ����σ|�s�����[�ɂȂ�܂����B�����Ƃ����̂��߂ɃI�[�^�T�����T�[�t�T�C�h�E���[�x�����,�����͂��̌�̃f�b�J�E���[�x���Ƃ̌_�ɂق��̃��[�x���ɏo��Ƃ��ɂ͎~�ނ��uPoki-San�v�ȂǂƂ�������
���i�����o���܂����j��p�������Ƃ�����܂����B
�@�f�r���[�E�V���O���Ɏ��グ��ꂽ�Ȃ͓��{�Ő��b�ɂȂ����D�c�L�I�F�̍�i�u�錜�̌a�v�Ɓu�X�̏��a�v�ł������A����܂��_���E�}�N�_�~�A�h�E�V�j�A�̃A�C�f�B�A�ɂ��A�����r���{�[�h�̂P��
���L�[�v���Ă�����{��́uSukiyaki�i��������ĕ������j�v�ɕ֏悵�āA�O�҂��uSushi�v��҂��uBonsai�v�Ƃ܂��������W�ȃ^�C�g���ɂ��Ă��܂��܂����B���������̃f�r���[�E�V���O���̑�q�b�g�ɂ��E�N�����t�҂Ƃ��ẴI�[�^�T���̒n��
�͕s���Ȃ��̂ƂȂ�A���݂Ɏ����Ă���܂��B
| ���C���E���b�c�^�E�N�����Ɩ����������R�O�N |
�@�P�X�R�O�N�P�����܂�̃��C���E���b�c�́A�w������Ƀ��T���[���X�̊y��X�ŃA���o�C�g�����Ă��܂����B�ނ̎d���͂��q����ɓX�̊y���e���Č�����Ƃ������̂ł����B���Ƃ��Ɣނ͎q���̍�����o�C�I����������Ă����̂ł����A�ǂ�Ȃɓw�͂��Ă��w�Z�̃o���h�̑�Q�o�C�I�����ɂ���Ɖ����ĖႦ����x�̘r�O�ɂ����Ȃ炸�A�o�C�I��������Ƃ��邱�Ƃ�������߂Ă��܂����B�Ƃ��낪������A���o�C�g��̊y��X�ŃE�N�����������e���Ă݂��Ƃ���A���̉��F�̑f���炵���ɖ�������Ă��܂��܂����B�����Ŕނ͂����Ɏ����p�̃E�N�������w�����Ė����̂悤�ɒe�����ނ��ƂŃE�N�����Ɠ��̃R�[�h�E���[�N�ɏK�n���Ă����܂����B���̃E�N�������P�X�T�W�N�Ƀ����[�X�����uHow
About Uke?�v�iVerve V-2087�j�Ɨ��N�����[�X���ꂽ�u50th
State Jazz�A�M��F�E�N�����ŃW���Y���iVerve VL-1045�j���{�����P�X�U�Q�N�v�̘^���Ɏg��ꂽ�J�b�g�E�E�F�C�`�i���������Q�Ƃ��������j�̃M�u�\���̃e�i�[�E�E�N�����������̂ł��B�����̔ނ͌��݂̂悤�ɑ����Ă͂��܂���ł������A�啿�ȑ̌^�ł����̂ŃX�^���_�[�h�E�E�N�����ł͂Ȃ��ތ��,���Ƃ���́u�}�C�E�T�C�Y�v�̃e�i�[�E�E�N������I�悤�ł��B
�@�w�Z���o�����C���E���b�c�͂`�����N�̃X�^�W�I�E�~���[�W�V�����Ƃ��ăA�b�v���C�g����уG���L�̃x�[�X��e���A�T�O�O�O�Ȃ��z����^�������Ă��܂����B�ނ��o�b�N���Ƃ߂��~���[�W�V�����̓t�����N�E�V�i�g���A�����_�E�����V���^�b�g�A���C�`���E�X�E�u���U�[�X�A�r�[�`�E�{�[�C�Y�A���C�E�`���[���X�A�e�B�i�E�^�[�i�[�A�W���j�C�E�}�`�X���̑��L���̎�A�O���[�v�������̂��Ƃ܂��Ȃ��قǂł��B
�@��قǂ̂Q���̃E�N�����E�\���E�A���o���͂��̃X�^�W�I�E�~���[�W�V�����Ƃ��Ă̊����̍��Ԃɒ��ԂƘ^���������̂����@�[���E���R�[�h�ɔF�߂��ă����[�X���ꂽ���̂ŁA����ȍ~�R�O�N�ȏ�Ƃ������̂̓E�N�����͔ނ́u��v�Ƃ��Ă̊y��ɂƂǂ܂��Ă���܂����B�v���E�~���[�W�V�������P�X�X�O�N��̂͂��߂Ɂu���ށv�������C���E���b�c�́A�Z�݊��ꂽ���T���[���X�����ƂɃE�N�����̌̋��ł���n���C�E�I�A�t���̃J�C���A�ɍȂƂ��삳��ƈꏏ�ɈڏZ���Ă��܂����B�����ăI�[�^�T����C�E�T�N�}���͂��߂Ƃ����n���C�̉��y�W�҂Ƃ̌𗬂��
���Ăӂ����уE�N������e���悤�ɂȂ����̂ł��B����Ƀ��C�E�T�N�}��ɂ́u�E�N�����E�t�F�X�e�B�o���v�ł͖��N�̂悤�ɂ��삳��̃G�����[��A��ăE�N�����E�\���ŏo������悤�ɂȂ�A���C���E���b�c���g�R���ڂ̃\���E�A���o���uTime...�v(Roy
Sakuma RSCD 5583)�������[�X���ꂽ���Ƃɂ���āA�ނ̒e���W���Y�E�E�N�������ӂ����ш��
�ɔF�m�����悤�ɂȂ�܂����B
| �E�N�����̎�ނƒ����i�`���[�j���O�j
|
�@�E�N�������a�������P�X���I�㔼����Q�O���I�ɂ����ẮA�E�N�����̃T�C�Y�ƌ`��ɂ͑傫�ȕω�������܂���ł����B���̃T�C�Y�ƌ`������E�N�����̂��Ƃ��u�I���W�i���E�E�N�����v�������́u�X�^���_�[�h�E�E�N�����v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂́A����Ȍ�Ƀp�C�i�b�v���`�̃E�N�������o�ꂵ�Ă���̂��ƂƎv���܂��B�����āA������g���������Ƃ����v�]����u�e�i�[�E�E�N�����v�u�o���g���E�E�N�����v���̑傫�ȃE�N�������a�����A����ɂ̓e�i�[�ƃX�^���_�[�h�̒��Ԃ̃T�C�Y�����u�R���T�[�g�E�E�N�����v�����a�����܂����B�����e��E�N�����̓o��ɂ��A�ŋ߂ł́u�I���W�i���E�E�N�����v�������́u�X�^���_�[�h�E�E�N�����v�̂��Ƃ��u�\�v���m�E�E�N�����v�ƌĂԌĂѕ����蒅���Ă��܂����B
�@�w���{�f�B�[�ɂȂ��镔���̃t���b�g�����A�����͌����̔����ɑ�������P�Q�t���b�g�ł������A��N�\���̃����f�B�[��e���₷������ړI�ŁA������P�S�t���b�g�ɂ������̂��o�ꂵ�܂����B����ɂ͂��ꂪ�G�X�J���[�g���A�Q�Q�t���b�g�Ƃ����悤�ȃE�N���������܂��B����M�^�[�ł悭�̗p�����`��́A�{�f�B�[�̃T�C�Y��ς��Ȃ��ł��̈ꕔ��茇�������Ƃɂ��P���̍�������e���₷�������u�J�b�g�E�E�F�C�`�v�̃E�N����������܂��B���C���E���b�c���ŏ��̂Q���̂k�o�^���Ɏg�p�����E�N�������M�u�\���̃J�b�g�E�E�F�C�d�l�̃e�i�[�E�E�N�����ł����B
�@�E�N�����̂S�{�̌����A�E�N����������������Ԃł̏�̌����Ȃ킿�S���i��������P���ƌĂԐl�����܂����E�E�j����f�|�b�|�d�|�`�i�J������e�����Ƃ��̃R�[�h���b�U�ɂȂ�܂��j�ƒ�������̂����݂ł͈��
�I�ł����A�E�N�������Ė{�y�ɓn��A�L���{�[�h�r���̐��E�Ŏg���Ă�������̂P�X�R�O�N��ɂ����钲���͂`�|�c�|�e#�|�a�i�J�����̃R�[�h���c�U�j���嗬�ł����B���鎞�����̂ӂ��̒��������݂��Ă������߁A�O�҂��u�n���C�A���E�`���[�j���O�v��҂��u�A�����J���E�`���[�j���O�v�ƌĂ�ł��܂����B�I�[�^�T�����P�X�T�O�N��ɒe���Ă����E�N�����̒������A�����J���E�`���[�j���O�̂ق��ł����B
�E�N���������̑傫�ȓ����Ƃ��āA�P���A�Q���A�R���ƃs�b�`�i���̍����j�����ԂɒႭ�Ȃ��Ă����A�S���ł�����x�����Ȃ�Ƃ����\��������܂��B���Ƃ��ƂP������S���܂ł̂��ꂼ��̌��̉����W�͉��̍��������قȂ�܂����M�^�[�̂���ƑS�������ɂȂ��Ă��܂��B���̉����W��N�����̂悤�Ɍ��߂����͕s���ł����A����ɂ��M�^�[��e����������r�I�e�ՂɃE�N�����̐��E�ɓ����悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������܂��B�����ē����̐l���S���̃s�b�`���P�I�N�^�[�u�����ݒ肵���Ƃ����̂́A�E�N�����t�y��Ƃ��Ĉ�
�u�Â��A�X�g�����i�R�[�h���܂Ƃ߂ăW�������ƒe���j�̕������ォ��ł�������ł������悤�ȉ��F��������悤�ɍl�����̂����m��܂���B�����ƒP���ɑz������ƁA�����̋Z�p�ł͒Ⴂ�s�b�`���������邽�߂ɂ͌��̃Q�[�W�i�����j���ɒ[�ɑ傫������K�v������A�E�N�����̂悤�Ȍ����̒Z���y��Ɏg������p�I�Ȍ������Ȃ������̂����m��܂���B
�@������ɂ��Ă��E�N�����̒����Ƃ��āA���̂S���������s�b�`�����X�^�C�����蒅���A�E�N�����E�\�����u�����t�Ƃ����̒����ʼn��t���A���̒����Ɠ��̃e�N�j�b�N���������a�����܂����B�I�[�^�T���̒����������͂��́u�S���������v���̂ł������A�L�͈͂̃W�������̉��y�����t����ꍇ�ɂ��̒����̂��u����̋����v�ɂ�萧�����邽�߁A�e�i�[�E�E�N�����̂R���p�ɊJ������Ă����������������X�^���_�[�h�E�E�N�����̂S���ɒ��邱�ƂŁu��c�A��v�ł͂Ȃ��̂ł����M�^�[�Ɠ��l�ɂS�����R�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ������������������E�N������a�������܂����B���̂S����Ⴍ�������邱�Ƃ��u���[�f�����v�ƌĂ�ŏ]���̒����Ƌ��
���Ă���̂ł����A�ŋ߂ł͂��̏]���̒����̂��Ƃ��u�n�C�f�����v�ƌĂԐl�������A�₪�Ắu�\�v���m�E�E�N�����v���l�ɒ蒅���Ă��܂������m��܂���B�Ƃ肠���������ł͏]���̒������u���M�����[�E�`���[�j���O�v�ƌĂ�ł������Ƃɂ������܂��B
�@�悭�A�u�I�[�^�T���̓��[�f�����e���Ȃ��v�Ƃ����b���܂�������͊��S�Ȍ���ł��B���݂ł����M�����[�E�`���[�j���O�̃E�N�������悭�e���Ă��܂����A���M�����[�E�`���[�j���O�̗ǂ��������^�����l�����Ă���悤�ł��̂ł����҂��������B
�@�e�i�[�E�E�N�����̒������܂��������Ă��܂��B���̊y�킽�Ƃ��T�L�\�t�H���̂悤�ȏꍇ�ł̓\�v���m�A�A���g�A�e�i�[�A�o���g���A�o�X�Ɗy��̃T�C�Y���傫���Ȃ�ɏ]���đS�̂̉��������ꂼ��S�x�������͂T�x���������čs���̂ɑ��āA�E�N�����̏ꍇ�̓{�f�B�[�̃T�C�Y���傫���Ȃ邱�Ƃł��̋�����s�b�`���Ⴍ�Ȃ�ɂ�������炸�A���̂��Ƃ������t�҂̉��t���₷�����特�������߂邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B�e�i�[�E�E�N�����̏ꍇ������ł���A�y�탁�[�J�[�Ƃ��Ă͐܊p�傫�ȃT�C�Y�̃{�f�B�[�������Ă���y��Ȃ̂ŁA�X�^���_�[�h�E�E�N�������S�x�Ⴂ�c�|�f�|�a�|�d�̒����Œe�����Ƃ�O��ɐ��삵�Ă���Ǝv���܂����A���t�҂̂ق��ł�����f�|�b�|�d�|�`�ƕύX���Ďg�����Ƃ����Ȃ���
�I�ɍs���Ă��܂��B�E�N�����̖��H�̂ЂƂ�ł���J���B�J�E�n�[�h���̌v�Z�ɂ��ƃe�i�[�E�E�N�����̍Œዤ�U�i���j���g���i�s�b�`�j�͂قڒႢ�f���Ƃ̂��Ƃł��̂Ńe�i�[�E�E�N�������c�|�f�|�a�|�d�Œ��������ꍇ�̂R�����f�|�b�|�d�|�`�Œ��������ꍇ�̃��[�f�̂S���������s�b�`�ƂȂ�̂Őv�̎�|�ɂ͍��v���Ă��邩���m��܂���,�B�t�ɍl����ƃX�^���_�[�h�E�E�N�����Ƀ��[�f�����Ă��{�f�B�[�͋����Ă���Ȃ��Ƃ������Ƃ�������A���̌��_�̓}�C�N��s�b�N�A�b�v�œd�C�I�ɕ���Ă�邵�����@�͂���܂���B�I�[�^�T�����s�b�N�A�b�v�����̃E�N�������g�p���Ă���閧�����̂�����ɂ��肻���ł��B
�@�������̂����������Ǝv���܂����A���C���E���b�c�̎g�p���Ă���e�i�[�E�E�N�����̒����͂S���������c�|�f�|�a�|�d�ɂȂ��Ă���܂��̂ŁA�����ł͂��̒����̂��Ƃ��u�e�i�[�E�`���[�j���O�v�ƌĂԂ��Ƃɂ������܂��B
�ȖڂƉ��t
�@�g�p�����y��̓I�[�^�T���͂��ׂă}�[�e�B���̃X�^���_�[�h�E�E�N�����ł����A���C���E���b�c�̂ق��͂Q�A�S�A�T�A�U�A�V�A�P�O�̂U�Ȃ��}�[�e�B���̃e�i�[�E�E�N�����Œe���A�c��̂S�Ȃ��R�I���E�̃e�i�[�E�E�N�����Œe���Ă��܂��B
�܂��A�Ȗڂ̉���ɂ͏o����玁�̒������ʂ��A�����ĉ��t����ɂ͏��ь���������̃R�����g���Q�l�ɂ����Ă��������܂����B
�@
- �V���[�t���C�E�p�C�E�A���h�E�A�b�v���E�p���E�_�E�f�B�[
�@ ���̉��Ƃ������^�C�g���̓A�����J�̓c�ɂōD�܂�Ă���V���[�t���C�E�p�C�ƃA�b�v���E�p���E�_�E�f�B�[�Ƃ����ӂ��̐H�ו��i����j��\�킵�Ă��܂��B�Ȏ��̂̓_�C�i�E�V���A���P�X�S�U�N�ɉS���ăq�b�g�����̂ł����A�����ăW���[���E�N���X�e�B�[���X�^���E�P���g���y�c�A�K�C�E�����o�[�h�y�c�A�t�����N�E�V�i�g�����������̉̎��O���[�v���J�o�[�������R�[�h�����X�Ƀq�b�g���܂����B
�@ ���̉��t��������ƒ��������ŃE�N�����E�f���I�E�A���o���̑f���炵�������ӂ�o�Ă���̂���������ɂȂ�Ǝv���܂��B�I�[�^�T���ƃ��C���E���b�c���y�������ɒe���Ă���p���ڂɕ����Ԃ悤�ł͂���܂��B�I�[�^�T���̉s���^�b�`�̉��ƃ��C���E���b�c�̃\�t�g�ȃ^�b�`�̉��Ƃ������ꂼ������鉹�F�A����ł��Ă�ǂ݂Ȃ����̗���̓A���o���̃g�b�v������ɂӂ��킵�������ƌ����܂��傤�B
- �T���H�C�ŃX�g���v
�@ �T���H�C�Ƃ����̂̓j���[���[�N�̃n�[�����n��ɂ������_���X�z�[���i�{�[�����[���j�̖��O�ŁA�P�X�R�O�N��ɂ͍ł��L���ȃz�[���ł����B�_���X�D���̐l�B�͂��̃z�[���ŃX�g���v�i���ݖ炷�Ƃ����Ӗ�����]���āu�x��v���Ɓj������̂��D�݂܂����B���̋Ȃ͂��̃z�[���ɂ��o�����Ă����x�j�[�E�O�b�h�}���y�c�ɂ��P�X�R�U�N�ɑ�q�b�g�����A�P�X�T�T�N�̃��j�o�[�T���f��u�x�j�[�E�O�b�h�}�������v�ł��g���܂����B
�@ ���̉��t�ł̓��C���E���b�c�̓����ł���e�i�[�E�E�N�����̃R�[�h�t�@���ӂ�ɓo�ꂵ�܂��B�P���P���̃����f�B�[�ɑ���R�[�h�E���[�N�̍I�݂��ƒP���e���������Ƃ��̔ނ̃}�C���h�œ����x�̍����T�E���h�ɂ́A���C���E���b�c�E�t�@���Ȃ炸�Ƃ���������邱�ƊԈႢ����܂���B
- �g���X�e�i�߂��݁j
�@�{�T�m���@�̐��݂̐e�A���g�j�I�E�J�����X�E�W���r���́A�t�����N�E�V�i�g���Ƃ̃��R�[�f�B���O�̂��߂ɂP�X�U�U�N�W���Ƀ��T���[���X�ɗ������̂́A�V�i�g���̓s���ŗ��N�P�����܂Ń��R�[�f�B���O����������T���������~�߂�H���܂����B���̊��Ԃɔނ́u�E�F�[�u�v�Ƃ��́u�g���X�e�v�̂Q�Ȃ���Ȃ��A�����̃A���o���u�E�F�[�u�v�Ɏ��߂܂������A�Q�ȂƂ����̌㐔�����̃~���[�W�V�����ɉ��t����Ă��܂��B
�@�I�[�^�T���ƃ��C���E���b�c�̓����f�B�[�ƃo�b�N�����݂ɒS�����Ȃ��牉�t���Ă���̂ł����A�����������t����l�̉��t�Ƃ������Ă��邩�̂悤�ȃX���[�Y�ȗ���̒��ŁA�I�[�^�T���ƃ��C���E���b�c���ꂼ��̓�������A�h���u�Ɠ�������o�b�N�̃R�[�h�E���[�N���������Ă��܂��B
- �͗t
�@ ���Ƃ��ƃW���b�N�E�v�����F�[���쎌�A�W���Z�t�E�R�X�}��ȁA�W�����G�b�g�E�O���R�̉S�łP�X�S�V�N�Ƀq�b�g�����V�����\���̕s���̖���ł������A���̌�W���j�[�E�}�[�T�[�̕t�����p��̉̎��ɂ�萔�����̉̎�i���Ƃ��P�X�T�U�N�R�����r�A�f��u�I�[�^���E���[�u�X�v�̒��ł̃i�b�g�E�L���O�E�R�[���j���S���A����ɂ̓}�C���X�E�f�C���B�X�����t�������Ƃɂ��|�s�����[�̖��ȂƂ��Ă̒n��
��s���Ȃ��̂Ƃ��܂����B
�@ ���t�͂܂����C���E���b�c�̖����t�\���ł͂��܂�A���̂܂ܔނ��Q�R�[���X���t���ăI�[�^�T���Ƀo�g���E�^�b�`�A�Ō�͂ӂ����єނ̉��t�֖߂�Ƃ����\���ł����A�ӂ���̒P���e���̃A�h���u�ƃ��C���E���b�c�̃R�[�h�e���̃����f�B�[�A�����Ăӂ���̐��m�ȃo�b�N���t�����̋Ȃ̑f���炵������w����グ�Ă��܂��B
- �e�B�[�`�E�~�[�E�g�D�i�C�g
�@ �T�~�[�E�J�[���ƃW�[���E�h�D�E�|�[���ɂ���ĂP�X�T�R�N�ɍ��ꂽ�u����͋M�����狳���Ă��炤��D�̂Ƃ�������A�`�a�b����w�x�y�܂ł̂��ׂĂ������Ă��傤�����I�ł��搶������ȂɊԋ߂ɂ��Ă������̂�����H�v�Ƃ���������ƃ��[�����X�ȃ��u�E�\���O�B�ŏ��ɐ������W���l�b�g�E�u���C�X�̉S�̓q�b�g���܂���ł������A���̌ケ����J�o�[�������l���̉̎��O���[�v�̐������݂Ńq�b�g���܂����B
�@ ���C���E���b�c���I�[�^�T�����u�W���[�N��D���l�ԁv�ł��̂ŁA���̂ӂ��肪�W���[�N�����킷���
�ł͔��̉Q�������N����܂��B���̋Ȃ�^�������ہA���̃Z�N�V�[�ȋȖ��������ɂ��܂��߂Ȓ��q�Ń��C���E���b�c�����������߁A��₠���ăI�[�^�T�������炦���ꂸ�����o�����l�q�����^����Ă��܂��B
- �T���o�h�E��
�@ ���ăZ���W�I�E�����f�X�ƃu���W���U�U�̃��[�_�[�Ƃ��Đ��Ȑl�C���ւ����Z���W�I�E�����f�X���P�X�X�Q�N�ɔ��\�����A���o���uBrasileiro�i�u���W���l�j�v�́A����܂ł̔ނ̍�i�̔w�i�ɂ���u���W�����y�ɏœ_�����Ă��A���o���ŁA�u���W�����y�̂��L�͈͂̉\�������l���̍�Ȏ҂ɂ��I���W�i���ŕ\�����܂����B���̋Ȃ͂��̒��ł����Ƃ��u���W���U�U����̉��y�ɋ߂����͋C�������Ă���Ɣގ��g���q�ׂĂ��܂��B
�@ ���̋Ȃ͈ȑO�̃I�[�^�T���̃A���o���ɂ����^����Ă��܂����A���̂Ƃ��̉��t�̓I�[�^�T�����P�ɃR���{�̈���Ƃ��ăA�h���u��e���Ƃ����X�^�C���ł����B����̘^���̓I�[�^�T���̖����t�\���ɂ͂��܂胉�C���E���b�c�̑���
�ȃR�[�h�ɂ�锺�t�������A�ӂ���̃A�h���u�ւƓW�J����A�܂��Ɂu���ꂪ�E�N�����E�f���I�I�v�Ƃ������t�ł��B
�@
- �����Y�E�o�b�N�E�C���E�^�E��
�@�n���[�E�E�H������ȁA�A���E�f���[�r���쎌�ō��ꂽ���̋Ȃ͂P�X�R�T�N�̃��[�i�[�f��u�u���[�h�E�F�C�E�S���h�����[�v�Ńf�B�b�N�E�p�E�G���ƃ~���X�E�u���U�[�X�ɂ���ďЉ��A�q�b�g�E�`���[�g�ɂ͓������P�X�R�T�N�Ƀt�@�b�c�E�E�H�[���[�̔Ղ��P�O�T�ԓ����Ă��܂������A�ō������N�͂W��
�ł����B�������f�B�b�N�E�p�E�G���̓o�ꂷ�郉�W�I�ԑg�ł͒����������ł��������N�G�X�g���ꂽ�Ȃ������̂ł��B
�@���C���E���b�c�ƌ������̋Ȃ��v���o���قǔނ́u�\���ԁi���͂��j���̏\���ԁv�̋Ȃł����A���̘^���ł͔ނ̓����ł���R�[�h���g�����\���ɉ����ĒP���e���ɂ��A�h���u�A�����ăI�[�^�T���̃\�����o�ꂵ�Ō�ɂӂ����єނ̃\���ɖ߂�Ƃ����\���ɂ�肱�̋Ȃ̃C���[�W����V���Ă��܂��B
�@
- �A�C�E�E�H���g�E�_���X
�@ �W�F���[���E�J�[����ȁA�I�b�g�[�E�n�[�o�b�N�A�I�X�J�[�E�n�}�[�V���^�C���Q���̍쎌�łP�X�R�S�N�̃~���[�W�J���u�X���[�E�V�X�^�[�Y�v�̎��̂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���̋Ȃ́A���P�X�R�T�N�̂q�j�n�f��u���o�[�^�v�Ńh���V�[�E�t�B�[���Y�̍쎌���t���b�h�E�A�X�e�A�ƃW���W���[�E���W���[�X���S���L���ɂȂ�A����Ƀ����[�E�V���[�E�b�h�����̔N�ɐ������Ղ͂P�S�T�Ԃ��̂������q�b�g�E�`���[�g�ɓ����Ă��܂����B
�@ ����̃A���o�����ōł����t���Ԃ̒����^���ł����A�I�[�^�T���̃R�[�h��t���Ȃ���̃\�����t�Ɉ��������A����̂���ꂽ�R�[�h�E���[�N�̔��t�ɏ���ė��҂��ꂼ��̒P���e���̃A�h���u�����݂Ɋy��������čs���Ƃ����\���ɂ��A������S�����������܂���B
- �u���[�Z�b�g�i�؉A�ɂāj
�@ �u���[�Z�b�g�Ƃ����̂̓|�s�����[���y�̂P����ł���u�u���[�X�v�Ɂu�������A���킢���v�Ƃ�����������\�킷�ڔ���u�`ette�v���������̂ŁA�u���[�X�Ƃ������y���[�l�����Ă��܂��B���̋Ȃ͂P�X�R�U�N�Ƀn�[���j�J�t�ҁA�M�^���X�g�Ƃ��ėL���ł������W�[���E�g�D�[�c�E�X�B�[���}���Y�ɂ���č�Ȃ��ꂽ�C���X�c�������^���Ȃł������A�P�X�U�S�N�Ƀm�[�}���E�M���x���ɂ���ă^�C�g���ɂӂ��킵���̎����t�����܂����B
�@ �I�[�^�T�����ȑO���̋Ȃ�^�������Ƃ��́A�I���W�i���̃n�[���j�J���S�̉��t���C���[�W�����s�A�j�J�����t�̎���Ƃ�����������܂������A����̘^���͍�Ȏ҂̖{�E�ł���M�^�[���ӎ����Ẳ��t�ƂȂ��Ă��܂��B���C���E���b�c�����ӂ̏I�~�R�[�h���������t���[�Y�ƃI�[�^�T���̒P���e���\���̗Z������i�ł��B
- �h���[�� �@�@
�@ ��L�S�u�͗t�v�̉p�����������W���j�[�E�}�[�T�[�̍쎌�E��Ȃɂ��P�X�S�S�N�ɂ���ꂽ���̋Ȃ́A���N���J���ꂽ�l�f�l�f��u���̂ЂƂƂ��v����тP�X�T�T�N�̃t�H�b�N�X�f��u���Ȃ����������v�Ɏg�p����܂������A���Ɍ�҂̉f�掩�̂̃q�b�g�ɂ��X�^���_�[�h�ȂƂ��Ă̒n��
���m�ۂ��܂����B���̋Ȃ̓I�[�^�T���̐t����̎v���o�̋ȂŁA�����̃r�[�`�{�[�C�B�͂S�p�[�g�̃R�[���X�Ŋy�����̂ł��B
�@ ���̋Ȃ̓I�[�^�T���ƃ��C���E���b�c�̃R���r�ɂ���ĉ��x�����x�����t����Ă��܂����̂ŁA���݂��́u�o�ԁv�Ɓu�����v���\���߂���قǂ킫�܂������t�ł��B�����ă��C���E���b�c�̑f���炵���R�[�h�E���[�N�ƃI�[�^�T���̃R�[�h���������P���e���̃\���́A���̃A���o������߂�����ɂӂ��킵�������ɂȂ��Ă��܂��B�@�@
���{�E�N��������@�� �� �� ��
Jam Selections
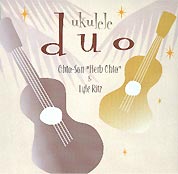 �@��������ƃI���`�����������ꂽ��n���C���y�̔��t�p�Ƃ��ẴC���[�W���������Ȃ������E�N�����Ƃ����y����A���h�ȃ\���y��Ƃ��Ă������n���C���y�݂̂Ȃ炸������W�������̊y��ƑΓ��Ɋ���y��Ƃ��Ă̒n��
�Ɏ����グ�����J�҂͉��ƌ����Ă��I�[�^�T���i�n�[�u�E�I�I�^�j�ł���A����ɂ̓I�[�^�T���قǒ��ڂ͂���܂���ł������W���Y�E�E�N�����Ƃ����W���������m���������C���E���b�c�̂ӂ���ł���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@��������ƃI���`�����������ꂽ��n���C���y�̔��t�p�Ƃ��ẴC���[�W���������Ȃ������E�N�����Ƃ����y����A���h�ȃ\���y��Ƃ��Ă������n���C���y�݂̂Ȃ炸������W�������̊y��ƑΓ��Ɋ���y��Ƃ��Ă̒n��
�Ɏ����グ�����J�҂͉��ƌ����Ă��I�[�^�T���i�n�[�u�E�I�I�^�j�ł���A����ɂ̓I�[�^�T���قǒ��ڂ͂���܂���ł������W���Y�E�E�N�����Ƃ����W���������m���������C���E���b�c�̂ӂ���ł���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
