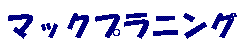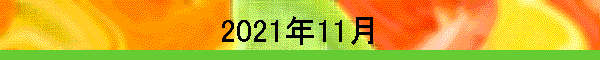|
「豚舎・設備のお悩み解決!」(100)「堆肥の減量化と販売工夫」
ここ数年、養豚の景気が良かったこともあり、規模拡大する農場が多くなりました。
それに伴い堆肥の処分(販売)に苦慮する農場も多くなりました。
そこで今回は堆肥販売の工夫と堆肥の減量化についてアイディアをご紹介します。 私自身、農家であり、かつて米作りも自分で行っていました。
養豚の堆肥を使うとお米が美味しくなり、収量も上がります。
農家の人たちはそのことは十分承知しています。
しかし散布のし易さの観点から化成肥料しか使わない農家が多いのです。
これは野菜などの畑作でも同じです。
耕種農家に堆肥を使ってもらうには、養豚場側では使いやすい堆肥を製造することが重要です。
では、どんな堆肥が耕種農家にとって使いやすいのかというと、ブロードキャスターで散布できることです。
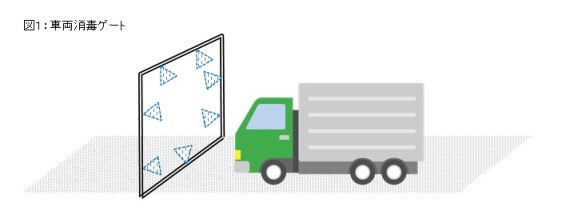 図1がブロードキャスターのイラストですが、漏斗状のホッパーに肥料を入れ、後に突き出たパイプを、
腕を振るような形に動かして散布する機械です。
ブロードキャスターで散布するには、直径2cm以下の粒状が最適です。
大きな固まりがあると、詰まってダメです。
また、ホッパーの中でブリッジを起こして落下しない堆肥も散布できません。
ですから堆肥の水分は30%~40%ぐらいが最適です。
このぐらいの水分になると堆肥の発酵は止まり、湯気は立たない状態ですが、
カラカラに乾いた状態ではなく少ししっとりした状態です。
このぐらいの堆肥を出荷すれば、使う側は喜びます。
また縦型コンポストで乾燥しすぎた堆肥は嫌われます。
水分20%以下になると乾いた粉末状になります。
これをブロードキャスターで散布はできますが、ホコリが舞い上がりますし、
遠くまで飛びません(散布幅が狭い)から、均一に散布することが難しくなります。
風があれば、堆肥のホコリが飛び散って周囲の迷惑となる場合場あります。
また、縦型コンポでは一次発酵が完全に終わっていませんから堆肥の品質としては良くありません。
まだ湯気が立つぐらいの水分状態で取り出して、
堆肥盤に堆積して2~3ヶ月間低温発酵させるとC/N比の低い良い堆肥になります。
図1がブロードキャスターのイラストですが、漏斗状のホッパーに肥料を入れ、後に突き出たパイプを、
腕を振るような形に動かして散布する機械です。
ブロードキャスターで散布するには、直径2cm以下の粒状が最適です。
大きな固まりがあると、詰まってダメです。
また、ホッパーの中でブリッジを起こして落下しない堆肥も散布できません。
ですから堆肥の水分は30%~40%ぐらいが最適です。
このぐらいの水分になると堆肥の発酵は止まり、湯気は立たない状態ですが、
カラカラに乾いた状態ではなく少ししっとりした状態です。
このぐらいの堆肥を出荷すれば、使う側は喜びます。
また縦型コンポストで乾燥しすぎた堆肥は嫌われます。
水分20%以下になると乾いた粉末状になります。
これをブロードキャスターで散布はできますが、ホコリが舞い上がりますし、
遠くまで飛びません(散布幅が狭い)から、均一に散布することが難しくなります。
風があれば、堆肥のホコリが飛び散って周囲の迷惑となる場合場あります。
また、縦型コンポでは一次発酵が完全に終わっていませんから堆肥の品質としては良くありません。
まだ湯気が立つぐらいの水分状態で取り出して、
堆肥盤に堆積して2~3ヶ月間低温発酵させるとC/N比の低い良い堆肥になります。 次に使いやすい堆肥を製造するための設備についてご紹介します。
写真1 写真2 写真2 最も簡単に粒状堆肥を作れるのがロータリーコンポです(写真1,写真2)
ロータリーの爪で攪拌して飛ばされるだけで自然に粒状の堆肥が出来上がります。
しかし、このタイプの欠点は悪臭対策が難しいことと、広い場所が必要な事です。
ロータリーコンポの中には深型のものもあります。
浅型ロータリーコンポの堆積厚さは60cmですが深型は1~1.5m堆積できますので、施設面積が少なくて済みます。
その他にスクープ式、スクリュー式、密閉縦型などのコンポストが養豚場では一般的に使われています。
これらのコンポではいずれも堆肥の形状は粒になりませんので、散布しやすい製品にするには造粒機が必要になります。
造粒機(ペレットマシン)は大抵のコンポストメーカーがオプションとして製品をラインナップしていますので、
手間とコストを考えながら機種の選定をして下さい。
最も簡単に粒状堆肥を作れるのがロータリーコンポです(写真1,写真2)
ロータリーの爪で攪拌して飛ばされるだけで自然に粒状の堆肥が出来上がります。
しかし、このタイプの欠点は悪臭対策が難しいことと、広い場所が必要な事です。
ロータリーコンポの中には深型のものもあります。
浅型ロータリーコンポの堆積厚さは60cmですが深型は1~1.5m堆積できますので、施設面積が少なくて済みます。
その他にスクープ式、スクリュー式、密閉縦型などのコンポストが養豚場では一般的に使われています。
これらのコンポではいずれも堆肥の形状は粒になりませんので、散布しやすい製品にするには造粒機が必要になります。
造粒機(ペレットマシン)は大抵のコンポストメーカーがオプションとして製品をラインナップしていますので、
手間とコストを考えながら機種の選定をして下さい。
最近では臭気対策がしやすくて設置面積が小さい、
縦型コンポを導入する農場が多くなりましたので、注意しなければならない点があります。
縦型コンポでは1次発酵が終了しません。
言わば乾燥豚糞に近い状態の製品であることです。
冒頭でも書きましたように、縦型コンポから取り出した物を堆肥盤で切り返しして、
発酵を進ませれば良い堆肥になりますが、なかなかそこまでやっている農場は少ないと思います。
未熟堆肥は、水田や水はけの悪い畑に施肥すると、嫌気性発酵するので、根腐れを起こす危険性があります。
ですから多量施肥は出来ません。
つまり養豚場側からすれば、堆肥のはける量が少ないということです。
堆肥は完熟させることにより、有機物の分解が進みます。
二酸化炭素と水蒸気となって発散しますので、堆肥の量が減ります。
ですから堆肥盤で寝かせて完熟させた方が、量は減るし使う農家からも喜ばれます。
但し、縦型コンポでカラカラに乾燥させて取り出したものは、そのまま堆肥盤に堆積しても発酵が進みません。
水分が足りないからです。
堆積して発酵が継続するぐらいの状態で取り出す必要があります。
次にどうしても堆肥の引取先が足りない場合の堆肥減量方法です。
方法としては大きく分けて3種類です。
①焼却する。
②熱分解装置を使って灰にする。
③特殊な酵素や発酵菌を混ぜて減量発酵させる。
①の堆肥や豚糞の焼却炉は昔からありますが、ランニングコストが大きいので普及していません。
②の熱分解装置とは、『パグマⅡ』という商品名で販売されている機械です(写真3)
 これの仕組みは上部から堆肥や豚糞、死亡豚などを投入し、密閉した状態で加熱して分解させ、
灰になって下部から取り出す。というものです。
最初だけ火種を投入しますが、後は先に投入したものが分解して発生する熱で次に投入したものを加熱する仕組みなので
、適正な投入管理を行えば加熱するための燃料が不要ですから、ランニングコストが安いです。
欠点は本体価格の高さです。豚糞を処理する場合、同じ処理量の縦型コンポに比べて、約2倍の導入コストが掛かります。
20年間のイニシャルコストとランニングコストの合計を比較すれば安くなる計算です。
死亡豚もレンダリングに出すことなく処理できるのは、衛生的なメリットです。
これの仕組みは上部から堆肥や豚糞、死亡豚などを投入し、密閉した状態で加熱して分解させ、
灰になって下部から取り出す。というものです。
最初だけ火種を投入しますが、後は先に投入したものが分解して発生する熱で次に投入したものを加熱する仕組みなので
、適正な投入管理を行えば加熱するための燃料が不要ですから、ランニングコストが安いです。
欠点は本体価格の高さです。豚糞を処理する場合、同じ処理量の縦型コンポに比べて、約2倍の導入コストが掛かります。
20年間のイニシャルコストとランニングコストの合計を比較すれば安くなる計算です。
死亡豚もレンダリングに出すことなく処理できるのは、衛生的なメリットです。
③の発酵菌や酵素は昔からいろんな業者が開発しては消えて、を繰り返してきましたので、
眉唾(まゆつば)物と思われがちです。
私も養豚場勤務20年とコンサルになって15年間いろんな菌を試してみましたが、これと言った決め手はありませんでした。
しかし、最近ホンモノかなと思える業者さんが見つかりました。
写真1の農場は今年1月から使用開始して、9ヶ月間堆肥の取出しをしていないそうです。
生糞の投入は毎日5~6トンだそうです。
私も農場勤務時代に同じ型式で同じ規模のコンポを使っていましたので、取出しは月に2回ぐらい必要でした。
加えて臭いが少ないことが驚きでした。
これなら悪臭公害も無くなると思いました。
  写真4と5は縦型コンポ利用で同じ酵素を使っている農場の様子です。
写真4は種菌と脱水汚泥を混ぜて1次発酵させているところ。
写真5は1次発酵後に縦型コンポストへ投入してさらに発酵させ、コンポから取り出した物です。
まだ湯気が立っていることが分かります。
これをまた種菌及び水分調整材として生糞や脱水汚泥と混ぜて1次発酵させる。
という循環処理になります。
ずっと発酵を継続させて減量することが出来ます。
菌や酵素メーカーは複数ありますので、他社への影響を考慮して、今回紹介した業者さんの名前は伏せておきます。
興味のある方は直接筆者までお問い合わせ下さい。
写真4と5は縦型コンポ利用で同じ酵素を使っている農場の様子です。
写真4は種菌と脱水汚泥を混ぜて1次発酵させているところ。
写真5は1次発酵後に縦型コンポストへ投入してさらに発酵させ、コンポから取り出した物です。
まだ湯気が立っていることが分かります。
これをまた種菌及び水分調整材として生糞や脱水汚泥と混ぜて1次発酵させる。
という循環処理になります。
ずっと発酵を継続させて減量することが出来ます。
菌や酵素メーカーは複数ありますので、他社への影響を考慮して、今回紹介した業者さんの名前は伏せておきます。
興味のある方は直接筆者までお問い合わせ下さい。
|