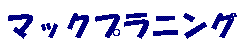
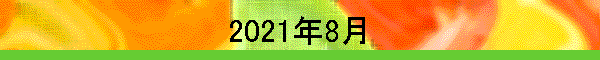
|
|
|
|
「豚舎・設備のお悩み解決!」(98)「オガコ豚舎の床管理」 読者の方より「オガ粉豚舎でオガ粉の確保が難しいので、オガ粉が足せなくて出荷間際にドロドロになってしまう」
というお悩みを頂きました。
確かに私のクライアント様でも数年前からオガクズの価格が上昇したので、使う量を少なくしたという話しも聞いています。 価格だけではなく、オガクズ自体も足りないという話でした。 一方、最近海外で住宅建築が増えたため、輸入木材の価格が上昇し、輸入自体もなかなか入ってこないそうです。 その影響で国産の木材需要が増えていると言います。 確かに、私の住む宮城県でも杉を伐採している現場を見かけることが多くなりました。 と言うことは、国内の製材所の稼働率も上がっているのではないでしょうか。 そしてオガクズの供給も増える。という好循環が起こってくれると良いのですが、それにはもう少し時間が掛かるのかもしれません。 さて、本題に戻ります。「オガ粉が足せなくて出荷間際にドロドロになってしまう」問題の対策としてですが、
まず第1はモミガラを調達して、オガクズと混ぜて敷料を増量する方法です。
モミガラ自体はオガコよりも吸水性が劣ります。
しかし、モミガラのみの踏込み豚舎で飼育している農場もあります。
モミガラは最初は吸水性が悪いです。
しかし、踏込み豚舎で豚に踏まれている間に繊維が柔らかくなってきて、吸水性が上がってきます。
また、モミガラをオガコと混ぜると通気性が良くなりますので、糞尿の発酵や水分蒸発が促進されますので、床材がドロドロになりにくくなります。
ただ、これには地域性もありますので、水田の少ない山間地ではモミガラの確保が難しいこともあるでしょう。
それから、季節的なものもあります。
モミガラの発生は通常9月〜11月です。
モミガラ保管庫を持っていない農家から譲り受けるためには、養豚場側で保管庫を用意する必要があります。
しかし、モミガラ保管庫は普通のビニールハウスで十分です。
下は土間のままで大丈夫ですから、たいして投資金額はかかりません。
もし、近くにJA等のカントリーエレベーターがあるのでしたら、1年中籾摺りをして季節を問わずにモミガラが手に入るかもしれません。
一度問い合わせてみると良いでしょう。
また、近くに大きな稲作農家が無い場合は、昨年の秋の事を思い出してみて下さい。
近所の農家をで、モミガラを畑に撒いているとか、田んぼで燃やしているところはありませんでしたか?
そのような農家へ声をかければ譲ってくれる可能性は大です。
モミガラの確保が難しい場合は、オガ床の再利用(リサイクル)を試してみて下さい。 出荷が終わって取り出したオガ床材は水分の少ない部分と水分の多い部分があります。 これを混合して堆肥舎などで発酵させて下さい。発酵温度を50度以上にすることが重要です。 それは、大腸菌などの病原菌や寄生虫を殺すためです。 堆積しておいて中心が60度くらいに上がっても表面付近は30度くらいにしかならない場合がありますから、途中で切り返しを行って1〜2ヶ月発酵させて下さい。 離乳舎や子豚舎から子豚を導入するときは、完成した堆肥を下1/3〜1/2ぐらい敷き、その上に新しいオガコを敷いて子豚を入れて下さい。 私のクライアント様では肥育豚舎の棟数を多く設置しており、豚を出荷した後は、 ドロドロの部分だけ取り出して堆肥舎へ持っていき、残りは豚舎の中までユンボを入れて残ったオガコを混ぜながら山にしてブルーシートを掛けて発酵させます。 1ヶ月後に切り返しをしてもう1ヶ月発酵させて後にそれを平にして、その上に新しいオガコを敷いて子豚を入れるローテーションをしています。 豚舎で発酵させる余裕もない、堆肥舎にも余裕がないと言うケースには、縦型コンポの導入をお勧めします。 縦型コンポを使うとサラサラの乾燥した粉状の半熟堆肥になります。 これを踏込み豚舎へ戻して使うとオガコの節約になります。 また、堆肥舎で発酵させたものを床材として再利用する場合に、発酵菌を使うと場外へ搬出する堆肥の量を減らすことが出来ることがあります。 これは使う発酵菌の種類と農場の立地条件(気象条件)によって変わります。 場外へ搬出する堆肥をゼロにすることも可能です。 堆肥の処分に困っている農場にはこの方法がお薦めです。 ご興味のある方は筆者のホームページからお問い合わせ下さい。 |
|
この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、お問い合わせフォームからお送りください。
|