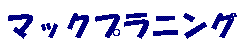
|
|
|
| 「豚舎・設備のお悩み解決!」(76)「浄化槽の管理と改善方法」今年の7月から窒素の暫定排水基準値が600mg/Lから 500mg/Lに引き下げられたことはご存じの方が多いこととおもいます。
水質汚濁防止法による浄化槽排水の一般河川放流の基準値は
pHが5.8~8.6、BODが120mg/L、SSが200mg/L、窒素含有量が120mg/L、りん含有量が16mg/Lと決まっています。
但し、放流先の河川が東京湾や瀬戸内海、霞ケ浦など、環境省が指定する地域へ流入する場合は上乗せ基準があります。
この機会に自社の排水が基準値をクリヤーしているかどうか。
また、超えているのならどうすればよいかを再確認していただければ幸いです。
【用語のおさらい】
BODとは、生物化学的酸素要求量のことです。 SSとは浮遊物質のことです。 水中に浮遊する粒子径2 mm以下の不溶解性物質の総称のことで、こちらも単位はmg/Lで表します。 養豚排水では主に糞やこぼし餌の分解物です。 前処理工程で豚舎汚水からSSを取り除くとBODのもとになる物質は主に豚尿だけになり、BODが下がります。 浄化槽を管理する上ではMLSSとSVとDOが出てきます。
MLSSとは瀑気槽内に生息する微生物・(汚れを食べてくれる)活性汚泥の濃度です。
単位はmg/Lです。これも少なすぎても多すぎても浄化はうまくいきません。
SVとは、活性汚泥の沈降度合いで、30分静置後の沈降度をSV30、60分後の沈降度をSV60と言います。
DOは溶存酸素量の事で、水中に溶けている酸素濃度です。
バッキレーターの種類や散気管の形式によって酸素を溶け込ませる効率が違います。
【水処理基本のおさらい】
一般的な養豚汚水処理は、活性汚泥法という生物処理によって行われます。 【日常の浄化槽管理】
① 前処理がうまくいっているかどうかのチェック。前処理には図2のような方式があります。
凝集剤を使った脱水処理をしている場合は、凝集剤と反応させて汚水を脱水機に入る直前で透明な容器に採って観察してください。
② 豚舎からの排水量が多すぎないか。浄化槽の設計よりも排水量が多くなっていれば当然、浄化処理も追いつかなくなります。 回分式浄化槽の場合は1日1回の投入ですから、調整槽(前処理後の汚水をためておく槽)にたまった量を見ればわかります。 しかし、連続式瀑気槽の場合は測定が難しいです。 確実なのは各豚舎の量水計を取り付けておき、それを読んで合算することです。 ③ 浄化槽の日常点検。
図4が点検簿の例です。農場には1リットルのメスシリンダーとpH計とDO計は最低限備えておきましょう。
MLSS計は高価ですし、SVを見ればだいたい見当が付きます。
SVの測定は、瀑気槽の水をひしゃくで汲み取り、メスシリンダーの1000mL目盛りまで入れて30分静置します。
沈降した活性汚泥と上澄みの境界の目盛りを読んで10で割ります。
図5
図5は雨水が大量に入って活性汚泥が流出し、SVが20まで下がっています。
図7はほとんど沈降していません。これですと綺麗な排水は得られません。
もうひとつ大切な値がDOです。
酸素の供給量が足りなければ微生物がBODを分解できません。
DOの正常値は0.5~1.0mg/Lです。多すぎても過曝気になって沈降しなくなります。
しかし、DOは微生物が使って余っている溶存酸素の量なので、もっと正確に曝気状態を管理するにはORP計(酸化還元電位計)を使います。
例えばDOがゼロでも、微生物への空気がちょうど間に合っている場合と、不足している場合があるからです。
ORP計ですと不足している酸素の量までわかります。
1台でpH、水温、ORPを測定できる機器が通販で4万円弱で買えますので、これを備えておくと便利です。
【浄化槽の改善策】
① 前処理を強化する。 BOD除去率の高い機器に替えるか機器を追加する方法です。 ② 酸素供給量を増やす。 ブロワーやバッキレーターは経年劣化で酸素供給量が減少しますので、水中曝気レーターは5年ぐらいで買い替えが必要です。 陸上のブロワーで送風する設備では、散気のズルノ劣化の方が早いです。 散気ノズルを微細気泡タイプに買い替えるだけでも酸素供給量が格段にアップし、瀑気槽が生き返ります。 ③ 3次処理(後処理)を追加する。 水量が増えて沈殿槽での沈降分離が間に合わなくなったならば、MF膜等の膜処理設備を追加すると、活性汚泥の流出が防げます。 ここでは詳しくは書けませんので、設備改善に当たっては複数の水処理業者さんと相談することをお勧めします。
。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、お問い合わせフォームからお送りください。
|