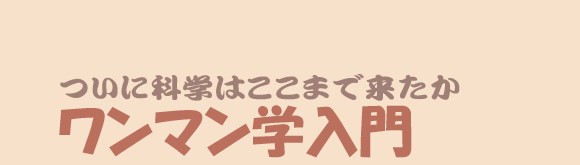
3 弊害例
組織力が低迷する、社員が育たない
組織が単なる社長の使用人(手足)となるため、優秀な使用人になるが、それ以上にならない。組織としての自律性が育たない。権限を与えないため責任感が育たない。何を提案しても最終的に社長の考えが優先されるので、誰も提案などしない。失敗が許されないので、誰もリスクテイカーに成りたがらない、また失敗から学ぶことが出来ない。組織への忠誠心や帰属意識が低下するため、容易に崩壊する組織となり、会社が危機に陥るとあっけない幕切れを迎える。
社会的に無責任な行動を起す危険が高まる
常に失敗の責任は自分になく、社員に責任を転嫁して自分の誤りを認めません。会社内では何をやっても許される立場にあることから、罪悪感、責任感についての感受性が低下し、自己批判力も減少する。そのため社内では社員に対する横暴がひどくなり、その様子を見た社員のモラールおよびモチベーションが著しく低下する。さらに感覚が麻痺して、社外の一般社会においても何をやっても許されるという安易な感覚を生み出し、やがて社会的責任感の欠落へと発展します。
社長の経営力が低下する
論理的に納得させなくとも社員が命令に従うために、論理的な説明能力を必要としなくなる(屁理屈ごり押しでOK)。このことが患者の論理的思考能力を徐々に退化させ、逆に命令に最も効果のある恫喝の方法が磨かれる。周囲の人間が誰も指摘しないので、そのことに患者は気が付かない。
論理的能力の低下から経営環境分析・戦略立案・事業計画作成能力などの経営企画能力が低下する。また、それがなくとも社員は動くので、そんなものは必要ないと考えるようになる。そのためPDCAサイクルが完全に麻痺する。
優先順位の決定、捨てるための論理的判断力が低下する。そのため、思いつくままに次々に命令する。社員は業務過剰となり、業務破綻を引き起こす。
問題解決が不能になる 追加記載
タブーや前提を作り出すので、ゼロベースでの発想を元に問題解決を図ることが難しくなる。問題の根本的な原因がそのタブーや前提に関係していると、ワンマン経営ゆえに社員には手が出せなくなるからです。その結果、最も大きな病巣を残したまま問題の解決を図ろうとするあまり、ゆがんだ対応になり、何ら効果的な対策を講ずることができない危険性がある。
