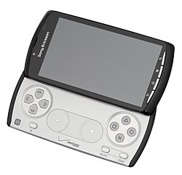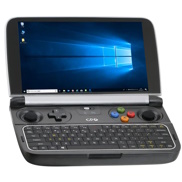【謎ペ~】謎のモバイルデバイスぺージ
制作者:KrK (Knuth for Kludge)
情報・ご感想はこちら
KrK's Cracked Text
>
雑多
【掲載基準】
- 名機
- 転機となった機種
- ガジェット魂を沸き立たせる機種
- その他、特筆すべき機種
電卓・ポケコン
HP-65
- ©1974 Hewlett-Packard
- 世界初の携帯可能なプログラム可能電卓
- 磁気カードにプログラムを格納できる
HP-41C
- ©1979 Hewlett-Packard
- 英数字を表示できる最初の電卓
- プログラム可能電卓
- 英数字表示は使いやすさに革命を起こした
- 数百個の演算や関数を提供している
- 計算用プログラムに留まらず、ゲームも発売された
- クロックアップ(オーバークロック)も試みられた
- 巨大なユーザーコミュニティが形成された
PC-1210
- ©1980 シャープ
- 世界初のポケコン(ポケットコンピュータ)
- BASICを駆使し、関数電卓より複雑な計算ができた
- 一体型のカセットインタフェースとプリンターが存在
- 乱数が無く、ゲームには不向き
PB-100
- ©1982 カシオ計算機
- ポケコン入門機
- およそLSIゲーム2台分という安さを実現
- 低年齢層にも支持された
- キャラクタパターンを多く持ちゲームが作りやすかった
- 数多くのゲームがコンピュータ雑誌に掲載された
fx-7000G
- ©1985 カシオ計算機
- 世界初のグラフ電卓(グラフィック電卓)
- プログラミングも可能
TI-83
- ©1996 Texas Instruments
- グラフ描画・プログラミングが可能な電卓
- バグ(ハッキング)必要無しにアセンブリ言語が使用できた最初の機種
- 欧米で当時の学生がよく使っていた名機
PC-E500
- ©1988 シャープ
- ポケコンの最終形態と言われる
- 新開発の8ビットCPUを採用
- RAMファイル機能を搭載
- 多次元配列や40文字までの変数名が使用可能
- RS-232Cでパソコンと通信が可能
- 日本語フォント『美咲ゴシック/明朝』が作成された
ノートパソコン
PC-8201
- ©1983 NEC
- A4サイズのハンドヘルドコンピュータ
- N-BASICの亜種
- 液晶ディスプレイとキーボードが一体となっている
- ラップトップパソコンの元祖的存在
- Microsoft製の通信ソフトやBASIC、エディタなどを搭載
- 電話機を取り付けてることでデータ通信も可能だった
- 京セラのOEMマシン
- 後の『PC-98LT』、更に『98NOTE』へと繋がっていく
T1100
- ©1985 TOSHIBA
- 世界初のラップトップパソコンと言われる
- MS-DOS
- 海外のみで発売
- 先に発売されたNEC『PC-8401A』は電池などが外付けなため分類外とされる
DynaBook J-3100SS 001
- ©1989 東芝
- 世界初のノートパソコンと言われる
- MS-DOS
- A4サイズと2.7kgで「持ち運べる実用マシン」を実現
- 19万8千円という価格も衝撃だった
- 快適な日本語入力が可能だった
- なお、ラップトップパソコンとノートパソコンに厳格な線引は存在しない
PC-286NOTE executive
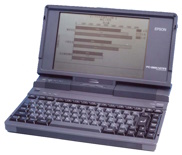
©コンピュータ博物館
- ©1989 セイコーエプソン
- PC-9801互換機ノートパソコン
- MS-DOS
- 当時としては非常に先進的なノートパソコン
- 45万8千円と非常に高価
- フロッピーディスクドライブ非実装
- 下記『98NOTE』に先んじて発売された
PC-9801N (98NOTE)
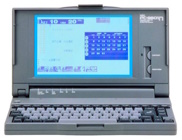
©コンピュータ博物館
- ©1989 NEC
- PC-9801ノートパソコン
- MS-DOS
- フロッピーディスクドライブ実装
- 2台目のフロッピーディスクの代わりに「RAMドライブ」を実装
- 本機により「ノートパソコン」という用語が広まったと言われている
- Cバススロットと互換性のある「98ノートバス」を搭載
- 翌年には、売上でJ-3100シリーズを抜いた
PC-9801NC
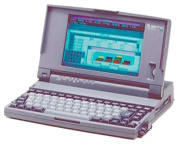
©コンピュータ博物館
- ©1991 NEC
- 世界初のTFTカラー液晶ノートパソコン
- MS-DOS
- 59万8千円と非常に高価
- オプションでテレビチューナーアダプタが用意された
PS/55 5535-S
- ©1990 日本IBM
- IBM最初のPC/AT互換ラップトップパソコン
- DOS/Vの初版「IBM DOS J4.05/V」を搭載
PS/55note 5523-S
- ©1991 日本IBM
- 「ThinkPadの原点」と呼ばれるノートパソコン
- IBM DOS/V
- レジューム機能搭載
- 「Noteメニュー」でDOSの扱いにくさをカバー
- 当時ノートパソコンとしては好調なセールスを記録
ThinkPad 700
- ©1992 日本IBM
- Windows3.0
- ThinkPadを冠する最初の機種
- 既に赤いトラックポイントを搭載
ThinkPad 550BJ
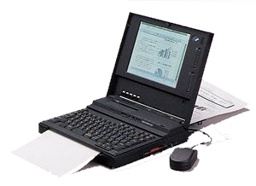
©ThinkPad Wiki
- ©1993 日本IBM
- Windows3.0
- インクジェット式プリンタ内蔵
- キーボード下から挿入した用紙が背面に排出される
- キヤノンとの共同開発
ThinkPad 220
- ©1993 日本IBM
- PC DOS/V
- 携帯性にこだわったモバイルノートパソコン
- A5サイズ+1kg
- 左上にトラックボール、右上にクリックボタンを搭載
- 持ったままでマウス操作ができる様に設計されていた
- 単3乾電池6本で8時間駆動した
- サブノートというジャンルの草分けとなった
ThinkPad 701C
- ©1995 日本IBM
- Windows3.1
- 分割式キーボード「TrackWrite」を搭載
- 天板を開くとキーボードが飛び出して左右に広がる
- 10.4型の小さな本体で、A4サイズと変わらないキーピッチを実現
- 小型化と、十分なキーボードサイズの確保を両立させた
- キータッチは良好で、TrackPointⅢも装備されていた
- 愛称「バタフライ」
Libretto 20
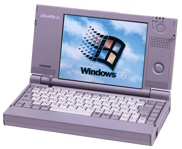
©コンピュータ博物館
- ©1996 東芝
- ミニノートパソコンというジャンルを開拓したパイオニア
- Windows95
- 慣れればタイピングできるキーボードを装備
- ディスプレイの右側に「リブポイント」を装備
- インターフェイスはPCMCIA TypeⅡのカードスロットのみ
- 付属のI/Oアダプタでシリアル、パラレルポートが使えた
- 当初日本国内でのみ販売された
- Librettoはイタリア語で「小さな本」の意
VAIO PCG-505
- ©1997 ソニー
- VAIOシリーズのノートパソコン第一号
- Windows95
- 厚さ23.9mmと極薄ノートの先駆け
- シルバーやパープルを多用したスタイリッシュなカラー
- 持っていてカッコいいパソコンとして、一気にメジャーブランドに
- 爆発的なヒットとなった
NP-10N(チャンドラ)
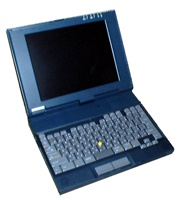
©PC Watch
- ©1997 ライオス・システム
- 小型ノートパソコン
- Windows95
- ライオス・システムはIBMとリコーの合弁会社
- 日本IBMとThinkPad220などを開発
- 本機はその直系と言える
- 内蔵バッテリーパックに家庭用ビデオカメラ用のものを流用
- Webで限定発売
- 50時間で300台を売り切り、幻のパソコンと呼ばれた
- ThinkPad535と競合するため、IBMからは発売されなかった
ThinkPad 235(チャンドラ2)
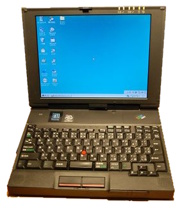
©ThinkPad Wiki
- ©1998 日本IBM
- 小型ノートパソコン
- Windows98
- 上記「チャンドラ」に、画面解像度向上などの改良を施したもの
- 「チャンドラ2」は日立、エプソンダイレクトなどからも発売された
- 長期にわたって使い続ける熱烈なユーザーを獲得した
- その作りこみ様から「幻のサブノート」の異名がある
ThinkPad 240
- ©1999 日本IBM
- 上記「チャンドラ2」の後継機
- Windows9x
- B5サイズながら、A4サイズと同等なインターフェイスを実現
- 周辺機器の接続性が特出していた
- モバイルユーザーの間で人気が高いモデルであった
FMV-BIBLO LOOX S5/53W
- ©2000 富士通
- モバイルパソコンの名機
- WindowsMe
- 1kgを切る重量、カバンに簡単に入るサイズ
- 基本性能に特化したコンパクトタイプ
VAIO U PCG-U101
- ©2003 ソニー
- 両手で持って操作できるミニミニノート
- WindowsXP
- 初期モデルは非力な謎CPU「TM5800」が弱点だった
- 本機ではCeleronを搭載し、弱点を克服
- 人気モデルになった
VAIO U VGN-UX50
- ©2006 ソニー
- スライド式キーボード付きパソコン
- WindowsXP
- ほぼ文庫本サイズで、500gを切る
- 前後2個のWebカメラを搭載
パームトップ機(謎パ~)
Atari Portfolio
- ©1989 ATARI
- パームトップパソコンの走り
- 独自開発のDOS互換「DIP Operating System」
- DIP社からのOEM供給機
- 日本製
- 解像度が独自で、DOSソフトがそのまま動かなかった
- 240×64(40文字×8行)
- PIMアプリケーションを搭載
- シリアルポートなど、様々な拡張ハードウェアが用意された
- 有志によって日本語化がなされた
Poqet PC
- ©1989 Poqet Computer
- IBM/XT互換アーキテクチャ
- MS-DOS
- モノクロCGA
- 「パームトップパソコンの原器」と言える
- Wikipedia「the first subnotebook form factor IBM-PC compatible computer 」
- 後に発売された『Poqet PC Prime』と区別するため「Poqet PC Classic」と改名
- 有志によって日本語化が行われた
- 後に開発元が富士通の関連会社に吸収された
- その小型化技術を応用して作られたのがオアシスポケット
PC-3000
- 1991 SHARP
- 品質の高いパームトップ機
- MS-DOS
- 元々「Portfoli 2」として開発されていた
- 有志によって日本語化が行われた
- SHARP製だが、日本では発売されなかった
Psion Series 3
- 1991 Psion
- PDA的な性格のマシン
- 独自「EPOC-OS」
- 欧州でヒットした
- 有志によって日本語化が行われた
Zeos Pocket PC
- ©1992 ZEOS
- 安価な超小型パソコン
- MS-DOS
- 台湾メーカー「TidalWave」OEM製品
- MS-Worksや予定表、住所録などPIMソフトウェアも内蔵
Poqet PC Plus
- ©1993 Fujitsu
- 『Poqet PC』の後継機
- MS-DOS
- 『Poqet PC』よりでかくてごつい
- 乾電池からバッテリーになった
- バックライト搭載
- 有志によって日本語化が行われた
HP95LX
- ©1991 Hewlett-Packard
- パームトップパソコン往年の名機
- MS-DOS
- Lotus 1-2-3が動くPDAとして発売された
- 名前は「Lotus Expandable」から
- 立派なIBM PC/XT互換機
- PCMCIA TypeⅠ搭載
- 有志によって日本語化がなされた
- 恵梨沙フォント第一水準完成
HP100LX
- ©1993 Hewlett-Packard
- 上記『HP95LX』の後継機
- MS-DOS
- MDA(240×128)からCGA(640×200)に拡張
- そのため、市販のIBM PC互換機用ソフトウェアが活用できた
- PCMCIA TypeⅡになったため、モデムカードなどが活用できた
- 単3乾電池2本で20時間(約1週間)駆動した
- 引き続き日本語化、通称「DOS/C」化が行われた
- 恵梨沙フォント第二水準完成
- クロックアップも実施された
HP200LX
- ©1994 Hewlett-Packard
- 上記『HP100LX』の後継機
- MS-DOS
- 基本はHP100LXと同じ
- 組み込みアプリケーションが更新された
- 1MBメモリ版と2MBメモリ版が存在
- 引き続き日本語化・クロックアップが行われた
- 恵梨沙フォント 1.00
- 日本語化キットが発売され、作業が大幅に簡略化された
- 4MB拡張メモリキットも発売された
- 長らく使われる名機
- 1999年まで生産された
- 生産終了発表時、ユーザーによる反対運動が起きた
HP1000CX
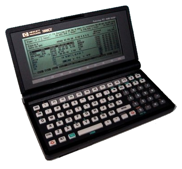
©Studio Pooh & Catty
- ©1995 Hewlett-Packard
- MS-DOS
- HP200LXの廉価版
- 内蔵PIMが省略されている
- それに伴い、ショートカットキーが記号キーに変更されている
- 1MBメモリ
- 何故かあまり話題に上がることが無い
- 純粋DOSマシンと言う意味ではこちらの方が使い勝手が良い筈なのだが…
OASYS Pocket3
- ©1994 富士通
- ポケットワープロ
- MS-DOS
- 1991年オアシスの携帯用として開発されたシリーズの3代目
- 其の実はROM-DOSマシン
- 予定表や住所録なども内蔵し、PDA的な要素を持っていた
HP300LX
- ©1997 Hewlett-Packard
- Windows CE
- 一応、上記『HP200LX』の後継機
- あまり話題に上がることはない
- 1997年、バックライト付き等が施された『HP320LX』発売
- 1997年、クロックアップ等が施された『HP360LX』発売
モバイルギア MC-MK
- ©1996 NEC
- モバイルパソコン
- MS-DOS
- 通称「モバギ」
- 長時間駆動、入力し易いキーボードで一世を風靡した
- モデム内蔵
- ユーザーによる解析により「DOS化」が可能に
- DOS化時は、デバイスドライバの用意などが必要であった
- FreeBSD2.2をベースにした「PocketBSD」も作られた
- モデムの替わりにNTTドコモ端末を接続する『MobileGear for DoCoMo』が存在
モバイルギア MC-CS
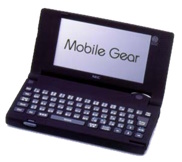
©PC Watch
- ©1997 NEC
- モバイルパソコン
- WindowsCE
- 小型化&軽量化
- モデム内蔵
モバイルギアⅡ MC-R
- ©1998 NEC
- モバイルパソコン
- WindowsCE
- モノクロディスプレイ機とカラーディスプレイ機が存在
- モデム内蔵
- モデムの替わりにNTTドコモ端末を接続する『MobileGearⅡ for DoCoMo』が存在
シグマリオン
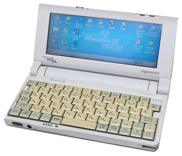
©PC Watch
- ©2000 NTTドコモ
- モバイルパソコン
- WindowsCE
- モバイルギアがベース
- NTTドコモの携帯・PHSと接続して使用する
- 代わりに内蔵モデムが外されている
- 筐体はゼロハリバートンがデザイン
- 2001年『シグマリオンⅡ』発売
- 2003年『シグマリオンⅢ』発売
PDA(Personal Digital Assistant)
PF-3000
- ©1983 カシオ計算機
- 初代電子手帳
- 電卓を中心にカレンダー、住所録などを搭載
- PDAの祖先と言える
- なお、「電子手帳」という用語はカシオの商標だそうである
PalmTop PTC-300

©Computer History Museum
- ©1991 ソニー
- 技術のソニーが放ったPDAの源流
- ペンは本体とケーブル接続する必要があった
- 基本的にはPIMソフトのみ
- プログラミングはできなかった
Apple Newton MessagePad
- ©1993 Apple
- 世界初のPDAと言われる
- 手書き認識機能を備える
- ただし、認識率は低く、却って販売不振の一因となった
- 一方で、20年ほど使い続ける人も存在したとか
PI-3000(ザウルス)
- ©1993 シャープ
- PDA
- 電子手帳の延長として発展したもの
- ビジネスマンを中心にが受け入れられ、同社の定番商品となった
- Appleと手書き認識開発で協力し、開発
- よって、Newtonとは親戚関係にあると言える
- 発売当初の正式な商品名は「液晶ペンコム」
- 「ザウルス」は愛称だった
- 様々なフリーソフトが開発・配布された
MI-10(カラーザウルス)
- ©1996 シャープ
- 32bit高機能PDA
- PIシリーズとはソフト面での互換性はない
- 独自OSながらMS-DOS互換のファイルシステムを持っていた
- 反射型液晶やLCフォントを搭載
- 「液晶のシャープ」をアピールする使命を帯びていた
Pilot1000 (PalmOS)
- ©1996 Palm Computing
- 初のPlamOS搭載機
- Hewlett-Packardの子会社が開発
- 素早い反応速度などで手軽に入力できるのが強みだった
- パソコンと簡単に連携できるのも評価された
- 当時のPDAマーケットシェアの3分の2をおさめるヒット商品となった
WorkPad
- ©1996 IBM
- PalmOS
- 基本的にPalm製品にIBMのロゴを載せたもの
- 利益がいまひとつであったらしい
CLIE (CLIÉ)
- ©2000 ソニー
- PalmOS
- PDAではなく「パーソナル・エンターテインメント・オーガナイザー」
- エンターテインメントツールとして、PalmOSを拡張
- いち早く高解像度カラー液晶を搭載
- マルチメディア路線を選んだ結果、PDAと縁の無かった層にも使用された
- 名前は「Communication Linkage for Information & Entertainment」から
- QWERTYキーボード搭載機あり
Zaurus SL-C700
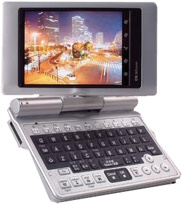
©ASCII.jp
- ©2002 シャープ
- Linuxを入れたモバイル端末
- 手に持って打てる小型QWERTYキーボード
- 動作は遅かった
- 有志による解析で機能の発展が進んだ
スマートフォン
BlackBerry
- ©2002 Research In Motion
- QWERTYキーボード搭載携帯電話
- セキュリティが高く、欧米の法人分野で広く使われた
- 日本でも約4,000社が導入していたと言われる
W-ZERO3(WS0003SH)
- ©2005 シャープ
- QWERTYキーボード搭載PHS
- Windows Mobile
- 「ガラケー」全盛期に、異色の携帯電話として注目された
- 「元祖スマートフォン」と言われることも
- パソコンとデータを同期することができた
- パソコンと接続し、モデムとして利用することも可能
- プリインストールのMicrosoft Office Mobileで閲覧・編集が可能
- 予約で初回出荷分が満了するなど売上好調であった
- NetBSDが移植されている
W-ZERO3[es](WS007SH)
- ©2006 シャープ
- QWERTYキーボード搭載PHS
- Windows Mobile
- 一般的な携帯電話に縮小
- esは心理学用語で「本能的な欲求」の意
Advanced/W-ZERO3[es](WS011SH)

©Amazon
- ©2007 シャープ
- QWERTYキーボード搭載PHS
- Windows Mobile
- 小型化の一方で、液晶を大型化(2.8"→3.0")
- 長らく使われることになる名機
- 通称「アドエス」
- CPU高速化、メモリ増量化、高解像度化(640×480→800×480)
WILLCOM 03 (WS020SH)
- ©2008 シャープ
- QWERTYキーボード搭載PHS
- Windows Mobile
- 小型化
- ワンセグチューナー追加
- Bluetooth追加
- 液晶面のフラット化
- 上記『アドエス』より人気がなかった
- 理由は、…なんでだっけな?
HYBRID W-ZERO3 (WS027SH)
- ©2010 シャープ
- 携帯情報端末
- Windows Mobile
- キーボードが無くなった
- PHSと3G携帯電話(W-CDMA)の両通信方式に対応
iPhone
- ©2007 Apple
- 一般に「スマートフォン」と言うと、これが初代
- 全面タッチパネルを初採用
- 専用OS『OS X iPhone』が開発・搭載された
- 2008年バージョン3から『iPhoneOS』と改名
- 2010年バージョン4から『iOS』と改名
Android
- ©2008 Google
- スマートフォンおよびタブレット用OS
- 初の搭載端末はT-Mobile『T-Mobile G1』
- オープンソース
- 一部キーボード搭載端末が存在
Windows Phone
- ©2010 Microsoft
- スマートフォン用OS
- 当時最新だったWindows7に合わせ、バージョンは「7」から開始
- 初の搭載端末はDell、HTC、LG電子、Samsungの4社から発売
Windows 10 Mobile

©ITmedia
- ©2015 Microsoft
- スマートフォン用OS
- デスクトップ版Windows10とプラットフォームを統一
- 初の搭載端末はMicroSoft『Lumia 950』『Lumia 950 XL』
その他
PenTop PT-304V
- ©1992 ワコム
- タブレットパソコンの走りと言える
- Windows for Penという、Windows3.0ベースのOS
- 付属のペンで直接入力できた
- 肝心のWindows for Penが別売り
PalmTopPC 110
- ©1995 日本IBM
- 超小型ノートパソコン
- 158mm×113mm(ThinkPad220の半分サイズ)、690g
- PC DOS/V+Windows3.1
- Windows95が動いたという報告あり
- 左上にトラックポイントとクリックボタンを配置
- 片手でWindowsを操作可能な様に設計されていた
- ノートパソコンをそのまま小さくした造形がマニアの心をくすぐった
- 電話線を繋げば単体で電話になる
- シリアルポートなどを配した拡張ドック(ポート・リプリケーター)を同梱
- PCMCIA TypeⅢのHDDカードが使用可能
- 愛称「ウルトラマンPC」
Chipcard TC-100
- ©1995 日本IBM
- カードサイズのコンピュータ
- PCMCIA TypeⅡカードサイズ(厚さ5mm)
- スロットにそのまま挿さり、パソコンと連動できた
- 自作プログラムが動いた
ChipCard VW-200
- ©1996 日本IBM
- PCカードサイズのコンピュータ
- 二代目モデル
- 二つ折り型に
- PCMCIA TypeⅢカードサイズ(厚さ10.5mm)
モバイルギア MC-MP
- ©1996 NEC
- MS-DOS搭載PDA
- タッチパネルによるペン操作モデル
- キーボードは無い
- 独自メニュー「UNISHELL」を搭載
- MS-DOS機として使うことはできない
- モデム内蔵
Ruputer

©Quiet Life
- ©1998 セイコーインスツルメンツ
- PCアーキテクチャ搭載の腕時計型端末
- 十字カーソル+4ボタンで操作
- 「Fontset」を「Japanese」にすると日本語表示可能
- 本体にファイラを内蔵
- Windowsとも連携できる
- 早過ぎたウェアラブルデバイス
iモード

©富士通
- ©1999 NTTドコモ
- 世界初の携帯電話IP接続サービス
- 初の対応機種は富士通『デジタル・ムーバF501i HYPER』
- Javaでプログラミングできた
P/ECE
- ©2001 AQUAPLUS
- 携帯ゲーム端末
- 電池込みで92gという小型軽量端末
- C言語による開発環境が同梱されていた
- 有志によって多くのゲームなどが作られた
- 日本語エディタ「P/Edit」も作られた
京ぽん (AH-K3001V)
- ©2004 京セラ
- PHS(AirH" Phone)
- 日本国内携帯電話・PHSとして初めてウェブブラウザにOperaを搭載
- パソコン向けのウェブページも表示することができた
- JavaScriptを利用して、有志によって簡易アプリケーションが開発された
- パソコンとの高い親和性がコアなユーザ達の人気を博した
- 「京ぽん」は愛称であったが、後に京セラにより商標登録された
- 「京セラ」と、AirH" Phoneがなまった「味ぽん」から
iPod touch
- ©2007 Apple
- 携帯型デジタル音楽プレイヤー
- 全面タッチパネル採用型
- 後の『iOS』である『OS X iPhone』を採用
iPad
- ©2010 Apple
- タブレット型コンピュータ
- 『iOS』を採用
- 2012年小型版『iPad mini』発売
- 2013年薄型・軽量版『iPad Air』発売
- 2015年上位版『iPad Pro』発売
Kindle
- ©2007 Amazon
- 電子書籍リーダー
- 電子ペーパー「E Ink」ディスプレイを搭載
- モノクロ
- アプリケーション「Kindle無料アプリ」の配信も行っている
- パソコンを介さずに電子書籍をダウンロードできるのが強みだった
Kindle Fire
- ©2011 Amazon
- 電子書籍リーダー
- Androidをベースに独自開発された「Fire OS」
- フルカラー
Xperia PLAY SO-01D
- ©2011 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ
- ゲームキー付きスマートフォン
- Android端末
- PlayStation Storeから初代PlayStationゲームを導入可能
- Androidマーケットからもアプリケーションを導入可能
Apple Watch
- ©2015 Apple
- ウェアラブルコンピュータ(スマートウォッチ)
- iPod nanoに通知機能等を付与
- iPhoneと連携して初めて可能な機能も多い
- 独自のwatchOSを採用
- Steve Jobs亡き後、初の新カテゴリー製品
GPD WIN
- ©2016 GamePad Digital
- ゲームコントローラー搭載の携帯型コンピュータ
- Windows10がフル動作する
GPD WIN2
- ©2018 GamePad Digital
- 強化版
- アナログスティックの配置が外側に変わっている
- 全体的に丸みを帯びた
GPD WIN3
- ©2021 天空
- Windows10
- 画面がスライドしてQWERTYキーボードが現れる様に
- ドッキングステーションによる外部拡張端子も存在
GPD WIN4
- ©2023 天空
- Windows11
- PSVita型に
GPD WIN Mini 2024
- ©2024 天空
- Windows11
- 『GPD WIN2』の後継機
- クラムシェルUMPC(Ultra-Mobile PC)
- 別売り脱着式グリップを用意
最終更新:2025/06/26
主要参考文献
- DOS/V POWER REPORT「PC/AT互換機名鑑」
- 月刊アスキー「完全保存版パソコン30周年」
- さらば愛しのDOS/V
主要参考ページ
©Wikipedia、他:当ページでは引用の範囲内で画像を使用しています。
免責事項








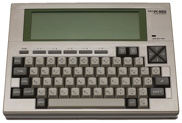
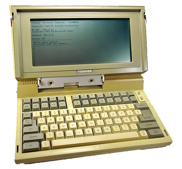
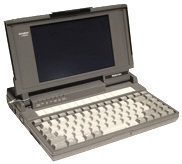
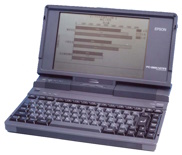 ©コンピュータ博物館
©コンピュータ博物館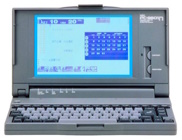 ©コンピュータ博物館
©コンピュータ博物館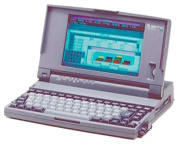 ©コンピュータ博物館
©コンピュータ博物館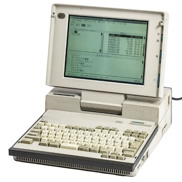

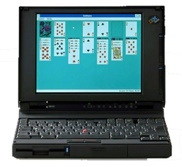
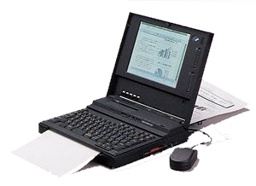 ©ThinkPad Wiki
©ThinkPad Wiki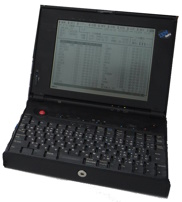
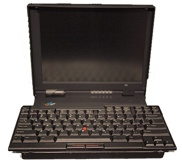
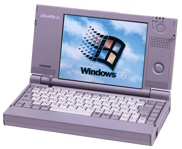 ©コンピュータ博物館
©コンピュータ博物館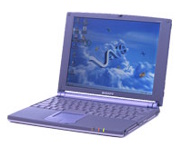
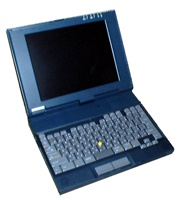 ©PC Watch
©PC Watch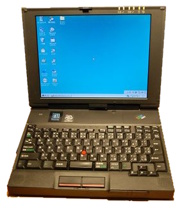 ©ThinkPad Wiki
©ThinkPad Wiki
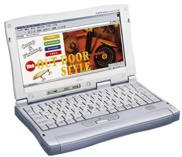
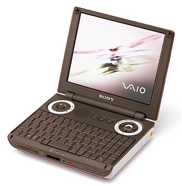
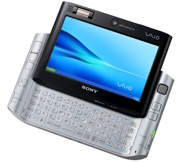

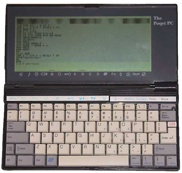
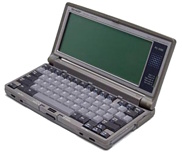
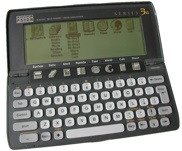
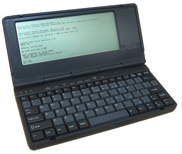
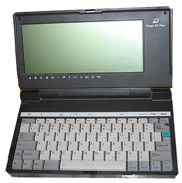
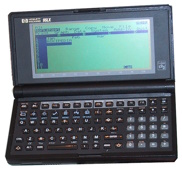
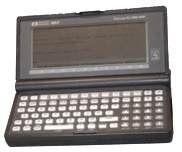
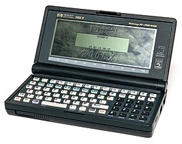
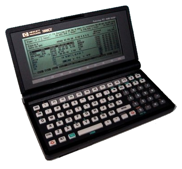 ©Studio Pooh & Catty
©Studio Pooh & Catty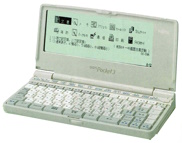
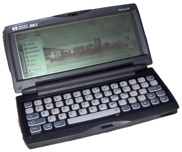
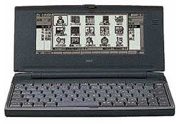
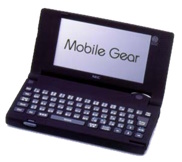 ©PC Watch
©PC Watch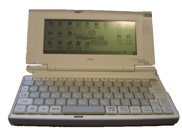
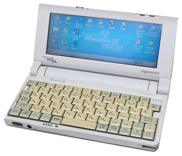 ©PC Watch
©PC Watch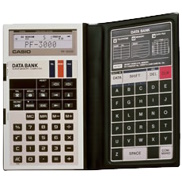
 ©Computer History Museum
©Computer History Museum





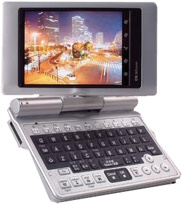 ©ASCII.jp
©ASCII.jp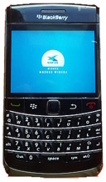

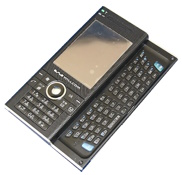
 ©Amazon
©Amazon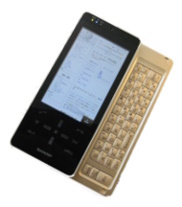
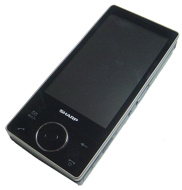



 ©ITmedia
©ITmedia
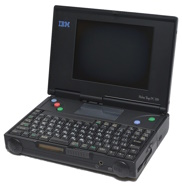
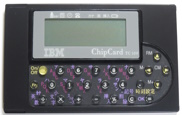


 ©Quiet Life
©Quiet Life ©富士通
©富士通